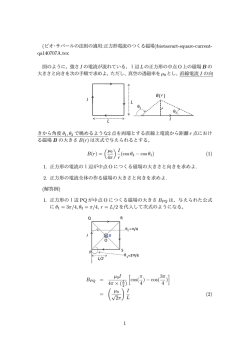Document 668357
14.11.6
線形微分方程式
*未知変数とその高階導関数に対して1次に
なる方程式
y ( n) + f1 (x) y ( n−1) +
+ f n−1 (x) y ′ + f n (x) y = g(x)
ここでg = 0の時方程式は同次(斉次)、 そうでない時非同次、と呼びg を非同次項とい
う。
線形方程式の例
1. 単振動:(摩擦項あり)
m!!
x = !kx ! m! x!
2. 多自由度の線形振動:(摩擦項なし) M!!
x = !Kx
3. 円形膜の振動方程式の動径部分:
# 2 m2 &
1
u !! + u ! + %% k " 2 ((( u = 0
%$
r
r ('
4. ルジャンドル方程式:
%
d "$
m2
2 d '
y + l(l +1) y = 0
$(1! x ) ''' y !
2
dx $#
dx &
1! x
1
14.11.6
線形同次方程式の性質 *任意の2つの解y1,2の定数による1次結合ay1 + by2も解に
なる。
( k≠i)
yij(i) (x0 ) = e j y を満たす解を基本
(x0 ) = 0
*初期条件 、
ij
解と呼ぶ。任意の解はこれの1次結合で書かれる。
定理からの帰結
1. 解は f j(x)が定義されている範囲で延長可能。(爆発現
象は無し)
2. 一般解を求めるには基本解さえ求められればよい。
y(x) = ∑ aij yij (x) が初期条件 y (i) (x0 ) = aij e j に対する
i, j
解になる。
*n個の1次独立な ajに対してzij(i )(x0) = aijを満たす解から
も一般解が構成できる。(独立な解の集合)基本解系を
y(x) = ( y0 (x), y1 (x),, y n−1 (x)) と書くことにすると
行列 を A = (a1, a2, , an) と定義すれば z = Ay。よって任意
の(積分定数)bに対してyb = b y = b A-1zだから。
の任意の解は有限の範囲にしか延長
y ′ = 1+ y 2
不能(解の爆発)
線形方程式の解
有限の x で y が無限大
はこうならない
になっている
2
14.11.6
* 方程式の係数fi(x)が定義されているx全体に解が延長できること
x = x0での基本解は x = x1でも一般解を構成できる。xの各小区間で
定義された解を「貼り合わせ」て大きな区間の解にできる。
行列式の性質より消える
ロンスキー行列式W:
W = det( y (i)
)
j
W!=
y1!
y2!
y1!
y2!
"
( n"1)
1
y
y
( n"1)
2
yn!
!
"
+!+
#
! yn( n"1)
y1
y2
y1!
y2!
"
y1( n)
y
( n)
2
!
yn
"
#
! yn( n)
= − f1 (x)W , y ( n) = − f1 (x) y ( n−1) − f 2 y ( n−2) ++ f n y
x
∴ W (x) = W (x0 )exp[−∫ f1 (x) dx ] ≠ 0
x0
この解が
各区間における基本解系用いて
各区間に延長可能
"
!
"
#
$
%"
結局f i (x)の定義された全領域に解が延長可能
3
14.11.6
非同次系線形方程式の性質
任意の特解y1と対応する同次方程式の一般解ybの和
が非同次方程式の一般解になる。
y1( n) + f1 (x) y1( n−1) ++ f n−1 (x) y1′ + f n (x) y1 = g(x),
yb( n) + f1 (x) yb( n−1) ++ f n−1 (x) yb′ + f n (x) yb = 0.
の両辺の和から
[ y1 + yb ]( n) + f1 (x)[ y1 + yb ]( n−1) +
+ f n−1 (x)[ y1 + yb ]′ + f n (x)[ y1 + yb ] = g(x).
この解は任意定数をn個含むから確かに一般解。
定数線形微分方程式
y ( n) + c1 y ( n−1) ++ cn−1 y ′ + cn y = g(x)a 、ここで ck 全て
は定数、という形のもの。
*定数線形微分方程式の解法
微分作用素Dによる方法
y′
関数 y にその導関数 を対応させる写像
D : y → y′
は線形写像になる。(このような、関数空間上の写像を演
算子と称する)
*厳密な定式化が欲しければ適当な関数空間(ベクトル空間の公理+適
当なノルム(ベクトルの大きさ)の公理を満たすもの)を設定すれば良い。
4
14.11.6
微分作用素を用いると同次方程式は
f (D)y = 0、 、と書か
f ( D) = D n + c1 D n−1 ++ cn−1 D + cn I
れる。(I は単位写像、以降省略) f ( D) = ∏ ( D − λi ) i
と因数分解すれば
D -aとD -bは可換
なので i
n
n
(D − λi ) i y = 0 ⇒ f (D) y = 0
( D − λi ) i y = 0
従って がn
i 個の独立な解を持てば元の方
程式の一般解が得られる。
n
1. (D -a)y = 0の解:( D − aI ) y = 0 ⇔ y ′ = ay ⇔ y = Ce ax
2. (D -a)2 y = 0の解:(D -a)y = z とおけばzは(D -a)z = 0、
つまりz = Ce ax。よってyは(D -a)y = Ce ax を満たす。
( は定数変化法で解けて
D − a) y = Ce ax ⇔ y ′ − ay = Ce ax
y = (Cx + F)e ax 。
n
3. ( :
D − λi ) i y = 0 2.の手法を帰納的に適用して
y = (C1x
ni −1
+ C2 x
ni −2
+ +Cn −1x + Cn )e ay
i
i
という一般解が得られる。
*残った問題:複素数の λ に対する ( D − λ ) y = 0 の解は
どうするか?
複素指数関数
e( a+bi) x の導入
5
14.11.6
*数学的に最もよい定式化 複素数の範囲で
の微積分:複素解析による定式化
*今回に必要な最低限の定式化 実変数に依
存する複素数値関数としての複素指数関数
実(独立)変数の複素数値関数f は
f (x) = u(x) + iv(x)
と、2つの実関数の和になる。そしてその導関数は
f ′(x) = u′(x) + iv′(x)
で与えられる。
そこで、微分すると自分の複素数倍になる複素数値
関数、を見つけられればよい。
ax
答: f (x) = e (cos[bx]+ isin[bx])
isin[bx]
三角関数を cos[bx]+
の形に組み合わせたも
のは純虚数の指数を持つ指数関数e ibx と見なせる。
指数法則e x e y = e x+yは複素指数において
eix eiy =(cos x+isin x)(cos y+isin y)
=cos x cos y−sin x sin y+i(sin x cos y+cos x sin y)=eix+iy
つまり三角関数の加法定理と同値になる。
*テーラー級数展開から
(ix)2 (ix)3
x2 x4
e = 1+ ix +
+
+ = 1− + −
2
3!
2
4!
3
5
ix
ix
+ix −
+
− = cos x + isin x
3!
5!
と合理化可能
ix
6
14.11.6
複素数 (D − λ ) y = 0 の解は
λ = a + bi に対する y = Ceλ x = Ceax (cos[bx]+ isin[bx])
*元々は実数係数の方程式 f (D)y = 0を解いて、実数値関
数を求めたかった。
いくつかの複素数の和、差、実数との積をとった後、その実
部、虚部をとっても、先に実部、虚部をとってから和、差、積
をとっても同じになることを利用。
Re [x+y] = Re x+Re y、Re ax = aRe x、etc.
実数変数関数の微分とは関数値の差を実数で割る操作な
ので実数係数多項式 f (u)に対してf (D)y = 0なら
Ref (D)y = f (D) Rey = 0、つまりyが解ならRey、Imyも解。
− λ) y ≠ 0)
故に y = Ce ax cos[bx] は f (D)y = 0の解( (D
ax
f ( D) y = 0 の解だ
* Ce ax cos bx も Ce
sin bx = Im Ceλ x も が ( D − λ ) y = 0 の解では無い。
*実多項式 の方程式 f (u) = 0 に対して λ が根ならその複素共
役 λ *も根。その結果 、 共に
Re eλ x Im eλ x
( D − λ )( D − λ * ) y = ( D 2 − 2aD + a 2 + b2 ) y = 0
の解になる。この2階方程式に2個の独立な解が存在するので
それらから一般解が構成できる。
* ( D − λ ) m y = 0 、m > 1の場合も(g(x)を実係数m-1次多項
λx
ax
λx
Re g(x)e = g(x)e cos bx Im g(x)e
式として) 、 ( D 2 − 2aD + a 2 + b2 ) m y = 0
= g(x)e ax cos bx は2m階方程式 の実数関数解になり、任意定数を合わせて2m個持つので一
般解が構成可能
7
14.11.6
具体例
減衰振動子ma = -kx-2m γ v:
D 2 + 2γ D + ω 02 )x = 0 、た
mで割ってから左辺に移項すれば ( ω 02 = k/m 。一般論に従って特性方程式 f (u) = 0を解い
だし て λ± = −γ ± γ 2 − ω 02 、ここで摩擦項 γ が大きすぎず平方
ω 1 = ω 02 − γ 2 として
根の中が負になるなら x = C1 Re e
λ+t
+ C2 Im e
λ+t
= e−γ t (C1 cos ω 1t + C2 sin ω 1t)
* λ+の代わりに λ−を用いても同じ結果になる。
*複素数の定数 C を用いて Ceλt の実部、という形でも表せる。
すなわち
x = ReCe
λ+t
= Re |C| eiα e
λ+t
= |C| Re e
λ+t+iα
= |C| e−γ t cos[ω 1t + α ]
なお α は初期位相と呼ばれる。
摩擦項が大きい場合、特性根は負の実数:
λ± = −γ ± γ 2 − ω 02 < 0
−λ+t
x = Ae
−λ−t
+ Be
γ の時特性方程式は重根
= ω0
γ を持ち一般論より
x = ( At + B)e−γ t。
*線形代数との関わり:行列Aはいつでも対角化できるとは
限らない。
⎛ 3
2 ⎞⎟⎟
γ = ω0
A = ⎜⎜⎜
例: ⎟⎟ は対角化不能。 の時の減衰振
⎜⎝ −2 −1 ⎟⎠
動の方程式を2変数1階の方程式(標準形)に書き換えれば
⎛ x ⎞ ⎛ 0
1
⎟⎟ ⎜⎜
⎜⎜
=
⎟
2
⎜
⎜⎜ y ⎟⎟ ⎜ −γ
−2γ
⎝
⎠ ⎝
⎞⎛
⎟⎟⎜ x
⎟⎟⎜⎜ ⎟⎠⎜⎝ y
⎞
⎟⎟ で、この行列は対角化不能。
⎟⎟
⎟⎠
8
14.11.6
減衰振動解の例
過減衰の例
振動する例
共にv(0) = 0
としている
ケーリー・ハミルトンの定理より行列Aの特性多項式 f (u)に対してf (A)
= O、そして各固有値 λi に対して少なくとも1つの固有ベクトルがある。
微分方程式の解法同様、元の n 次元空間は、その上で ( A− λi I ) i = O が満たされるいくつかの部分区間にわかれ、
n
( A− λi I )u1 = 0 (これは通常の固有ベク
一般化固有ベクトルが順次 、と求められていく。
A− λi I )u2 = u1 、 ( A−
λi I )u3 = u2 、 トル)、 ( 基底系 u1 unを用いれば行列 A は
i
⎛ λ 1 0
⎜⎜
⎜⎜ 0 λ 1
⎜
J = ⎜⎜⎜ λ
⎜⎜
⎜⎜
⎜⎝ 0
0
0
0
1
λ
⎞
⎟⎟
⎟⎟
⎟⎟
⎟⎟ のようになる。(ジョルダンブロック)
⎟⎟
⎟⎟
⎟⎟
⎟⎠
9
14.11.6
非同次方程式の解法
特解を1つ見つけられれば同次方程式の一般解を足し合わ
せて非同次方程式の一般解になる(7枚目のスライド参照)
何でもいいから1つの特解が見つかればいい。
(地道にやる方法: f (D)y = g において f = 0に重根があった時と同
様に定数変化法を繰り返せばよい)
応用上重要なのは g = eλ xのケース。ここで f ( λ ) ≠ 0 の場合
は方程式の両辺にf (D)の逆演算子f -1(D)をかけて
y = f −1 ( D)g = f −1 ( D)eλ x = f −1 ( λ )eλ x
とすればよい
*通常フーリエ解析と組み合わせて用いられる
性質のいい(非周期的)関数g(x)は周期関数の和として
表現できる。すなわち
1 ∞
g(x) =
h(k)eikx dk
∫
2π −∞
が成立する。ここに
∞
h(k) = ∫ h(k)e−ikx dk
−∞
である。
hをg のフーリエ変換と呼ぶ。このフーリエの定理よりf (D)
y = g の特解は
1 ∞ −1
y(x) = f −1 ( D)g(x) =
f ( D)h(k)eikx dk
∫
−∞
2π
1 ∞ h(k) ikx
=
e dk で与えられることが分かる。
2π ∫−∞ f (ik)
10
14.11.6
具体例 RC 回路に交流電流をかけること:
t = 0から V = V0 cos ω t の交流をかける。
C
右回りに流れる電流を正方向とし、
R
V
コンデンサーの左側にたまった電荷を
L(コイル)
Qとして
Q
+ RQ + Q = V cos ω t = ReV eiω t
+ RQ + LI = LQ
0
0
C
C
t
+ Q + ω 2 Q = ReV eiω、 Q
ω 02 = 1 / LC 。
τ L = R / L 、 すなわち 0
0
τL
一般論より特解Q1は
Q1 = (D 2 + D / τ L + ω 02 )−1 Re
V0 iω t
(V0 / L)eiω t
e = Re 2
L
ω 0 − ω 2 + (iω / τ L )
と求められる。
よって一般解は
Q=
V0 [(ω 02 − ω 2 )cos ω t + (ω / τ L )sin ω t]
L[(ω − ω ) + (ω / τ L ) ]
2
0
2 2
2
−(t /2τ L )
+e
[ Acos ω 1t + Bsin ω 1t]
となる。そして初期条件Q(0) = 0、I(0) = 0より
V0 (ω 02 − ω 2 )
L[(ω − ω ) + (ω / τ L ) ]
2
0
2 2
2
+ A = 0,
V0 (ω 2 / τ L )
L[(ω − ω ) + (ω / τ L ) ]
2
0
2 2
2
−
A
+ ω1 B = 0
2τ L
となる。
*減衰振動系において周期的な「外力」がかかっているならそ
の外力にf -1(D)を作用させて得られる特解が、そのまま t が大
なる時の解になる。系の減衰定数をγ として
では同次
方程式の一般解は無視できるからである。(同次方程式の一
般解は過渡現象を表す)
11
14.11.6
応答関数
固有角振動数 ω0、減衰定数 γ に対する角振動数 ω
の 減衰振動
f = f0 eiω t ⇒ x = χ (ω )( f0 / ω 02 )eiω t
|χ|
#
χ (ω ) =
argχ ω 02
(ω 02 − ω 2 ) + iγω
"
!
"
#
ω/ω0
共鳴現象の扱い
iω t
摩擦が無い場合: x + ω 02 x = Ae 0 の特解をどう求めるか?
1
1
1 iω t
iω t
iω t
e 0 =
e 0 = e 0
2
2
f ( D)
0
(iω 0 ) + ω 0
x + ω 02 x = Aeiω t ,ω ≠ ω 0 を解いて
ではどうする? うまい特解を作った後 ω → ω 0 の極限を取る。(他の方法
でも解ける)
⎡ eiω t − eiω 0t ⎤
A ⎡ iω t
−A
iω t
⎣⎢
⎦⎥
e − e 0 ⎤⎥ =
2
2 ⎢⎣
⎦ ω + ω ω −ω
ω 0 −ω
0
0
−iAt iω 0t
→ω 0
⎯ω⎯
⎯
→
e
2ω 0
12
© Copyright 2024