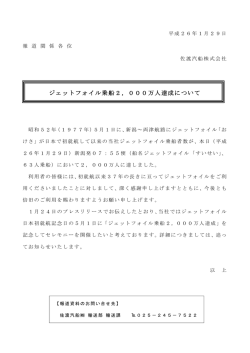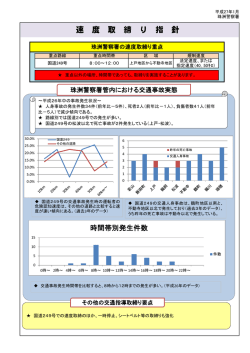日本経済中期見通し(2015-2024年度)
2015年3月20日 明治安田生命 日本経済中期見通し(2015-2024年度) ~ サービス産業の生産性上昇が持続的成長の鍵を握る ~ 明治安田生命保険相互会社(執行役社長 根岸 秋男)は、2015-2024年度の中期経済見 通しを作成いたしました。 主要なポイントは以下のとおりです。 要 点 ①【成長率】向こう10年の日本経済は均せば1%台前半を中心とした成長が続くと予想する。足元 で前年比+0.5%前後まで落ち込んでいると考えられる潜在成長率は、女性と高齢者の労働参加 率の上昇や、生産性の改善を受けて、緩やかに上向くとみる。 ②【財政・経常収支】財政再建に向けた動きは鈍く、東京オリンピックを控え、むしろ一段の財 政支出拡大も考えられるため、プライマリーバランスの黒字化には至らないと予想する。貯蓄・ 投資バランスは、家計が2010年代後半に投資超過に転じるとみられるほか、企業の貯蓄超過幅 も次第に縮小するとみる。経常収支は、2020年代前半までに恒常的な赤字に転じよう。 ③【物価・金融政策・長期金利】物価上昇ペースは鈍く、予想期間内に日銀の物価目標である2% の安定的な達成は困難とみる。金融政策については、2016年~2017年に、日銀による国債の買 入れ額が縮小へと方向転換を強いられる可能性が高い。金融緩和政策のペースが緩められるこ とで、長期金利も上昇傾向に転じると予想する。 ④【海外経済】米国経済は、生産年齢人口の増加などが下支えとなり、緩やかな回復が続くとみ る。ユーロ圏経済は、債務問題の鎮静化と周辺国の競争力改善により、回復へ向かうと予想す る。中国は、高度成長から安定成長へ移行しよう。新興国は、国内産業の育成が遅れ、中所得 国の罠に陥ることが懸念される。今後、インド・タイ・マレーシアが成長国として期待される。 ⑤【リスクシナリオ】東京オリンピックが財政不安を助長する可能性には警戒が必要。スタグフ レーション的状況が長期化するリスクシナリオの示現確率は15%。 〈主要計数表〉 2009-2013年度 2014-2024年度 実績 2014-2018年度 2019-2024年度 実質成長率 1.0% 1.1% 0.8% 1.3% 成長率寄与度・内需 1.2% 0.8% 0.6% 0.9% ・外需 ▲0.2% 0.3% 0.2% 0.4% ▲0.2% 1.9% 1.6% 2.2% 名目成長率 1.世界経済の現状と見通し たバランスシート調整が大幅に進展してきたこ 実質GDP とが大きい(図表 1-2) 。加えて、生産年齢人口 2014 -6 2013 た資産価格の上昇に伴い、個人消費を抑制してき 2012 -4 2011 米国景気の回復要因としては、株価や住宅といっ 2010 -2 2009 に支えられ、力強さを増している(図表 1-1) 。 2008 0 2007 邦準備制度理事会)による異例の低金利政策など 2006 2 2005 4 症で低成長が続いていた米国経済は、FRB(米連 2002 住宅バブル崩壊に端を発する金融危機の後遺 (図表1-1)実質GDP成長率(前年比) % 2004 6 2003 (1)米国景気は緩やかな回復が続く 内需 (出所)米商務省 の増加が続いていることが、構造的な押し上げ要 150 因となっている。先進国諸国では少子高齢化によ り、生産年齢人口が伸び悩んでいることが成長の 抑制要因となっている。米国についても、1946 年~1964 年に生まれたベビーブーム世代の労働 市場からの退出や、出生率が人口置換水準である (図表1-2)家計資産、負債残高の推移 % % 850 130 800 120 750 110 700 100 650 90 600 生産年齢人口に限ってみると、移民の受け入れを 家計負債/可処分所得 家計資産/可処分所得(右軸) (出所)FRB、米商務省より明治安田生命作成 行なっていることもあって、増加基調を維持して いる(図表 1-3)。国際連合が発表している人口 2500 動態の推計によると、中位で推移した場合、2025 年までに約 400 万人の生産年齢人口の増加が見 2000 込まれており、予想期間中の成長を押し上げると 1500 みられる。 1000 550 14/03 12/03 10/03 08/03 04/03 02/03 00/03 98/03 96/03 94/03 92/03 景に、人口ボーナス期 1を越えつつある。ただ、 90/03 70 06/03 黒線は家計負債/可処分所得の 1980年-1999年トレンド 80 2.1 人を下回る水準が続いていることなどを背 900 140 500 1980-1999年トレンド (図表1-3)各国の生産年齢(15-64歳)人口の推移 万人 予想値 一方、労働分配率の推移を見ると、1970 年代 500 以降、低下が続いている(図表 1-4) 。背景には、 ストを削減しながら、積極的な設備投資や M&A フランス 英国 カナダ ドイツ 日本 2030 2025 2020 2015 2010 2005 2000 1995 1990 1985 1980 1975 1970 1965 1960 1950 1955 0 技術革新が進むなか、企業は人件費などの生産コ 米国 (出所)国連より明治安田生命作成 などにより成長を続けてきたほか、コーポレート ガバナンス(企業統治)が徹底されている米国で (図表1-4)労働分配率の推移と上位所得者1%の全体に占める 収入(キャピタルゲインを含む)比率の推移 % % は、株主が強い影響力をもっていることを受けて、 63 収益を株主へと高配当で還元してきたことがあ 60 25 る。加えて、家計部門の内部では、技術水準の向 57 20 上により、高スキルを保持する労働者とスキルを 54 15 有さない労働者との間で、所得格差の拡大が続い 51 10 ている。家計の資産から負債を控除した純資産を 48 見ると、中央値と平均値に大きな差があるほか、 45 (出所)米商務省、The World Top Income Database 1 従属年齢(0~14歳人口+65歳~人口)に対する生産年齢人口(15歳~64歳)比率が高く、労働力が豊富な時期 2 2011 5 2008 2005 2002 1999 1996 1993 1990 1987 1984 1981 1978 1975 1972 1969 1966 1963 労働分配率 収入(キャピタルゲインを含む)比率の推移(右軸) 収入(除.キャピタルゲイン)比率の推移(右軸) 30 0 ※HPフィルターで標準化 (図表1-5)家計資産の中央値・平均値の推移 足元では差がさらに開く傾向にある (図表 1-5) 。 千万ドル 7 低中所得者層が保持する資産の内訳を見ると、住 6 居用の住宅比率が高い一方、富裕層については、 5 住居以外の不動産や金融資産比率が高くなって 4 約6.6倍 3 いる。一部からは、FRB による金融緩和が、金融 米国経済は回復傾向が続くとみられる。ただ、労 中央値 2013 2010 平均値 ※ここでの資産は、家計の資産から負債を 控除した純ベースでの資産を指す (出所)FRB 働分配率の低迷や、所得格差の拡大を背景に、中 2007 2004 2001 今後も、生産年齢人口の増加が下支えとなり、 1998 0 1995 いう見方もある。 1992 1 1989 2 資産価格を押し上げ、格差拡大を助長していると (図表1-6)ユーロ圏各国の競争力指数(単位労働コストベース) 1999Q1=100 140 低所得者の購買力の改善ペースは鈍いものにと どまることが予想され、向こう10年の米国景気は 130 均せば緩やかな回復にとどまるとみる。 120 ↑競争力低下 ↓競争力上昇 110 (2)本格的な回復には程遠いユーロ圏経済 100 ユーロ圏経済は、アイルランドやスペイン、ポ 90 ルトガルでEU(欧州連合)の金融支援が終了した 州債務危機後の混乱期から脱しつつある。周辺国 を中心に対外競争力の改善が進んでおり、域内不 (出所)ECB 均衡の蓄積によるユーロ崩壊の可能性も低下し 100 ている。ただ、南欧を中心とした緊縮財政の継続 50 や、民間部門のバランスシート調整圧力などを背 0 景に、成長率は長期にわたって低水準にとどまる -50 14/03 13/03 12/03 11/03 10/03 09/03 08/03 07/03 06/03 05/03 04/03 03/03 02/03 01/03 00/03 99/03 80 ほか、2014年にはマイナス成長を脱するなど、欧 ユーロ圏 ギリシャ スペイン スロベニア ポルトガル アイルランド (図表1-7)ユーロ圏周辺国の経常収支 十億ユーロ -100 と予想する。 -150 スペインやアイルランド、ギリシャなど一部の ポルトガル 降、改善基調で推移しており、今後は輸出の持ち イタリア フランス スペイン ギリシャ アイルランド (出所)ユーロスタット 直しにつながるとみている(図表1-6) 。 30 欧州債務危機が深刻化した要因である各国経 (図表1-8)ユーロ圏各国の失業率 % 25 常収支の不均衡にも改善がみられる。経常収支の 0 ペインなどが経常黒字に転じている(図表1-7)。 ユーロ圏 スペイン ただ、実体経済は依然として弱く、域内の経済 (出所)ユーロスタット 不均衡は拡大している。雇用環境を見ると、ドイ 3 ドイツ イタリア 14/01 背景に、アイルランドやギリシャ、イタリア、ス 13/01 5 12/01 たものの、危機後は緊縮財政や輸出の持ち直しを 11/01 10 10/01 は、金融危機前まで経常赤字が大幅に拡大してい 09/01 15 08/01 ンド、イタリア、ポルトガル、スペイン)などで 07/01 20 推移を見ると、GIIPS諸国(ギリシャ、アイルラ ギリシャ フランス 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 府の労働市場改革への取組みを背景に、2010年以 2002 -300 2001 -250 労働コストベースの競争力指数を見ると、各国政 2000 -200 周辺国では、対外競争力に改善がみられる。単位 ツの失業率が低水準で推移している一方、解雇規制が緩和されたスペインやギリシャなどは、競争 力改善の代償として失業率が高止まりしたままである(図表1-8)。今後も長期にわたって不安定な 雇用環境が消費の下押し圧力となるとみられるほか、住宅価格の下落を受けた民間部門のバランス シート調整の進展が緩慢であることもあって、域内消費の本格的な回復にはまだ時間を要するとみ ている。 (図表1-9)真のEMU(経済通貨同盟)に向けての諸段階 財政の持続可能性の確保および 銀行と財政の連鎖を遮断 EUおよびユーロ圏の統合深化を巡る 議論が停滞していることも懸念材料で 金融統合の枠組み完成および 国家レベルでの健全な構造政策 の促進 銀行監督一元化制度の創設および単一規則書(自己資本基準)の遵守 ある。2012年12月にEUのファンロンパイ 大統領(当時)が「真のEMU(経済通貨 各国預金保険制度の調和 金融統合 国別銀行破綻処理制度の調和 財政ガバナンスの強化(シックスパック、ツーパック、TSCGなど) 報告書では、欧州債務問題に伴う金融不 構造改革の契約に基づく金融 支援 財政統合 一時的・柔軟・対象 を絞った支援を実施 され、EUが今後めざすべき構造改革の方 向性が打ち出された(図表1-9) 。同報告 適切な危機防止装置を備えた単一の銀行破綻処理制度の創設 欧州安定メカニズム(ESM)によ る銀行への直接公的資金注入 枠組みの創設 同盟)に向けて」と題して発表した最終 安の解決、収束に向けた作業工程表が示 国別の経済危機などのショックを 吸収するための財政能力の確立 条件への適合 で参加を認める 継続的な条件適合 を参加条件とする ユーロピアンセメスターとの統合 経済統合 経済政策改革のための事前調整枠組みの創設 書では、金融統合(銀行同盟) 、財政統 民主的正当性と説明責任の進展 政治統合 合、経済統合、政治統合を4つの柱とし ステージ2 2013年-2014年 ステージ1 2012年末-2013年 て掲げており、そのなかでも金融統合 (銀行同盟)が構造改革の土台となって 国別の経済危機などのショックを 吸収する機能の創設 ステージ3 2014年以降 (出所)欧州委員会「真のEMUに向けて」より明治安田生命作成 いる。金融統合(銀行同盟)は、銀行監督や銀行破綻処理制度、預金保険制度の一元化をめざすも のであり、銀行経営に対する監視を強化するとともに、危機時の銀行救済と国家財政の信用不安が 連動する負の連鎖を断ち切るねらいがある。銀行監督の一元化は、ほかに先駆けて2014年11月から 実行されているものの、銀行破綻処理制度と預金保険制度の一元化については、各国間の意見対立 が深刻で、議論が先送りされているのが現状である。また、財政統合では、財政規律や予算監視の 強化などを進めるほか、将来的には、債務残高の一部をユーロ圏で共同管理・償還する償還基金の 創設や、各国の国債に代わるEUやユーロ圏の共同債の導入も検討するとされている。このうち、財 政規律や予算監視の強化については、すでに一定の進展がみられる。しかし、EUやユーロ圏の財政 危機の連鎖に歯止めをかける効果を持つと期待されている共同債の導入については、南欧諸国の放 漫財政につながり、モラルハザードを起こしかねないほか、自国の財政負担が増加する恐れがある として、ドイツが強く反対している。ただ、欧州債務問題の再発防止と圏内経済の持続的成長のた めには、各国が利害対立を乗り越えて一段の経済、財政統合に向けた努力を今後も続けていくこと が望まれる。国民の間で緊縮疲れが広まっていることなどを背景に、各国で反統合深化やEU離脱の 世論が高まるなど、難しいかじ取りを迫られる なか、低成長が長期化することへの危機意識か 15 ら、今後、EUの統合深化を巡る議論が再び活発 (図表1-10)中国実質GDP成長率の推移(前年比) % 14 13 化することが期待される。 12 11 10 (3)産業構造の転換を迫られる中国 9 鄧小平以来の改革開放路線を受け、2011 年ご 8 ろまで高成長が続いた中国経済であるが、2014 6 7 (出所)中国国家統計局 4 14/12 13/12 12/12 11/12 10/12 09/12 08/12 07/12 06/12 05/12 04/12 03/12 02/12 00/12 向が続いている(図表 1-10) 。全国人民代表大会 01/12 5 年の実質 GDP 成長率は前年比+7.4%と、鈍化傾 (全人代)で設定される実質経済成長率の目標 (図表1-11)中国全人口に占める農村・都市人口の割合の推移 は、2004 年から 2011 年まで、同+8.0%とされ % 100 90 ていたものの、 2012 年から 2014 年は同+7.5%、 80 2015 年には同+7.0%前後へと引き下げられた。 70 中国政府は、これまでの過度な投資に依存した 50 成長モデルから脱却し、安定成長に重点を置い 30 60 40 20 た成長モデルへの転換をめざしている。 10 予想値 同様、農村の過剰な労働力が都市部に流入する 農村人口割合 2050 2045 2040 2035 2030 2025 2020 2015 2010 2005 2000 1995 1990 1985 1980 1975 1970 1965 1960 1950 中国では、ほかの新興国が発展してきた過程 1955 0 都市人口割合 (出所)国連より明治安田生命作成 なかで、労働集約的産業を中心に経済発展を遂 げた。さらに 2001 年には WTO(世界貿易機関) に加盟したことで、輸出産業を中心に成長を加 75 速させ、 「世界の工場」としての地位を築き上げ 70 るに至った。ただ、足元では、農村から都市部 (図表1-12)各国の総人口に占める生産年齢人口の割合 % 65 への余剰労働力の流入が止まる「ルイスの転換 60 点」を迎えたことに加え、人口ボーナス期の終 焉という二つの転換点を迎えつつある(図表 55 1-11,12) 。 50 賃金上昇圧力はより強まるとみられ、これまで 中国 日本 ドイツ 2050 2045 2040 2035 2030 2025 2020 2015 2010 2005 2000 1995 1990 1985 1980 1975 1970 1965 1960 1955 今後、人口オーナス期 2への移行が進むなか、 1950 予想値 米国 (出所)国連より明治安田生命作成 のような労働集約的な低付加価値産業における 80 比較優位性は次第に失われるとみられる。加え て、これまで過剰投資を可能にしていた貯蓄も、 労働力人口の減少に伴い、減少していくこと 3が % (図表1-13)中国のGDPに占める最終消費・資本形成の割合 70 60 50 業で国有企業が支配的な地位を占めていること 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 過剰投資が続いてきた要因として、多くの産 資本形成 1996 0 最終消費 1994 10 1992 ことが必要である(図表 1-13) 。 1990 20 1988 率化による持続可能な安定成長へとシフトする 1986 30 1984 過剰投資・生産による成長から、資源分配の効 1982 40 1980 予想される。同国が成長を維持させるためには、 (出所)中国国家統計局 が挙げられる。国有企業は、国有銀行からの資金調達や税制面などから優遇されており、民間や外 国資本への市場開放が進むなかでも、依然として各種産業において大きなシェアを占めている。市 場経済化の遅れや、高成長維持を目的とした地方政府の介入などを背景に、国有企業はこれまで過 剰な設備投資を行なってきた。産業構造の転換をめざす中央政府は、過剰生産設備の淘汰を進めて いるものの、改善ペースは緩慢なものにとどまっている。今後、習近平政権には、強固なイニシア チブのもとで、産業再編を断行することが求められる。予想期間中は平均して 6.0~6.5%の成長を 予想する。 2 少子高齢化による生産年齢人口に対する従属年齢の比率が上昇し、財政・経済的な負担が拡大する時期 ライフサイクル仮説に基づくと、個人は、その個人が一生の間に消費できる所得の総額(生涯所得)の現在価値を制約条件とし て、長期的な効用の現在価値を最大化するような消費行動計画を立てる。そのため、高齢者は貯蓄を切り崩して、消費すること から、貯蓄率が低下するため、中長期的には少子高齢化は家計貯蓄率の低下に大きな影響を与える。 3 5 (4)中所得国の罠が懸念される新興国 新興国経済は、2000 年から 2010 年にかけて、 (図表1-14)資源国の実質GDP成長率 % 20 15 リーマンショックの影響を受けながらも、先進 10 国の金融緩和を背景とした資金流入などに支え 5 られ、高成長が続いてきたが、足元では明暗が 0 分かれつつある。 -5 ブラジルを筆頭に、石油や鉱物などの天然資 -10 源に恵まれ、一次産品の輸出に依存して成長を ブラジル 資源国では、成長ペースの減速傾向が続いてい チリ ロシア ベネズエラ 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1994 遂げた南米諸国や、ロシア・南アフリカなどの 1992 1990 -15 南アフリカ (出所)世界銀行 る(図表 1-14) 。これらの国々では、2000 年以 20 降の中国経済の急成長を原動力に、資源輸出や 15 資源関連の開発の増加を通じ、5%前後の実質成 10 長率を維持してきた。ただ、2011 年をピークに 5 中国景気が減速に向かうなか、いわゆるコモデ 0 ィティの「スーパーサイクル 4」に陰りが見られ、 (図表1-15)非資源国の実質GDP成長率 % -5 -10 資源需要の後退による商品価格の下落に連動す インド フィリピン る。 メキシコ ベトナム 2012 2010 2008 2006 2004 2002 2000 1998 1996 1994 1992 1990 -15 る形で、経済成長のペースも鈍化に向かってい マレーシア 中国 (出所)世界銀行 一方、労働集約的な産業などを中心に発展し てきた ASEAN 諸国や、インド・メキシコといった非資源国は、5%付近で安定した伸びを維持してい る(図表 1-15) 。これまで安価で大量な労働力を活用し、 「世界の工場」として君臨してきた中国の 賃金上昇が続いていることから、ASEAN 諸国を中心に、中国に代わる生産拠点としても注目されて いる。また、一国の消費市場としての規模を示す高所得・中間所得層人口の推移を見ると、2023 年 にはインドネシアの高所得・中間所得層が 2 億人を超えると予想されるほか、フィリピンでも同層 が 8,000 万人を超える見込みである。購買力の高い高所得・中間所得層の広がりによる需要サイド の増強に支えられ、最終消費地としての魅力上昇も期待されよう。 今後も、世界経済のけん引役として新興国の成長持続が期待されるものの、いわゆる「中所得国 の罠 5」に陥る可能性も懸念される。中所得国の罠とは、成長発展段階にある国が、労働集約的な産 業や資源輸出などに依存する形で高成長を遂げるものの、産業構造の高度化が進まず、一定のとこ ろで成長ペースが頭打ちになってしまい、高所得国へ移行出来ずに中所得国として停滞してしまう 状況を指す。中所得国の罠について提唱された「東アジアのルネッサンス」(2007 年)のなかで、 新興国が中所得国の罠を回避して、経済成長を維持するためには、①製品や人材の高度化を進め、 ②これまでの投資重視から技術革新を推進し、③新しい技術へ順応するためではなく、新しい製品 や過程を形作ることを目的とした教育システムを構築し、スキルを備えた労働者の育成が必要であ ると述べられている。 4 中国や新興国の急成長による需要拡大などを背景とした、2010年~2012年ごろの商品相場の価格上昇局面 2007年に「東アジアのルネッサンス」のなかで世界銀行が提唱。ここでは、IMF(国際通貨基金)における中所得 国・高所得国の定義に則り、中所得国の一人当たりGDP(購買力ベース)が3,000ドル~10,000ドル、高所得国は同 10,000ドル以上と定義する。 5 6 中所得国から高所得国へと転換することに成 1.2 功した国としては、韓国・台湾が挙げられる。 米国=1.0 (図表1-16)TFP(全要素生産性)の比較(アジア) 1.0 韓国は、造船や輸送機器、電子機器産業などを 0.8 中心とした工業化の発展により成長を遂げてき マレーシア インドネシア 維持している(図表 1-16)7。台湾は、電子・電 フィリピン インド タイ 中国 2010 2005 2000 1995 1990 1985 1980 1975 降上昇傾向で推移し、80 年代以降も高い水準を 1970 0.2 1965 場合のTFP(全要素生産性) 6を見ると、60 年以 1960 0.4 1950 ーブルをもとに算出された、米国を 1.0 とした 1955 0.6 た。ペンシルバニア大学のペン・ワールド・テ 台湾 韓国 (出所)グローニンゲン大学 気機器産業といった高付加価値製品の製造など (図表1-17)一人当たりGDP(購買力平価ベース)が 3,000ドルに達した後の推移 千ドル がけん引役であるが、TFPは 80 年代後半以降、 一人当たり GDP ( 購買力平価ベース) 21 米国と同水準で推移している。一方、中所得国 にとどまっている国のTFPの推移を見ると、多く の国は 80 年代でピークを迎え、2000 年代後半以 降については、米国の 3 割~5 割程度にとどまっ ており、TFPの伸び悩みが、成長の足かせになっ ている可能性を示している。 35 17 31 15 27 13 23 11 19 9 15 7 11 5 7 3 1 今後、成長が期待される国としては、インド・ 4 7 10 マレーシア 中国 タイ・マレーシアが挙げられる。インドは市場 千ドル 39 19 13 16 19 タイ インド 3 22 25 28 31 34 3,000ドルに達してからの経過年数 インドネシア 韓国(右軸) (出所)IMF 規模が大きく、また人口の増加が続いており、 市場の拡大が見込まれるほか、TFP も 2000 年以降上昇傾向にある。タイは積極的な外資誘致やイン フラの整備が成長を下支えするとみられる。マレーシアは、電子・電気機器産業などを中心とした 高度産業化が推進されており、すでに一人当たり GDP(購買力平価ベース)でも 1 万ドルを上回っ ていることから、いずれ先進国入りすることへの期待が高い(図表 1-17) 。ただ、成長を阻害して いる要因として、インドは電力供給が不安定であるほか、道路や鉄道といった物流インフラの整備 が遅れていることや、国民の約 3 割を貧困層が占めており、依然として識字率が低いなどといった 問題がある。そのため、今後インフラ整備や教育制度の充実を推進していくことなどが求められる。 タイでは、高齢化による労働力人口の減少が進みつつあり、低賃金産業に依存する成長モデルは持 続不可能である。今後、高度人材の育成などを通して、高度産業をさらに発展させることが、高成 長維持のために必要である。マレーシアでは、マレー系民族を優遇するなどの経済政策が、国際競 争力の足かせとなっていることから、市場の自由化を進めることが必要となろう。各国がより効率 的な資源配分を可能にすることで、国際競争力を高めつつ、国内産業の高度化を推進していくこと が求められよう。 6 全要素生産性(TFP)とは、経済成長を供給面から見たときに、労働生産要因、資本ストック要因によらない成長 要因。技術革新による効率化などが例として挙げられる。 7 出所:Feenstra, Robert C., Robert Inklaar and Marcel P. Timmer (2013), "The Next Generation of the Penn World Table" www.ggdc.net/pwt 7 2.日本経済の見通し (1)サービス産業の生産性上昇が重要 (図表2-1)名目GDPに占める産業別割合 1970年 日本の名目GDPに占める産業別割合を見ると、 1980年 製造業が低下基調となっている一方、運輸・情報 1990年 通信・サービス業や金融・保険・不動産業など 2000年 のサービス産業は拡大傾向で推移している(図表 2005年 2-1) 。背景には、所得水準の向上や余暇時間の増 2010年 2012年 加に伴う生活様式の変化で、サービス需要が高ま % 0 っていることがある。内閣府による「国民生活に 関する世論調査」を見ると、 「今後の生活の力点」 20 農林水産・鉱業 40 60 製造業 80 100 建設業 電気・ガス・水道業 卸売・小売業 金融・保険業・不動産業 運輸・情報通信・サービス業 その他 (出所)内閣府 として、自動車や電気製品、家具などの耐久消費 40 財よりも、レジャー・余暇生活などを挙げる人の (図表2-2)今後の生活の力点 % 35 割合が大きい(図表2-2) 。一方、「現在の生活の 30 各面での満足度」では、レジャー・余暇生活に対 25 20 する満足度は対象項目内で最低水準となってお 15 り(図表2-3) 、サービスに対する潜在的需要が大 10 きいことを示唆している。 5 電気製品 業の生産性上昇率は、製造業を大きく下回る(図 家具などの耐久消費財 2014 自己啓発・能力向上 自動車 2013 レジャー・余暇生活 2014 が見込まれるものの、サービス産業を含む非製造 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2001 2002 0 少子高齢化を背景に、今後も経済のサービス化 (出所)内閣府「国民生活に関する世論調査」 表2-4) 。そのため、産業の中心が製造業からサー 70 ビス産業へ徐々に移行するのに伴い、経済全体の 60 生産性上昇率が抑制され、長期的には、日本経済 50 の成長力が伸び悩むことが懸念される。 40 そこで、サービス産業の生産性上昇に向けた取 30 組みが重要となってくる。サービスはモノと異な 20 (図表2-3)現在の生活の各面での満足度 % 10 り在庫や輸送が困難で、市場の地理的範囲が限ら 耐久消費財 自己啓発・能力向上 住生活 (出所)内閣府「国民生活に関する世論調査」 あり(図表2-5) 、都市計画がサービス産業の生産 1.8 2012 2011 2010 2009 レジャー・余暇生活 口密度の高い地域ほど労働生産性が高い傾向に % 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2001 える。人口密度と労働生産性の関係を見ると、人 2002 0 れることから、立地先の需要が生産性に影響を与 (図表2-4)製造業・非製造業の生産性上昇率 1.6 性に影響することが示唆される。今後は、すでに 1.4 複数の都市で実行されている集約型の都市構造 1.2 (コンパクトシティ)の形成を進めることが重要 1.0 製造業 非製造業 0.8 となろう。コンパクトシティの効果として、サー 0.6 ビス産業の活性化に加え、訪問介護などの行政サ 0.4 ービスを効率的に提供することを通じ、財政支出 0.2 0.0 の抑制が可能になるなど、多方面から経済の持続 -0.2 的成長を後押しすることが挙げられる。 -0.4 1970-1980 一方、積極的なIT投資も、企業のイノベーショ 1980-1990 (出所)経済産業研究所より明治安田生命作成 8 1990-2000 2000-2011 ン(技術革新)を促進し、生産性上昇に寄与し 3.0 ていくとみられる。現状では、業務効率化など 2.8 の「守りのIT投資」が主で、製品・サービスの 2.6 (図表2-5)人口密度と労働生産性 労働生産性( 対数) 開発強化やビジネスモデル変革といった「攻め 2.4 2.2 のIT投資」は少ない。産業ごとのTFP(全要素生 2.0 産性)水準と新システム構築などの関係を見る 1.8 と、新規システム構築に積極的な製造業ほど生 1.6 産性が高い(図表2-6)。今後は、事業革新のた 1.4 めにビッグデータ、モバイル、クラウドなどの 1.2 4 IT新技術をどの程度活用しているのか、といっ 5 6 7 人口密度(対数) 新たなシステム構築またはシステムの再構築に 取り組んでいる企業の割合( %) ービス産業のIT投資への対応を変化させていく 電気機器 55 ことも重要である。 製造業 金融・保険 50 経済の持続的な成長には、産業の新陳代謝の 促進も必要である。市場経済において、企業の その他製造業 化学 卸売 電気・ガス・水道 40 よるイノベーションが促進され、経済全体の生 産性は高まる。ただ、日本の開業率・廃業率を 一般機械 輸送用機器 金属 45 新規参入と市場退出の頻度が高いほど、企業に 運輸・倉庫 サー ビス産業 小売 35 40 欧米諸国と比較すると、日本の水準は欧米諸国 50 60 70 80 90 100 110 120 TFP(全要素生産性)水準(米国=100) (出所)経済産業省「通商白書」、「情報処理実態調査」より明治安田生命作成 の半分程度にとどまっており、産業の新陳代謝 が進んでいないことが示唆される(図表2-7) 。 10 (図表2-6)産業別TFP水準と新システムの構築などの関係 60 進し、投資家など外部からの評価によって、サ 9 ※対象は都道府県及び一部の政令指定都市 (出所)国土交通省 た「攻めのIT投資」を評価する指標の策定を推 8 14 % (図表2-7)日米欧の開業率・廃業率比較(2001-2012年平均) ※米国は2001-2010 年平均、ドイツは2008-2011年平均 背景には、日本の事業環境の悪さがあるとみら 12 れる。世界銀行が発表している「Doing Business 10 2015」によると、日本における事業活動のしや 8 すさは189ヵ国中29位と、ほかの先進国(OECD 6 加盟国)と比較して低く、内訳を見ると、事業 4 開業率 廃業率 設立や建設許可取得、納税などの項目が上位10 2 ヵ国の平均を下回る水準となっている(図表 0 2-8)。今後は、参入規制の緩和や事業設立に要 ドイツ 米国 する手続きの短縮に加え、法人税引き下 ( 事 業 総 の 合 し 順 や 位 す さ 税制改正の推進が期待される。産業別で 建 設 許 可 取 得 事 業 設 立 ) は、高齢化が進むなかで、需要がさらに の生産性改善が特に重要となろう。ただ、 英国 日本 (図表2-8)事業環境の国際順位比較 げや先端設備投資への減税措置といった 高まると見込まれている医療・介護分野 フランス (出所)中小企業庁資料より明治安田生命作成 電 気 取 得 財 産 登 記 投 資 家 保 護 資 金 調 達 国 境 貿を 易越 え た 納 税 契 約 執 行 破 綻 処 理 シンガポール 1 6 2 11 24 17 3 5 1 1 19 ニュージーランド 2 1 13 48 2 1 1 22 27 9 28 25 香港 3 8 1 13 96 23 2 4 2 6 医療・介護分野は公共性が高いとの理由 デンマーク 4 25 5 14 8 23 17 12 7 34 9 韓国 5 17 12 1 79 36 21 25 3 4 5 で、現在は国によるさまざまな規制がか ノルウェー 6 22 27 25 5 61 12 15 24 8 8 米国 7 46 41 61 29 2 25 47 16 41 4 かっている。生産性の高い企業による市 英国 8 45 17 70 68 17 4 16 15 36 13 フィンランド 9 27 33 33 38 36 76 21 14 17 1 10 7 19 55 53 4 71 39 49 12 14 20.4 17 33.1 40.2 22 23.2 20.6 15.8 16.8 12.6 83 83 28 73 71 35 122 20 26 2 場への新規参入を促すためには規制緩和 が必要であり、政府には一段の岩盤規制 オーストラリア 上位10ヵ国平均 日本 29 (出所)世界銀行「Doing Business 2015」より明治安田生命作成 9 への切り込みが求められる。 (図表2-9)世界の輸出額に対する日本の輸出額の占率 % 30 25 (2)製造業の高付加価値化 代には、電気機器や輸送機器、精密機械が全体の 0 2割以上を占めていたものの、足元ではそれぞれ 全体の1割程度まで低下している(図表2-9) 。 2010 5 2005 からの輸出額のシェアを製品別に見ると、1980年 2000 10 1995 ェアは後退している。世界の輸出額に占める日本 1990 15 1980 あるなか、世界全体で見ても、日本の製造業のシ 1985 20 産業全体に占める製造業の割合が低下しつつ 輸送用機器 一般機械 電気機器 化学製品 精密機械 産業計 (出所)「REITI-TID」より明治安田生命作成 背景には、東アジア諸国の技術面でのキャッチ (図表2-10)日本と主要国との競合性(貿易相関指数) 0.8 アップが、日本製品の国際競争力低下につながり、 0.6 シェアの低下をもたらしている面があるとみら 競合的 0.4 0.2 貿易相関指数を見ると、日本の場合、米国やドイ 0.0 国の産業高度化のペースが早く、高付加価値製品 の輸出が増加しているため、結果として日本と貿 易構造が似通ってきている。 中国 台湾 韓国 ドイツ 英国 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 -0.4 性も年々高まっている(図表2-10)。東アジア諸 1998 ほか、韓国や台湾といった東アジア諸国との競合 1997 -0.2 1996 ツなどの先進工業国との競合性が一貫して高い 補完的 て、UNCTAD(国連貿易開発会議)が発表している 1995 れる。二国間の貿易構造の類似性を示す指標とし 米国 (出所)UNCTAD (図表2-11)貿易特化係数 0.35 0.30 0.15 0.10 1999年代後半から金融危機前まではほぼ横ばい で推移していたものの、2009年以降はやはり大き く低下している。BIS(国際決済銀行)が公表し ている実質実効為替レートを見ると、2009年から 2012年まで安定した推移が続いていたことから、 鉱物性燃料の輸入や為替変動による影響を除い ても、近年、製造業の競争力悪化が顕著となって いることが示唆される。製品別に見ると、自動車 貿易特化指数 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 -0.10 物性燃料の輸入を除いた貿易特化係数を見ると、 ※貿易特化係数=(輸出―輸入)÷(輸出+輸入) +1に近いほど輸出競争力が強く、逆に-1に近いほど輸出競争力は弱い 1998 入額の増加が指摘されることが多い。そこで、鉱 -0.05 1997 0.00 1996 石油やLNGなどの鉱物性燃料の価格高騰に伴う輸 1995 0.05 1994 貿易特化係数に大きな影響を与えた要因として、 1993 で推移している(図表2-11) 。2000年代前半以降、 0.20 1992 化係数の推移を見ると、1990年代以降、低下傾向 0.25 1991 また、輸出品の他国との比較優位を示す貿易特 貿易特化指数(鉱物性燃料輸入除く) (出所)財務省 (図表2-12)製品別の貿易特化係数 1.0 0.8 0.6 0.4 0.2 0.0 -0.2 -0.4 -0.6 -0.8 っているものの、通信機や映像・音響機器、半導 体等といった電気機器は、2009年ごろから国際競 争力を失いつつある(図表2-12) 。 -1.0 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 を中心に輸送用機器は一貫して高い競争力を保 一般機械 電気機器 映像・音響機器 通信機 家庭用電気機器 半導体等 輸送用機器 自動車 (出所)財務省 10 (図表2-13)各国の研究開発費(R&D)比率(2011年) % 4.5 日本の製造業が競争力を高めるには、研究開 4.0 R&D/GDP 発(R&D)を通じた技術革新による製品の高付 3.5 加価値化が必要である。人口減少などを背景に、 3.0 潜在成長率の低下が懸念されていることから 2.5 も、技術進歩に貢献する研究開発の重要性は高 2.0 企業R&D/GDP 政府負担R&D/GDP 1.5 い。ただ、日本の研究開発の現状を見ると、GDP 1.0 に占める研究開発の割合は海外諸国のなかで 0.5 は高いものの、民間企業が中心となっており、 また、研究開発費を分野別に見ると、日本は基 ロシア 英国 中国 フランス 米国 ドイツ 日本 韓国 0.0 他国と比べて政府の支援は少ない(図表2-13) 。 (出所)文部科学省「科学技術要覧」 (図表2-14)性格別研究費割合(%) 礎研究の割合が低く、商品設計や複数の技術を 基礎研究 組み合わせる応用・開発研究が中心となって 応用研究 開発研究 フランス 25.3 38.0 32.8 ロシア 19.6 18.8 61.6 基礎研究が重要といわれているが、基礎研究に 米国 19.0 17.8 63.2 は、多額の資金がかかるうえ、成果として表れ 韓国 18.2 19.9 61.8 るまでの時間や収益性などに不確実性がつき 日本 14.8 22.9 62.3 ものである。収益性が求められる企業の取組み 英国 8.9 40.7 50.4 だけでは限界があることから、産学官連携によ 中国 5.2 16.8 78.0 る効率的な資金活用や、研究施設の共同利用、 (出所)文部科学省「科学技術要覧」 いる(図表2-14)。画期的な新技術や新製品を 生み出す「プロダクト・イノベーション」には 人材育成のほか、研究開発費補助金の拡大など 40 が、製造業の国際競争力改善の鍵を握るとみて (図表2 -15) 経常収支の推移 兆円 30 いる。 20 10 (3)経常収支は2020年代前半までに赤字転換 の原子力発電所の停止に伴い、不足分を火力発 100 電で補っており、液化天然ガス(LNG)を中心 第一次所得収支 誤差脱漏 経常収支 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 サービス収支 第二次所得収支 (図表2-16) 貿易収支の推移 兆円 80 に燃料輸入費が急増していることなどを背景 60 に、2011 年以降、貿易赤字が恒常化している(図 20 表 2-16) 。円安が進み始めた当初は、円高が解 -20 40 0 消することで輸出数量が改善し、輸出は持ち直 -40 -60 しに向かうと考えられていた。ただ、2012 年後 輸出の回復ペースは鈍いものにとどまってい 輸入(鉱物性燃料) (出所)財務省「貿易統計」 現行の統計方法となった 1996 年以降 11 輸入(除く鉱物性燃料) 輸出 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 -100 1997 -80 半以降、円安局面が続いているにもかかわらず、 8 2002 貿易収支 (出所)日銀「国際収支統計」 1996 まず、貿易収支を見ると、東日本大震災以降 2001 。 字幅は縮小傾向が続いている 8(図表 2-15) 2000 -20 1999 赤字の拡大が続いていることで、経常収支の黒 1998 -10 1997 は、所得収支が黒字を維持している一方、貿易 1996 0 リーマンショック以降、経常収支(年ベース) 貿易収支 ※2014年は速報値 る。背景には、企業が生産拠点の現地化を進めて いることや、電機・電子機器分野といった主力輸 2010年平均=100 (図表2-17)輸出物価指数の推移 170 円/ドル 170 160 150 150 140 140 130 130 120 120 コストの上昇が続いており、企業が価格引き下げ 110 110 100 100 を抑制していることも挙げられる(図表 2-17)。 90 90 80 80 契約通貨ベースで見ると、輸出物価指数は小幅な 70 70 出品目の国際競争力の低下があるとみられる。ま た、国内では円安や労働需給のひっ迫による生産 低下にとどまっており、価格の引き下げに踏み切 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 160 輸出物価指数(契約通貨ベース) る動きに広がりが欠ける様子がうかがえる。今後、 中長期的には東アジアなどの後発国による技術 面でのキャッチアップが進むと考えられること (出所)日本銀行「企業物価」、「外国為替市場」 140 (図表2-18)地域別訪日外国人客数 万人 アジア計 もあり、貿易赤字トレンドが続くと予想する。 輸出物価指数(円ベース) 円/ドル(右軸) その他 % 250 前年比(右軸) 60 50 「旅行収支」の赤字幅は縮小傾向が続いている。 40 0 ビザ要件の緩和のほか、円安や免税対象商品の品 20 -50 目拡大などを背景に、訪日外国人旅行客数が増加 0 -100 しており、2013 年度には 1,000 万人を突破した 14/07 化を受け、2 年連続の赤字幅拡大となった。ただ、 14/01 100 13/07 80 13/01 の赤字幅拡大や「その他サービス収支」の赤字転 12/07 150 12/01 100 11/07 200 11/01 120 一方、サービス収支は、内訳である「輸送収支」 (出所)日本政府観光局(JNTO) (図表 2-18) 。今後、特許等使用料の受け取り額 の拡大や、訪日外国人旅行客数の増加などが見込 まれることから、サービス収支の赤字幅は縮小傾 20 (図表2-19) 第一次所得収支の推移 兆円 15 向に転じるとみる。 後も、企業のグローバル化が進むなかで、収益率 の高い直接投資の増加が見込まれ、所得収支は拡 大傾向での推移を予想する。 証券投資収益 直接投資収益 その他投資収益 第一次所得収支 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 -5 上げや、海外への直接投資の増加が寄与した。今 2002 った(図表 2-20) 。円安による資産価格高の押し 2001 0 2000 年の対外資産残高を見ると、2 年連続で増加とな 1999 5 1998 大幅な黒字基調を維持している (図表 2-19) 。 2014 1997 10 1996 第一次所得収支は、積極的な海外投資を背景に、 雇用者報酬 (出所)財務省「国際収支統計」 1000 (図表2-20) 対外純資産の内訳 兆円 800 (4)貯蓄投資バランスは家計が投資超過へ 600 200 きた家計部門だが、企業の人件費削減や少子高齢 化による労働人口の減少などを背景に、貯蓄率は 12 直接投資(資産) 直接投資(負債) 証券投資(資産) その他の投資(資産) その他の投資(負債) 外貨準備(資産) (出所)日銀「資金循環統計」 証券投資(負債) 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 高度成長期以来、恒常的に貯蓄超過を維持して 2003 -600 2002 過といった状況にある(図表 2-21) 。 2001 -400 2000 貯蓄超過であることから、IS バランスも貯蓄超 1996 -200 1999 0 家計、企業部門(非金融法人企業、金融機関)が 1998 ると、近年は一般政府が投資超過であるものの、 400 1997 経常収支を貯蓄投資(IS)バランスの側から見 低下傾向が続いている(図表 2-22) 。2025 年に (図表2-21) 各部門の資金過不足 80 兆円 は 65 歳以上の人口割合が人口全体の 3 割に達す 非金融法人企業 金融機関 ISバランス 慢とみる。 一般政府 対家計民間非営利企業 2013 2012 2011 2010 2009 2008 れることもあり、投資超過幅の拡大ペースは緩 2007 -60 2006 しよう。ただ、住宅投資も低調な推移が予想さ 2005 -40 2004 代の負担が増すことも投資超過への動きを助長 2003 -20 2002 引き上げや社会保障費の拡大により、労働力世 2000 0 2001 ることが避けられないとみている。消費税率の 1999 20 1998 あり、家計部門は予測期間内に投資超過に転ず 1996 40 1997 60 る超高齢化社会へと突入していくという事情も 家計 統計上の不突合 (出所)日銀「資金循環統計」 家計部門の貯蓄超過幅が縮小傾向にある一 (図表2-22)65歳以上の人口の比率と貯蓄率(1994年~2012年) 12 % 方、企業部門の貯蓄超過幅は拡大傾向にある。 設備投資や人件費の削減を行なってきたことで、 民間企業部門は 1990 年代に貯蓄超過に転じた。 足元では、低金利環境が続くなか、利払い費用 が抑制されていることも貯蓄超過幅の拡大要因 家計部門の貯蓄率( 調整貯蓄率) バブル期に積み上げた過剰債務の返済のため、 y = -0.879×[65歳以上人口比率] + 20.594 R² = 0.783 10 8 6 4 2 となっていよう。今後については、名目金利の 0 緩やかな上昇に伴い、利払い費は拡大していく -2 12 14 (出所)総務省、内閣府 ことが予想される。ただ、設備投資については、 国内市場の縮小に伴い、海外向けは拡大・強化 120 16 20 18 22 24 26 % 65歳以上人口比率 (図表2-23)対外直接投資残高 兆円 ※業種別内訳は2005年以降 が進むと予想されるものの(図表 2-23)、国内 100 向けは更新・維持にとどまるとみられることか 80 ら、企業部門の貯蓄超過幅は緩やかな縮小傾向 60 で推移するとみる。 投資超過幅は緩やかながらも縮小傾向で推移す 製造業 卸・小売業 金融・保険業 その他非製造業 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 率の引き上げなどによる税収の拡大が見込まれ、 2000 0 1999 う公共事業の増加が予想されるものの、消費税 1998 20 1996 は、社会保障費の拡大や東京オリンピックに伴 1997 40 国内唯一の投資超過セクターである政府部門 全体 (出所)日銀 るとみられる。同シナリオでは、消費税は 2014 年度(5%→8%) 、17 年度(8%→10%)に引き続 き、2024 年度までに 12%への引き上げを想定している。 中長期的な IS バランスの推移は、政府部門については投資超過幅の小幅な縮小が予想されるもの の、家計や企業を合わせた民間部門の貯蓄超過幅が縮小していくとみられることから、予測期間内 に投資超過方向に転ずると予想する。 (5)社会保障費が歳出の重石に 日本の政府債務残高は増加の一途をたどっており、2013 年 6 月には 1,000 兆円を突破、対 GDP 比 は 200%を超えている(図表 2-24)。近年の財政収支を見ると、歳出が拡大傾向にある一方、税収 が縮小基調で推移する、いわゆる「鰐口型」が特徴となっている(図表 2-25)。歳出拡大の最も大 きな要因は、少子高齢化に伴い、社会保障給付費が増加していく一方、社会保険料収入が伸び悩ん 13 でいることで、財源における国費の割合が高ま 250 っていることである。 国立社会保障・人口問題研究所のデータによ (図表2-24)各国の政府債務残高の推移(対GDP比) % 200 ると、2012 年度の社会保障給付費は 108.6 兆円 150 と、ここ 20 年で 2 倍程度(年平均+3.6%)に 100 まで増加しているのに対し、社会保険料収入は 61.4 兆円と、おおよそ 1.4 倍(年平均+1.7%) 50 の拡大にとどまっている(図表 2-26)。社会保 7 割程度を占めており、給付費の増加は高齢化 の進展による影響が大半である。一方、社会保 日本 米国 英国 イタリア ギリシャ ドイツ 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1995 1996 0 障給付費の内訳を見ると、高齢者関係給付費が フランス (出所)OECD 険料収入は、賃金上昇率の低迷などから、2005 120 年以降、厚生年金および国民年金の保険料率を (図表2-25)税収と国債発行額の推移(年度ベース) 兆円 100 年々引き上げているにもかかわらず、給付費と 80 比較すると増加幅は鈍いものにとどまっている。 60 社会保障給付費の財源は、社会保険料収入、国 税負担、地方税負担が主だったものであり、こ 40 のうち国税負担が一般会計歳出における社会保 20 障費に対応しているが、2015 年度(予算ベース) 建設公債 礎的財政収支対象経費における 4 割)を占める 特例公債 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 2001 2000 1999 1998 1997 1996 1995 1994 1993 1992 の社会保障費は約 31.5 兆円と、歳出の 3 割(基 1991 1990 0 一般会計税収 一般会計歳出 (出所)財務省 までに増加しており、財政赤字拡大の大きな要 120 因となっている(図表 2-27)。 兆円 (図表2-26)社会保障給付費と社会保険料収入(年度ベース) 100 歳出の重石となっている社会保障制度につい ては、2014 年 4 月に引き上げられた消費税の増 80 収分に加え、2017 年 4 月に引き上げが先送りさ 60 れた消費増税で得られる税収が、すべて社会保 40 障費の財源として充当される予定となっている。 社会保険料 20 社会保障給付費 ただ、社会保障給付費の純増額(給付額-負担 0 となっており、政府が消費税率 10%への引き上 (出所)社会保障・人口問題研究所 げで見込んでいる約 13.5 兆円 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 額)は、年間約 1.8 兆円(2000-2012 年度平均) (図表2-27)2015年度の一般会計歳出・歳入(当初予算ベース) の増収分も、7 年程度で費消す る計算となる。 高齢化がより顕著になるなか で(図表 2-28)、社会保障給付 費の拡大傾向は維持される 9と みるものの、マクロ経済スライ ドの発動に加え、将来的には、 国債費 24.3% 利払費等 10.5% 債務償還費 13.8% 社会保障費 基礎的 32.7% 財政収支 一般会計 対象経費 歳出総額 75.7% その他 9 63,420億円 9.9% ( 100%) 防衛 地方交付税 5.2% 交付金等 公共事業 16.1% 6.2% 文教及び 科学振興 6.2% 所得税 17.1% 公債金 特例公債 38.3% 32.0% 一般会計 法人税 歳入総額 11.4% 租税及び 9 63,420億円 印紙収入 ( 100%) 56.6% 建設公債 6.2% その他 収入 5.1% その他 10.4% (出所)財務省資料より明治安田生命作成 9 財務省の見通しによると、現行制度を維持した場合、2025年には145兆円に達するとの見込み 14 消費税 17.8% 年金支給開始年齢の引き上げや、医療・介護の (図表2-28)人口ピラミッドの関係 歳 効率化推進による保険料負担の軽減などに踏み 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 切らざるをえないとみられることから、増加ペ ースには徐々に歯止めがかかるとみている。 (6)利払い費は増加傾向を予想 金利上昇に伴う利払い費の増加も、今後の財 政健全化の足かせになるとみる。これまで日本 は債務残高がきわめて大きいにもかかわらず、 利払い費は他国と比較しても低く抑えられてき 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0 2014年 0 10 20 2024年 0 30 (出所)国立社会保障・人口問題研究所 「日本の将来推計人口(平成24年1月推計)」の中位推計による た。純利払い費と純政府債務残高の関係を OECD 5 加盟国について見ると、両者には概ね正の相関 10 20 (図表2-29)純利払い費と純債務残高(OECD加盟国との比較) イタリア 4 がある(図表 2-29)。これは純債務残高の増加 純利払い費( 対 務残高が増えることに伴う財政リスクプレミア 比、%) GDP ムが、金利上昇につながっているためである。 ただ、日本は低金利政策や日銀による国債買入 ポーランド 2 フランス ドイツ 1 フィンランド 0 -2 ギリシャ スペイン 日本 カナダ 韓国 -1 れの年限の長期化などを背景に、低金利環境が ポルトガル アイルランド 3 による純利払い費そのものの増加に加え、純債 30 十万人 ノルウェー y = 0.019x + 0.8601 -3 続いていることから(図表 2-30)、傾向線から -4 -250 下方にかい離している。一般会計における利払 -200 -150 -100 -50 0 50 純債務残高(対GDP比、%) 100 150 200 (出所)OECD、IMF い費と公債残高の推移を見ると、公債残高は 14 1980 年代以降、積み増し傾向で推移していたに % (図表2-30)OECD加盟国の長期金利(2010-2014年平均) 12 もかかわらず、利払い費は抑制された状況が続 10 いてきた(図表 2-31)。利払い費への影響を国 8 債残高と金利の二つの要因に分けて見ると、90 6 年代終盤から 2000 年代の前半にかけては、金利 2 る押し上げ効果を上回り、結果として利払い費 0 負担は軽減されていた。ただ、足元では日本の 金利低下余地が限界に近づきつつあることから、 金利低下による利払い費負担の軽減効果(金利 ギリシャ トルコ ポルトガル ハンガリー メキシコ アイスランド アイルランド ポーランド スロベニア スペイン ニュージーランド イタリア 豪州 韓国 スロバキア ベルギー チェコ ノルウェー 英国 フランス 米国 オーストリア カナダ オランダ フィンランド ルクセンブルグ スウェーデン デンマーク ドイツ スイス 日本 4 低下による押し下げ効果が、国債残高増加によ (出所)OECDより明治安田生命作成 ボーナス)は消滅しつつある(図表 2-32)。現 12 在は低水準にとどまっている金利が今後上昇に 10 転じた場合、国債残高の増加と相まって、利払 8 %、兆円 (図表2-31)利払費と公債残高(年度ベース) 兆円 700 600 い費負担は大きく拡大すると見込まれる。 500 400 6 利払い費に与える金利上昇の影響について、 300 4 10 ①国債の平均利回り が今後 10 年間横ばい、② 200 当社予測のプライマリーバランスを前提に、利 0 100 0 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 平均利回り毎年+0.1%、の 2 パターンにおいて、 2 公債残高(右軸) (出所)財務省 10 800 2013年度決算における、利払費を公債残高で除した値(1.09%) 15 利払費 金利 のもとで試算したところ、パターン②の利払い費は 2024 年に 30 兆円程度まで増大し、パターン①に比 して 15 兆円近く負担額に差が出ることが確認でき た(図表 2-33)。今後は、日銀による国債買入れが 縮小方向へ転じるとみられるほか、潜在成長率の持 ち直しもあって、中長期的には名目金利が上昇して いくと予想しており(巻末の係数表参照)、利払い 費の増加ペースの加速が公債残高のさらなる増加 につながるとみている。 30 (図表2-32)利払費の寄与度分解(年度ベース) % 25 国債残高要因 20 金利要因 利払費前年比 15 10 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 払い費の差額がすべて新規国債発行で賄われると (出所)財務省資料より明治安田生命作成 30 (図表2-33)利払費の試算(年度ベース) 兆円 (7)プライマリーバランスの黒字化は困難 中長期的なプライマリーバランス(基礎的財政収 支)は、2014 年度に実施された消費増税(5%→8%) や、2017 年度に予定されている消費税の引き上げ 25 平均利回り横ばい 20 平均利回り毎年+0.1% 15 (8%→10%)などを受け、赤字幅が縮小傾向で推 10 移するとみている(図表 2-34)。一方、政府が目標 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 (出所) 内閣府、財務省より明治安田生命作成 の抑制策も難航するとみており、黒字化の達成は厳 しい。また、政府債務残高(対 GDP 比)も、基礎的 2016 が拡大するなか、社会保障給付費を筆頭とする歳出 0 2015 化については、東京オリンピックに向けて公共投資 5 2014 とする 2020 年度までのプライマリーバランス黒字 300 (図表2-34)基礎的財政収支と政府債務残高 (対GDP比、年度ベース) % % 2 見通し 財政収支の赤字傾向が続くことに加え、名目金利の 250 0 上昇に伴う利払い費の拡大が見込まれることを踏 200 -2 150 -4 まえると、今後も上昇傾向で推移するとみる。 100 (8)物価目標2%の安定的達成は前途遼遠 4 (図表2-35)前年比CPIと家計の1年後の期待インフレ率の推移 家計の期待インフレ率(*) 0 -1 パーキン法 11を用いて、家計の期待インフレ率を推 -2 計したところ、期待インフレ率は、消費増税を控え -3 (*) 修正カールソン・パーキン法(閾値を最小二乗法で推計)により抽出 04/06 内閣府の消費動向調査をもとに、修正カールソン・ (出所)総務省「消費者物価指数」、内閣府「消費動向調査」より明治安田生命作成 物価上昇/下落の認識閾値を最小二乗法により導出。詳しくは中山・大島[1999]参照 16 14/06 によりインフレ期待が広く浸透したとは言い難い。 13/06 1 12/06 待されてきた。ただ、これまでのところ、金融緩和 前年比CPI実績値 11/06 2 10/06 る波及メカニズムとして「期待の抜本的転換」が期 09/06 3 08/06 2013 年 4 月に始まった量的・質的金融緩和におけ た 2013 年 4 月-2014 年 4 月にかけて、上昇基調で % 07/06 いとみている。 (出所)財務省、内閣府資料より明治安田生命作成 06/06 し、その後も日銀の目標である同+2%には達しな 0 基礎的財政収支(右軸) 05/06 者物価指数(CPI)は当面、前年比+1%未満で推移 50 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 物価については、消費増税の影響を除けば、消費 11 -6 政府債務残高 -8 -10 推移したが、増税後は鈍い伸びにとどまっている 40 (図表 2-35) 。 期待インフレの変動要因について、マネタリー (図表2-36)期待インフレ率の分散分解 % TOPIX 35 輸出 30 ベース、輸出、東証株価指数(TOPIX) 、期待イン 25 フレ率からなる 4 変数無制約VARモデル 12を構築 20 し、計量的な分析を試みた。各変数ショックに対 15 する期待インフレ率の分散分解 13をとると、輸出 10 マネタリーベース 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 横軸は経過月数、縦軸は各変数からの影響の大きさを示す (出所)内閣府、財務省、日本銀行、東京証券取引所より明治安田生命作成 (図表2-37)潜在GDP成長率と寄与度 (年度ベース、前年度比) にわたり軽微であることが示唆された(図表 % 3.0 資本ストック要因 生産性要因 潜在GDP成長率 2.0 予想値 1.5 けば、日銀の目標である「2015 年度を中心とす 1.0 る期間に CPI 前年比+2%の達成」の実現は困難 0.5 とみる。加えて、国債買入れを続けるとしても、 0.0 すでにストックベースで発行額の約 7 割を日銀 -0.5 が購入しており、今後、買い取ることができる資 -1.0 産が枯渇する可能性が高い。日銀の国債大量買入 れを事実上の財政ファイナンスと受け止める見 労働力要因 2019-24 き上げることは困難であり、消費増税の影響を除 2.5 1999-03 ベースマネーの増強だけで、物価を持続的に引 1994-98 2-36) 。 10 2014-18 フレ率へ直接的に与える影響については、全期間 0 2009-13 影響が大きい一方、マネタリーベースが期待イン 2004-08 やTOPIXのショックに対する期待インフレ率への (出所)日本銀行、内閣府、総務省、厚生労働省より明治安田生命作成 方が広まる可能性も高く、2016 年~2017 年には、 買入れ縮小へと方向転換を強いられると予想す る。 14 (図表2-38)労働力人口(15歳~64歳)の推移 千万人 % 73 12 70 10 67 8 64 当社の推計では、 日本の潜在 GDP 成長率は 1994 6 61 年度から 2008 年度にかけて、前年比+0.5%から 4 58 災によるサプライチェーンの寸断を受け、潜在 全体 GDP 成長率は低下している。ただ、今後は、やや (出所)国立社会保障・人口問題研究所 労働人口(15歳~64歳) 2025 2023 2021 2019 2017 2015 2013 2011 2005 1995 1985 1975 1965 1955 1947 0 55 予想値 1930 2-37) 。2009 年以降は、金融危機や、東日本大震 2 1908 同+1.5%付近で推移してきたとみられる(図表 1888 (9)潜在成長率はやや持ち直し 52 労働人口割合(右軸) 持ち直すとみており、2014-2018 年の潜在 GDP 成長率は同+0.6%、2019-2024 年は同+0.9%と予 12 各変数の定義: マネタリーベース 株価 マネタリーベース平均残高 (日本銀行) 東証株価指数(TOPIX) (東京証券取引所) 輸出 財務省「貿易収支統計」 期待インフレ率 内閣府「消費動向調査」をもとに、 修正カールソン・パーキン法を用い 明治安田生命作成 ※分析期間:2008年4月-2014年1月 13 SC(シュワルツ情報量基準)により1期のラグを設定。分散分解の算出では、変数間に構造的関係を仮定しないコ レスキー分解を利用し、標準誤差の計算は500回のモンテカルロ・シミュレーションによる。変数の順序は、マネタ リーベース→輸出→TOPIX→期待インフレ率とした。 17 想する。 90 潜在 GDP 成長率は、労働力要因と資本ストッ (図表2-39)先進国の女性の就業率比較 % 80 ク要因、生産性要因の 3 要因から定義される。労 70 働力要因は、人口オーナス期に入ったとされる 50 60 40 1990 年ごろ以降、一貫してマイナス寄与となっ 30 20 ており、少子高齢化による人口減少を背景に、今 日本 米国 60~64 55~59 50~54 45~49 40~44 35~39 ドイツ 英国 65歳以上 本再興戦略」といった政策もあり、女性と高齢者 30~34 ただ、労働力人口の減少ペースは、 安倍政権の「日 20~24 15~19歳 0 25~29 10 後も減少基調となることは避け難い(図表 2-38) 。 フランス (出所)総務省、ILO の労働参加率の改善が見込まれ、一定程度緩和さ れるとみられる。 (図表2-40)女性の雇用体系内訳 万人 360 % 90 非正規雇用者 会社などの役員 自営業主 非正規雇用者比率(右軸) (出所)総務省統計局「平成24年就業構造基本調査」 った非正規雇用者比率が上昇している(図表 2-40) 。特に、30 歳代後半以降は、非正規雇用者 70~74 20~24 バイト」および「派遣社員・嘱託・その他」とい 85歳以上 0 雇用者比率が低下している一方、 「パート・アル 80~84 10 0 75~79 40 65~69 20 態別の女性の就労者を見ると、30 代以降は正規 60~64 30 80 55~59 善傾向が続いている(図表 2-39) 。ただ、雇用形 50~54 40 120 45~49 50 160 休制度の拡充といった企業努力などを背景に改 40~44 60 200 35~39 240 30~34 70 働市場から退出する M 字カーブ現象も、産休・育 25~29 80 280 15~19歳 女性の労働参加については、30 代の女性が労 320 正規雇用者 家族内従業者 正規雇用者比率(右軸) 比率が正規雇用者比率を上回っている。保育施設の児童待機など、子供を安心して預けることがで きる環境が不足しているなど、女性の職場復帰への環境が整備段階であることから、意に反して非 正規雇用として就労するか、もしくは就職をあきらめている女性も多いとみられる。また、超高齢 化社会を迎えるなかで、家族の介護負担が拡大傾向にあることも、就業への抑制要因となっていよ う。今後は、官民による仕事と家事・育児や介護を両立できる環境の整備により、現実の労働力率 と潜在労働力率のギャップを縮めることが必要となろう。 高齢者の雇用者数も増加傾向にある。内閣府の「高齢者の地域社会への参加に関する意識調査」 では、高年齢者雇用安定法で就労可能となった 65 歳までに退職を希望する人は 3 割に満たず、残り の約 7 割の人はその後も就労を希望している。年金受給開始年齢の 65 歳までの引き上げや、医療費 の負担額拡大などが背景にあるとみられる。内閣府の「高齢者の経済生活に関する意識調査結果」 を見ると、経済的な理由に次いで、 「生きがいを 新設投資額 前年比(%) 得られるから」 (35.7%) 、 「健康のため」 (34.2%) が高い割合となっている。超高齢化社会が進み、 15 12/09 10 平均寿命が延びるなかで、生活の充実度合がより 5 重視されるとみられることから、意欲と能力に応 (図表2 -41)資本ストック循環図(全産業) 04/09 1 4/09 -5 01/09 03/09 -10 負担増や増税により、家計の支出は拡大傾向が続 -20 4.0 ことから、女性と高齢者の労働力人口の増加ペー 0%成長 4.5 18 99/09 09/09 1%成長 5.0 (出所)内閣府資料より明治安田生命作成 スは緩やかなものにとどまるとみる。これらの想 00/09 02/09 10/09 -15 くとみられるものの、労働環境が整備段階にある 98/09 06/09 13/09 今後も実質賃金が伸び悩むなか、社会保障費の 2%成長 08/09 11/09 0 じた労働を可能とする労働環境が求められる。 07/09 05/09 5.5 6.0 6.5 前年の新設投資額/前年末の資本ストック 定のもと、国立社会保障・人口問題研究所によ 120 る将来人口の推計を用いて労働力人口の推移を (図表2-42)非金融法人企業の投資などの内訳 兆円 % 130 100 125 試算すると、 予想期間中の労働力要因の潜在 GDP 80 120 60 115 成長率へのマイナス寄与幅は、2014-2018 年は 40 110 20 105 前年比▲0.4%、2019-2024 年は同▲0.3%との 0 100 固定資本減耗 総固定資本形成 を見ると、1990 年代以降資本ストックの増加幅 在庫品増加 土地の購入(純) 純貸出(+)/純借入(-) 資産の変動 は縮小基調にあり、2000 年以降は前年比+1.0% 総固定投資/固定資本減耗(右軸) 2013 2012 2011 2010 2009 2007 2008 2006 2005 2004 2003 2002 2001 幅が縮小している。過去の資本ストックの推移 2000 80 1999 85 -80 1998 90 -60 1997 資本ストック要因は、2008 年以降プラス寄与 95 -40 1996 結果が得られた。 -20 (出所)内閣府 前後にとどまっている(図表 2-41) 。非金融法人 企業の投資の内訳を見ると、総固定投資額は固定資本減耗額を小幅に上回る水準となっている(図 表 2-42)。輸出企業の現地生産化や国内市場の縮小を背景に、企業の設備投資は更新・維持にとど まっているとみられる。今後についても、企業は海外投資を優先し、国内での投資を手控えるとみ られることから、国内資本ストックの蓄積ペースは鈍いものにとどまろう。予想期間中の資本スト ック要因の潜在 GDP 成長率へのプラス寄与幅は、2014-2018 年は前年比+0.3%、2019-2024 年は 同+0.4%とみられる。 最後に、生産性要因については、小幅の改善を見込んでいる。技術進歩により生産性要因は改善 するものの、金融危機以降、対前年度比で減少が続いていた科学技術研究費は 2011 年度にプラスに 転じており、企業による研究開発費用への資産の振り向けが増加している。今後、政策的努力が R&D 投資を刺激するとみられ、生産性要因の成長率へのプラス寄与は緩やかに拡大すると予想する。予 想期間中の生産性要因の潜在 GDP 成長率へのマイナス寄与幅は、2014-2018 年は前年比+0.7%、 2019-2024 年は同+0.8%とみられる。 (10)長期金利フェアバリューは緩やかに上昇へ 長期金利(10 年物日本国債)は、2012 年以降、 (図表2-43)長期金利実績値の推移とフェアバリューの見通し 5.0 % 1%を下回る推移が続いている (図表 2-43) 。2014 4.5 10年物国債金利実績値 年 10 月には、日銀の追加緩和が決定され、マネ 4.0 当社長期金利モデルによるフェアバリュー タリーベースの年間の拡大幅は 60~70 兆円から、 3.0 3.5 2.5 80 兆円まで引き上げられた。それに伴って、中 1.5 長期国債の買入れペースも 50 兆円から 80 兆円 1.0 へと引き上げられたことで、中長期の国債市場 である(図表 2-44) 。通常のフィッシャー方程式 では、長期金利は潜在成長率に期待インフレを 加えることで算出される。ただ、1992 年以降の マネーサプライと長期金利の関係を見ると、負 の相関が確認でき、日本銀行による金融緩和が 22/03 19/03 16/03 13/03 10/03 07/03 04/03 01/03 98/03 (出所)ファクトセット、日本銀行、OECDより明治安田生命作成 当社金利フェアバリューモデルは、フィッシ ャー方程式にマネーサプライ項を付加したもの 95/03 0.0 92/03 0.5 は需給がいっそうひっ迫し、長期金利はきわめ て低位での推移が続いている。 予想値 2.0 (図表2-44)当社長期金利フェアバリューモデルの詳細 ln(10年債金利)=94.16+3.84×ln(潜在GDP) +0.01×(3年前比コアコアCPI上昇率年率換算 *)-5.68×ln(M3 **) * 期待インフレの代理変数 …期待インフレ率は足元3年間の物価変動を基に適応的に形成されると仮定 ** 国内流動性の代理変数 …日銀による積極的な金融緩和がインフレ期待へ与える影響を考慮 潜在GDP 3年前比コアコアCPI上昇率年率換算 M3 (切片) 1.5 t値 3.3 -11.7 13.3 自由度調整済決定係数 0.87 推計期間 1992年1-3月期-2014年10-12月期 (出所)総務省、日本銀行、OECDより明治安田生命作成 19 長期金利の低下につながっていることが示唆さ (図表2-45)長期金利とマネーストック(1992年1-3月期-2014年10-12月期) れる(図表 2-45) 。よって、当社では日銀によ 2.0 る積極的な金融緩和をモデルに反映するため、 10年債金利対数値 ln[ 10年債金利]=-4.43×ln[M3]+92.12 (-23.48) (23.60) R2=0.86 1.5 上記フィッシャー方程式にマネーサプライ(M3、 1.0 季調済)を変数に加えた修正フィッシャー方程 式で推計している。 0.5 2015 年以降も、日銀による金融緩和政策を背 0.0 景に、マネーサプライは増加傾向での推移が予 -0.5 想されることから、当面低金利環境が続くとみ -1.0 20.4 る。ただ、日銀が買い取ることができる資産が 枯渇する可能性が高いことなどもあり、金融緩 20.5 20.5 20.6 20.6 20.7 20.7 (出所)日本銀行、ファクトセットより明治安田生命作成 20.8 20.8 20.9 20.9 21.0 M3対数値 和政策を維持することは困難になるとみられる。2016 年~2017 年には、買入れ縮小へと方向転換を 強いられるとみられ、長期金利は上昇傾向へ転じると予想する。 なお、長期金利の見通しは、あくまでフェアバリュー(適正水準)の予想値であり、各時点の需 給要因を反映するものではないことには充分留意されたい 14。 主要係数表 実質GDP(前年比) 国内需要(前年比) 輸出(前年比) 名目GDP(前年比) 鉱工業生産(前年比) 消費者物価(前年比) 失業率 経常収支(対名目GDP) 政府債務残高(対名目GDP) プライマリーバランス(対名目GDP) 期中平均為替レート(円/ドル) 無担保コール翌日物(期末値) 10年債利回り(期末値) 消費税率(期末値) 予測 2013年度 2014年度 2015年度 2016年度 2017年度 2018年度 2019年度 2020年度 2021年度 2022年度 2023年度 2024年度 2.3 ▲ 0.8 1.7 1.5 0.4 1.1 1.8 1.1 0.7 1.4 1.6 1.3 2.1 ▲ 1.5 1.5 1.5 0.3 1.0 1.5 0.6 0.5 1.0 1.2 0.9 4.7 6.9 2.9 2.4 5.3 4.7 6.4 7.0 6.7 7.2 7.5 7.9 1.9 1.1 2.3 2.2 1.1 1.4 2.2 1.7 1.5 2.6 2.8 2.5 3.2 ▲ 0.3 4.2 2.8 0.9 2.5 2.3 2.0 2.1 2.3 2.6 2.8 0.9 3.1 0.4 0.7 2.0 0.5 0.8 1.1 1.3 1.5 1.7 1.9 3.7 3.5 3.9 3.6 3.5 3.5 3.6 3.6 3.6 3.5 3.5 3.4 0.2 1.1 1.3 1.0 1.1 0.7 0.6 0.3 ▲0.1 ▲0.2 ▲0.4 ▲0.6 212.2 213.7 215.4 217.3 219.4 221.2 222.9 225.2 227.7 229.4 230.6 231.7 ▲ 4.9 ▲ 4.1 ▲ 5.7 ▲ 5.1 ▲ 4.7 ▲ 4.2 ▲ 4.1 ▲ 4.2 ▲ 3.9 ▲ 3.7 ▲ 3.6 ▲ 3.4 100 112 121 122 125 126 123 120 118 114 112 116 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.07 0.10 0.15 0.20 0.25 0.30 0.6 0.5 0.5 0.5 0.6 0.7 0.8 1.0 1.2 1.4 1.7 2.0 5 8 8 8 10 10 10 10 10 10 10 12 (為替レートを除き%) 2013年 実質GDP(前年比) 2.2 米国 政策金利(FFレート) 0.25 実質GDP(前年比) ▲0.4 ユーロ圏 政策金利(リファイナンス金利) 0.25 世界 実質GDP(前年比) 2.5 2014年 2.4 0.25 0.8 0.05 2.6 2015年 3.0 0.75 1.3 0.05 2.8 予測 2016年 2.9 2.00 1.5 0.05 2.9 2017年 2.7 2.25 1.6 0.05 3.3 14 2018年 2.5 3.00 1.7 0.05 3.6 2019年 2.5 3.25 1.9 0.05 3.4 2020年 2.4 3.50 1.6 0.05 3.3 2021年 2.4 3.50 1.7 0.10 3.6 2022年 2023年 2024年 2.3 2.3 2.2 3.75 3.75 3.75 1.8 1.9 2.0 0.10 0.10 0.10 3.9 4.1 4.2 (%、各国政策金利は年末値) マネタリーベースとマネーストックの関係は一様でないことから、日銀によるベースマネーの増強がとりもなおさ ず長期金利の低下を指すというものではないことに留意されたい 20 (11)サブシナリオ分析 当社では、メインシナリオに加え、3 つのサブシナリオを想定。それぞれの概略は下記のとおり。 <サブシナリオ1>「アベノミクス」大成功(示現確率:20%) 米国を中心とする世界経済の急回復を受け、国内企業業績は V 字型回復。賃金も大幅に上昇し、 CPI は早期に 2%に到達、金融政策は正常化へ向かう。物価上昇により為替は円安方向へ。与党支持 率が長期にわたり高水準で推移するなか、オリンピック開催も追い風となり構造改革が進展し、潜 在成長率が 1%台後半まで上昇。消費税率は 2017 年度、2024 年度までにそれぞれ 8→10%、10%→ 12%に引き上げられ、税収の増加によりプライマリーバランスはプラスに転換。経常収支は、輸出 の回復と所得黒字の拡大によりプラスを維持。 <サブシナリオ2>失われた 30 年(示現確率:15%) 中国は産業構造の転換に失敗し、景気は急減速。欧州も内需が振るわず、景気低迷が長期化。日 本はデフレ脱却が遅れ、成長率は平均で 1%を下回るなど、 「失われた 30 年」的状況が続く。長期 金利は低位で推移、為替は円高へ向かう。景気低迷により財政再建はより困難となり、消費税率は、 2017 年度に 10%まで引き上げられた後すえ置かれ、政府債務残高は増加基調で推移、プライマリー バランスもマイナス圏内にとどまる。経常収支は、財政赤字幅が拡大することで、2020 年度にも赤 字に転じる。 <サブシナリオ3>オリンピックが財政不安を助長(示現確率:15%) 2020 年まではメインシナリオ同様の堅調な経済成長が続くも、オリンピック開催に伴う歳出の拡 大により、政府債務残高は加速度的に増加。財政リスクが意識され、広範な投資家が日本国債の売 りに走ることで、国債金利は急騰。日銀は大規模な国債買取りを実施するも、財政ファイナンスと 受け止められ、市場の信認は失墜。金利の高止まりが続き、スタグフレーション的な状況へ向かう。 実質 GDP 成長率は、オリンピック終了後マイナスに転じる。経常収支は輸入減を受けて黒字圏内に とどまる。 サブシナリオ係数表 サブシナリオ① サブシナリオ② サブシナリオ③ 2019年度 2024年度 2019年度 2024年度 2019年度 2024年度 実質GDP(前年比) 2.0 2.2 0.4 0.7 1.9 ▲ 0.3 国内需要(前年比) 1.7 1.5 0.5 0.4 1.6 ▲ 0.6 輸出(前年比) 6.8 8.2 4.3 3.0 6.5 4.1 名目GDP(前年比) 3.4 3.8 1.0 1.3 2.7 2.2 鉱工業生産(前年比) 2.7 3.1 1.5 1.3 2.6 ▲ 0.1 消費者物価(前年比) 2.1 2.3 0.4 0.2 1.4 3.8 失業率 3.5 3.0 4.1 4.9 3.7 6.0 経常収支(対名目GDP) 0.7 1.6 0.7 ▲ 1.1 0.8 0.1 政府債務残高(対名目GDP) 212.6 206.4 229.9 242.3 261.2 262.8 プライマリーバランス(対名目GDP) ▲ 2.1 0.6 ▲ 5.2 ▲ 4.8 ▲ 6.4 ▲ 11.6 期中平均為替レート(円/ドル) 127 117 103 92 115 147 無担保コール翌日物(期末値) 0.50 1.50 0.07 0.07 0.07 3.60 10年債利回り(期末値) 1.60 0.70 4.20 2.40 0.30 0.80 消費税率(期末値) 10 15 10 10 10 10 (為替レートを除き%) 21 本レポートは、明治安田生命保険 運用企画部 運用調査Gが情報提供資料として作成したものです。本レポートは、情報 提供のみを目的として作成したものであり、保険の販売その他の取引の勧誘を目的としたものではありません。また、記 載されている意見や予測は、当社の資産運用方針と直接の関係はありません。当社では、本レポート中の掲載内容につい て細心の注意を払っていますが、これによりその情報に関する信頼性、正確性、完全性などについて保証するものではあ りません。掲載された情報を用いた結果生じた直接的、間接的トラブルや損失、損害については、当社は一切の責任を負 いません。またこれらの情報は、予告なく掲載を変更、中断、中止することがあります。 22
© Copyright 2026