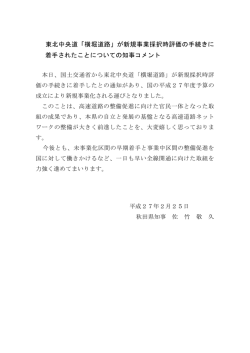Title 懲戒処分法理の比較法的研究 II Author(s) - HERMES-IR
Title Author(s) Citation Issue Date Type 懲戒処分法理の比較法的研究 II 盛, 誠吾 一橋大学研究年報. 法学研究, 14: 367-537 1984-06-30 Departmental Bulletin Paper Text Version publisher URL http://hdl.handle.net/10086/10083 Right Hitotsubashi University Repository 懲戒処分法理の比較法的研究 ロ 懲戒処分法理の比較法的研究 目 次 第一部 ドイツにおける懲戒処分法理 序章 ︵以上前号︶ 第二部 フランスにおける懲戒処分法理 第二章私的企業における懲戒処分制度の現状 第一章序説 一 就業規則による懲戒制度 二 労働協約による懲戒処分の規制 誠 一 序説 第一節制度説による懲戒権の基礎理論 第四章制度説による懲戒理論とその影響 二 初期懲戒法理の性格 一 罰金に関する初期の判例・学説 第二節初期の懲戒法理 二 立法の内容とその影響 一 立法に至る経緯 第一節 一九三二年法による罰金の規制 第三章 罰金の立法的規制と初期の懲戒法理 盛 ニ レガル目ブレートの基礎理論 367 H 吾 一橋大学研究年報 法学研究 14 第二節 懲戒処分に対する裁判所の審査 三 懲戒としての解雇に関する審査 一 序説 第三節 懲戒処分をめぐる主要問題に関する判例 デュランの基礎理論 懲戒の目的と対象 の概要 二 解雇以外の懲戒処分に関する審査 懲戒罰の形態 制度説による懲戒理論の展開 使用者 の 内 在 的 懲 戒 権 二 懲戒処分の形態 一 序説 制度説の波及 懲戒権 行 使 の 限 界 制度説 の 意 義 四 懲戒手続 三 懲戒処分の対象 一 一 判例の基本的理解とその批判 二 固有の懲戒法理の不存在 第四節判例の評価と批判 響 第一節 従前の法状態と立法的規制の要請 第六章懲戒処分をめぐる立法的規制の展開 制度説に対する批判 批判的学説による基礎理論 二 一 第二節 一九七三年法による解雇規制 懲戒法理の内容とその問題点 第五章判例における懲戒理論 二 解雇法改正の内容とその意義 三 立法の懲戒法理への影響 一 序説 第三節 一九八二年法による懲戒処分規制 第一節判例における基礎理論とその動揺 三 判例における制度論的理解と契約論的理解 二 懲戒の法的基礎に関する判例の変遷 一 序説 二 第四節 批判的学説による懲戒理論と制度説の影 第三節 制度説の評価と批判 裁判所によるコント・ール 第 五四三二一二 節四三 368 懲戒処分法理の比較法的研究・H ﹃一 一九八二年法による懲戒処分規制の内容とそ 懲戒処分の立法的規制の展開 の意義 三 一九八二年法の問題点と懲戒処分法理への 影響 第七章 小括 ︵以下次号︶ 369 二 一橋大学研究年報 法学研究 14 第二部 フランスにおける懲戒処分法理 第一章 序説 一 フランスの私的労使関係における懲戒処分に関する立法的規制は、長い間全く不十分な状態に置かれてきた。 各国において前世紀の末葉以降相次いで成立を見た工揚における罰金制度の法的規制がフランスにおいて実現したの は、ようやく一九三二年のことであった。その後も、一九八二年のいわゆるオールー法による本格的規制に至るまで、 ︵−︶ ︵2︶ 労使関係における懲戒処分は、その実際上の多くの濫用や弊害にもかかわらず、フランスの立法上はほとんど顧みら れることがなかったのである。 現在フランスでは、多くの私的企業において、懲戒処分は就業規則中にその形態.事由.手続等が定められ、一個 パヨソ の制度として形成され、行使されている。それは一面において公務員の懲戒に関する法令上の定めや公的企業におけ る身分規定の定めに倣うものであるが、わが国のように﹁制裁﹂の定めを就業規則の必要的記載事項とする法規定が ︵4︶ 存在してこなかったフランスの事情を考慮すれぱ、それはやはり労務管理上の実際的必要性に基づくものとしての性 格の強いものであった。また、労働協約による懲戒処分の規制は、とくにその手続を中心に一部において見られるが、 必ずしも一般的なものではない。 ︵5︶ フランスにおける懲戒処分法理は、このような状況の下で、使用者の懲戒権︵宕質くo罵良毘℃ぎ帥一.。︶の間題として、 370 懲戒処分法理の比較法的研究 n 学説.判例上の活発な議論の対象とされてきた。それは、使用者の包括的な制裁権限としての懲戒権について、その 法的根拠、要件、限界、手続等を論ずるものである点において、わが国のそれと著しく類似している。しかしフラン スにおいてもやはり、そのような形での懲戒法理の展開は、決して古くから存在していたものではない。他の諸国と 同様、当初は罰金を中心とした個別的制裁措置についての契約法理に基づく理論構成が見られたにすぎないのである。 このような理論状況に一大転機をもたらし、その後のフランス懲戒法理の性格を特徴づけたものが、一九三〇年代後 半にレガル︵い甜巴︶およぴブレート・ド・ラ・グレッセイ︵ωみ跨①号﹃Oお霧爵o︶によって提唱され、次いでフ ランス労働法の権威ともいうぺきデュラン︵国U貫きα︶によって展開された、いわゆる企業制度理論︵98鼠。号 豊εぎコα.o暮吋o冒凶器︶に基づく懲戒理論︵以下では﹁制度説﹂と呼ぶことにする︶である。その理論は、単に 使用者の﹁懲戒権﹂に関する最初の統一的理論であっただけでなく、その法的根拠を契約とは別個の制度それ自体に 求めた点において、また、それに基づいて大胆に懲戒権の理論的限界を提唱した点においても、まさに画期的なもの であった。フランスの懲戒法理は、企業の制度としての把握そのものの当否は別として、少なくともその基本的な理 論的枠組に関する限り、現在に至るまで、この制度説によって色濃く縁どられている。 観念、したがって一般的な私法理論が、依然として重要な役割を果たしていることも事実である。そのことは、フラ とはいえ、ア一のような制度説の多大な理論的影響にもかかわらず、フランスにおいて伝統的に優位を占める契約の ンス労働法において極めて重大な影響力を有する破棄院︵9ξ留8誘讐8︶判例において最も顕著に現われる。破 棄院は、確かに一方で懲戒権の法的根拠に関して制度説への一定の傾倒を示しながら、他方では、とりわけ懲戒権行 使の司法審査に関して伝統的契約法理に固執するがごとき立場をとることによって、結果的に使用者に対し広範な懲 戒権行使の自由を承認してきたのである。制度説登揚以後のフランスにおける懲戒法理は、一面において、このよう 371 一、 一橋大学研究年報 法学研究 14 な破棄院による多数の判例の蓄積と、それに対する学説の絶えざる批判のうえに展開されてきたと言っても過言では ない。近年における使用者の懲戒処分に対する根本的な立法的規制の実現も、まさにそのような確立した判例の状況 と、懲戒処分法理の限界性を背景とするものであった。 ︵−︶ 一九三二年二月五日法︵労働法典旧第一編第二二条b“L一二二−三九条以下︶。後述第三章第一節参照。なお、同法に よる労働法典上の規定は、一九七八年の改正によって罰金その他の財産的制裁の全面的禁止にその内容が変更されたが、それ ︵2︶ 一九八二年八月四日の企業内の労働者の自由に関する法律第八二−六八九号。第六章第三節参照。 については第六章第三節において触れる。 ︵3︶ 一九五九年二月四日オルドナンス五九ー二四四号第三〇条以下︵季刊人事行政二二号一〇〇頁以下に邦訳がある︶、一九 五九年二月一四日デクレ五九−三一一号、一九六〇年九月二八日オルドナンス六〇1一〇三六号。9霊帥暮①ざ≧巴戸円機黛慧 鳶ミ誉鳶鳶碧誉§§醤ミミ黛8墓ご評﹃一ワ堕這ひ一、や。o刈①叶㎝∴ω巴茸﹂o口βく<①ω・卜象暁恥、§。醤い§馬憶a噌黛鴇亀§砺﹄恥 防零鳶ミ憾黛ミ貴則O。∪■︸;勺貧ぴ一Sざ℃■Nお99 ︵4︶Ro壁一ρ蜜8一①ト、恥ミ愚ミ墨円ミ賦魯ミ盲ミミミ§江。幕避∪巴囲。N・評量一。。。。も﹂刈。。;・ ︵5︶ フランスでは、従来一般に、使用者の懲戒権は、法的権利を意味する・.身鼻、.ではなく、より広い権力や権限を意味す る、.宕瑳oマ・.の語によって表現されてきた。ただし、それが実際にいかなる範囲の懲戒措置を包含するのかについては、特 から、.費葺.、に変質したと言われることが多い。 に判例に関して問題がある。なお、後述するように、最近の懲戒処分に関する新たな立法の出現に伴い、懲戒権が・づ。瑳。凹..・ 二 そこで次章似下では、まず最近のフランスにおける労使間の懲戒処分の実態について、就業規則上の懲戒規定 などをもとにその概要を一瞥した︵第二章︶のち、罰金規制立法の成立と罰金を中心とする初期の懲戒法理について 検討し、制度説が登場した当時の情況と背景を明らかにする︵第三章︶。次いで、フランスの懲戒法理を特徴づける 制度説について、その内容をやや仔細に検討し、その意義やその後の懲戒処分をめぐる学説への影響を明らかにする 372 懲戒処分法理の比較法的研究 n ︵第四章︶。ア︺のことは、わが国において一般に固有権説として理解される学説のもつ意味や、本稿の冒頭において述 べたような、わが国の学説.判例においてあたかも先験的に措定されてきた懲戒の一般原理の起源やその意義の理解 にとっても、なにがしかの示唆を与えてくれるはずである。続いて、制度説登揚以降、最近に至るまでの判例につい て、その内容と意義、およびそれに対する学説からの批判を検討する︵第五章︶。このことは、フランスの懲戒法理 の展開に占める判例の地位そのものの重要性もさることながら、制度説ひいては懲戒処分法理そのものの実際的な限 界性を暗示するものとしても、大きな意味を有するものである。そして最後に、以上の学説、判例によって形成され たフランス懲戒法理の一応の帰結としての限界性について論じ、それをふまえて近年の懲戒処分に関する新たな立法 的規制の動向とその意義について考察を加えることにしたい︵第六章︶。 フランスにおける懲戒処分法理は、近年の立法的規制の出現によって大きな転機を迎えようとしている。学説では、 従来の使用者の懲戒権限︵陽肇o冒窪ω・苞冒巴﹃o︶に代わる懲戒﹁権﹂ないし懲戒法︵辞o淳良ωo覚冒巴3︶の登揚に ついて語るものも多い。しかし、懲戒処分法理の新展開は、いままさにその端緒に着いたばかりであり、本稿におけ る検討も、残念ながらその展望の段階にとどめざるをえない。 ︵1︶ 以下で著者名または略記によって引用した文献を予め掲げておく。 ω闇尋﹂。Q。。扇ぎ。,盲奉p﹀︻畳の﹃㍉濤①b﹃一ω①﹄奪ミミ恥§き軌ミミミ§需.ひα‘up=。N一評冴一。Nα茄昌p>&昼 >舞一ρζ憤鳶ミヤ恥麟守§焼鯉馬§8ミ㌣ミ誉㌣ミミき評房G象い切。露&こ。彗之碧pg防§感§箋§誉sミ、ミ警、貰言麟 N。ひq・しoN。。旧9日の﹃一岩。ぎρ=こ9ミ・ミ警㌣ミ&さ辱ミ載詩辱ミ§ヘミ。ミき8ヨ。どu四=oN︾評募一8。。b謂α‘G。。押 g風ミ軌落ミ匙§“恥馬器辱。魯ミ馬、魯qミさo。一﹃Φざ評蔚這ひざ国置p>且逐9=p&ヤコ窪芦oミミ黛覧ミqミ、ωぎざ評房G軌。。魎 9幕﹃一旨。ぎo・串\ξg,o器p象﹃帥﹃阜b§ミミミミきの葺8鳥①舞。=o。貧いup一一〇N后畳巴o鶏①=。。。ごoも一g算い揖、9− 。げρ℃こ等魯静魯、甜乾ミ帖§きミ豊ミミやu毘o欝℃畳ω6呂嚇9芭欝客8一ρ卜、恥ミ・もこ罫⇒&愚魯辱ミ織ミミ鮭ミさ8ヨ。合 373 一橋大学研究年報 法学研究 14 374 u巴一。N﹄畳ω一。。。9u①。・冨×魎冨。一糞卜.恥ミ悪誌ミミミミトいo・u﹂こ評冴まごu。招畏忌喜①量価=の。・一Φ﹃こ①帥・トa §さ8壽どu巴一。N、評﹃一ω一£N︵評β呂﹂yu・毒&”評亀≦β>&﹃ρ専。焼瓠憂ミミ簿8馨ρ身一一〇斜評二ω6q。 駿馬§&篤恥§乳 誇、ミこミ§崎§勲8髪N。乙㌧9奮㌔覧ω一ミ∋響3一二評・ξ霧雷&鳶誉敬魯織ミミミミ, ︵o基区﹂一︶こ帥<⋮曾こ㊦學Ω程實卜跨養。§器§亀§ミミミ§ミ愚ミ之恥ミ§ミ§ト・9∪・旨㌔畳ω一。。。押 い曹一専憲a①一po弱ω馨ト§。§。㌣§§喜§ミ織§⇔醇誉ミ§§も、帆壁魯恥㌧評ユω漠。。︵ま⑳巴専窪①︶期ξ。・,9①昌 、ミ鷲ミb>目餌民oo一昼勺曽一ω一鶏押OH置p9ミ義ミミミ噌ミさ8ヨΦ∋国霞■国;評身一80。㌔ひ=。・切一Φ5一①嘗ト§。§恥§ 象賛9ミ§§h警織§ミ裳㌣ミミ亀警ぎ艮ミ慧§ミ騨rgoζこ勺畳ωお器旧○一一一①﹃㌔一曾﹃①6。巨三ρ・ρb§、§ 旨昌一一邑瞬pミ§恥恥肋§誉織斎§ミ§ミ㌧g一一。Nい評冴一。。。一讐℃■NNQ︵墨一㎝・・互ミ膏醤讐y勺一p評二↓§隷 き魯§ミ軸§篤§ミ亀卜。㊤貧あ浮ざ評岳這。。9審琶3一雷pい。鼻2ヨ弩。暮℃胃一、。旨暑藩弩8る。8宕髪魯 導ミミ&§譜壽乾ミ§欝§恥ミミ恥﹂。$魯ひ。ひα、︾評蔚G鵠。江8ご勾回<Ro﹂Φ撃\留く器①5﹄8昌bミミミミミミ・ 一。。ごω。同⋮①いωΦヨ貧9卜、§R嘗ミミ焼爵§§語、§恥ミミミ恥ミ戚、恥ミ・魯諄やrPO﹂・﹄監ω一。N9く還量8霞霧・ 。。①ひαこ牢①馨。・d号。邑梓p一§α①牢彗。ρ評ユm一。。。ご勾。甕“︾民昼∪仁§昼評・ンoミ、§ミ§きb。①ひαこ評身 客8一器ト塁ミ§§笥ミ馨凝ミ㌣鴇籍義&養ミこミミ駐§ミ災馬ミ8ミミ馬“§=、恥ミ濫㌣蓄§&ミミ・評冴ま。 た、以下で用いた雑誌、定期刊行物の略号は次のとおりである︵これ以外のものは、文中において適宜表示する︶。 即■コo、ω甲”却q§等ミ蔚§籍bさ貸切。黛ミ 旨ρ汐∼ミ§薄鴇ミ頴篭&赴§︵的§ミ§、ミミ喝§︶ Uひω駈bε疑動8帖ミ U。○乙bさ笥O巽ミ帖ミ O乙㌍馬§淺bミご雫吻ミ棲 懲戒処分法理の比較法的研究 H 第二章 私的企業における懲戒制度の現状 一 就業規則による懲戒制度 − 就 業 規 則 に よ る 懲 戒 の 制 度 化 と 就 業 規 則 法 制 はじめにも指摘したとおり、フランスの私的労使関係における懲戒処分は、長い間極めて乏しい立法的規制の下に 置かれてきた。しかし実際には、大企業を中心として多くの企業において就業規則︵みαqざヨ。韓ぢ器器目︶中に懲戒 に関する定めが置かれ、それは一個の懲戒制度として形成され、運用されている。フランスにおける懲戒処分法理が 大きな展開を示したのも、当然にそのような実態を前提とするものであった。 懲戒処分の法理的研究を目的とする本稿にとって、その実態を実証的見地から明らかにすることは、もとよりよく なしうるところではない。ここでは、以下の叙述にも必要な限りで、就業規則上の懲戒規定を中心に、私的労使関係 における懲戒制度の一端を窮い知るにとどめざるをえない。なお、その検討に先立ち、ここでフランスの従来の就業 規則法制の特徴について一瞥しておきたい。 ︵−︶ フランスの就業規則法制およぴそれをめぐる議論については、わが国でも既に若干の紹介・研究がなされており、 ︵2︶ 懲戒規定との関連においてその特徴を挙げるとすれば、以下の諸点を指摘することで十分であろう。’ 第一に、就業規則は、わが国におけると同様、使用者の一,方的作成にかかる。法律上、通常二〇人以上の労働者を 雇用する企業では就業規則の制定が義務づけられ︵労働法典L一二二−三三−以下、特に断わらない限り、一九八 二年改正前の労働法典OaΦ9日声く毘の条文である︶、使用者はその作成にあたって、事前に労使の代表で構成さ れる企業委員会︵8菖泳α、。葺お屈一器︶またはそれが存在しない場合には従業員代表者︵騒一粛器ω含鷲誘o旨巴︶の 375 一橋大学研究年報 法学研究 14 意見を聞かなければならないことになっているが︵L一二二−三五︶、この企業委員会ないし従業員代表者の関与は あくまで意見の聴取にとどまり、西ドイツのような労使共同決定の制度はとられていない。従って、少なくとも制度 ︵3V 的には、使用者は労働者側の意思に反しで就業規則を制定・改正することも可能である。 第二に、就業規則の記載事項に関する規定の不備が挙げられる。わが国の労働基準法が第八九条において詳細な必 要的記載事項を定め、特に第九号が﹁制裁の定﹂をその一つとして掲げているのに対し、フランス法においてはその ような就業規則の記載事項に関する一般的規定は存在せず、懲戒に関する定めは、最近まで例外的に許可された罰金 ︵4︶ 等が就業規則に定められξべきものとされていたことを除き、就業規則への記載が義務的なものとはされていない。 その意味で、現在多くの企業の就業規則に見られる懲戒に関する定めは、決して法的な強制によるものではない。 ︵5︶ 第三に、就業規則の効力や、労働協約・法令との関係についての明文規定の欠如である。わが国の労働基準法第九 二条・九三条や、ドイツの旧営業法第一三四条cのような規定は、フランスにおいては存在しない。そしてこのよう ︵6︶ な状態を前提として、フランスでは古くから就業規則の法的性格や根拠に関する法理論が展開されてきたのであるが、 そのことが懲戒権理論に対しても重大な影響を及ぽしていることは、この後の検討を通じて明らかとなるであろう。 ︵−︶ 石崎政一郎﹁就業規則の地位についてーフランス法の考察ー﹂法学一六巻三号一頁以下、同﹁就業規則と法の階序お よぴ適用についてーフランス法の研究ー﹂法学一六巻四号一頁以下。 。。=二。﹃甜一。ヨ①暮一暮曾一Φ賃ヤU。oD、一〇ごヤマどOo箒p寓帥目凶。ρro唖甜一〇g①算一糞9一①霞〇二〇℃oロ<o冒α一ω。苞ぎ巴器倉号①h ︵2︶Ω,ξ86器po曾帥a㌧d奉雪。ヨ巴一。一¢邑一ρ・R一①議⑳一①幕緊鐸貧①章∪﹂8P98ロも,撃N一匹く段oこ臼p乞08 U露℃四其勺ひ一一器凶oき8ヨoN一マ軌9ω・ α、撃賃弓誹pu’oo■む。。ρ℃り一訟“b窪のω一Φび﹄$p幕吊⑳一。ヨ。馨一簿窪。貝g一田88㎝伽ΦのR<一8︸u●oo噂一〇。。ρや謡“ ︵3︶使用者はこのほかに、作成した就業規則を労働監督官に提出しなければならず、労働監督官は法規に反する就業規則規定 376 懲戒処分法理の比較法的研究 H の削除または修正を要求することができる︵L一二二−三七条︶。この揚合、必要なときは、企業委員会または従業員代表者の 意見を付さなければならない︵R一二二−一五条︶。なお、この労働監督権限行使の前提となる﹁法規﹂には一般法上の原則 一α目帥器一8押U。ω■むa噂唱。o。9いρ型お爲.目噂旨O一N また、Oo房亀α、団9“一9欲<,GooρO、ω,這o。ρマ訟Nは、 およぴ公的自由が含まれるが、法律に基づく拡張適用の対象となっていない労働協約は含まれないとされる︵9暴亀含、卑盤 一般的なアルコール検査を定める就業規則規定が労働者の権利を侵害するものとして、その削除を求めた労働監督官の措置を 一二二−一三条︶を義務づけられる。 適法としたものである︶。以上の手続を経た就業規則について、使用者はさらに、掲示︵R一二二−一二条︶およぴ登録︵R ︵4︶ このほか法令上就業規則への記載が義務づけられる事項としては、集団的解雇について解雇の順位に関する事前の定め ︵L三一二−二条︶のほか、アルコール類の持込み禁止など若干の安全衛生に関する事項など︵R二三二−一二条以下︶が個 ︵5︶ L=一二ー三六条は、就業規則にはそれが発効する日付を定めなければならない旨を規定するが、それがいかなる効果で 別的に掲げられているにすぎない。 あるのかについては定めがない。このように、就業規則それ自体の効力、およぴ法令や協約との関係についての法規定が存在 ︵6︶注︵−︶・︵2︶の文献参照。なお、判例については、第三章第二節一−、第五章第一節一一一2を参照。 しないことが、フランス就業規則法制の大きな欠陥の一つとされてきた。 2 就 業 規 則 に よ る 懲 戒 制 度 の 実 情 労使関係における懲戒処分の実態についての研究・資料が乏しいことは、フランスにおいても例外ではない。ここ では、そのようななかにあって、公に刊行されたものとしてはほとんど唯一のものと思われるソワンヌによる就業規 ︵1︶ 則の分析をもとに、就業規則に基づく懲戒制度の一般的傾向を明らかにしておきたい。この研究は、一七〇以上の就 業規則例を分析対象としたものであり、その実際の運用状況の検討にまで立入ったものではないが、フランスにおけ 377 一橋大学研究年報 法学研究 14 ︵2︶ る懲戒処分の実態の一端を知るうえで格好の材料を提供するものである。 ω 懲戒事由 多くの就業規則には、なんらかの形で懲戒事由が定められている。それは、時としてかなり概括 的なこともあるが、多くの場合には懲戒処分の対象となりうる労働者の具体的行為が列挙されており、多いものでは 三〇ないし四〇項目以上に及ぶことがある。しかもその場合でも、その列挙は限定的ではない旨が明言されることが ︵3︶ 多い。刑法におけるような罰刑法定主義の原則は採用しないことが意図されているのである︵ωo言冨一マ2、8︶。 懲戒事由は、当該企業の産業、業種やその業務上の必要性などに応じて極めて多様であるが、同時に企業の種類を 間わず共通の事由が定められることも多い。ソワンヌは、そのような懲戒事由について、次のような分類に従い、そ れぞれの特徴を指摘している︵ωo一旨9やS占旨︶。 ω 企業の円滑な秩序およぴ運営の素乱 これは、⑥労働者間の協調を乱す行為︵同僚に対する暴力行為、侮辱 など︶と、㈲その他の事業揚内の秩序を乱す行為に大別され、後者はさらに、労働者の基本的自由権の制約という観 点から、①移動ないし往来の自由の制限、②言論・集会の自由の制限、③労働・取引の自由の制限に細分される。 右の①としては、事業揚内の通行規制として出入口の指定、職場離脱の禁止、就業時間外の職揚滞留の禁止などが、 また業務運営を確保するための規制として、部外者の招き入れの禁止、物品の持込み・配布.着用等︵ピラ、印刷物、 バッジなど︶の禁止が、ほとんどの就業規則で定められている。②としては、多くの就業規則が原則として労働者の 集会や意見表明の活動を禁止している。一般に、労働者の企業内での募金、ビラ配布・貼付などは厳格な規制を受け ており、そのことは特に、企業の中立性の原則︵屈言9需3﹃旨窪ヰ畦一濫留一、魯霞Φ冥一器︶に基づいた組合または 政治活動としての文書活動の禁止となって現われる。労働者のこの種の活動を実質的に制約する規定を含まない就業 378 懲戒処分法理の比較法的研究 n 規則は皆無であるという。③としては、企業内での商行為を禁止するものが多い。 ω 職階的権威の無視 監督者の命令の拒否、上司に対する侮辱や不適切な言動は、すべての就業規則によって 懲戒事由として定められている。ソワンヌは、さらにこの中に、①労働者の義務の不覆行として、欠勤や遅刻、理由 のない持揚の離脱、居眠り、労働時間中の業務以外の仕事への従事、労働拒否のほか、労働時間の不遵守、法律の枠 内での時間外労働命令の拒否などが、②不完全覆行の揚合として、指示された態様とは異なる労働の遂行が含まれる としている。 ㈲ 業務活動の自己または第三者の利益のための転用 この例としては、会社財産の窃盗や無許可の持出しなど があり、そのために所持品検査や身体検査が定められることも多い。このほか、会社物品の私用︵作業衣、電話な ど︶、業務活動の自己または第三者の計算による遂行︵たとえば銀行における不正貸付け︶などが禁止される。 @ 安全・衛生規定の不遵守 これらの規定の内容は企業活動の性質に応じて極めて多様であり、しかもその技 術的性格の故に、就業規則は一般的規定のみを定め、詳細は附属規定等に委ねられることが多い。具体例としては、 危険な揚所での喫煙が一般的なものであるが、その他機械など工場施設の操作上の義務や工揚内の清潔さを保持すべ き義務の違反などがある。なお、この点については、労働法典中の安全・衛生に関する規定も重要な意味を有してい る。 図 懲戒処分の形態 懲戒処分の種類・形態についても多様なものが定められているが、フランスでは以下の三 つの種類に大別することが一般的であり、ソワンヌもその分類に従って一般的な傾向を指摘している︵ωo日琴やご令 ︵4V 一占︶。 ω 道徳的制裁︵聴冒窃目9巴8︶ これは、労働者に懲戒事由にあたる非行を犯したことを告げ、警告を与え 379 一橋大学研究年報 法学研究 14 ると同時に違反の再発を防ぐことを目的とする。用いられる名称は、帥くR富器旨o塁o富R<簿一〇P詠冥言昏ρ声唱o一 帥一、o己β巨鍵蚤8霧賃①と多様であり、その制裁としての程度も一定していない。ただ、口頭のものと書面のもの が段階的に定められることが多く、最も重いものとして最後的戒告︵αR巳R翠R鼠器旨Φ酵︶がある。 ω 財産的制裁︵需旨Φ。・℃ひ自巳aおω︶ 典型的な形態として罰金︵費目聲留︶がある。その他、一定の手当の減 額または不支給が定められることがある。また、遅刻の場合の賃金減額に関する定めが、罰金と同様の機能を果たす こともある。 なお、罰金は一九三二年の法律によって原則的に禁止され、労働監督官の許可にかからしめられることになり︵第 三章第一節参照︶、その結果、実務上は罰金の定めが影をひそめ、代わって手当の減額や不支給という制裁形態が普 及していたが、一九七八年に至り、罰金と並んで﹁その他の財産的制裁﹂もまた法律上禁止されることになった︵こ ︵5︶ の点 に つ い て は 第 六 章 に お い て 改 め て 述 べ る ︶ 。 ㈲ 職業的制裁︵需ぎ窃屈08釜o旨色一$︶ これは、労働者の企業内における職務上の地位に影響を及ぼし、あ るいは労働契約の存続に関係する制裁である。 前者としては、配転︵糞暮豊8︶、降格︵詠霞oαq﹃呂魯9︶などがある。これらは、かつては公共・準公共部門でし か見られなかったものであるが、次第に私的企業においても増えつつある。配転には恒久的な場合と一時的な揚合が あり、多くは金銭的利益の喪失を伴う。また、他の工揚、事務所への配転がなされることもある。降格については、 その範囲は使用者の裁量に委ねられ、何らの制限も置かれていない揚合が多い。 後者としては、労働契約を終了させる最も重い制裁としての解雇︵ぎ曾90ヨ。葺ヤ8お&㊦ヨo暮︶および労働契約 の一時的停止としての出勤停止︵旨一器箇ロ巴︶がある。解雇はすぺての就業規則に定められており、予告ないし手 380 当を伴い、または即時になされる。解雇について、近時大幅な立法改革がなされるに至ったことは後に述べる︵第六 って定められている。その最長期間は三日とするものが多く、一週間を超えるものは少ない。また、一定期間内にと りうる出勤停止処分の回数が限定されることも多い。 ㈲ 違反と制裁の均衡 すべての就業規則は四ないし五、あるいはそれ以上の制裁形態を定めており、しかも制 裁は違反行為の重大性に応じて選択すぺきことを明記しているものがほとんどである。しかし、制裁が段階的に定め られることは、それらを段階に応じて順次用いるぺきことを意味するものではなく、いずれの制裁を適用するかは使 用者の裁量にかかるものとされる。また、再犯の揚合の加重、情状酌量事由、処分事実の消滅について定めるものも ある︵ωoぢbP唱一お占&︶。 個々の懲戒事由に対して一定の制裁措置が自動的に対応するような規定は、特定の違反についてのみ定められるこ とが多い。最も典型的な例が遅刻・欠勤の揚合である。また、個々の制裁.ことにその重大性に応じた懲戒事由が概括 的に定められることも少なくないが、特に予告や手当を伴わない即時解雇については、そのための重大なく非行V 暮。σq寅お︶を構成する行為が別個に規定されることが多いようである︵ω9呂P℃・一器ム鴇・や二〇−旨ω︶。 懲戒の手続に関してはきそれを規定する多くの就業規則が労働者の企業管理者のもとへの出頭と弁明の機会の保障 き、他のより軽易な制裁は職長などの職制に委ねられることも多い︵ωo巨5や旨斜︶。 の就業規則は企業管理者がすべての懲戒措置をとりうる旨を定珍るが、解雇.出勤停止・降格などの重大な処分を除 凶 懲戒権者および懲戒手続 懲戒権者は原則として使用者ないし企業の長︵9臥α、曾ヰ吊ユ器︶である。一定 (h を定めるほか許従業員代表者の関与を定めるものがある。また、処分の通知、公表、記録の保存について定められる 381 章第二節︶。出勤停止は罰金に代わる懲戒措置として広く用いられるようになったものであり、多くの就業規則によ 懲戒処分法理の比較法的研究 H 一橋大学研究年報 法学研究 14 こともある︵ωo一導ρや一銘や旨。。−嵩o︶。なお、重大な懲戒処分の決定に際して、調査・決定の期間中労働者を出 勤停止とする旨が定められることがある︵ω9目ρマ辰o︶。 懲戒委員会のような特別の機関は、準公共部門の企業における就業規則ないし職員規程︵。。3ε什身需誘9需一︶に よって定められるものが大部分であって、私的企業における一般的制度とは言い難い。そのような懲戒委員会制度は ︵6︶ 労使構成による場合が多いが、その権限は単なる諮問にとどまるものが大部分であり、懲裁戒判所の.ことき機能は果 たしていない︵ωo冒昌Pや旨?旨oo︶。 懲戒手続に関しては、次に見るように一部の労働協約によって規制が加えられているほか、一九七三年法が特に解 雇について手続的規制を定め、一九八二年法は同様の規制を懲戒処分一般に拡大した。これらの立法については、後 に改めて検討する︵第六章︶。 ︵1︶ のoぎ口やωoヨ胃“卜、&ミミヤ鷲風ミ民避§亀貸蕊恥驚§恥ミき獄蕊恥ミ“、§ミ魯蓋器’﹃ΩU,旨、勺巽け6NOこのほかにも就 ︵2︶ フランスの就業規則例の邦訳として、林迫広﹃世界の就業規則﹄︹法律文化社・昭三九︺一七九頁以下参照。 業規則の実証的研究はいくつかなされているが、いずれも学位論文であり、直接参照しえなかった。 ︵3︶ ソワンヌ・前掲書巻末と、頴一誇一P一雷Pb8貸§§冴魯ミミ馬§鳳ミ§き国αぼo暴冨o暮o訂o鴇。P勺霧﹃這器㌧やN鴇 9ω・には、かなり詳細な就業規則規定の例が掲載されている。 ︵5︶O色一。eoけこ$PHし。℃8<。マo一。。9一ぎ嘗。ロ①一.。日覧2①ξ。398算邑①冒二窃三げ琶塁きU●○﹂8N︾℃・田。 ︵4︶∪=揖&﹂、勺●云一①梓ω’ ︵6︶ たとえぱ、懲戒委員会︵8奮亀留島。覚言9フランス国有鉄道、全国移民局、パリ交通公社など︶、調査委員会︵8昌、 る。qりωOぎ口ρヤ一誤9ω∴O暮巴欝℃■鴇一 目一ωの一9畠.自ρ岳貫8冨色“.撃2卑9フランス電力公社、フランスガス公社、フランス国営放送など︶などの制度が存在す 382 懲戒処分法理の比較法的研究 皿 二 労働協約による懲戒処分の規制 労働協約中に懲戒処分に関する規定が置かれることは、これまでのところ必ずしも一般的なことではない。しかも、 右に見た就業規則におけるように、詳細な懲戒事由や懲戒処分の実体的要件を定める規定は見あたらず、ほとんどが 手続的規制と制裁形態の列挙にとどまっている。 手続的規制に関しては、弁護人︵従業員代表者とされることが多い︶を伴った弁明の機会ないし異議申立の機会を 保障するものが大部分であるが、まれに労使構成による懲戒委員会を制度化するものが散見される。たとえば旅行代 ︵ − ︶ 理店職員の全国協約︵08<。耳帥88箒魯お器島Oロ巴。9需拐冒冨一α霧品28ω留く2お①鉾σ目$莫留<β品霧 。一α。8百.置冒。身ω一〇。梓。σ.o一。蕊︶によれば、一一人以上の労働者を使用する事業揚には労使同数で構成される懲 戒委員会︵8拐亀留良毘宴需︶が置かれ、使用者は特に降楕および解雇処分について事前に懲戒委員会の意見を聞 かなければならないとされている︵同協約四三条−四五条︶。同協約にはこのほか、懲戒委員会の手続に関する規定 ︵四六条︶、同委員会の意見が分かれたときは全国労使協議会︵8ヨ三塗8犀簿魯①冨ぎ冨一Φ︶に異議申立がなさ れうるが、使用者はその結果を無視しうる旨の規定︵四七条︶、以上の手続は当事者が紛争を裁判の揚に持ち出す権 利を妨げるものではない旨の規定︵四九条︶などが置かれている。 ︵2︶ ︵3︶ 以上は主として全国ないし地域レベルでの労働協約の一般的傾向であるが、企業レベルでの企業協定についても事 情は異ならないようである。 られる。ODOPヨO﹃ぐ8遅■冤96器Fε①&こや畠倉O簿巴欝マQVN ︵−︶ それは一般に、銀行や保険会社といった半国営企業や、社会保障機関のような公共事業部門の職員に関する労働協約に見 383 一橋大学研究年報 法学研究 14 ︵2︶ このほか、市街電車・バス・ト・リーバス職員全国協約︵08奉ロぎコ8一一Φ。江く。コ帥匡。ロロ一①山ロ℃。﹃ωo目。一α㊦ω梓﹃昏≦即冤の層 程8ご5卑賃o一一①旨房︶第四〇条以下にも同様の規定が見られる。また、バリ地区百貨店労働協約の規定につき、松岡三郎監 修・日本商業労働組合連合会編﹃世界の労働協約と労働法﹄︹総合労働研究所.昭五じ二五五頁参照。 ︵3︶ たとえば一九七三年一月一七日に締結されたルノi公社の企業協定︵漂冴旨﹃、一$po。ミミミ砺織馬織梗。職織ミミ受&き。︾ ミも。ま︶には懲戒に関する規定は含まれておらず、単に解雇について理由の開示と従業員代表者の立会いが定められてい るにすぎない。二のほか、参照しえた限りでの企業協定例の中にも懲戒に関する詳細な規定は見出しえなかった。 第三章 罰金の立法的規制と初期の懲戒法理 第一節 一九三二年法による罰金の規制 一 立法に至る経緯 フランスにおいても、一九世紀の大企業の発生や機械制生産の発展に伴い、罰金制度は非常な猛威をふるった。企 業の秩序・運営にとって不可欠であるとの使用者の主張する正当な目的の範囲を超えて、罰金は使用者の新たな利潤 の源泉、あるいは賃金引き下げのための手段となったのである。労働者は、そのささいな規則違反についてさえ、罰 ︵1︶ 金の名目により多額の賃金を控除された。しかもその規則を作成、運用するのは使用者であったために、労働者は常 に使用者の恣意の危険にさらされ、はなはだしきは規則自体が存在せず、あるいは仮に存在してもそれが一切労働者 ︵2︶ に知らされないまま、罰金が行使されることもあった。 ︵3︶ このような使用者による罰金の濫用と恣意的行使は、一方で労働者の集団的反抗を惹き起こし、他方において立法 384 懲戒処分法理の比較法的研究 H による規制をもたらした。しかし、フランスにおいて罰金の立法的規制が実現したのは、各国のそれに比して著しく ︵4︶ 遅れ、議会への最初法案の提出から実に五〇年を経た一九三二年のことであった。 最初の立法の提案は一八八二年になされた。それは罰金の全面的廃止を内容とするものであり、下院の賛成は得ら れたものの、上院は罰金の廃止よりもその厳重な規制を主張してそれを否決した。一八九〇年にも同趣旨の提案がな されたが、同様に上院によって否決され、その後も両院の意見が一致しないまま罰金の立法的規制は見送られた。そ ︵5︶ してようやく一九二七年になって、政府提案にかかる罰金の原則的禁止と例外的許可制を内容とする法案が両院の意 ︵6︶ ︵7︶ 見の一致を見るところとなり、法文の修正をめぐる遅延の末、一九三二年二月五日の法律により、労働法第一巻第二 編第一三条bとして立法化されるに至ったのである。なお、これと同時に、常時二〇人以上の労働者を使用する企業 において就業規則の制定が義務づけられることになった。 ︵1︶ <きコ碧o葺o霧㌧やo。①け9 ︵2︶<彗畠8葺89℃﹂O .︵3︶ 9口叶器ミ93ρ口一認によれば、罰金の廃止または減額の要求が原因となった労働争議は、統計に現われただけで次 のような数にのぼる。 岳 野 令餅季蝉 蜘驚軸薄 騨営瞭蝉 一〇〇刈 一〇 卜oO Qo一〇〇 一80 ま 一ひ bo払8 一800 ま ぐ 一b& ︵4︶鉱夫に対する罰金については、既に一八九四年六月二九日の法律によつて立法的規制が実現していた。 385 一橋大学研究年報 法学研究 14 ︵5︶ 一八九二年には上院議員による罰金規制の立法提案がなされたほか、一九〇二年、一九〇九年にも罰金の立法的規制の問 題が議会で審議の対象とされている。 ︵6︶ 一九七三年の労働法典の再編により、同条は新たにL=一二−三九条ないしL一二二−四二条となった。 ︵7︶ 以上の立法の経緯については、主としてく塁養8弩$9マ89u・による。ほかに、ピック︵協調会訳︶﹃労働法.下巻﹄ ︹協調会・昭八︺一一四頁以下参照。 二 立法の内容とその影響 一九三二年法による罰金規制は、上下両院の長年にわたる見解の対立を反映し、罰金の原則的禁止と労働監督官に よる例外的許可、および許容される罰金の要件、金額等に対する厳格な制限という、折衷的性格の強いものであった。 ︵−︶ 具体的には、およそ次のような内容を含んでいた。 法の公布時に罰金制度が存在する企業においては、六か月以内にそれを廃止すべきものとされた。 ①罰金の原則的禁止ーすぺての使用者は、罰金によって就業規則規定に対する違反を罰する.︼とを禁じられる。一九三二年 ②例外的許可−法律の公布時に罰金制度が存在する企業においてはその維持を、それ以後に設立される企業についてはその ︵2︶ 創設を、労働監督官は許可することができる。これによって、法律公布時に存在する企業であって罰金制度が存在しない揚合 ③罰金の対象ー罰金は、規律違反または労働者の安全・衛生に関する規定に対する違反についてのみ、定める.︶とができる。 には、罰金制度の新設は否定されるア︼とになった。 ︵3︶ ④ 罰金の額およぴ使途−罰金の額は就業規則に明示されねぱならず、また、一日に科される罰金の額は、一日分の賃金の四 分の一を超えることができない。徴収された罰金は、従業員のための安全基金に払い込まれねぱならない。 ⑤ 記録1−罰金が科されたときは、そのための特別の登録簿に記載されねばならず、それは労働監督官の閲覧に供される。 386 懲戒処分の法理比較法的研究 H ることによって罰金制度を維持するよりも、むしろそれを放棄し、他の懲戒手段に依存する途を選んだので敵麗。そ このような内容を持つ一九三二年法は、その後の実務に対して重大な影響を及ぼした。使用者は、煩項な手続を経 の後の就業規則には罰金の定めがほとんど存在しないことについては既に指摘した。右の立法を契機として罰金に関 する判例は影をひそめ、代わって出勤停止処分がその後の判例の展開における中心的事案となることも、そのような 事情を反映するものであろう。 ︵2︶ この許可にあたっては、労働監督官は当該職業およぴ当該地域の使用者団体と労働者団体に諮間を行うべきものとされた。 ︵−︶ 花見忠﹃労使間における懲戒権の研究﹄︹勤草書房・昭三四︺一二〇頁以下参照。 また、罰金が主として労働者の衛生およぴ安全に関する法令の不履行に対して科される揚合であって、許可に必要な他の条件 ︵3︶ ピックはこの点に関し、立法によって制限される罰金と、仕事の不出来を理由とする賃金控除とを明確に区別している。 が満たされるときは、許可は当然の権利であるとも定められた。 後者は真の損害賠償であり、立法によっては制限されていないというのである︵ビック・前掲書一四六頁以下︶。このことは、 ︵4︶o亀聲。“u,○■一8Nも■N一。 後の制度説によって、形を変えて明確に強調されるに至る。 第二節 初期の懲戒法理 一 罰金に関する初期の判例・学説 − 判例 一九三二年法による罰金の立法的規制以前の初期の段階において、判例は、工揚における罰金制度は民法典一二二 六条以下の解怠条項︵。一㊤ロ。。℃。昌p一。︶、すなわち違約金の合意であるとして、その合法性を肯定した。つまり、解怠条 ︵1︶ 387 一橋大学研究年報 法学研究 14 388 項は、契約当事者の一方が契約上の義務違反について負う損害賠償額を事前に包括的に定めるものであるが、罰金は、 労働者の規則違反が使用者にもたらす損害額の包括的な予定にほかならないとしたのである。しかも判例、殊に破棄 院は、罰金について民法典の違約金に関する規定を忠実に適用した。すなわち、破棄院は、裁判官が損害賠償の予定 額を変更しえない旨を定める民法典第二五二条に従い、就業規則に違反行為と罰金額が定められている揚合につい パ レ て、実際に科された罰金が違反の程度に比して過度であることを理由に事実審裁判官がそれを減額するア︶とを、厳に 否定したのである。 ︵3︶ パユ このような判例の立場は、その就業規則に関する理解と密接に結び付いたものであった。フランスの判例は、就業 規則の法的性質について古くから契約説の立揚に立ち、その法的効力は労使間の個別的合意に基づくものと解してい 用者の作成した就業規則は、労働者の同意があったことによって労働契約の一部となり、労働者を拘束すると るので臥罷。しかし少なくともその掲示がなされている限り、その推定を覆えすことは労働者にとって極めて困難で 示され、あるいは事業揚に掲示されるが、掲示それ自体は営働者が就業規則を知っていたことを推定させるにとど壷.“ を知っていたのでなければ、労働者はそれによって拘束されないという。通常就業規則は労働者の採用にあたって提 て雇用されたことにより黙示の合意があったものとされる。ただし、,判例によれば、労働者が実際に就業規則の存在 パれレ 締結を拒否しなかったことで十分である。この条件が満たされる限り、労働者が実際に就業規則を読み、それを理解 ︵8︶ ︵9︶ ︵m︶ しえたか否かは問題ではない。また、労働契約締結後の就業規則の変更・新設や企業譲渡の場合も、労働者が継続し パアレ リるとした。労働者が就業規則に合意したものとされるためには、労働者が就業規則の存在を知り、かつ労働契約の ハ レ どありえない。そこで判例は、就業規則に対する労働者の合意は、合意に関する一般原則に従い、黙示的なもので足 いうのである。しかし実際には、個々の労働者が就業規則の内容についていちいち明示の合意をなすア︾とは、ほとん 畑醒 懲戒処分法理の比較法的研究 H あろう。そして、このようにして労働者を拘束する就業規則は、同時に裁判官をも拘束する。たとえ就業規則の条項 が労働者にとって苛酷なものであっても、公序違反を唯一,の例外として、裁判官はそれを無効とし、あるいはその適 用を拒否することはできない。就業規則は、合法的になされた合意の内容として、民法典第一=二四条に基づき、当 ︵B︶ 事者間の法︵一9︶に代わるものだからである。 ︵耳︶ さて、このような判例の理解に立つならぱ、罰金が就業規則に定められる限り、その規定ぱ労使間の合意として労 働者を拘束する。判例が罰金を違約金としてとらえ、民法典第一一五二条に基づきその減額を認めないことは、その 限りでは一貫した態度であった。しかし、就業規則が使用者の一方的作成にかかり、しかも労働者はそれを全体とし てうのみにして雇用契約を締結せざるをえない従属的状態にある以上、そのような判例の態度が現実の罰金制度をそ れとして許容し、使用者の恣意を放任するものであることは、疑いえない事実であった。既に指摘したように、ドイ ツにおいて罰金を違約金としてとらえることは、それが不当に高額な揚合の裁判官による減額の可能性︵独民法第三 四三条︶を導くことに意義があったのに対し、フランスの判例にとっては、同じことが全く逆の結論をもたらしたの ︵15︶ である。 ︵−︶ Ω<,峯欲く﹂o。ひ9一■o。∋oo﹂o。象﹂、一睾この内容については注︵3︶を参照。 たは増額しうる旨の定めが付加された。 ︵2︶なお、本条は、一九七五年の改正により、賠償の予定額が明らかに高額または低額であるときは、裁判官はそれを減額ま ︵3︶Ωく・芯欲く﹂。。8魯・ミこの事件は、カーベットエ揚を経営する被告会社が木靴を履いて工揚にはいった労働者に対 控除したというものである。原審は、右罰金が違約金であることを認めながら、民法典第二一三一条は主要義務がその一部に して一〇フランの罰金を科す旨の規則を工揚入口に掲示していたところ、それに違反した原告労働者の賃金から一〇フランを ついて履行された揚合について違約金の減額の可能性を裁判官に認めていること、およぴ当該罰金が原告労働者の一か月の賃 389 一橋大学研究年報 法学研究 14 に対し、破棄院は、﹁民法典第一二二四条、第一一五二条によれば、適法になされた合意は、それをなした者にとって法律に 金の約半額に及ぶものであることから、それを明らかに過度のものであるとし、その金額を五〇サンチームに減額した。これ 代わるものであり、その合意がそれを履行しない者は損害賠償として一定の金額を支払わねばならないと定めるときは、その 者はそれより高い額も、あるいは低い額も支払わされることはない。他方、民法典第一二三一条は、単に主要義務を部分的に 履行したのではなく、全体としてそれに違反したという本件については適用されない。﹂として、原判決を破棄した。 ︵4︶ 以下の記述は、主として∪猛β&﹂・や一爵9翌浬嘗陣o一\匹需3↓ミ慧黛ミ蔚§魯専ミ亀ミ馬ヤ§噺&88目o図一・ 08葺跨畠o賃巽p=︵℃胃国o轟。。“>昌α賊ひy﹃Ω∪,一こ℃賀一ω一3資や呂g㎝■い切﹃琶\O毘帥且いN。&■蓉■ρ℃ 一〇。軌o什ω・ による。邦語文献として、石崎政一郎﹁就業規則の地位についてーフランス法の考察1﹂法学一六巻三号五頁以下参照。 ︵5︶冨﹃象Ωく﹂8雪<﹂。。8u■勺﹂。。ひひ﹂ふ合Ωく﹂ひ暴房むβq国一。8一﹂§Ωく﹂ご旨一8ざu・℃・ 一〇〇QQ、一隆一轟O ︵7︶ Ω<’NNヨ巴一8。。︸落■亀卜㌦Ω︿・一〇欲<﹂oNρO・ロ一〇b。9一・誌o ︵6︶Ω<,ま喜<﹂。。ひ9。︾ミ■嚇Ω<甲曽暴二8。。、u。℃﹂ε。■一﹄9Ω<﹄。。ヨ巴一。一ρ∪砧﹂。F卜鴇 ︵8︶ Ω<乙一睾<﹂ερuo﹂ερ一﹂o。“労働者が文字を読めず、規則の内容を理解しえないことを理由にその適用を否定し ︵9︶Ω<・。象。﹂8N訪﹂8。。﹂、軌o曾Ωく.N。。ヨ巴一〇一〇も>ミ・ た原審の判断を、採用の際に規則を読み聞かせたとの使用者の主張に答えていないとして破棄した事例である。 ︵10︶ Ω<ひト。刈旨巴一80。’ψ一800倉一薗N自 ︵11︶Ω<﹄。。甘甘一8Pq℃■ら一〇﹂﹄一本件においては、一審が原告労働者は採用の際に就業規則について知らされなか 棄院はこれに対し、就業規則が相手方に知らされることができたというだけでは不十分であるとして、原審の判断を破棄した。 ったとの理由でその適用を拒否したのに対し、原審は、同僚によってそれを知らされたはずだとしてその適用を肯定した。破 ︵12︶Ωく﹂どきくレ8ρq唱﹂8ひレ﹄台労働者が実際に就業規則について知り、それに同意したと評価されるか否かは、 原則として事実審裁判官の権限に属する。RΩ<ヒ念。﹂8ざq℃﹂8。。・一・命o 390 懲戒処分法理の比較法的研究 H ︵13︶9Ωく,卜。隷<﹂o。oo。bq℃﹂o。oo。.一・いま︵予告期間を遵守せずに退職することに対して違約金を定めた就業規則の適用 を否定した原審判断を破棄した事例︶uΩ<・一。。甘一﹂8避ω﹂8頓﹂・轟ω︵レストランのボーイにつき、受領しなかった飲食 ないとして、立替代金の半額の返還を使用者に命じた原審判断を破棄した事例︶ 代金を立替えさせる旨を定める就業規則が存在する揚合に、裁判官は衡平を理由に適法な合意の明確な条項の適用を拒否でき ︵14︶逆に、就業規則に罰金の定めのない場合について、使用者は罰金を行使しうるか否かについて明確な判断を下した判例は 見出しえなかった。ただし、出勤停止については、就業規則等に明文規定のない揚合には使用者はそれを行使しえないとする ︵15︶本稿第一部・法学研究13二〇三頁参照。 ものがあったが、これについては第五章第二節参照。 ︵1︶ 2 学説 これに対して一九三二年法成立以前の学説も、罰金がそれとして合法的なものであり、それが民法典にいう違約金 であることを承認していた。しかし学説は、判例が罰金を違約金としてとらえることによって、裁判官による減額を ︵2︶ 否定したことについては批判的であった。たとえば、カピタンuキューシュによれば、罰金は使用者に対して何らの 財産的損害をもたらさない行為︵不服従、礼節を欠く行為、規律違反など︶にも科されるが、そのような揚合には罰 金は厳密な意味での違約金でも損害の填補でもなく、真正の刑罰であって、そのようなものとして契約の内容になっ ているという。そして、労働者は科された罰金の額が高すぎることに対して異議を述べる権利を放棄しているわけで はないとして、罰金の額に対して司法審査が及ぶべきことを主張した。しかし当時の学説にとっての最大の関心は、 ︵3︶ やはり現実の罰金制度に付随する多くの弊害に対する立法的規制の必要性にあり、罰金の本質やその法的根拠の間題 ︵4︶ にまで立ち入ったうえでの判例に対する本格的批判は、後の制度説の出現に侯たねばならなかった。 ︵−︶ ピックは、罰金は労働者自らの利益によっても正当化されるとする。つまり、使用者から罰金という手段を奪うことは、 391 一橋大学研究年報 法学研究 14 使用者に対して、解雇または出勤停止という、労働者にとってより不利益な措置をとることを促すというのである︵ピソク・ ︵2︶ ピック・前掲書一四四頁。O巷一3暮、99ρマぐ一 前掲書一四四頁以下 ︶ 。 ︵3︶08誇算\99ρや一Σ雲ω■ただしそこでは、真正の刑罰としての罰金も、契約自由の原則により、契約の内容たりう ︵4︶たとえばビックは、フランス議会は罰金規制問題の審議再開について合意するまで待つことで、実際には暗黙のうちに使 ることが主張されて い る 。 約的な自由の状態よりは規制のほうが良いことは確かだとして、その実現を促していた︵ピソク・前掲書一四五頁︶。 用者の恣意を正当化することになったとし、下院が罰金の規制よりもその全廃を好むことは理論的には認めるが、現実の無制 二 初期懲戒法理の性格 以上のように、一九三二年法制定以前の罰金に関する判例および学説は、その法的基礎を労使間の契約による合意 に求めるという点では、純粋な契約説と呼びうるものであった。しかしながら、この時期のフランスにおいて、使用 者が労働者の非違行為を理由に懲戒処分として行使する種々の措置について、それらを使用者の懲戒権の発現として とらえ、統一的な懲戒法理の下に包摂することは、未だ確立していなかったように思われる。 たとえば使用者により懲戒ないし制裁の趣旨でなされた即時解雇について判例上問題とされたものは、それが使用 者に解雇予告義務を免れしむるに足るような労働者の重大な︿非行﹀︵融暮①鴨巽o︶に基づくものか否か、あるいは それが労働者に損害賠償請求権をもたらす濫用的解雇か否かであって、そのことは決して﹁懲戒﹂としての解雇であ ︵−︶ ることに特別の意義を認めるものではなかった。判例は、懲戒としての解雇についても、使用者の雇用契約に基づく 解約告知権ないし解除権の行使として、あくまで一般的な解雇法理の枠組のなかでそれを処理したのである。他方で 392 懲戒処分法理の比較法的研究 H 特に破棄院は、会社の規則に即時解雇事由が定められている場合にそれを適用してなされた即時解雇について争われ た事案において、次のように判示した。 ︵2︶ ﹁その処分が、︵中略︶その重大性において明白であり、服務規程によれば免職︵器莫o一︶によって罰せられうるような︿非行﹀ ︵猷暮o︶を理由になされたことは否定されていない。従って、当事者の法である上記規程の文言に照らし、会社は職員の規律 と安全のためにその規程が適用されるべきか否かを認識することについての唯一の判定者︵器三冒鴨︶である。﹂ ︵3︶ このように破棄院は、解雇についても先に見た罰金と同様、就業規則の規定に絶対的な効力を認め、しかもその適 用について、使用者こそ﹁唯一の判定者﹂であるとして裁判所の介入を否定した。その基礎にあるものは、あくまで、 就業規則を媒介とした労使間の合意の絶対性と、企業運営に対する使用者の絶対的支配権限の承認である。 一方、当時の学説においても、使用者の懲戒処分を包括的に懲戒権の概念によってとらえ、あるいは統一的な懲戒 ︵4︶ 法理を構成するものは見当たらず、主として罰金およぴ解雇について、あくまで個別的な考察がなされているにとど まる。従ってここでは、それらの学説にいちいち立入って考察することは差控え、引き続き制度説の検討に移ること にしたい。 ︵1︶ 当時の解雇に関する法制度およぴそれをめぐる学説・判例、特に即時解雇およぴ濫用解雇の概念や意義については、外尾 健一﹁フランスにおける解雇の法理﹂季刊労働法一八号二〇頁、石橋主税﹁フランスにおける解雇権濫用の法理﹂九大法学 ︵2︶ oo8■ぐぎく﹂80。’qoり,這QPマ象o本件は、電力会社の従業員が酒に酔って出勤し、同僚に傷害を負わせたことを 四号二三頁、同﹁解雇権の濫用ーフランス法における特質ー﹂法政研究二八巻四号四二九頁参照。 対し、破棄院は本文に引用したような理由でそれを破棄した。 理由に即時解雇されたという事案であるが、原審がその処分は過重であるとして予告期間に相応する賠償の支払を認めたのに ︵3︶ ﹁唯一の判定者﹂の概念そのものは、それ以前にも、経済的理由に基づく整理解雇対象者の人選︵Ω<●田ヨ弩のG寅層 393 一橋大学研究年報 法学研究 14 甲一〇いN一舘9Ω<,一轟ヨ臥6雛’ω■G雛﹂.まい︶や企業組織の変更︵OOOρ田9<,ちお、qOO。一30”サい獣︶、労働者の 提供する労務の性質︵Ω<・一〇。旨胃ω這いρ∪・型這8・ドNごΩく・一軌αひ。﹂£9Uり一8ざやo。“︶などの評価についても、 である。なお、この﹁唯一の判定者﹂の概念は、その後の判例においても拡大の一途をたどることになる。 破棄院が言及していたものであった。破棄院はそのことを、懲戒措置行使のための就業規則適用の評価についても拡張したの ︵4︶ 解雇に関する学説の状況については、前掲注︵1︶の文献に譲る。 第一節制度説による懲戒権の基礎理論 第四章 制度説による懲戒理論とその影響 一 序説 フランスにおける初期の契約説に対する批判とその克服のうえに、懲戒処分に関する統一的法理を形成しようとす る試みは、右に見た罰金規制法の制定ののちに、有力な学説によって推し進められることになる。それは、当時のフ ︵−︶ ランスにおいて擾頭しつつあったいわゆる制度理論︵些8言号一.一塁葺註9︶に依拠し、企業を一種の制度︵5畏ξ− 菖8︶としてとらえることにより、企業の長の懲戒権︵宕瑳oぼ象豊讐旨一器3畠鉱α.Φ旨器冥羅︶を法的に基礎づ け、それを中心に労使間における懲戒処分を体系的に理論化しようとするものであった。このような立揚を最初にか つ大胆に提唱したのがレガルおよぴブレート・ド・ラ・グレッセイ︵以下ではレガル“ブレートと略称︶であり、そ れをさらに理論的に整理・精緻化したのがデュランであった。ここではこのような見解を、それまでの契約説と対比 394 懲戒処分法理の比較法的研究 n する意味で﹁制度説﹂と呼ぶことにする。この制度説こそは、その後の学説・判例に対しても直接・間接に多大の影 響を及ぼし、現在のフランスにおける労使間の懲戒処分に関する法理の基礎を形成したものである。 ︵2︶ この制度説による懲戒理論は、わが国にも少なからざる影響を及ぼした。ただし、従来のわが国においては、それ を支持する立揚にせよ批判する立揚にせよ、ともすれば制度説による懲戒権の根拠づけについての理論構成のみが過 度に重視されてきたきらいがないではない。使用者に対し、その資格に内在する固有の懲戒権を承認することがそれ である。しかし、制度説の持つ意義は、決してそれにとどまるものではない。むしろそれに対する批判のうえに形成 されたわが国の懲戒理論自体が、たとえ間接的であるにせよ制度説による影響を受け、あるいはその多くの帰結を理 論的に形を変えて取り込んできたことも事実である。そのような意味で、ここで改めて制度説の内容とその意義を検 討することは、同じく使用者の懲戒権に関する法理論として形成されてきたわが国の懲戒法理を再検討するうえでも、 一つの重要な前提となるものと思われる。 そこで以下では、まずレガルnブレートおよびデュランの懲戒理論についてやや詳細な検討を加えることにより、 制度説による懲戒理論の意義と問題点を明らかにしたい。 ︵1︶ =p9冨Fび曽什募03自o一、旨駐ε試曾9山o一㊤︷9α鋒凶oP高9霞Φ﹃αo訂20ロ<〇一一①一〇9幕96N卸寓窪﹃一①F、嵩§愚塁 隆三﹃米谷隆三選集︵第一巻︶﹄︹﹁米谷隆三選集﹂刊行会・昭三五︺第一編を参照。 辞辱ミ博さミ﹂29菊魯畦99ミ鳳ミミ誉∼、焼誤ミミ軌§層o∩ぎざ評冨一8ρ なお、これらの制度理論については、米谷 法の理論﹄︹有斐閣・昭三五︺四四五頁以下などによってわが国にも紹介されており、一部の学説の支持を受けたものの、い ︵2︶制度説の概要については既に、花見・前掲書一五七頁以下、片岡昇﹁懲戒権の根拠と限界﹂菊池還暦記念﹃労働法と経済 わゆる固有権説として活発な批判の対象ともなった。以下の検討も、それらの紹介・研究に負うところが大きい。 395 一橋大学研究年報 法学研究 14 ニ レガル”ブレートの基礎理論 − 序説 ︵1︶ レガル”ブレートは、一九三八年に出版された﹁私的制度における懲戒権﹂と題する著書において、私的団体にお ける懲戒権についての総合的・体系的な法理の構築を試みた。同書では、単に経済的企業における使用者の懲戒権の みならず、家族や組合を含む多様な社会的団体における懲戒権が研究の対象とされている。そこでの著者の基本的態 度は、団体の内部における懲戒という集団的現象について、個人主義思想に基づく契約理論による理解を否定し、そ の実体に則した団体法理によって説明しようとするにある。そしてその理論的基礎が、それらの団体の﹁制度﹂とし ての把握であった。ここでは、そのような包括的理論の中から、経済的企業における使用者の懲戒権について論じら れた部分を抽出し、同書の全体的構成との関連をも考慮しながら検討を加えることにしたい。 ︵1︶ H粛巴葛器芸0359窃ω曙ρ壽唐ミoミ禽鶏愚鳶ミ蓄駄§砺醇帖着ミミ軋§恥篭註鼠罫勺貰跡ちお︵本書については、 法学協会雑誌五八巻五号七〇一頁に川島武宜博士による書評がある。︶なお、ブレートが使用者の懲戒権を論じたものとして、 切措苗①αoす08ω舞畷9Uo℃o仁くo貯象曽昼一ぎ巴おα999α、窪#o冒﹃PU■ω■一8ρ℃・α象がある。 2 内容 ω 集団的現象としての懲戒の把握と契約的理解の排除 レガルuブレートは、まずはじめに、フランス法にお いて伝統的に支配的であった個人主義的法思想と、それに基づく懲戒の契約的把握方法に対して次のような批判を加 える。 ー フランス法においては、従来個人主義的法思想が支配し、意思の自治の論理に基づく契約法理と契約的構成が大き 396 な影響力を有してきた。そのような法思想によれば、法の淵源は法律と契約の二つしかなく、また、国家以外には権 ︵1︶ したがって、団体とその構成員の関係は相互に平等な個人対個人の関係に帰せしめられれ、私的集団においては、権 威に基づく懲戒権や構成員に対する団体の優位は存在しえない︵まαq蔓︼w冨跨ρや軍し一い︶。その結果、経済的企業に ︵2︶ おける就業規則は労働契約の延長ないし付属文書としてとらえられ、罰金の定めは民法典にいう違約金として構成さ れる。しかし、罰金は、使用者に対してはじめから損害を生じえない行為について科されるときは賠償としての性格 ︵3︶ ︵4︶ を有せず、違約金の概念と相容れないだけでなく、それが被害者たる使用者以外への支払を強制される.︺とを説明し えない。また、契約説による限り、戒告や謎責についても有効な説明を見出すことはできない。したがって、懲戒の 契約法的理解は、懲戒の実体にそぐわず、その具体的な理論構成においても破綻をきたすものである︵■甜p一扇︻窪冨㌧ や嶺︸や一薯9ω■︶。 以上のような批判のうえに、レガル“ブレートは、懲戒罰の性質と目的を明らかにするためにその現象を分析し、 それは集団の存在と円滑な運営を確保するために必要とされるものであり、その集団が創設されるところの目的、す なわち個人に対して犠牲を強いる集団的利益という目的を達成するためのものであると結論づける。そア︶で見出され るものは一つの権威の存在であり、個人としての構成員に対する集団の優位である︵■粛巴葛門窪一ρつぐ︶。このこ とから、レガル一ブレートは私法上の団体においても公法におけると同様の懲戒権が存在するものとし、それを﹁団 体の構成員に対し、一定の制裁により、その存在理由である集団的利益という目的に沿って行動する.︶とを強制する ための行為準則を課すことを目的とする、一つの法的権限﹂︵い謬巴窃冨芸ρ℃﹂。。︶と定義づけている。そこで問題 は、右のような懲戒権が、いかにして法的に根拠づけられるかである。 397 威︵鎧ε目蒙︶は存在しえず、国家と個人の間には主権を有する中間団体︵8もω一旨窪琶&芭8の︶は存在しない。 懲戒処分法理の比較法的研究 n 398 働 制度理論による懲戒権の根拠づけ 団体の個人主義的法思想による理解の克服は、その対外的関係につい ては法人実在説により、その内部的関係についてはオーリウの制度理論によってなされた︵u甜旦ω冨9①・や曽6Q︶。 レガル“ブレートは、私的団体における懲戒権をこの制度理論によって基礎づけようとする。 行使は、決して機関自身の利益においてではなく、共同の利益において行使されるぺきものであり︵ま竪<ωみ99 ︵8︶ や象︶、そこに後に述べるような懲戒権行使の限界の根拠がある。要するに制度は、法的観点からすれば、本質的に 性は、同時に制度の集団的利益によって限界づけられるものである点に留意しておく必要がある。機関による権限の 機関により行使される権威は、制度をその目的の方向に導き、それに応じて構成員の活動を統制するために不可欠の ︵6︶ ものであり︵い粛ミ国盛芸9サミ︶、その意味で、﹁権威は制度に内在する﹂︵■費旦卑窪5や翫︶。そしてその限り ︵7︶ で、制度における権威は構成員の利益に優位し、機関と構成員の関係は不平等関係となる。ただし、この権威の優位 このような社会的実在としての制度は、その機関が権威ないし命令権限を行使することによって法的実在となる。 いい9幹︶。 に必要な安定的.継続的な組織、すなわち永続的組織︵oおき一紹怠自究同旨目Φ暮①︶の存在である︵■£旦b准夢ρう は必然的に構成員の個別的利益に優位する︵[猪巴扇3跨ρ℃﹄。。9ε。いま一つは、共同の理念を実現するため ︵び粛卑一葛.鍔一①・やト。軌9ε。そのような社会的実在としての制度は、二つの要素を有している。一つは、団体にお ︵5︶ いて共同で実現されるべき共同の理念︵一α魯8ヨヨ昌o︶ないし集団的利益︵首富議酔8一一8試窪︶の存在であり、それ それは個人の個人に対する関係とは異なる性格を有する社会的関係︵一一曾。。8芭︶の存在によって特徴づけられる 社会的実在としての制度を論ずる。すなわち、制度の基礎となる事実とは個人を超えた独自の人的集団の存在であり、 レガル目ブレートはまず、制度理論は社会学に基礎を置き、社会学的観察から法的結論を導くものであるとして・ 一橋大学研究年報 法学研究 14 共通の利益に奉仕し、個人的権利とは全く異なる権威・権限の存在によって特徴づけられるのである︵■譜巴窃&夢ρ や$︶。 以上のような制度理論の展開を前提として、私的集団の機関により行使される制裁は、構成員の一般的利益という 目的への服従に基づく客観的権限の発現としてとらえられる。それは契約とは無縁のものであり、あくまで集団の法 にょって規律されねばならない︵い甜巴扇5跨ρやミ簿ω■︶。 ㈲ 制度理論の企業への適用 このようにして団体の内部的関係についての制度理論を展開したのち、レガ の巴\卑卑ぎ・や曾9εが、ここでの直接の検討対象である経済的企業は、家族と共に第一の﹁支配的形態による ︵n︶ 制度﹂ に 分 類 さ れ る 。 右の制度形態のうち、第一と第二の形態を区別するものは、それぞれにおける構成員と権威の地位の違いである。 第二の形態においては構成員は相互に平等であり、ただ、選挙により機関の地位に就く者が職務として権威を行使し、 その限りで不平等関係が帰結されるのに対し、第一の形態においては構成員相互の関係は本来的に不平等であり、権 威はその長に固有のものである。経済的企業の揚合、労使間には平等関係は存在せず、しかも権威は企業の長として 一■・αq巴葛﹃α跨ρや訟︶。 の使用者にとって、その資格に内在する権利である︵..■.砦8簿価o韓呂爵o詳窓目一Φ饗貫oP冒竃お諄酔路2p− 一一 しかし、実際には使用者は利潤獲得という個人的利益において行動し、労働者もまた独自の個人的利益を有してい .、 ることは否定しえない。それにもかかわらず、経済的企業は制度という一般概念に含ましめうるものであるのか。レ 399 ルuブレートは、制度を﹁支配的形態による制度﹂︵言ω窪9一9窪9旨①℃緯8轟一①︶、﹁協同的形態による制度﹂︵目の− ︵9︶ 簿暮一9眺︷9日①8弓o旨自くΦ︶、﹁財団﹂︵8邑塾8︶の三つに分類し、それぞれの懲戒権の範囲を論じている︵い傘 懲戒処分法理の比較法的研究 E 一橋大学研究年報 法学研究 14 ガル”ブレートは、以下の諸点を指摘することによってそれを肯定する︵■紺亀ω冨9Pう訟9ω・︶。 第一に、経済的企業においては、労使の個人的利益を超えた共同の利益が存在する。確かに企業の長は利潤という 個人的利益において命令を発するが、同時に富の生産という共同の利益の観点からの支配を行なうのであり、労働者 もまた、その個人的利益を超えて富の生産という集団的利益に関与する。そしてそのような利益は、使用者および労 働者の個人的利益に優位するものである。 第二に、企業は一つの永続的組織を形成している。一方で、従業員はしばしば入れ替わるものの、全体としては変 動しない。他方で、企業はその財産的所有者の変更、在庫、施設などの物的要素や顧客の変動にもかかわらず、その 同一性を保つ。また、使用者の法律上の地位の変更にかかわらず労働契約が新事業主との間に存続するという労働法 ︵U︶ 典の規定も、その趣旨を示すものである。 第三に、企業には制度を特徴づけるいま一つの要素である制度の内部的関係を規律する法としての、就業規則およ ぴ労働協約が存在する。就業規則は、一般に考えられるように契約としてとらえられるべきものではなく、少なくと も事業揚内の規律、安全、衛生に関する部分については法規とみるべきものである。 ︵12︶ 第四に、企業は他の制度と同様、独自の機関を有している。支配人や経営担当者、工揚・支店の長などは、企業の 長との関係では契約によって結ぴ付き、その個人的利益において行動することは否定できないとしても、同時に企業 の発展という集団的・永続的目的のために業務の遂行を確保し、その限りでまさに制度のために権限を行使するので あり、その意味でそれらの者を制度の機関とすることに何らの妨げもない。また、それとは別個に、従業員の利益を ︵13﹀ 代表するものとしての工揚委員会︵8屋包α、拐言Φ︶が外国法上承認され、フランスの一部でも設置されることがあ るが、それもまた企業における固有の機関と呼びうるものである。 400 懲戒処分法理の比較法的研究 H においては、﹁協同的形態の制度﹂とは異なり、権威は使用者のみに帰属し、労使間にはいわば本来的な不平等関係 以上のようにして、経済的企業もまた、制度としての共通の要件を備えることが説明される。しかし、経済的企業 が存在するのであって、懲戒もまた、使用者から労働者に対する一方的関係において発現する。このことは、単に企 業の制度としての一般的要件の具備を指摘するだけでは済まされない問題であろう。そのような﹁支配的形態の制 度﹂としての企業の特殊な性格が、いかなる理由によって正当化され、またそこで発現する権威および懲戒が、いか にして他の制度形態におけるそれと同一の法的基礎に服するのかが明らかにされねばならないはずである。 ところが、この点に関するレガル“ブレートの説明は、必ずしも十分なものではない。この点に関して述べられる ことは、せいぜい企業所有権の帰属主体の問題と、企業運営についての責任と危険の負担問題にすぎないからである。 すなわち、使用者と労働者の間の不平等関係の根拠として説明されることは、企業が使用者の排他的所有にかかり、 ︵耳︶ 労働者はいかなる責任や危険をも負わないということに尽きる。先に指摘したように、経済的企業においては権威が ︵15︶ 使用者の企業の長としての資格に内在するということも、同様の理解に基づくものであった。 四 使用者の懲戒権に対する服従 最後に、使用者により労働者に対して懲戒権が行使されるためには、懲戒 権への労働者の服従︵霧ω三&器Φヨo馨︶がなけれぱならない。しかしその服従は、決して契約に基づくものではなく、 ︵16︶ 労働者による共同の目的ないし集団的活動への任意の附合︵区ま巴9︿o一9琶3︶により基礎づけられる。附合とは、 個人を制度の構成員たる客観的地位につけるという効果を伴う地位設定行為︵p9Φ占o民識2︶であり、それに附随 する個々の結果についての合意は不要である。また、そのような附合は、私的制度においては強制されたものであっ てはならず、あくまで任意的なものでなければならない。そして、経済的企業においては、そのような附合による労 働者の懲戒権への服従は、採用の二次的結果であるにすぎないという︵い粛ミ団3昏ρで一象o叶ε。 401 一橋大学研究年報 法学研究 14 ︵−︶ すなわち、法律によって禁じられないすぺてのことは個人間の契約による意思の合致によって決められる。﹁契約はすべ ての二とを説明する﹂のである︵ピ費巴鳶&些ρや軍︶。 ︵2︶ 前章において検討した初期の判例および学説を参照。 ︵3︶ レガル“プレートは、そのような例として、労働者が工揚内で歌を歌ったり、上司に対して不遜な態度をとったような場 害の填補を目的とする賃金控除は、違約金としてとらえうるとしている︵匿σq巴扇3些9唱﹄曾。梓、,︶。 合をあげている。それに対して、たとえぱ仕事の不手際︵日鐘君8︶の揚合のように契約上の債務不履行によって生じた損 ︵4︶ 一九三二年の罰金規制立法により、罰金として徴収された金員が使用者ではなく従業員の安全基金に払込まれねぱならな くなったことを指す。 ︵5︶ レガル”ブレートによれぱ、それは、社会的関係を結合し、構成員の考えや行動を統合させる.一とによって、団体にその 存在を与幻るものとして理解される︵い粛亀切審葺9マ8︶。 ︵6︶ しかしその揚合にレガル艮ブレートが制度に内在する権威を基礎づけるために持ち出すものは、自然法の原則、すなわち ではなく、永続的な社会的団体ではないことを確信せしめる﹂と述べられているにとどまる︵い命巴萄.α9。・つ出︶。 ﹁事物の性質により要求される自然法の原則﹂にすぎず、そのほかには﹁理性と経験とが、我々をして、権威がなければ制度 ︵7︶ ただしその条件として、目的が合法的であること、他の制度の優位的目的を不当に害さない.一と、構成員の絶対的個人権 を害さないことがあげられる︵■拾巳、切箒9ρや睾︶。 ︵9︶ これらの訳 語 は 、 川 島 ・ 前 掲 書 評 に よ る 。 ︵8︶本章第二節四 参 照 。 ︵−o︶ このうち第一の類型には家族およぴ経済的企業が、第二の形態には、協同組合、株式会社、社団、職業組合などの、他の 多くの団体が属するものとされる。 ︵12︶ レガル”ブレートは、就業規則が全体として法規たる性質を有するものとはとらえていない。就業規則のうち、賃金や解 ︵11︶労働法典︵旧︶第一巻第二三条六項、現行L=三ー一二条。 402 懲戒処分法理の比較法的研究 H 約告知期間などの労働条件を定める部分を契約的部分、規律や安全衛生に関する部分を法規的部分として区別する。そして、 前者については契約の方式を支配する原則にしたがって処理され、労働者の合意が問題とされる︵レガル”ブレートは、ひと たぴ締結された契約は一方当事者の意思により変更されえないという︶のに対し、後者は使用者が企業の長として企業の利益 o鈴ω,︶。 において一方的に定めるものであり、当事者の合意とは無関係に公示によって効力を生ずるとしている︵い粛巴葛器荘。も﹂鴇 ︵13︶本書が出版された時点では、フランスの企業委員会およぴ従業員代表制度は未だ法制化されていない。 ︵14︶ ﹁権威が労働者と分かたれることなく使用者の手に集中しているとしても、それは、現在の経済体制においては唯一資本 と利潤の所有権を有する企業家がーただし議論はあるがー企業それ自体と同一のものと考えられ、しかもその排他的権威 ︵15︶ ﹁資本主義的企業にあっては、それは使用者の排他的所有物であって、そこでは指揮権は当然に使用者に帰属し、それが は彼のみが負う責任と危険に必要的に見合うもの︵8耳﹃。−饗丑・︶だからである。﹂︵い諸巴窃み些9やお︶ ︵16︶ レガルロブレートは、労使関係が契約関係であること遼全面的には否定していない。しかしそれは労使間の労務およぴ賃 全体として使用者から奪われることはできない。﹂︵U甜巴葛抽芸ρや9︶ されるのである。 金の交換関係に限定され︵その限りでは当事者は平等である︶、懲戒関係はあくまで労働者による任意の附合に基づくものと 3 若干の検討 制度説そのものについての評価・批判は後に譲るとして、ここでは右に見たレガル“ブレートの基礎理論に現われ た基本的視点および方法について、若干の問題点を指摘しておく。 レガル,ブレートは、当時少なくともその法律学上の意義や内容については発展途上にあった制度理論に依拠し、 私的団体における懲戒についての統一的法理をうち立てようとした。当時の制度理論の私法関係への適用の主要な関 403 一橋大学研究年報 法学研究 14 心が、主として民商法学者による、契約と対比される意味でのいわゆる創設行為︵螢9¢38呂駐9︶の概念による ︵1︶ 約款理論の構築に向けられていたのに対し、私的制度の内部活動における秩序形成手段としての制裁権限に着目し、 それを制度理論における権威の一発現ととらえることによってその理論化を志向したこと、およびそれによって従前 の契約理論に依拠した懲戒法理を真正面から批判し、懲戒法理に全く新たな展開をもたらした点に、レガル旺ブレー トの懲戒理論の意義がある。しかし、それが制度における懲戒権に関する法理論であることを考えるならば、その理 論展開については少なからざる疑問が生じてくる。 ︵2︶ レガル“ブレートの基礎とする考察方法、それは、自らも言明するごとく、法社会学的なそれである。オーリウ、 ルナールらが、制度の要素として共同の目的ないし利益︵答曾曾弦88旨ヨ巷︶、権威︵窪8同ま︶、協和ないし ︵3︶ 親和︵8ヨ目目巳92冒葺巳泳︶を挙げるのに対し、レガル”ブレートが社会的実在としての要素として目的︵理念︶ と永続的組織を挙げ、法的実在としての制度の要素として権威および機関と制度内の法の存在を挙げるのも、そのよ うな立場に基づくものと思われる。しかし、その論述を見る限り、社会学的観察から法理論への移行ないしそれらの ︵4V 相互の連関については、十分な説明がなされているとは思われない。制度の本質的要素としての目的と永続的組織の 存在が確認されるとしても、そこから何故に制度に権威が存在することが導かれ、法的に承認されるのかが明らかで はないのである。そこで示される唯一の説明、すなわち、﹁事物の性質により要請される自然法の原則﹂︵い粛巴\ 団5荘ρや挨︶についての言及も、それが﹁理性と経験﹂に基づく確信であるとの指摘にとどまらず、少なくとも その国家法上の意義、ないしはそれとの関連性を明確にするのでなければ、未だ十分な法的論拠とは言い難い。事実 的な法則性から法的な、ないしは規範的な論理への移行の過程が曖昧なのである。 このことは、経済的企業に関して使用者の内在的権威を説明する揚合にも現われる。そこでは、権威が使用者に帰 404 懲戒処分法理の比較法的研究 皿 属する.︸との根拠として、企業が使用者の排他的所有にかかることが指摘される。しかし、後に見るデュランも指摘 ︵5︶ する..一とく、﹁物に対する物権である所有権は、人に対する命令権を説明することはできない﹂。レガル”ブレートの 理解は、企業の所有者である使用者が労働者を支配しているという事実的確認を、十分な理論的媒介によることなく そのまま所有権の機能として法的にも承認し、ひいては制度における権威の発現として正当化するものにほかならな い。 次に、レガル”ブレートにあっては、私的団体における統一的懲戒法理の形成が志向されており、多様な団体や集 団を制度という単一概念によって把握することは、そのための理論的前提である。しかしその反面、そこでは個々の 団体や集団の有する特殊性は軽視され、ことさらに制度としての共通性のみが強調されていることも否定しえない。 レガル睡ブレートは、先に指摘したように、現実の私的団体を三つの制度類型に分類し、それぞれについての制度の 一般理論への適応性を検討しているが、そこで見られるものは、むしろ制度の一般的要件の個々の団体への強制的な あてはめとも言うぺきものである。経済的企業について言えば、企業の共同の利益が強調される反面で労使の個別的 利益は軽視され、また、企業の永続性が重視される反面で労働者が解雇という一方的措置によって企業外に放逐され ることは無視される。さらに、企業の監督者や管理職員が、きわめて抽象的な検討によって制度の機関の地位に押し 上げられてしまう。そして経済的企業がこのような考察によってひとたび制度の一形態とされるや、労使間の不平等 や使用者の絶対的権威は法的にも承認され、そこに統一的な懲戒法理が妥当するというのである。このようなレガル ”ブレートの基本的態度は、その社会学的考察方法の標傍にもかかわらず、きわめてドグマティッシュなものと言わ ざるをえない。結局それは、使用者による事実上の支配を家父長的支配と同質のものとしてとらえる封建的労使関係 ︵6V ︵7︶ 観によって規定され、それを単に制度理論によって新たな装いをまとわせたにすぎないとも評しうるであろう。 4D5 一橋大学研究年報 法学研究 14 ︵−︶ たとえば米谷・前掲書、同﹃約款法の理論﹄︹有斐閣・昭二九︺三八九頁以下参照。約款法における制度理論の意義につ ︵2︶ レガル“ブレートの前掲書は、その副題として﹁社会学的研究﹂を標傍している。また、訓度理論切適用にあたっても、、 いては、安井宏﹁普通約款の拘束力に関する一考察﹂法と政治二四巻二号一〇九頁以下参照。 ①叶呂。 ぐれが社会学を基礎とする法理論であり、社会的観察から導かれる法理論であるア︸とを明一一一一口している︵U訟p一扇.窪一一①︸℃.醸 ︵3︶ 米谷・前掲﹃約款法の理論﹄四〇七頁以下参照。 ︵4︶経済的企業については、いかにして二の目的が認識され、労使の個別的利益に優位する共同の目的となるのかも明らかで ない。レガル“ブレートはそれを﹁富の生産﹂としてとらえるが、それは本来使用者の個人的目的.利益であゆ、労働者が独 自の個人的利益に基づいて結果的にそれに関与するとは言いえても、それを制度の基本的要件としての共同の目的とすること ︵5︶U目帥呂﹂︾℃■爵命 は大いに疑問である。 ︵6︶川島・前掲書 評 七 〇 七 頁 。 ︵7︶ このことは、経済的企業を他の一般的団体と区別し、家族関係と同一範疇のものとしてとらえるレガル,ブレートの態度 経営がむしろ一般的団体と対比され、それとの関連において経営罰が論じられていることを想起すぺきである︵本稿第一部、 に端的に現われている。ドイツにおいては、初期における封建的労使関係観に基づく経営罰理論が次第に克服され、現在では 特に第三章第一節二、三参照︶。 三 デュランの基礎 理 論 − 序説 レガル“ブレートによって提示された制度理論に基づく懲戒理論は、 その後デュランによって再構成され、展開さ 406 懲戒処分法理の比較法的研究 H ︵−︶ れた。レガル“ブレートにおいては、多様な私的団体における懲戒についての統一的法理の形成が志向され、私的企 業における懲戒はその一環として論じられた。それに対してデュランは、むしろ制度理論を基礎とした労使関係にお ける懲戒権についての独自の法理論の形成を意図したのである。以下では、デュランの懲戒理論の基本的概念である 労働関係︵邑呂83可轄毘︶および企業︵魯鉾名岳①︶の意義を中心に、その基礎理論を見ることにする。 ︵−︶穿鵠&り評星円ミ慧魯辱ミ§、ミミ嚇ぎ旨①一︵巽8冒扇器且ソ評器一。ミ一8目。N︵還8≦εy℃碧一ω一凛9 男o養ωミUq声&りbミ魯§、ミミ騨O①8こ勺鴛冨一8一 2 内容 ︵1︶ ω 労働関係論と制度理論 労働関係の概念は、ドイツにおいて形成され、展開されたものである。デュラン はその理論に着目し、とりわけ経営協同体への組入れないし編入を重視するジーベルトおよぴニキッシュによる労働 関係理論を高く評価する。そしてそれをフランス労働法にも導入しようとし、その接点をフランスにおける制度理論 に求めた。 ︵2︶ デュランをして労働関係理論の継受に向かわしめるもの、それは、現実問題としての労働契約の占める地位の後退 ︵3︶ と、それに代わる新たな法的範躊の必要性についての認識である。労働関係論こそは、そのような事態に対して適切 な対応を示すものであるという。そして、デュランによれば、労働関係論が基礎を置く諸原則がフランスに持込まれ ることを妨げるものは何もない。むしろ労働関係論における組織的共同体の概念は、フランスにおいてなじみ深い制 度の概念と同質のものであるという。たとえば、それらの二つの概念は、人的要素と物的要素の結合、内部的秩序、 共同の目的という同一の要素を有しており、共同体︵デュラン■によれば、連帯性に基づく労働共同体︶への編入は、 407 一橋大学研究年報 法学研究 14 408 まさに制度への附合︵区︸・診一8帥一、冒ω葺耳一8︶である。労働関係は、制度において企業の長とそれぞれの従業員を しかしこのことは、デュランにとって、無批判的な制度理論への依拠を意味するものではない。特に制度と契約の 結ぴ付ける法的関係である。 関係については、それらは相互に排除しあう関係にあるのではなく、むしろ制度理論の法的構造上の不完全性が契約 ︵4︶ によって補われるものと解されている。 このようにしてデュランは、労働関係論を媒介として、経営︵陣3冴器ヨ。算︶ないし企業の制度理論的理解に到達 する。そしてデュランによれば、経営は一つの強行的法規を有しているという。経営は一定の規則なしには存在しえ ず、そのあるものは国家に由来し、あるものは指揮命令権や懲戒権に関する規則のように内部的組織づけの必要性に よって課されるが、いずれにせよ経営が機能するための条件を定めるそのような規則は、まさに制度の法︵身o詳留 畳ε試8︶として理解される︵∪震彗ρ昌・やb。お魯幹︶。 てこのような観点からは、経営とは﹁継続的活動によって技術的目的を達成するために配置された、人的、物質的、 まで組織的社会としての企業・経営を研究することに基づかねばならないという︵∪目昏ρ卸マお頓卑ε。そし 済的社会的実体を個別的関係に解体することなく、その実体に則した構成要素およびそれを支配する法に従い、あく は共同の精神に支配された労働共同体︵8目目曽窪ま留#零毘︶となる。企業・経営理論の形成は、そのような経 デュランによれば、同一企業構成員の間にはその集団的経済活動の故に一種の連帯性︵のoま毘ま︶が存在し、それ ついての認識である。 成を志向する。その基礎にあるものは、労使関係における、個別的関係を超えた、より高次の法的・社会的実在性に ③ 企業・経営概念の理解 次にデュランは、企業および経営概念の意義を強調し、それらに関する理論の形 一. 懲戒処分法理の比較法的研究 ∬ 非物質的手段の統一体﹂︵U日器負どや80。︶であり、いわば生産の技術的統一体であるのに対し、企業とは、﹁市 揚のために一定の財を生産し、またはサービスを提供することを本質的に意図する組織体であり、経済的に他のあら ︵5V ゆる組織から独立したもの﹂、換言すれば﹁企業家の危険において運営される生産の経済的統一体﹂である︵U霞弩倉 Hbや80︶。 以上のように定義づけられる企業と経営は、労働法においては共同の目的のために組織化された集団として現われ る。デュランは、そこには制度としての特徴が見出されるとし、レガル”ブレートの用語にならって﹁支配的制度﹂ ︵冒ω葺暮一9饗茸8巴︶と呼び、その法的構成と組織について検討している。そこでは法的・社会的に独立した組織 的社会としての企業が直接の対象とされ、特に企業の内部秩序が従うべき原則として四点が掲げられているが、ここ では次の二点が重要である︵∪ロ声コρどやおN9幹︶。 ︵6︶ 第一に、企業は階層的社会︵89価ま巨鋤巽畠5垢︶として現われる。そこには一人の長、すなわち企業の長︵9巴 ロ、窪貫①駿ぎ︶が存在し、その資格に基づく幅広い権限を行使する。企業の長は優越的地位を有しており、彼が支配 ︵7︶ する集団は平等の基礎 を 有 し な い 。 第二に、企業はそのすぺての構成員の共同の利益︵臣窪8ヨ日巨①︶を確保しなければならない。使用者と従業員 は同一の組織体に属し、その利害は同一であり、その行動は共同の有用性︵暮ま菰8日日9。︶に奉仕しなければな らない。そのような共同の利益ないし有用性の観念が、企業家およぴ従業員集団の機能を基礎づけ、同時にその限界 を画定する。 このような企業の内部的秩序の原則に基づき、次に述べるような使用者の諸権限についての理論が展開されること になる。 409 一橋大学研究年報 法学研究 14 ⑬ 使用者の資格に内在する懲戒権 使用者は、企業の長として三つの権限を行使する。規則制定権︵宕量o耳 一甜芭ロ窪︶、指揮命令権︵℃8くo冒身盛お&8︶およぴ懲戒権︵窓瑳o蹄象豊讐轟ぼo︶がそれである︵∪目目ρ押や 畠い︶。これらの権限が使用者に認められることの根拠に関して、デュランは次のように述べている。 ︵8︶ まず、その根拠を企業の諸要素についての所有権に求める見解は正しくない。所有権は物に対する物権であるにと どまり、それによって人に対する命令権を説明することはできないからである。また、企業家は常に生産手段の所有 者であるとも言えない。そのためデュランは、その真の根拠は、企業の長が引き受けている責任︵み名o房魯葭ま︶ に見出されるぺきであるとする。﹁現在の経済組織においては、企業の長は営業上の危険の発生を伴う生産と交換を 確保する責務を負い、企業構成員の共同の利益を確保し、その目的を追求するために必要な権限を行使しなければな らない﹂。したがって、企業の長の権限は、その資格に内在的なもの︵言竃お算呼。。帥2巴ま︶である︵∪自塁ρH や畠斜︶。 デュランはこのようにして使用者の権限の統一的な根拠を示したのち、三つの権限について個別的な検討を加えて いる。 まず、規則制定権は、実際には就業規則制定権として現われる︵U巽睾“﹂や鳶軌9ε。それは経営における 労働条件を統一的な方法で定めるものであるが、同時に指揮命令権およぴ懲戒権に関する定めは、その行使に伴う不 ︵9︶ 確実性を排除することにより、従業員に対して一定の保障をもたらすという重要な意義を有している︵Uロ寅区・H・ マ一&︶。 次に指揮命令権は、業務について、一般的または個別的に、命令ないし指図を与える権限である。使用者は原則と して自由にその権限を行使しうる裁量権を有しているが、それは決して無制限的なものではない。第一に、それは公 410 懲戒処分法理の比較法的研究 n 序良俗に反しえない。第二に、使用者は労働協約、就業規則、労働契約の定めを守らなければならない。そして第三 に、使用者の指握命令権は、それが持つ目的性︵旨巴募︶によって規定される。それは、企業における労働の適切な 組織づけの実現のために使用者に認められるものである以上、その範囲内においてのみ合法的であり、その限界を超 えては存在しえないのである︵U霞雪“ごマao露ε。なお、このような指揮命令権の限界は、後に見るように、 懲戒権の行使を限界づけるものとしても重要な意味を有している。 最後に、懲戒権は、労働者が使用者の命令に違反した揚合に犯されたく非行V︵︷暫一。︶を罰することを目的として いる。ぐれは、企業の長としての使用者に認められる規則制定権および指揮命令権を補充飢るものとしての役割を果 ・ンできなければ危険にさらされるのであり、その意味で、懲戒権は、公的・私的を問わず、家族、社団、企業など たしている。デュランによれば、社会的団体の生活は、責任ある権威者が集団構成員に課された行為準則をサンクシ すべての制度において自然発生的に形成されるものであるという︵Uξ昏9どサ&ひ9ε。 ところで、デュランによれば、懲戒権の根拠は、国家により授けられた刑罰権にも、個別的契約にも求めることは できないものである。いかなる法規定もそのような授権をしておらず、しかも懲戒権は本質的に刑罰権とは異なる。 また、それは実際には契約により特別に定められていない揚合でも行使されており、他方で、契約にはよらない企業 構成員、たとえば特別配属者や徴用者、労働契約が無効な労働者に対しても、それらの者が経営内で就労する限りで 懲戒が科される以上、懲戒権の基礎を契約に求めることはできないという︵U9塁負押や&ひ︶。なお、懲戒権と労 働契約の関係については、後に懲戒理論の展開を見る際に、より具体的に明らかとなるであろう。 ︵−︶ ドイッにおける労働関係論については、片岡昇﹃団結と労働契約の研究﹄︹有斐閣.昭三四︺二四〇頁以下参照。また、そ れと懲戒理論の関係については、本稿の第一部第二章第二節二、第三節二︵法学研究13.一九七頁以下、二一八頁以下︶参照。 411 一橋大学研究年報 法学研究 14 ︵2︶ デュランの労働関係の理解については、次の文献を参照。U目㊤呂︸>簑宰8籔器身8簿﹃pけ魯3一、ぎ毘叶旨o員﹃ ︵3︶ その根拠として述べられることは、労働契約の内容が契約当事者の合意以外の要因︵法令、就業規則、労働協約など︶に 器一p鼠o昌留賃塁巴一廿いOー型一宝合p。いooざ∪ロβ⇒“一押やト。Oα9ω. 契約が無効な揚合にも適用されることなどであるが、これらはドイツの労働関係論において主張されることと同一であるので、 よって決定されること、労働法に固有の現象の説明について労働契約による説明がしばしぱ妥当性を欠くこと、労働法は労働 ︵4︶ このことは、デュランの労働関係と労働契約の関係についての理解を前提としている。デュランはこの点について次のよ ここでは詳述しない。 うな理解を示していた︵Uξきρ旨ρ型お盆=・。いo。N︶。 り、将来の時点での編入の義務を約定することが可能である。 ①労働関係は、労働契約を全く排除し、廃止するものではない。それは予備契約︵帥轟葺−8暮﹃馨︶に先行されうるのであ み形成される。それは、労働者が経営に組入れられた︵ぎ8壱o昼①ぎσq8&房梓︶ときである。 ②しかし、予備契約は労働関係を創出しない。労働関係は、経営協同体に入り込むという、事後の別個の行為によっての 有利な労働体制を形成することを可能にする。 ③使用者と労働者は個別的な合意を結ぶことができる。それは、立法者が課していない義務を創造し、あるいは労働者に デュランは、このような労働関係の理解に立ち、それと制度理論の接合を試みるわけであるが、そこでは特に制度理論にお ける契約の役割が強調される。たとえぱ、制度理論が制度への附合を問題とするだけでは不十分であり、共同体に入り込むた めの義務を問題としなけれぱならず、それは、通常は意思の合致、したがって契約に見出されなければならないとする。また、 ︵5︶ このように、経営の概念が生産活動の遂行といろ技術的要素を有するのに対し、企業の概念は企業家により意図された経 契約によって労働関係の内容を決定する可能性も残される。 済的目的を伴うものである。また、それぞれの経営は単一の小社会を形成するが、企業を特徴づける法的・経済的独立性を欠 いている。しかし、経営と企業はあくまで同一の組織の異なった二つの観点であり、企業を経営の全体または集合と解するこ 412 懲戒処分法理の比較法的研究 H とはできないという︵U葺きα㌧どマ全O簿幹︶。 ︵6︶ ﹁企業家は企業を構成する社会の当然の長である。その長は、実際に企業の目的を決定し、物質的手段を動かし、従業員 の労働を支配しなけれぱならない。労働法は、しばしばそれを使用者という語で示す。なぜなら、それは本質的に、企業にお ︵7︶ しかし、デュランによれぱ、従業員は純粋に受動的役割を有するのではない。とはいえ、従業員は決定する権限を持たず、 いて企業の畏とその労働者の関係に注目するからである。﹂︵Uξ雪負押マ盒。︶ ︵8︶ デュランは、その例としてジンツハイマーをあげている。本稿第一部第二章第二節二2㈹︵法学研究13・一九八頁以下︶ 企業の階層そのものは依然変更されていないという︵U日騨&﹂︸℃ト器①;■︶。 ︵9︶ デュランは、このような就業規則を実質的意味での法としてとらえる。すなわち、制度理論にいうところの制度に固有の 参照。 法である。ただしデュランは、レガル”ブレートのように就業規則の条項を二分してとらえることに反対し、就業規則はあく まで全体として法規と解すぺきことを主張している︵∪日彗ρどつ一摯9ε。 3 若干の検討 さて、以上にも見た。ことく、デュランは、レガル”ブレートのごとく最初に制度の一般理論を措定し、それに企業 をあてはめることによって労使間の懲戒権を基礎づけようとするのではなく、あくまで労働関係の特質と企業の内部 組織構造の分析のうえに懲戒権を基礎づけようとした。その意味では、先に指摘したようなレガル”ブレートに見ら れた理論的限界性は克服されているかのように見える。しかし、その懲戒権を法的に根拠づけるための論理過程をた どるならば、デュランの理論もまた、制度理論を前提とし、それに全面的に依拠するものであることが知られるであ ろう。 413 一橋大学研究年報 法学研究 14 デュランの理論は、ドイツにおける経営協同体思想に基づく労働関係論とフランスの制度理論を接合し、それによ って一般理論としての制度理論を労使関係の揚において具体的に展開しようとした点に意義があったものと思われる。 また、デュランが企業と経営を個別的関係に分解し尽くすことのできない集団的組織的関係としてとらえ、それらの ︵−︶ ︵2︶ 概念を法律学上および経済学上の意義を基礎として明確に区別したことも、その後のフランス労働法の展開を見るな らば、確かに重要な意味を有していた。しかし、それに続く企業の内部的組織に関する説明を見る限り、そこには制 度理論の多大な影響、というよりは、むしろ制度理論に全面的に依拠した議論の展開が見られるにすぎない。 デュランは、企業の特質として階層的社会としての性格と共同の利益を挙げ、そこから企業の長の三つの権限を導 き出す。ところが、それらの権限の法的根拠としてデュランが掲げるものは、企業の長が資本主義制度の下において 引き受けている責任と、企業の共同の利益を確保する必要性にとどまる。懲戒権についても同様である。そこでも、 社会的団体の生活にとっての制裁の必要性が強調されているにすぎない。しかし、そこでの問題の核心は、あくまで そのような責任ないし必要性に基づく使用者の権限が、いかにして法的に根拠づけられるかにあるはずである。とこ ろが、デュランがその点を曖昧にしたまま使用者の責任について語り、他方で企業における共同の利益が企業の長の 権限を基礎づけ、懲戒権がすべての制度において自然発生的に形成されると述べることからは、その問題はあげて制 度理論それ自体の問題として回避されてしまうようである。そこでは、企業がそれをめぐる現象の分析によって制度 としての要素を有すると結論づけられるや、事実的な必要性に基づく使用者の権限は直ちに法的なものへと転化せし められる。しかもそれは、あたかも制度理論からの当然の理論的帰結として説かれるものであった。その意味で制度 理論は、デュランにおいても、使用者が事実上の必要性に基づいて行使する権限を、まさにそれとして法的なものに 高めるための所与の理論的媒介項としての機能を果たすものにほかならない。 414 懲戒処分法理の比較法的研究 ∬ 勺巽一ω一〇軌ざb■ひ9ω■ ︵−︶ 企業が特に商法のような他の法分科で考慮されるのに対し、 経営の概念は第一に労働法で考慮される︵U弩p且﹂も﹄8 ①叶団,︶。 ︵2︶9u窃窟き置3。ごト.恥ミ需黛欝災驚昏ミ㌧■■o■o﹂; 四 制度説の波及 ,デュラン以降、彼の呈示した企業理論はフランス労働法学において広く受け容れられるところとなり、労働法上の ︵−︶ 基本的範瞬の一つとなった。それに伴い、懲戒権に関する制度説も、学説において優位を占めるに至った。 ︵2︶ その後の制度説の理論的展開のなかで特に注目されるのは、﹃企業と法﹄と題する著書において、それまでの企業 理論を集成し、総合的な理論化を試みたデスパックスである。彼はそのなかで、企業理論の基礎として企業と企業家 の分離︵e畏8鉱90耳お一、o艮お屈一8卑一、曾貫名お諾葺︶、すなわち経営と資本の分離を強調し、使用者の権限が機 ︵3︶ 能的︵8暮怠88なものであることを主張している。ただし、そのような権限の基礎として語られることは、制度 理論の承認とそれへの依拠の表明にとどまり、懲戒権の理解についても、レガルー−ブレートおよぴデュランのそれの ︵4︶ 域を出ないように思われる。 ︵5︶ また、企業理論への傾倒を示しながら、労働契約と並ぶ新たな法律関係として企業関係︵一ゆ8山、臼#。冒蓉︶の概 念を提唱したのがブルンである。ブルンは、それまでの労働関係論が結果的に契約関係を著しく後退させ、ほとんど その存在意義を否定し去ったのに対し、むしろその意義を積極的に認め、企業関係は契約関係と等位関係にあり、た だ企業関係の適用関係が契約よりも広いとする点に特色がある。そして、企業関係は労働契約とは異なる特別の権 利.義務を生ぜしめるものとし、その具体的な内容として懲戒権が語られる。しかしその企業関係の概念とは、ブル 415 一橋大学研究年報 法学研究 14 ン自身のいう従来の労働関係論を多少修正し、それに異なる名称を与えたにすぎないもののように思われる。そこで も、懲戒権の法的基礎についての独自の理論的展開はほとんど見られず、単にデュランによる労働関係論およぴ制度 理論に基づく懲戒理論への依存が述べられるにとどまる。 ︵6︶ ︵7︶ このように、懲戒権に関して制度説に立つその後の学説は、もっぱら制度理論に言及し、レガル“ブレートおよぴ デュランによる懲戒理論に依拠するにすぎないようであり、制度説の基礎理論それ自体のその後の新たな展開は、遂 に現在に至るまで見られない。その意味で、既に指摘したようなレガルuブレートおよびデュランの基礎理論に伴う 問題性は、そのままその後の制度説に立つ学説にもあてはまるものと思われる。 制度説が、使用者の懲戒権を基礎づけるために制度理論に依拠し、またそれに言及することによって懲戒権をめぐ る多くの問題があたかも論理必然的に解決されるかのごとき態度を示すことは、かえって非論理的なものとして批判 されるであろう。後に見る制度説に対する批判も、特にこの点を衝いている。しかし、単にこの点にのみ着目して制 度説に対して否定的評価を下すのであれば、それは不十分と言わざるをえない。制度説がそれまでの契約説に対する 批判のうえに登揚し、学説における主流的立場となったことの意義や原因が正当に評価されねばならないからである。 そしてこのことは、制度説による懲戒理論の具体的内容とその帰結を検討することによって明らかにしうるであろ ︸つo そこで次に、レガル”プレートおよぴデュランの所説を中心に、制度説による懲戒理論の具体的展開について見る こと に し た い 。 ︵−︶ 現在ではフランスにおける労働法概説書のほとんどすべてが﹁企業﹂を独自の基本的範晴として掲げ、その中で特に使用 者の諸権限と従業員代表制ないし労働者の企業参加問題を論じている。このことは、わが国の労働法学と対比した揚合の、フ 416 懲戒処分法理の比較法的研究 H ンスにおける﹃企業。耳.。℃円一。。。﹄概念の歴史的沿革﹂鈴木古稀記念﹃現代商法学の課題・下﹄︹有斐閣・昭五〇︺一六七一頁 ランス労働法学の大きな特色の一つである。なお、企業概念の沿革と特に企業参加に関する意義については、山口俊夫﹁フラ て﹂阪大法学一一八.一一九号一一三頁が立ち入った検討を加えている。その他、それがたとえぼ争議行為法の分野において 参照。また、企業制度理論の解雇理論への影響については、野田進﹁フランス解雇法改正の法理論的背景ー学説を中心とし がある。ただ、同じく企業制度理論といっても、実際にはそれが問題とされる局面や論者によって多様な理解が存在すること も論及されている.一とについては、石井保雄﹁現代フランスにおける職揚占拠の法理﹂労働法律旬報一〇〇一号八一頁に紹介 に留意しなければならない。たとえば、それが使用者の懲戒権︵およぴその他の権限︶に関して論じられる揚合には、労働契 約に代わる︵ないしはそれと同格の︶独自の法律関係形成の基礎として理解されるのに対し、右の解雇法や争議法の領域で は、むしろ労働法ないしは労使関係を広く支配する一種の指導理念として理解される傾向にある。フランスにおける議論自 体がこのように多様なものであることが、企業制度理論についてのわれわれ部外者の理解を一層困難ならしめているよヶに思 われる。 OhU。も弓饗き℃・N鴇gω∴u。ω鵠図㌧顛膏o℃誘p勘奪ミ鳳。ミ魯辱ミ憂∼ミ磐&き℃■圃。。いgp このことは、特に指揮命令権について重要な意義を有する。RO。ω冨〆マ爲ひ9望℃﹄& 切昌P︾p費ρい①=o昌山.o口賃o冥房ρ旨ρマ一8N●り一刈G U①ω℃貧︸三8冨ごト.恥ミ濫腎篭雛魁融昏o貰rPq触︸℃曽厨お鴇 ︵4︶ ︵3︶ ︵5︶ なお、ブルンが基本的には制度説に立つと思われることについては、右の論文の低か、ω歪ξO毘きq﹂。.融こ℃﹂湖9 ︵2︶ ︵6︶ o o こ 以上のほか、制度説に立つと思われる見解として、次のようなものがある。民8。嘗P年男始卜、§感ミ、ミ匙蔚§籍恥 マまωg幹を参照。 織N“馬鴨9建&きいρu﹂こ評ユの一〇蚕℃r。。N。戸ヨ穿婁ぎ一冒8・旦部・σq一〇一p写陣一一窓ρミミ§、ミ噌ミ、、N。畿こ 、恥馬a融O討笥 417 ︵7︶ 評房一〇N。。・㌻Bgの∴切Φ﹃p&こΦ雪まaρg肋§特§篭§§8ミ㌣ミ魯ミ§&きoo凶話ざ℃豊ω一〇。。ρや一〇。。簿の∴ ざ 誓β ざ = 色 警 99。。一一鵬輯︶Φ=の一8q戸一8一一嘗曾曾一﹃髪包㌧o﹂8ρΩ・番・・マ銭沖些嘗旦8く婁℃﹂。gヨ9琶欝℃﹂a qo 一橋大学研究年報 法学研究 14 99.ωoぎ昌9やooN9の■ 第二節 制度説による懲戒理論の展開 一 懲戒の目的と対象 制度説によれば、懲戒権は、一般に、制度としての組織的集団の共同の目的ないし利益の実現のために必要な行為 準則を構成員に強制するための、制度に内在する権威に由来する制裁権限としてとらえられる。.一の.一とからは、懲 戒権の対象たる行為に関して二つの要素が導かれる。一つはそれが共同の目的ないし利益を侵害するものであるア︾と、 いま一つはそれが労働者の︿非行﹀︵塗暮①︶と評価されることである。 ︵−︶ ︵2︶ まず、懲戒の対象たる行為は、企業の共同の目的ないし利益を害し、または少なくともそのおそれのあるものでな ければならない。使用者は企業の共同の利益を確保する責任を負い、その実現のために必要な権限を行使するのであ り、逆にその一環である懲戒権の対象となしうる労働者の行為も、企業の共同の利益の実現に向けられた行為準則ま たは一般的、個別的命令に反する行為でなければならない。労働者が使用者の権限に基づいて懲戒を科されるのは、 ︵3︶ その行為が契約違反と評価されるからではなく、集団的目的に対する直接・間接の侵害だからである。 次に、懲戒が集団の目的に反する行為についての﹁制裁﹂であることからは、その前提として、当該行為が非難可 ︵4︶ 能なものでなければならず、したがって︿非行﹀︵隔窪富︶が存在することが必要である。この揚合の暁き$の概念は、 ︵5︶ 富暮・概念一般がそうであるように、フランス法独自のものであり、単一の定義づけはむずかしい。ただ、レガル“ の回復ではなく、将来の行為に対するみせしめと威嚇を目的とするとされることからは、それが主観的な意味での帰 ブレートの論述を見る限り、それは人的な非難可能性︵εゼ号旨泳需誘o旨巴一。︶として理解され、懲戒が財産的均衡 ︵6V 418 懲戒処分法理の比較法的研究 n 責性として理解されていることが窺われる。その限りでは、それはどちらかと言えば刑事法的な﹁責任﹂の意味に近 い。 以上のように懲戒の対象をとらえることからは、さらに次のような帰結が導かれる。 第一に、懲戒の対象としての︿非行﹀と、単なる契約上の義務違反が区別される。たとえば労務の不完全な履行は、 原則として使用者の私的利益を害するような契約的︿非行﹀︵壁5。8昇轟。ε色。︶としてとらえられるにすぎず、懲 戒の対象とはならない。このことは、後に懲戒罰とその他の措置の区別を検討することによって、より明確となるで ︵7︶ あろう。 に類似し、また、刑事法と同一の原則が支配する。しかし、同時にそれらは発現の揚の差異によって明確に区別され ︵8︶ 第二に、懲戒は、組織的社会の内部における集団的秩序維持のための制裁としての性格を有する点において刑事罰 る。すなわち、刑事罰が政治的社会にもたらされた秩序素乱を罰するものであるのに対し、懲戒はより限定された集 団、つまり自治的な制度内においてその機能を果たすものである。したがって、一個の行為が双方の秩序素乱を惹起 ︵9V するものであるときは、その双方の制裁を受けることも可能である。 ︵−︶ ︷㊤ロ叶。の語は、過失、非行、黄任、過誤、過貴など多様に訳出され、これまでのところ定訳のようなものは見られない。 そのア︸と自体が、h帥⊆酔。の意義が容易に補捉し難いものであることを示すものとも言いうる︵鼠葺①の概念については、特に、 レ・タンク﹁不法行為貴任におけるフォート︵に葺。︶の地位﹂法学協会雑誌八二巻六号七一七頁参照︶。本稿では、本文にも 野田良之﹁フランス民法における砂暮。の概念﹂我妻還暦記念﹃損害賠償の研究﹄上巻︹有斐閣・昭三二︺一〇九頁、アンド 述ぺるように、﹁懲戒上の有責行為・非違行為﹂という意味で、文脈上支障のない限り、︿非行﹀として表示する。 ︵2︶■粛帥一専婁①も■一。。 9 ︵3︶犀σp蔓卑婁①も﹄。。 4 一橋大学研究年報 法学研究 14 ︵4︶b粛巴窃聾一・9℃﹄。。。いu=声&﹂もトま ︵5︶前掲注︵1︶参 照 。 ︵6︶■甜巴扇﹃①穿。も﹂。一 ︵7︶尽覧扇聾げρつ一〇一 ︵S︶ ■甜巴葛お9㊦も﹂一曾ug旨&﹂も,&o。ただし、この点についてレガル“ブレートが、懲戒は自治的制度に特有の制度で あり、刑法とは非本質的な適用領域の差異があるにすぎないとし、また懲戒法は未発達の刑法であると述べる︵い粛四一扇増・穿ρ や二〇。︶ことからは、デュランに比して、両者の区別に曖昧さが残っている。 ︵9︶U・田呂﹂”℃、ホ。。 二 懲戒罰の形態 制度説によれば、懲戒罰はその形態上の独自性によっても特徴づけられる。すなわち、懲戒罰は、同じく使用者に とってとられ、形態上も類似した措置であるところの内部秩序形成措置︵ヨ。も。岳8山、o巳.。言5.一窪.︶および民事罰 ︵。・雪9一99邑。︶とは、本質的に区別されなければならない。懲戒を契約によって基礎づけることを否定し、その性 質と目的の独自性を主張する制度説にとって、この問題は重要な意味を有している。 まず、内部秩序形成措置は、使用者が指揮命令権の行使として事業揚内の業務の組織づけを確保するためにとられ るものであり、たとえそれが労働者に対して損害を惹起することがあるとしても、懲戒とは区別され、懲戒に関する 規定や原則の適用はない。ところが、実際間題として、それらの措置の区別は必ずしも明確ではない。たとえば配転 や解雇は、少なくとも外見によっていずれかの措置かを判断することは困難である。そのためその基準は、結局、当 該措置が労働者の︿非行﹀を理由に制裁としてなされたか、それとも業務上の必要性に基づいてなされたかという、 420 懲戒処分法理の比較法的研究 H ︵1︶ 動機︵ヨo島︶の違いによるほかはないという。 次に、懲戒罰は民事罰とも区別される。これに関しては、特に罰金について、民法上の違約金との差異が強調され る。 レガル日ブレートによれば、民事罰は原則として損害の填補という純粋に補償的性格を有するのに対し、罰金は制 度内部の秩序の維持を目的とするものであり、明らかに刑罰的性格を有している。また、違約金はあくまで損害を惹 起しうる行為について定められることが必要であるが、罰金は必ずしもそのような行為について定められるとは限ら ないという。 ︵ 2 ︶ デュランも、懲戒罰としての罰金を違約金に還元しえないことを強調する。すなわち、第一に、違約金については 民法典第一二二九条により、約定された違約金の支払か主たる債務の履行のいずれかが選択されるのに対し、懲戒罰 については同時に義務の履行を求めうること、第二に、違約金が使用者の利益となるのに対し、罰金は労働法典の定 めにより従業員の安全基金に払込まれねばならないこと、第三に、罰金については一身専属性が認められ、相続人に ︵3︶ は科されないこと、がその理由である。 解雇についても同様の区別がなされる。この点、レガルnブレートは、解雇が制度の集団的利益により理由づけら れる揚合と契約上の給付の不履行による揚合とを区別し、前者は契約上の権利行使ではなく懲戒権の発現であるとし ている。 ︵4 ︶ 、二のように、懲戒罰と民事罰の区別についても、実際にはその外形上の区別はしばしば困難であって、その場合も ︵5︶ 両者の区別はそれを行使する動機によらざるをえないことは、制度説の論者自身の認めるところである。 さて、以上のような懲戒罰とその他の使用者の措置の区別そのものの当否の検討は後に譲るが、そのような区別の 421 一橋大学研究年報 法学研究 14 結果として、直接的には、罰金について一九三二年法の適用対象が限定的に解されることになった。同法にいう罰金 ︵6︶ はあくまで右のような意味での懲戒罰としてのそれであって、それ以外の違約金の合意には関与しないとされたので ある。しかし、右のような区別のより重要な意義は、むしろ、使用者の具体的措置が客観的に懲戒罰と認められる限 りにおいて、それが後述のような懲戒としての同一の原則、評価基準あるいは手続的規制に服すると解することの前 提であることにあると思われる。懲戒罰をそのようにあくまで固有の統一的法理によって把握することは、まさに制 度説による懲戒理論の核心であり、その意味で懲戒罰の概念規定が重要な意義を有するのである。 ︵1︶ 犀αqpぐ切笛3ρや一〇卸O信β区㌧マ轟鴇。仲ω∴U貫p&﹂H曽やo。ま99 ︵2︶ 募撃一葛識浮P℃﹂oo讐や一鶏①区■なお、レガルロブレートは、現実の罰金には仕事の不手際を理由とする違約金の性質 を持つものと、規律違反を理由とする真正の罰金の二種類があるとし、具体的にそのいずれにあたるかは労働者の︿非行﹀の 性質によって区別されるという。しかし、一個の行為が同時に懲戒的︿非行﹀と民事的︿非行﹀の双方に評価されうることも 認め、その揚合には違約金としての罰金と懲戒罰としての罰金が二重に科されうることを認めている︵■謝巴葛聾ぎも、いS︶。 両者を本質的に区別することからの当然の帰結と思われるが、同様の問題がドイツにおいても議論されていることについては、 ︵3︶U=β&﹂いサ & 。 。 本稿の第一部において既に述べた︵特に、法学研究13・三四五頁以下参照︶。 ︵4︶ 頴駆一窃み9。︸マト。一〇。9。n,デュランもまた、解雇が労働者により犯された︿非行﹀に対する制裁でありうるとし、その 場合、契約の破棄は企業の長の懲戒権を表わす免職︵8お畿δヨ①葺︶であるとしている︵∪・β&﹂どマ。。ま︶。 ︵5︶累σQ曽一葛憂げρ℃﹂o。︸U賃四呂一一℃ツao 判官による審査と減額を認めるぺきことが主張される︵■醤旦ω准讐9℃﹂ミ①貯8軌︶が、罰金の額が既に一九三二年法によ ︵6︶■粛隻卑倖茎や8押uβ﹃帥&﹂始や衰いただし、その反面、罰金については民法典第二五一条の適用を排除し、裁 って限定されていた以上、その意義はさほど大きなものではない。 422 懲戒処分法理の比較法的研究 H 三 使用者の内在的懲戒権 制度説は、先に検討したように、使用者に対してその企業の長としての資格に内在する懲戒権を認める。いわば、 使用者に固有の懲戒権を認めるわけである。このことは、直接的には、使用者が懲戒権を有することについて国家に よる授権や労働者の同意を要しないことを意味するが、さらに次のような意義をも含んでいる。すなわち、第一に、 使用者は懲戒に関する特別の規則や定めが存在しなくとも、また、たとえ存在してもそれを超えて、懲戒権を行使し うることである。その意味で、刑法におけるような罪刑法定主義の原則は、懲戒に関しては適用されない。第二に、 懲戒権の行使にあたり、懲戒の対象たる行為の評価および懲戒罰の選択について使用者が自由で広範な裁量権を有す るということ、第三に、たとえその行使にあたり労働者の関与を受けることがあるとしても、懲戒権を使用者から全 ︵−︶ ︵2V く奪い去ることはできないこと、である。 これらの意義のなかで最も注目されるのは、やはり第一点であろう。制度説の論者は、一方で懲戒法と刑法の類似 性を説き、刑法上の原則の懲戒法への適用ないし類推を唱えながら、刑法上の原則の一つである罪刑法定主義につい ては明確にそれを否定しているのである。このように一見矛眉するが.ことき態度を正当化するための根拠として、レ ︵3︶ ガル“ブレートは次の 諸 点 を 指 摘 す る 。 第一は、刑法において罪刑法定主義が妥当するための状況ないし背景が、懲戒においては存在しないということで ある。つまり、刑法においてその原則が優位したのは、同時に国家があらゆる犯罪を処罰しうるような完全な︵もち ろん予測しうる限りで︶刑法典を制定したためであるのに対し、懲戒法は未だ十分に整備されておらず、それにもか かわらず懲戒の行使が明文の定めに限定されるとすれぱ、制度における権威者はしばしば共同の利益に反するく非 423 一橋大学研究年報 法学研究 14 ︵4︶ 行﹀を罰する手段を持たないことになってしまうという。また、このような懲戒における規定の不備・欠如は、懲戒 の対象たる行為の性質に由来するものでもある。一般に団体の構成員がその団体の利益を害するような行為はあまり に多数であり、多様であるために、団体の規則で定められた最も重大で頻繁に生ずる︿非行﹀にのみ懲戒を限定する ことはできないというのである。第二に、集団の基本的な利益を保護する必要のため、構成員の個人的保障の尊重は ︵5︶ 後退しなければならないという。集団的利益すなわち共同の目的は、個人的利益に優先すると解されるからである。 第三の理由として、国家の刑罰が市民の自由に重大な侵害をもたらすものであるのに対し、懲戒罰は最も重いもので も除名や解雇にとどまり、個人の自由は保持されることがあげられる。 ︵6︶ 以上のような理由により、懲戒法には罪刑法定主義の原則は適用されないと解されるわけであるが、そのことは実 際に懲戒規定が定められる揚合の解釈についても一定の影響を及ぼすことになる。たとえば、懲戒罰の種類について の定めは、それが限定的であることを明示し、、またはそれが網羅的であるためにそのように解しうる揚合を除き、限 ︵7︶ 定的列挙とは解されない。懲戒事由の列挙についても全く同様である。 このようにして制度説は、自ら言うところの﹁不文の懲戒法﹂︵昏o詳良毘覧首巴おロo昌ω鼠ε聾器︶の存在を承認 する。しかし同時に、制度説はその揚合の懲戒権行使を決して無制限のもとと解しているのではなく、むしろ全く逆 に、それがこの後に述べるような対象および形態上の厳重な制約に服し、その観点からの広範な裁判所による審査に 服することを前提とするものであることに着目する必要がある。それによって、結果的に共同の利益確保の必要性と 実際上の恣意的懲戒権行使抑制の要請との調整を図ろうとしたのである。 なお、以上のことは、使用者が懲戒規定を制定することを無意味ならしめるものではない。むしろ、制度はその目 ︵8︶ 的を考慮し、それにふさわしい規制を制定しうるのであって、それは制度の自治に基づくものと解される。そして現 424 懲戒処分法理の比較法的研究 n 在では、多くの企業の就業規則中に懲戒規定が定められていることは、第二章において指摘したとおりである。その ことを前提として、ソワンヌは、制度説の立揚に立ちつつ、現実の懲戒規定が整備され、詳細になれば、それだけ罪 刑法定主義が懲戒法においても確立されることになるであろうとし、一般条項を介した使用者による懲戒内容の自由 ︵9︶ な決定という原則も、純粋に理論的なものにすぎないものとなると指摘している。 一℃爵︸U。oo、一翼辞㌻ωOひ9の、 ︵−︶ ただし、特に﹁不文の懲戒権﹂行使の揚合については、それが限定されたものとなることについては、次項において述べ 回5費﹃ω レガル“ブレートは、その例外として加重事由 ︵8器窃畠、甜揖く暮o己の揚合をあげる。制度は、規則または一般懲戒法 切﹃030αo一 四 〇 器 ω 路 冤 ρ ∪ ’ o り , 一 8 ρ や a 斜 Ω■旬3穿oα①σO器器p図ρ客o冨。。050009ら ■譜帥一扇冨魯9℃ー嵩一g毛。・ ︵2︶ まαQρ一葛53ρ℃■“a る。 ︵3︶ ︵5︶ ︵4︶ ︵6︶ 上の懲戒権を有することで十分な規律権限を手にしてい る 以 上 、 この揚合にはむしろ個人保護の原則たる罪刑法定主義の原則 に立ちかえるのが妥当であるというのがその理由であ る ︵[£帥一窃み99マ呂Qo梓の。︶。 ︵7︶ ■甜巴葛&二声℃﹂o。ひ①けの■、℃■No。ひ ︵9︶ωo凶量ρマ。9 ︵8︶ ま鵯一扇吊99唱﹂鵠 四 懲戒権行使の限界 制度説は、右に指摘したような意味での使用者の内在的懲戒権を認め、たとえ明示の規定や合意が存在しない揚合 にもその行使を容認する。しかしその懲戒権は決して無制限のものではない。むしろそれは、以下に述べるような、 425 一橋大学研究年報 法学研究 14 それまでの契約説によっては主張されなかったような重大な制約に服するものと解される。しかもそれは、制度説に よる基礎的懲戒法理からの理論的演繹として説かれるものであった。 制度説によれぱ、使用者の懲戒権の行使は次のような制約を受ける。 ω 対象上の限界 懲戒権の対象は、まず第一に、それが認められる根拠である企業の共同の目的ないし利益 によって、逆に限界づけられる。制度説の理解として、使用者の権限は、企業における共同の目的ないし利益の実現 のために必要な限りにおいて認められるものである。使用者は、そのために規則を制定し、命令を発することによっ て労働者の行動を規制する。従って、使用者の権限の一環である懲戒権も、そのような規則・命令に違反する労働者 の行為に対してのみ行使されうるものである。制度たる企業の目的を超えてそのような権限は存在しえず、集団的利 ︵1︶ 益を離れて使用者の個人的利益、特に契約上の給付確保のために、または企業外での労働者の行為を罰するために、 ︵2︶ その権限が行使されることはできない。デュランは、このことを懲戒の目的性︵昔盆ま︶による限界として語ってい る。また、レガル目ブレiトは、特殊性の原則︵冥旨9鷲号。。冨。芭詳ひ︶という制度一般について妥当する原則によ って同一の趣旨を説いている。すなわち、国家以外のすべての制度は特殊化されたものであり、ただ一つの目的にの み向けられたものである。従って、制度はその特殊な目的を達成する限りにおいてのみ、懲戒を科すことができるの だという。 ︵3︶ ︵4︶ 第二に、懲戒によって制度の目的に優位するような権利を害することはできない。レガル“ブレートは、これを従 属性の原則︵冥冒9需留曽σo乱日p鉱8︶として説明する。それによれば、制度の秩序はそれに優位する一般的な社 会秩序にはめ込まれており、制度における共同の利益も社会の一般的利益に服するが、それには国家の利益およぴ個 ︵5︶ 人の固有の利益が含まれる。国家は、その内部に存在するすぺての制度に優位する至上の性格を有している。また、 426 懲戒処分法理の比較法的研究 H 個人は制度に附合することにより、共同の利益のためにその自由を制約されるわけであるが、なおかつ個人は不可侵 の︵一耳目σq琶o︶権利を有している。それには、一つには自由な人格の展開、身体の自由などの基本的な人権が、一 つには、構成員としての権利であってその性格上奪われることのできない固有の権利︵身o富冥o駿窃︶ないし留保 ︵6︶ 権︵身o房お器署訟︶ と 呼 ば れ る も の が 属 す る 。 第三に、懲戒は労働者のく非行Vに対してのみ科されうる。たとえ企業の共同の目的・利益が害されたとしても、 労働者が︿非行﹀を犯したのでなければ懲戒は科されえない。このことは、先に懲戒の対象に関連して述べたところ である。 ③ 形態上の限界 懲戒罰としてとられうる制裁の形態は、原則として制度内の資格や役割に影響を及ぽすも の、企業においては、いわゆる職業活動に影響を与える制裁︵たとえば、配転、降格、出勤停止、解雇など︶と純粋 ︵7V に道徳的な制裁︵戒告、謎責など︶に限られ、罰金など財産的制裁は、規則上の明文の定めがない限り科されえない。 つまり、不文の懲戒権の行使としてとりうる懲戒の形態は、前二者に限られる。また、身体的な拘束を伴う制裁は、 先の対象上の第二の限界の観点からも許されない。 ㈲ ︿非行﹀と制裁の均衡 最後に、懲戒罰は、その性質およぴ程度において、︿非行﹀の重大性に比例しなけ ればならない。つまり、懲戒罰と︿非行﹀の均衡性︵冒εo益o轟一ま3蜀℃①ぢ①島ω。旦冒aお餅すσq声く一ま3﹃ 蜜暮①︶が要請される。これは、刑法におけると同様、正義の理念からの要請である。行為の重大さは、行為それ自体 ︵8︶ およぴその結果において評価されねばならない。心理的・道徳的要素、故意・過失のいかんのほか、制度の存在を危 険にさらす行為か、軽易な秩序棄乱行為かによってもその評価は異なる。また、制裁は、その形態によりその重さの 程度に段階性が認められる。一般に、道徳的制裁、財産的制裁、職業上の活動に影響を及ぼす制裁の順にその重さが 427 一橋大学研究年報 法学研究 14 増すのであり、 特に解雇は、他の団体における除名と同様、いわば極刑として最も重い︿非行﹀に対して科されねば ならない。 さて、以上のように制度説は使用者の懲戒権に対していくつかの重大な制約を加える。それは、とりわけ明文の懲 戒規定に基づかない懲戒権について意味を持つものであるが、明文の規定に基づく揚合についても同じ制限に服する ものであろう。使用者は、あくまで右のような制約をふまえたうえでのみ、企業の利益.目的を害するすべての行為 ︵9︶ ・・ を、適切な制裁によって罰する権利を有するのであり、そのような制約を離れて、制度説のいう使用者の内在的懲戒 ︵10︶ 権を語ることはできない。もちろん、このような制限も、それが単に理論的要請にとどまるのであれば、制度説によ る懲戒理論は、使用者に対して不文の懲戒権を認めるものである点において、労働者にとっての現実的危険は契約説 によるよりも大なるものとなろう。制度説は、右のような懲戒権制約理論の実効性確保を、裁判所による広範な司法 審査に 期 待 す る 。 ︵−︶ ただし、労働者の企業外での私生活上の行為については、それが労働環境の道徳性や、経営の良好な運営や評判を害する ことによって企業に影響を及ぼす限りでは、懲戒権の対象となりうるとされる。それは、非難される行為の性質、経営の性格、 ︵2︶ ∪賃磐倉鰹℃ト&①けψ﹁懲戒権はその目的性によって制限される。それは、企業の秩序を維持するためにのみ役立たね 当該労働者の職務、従業員への影響などの諸事情にかかる。U旨目阜りや&甜い粛巴、卑窪β℃﹂郵総N。3・ ︵3︶ い粛巴鳶答3P℃■一〇ど一い鈎い8 ばならない。経営の運営を害しないような労働者の行為は罰せられてはならない。﹂ ︵4︶い禽巴扇曇げp℃・ごひ。瓜‘や8。。Φけ。。。 ︵5︶ その結果、私的制度は、その懲戒権によって、公序に反する命令を強制したり、構成員の訴権を制限したりすることはで 428 懲戒処分法理の比較法的研究 n ︵6︶ ただし、このうちの後者のものは企業の労働者には認められず、もっぱら前者のみが問題となるという。後者の権利とは、 きない︵[緯巴、ω議浮ρマ鵠O卑ω﹃︶。 たとえば団体構成員の議決権など、その構成員としての地位に密接に結ぴついた基本的な権利︵いわゆる社会権︶であるが、 減額できるものであるから、そのような特別の権利の存在は認められないとする︵ぴ粛巴萄鐸一声やω軍㊦怜﹄・︶。 労働関係においては、労働条件は労働契約による処理がなされ、また、任意の退職手当や疾病手当は使用者が一方的に廃止. ︵7︶ ■禽巴\ω3浮Pつちρ一〇〇︸U=β一己智ンつ茸ひ ︵8︶ ■甜巴、ω3浮P℃N8り睾09ω∴U霞睾9炉マ轟&簿9 ︵9︶ このように不確定的に述ぺるのは、この後に指摘するように、特にデュランが明文の懲戒規定の存否いかんによって裁判 所による審査対象を明確に区別するためである。それがまたその後の破棄院の立揚でもあることは、後の判例の検討を通じて ︵10︶ ■譜巴葛3夢 9 や 一 踏 明らかとなろう。 五 裁判所によるコントロール 制度説は、右に述べた懲戒権の限界性に関する理論的帰結の実効性を確保するため、裁判所による広範な司法審査 の可能性を承認し、主張する。契約説、特に既に検討した初期の判例が、一般的な契約法の原則に依拠することによ って罰金や解雇についての司法審査の範囲を限定したのに対し、制度説は、すべての懲戒処分の形態について、懲戒 の対象たる労働者の︿非行﹀の存否、性質や重大性の程度、︿非行Vと制裁の間の均衡などの幅広い問題について、 ︵1︶ 裁判所が審査権限を有すべきことを主張する。また、既に検討したところからは、懲戒罰とその他の措置の区別、特 に個々の制裁が他の措置を口実とした懲戒罰か否かの認定もまた、裁判所による評価に服することになろう。 429 一橋大学研究年報 法学研究 14 ところで制度説は、先に検討したように、企業運営上の内部秩序の維持のため使用者に対して不文の懲戒権を認め、 厳格な懲戒権制約法理と広範な司法審査によってその適正な行使を確保しようとするわけであるが、使用者の懲戒権 が、明文の規定の存否にかかわらず同一の法的基礎に由来するものであるならば、それから演繹される懲戒権の一般 的限界は、単に不文の懲戒権のみならず、明文の規定に基づいて行使される場合にも同様に妥当するはずであり、従 って、裁判所による審査についても、そのいずれかによって差異はないとすることが一貫した帰結であろう。ところ が制度説の主唱者たるデ.一ランによれば、懲戒権が懲戒規定に基づいて行使されたか否かによって裁判所の審査の範 囲には広狭の違いがあり、むしろその点に成文上の懲戒権行使と不文のそれを区別する意義があるとして、右のこと とは逆の結論が導かれている。 すなわち、デュランによれば、まず懲戒権が明文の規定に基づかずに行使された場合は、裁判所の審査は先に指摘 ︵2︶ した懲戒権の制約条件のすべてに及ぶ。それに対し、懲戒権が明文規定に基づいて行使されたときは、一方でそれは、 ︵3︶ そのような懲戒規定の有効性にも及ぶことによって明文の規定のない揚合よりも拡大する。しかし他方で、それは行 為の事実認定および︿非行﹀の存否には及ぶものの、規定中に︿非行﹀が詳細に定義づけられている限り、裁判官は 当該行為の性質すなわちそれが︿非行﹀か否かの評価にとどめねばならず、さらに、規定中に一定の︿非行﹀に対し てとられうる制裁が明確に定められているときは、裁判官のなしうる審査は使用者がその規定どおりに制裁を適用し ︵4︶ たか否かに限られ、制裁に理由があると認められるならぱ裁判官はそれを変更できないとする。たとえば罰金につい て上限と下限が定められている揚合に、使用者が労働者の︿非行﹀を理由にその範囲内で罰金を科したときは、それ ︵5︶ だけで懲戒権の行使は濫用との評価を免れるというのである。しかも、いずれの揚合にも、規律が害された揚合に懲 戒を適用することが妥当か否かという適宜性︵o聴9ε三ま︶の問題には司法審査は及ばないという。それは、使用 430 懲戒処分法理の比較法的研究 n ︵6︶ 者のみが判断しうるものと解されるからである。 このようにデュランは、懲戒規定が存在し、︿非行﹀と制裁が定められる揚合について、裁判所による審査の範囲 を大幅に限定する。しかし、そのような制約の根拠としてあげられることは、使用者は﹁規律という利益が制裁の適 ︵7︶ 用を要請するか否かを知ることについての唯一の判定者﹂であるという破棄院判例の判示にすぎない。それがいかに してデュラン自身の制度理論に結び付くのかは、その文脈からは遂に明らかにしえないのである。 ︵8︶ ︵9︶ 以上のようなデュランの理解に対しては、同じ制度説に立つ学説からも、制度説として理論的に一貫しないとして 批判が加えられた。このことは、デュランの理解と軌を一にすると思われる破棄院判例に対する批判と共通のもので あるので、後に判例を検討する際に改めて取上げることにしたい。 し︵い粛巴萄﹃弩5℃レoyい8︶、解雇については、それが企業の集団的利益の侵害を理由とする懲戒手段としてなされると ︵−︶ レガル”ブレートは、たとえば罰金について、その金額についての裁判所による審査、ひいてはその変更の可能性を承認 きは、あくまで懲戒的︿非行﹀の観点からの評価が加えられるべきであるとする︵ピ譜巴葛δ39℃﹄賂。一︶。ただし、その後の ︵2︶9β&㌧H︸℃■“&魯p プレートの見解につき、後掲澄︵8︶参照。 ︵3︶u弩卑鼠、どマ云o ︵4︶ U目き“ンや云一﹄まただし、たとえ︿非行﹀についての規定が存在する場合でも、それが一般的ないし不完全である ︵5︶ そのような揚合の使用者の裁量権に限界を設けようとするのであれば、それは裁判官の介入によってではなく、立法また ときは、裁判官は全幅的な審査権限を有するとされ、その限りでは不文の懲戒権行使と同様に扱われる。 ﹃嘗負ドマ奪軌︶。 は労働協約によるほかはないとする。一九三二年法による罰金規制も、まさにそのような意味の立法として理解される︵Uロー ︵6︶評β&﹂㌧℃■茸一 431 一橋大学研究年報 法学研究 14 ︵7︶ oり8■霜3<’一εo。’∪。uり■一3P℃軍O ︵8︶ なお、その後ブレートは、上記の問題についてデュランと全く同旨の内容を説いている︵切39。αの訂 ︵9︶ωぎ避一U﹂8ρOξo芦℃■爲。 一〇ひρやα呂簿u。・︶が、そのことが制度説の理論的前提といかに結ぴ付くのかは、やはり明らかでない。 第三節 制度説の評価と批判 一 制 度 説 の 意 義 O﹃窃器堵ρO■oo、 制度説による懲戒理論は、それまでのフランスにおける理論状況を考慮するならば、特に次の点で積極的な意義を 有する も の で あ っ た 。 第一に、実務上の多様な懲戒措置を懲戒権という単一の法的権限の発現としてとらえることにより、それを基礎と する統一的な懲戒処分法理を形成しようとしたことである。フランスにおける私的企業の懲戒処分に関する統一的法 理の形成は、制度説によってはじめて実現したと言える。しかもそれは、単なる抽象的理論志向にとどまらず、多様 な懲戒処分を統一的に把握することによって、たとえば制裁と︿非行﹀との間の均衡性の要請を基礎づける点で、大 ︵1︶ きな実際的意義をも有するものであった。 第二に、制度説が懲戒処分を近代的企業における内部的規律・秩序維持の必要性と、企業の円滑な運営についての 責任によって法的に根拠づけたことは、それが、使用者の個人的ないし契約的利益とは明確に区別された、企業の集 団的利益という、より客観的な利益によってはじめて正当化されうることを意味する。そしてそのことは、懲戒権の 客観的限界性を導くための理論的前提でもあった。企業の共同の利益や目的は、懲戒権を根拠づけると同時に、それ 432 懲戒処分法理の比較法的研究 n を限界づけるための基準ともされたのである。懲戒権の根拠と限界を一体のものとしてとらえるという一見自明のご とき理解は、フランスにおいては制度説によってはじめて明確に提示されたのであり、その目的論的解釈方法は、そ ︵2︶ の後の懲戒理論に対しても大きな影響を及ぼすことになった。 第三として、制度説は、右のような懲戒権の限界性を担保するため、裁判所による懲戒権の広範なコント・ールを 主張した。このこと目体は、それまでの判例の状態を考慮するならば、制度説の持つ重要な意義の一つである。とは ︵3︶ いえ、.︶の点については、制度説が広範な司法審査を主張したことが、他方で契約理論の制約を超えて使用者の懲戒 権を承認したことと対をなすものであり、そのような結果を正当化するためのものでもあったことに留意する必要が ある。つまり、実際にそのような広範な司法審査を伴わない限り、制度説は、単に契約理論の枠を超えて懲戒権を基 ︵4︶ 礎づけるための理論に容易に転化する危険性を、既にその内に含んでいたのであるρ 以上のような意義を有する制度説による懲戒理論は、その後のフランスの理論状況に一大転機をもたらしたが、そ れは同時に、当然のことながら、多くの批判を惹起することにもなった。そこで以下では、これらの批判を主要な論 ︵5︶ 点ごとに取り上げながら、制度説の間題点について検討を加えることにしたい。 ︵−︶ アあ.︶とは、特に解雇自由の原則の制限に関して重要な意味を持つ。すなわち、上記の理解を推し進めるならば、懲戒と しての解雇は、あくまで懲戒処分としての統一的観点から、労働者の十分に重大な︿非行﹀に対してのみ科されうるものであ >昇一ρb■お り、それに至らない︿非行﹀については、より軽易な懲戒処分の行使のみが許されるとの結論が導かれるからである。R ︵2︶○一一一。5uあ■一8Nも■㎝。N も懲戒処分一般についての司法審査の拡大を主張した点に、その意義があったと言える。 ︵3︶第三章第二節参照。制度説は、そのような判例の状態に対し、従前の学説とは異なり、明確に懲戒法理の観点から、しか 433 一橋大学研究年報 法学研究 14 ︵4︶ このことは、その後の判例の展開を通じて現実のものとなった。第五章参照。 ︵5︶ なお、制度説の基礎理論、特にそれが制度理論に依拠することの意義と問題点については、既にレガル目ブレートおよぴ デュランの基礎理論に関連して若干の検討を加えたので、ここでは立ち入らない。本章第一節一一3、三3を参照。 二 制度説に対する批判 − 企業の制度的・共同体的把握 制度説は、その理論的前提として企業の概念を措定し、それを制度ないし共同体としてとらえることにより、制度 理論を媒介として使用者の懲戒権を基礎づけた。確かにこの企業の概念は、今日ではフランス労働法の基礎的範疇の 一つとなり、また、企業の制度的把握そのものは、たとえそれに対して批判的な立揚からも、少なくとも純粋に契約 的発想によっては十分に説明しえないような問題の解決に資すること、とりわけ実定法の発展方向を示すものである 点において、積極的意義が認められている。しかしここでの問題は、企業概念およびその制度論的把握が、そのよう ︵ − ︶ な意義を超え、直接に労使間の法律関係を形成するための基礎とされていることにある。制度説の主唱者が、企業は 単なる社会的実在にとどまらず法的実在であるとしたことも、まさに企業における労使関係を契約関係とは別個の法 律関係としてとらえ、それによって懲戒権を基礎づけようとしたものにほかならない。 ︵2︶ 、このような制度説の理解に対しては、まず企業の制度ないし共同体としての把握そのものについて批判が加えられ た。企業が現実の労使関係形成の揚として社会的実在性を有するとしても、そのことから労使間には一種の連帯性が 存在し、したがって企業が法的な意味での制度・共同体であると解することはできないというのである。たとえば、 労使間には一定の揚合にある種の連帯性と言いうるものが存在するとしても、他方で労使間には特に賃金と利潤をめ 434 懲戒処分法理の比較法的研究 H ぐって典型的な形で現われる明白な対立関係が存在し、それによってそのような連帯性は容易に否定されるこ︵昆、単 なる事実上の連帯性の客観的確認は一定の社会的集団の成立には十分であるとしても、それが共同体にまで高まるに は構成員の連帯の意識が存在しなけれぱならないのに、それは未だ実証されていないこと、などが指摘されている。 パィマ また、そこで問題とされる共通の利益の存在についても、現実の多様な利害のうちの一部のみをことさらに強調し、 企業の制度的.共同体的把握に適合すべく、牽強的に抽象化するものとの批判を免れないであろう。その意味で、企 業の制度的.共同体的把握は、単に労使関係における部分的な連帯性および共通の利害の存在についての事実的確認 ないしは理念的要請にとどまり、使用者の広範な権限を導出するための独自の法律関係としては、未だ十分な論証は なされていないと言わざるをえない。 確かに企業の制度ないし共同体的把握の主唱者は、それが企業における集団的現象や実態に合致し、なによりも・ 契約理論によっては十分にとらえることのできない多くの問題に実際的解決を与える点に、契約的把握に対する優位 性を自認する。しかし、それが立法の解釈・指導理念たることを超えて労使関係における具体的権利義務の基礎とし て現われるとき、そのことは決して労使間のすべての権利義務を基礎づけるものではなく、実際にはむしろ、契約に よっては導きえないような使用者の広範な権限を根拠づけ、あるいは何らかの根拠に基づいて認められる使用者の権 ︵5︶ 限をいっそう権威づける点に最大の機能を有するものであった。 ︵−︶ このことは、企業が独自の法律関係の基礎たりうることを否定する学説によっても肯定されている。たとえば、9日零 ︵2︶ 歪<。﹃。、ω四く帥餓。﹃、や一〇。斜簿望9ヨ毘看。ぎ℃﹂o。簿契い岩〒O器Pワひ。b。Q9切■また、企業理論についての包括的な ぞ昌oF︸︶・卜o押菊ぞRo\ω帥く緯一R,やHoo軌卑p 批判的検討として、9目鼠FOξ”卜.馬ミ濫憶§・8蔑慧濠&ミ斜留§馬・勺巽厨G訓参照。 435 一橋大学研究年報 法学研究 14 性が存在するとしても、繁栄が使用者のみが享受する利潤の増大という形で現われるや、それは止むであろう。﹂︵O螢日。同ξ昌。F ︵3︶ カメルランクは次のように述ぺる。﹁確かに不況時には労働者と打撃を受けた企業の長の間には不可避的に事実上の連帯 や一。。︶ ︵4︶困<R。\・り塁区。﹃も・嵐・。。a・ である。﹂︵U冤O昌6器PやBごo浄○≡①さやO汐〇三=oヨO“U・○・一まざマN一〇〇︶ ︵5︶ リヨン・カーンはこの点について次のように指摘する。﹁もし現代の学説が企業の概念に労働法上の場所を与えようとす るなら・それは純粋に契約的なテクニックによっては説明が困難であるような、使用者の一定の権限の拡大を正当化するため 2 企業の集団的利益の優位性 制度説によれば、懲戒は、企業の共同の目的ないし利益の達成のため、それを害する行為に対して科される独自の 制裁としてとらえられる。そのこと自体は、懲戒の本質や目的を明らかにし、それに基づいて懲戒の限界性を導いた 点において一定の意義を有している。しかしそのような懲戒の理解は、単にそれのみにとどまらず、さらに進んで、 ︵−︶ 企業の集団的利益の労働者の個人的利益に対する絶対的優位の肯定へと容易に結び付くア︸とになった。レガル,ブレ ートによれば、一般に﹁団体とそれを構成する個人の間には平等は存在せず、集団的利益、つまり共同の利益は構成 ︵2︶ ︵3︶ 員の個人的利益と個人的意思に優位する﹂。企業においても全く同様である。確かにそこでは、企業におけぞ集団的 利益は労使に共通のものであることも強調されている。使用者もまた、それによって支配されるというのである。し かし、そのような共同の利益の優位が説かれるとき、そのことが労使双方にとって意味するア一とは全く異なるもので あることに注目しなければならない。 制度説のいう企業の共同の利益、それは富の生産と交換である。また、使用者の個人的利益とは、資本の利潤であ 436 懲戒処分法理の比較法的研究 H る。すなわち、使用者にとっての個人的利益とは、企業の共同の利益の実現の結果にほかならない。しかも制度説に よれば、使用者は企業の長としてその共同の目的のために内在的諸権限を行使する。従って、企業の共同の利益は容 易に使用者の個人的利益と不分明なものとなり、同一視され、むしろ一個のものとして追求される。それに対して、 労働者にとっての共同の利益とは、企業の共同の利益の名において行使される使用者の権限への服従そのものである。 そこでは、共同の利益の優位性は、もっぱら労働者の個人的利益の犠牲として現われるにすぎない。 しかも労働者にとって、集団的利益の個人的利益に対する優位は、その地位にもたらされる危険の受忍としても現 われる。既に見たように、制度説によれば、使用者はたとえ明文の規定がなくとも、またはそれを超えて懲戒権を行 使しうる。そのこと自体、労働者の地位を極めて不安定な状態に置くものであるが、それについて制度説の論者は ︵4︶ ﹁集団の基本的利益を守る必要性のため、構成員の個人的安全の尊重は後退しなければならない。﹂と断言し、また、 ︵5︶ たとえ不文の懲戒者を認めても、労働者はせいぜい解雇されるにとどまり、その自由は確保されているとも言う。し かし、いかに事後的な司法審査の可能性が開かれているとはいえ、恣意的な解雇の危険にさらされた労働者にとって、 そのような抽象的自由の確保がいかなる意味を持ちうるのかは疑問である。まさにそのような主張に、企業の集団的 利益の絶対的尊重と、労働者の利益や地位の軽視という制度説の基本的特徴を見出しうるであろう。 以上のことと関連して、制度説による共同の利益の強調は、むしろ労使間の根本的な利益対立を隠蔽するイデオロ ギー的機能を果たすとの批判が加えられる。リヨン・カーンによれば、使用者の利益と労働者の利益が完全に対立し た状態の下でことさらゆ共同の利益が語られることは、﹁社会闘争の熾烈さを弱め、労働者にその真の利益を忘れさ ︵6︶ せようとする欺隔﹂にほかならない。 ︵−︶本節一を参照。このことは、後に見る折衷的見解のみならず、その後のフランス懲戒法理全体に対しても大きな影響を与 437 一橋大学研究年報 法学研究 14 ︵2︶頴鵯一\卑ひ子pマ弓 えた。 ︵3︶ ﹁ここでもまた、構成員すなわち労働者に対して、制裁の威嚇の下に、すぺての者が企業の利益の実現のためにその尽力 を整合し、優越的な集団的利益の要請に応じて労働者としての個人的利益、とりわけその階級的利益の一部を犠牲にするため ︵4︶累αq巴萄識3pや嶺一 に、一つの行為準則が課されねぱならない。﹂︵■禽旦羅浮ρ︾旨9ω,︶ 刑や投獄を受けないのであるから、使用者による懲戒権の恣意的行使に異議を述べえないとするものだ。﹂として批判する ︵5︶ い禽巴葛鐸ぼ、℃﹂旨一ω憂冨留﹃9。器喫PU臼ω﹂まρやひ巽 ギルモはそれに対して、﹁それは結局、労働者は死 ︵6︶ [鴇86器P℃,N8 ︵Oロ三〇ヨo“∪’ρ一8yやN一〇〇︶。 3 制度説と契約理論 制度説についてここで特に問題としたいのは、それと労働契約ないしは契約理論そのものとの関係である。制度説 は、懲戒権の根拠を契約に求めることを否定すると同時に、懲戒の対象が契約違反としての民事的く非行Vとは異な る集団的利益の侵害という独自の懲戒的︿非行﹀であること、また、懲戒罰は使用者が契約に基づいてとりうる措置 とは区別された独自の制裁であることを主張する。 ︵ − ︶ 制度説によるこれらの区別は、抽象的理論として見る限り確かに明快である。しかし同時に、制度説によっても、 実際には懲戒罰とそれ以外の制裁措置とがその形態上は区別しえない揚合があり、結局は個々の措置がとられた動機 のいかんによって判断せざるをえないとされることは、既に指摘した。この点については、果たしてそのような動機 ︵2︶ 438 懲戒処分法理の比較法的研究 n いかんという主観的要素が、その本質や法的根拠において全く異なるはずの両措置を区別するための基準となりうる のかということも間題であるが、さらに一つの重大な理論的疑念が生ずることになる。それは特に、制度説による解 ︵3︶ 雇についての理解をめぐって現われる。 制度説によれば、労働者の懲戒的︿非行﹀を理由とする即時解雇は使用者の懲戒権の発現としてとらえられ、通常 ︵4︶ の解約告知権ないし解除権の行使とは全く異なるものと解される。しかしながら、即時解雇は、契約法上も労働者の 重大なく非行V︵壁暮o鴨巽o︶がある揚合には可能である。それは、その結果において懲戒としての解雇と同一であ り、しかも契約法上の即時解雇︵即時解約︶における労働者の︿非行﹀は、労働契約の履行に附随するものである限 り、その性質や内容は限定されていない。従って、右のような制度説の主張が成り立ちうるためには、単に懲戒と しての解雇が懲戒権に基づくとの指摘のみでは足りず、さらに懲戒的︿非行﹀が即時解約の理由で■ある労働者の重 大な︿非行﹀に含まれないことを論証する必要がある。そうでなければ、それらの解雇はいずれも使用者の即時解約 ︵5︶ 権の行使であり、単にその理由となる︿非行﹀の性格によって区別されるにすぎないとの批判に耐え得ないからであ る。ところがこの点についての制度説の説明は全く不十分と言うほかはなく、しかも、懲戒権という労働契約とは全 く別個のものとして構成される権利の行使によって、労働契約そのものが終了せしめられるという一見奇妙な結果に ついてさえ、何らの考慮も払われてはいない。 制度説による懲戒権と解約権の不分明さを示すいま一つの例証は、出勤停止、配置替、降格などの懲戒措置に関す る理解にも現われている。デュランは次のように言う。﹁それらは企業の長の解約権︵身o騨3犠毘馨一8︶によって 正当化されるように思われる。彼が労働契約の終了をもたらしうるのであれば、より強い理由によって、より軽度の 手段を言渡すことができなければならない。﹂と。しかし、制度説の論理を貫く限り、右の懲戒措置はあくまで懲戒 ︵6︶ 439 一橋大学研究年報 法学研究 14 権から派生するものとして説かれるぺきものであり、契約上の解約権に言及すること自体が背理であろう。いわんや、 解約権によってそれらの懲戒措置を基礎づけることなど、全くの矛盾と言わざるをえない。また、解約権に基づく解 雇をなしうることから当然にそれよりも軽い制裁を行使しうるとすることは、あらゆる︿非行﹀に対して解雇をなし ︵7︶ うることを前提とするものであり、それは自ら︿非行﹀と制裁の均衡という原則を放棄するものにほかならない。 以上のように、制度説は、その理論的前提として使用者の懲戒権を契約から切り離し、それとは別個の制度理論に よって基礎づけようとするものの、そのことは具体的な懲戒法理の展開のなかで必ずしも一貫されてはおらず、契約 法理との分離は未だ不十分なままである。その根本的な原因は、おそらくは、制度説が既にその立論の前提において、 懲戒権を含む使用者の諸権限が契約に基づくものではなく、制度としての企業の長の資格に内在するものであるとの 命題を措定したこと、そしてそれにもかかわらず、制度説によっても労使関係が契約関係でもあることは否定されず、 その結果、理論的には二重の法律関係形成の基礎が混在するに至ったことにあるものと思われる。そのことは、制度 ︵8V 説の措定する理論的前提そのものの当否についての疑念を惹起するだけでなく、ひいては懲戒処分法理から契約的要 ︵9︶ 素を全く分離し去ることの一種の理論的限界をも示唆するものであろう。 ︵−︶︵2︶本章第二節一、二参照。 ︵3︶ 同様の問題は、本稿の第一部でも検討したように、ドイツにおいても経営罰と契約上の措置の区別をめぐって生じていた ︵特に第一部第三章第二節一、第四節・法学研究13 二九五頁以下、三三六頁以下参照︶。しかし、ドイツにおいては解雇や降 格、出勤停止などは一般にはじめから契約上の措置と解される傾向にあり、右の問題は主として罰金や戒告、講責を対象とす るものであったのに対し、フランスにおいては懲戒罰の概念がドイツの経営罰よりもはるかに広範なものとしてとらえられる ︵4︶u・β呂﹂一︾マ。。。。N 結果、懲戒罰をその形態や効果によって他の措置と区別しえない揚合も多数生ずることになる。 440 懲戒処分法理の比較法的研究 H ︵6︶ U旨雪鼻ンマ童ひ卑ヨ即o皿塁ミO菖p呂も﹂禽レガルロブレートもまた、﹁大は小を兼ねる﹂という趣旨の格言︵、、〇三 ︵5︶○≡。﹃サマ一ミ ︵7︶ 制度説の論者が解約権によって軽度の懲戒処分を正当化するにあたり、それが解雇を相当とする程度の労働者の重大な ℃Φ耳下覧霧︸ヌ耳一〇ヨOぎω■”.︶を引用し、同様の結論を導いている︵び譜巴葛﹃窪5マ謡一碑。。。︶。 化されるというのであれば、そのことはあくまで解雇が許容される揚合に限られるはずであるのに、そのような限定は付され ︿非行﹀のある揚合に限定されるとは解していない。つまり、それらの懲戒処分が解雇という極刑処分の減刑措置として正当 てはいないのである。むしろ右のような一般的正当化は、たとえ労働者の軽度のく非行V︵診暮。一譜警o︶の揚合であっても解 雇は適法であるとする伝統的解雇法理に従ってはじめて可能となるものであろう。 ︵8︶ デュランが制度理論における労働契約の意義を強調していたこと、また、レガル“ブレートが労務提供義務を労働契約上 の義務とし、それに関する労働条件の問題は労働契約によって処理されると解していたことについては既に指摘した。従って、 制度説によっても労働契約はなお独自の法律関係形成の基礎であることが認められており、それから派生する使用者の諸権利 は制度説のいう企業の長の内在的権限とは別個に存在し、それらの間に一種の競合状態を惹起することになる。しかし、制度 説によるその間の区別は未だ原理的・抽象的なものにとどまり、契約法理の克服のうえに独自の懲戒法理を構築するという制 ︵9︶ カタラは、使用者の懲戒権を制度説に従い使用者の貴任によって基礎づけることを肯定しながら、それは債務法から導か 度説の意図は、その意味では十分な形で達成されているとは言い難い。 制度説およぴ企業の制度論的把握に対する批判をふまえてかなり折衷的なものとなっているが、制度説の新たな動向を示すも れる評価基準を排除しないとし、むしろそれが契約法と結び付けられるぺきだとする︵O簿巴曾℃まひ卑呂。その論旨は、 のと言えるかも知れない。 441 一橋大学研究年報 法学研究 14 第四節 批判的学説による懲戒理論と制度説の影響 一 批判的学説による基礎理論 − 序説 右に見たように、制度説に対する批判は、特に、制度説が企業を制度ないし共同体としてとらえ、そのことから直 接的に使用者の懲戒権を法的に基礎づけようとしたことに対して向けられた。制度説に対する批判的見解にとって、 労使関係は基本的にはあくまで契約関係であり、労使間の権利義務の起源もまた、労働契約に求められなければなら ない。企業は、法律関係形成の起源であるような法的カテゴリーとしてはとらえられないのである。 ︵1︶ しかしながら、労使関係を基本的には契約関係としてとらえるとしても、制度説登揚以降の理論状況下において、 企業概念それ自体を否定し、あるいはそれに基づく企業理論を全く無視した形で労使間の懲戒を論ずることが困難と なったことも事実である。かつての契約説の、ことく、単に労使間の抽象的合意を持出すだけでは、懲戒理論として全 く不十分なものであることは、制度説に対する批判的見解においても一様に認識されている。企業概念をいかなるも のとしてとらえ、それを懲戒の契約法的構成にいかに反映させ、あるいはそれをいかに調和せしめるか、それはその ︵2V ような批判的見解においても避けて通ることのできない問題である。 ︵1︶ ○臣oきや鶏 ︵2︶ なお、以下で取り上げる学説は、いずれも制度説に対して批判的立揚に立つ点では共通性を持つものの、必ずしも系統的 な分類になじむものではない︵もちろん一定の近似性は認められるが︶。従って、以下において主要な学説およぴその内容と して整理したことは、あくまで便宜上のものであり、それらが単一の学説や統一的懲戒法理として形成されているという趣旨 442 懲戒処分法理の比較法的研究 H ではない。 2 懲戒の契約的理解 ︵−︶ まず、企業の制度論的理解を否定し、その独自の法的意義を認めない代表的見解として、リヨン・カーンがある。 彼にとって企業とは物、すなわち資本という使用者の所有物であり、資本と労働の結合としてとらえることはできな い。しかも、企業の中では使用者と労働者の利益は完全に対立したままであって、利益共同体・生存共同体の存在を ︵ 2 ︶ ︵3︶ 認めることはできないという。リヨン・カーンにとっての企業とは、﹁多数の労働者を一人の使用者に結び付ける労 働契約の集合としての法的実在﹂にほかならない。また、制度説による懲戒理論は、そもそもフランスにおいては妥 当すぺき基盤を欠いているという。その当然の理論的帰結であるべき懲戒委員会などの管轄機関も、違反事由と制裁 の法定原則も存在せず、使用者が無制限の権限をもって行動しているのであり、そのような状況の下では、むしろ伝 ︵4︶ 統的な契約の概念に依拠することがより賢明であるというのである。 ︵5︶ このようなリヨン・カーンの理解は、制度説がドイツ労働関係理論の影響の下に制度理論に基づいて企業それ自体 から使用者の絶対的権限を導き、その結果、労使間の法的平等を否定し、使用者による労働者の権力的支配を容認し ようとしたことに対し、あくまで契約理論に依拠することによってそれを批判し、労働者の固有の利益と立場を明確 にせんとしたものである。リヨン・カーンにとって契約とは、法の下に自由かつ平等な二個人を結び付けるものであ り、労働者にとっても法的平面における人間的自由と労働者人格の最大限の尊重を意味するものである。制度説は、 そのような契約の持つ意義を否定し、企業概念の下に労働者にとってはるかに危険な結果をもたらそうとするものに ほかならないという。 ︵6︶ ここにおいて、リヨン・カーンの見解が、かつての初期的な契約説の単純な延長としてはとらえられないことは明 443 一橋大学研究年報 法学研究 14 らかであろう。それは、かつての契約説のように抽象的合意を媒介として使用者の事実上の労働者支配をそれとして 法認しようとするものではなく、制度説による使用者権限の拡大と労働者の自由制約という新たな脅威に対し、あく まで契約法理にとどまることによって逆に使用者の権限を限定づけ、労使の対等原則を維持しようとするものである。 その意味で、懲戒法理における契約的理解は、制度説の出現を契機としてその意義を一変したと言いうるであろう。 ︵7︶ ︵1︶い紀o亭O器PO曾費“ミg醤§馬匙恥匙き貸職袋㌣象ミ蔑災魯騨吻魯ミ蕊蔵魯竃ミ魯いPU■触”勺貧厨ち蟄いや鵠ω9。・。この ほかリヨン・カーンの懲戒理論およぴそれに関連する理論については、次の文献を参照。び.傘魯身身8旨邑。留ωけき午 畠長α馨㎝一①昏o一け色㎝o骨一ぎ巴﹃①身けβ<区ヤ勘8§匙職醤無ミ亀塁ご芦おひρ℃●O嚇d羅ゆ8ヨ巴一εg置5ロ①﹂Φ﹃甜一Φ5①暮5・ a践窪さU,這ひPO耳目。やNミいUβ3一〇αΦ㎝冥凶o首Φωσp曾Φ﹃㊤長曾昏o犀。三一撃毎o一け費賃p<p認︵冥。5M雪の8冥o。ぎy ︵2︶ 先に指摘したように、リヨン・カーンは、そのような状態の下で共同の利益を強調することは、社会闘争の熾烈さを弱め、 菊 塁 § 籍 野 o 無 ミ ミ き G N ♪ や B O ︵3︶ い冤昌6器劃マ認斜 労働者にその真の利益を忘れさせようとする欺購にすぎないとして批判する︵■岩マ99層マ8い︶。 ︵4︶ U冤g−O器pマ田O ︵5︶ リヨン・カーンは、ドイツの労働関係論について、それはナチの支配下において強制労働を正当化するためのものであっ たとして否定的である。 ︵6︶ξ9−O器pや認い ︵7︶ リヨン・カーンのほか、懲戒の契約的理解に立つと思われる学説として、9ぎ窪旨。ぎや圏︵豊9ヨ豊旨。ぎ9﹃①σqす 冒≦臣R︸bこミ§馬ミミ墨卜D。盆こじρ∪,﹄こ℃胃冨Gooン℃・ミQ。9幹などがある。 目①昇α8良譲諾呂もっ8βg昏二.㊦器こ8身忘塁o梓駐。望ぎ葺Φ留一.弩互o藩日暫冤8ヨ冥一2段窪<9qω●6象も、。。oy 444 懲戒処分法理の比較法的研究 皿 3 折衷的見解 制度説は、使用者の懲戒権を制度としての企業それ自体から導いたこともさることながら、懲戒が一般に組織的集 団における特殊な現象であることを前提とし、そのような実態に則した懲戒の本質の把握、および法的理論構成を標 榜するものであった。いわば、企業および懲戒制度の集団的・組織的特質と、それに基づく独自の懲戒法理の形成を 志向したのである。それに対して、右に見た契約的理解が企業を労働契約の集合としてとらえ、懲戒もまた個別労働 契約に基礎を置くものと解することは、当然のことながら、それが懲戒という特殊な制裁の本質や実態との関連にお いて果たして妥当な懲戒法理をもたらしうるのかという疑間を惹起することになろう。このような観点に立ち、懲戒 ︵1︶ 権の契約的構成に組織法的視点からの修正を試みようとしたのがオーリエである。 オーリエは、一方で使用者の権限は労働契約にのみその根拠を置き、企業それ自体は独自の法律関係の起源たる法 的カテゴリーではなく、同一の使用者により締結された労働契約の総体であるとしながら、同時にそれは労働者の集 団に対して行使される権威の揚であり、その実在性は否定できないとする。そして、労働の分業および組織化の現代 的形態としての企業は、使用者の権限行使に対しても影響を及ぼすという。すなわち、企業の規模が増すにつれて労 使の関係は個別的な債権者・債務者の関係としての性質を失い、使用者の権限は他のすべての集団における一般的な 命令・組織権限に接近するのであり、その結果使用者の権限行使は、それが労働契約に根拠を置くにもかかわらず、 ︵2︶ 労働契約から引出される独自性よりも、一般の団体や行政組織における権限行使に類似した様相を呈するに至るとい うのである。そしてこの観点からオーリエはすぺての組織的集団において現われる懲戒権限︵唇量o胃島豊旨畠貯o︶ について語り、それを基礎として、懲戒権行使における恣意を回避し、被処分者に法的保障を与えるという、刑法と ︵3V 目的を同じくする独自の懲戒法︵身o詳9鴇旦冒aお︶が形成されるとしている。 445 446 オーリエの見解は、懲戒が組織的集団における現象として現われるという実体的特質の問題と、その法形式上の根 拠の間題を明確に区別しようとするものである。オーリエは言う。コ方で、契約への言及は懲戒法の自立性︵鍔δ− まり、﹁使用者の権限が企業の資格に内在するとしても、それが個別化されるのは労働契約によるほかない。使用者 ることはできず、結局それは、法理論上はあくまで労働契約によって基礎づけられねぱならないとするのである。つ るという。しかし、だからといって企業を制度ないし共同体としてとらえることによってそのような権限を基礎づけ ぺての組織的集団に共通な権限としての性格を有し、懲戒権はそのような集団に特有の権限の行使としてとらえられ 同じことは、使用者の権限についてもあてはまる。それは、単に契約のみによってはとらえることのできない、す ︵7︶ すら認めず、企業の全体的な現実性を考慮しないものだとして反対する。 いう。同時に彼らは、契約説による純粋に個人主義的な理解に対しても、それは企業における客観的な連帯性の存在 業を制度・共同体としてとらえるには十分ではなく、それによって使用者の法的権限を基礎づけることはできないと については積極的評価がなされてはいるものの、労使間に事実上の客観的連帯性が存在するというだけでは、未だ企 ︵6︶ る。彼らは、既に指摘したように、企業の制度・共同体としての把握に反対する。そこでは、企業概念の実際的意義 ︵5︶ このほか制度説・契約説双方の批判のうえに一種の折衷的立揚を示す見解として、リベ・”サバティエのそれがあ ば、懲戒の本質と法的根拠の峻別論である。 しかし、他方で懲戒の法的基礎はあくまで契約にあるとする点において、それは一種の折衷的見解と言いうる。いわ 団における懲戒と共に統一的な懲戒法の形成を展望する点では、確かにそれは制度説と類似の観点に立つものである。 ない。﹂と。労使間における懲戒を、組織的集団の存在を前提とした独自の目的と性格を有する制裁と解し、他の集 ︵4︶ 8昌。含魯鼻象ω9嘗巨巴お︶を認めない。しかし他方で、企業の現実を無視する制度理論にも反対しなければなら 一橋大学研究年報 法学研究 14 懲戒処分法理の比較法的研究 H 、 ︵8︶ にとって、個々の労働者に対してそれを行使する可能性が生ずるのは、労働契約からである﹂。 このように、リベロuサパティエは、一方において懲戒の本質や性格の把握については制度説的な理解を高く評価 しながら、使用者の権限、従って懲戒権の法形式的根拠については制度理論ないし企業理論に依拠することを否定し、 それはあくまで労働契約によって基礎づけられるぺきだとする。ただし、そのような労働契約への依存は、リベ・“ サバティエにおいてはもっぱら使用者権限の法理的な根拠づけに限定されている。その問題を離れて、懲戒法理の具 体的内容として説かれるものの多くは、むしろ制度説による理論的帰結に接近する。 以上のような折衷的理解に立つ学説は、その内容にこそ大きなニュァンスの違いはあるものの、次第にその数を増 しつつある。ここにおいて、懲戒権の法的基礎に関する議論は、制度説対契約説という図式的対立の様相を弱め、む ︵9︶ しろそれらの統合に向かいつつあると評価しうるようにも思われる。 ︵−︶9醇㌧霊§。−u。昌㎜昌声b§ミミミ暴麟鳶ヨρ&9一5評箭這鮮やS。3∴家oa83日一。騨。一呂9。邑お ︸島賦8帥ωo一−ヨひヨoα即島一〇。。﹃ぞ℃g岳αo什β<巴一︸U、oり・一8N一やおO ︵2︶○臣Φさ℃■。N。ヨ● ︵3︶○田①5℃﹂獣①9■ ︵4︶ ○≡Φ、一U。oo.一〇隻いマ軌8オーリエにとって企業とは、﹁共同体としてではなく、権限の保持者とそれを行使される者の ︵5︶困義。こ。畳ω塁鋒R︸言pu§ミミ§ミ、。。。&こ牢。・・虜9一<。蜂餌幽﹃窃自。局馨。ρ評冴一。。。一も﹂。pΦ箪“。h 集団との間の対立の揚﹂としてとらえられる。 uo即く鋒。ンい.帥ヨ巳昌①号ω旨ロg凶o冨α一の。旦ぎ巴﹃8匿島一。ωo耳﹃。冥一器ω︵いo一含恥帥呂梓這o。一yu、oo■一〇〇。ご℃■ooo旧oD即く典帥。﹃、 ︵6︶ 困く雪o訪塁毘3や一〇。ω9幹前節二参照。 ℃o薯o一﹃℃p三ヨg芭簿臼89一8切αo。。℃①嵩g器。りbU,oo酢Go。N篭℃●一 447 一橋大学研究年報 法学研究 14 ︵7︶ 勾凶<Ro、ω餌く鱒岳R、マトoOV 切一く臼o\oo麟く舞凶oき℃●一〇〇魯℃’8ひ ︵9︶ q■U①もロ恩℃ 0 一 置 臥 ① び 8 ヨ o N ” ℃ ー ︵8︶ 二 懲戒法理の内容とその問題点 − 懲戒の対象と形態 卑幹 一〇〇9ω..O暮巴欝やまひ9ω∴ 切鋤程“唱■一〇Qo卑9 懲戒を契約によって根拠づける見解においても、それは労働者の︿非行﹀すなわち懲戒的︿非行﹀に対する制裁と してとらえられる。しかしそれは、あくまで労働契約履行上の︿非行﹀に還元されるものであり、契約上のく非行V ︵1︶ である。懲戒の対象としての︿非行﹀は、理論的にはいわば契約上の︿非行﹀の中の一つの変種にすぎない。そのよ うな懲戒的︿非行﹀の具体例としては、就業規則上の規定違反や使用者の命命違反などがあげられるが、労働者は労 働契約に基づいてのみ、それらを遵守して労働する義務を負うものである以上、それらの違反は、制度説によれば民 事的︿非行﹀とされるものと共に、上位概念たる契約的く非行Vに包摂されるものである。また、懲戒的く非行Vと 民事的く非行Vの区別は、一九三二年法による労働法典中の罰金規制条項が仕事の不手際に対する罰金の行使を禁止 している限りでは解釈論上の意味を有するが、実際には労働者の︿非行﹀がそのいずれに属するかは重要ではないと ︵2︶ いう。いずれにせよそれらのく非行Vは使用者によってその当否が判断されるのであり、また、制裁の形態に関して もほとんど影響がないからである。 ︵3V ︵4︶ 次に、懲戒の形態は、﹁企業の長が、労働者による労働契約上の義務の履行を確保するため、労働契約から引き出す 法的手段の全体﹂としてとらえられる。たとえば罰金は、あくまで債務不履行についての違約金の一種、または損害 448 懲戒処分法理の比較法的研究 H ︵5︶ 賠償額の予定である。罰金の規制に関する労働法典の規定も、そのような罰金の本質そのものを変更するものではな い。また、懲戒としての解雇は、すべての契約当事者に認められる契約解除権の行使としてとらえられる。つまり、 ﹁懲戒の目的で行使される契約上の措置﹂にほかならない。解雇は、労働者の重大なく非行Vに対しては予告または 手当なしに言渡されうるが、その︿非行﹀とは懲戒的なものであることも職業的なものであることもできるのであっ て、幅広い内容を有するものである。従って、労働者の︿非行﹀を理由とする解雇を使用者の契約解除権とは異なる ︵6︶ 懲戒権の発現としてとらえることはできず、またその必要もない。同様のことは、それ以外の懲戒措置についてもあ てはまる。出勤停止、配転、降格などは、それらが労働契約上当然に使用者に認められる権利ではない以上、労使間 ︵7︶ の合意があってはじめて使用者のとりうるところとなる。 このように、懲戒の法的基礎を労働契約に求める見解においては、懲戒は、制度説の説くように独自の対象およぴ 形態を有するものとしてはとらえられない。それらはあくまで契約法理の中で処理すべきものとされるのである。 しかし、このような理解については、当然に一つの問題が提起されることになる。すなわち、フランスの伝統的解 雇法理を前提とする限り、懲戒の契約的理解は、右に指摘した労使間の合意を必要とする懲戒措置について、たとえ 事前の合意が存在しない揚合であっても、使用者の解雇権によってそれを正当化することに通ずるという点である。 なぜなら、それは使用者による労働条件変更の申込みとして、労働者の拒否に対しては労働契約の解消がもたらされ ︵8V ついて最もよくあてはまる。そのような理解に立つ限り、使用者はたとえ懲戒規定に定めのない懲戒措置であっても うるからである。その意味で、﹁大をなしうる者は小もなしうる︵大は小を兼ねる︶﹂という絡言は、そのような理解に ︵9︶ 自由に行使しうることになる。解雇権がすべてを説明するのである。それは結局、制度説による不文の懲戒権の承認 と低とんど大差のない結論を導くものであろう。ただし現在では、後述のように一九七三年の法改正によって解雇に 449 一橋大学研究年報 法学研究 14 は正当な理由が必要とされるに至ったことにより、右のような論理構成がそのままの形で妥当するとは思われない。 450 ︵10︶ ︵−︶ξ8−9。pや890一一一。﹃も﹂NNこp<⋮①5ミミ§㌧ミe§・︾鴇。。︸9ヨ。﹃一旨。ぎ℃﹄一 ︵2︶ 一九三二年の罰金規制立法により、例外的に許可された罰金も、﹁規律と、労働者の衛生および安全に関する違反﹂につ 不履行としての仕事の不手際に対しては、罰金が行使されえないと解されていた︵第三章第一節二注︵2︶、第四章第二節二 いてのみ、定められうることになった︵第三章第一節参照︶。その結果、そのような違反とは区別された単なる契約上の債務 参照。ただし二れらの見解は、むしろ同法の規定は仕事の不手際を理由とする違約金には適用がないとする点にその意味があ った︶。 ︵3︶ ○≡①5や一曽 ︵4︶浮σQ仁魯曙ここご唐§ミ舞馨鋭蓉㌣馬憂息“亀.恥ミ・も詳辞け冨ωρ評計望。。も﹂ω︵。⋮ぶ帥毘p⇒。,︸。信<㊧p℃﹂o︶ ︵5︶ ξ86零Pマ8一制度説の論者が、一九三二年法によって罰金が使用者に帰属せず、労働者のための安全基金に払込ま れるべきことをとらえて、それが違約金ではないとすることの根拠の一つとしていたのに対し、リヨン・カーンは、むしろ立 法以前には罰金はすぺて使用者のものとなっていたのであり、安全基金への払込みは、法律による罰金の濫用防止のための特 別の規制にすぎないとする。 ︵7︶ r冤oローO内o昌や舘一 ︵6︶o弩Φ量臭㍉嚢§§ゆ§織ミ黛ミ婁濫嚢§ミミミ§ミ評﹃!§も乙分○≡。﹃も・一N。 ︵8︶ Ω,○=一R噂マ一NO引O即ヨ。﹃一鴇ロ鼻P冤86m。P命α9・。・ ︵9︶ 9B亀旨oぎU●oo。一〇ひ♪マ。。一この主張は制度説の立揚からもなされるが、それが制度説の基本的立場とは必ずしも相 懲戒権の概念とその限界 ︵10︶ O蝉ヨRぞ8遅い図o㌣O器Pや鳶刈 容れないことについては既に指摘した︵第二節五参照︶。 2 懲戒処分法理の比較法的研究 H 懲戒権の概念は、制度説においては個々の懲戒罰の法的淵源であり、また、それらを固有の懲戒法理の下に統一的 に把握するための基礎でもあった。それに対して懲戒を契約によって基礎づける見解にあっては、個々の懲戒罰は一 般法上あるいは個別労働契約によって使用者に認められる権利に基づくものとしてとらえられ、その限りでは懲戒権 の概念は制度説におけるごとき独自の法的意義を有しない。それはせいぜい、使用者が右のような根拠に基づいて行 使しうる個別的権利の集合概念であるにとどまる。 このような懲戒権概念の理解に立つ揚合の一つの、しかも重要な問題点は、懲戒罰の相互関係、特に懲戒罰とく非 行Vの均衡性をいかにとらえるかということにある。たとえば、解雇と罰金について、前者が労働契約上使用者に認 められる解約権の行使、後者が合意に基づく違約金としてとらえられることは、労働者の︿非行﹀の程度に応じてそ のいずれかが選択されるべきことを当然に帰結するものではなく、むしろその双方の行使を可能とすることになろう。 他の制裁形態についても同様である。そのような結果を避けようとする限り、そこには何らかの概念上・論理上の操 作を必要とする。 ︵−︶ このことと関連して、懲戒を契約によって基礎づける揚合には、使用者の懲戒権行使の一般的限界がいかにして導 出されるのかという間題もある。制度説においては、懲戒権を根拠づけるための論理が同時にそれを限界づけるため の論理としても機能した。それに対して懲戒を契約によって基礎づける揚合には、伝統的契約法理による限り、懲戒 の対象や範囲などはすべて、原則として労使間の合意によって定まることにならざるをえないと思われるが、使用者 による一方的な就業規則の作成および懲戒の評価・行使という現状の下では、それは使用者による恣意的・濫用的な ︵2︶ 懲戒権行使を防止するための論理たりえないとの批判を免れないであろう。たとえばリヨン・カーンは、契約法理の 観点から出勤停止の合法性を否定しようとし、それは契約条件の一方的変更であり、既に締結された契約の尊重とい 451 一橋大学研究年報 法学研究 14 ︵3︶ う原則とも相容れないという。しかし、確かにそれは、労使間に出勤停止に関する合意が存在せず、あるいはそれが 就業規則中に懲戒手段として定められていない揚合には、使用者によるその行使を否定するという意味は持ちえても、 逆にそのような合意や規定が存在する限り、その行使を否定または制約する論拠とはなりえない。 以上のように、制度説に対する批判的見解が懲戒の法的基礎を契約に求めるとしても、単にそれだけでは必ずしも 個々の懲戒措置相互の関連性を適確に把握しうるとは言えず、懲戒権の限界性に関しても、それを論拠づけるための 十分な理論的基礎を提供しうるのかも疑問である。そのためか、オーリエにあっては、使用者の懲戒描置はあくまで 労働契約にその基礎を置くとしながら、他方で企業の組織的集団としての実在性を承認し、そのことは使用者による 権限行使の態様に影響を及ぼすとして、すぺての組織的集団に妥当する懲戒法の形成を示唆していた。それは、懲戒 ︵4︶ の現象形態に則したその本質の把握をふまえることにポって、懲戒の法的基礎を個別労働契約に求めることに伴う理 論的限界性を回避しようとする試みと評しうるであろう。しかし同時にそのことは、たとえ懲戒を契約によって基礎 づける揚合であっても、それを限界づけるための統一的な懲戒法理の形成を志向する限り、何らかの形で制度説的な 懲戒の理解ないしはその理論的帰結を取り込まざるをえないことを暗示するものとも言えるであろう。 ︵1︶ このことは、この後で指摘するオーリエの見解に現われるように、何らかの形での制度説的理解の受容として現われざる をえない。 ︵3︶ ξ96舘P℃﹄鴇再切’リヨン・カーンは更に、出勤停止は賃金の全部を奪うものである点において罰金よりも重く、 ︵2︶卑冒、O﹄彗9℃旨a また、その期間中は労働契約が存続することから労働者は新たな職を捜すことができないことなどの故に解雇よりも重い措置 勤停止処分の合法性については、後に判例を検討する際に改めて触れる。 であり、労働の自由を奪うものであるとも言う。その意味では、出勤停止そのものを違法とする趣旨かと思われる。なお、出 452 懲戒処分法理の比較法的研究 H ︵4︶ 前述のオーリエによる基本的理解を参照︵本節輯2︶。 3 裁判所によるコントロール ︵1︶ 制度説は、かつての契約説が懲戒に関する裁判所の関与を著しく制約する結果となったことを批判し、原則として 裁判所による幅広いコントロールの可能性を主張した。それに対して、今日懲戒を労働契約によって基礎づけようと する立場においても、懲戒に関する裁判所によるコント・iルを広く認め、主張する点では、多くの見解が一致して いる。ただし、その論拠や範囲、内容については必ずしも明確ではない。 たとえばリヨン・カーンは、懲戒に関する裁判所のコントロールは︿非行﹀のあるすべての債権者に対するのと同 ︵2︶ 様に行使されるとし、それは権利濫用理論の適用によって判断されるべきであると解するようであるが、その具体的 な対象や内容は明らかでない。また、オーリエは、使用者の権限行使が他の一般的な組織的集団におけるそれと類似 することから、特に行政法との比較において、それが裁判所のコント・ールに服すべきことを主張するが、それは使 ︵3V 用者の権限の契約法上の限界を基礎とし、権利濫用理論を媒介とするものとしてとらえられる。しかしそこでも、契 ︵4︶ 約上の措置としての懲戒処分に対する広範な裁判所のコント・ールを肯定するための十分な論拠を提示しえているか 否かについては、疑問が残る。 総じて懲戒を契約によって基礎づける見解においては、そのような理論構成が裁判所による懲戒のコント・ールに っぱら懲戒に関する介入を一貫して自己規制しようとする判例の立揚に対する批判に向けられ、懲戒の法的基礎につ 関して具体的にいかなる結論をもたらすかについて明確ではない。そのことは、この問題に対する学説の関心が、も いての理論構成の違いは、裁判所によるコント・iルの対象や範囲そのものについては重大な結論上の差異をもたら 453 一橋大学研究年報 法学研究 14 さないと解されることによるのかも知れない。 ︵5︶ ︵−︶ 本章第二節五参照。なお、第三節一もあわせて参照。 ︵2︶ξoコー9。p§ミミ覧慧瞳ミ籍篭翁﹂80も■一轟 ︵3︶○臣3℃﹂8﹁企業の長の権限は、その契約上の義務によって制限されるのであり、権利濫用の理論は、裁判官に対し、 使用者による企業の長としての権限の行使が契約的正義と相容れるか否かを評価することを可能にする。﹂ ︵4︶ 仮に権利濫用理論に依拠するとしても、フランスにおける同理論の理解からして、それが懲戒処分の無効という効果まで ては、依然疑問が残る。 をもたらしうるのか、あるいは懲戒処分の相当性についての裁判所による評価の可能性をもたらしうるものであるのかについ ︵5︶ たとえばオーリエは、判例が一方で制度説によって懲戒権を基礎づけ、他方で契約法に依拠することによって司法審査の 範囲を限定するが如き態度をとっていること︵次章参照︶について、たとえ懲戒権を契約に基づくものと解しても、それを私 ついてそのコントロールを広げるであろうとし、契約か制度かは真の問題ではないと述べている︵○臣璽曼匂D﹂まざや軌oN︶。 法上の﹁コント・ールされた権利﹂としようと欲するならば、裁判所はむしろ契約上の法規たる懲戒規定の公序への適合性に 第五章 判例における懲戒理論 第一節判例における基礎理論とその動揺 一 序説 一九三二年法による罰金の原則的禁止と例外的許可制の導入は、その後の判例に現われた懲戒をめぐる事案に対し ても大きな変化をもたらした。それまでの罰金に関する事案に代わり、出勤停止︵ヨ一器餅風a︶に関する事案が著 454 懲戒処分法理の比較法的研究 H しく増加したのである。そして判例は、この出勤停止についても、当初、それまで罰金についてとっていた契約説的 立揚を踏襲した。しかし、その当時学説において新たに登場した制度説による懲戒理論は、そのような判例の状況に 対しても影響を及ぼさずにはおかなかった。程なくして破棄院は従来の態度を改め、使用者はその﹁内在的懲戒権﹂ に基づき、たとえ明示の合意や規則のない揚合にも、出勤停止処分を行使しうると判示するに至ったのである。 しかしながら、このような判例変更、とりわけ使用者の内在的懲戒権の承認が制度説の影響によるものであるとし ても、そのことは判例が全面的に制度説を採用したことを意味するものではなかった。そのことは、懲戒に関連する 法的問題についての判例の基礎的理解、および懲戒に関する裁判所のコントロールについての抑制的態度に端的に現 われている。このうち後の問題は次節で詳しく検討するとして、本節ではまず、懲戒に関する判例の基礎的理解の変 遷と、判例理論の一貫性の欠如について取り上げる。 一一懲戒の法的基礎に関する判例の変遷 − 鼠勤停止処分の契約的構成ー一九四二年破棄院判決 ︵−︶ 出勤停止に関する破棄院の見解は、一九四二年三月一九日の判決によってはじめて示された。この事件は、職工長 である労働者が仕事上の不注意を理由に一五日間の出勤停止処分を科され、その間の賃金を支払われなかったが、当 ︵2︶ 該工揚には出勤停止についての労働契約や就業規則の定めが存在しなかったという事案に関するものであった。破棄 院は、その揚合の出勤停止処分の合法性に関し、使用者が労働者のく非行Vを理由に出勤停止の制裁を加えることは 法律によって禁止されていないのであるから当然に許されるとした使用者側の上告理由を斥け、次のように判示した。 ﹁企業の長が、たとえ慣習上の予告期間を守って、その職務がもはや満足しえないような労働者との間の労働契約をいつにても 455 一橋大学研究年報 法学研究 14 加えることは、その権限を逸脱するものである。但し、労働協約または労働者との間の労働契約、または労働法典第一編第二二 解約しうるとしても、自らがその存否や程度の判定者となるようなく非行Vの故に、賃金を支払わずに出勤停止という懲戒罰を 条aの規定に則った就業規則により、使用者がそのような権利を得ているときは、この限りでない。﹂ このようにして破棄院は、労使間の合意または協約・規則に基づかない使用者による出勤停止処分の効力を明確に 否定した。それは、既に検討した罰金に関する判例の理解と同様、出勤停止処分の法的根拠を労働契約に求めること を前提とするものと解される。解雇権とは異なり、賃金喪失を伴う出勤停止の権利が労働契約上当然に使用者に認め られるものではない以上、労使間の合意がない限り使用者がそれを行使しえないことは、そのような理解からの必然 ︵3︶ 的な帰結である。また、右の判決が、出勤停止処分は解雇権によっては正当化されないとしている点も注目されよう。 ︵1︶ ωoo﹂Oヨ曽。。一〇お㌔U■oo■一〇&㌧℃■いO轟 ︵2︶正確には、本件は出勤停止処分の効力それ自体が争われたものではなく、使用者による出勤停止処分は実質的に即時解雇 にほかならないとして、即時解雇手当︵ぼ幕ヨ旨芯3σ昌呂垢お暑9︶および解雇補償手当︵ぎ号昌口ま留浮聲含①き①暮︶ の支払が請求されたものである。破棄院は、会社が出動停止処分の行使によって契約の履行を不可能としたものであり、それ によって即時解雇を行ったことになるとした原審の判断を支持し、また、労働者の犯した︿非行﹀は即時解雇を正当とするほ 使用者の出勤停止がいかにして即時解雇と評価されるのかという理論的問題もあるわけであるが、ここでは立入らない。 ど重大なものではなかったとして、右の手当支給の講求を認容した原審についての会社側の上告を棄却した。従ってそこには、 意がなくともそれらの行使が正当化されるとするものがあったが、右破棄院判決は出勤停止が解雇権を逸脱すると述べること ︵3︶ 既に指摘したように、学説の中には、解雇に至らない懲戒措置について、使用者の解雇権を根拠として、たとえ明示の合 によって、そのような見解を否定したと言える。 456 懲戒処分法理の比較法的研究 H 2 ﹁内在的懲戒権﹂の承認−一九四五年破棄院判決 ︵1︶ 右の一九四二年の破棄院判決に対しては、当然のことながら、制度説に立つ学説からの強い批判が加えられた。そ して破棄院は、その後間もなくして、少なくともその文言およぴ結論において、出勤停止処分の契約的理解を放棄し、 制度的に依拠するがごとき判断を示すに至った。すなわち破棄院は、一九四五年六月一六日の判例において、就業規 則中に定めのない出勤停止処分を受けた労働者が、その期間中の賃金額に相当する損害賠償を請求したという事案に ︵2︶ 関し、次のように判示してその請求を認容した原判決を破棄したのである。 ﹁︵出勤停止処分が就業規則に定められていないという︶皐情は、使用者の資格に内在し、かつ就業規則の制限規定が存在しな い限り裁判所のコント・ールを唯一の条件として行使しうる懲戒権を、使用者から奪うものではない。﹂ このようにして破棄院は、﹁使用者の資格に内在する懲戒権﹂に基づき、たとえ就業規則に明文の定めのない場合 であっても、使用者が出勤停止処分を行使しうることを認めた。このような概念および結論は、従来の判例の理解と は異質のものであり、明らかに先の一九四二年判決を変更するものであった。そしてこの判決は、破棄院が使用者の ︵3︶ 懲戒権について従来の契約説の立揚を棄て、制度説を採用することを明言したものとして、制度説に立つ学説からの 積極的評価を受けることになった。 ︵4︶ 破棄院による﹁使用者の内在的懲戒権﹂の説示はその後の判決においても繰返し言及され、定着していった。しか し、ここでは特に、破棄院が﹁使用者の内在的懲戒権﹂について語る判例の事案が、いずれも出勤停止処分に関する ものであったことに留意する必要がある。つまり、そのような懲戒権の根拠づけは単に出勤停止処分について問題 とされているにとどまり、実務上最も重大な懲戒処分として行使される解雇については、破棄院は﹁内在的懲戒権﹂ 7 さ には一切言及することなく、あくまで従来どおりの一般的解雇法理の枠内での問題処理という態度を一貫して維持し 4 一橋大学研究年報 法学研究 14 たのである。その意味で、判例にとって懲戒権の概念およびそれを使用者の資格に内在的なものとしてとらえること の意義は、かなり限定的なものであった。しかも右の﹁内在的懲戒権﹂についての説示すら、一九六一年以降、破棄 ︵5︶ ︵6︶ 院判例の文言からは忽然として姿を消すに至る。それに代ってその後の破棄院判例によって述べられるものは、単に ﹁企業の円滑な運営という利益において行使される懲戒権﹂︵℃o髪o冒島毘喜轟貯o賃R鼠3島一、一馨曾蝉身ぎ.一︷象, ︵7︶ ︵8︶ 註9器ヨo葺階一.oロぼo冥厨。︶という懲戒権の性格づけにすぎない。従って、その後においてもなお、右の一九四五 年判決に示された理解が破棄院によって維持されているか否かは定かではない。 ︵1︶ ω吊夢。αΦ峯O﹃①鴇昌ρZo8ωo霧uりoP6ヨp誘一〇お”O・oQ﹂O醸一マ8鼻 ︵2︶ uりoρま嘗5這&”∪’ω・一翠9や畠N本件の事実関係は、セメント製造工である原告労働者が、監督者から砕炭作業に 従事するよう命じられ、それを拒否したために一週間の出勤停止が言渡されたというものである。原判決は、出勤停止処分を 定める就業規則が存在しないこと、および原告労働者が専門職の労働者であり、彼に与えられた仕事を拒否することは︿非 によって出勤停止処分の行使を肯定したほか、原判決の掲げた理由の第二点に関しては、直接原告労働者の︿非行﹀の存否に 行﹀を犯したことにはならないことを理由に、原告労働者の請求を認容した。それに対して破棄院は、本文中に引用した理由 更が一時的であることを明示して、原告労働者の失業を避けるぺく、当時としては与えうる唯一の仕事を提供したものである ついては触れることなく、監督者が職務変更を命じたのは工場の原料の入荷がなかったことを理由とするものであり、職務変 として、その点に関する会社側の有黄性︵夢三〇︶を否定している。 ︵4︶。D。。﹂。魯まhΦ<﹂裟も■一§も、答一ω。ρ一。。一言一。鴇﹂・ρ℃・一§﹂一㍉§泌。。・試<﹃一=。q♪U・。。・ま♪ ︵3︶9声&層之。斤3。窃の。。﹂Ω言一。参∪・ω﹂£ひも・お。。 ℃﹄8る。ρ睾暴誘一裟ヒひuり﹂霧も■§る。。レ。⋮﹂霧・じ﹂裟あ§日も﹂$あ・。﹂。暴二尋こ6コ ︵5︶ なお、破棄院は、戒告・謎責については懲戒権の行使としてとらえている。Oやω8・8導p=30。・qρ一3Q。も﹄巽︵適 一300,=,ろひ“∋ωoρ轟欲く,一〇ひρ9ρ口ちひ9一く,& 458 懲戒処分法理の比較法的研究 n ︵6︶9ぽpo。。■6。。ρやま。。 法なストライキ権行使に対する手当カットおよぴ誕責処分を懲戒権の濫用とした事例︶ ︵7︶ q・℃・①×,oooρひ昌o<﹂OqOり旨ρ型一89目ニミざPω■一8ρマO曾oooρ嵐濠o﹂8ン一りρ℃﹂O総、一一■一誠Oy U■一8ρ℃乙8なお、これらの判例は、いずれも懲戒処分の相当性についての裁判所によるコント・ールに関するものであ ︵8︶ 本章第四節一参照。 る。詳しくは次節参照。 三 判例における制度論的理解と契約論的理解 1 使用者の黄任とその権限 判例による懲戒権の法的根拠に関する理解の評価については本章の最後に取り上げるとして、ここではさしあたり、 そのための前提となる若干の附随的問題に関する判例の理解について触れておく。それは、一言でいえば、制度論的 理解と契約論的理解の混在であり、理論的一貫性の動揺である。 まず、右に見た判例による懲戒権の理解は、使用者に対して幅広い権限の行使を承認しようとする判例の基本的傾 向と不可分のものとして位置づけられるものである。既に指摘したように、判例、殊に破棄院は、以前から、労働者 の労務遂行の評価や人員整理における対象者選択などについて使用者こそが﹁唯一の判定者﹂であるとの理解を示し ︵1︶ ︵2︶ ︵3V ていたが、そのことは、その後明確に﹁企業の円滑な運営を確保すべき使用者の責任﹂によって根拠づけられるに至 り、更にその対象を拡大されることになった。すなわち、そのような責任を有する使用者は、単に企業の組織づけの みならず、企業閉鎖そのものについても、また、労働者の行動が企業の運営にとって有害か否かの評価についても、 ︵4︶ ︵5︶ 459 一橋大学研究年報 法学研究 14 ﹁唯一の判定者﹂であるとしたのである。このように判例は、使用者に対して企業運営に関する極めて広範な裁量権 ︵6︶ を承認しているのであって、先に指摘した一九六〇年代以降の破棄院判例による﹁企業の円滑な運営という利益にお いて行使される懲戒権﹂という観念も、まさにそのような判例における基本的理解の一環として位置付けられるもの であった。 ︵7V 判例のいう企業の円滑な運営についての﹁使用者の責任﹂の観念は、少なくともその文言上は、制度説において使 用者の権限の法的基礎とされるものと同一である。その限りでは、判例が古くから維持してきた使用者権限の絶対性 の承認は、制度論的影響の下に、新たな正当性の根拠を見出したと言えるかも知れない。しかし、判例のいう﹁使用 者の貴任﹂の観念は、常に抽象的脈絡の中で言及されるにとどまり、その具体的内容や根拠は決して明確なものでは ない。そのため、そのような判例の基本的理解をめぐっては、後に見るように様々な評価と批判が加えられることに なる。 ︵2︶ωoPo9け■一翠一こ■ρ型G斜一﹂一■一NS ︵1︶ 第三章第二節参照。 oりoヨ日■℃・象︶などが、それ自体としては使用者の有責事由︵鼠再。︶とは解されないことを意味する。 ︵3︶ このことは、企業の組織変更に伴う解雇︵oo8・望冒コ這茎qω﹂o軌♪マ爲o︶や職務替︵ω8砧一9け﹂8♪q這象・ ︵4︶ωoρい一日巴一。軌ひこ,ρ℃﹂39一一●80N ︵5︶o。。ρ峯象p一890﹂。驚㌧やミ。 である。ω09ω臼巴一SPU■一ミPH菊﹃マまQo ︵6︶ このほかにも、使用者は、たとえば労働災害防止のため労働者に課されるべき安全措置の内容について﹁唯一の判定者﹂ ︵7︶ 特にデュランの理解︵第四章第一節三2㈹︶を参照。 460 懲戒処分法理の比較法的研究 H 2 就業規則と懲戒権 他方、判例が明らかに契約論的理解を示し、判例による懲戒権に関する基本的理解の捕捉を一層困難なものとして ︵1V いるのが、就業規則の法的性質および効力に関する判例の状況である。 判例が以前から就業規則を契約によってとらえ、特に労働者の同意の有無を問題としていたことについては、既に 指摘した。判例はその後も、基本的にはそのような立揚を変えてはいないように思われる。そのことは、たとえば、 ︵2︶ 就業規則による懲戒規定が、民法典第一一三四条に基づき、﹁当事者の法﹂として裁判官をも拘束するという判例、 あるいは、就業規則に定める懲戒手続を履践しないことは単なる契約上の帰責原因たるにとどまり、当該懲戒処分の 無効をきたすものではないとする判例からも窺われる。ところが、他方において判例は、適法に登録された就業規則 ︵3︶ については、労働者の個別的な同意をまつまでもなく、使用者はそれをもって労働者に対抗しうる︵ε℃o鴇三。︶と の判断を示しており、その﹁対抗﹂ということの意味と共に、判例の就業規則についての理解は必ずしも明確なもの ︵4V ではない。そのため、このような判例による就業規則についての理解と、先の使用者の権限に関する判断がいかに調 和的に結ぴ付きうるのかは、それ自体が一つの大きな間題である。 ところで、就業規則と懲戒権の関係についての判例の理解に関して興味ある素材を提供するものが、ストライキに 附随してなされた懲戒処分をめぐって破棄院の示した判断である。すなわち破棄院は、時限スト中になされた職揚退 去命令に違反したことを理由とする出勤停止処分が問題となった一九六八年の判決において、﹁労働契約の履行はス トライキの期間中停止されるのであるから、使用者は、重度の︿非行﹀︵壁暮22己。︶を構成することを主張しない ストライキに参加したことを理由として懲戒処分を科すために、就業規則または服務規定の定めを利用することはで きない。﹂と判示したのである。同様の判断は、その後、ストライキ中の職場集会参加を理由とする戒告処分が問題 ︵5︶ 461 一橋大学研究年報 法学研究 14 となった一九七二年の判決においても踏襲されている。 ︵6︶ しかし、仮に破棄院が懲戒権の法的根拠について、制度説に従い、それを使用者の資格に内在的なものとして理解 しているのであれば、それは労働契約の停止いかんや就業規則上の懲戒規定の有無とはかかわりなく行使されうるは ︵7︶ ︵8︶ ︵9︶ ずであり、就業規則の定めを利用できないことの故に懲戒権の行使そのものを否定することは、明らかにそのような 前提と矛盾する。懲戒権とストライキの関係については後に改めて検討するが、少なくとも右に見た限りでは、前掲 した一九四五年判決によって示された懲戒権の制度説的な理解は、その後の判例の中では必ずしも一貫した形では維 持されておらず、多分に契約論的理解ないしはその影響の跡を留めていると言いうるであろう。 琶塾馬織ミ冬&∼§鳳ミミ㌣幅盆。∪毘o斜℃帥冴一〇N曾ω三ミO巴一塁ρN。8こけρマ一〇。U①鉾も・■一〇〇ρβ昂圃8、牢塁9。。い■Φ8− ︵−︶ 就業規則に関する従来の判例の状況については、次の文献を参照。国器ε8舌pX撃耳・履磐ヨ窪二暮窪。章謁奪聖 αo一。ヨ象二耳豊2﹃鼠冨一①ω。暮器℃身βu■○﹂80。一PN&︸∪仁Roω,=①昌㌧ピ①議。p一①B①コニ暮曾一。章∪■○﹂oNP℃﹂緯 ︵2︶ωo。■ひ8<、一εPいρ℃﹂。ひ。﹂一■二轟NざU,ω﹂8ρ℃●3訪。。臼3召<■一〇ヨ∪﹂。NざH勾■や9 ︵3︶ ωoPN日貧ω一8γ旨ρ℃■一8﹃同<.9ωoρO目曽ω一8ど旨O、℃■一8一,一<■9 ︵4︶ oooρ撃隷く﹂呂一こ◎ρ℃レリ鐸目ままρu.oo﹂ミ一︸M︶﹂9これに対し、労働契約の本質的変更をもたらすような ω帥く卑江oき09R<馨一〇⇒ωo=研ωoρN一〇9,一8♪U●ω.一8魯つトo斜ooo枠○げωΦ﹃<馨凶op。ゆ◎岳ooop繋泳<●一〇NどO。oo●む刈ど 揚合については、使用者は就業規則の変更をもって労働者に対抗しえないとする。oooρ曽03這皐qψち9・℃﹄ミ“9 ︵5︶ω09ま象。﹂oα。 。 ︸ u ● o o ﹂ 。 ひ P ℃ 乙 一 。 。 や轟8 ︵7︶ 前掲︵本節二2︶一九四五年破棄院判決参照。そこでは、使用者の内在的懲戒権は、たとえ就業規則に定めのない揚合で ︵6 ︶ ω 。 ρ ど 巨 ﹂ 。 鋼 U , ω ■ む 団 ♪ つ 象 あっても行使されうるとしていた。そのことは、使用者の懲戒権は、そもそも就業規則の存否とは無関係に︵就業規則による 462 懲戒処分法理の比較法的研究 H 制限のある揚合を除いて 同破棄院判決参照︶根拠づけられ、行使されうることを意味しよう。それはまた、労働契約の停 止いかんにもかかわらないはずである。Oい切曾磐“甘鴛き貿P日.ぎ評98幕5ω島窮目一〇ロ倉8昇βけ留賃塁巴一ω弩一8 ︵8︶ そのような前提に立つ限り、裁判所によるコント・ールを唯一の留保条件として懲戒権を行使しうるとの結論は導きえて 邑帥低o嵩一房捧暮一〇ロ昌①一一。ω鼠霧一、。昇器冥一ωpU’ω■一〇。。ρ℃■一$ ㎝ o = o o ω o ρ 斜 廿 一 一 ■ む 認 い 旨 。 ρ 型 一 〇 蕊 ・ 目 ■ 一 翼 ひ 斜 も、就業規則を利用しえないことから懲戒権行使を一律に否定することはできないはずである。9頴冴旨50訂R<碑一8 第二節懲戒処分に対する裁判所の審査 ︵9︶本章第三節三3参照。右判例の上記以外の解釈の可能性についても、そこで指摘する。 一 序説 破棄院判例は、右に見た﹁使用者の内在的懲戒権﹂を承認するにあたって、それが﹁裁判所のコント・ールを唯一 の留保条件とする﹂︵。。。島一塑の。巳。誌。。。署。身8口貫ひ一〇3一、碧ε﹃ま甘象o芭8︶ものであることを認めていた。逆 ︵−︶ に言えば、懲戒権に対する裁判所による審査の可能性を原則的に承認したことを意味する。右の説示自体は、﹁内在 的懲戒権﹂への言及と共に、その後の破棄院判例の上からは消失するに至るが、裁判所による審査の可能性そのもの は否定されていない。また、懲戒としての解雇についても、あくまで解雇一般に関する判例法理の枠内においてであ るとはいえ、裁判所による審査が及ぶことが認められている。問題は、それらの対象およぴ範囲である。すなわち、 判例は、懲戒処分をめぐる一定の事項については裁判所の積極的関与を認めながら、特に懲戒処分の担当性、つまり 制裁と︿非行﹀の均衡性の評価については、一貫して裁判所による審査を否定しているのである。懲戒権に関する判 例の基本的理解も、そのような判例の状況と対比することによって、より明らかとなるであろう。 463 一橋大学研究年報 法学研究 14 ︵2︶ ところで、この問題を考慮するにあたっては、懲戒処分のうち解雇とそれ以外のものを区別することが、判例を理 解するうえでは有意義である。以下でも、この区別に従って検討を進める。 ︵−︶ 前節二2で掲げた一九四五年判決およぴ注︵4︶のその後の判例は、いずれもア一のことに言及していた。 ︵2︶ 解雇以外の懲戒処分として判例に登揚するものは、大半が出勤停止処分である。先に見た判例による懲戒権の根拠およぴ 性格についての説示は、すぺて出勤停止処分に関して述べられたものであり、この後に見る解雇以外の懲戒処分に対する裁判 所の審査に関する判例も、多くは出勤停止が問題となったものである。 二 解雇以外の懲戒処分に関する審査 − 審査の及ぶ事項 解雇以外の懲戒処分に対する裁判所の審査は、まず、その理由となった労働者の︿非行﹀の存否およぴ性格、つま り、懲戒の理由とされた労働者の行為の有無と、それが懲戒処分を正当化するような︿非行﹀を構成するか否かの問 ︵1︶ 題に及ぶ。そしてこの観点から、労働者の︿非行﹀が認められない揚合に当該処分を懲戒権の濫用とし、使用者の損 害賠償責任を肯定した事例が多数存在する。 次に、裁判所による審査は、当該処分が就業規則や労働協約による制限規定に反していないか否かに及ぶ。先に見 た﹁使用者の内在的懲戒権﹂について語る判例は、それが﹁就業規則による制限規定がない場合には、裁判所による コント・ールを唯一の留保条件として﹂行使されるものであると述べていた。そのことは逆に、そのような制限規定 ︵2︶ が存在する限りで使用者の懲戒権は制約を受け、そのことが裁判所の審査に服することを意味しよう。しかし、実際 にはそれが極めて限定的な意義しか持ちえないことも確かである。実務上そのような規定が就業規則中に定められる 464 懲戒処分法理の比較法的研究 n ことはまれであり、また、そのような規定として意義を有するはずの懲戒手続に関する就業規則およぴ労働協約上の ︵3︶ ︵4︶ 規定も、判例による限り、かなり限定的な効力を有するにすぎないからである。しかも、当該懲戒処分が就業規則の ︵5︶ 定める限度内で行使された.︼とは、判例によれぱかえってそれを正当化する理由となり、裁判所の介入を抑制する機 能を果たすことになる。 ︵6︶ 以上のほか、懲戒権行使の態様についても、たとえばそれが差別的な性格を有するものか否かについて裁判所の審 査が及ぶ。さらに、使用者の懲戒権が労働者の基本的権利・自由を定める公序規定に反しえないことは当然であり、 それについてはもちろん裁判所の審査権限が及ぶことになる。 ︵7︶ ︵−︶ たとえば、従業員に対する外出の不許可が慣行およぴ例外的事情に照らして権利濫用とされ、それを無視して外出したこ とを理由とする出勤停止処分を不当とした事例︵ωoρ卜⊃oo3む総、qoo﹂8斜℃﹂ひひ︶、使用者がいかなる明確な理由も主 張しない出勤停止処分を濫用とした事例︵ωoρ。。宣量﹂頴♪qO﹂8ざ℃﹄総︶、職務を定めて雇われた労働者が、約定 請求を認容した事例︵oooΩ8ぎ<﹂SざU・おNo。㌧oooヨ日・や9︶などがある。なお、次節二も併せて参照。 によれぱ任意とされる職務への従事を拒否しても︿非行﹀を犯したことにはならないとして、出勤停止処分による損害の賠償 ︵2︶ 前節二2注︵4︶に掲げた判例参照。 ︵3︶ 実際の就業規則上の懲戒規定が概括的なものにとどまり、懲戒権の行使を厳格に限定する趣旨で定められてはいないこと ︵4︶ この点は、次節四で検討する。 については、既に第二章において概観した。 ︵5︶ω。。・診。く﹂§こ・・も﹂§・目毫ヨu。。。﹂§らβ。。。。﹂。暴﹃三塗ヒ﹂義も.馨 ︵6︶ しD8.誌すミ﹂8yqω﹂。9℃﹂8企業内での示威行動に参加した従業員代表者に対してなされた出勤停止処分に る差別的行使として、懲戒権の濫用とされた事例である。 つき、当該労働者がその行動の主謀者ではなく、特別の責任もなかったと認定され、従業員代表者であることのみを理由とす 465 一橋大学研究年報 法学研究 14 ︵7︶ たとえば、憲法前文で保障されたストライキ権の行使に対する懲戒処分︵手当カットおよぴ認責︶を懲戒権の濫用とした 事例︵oo88旨巴一凛Q。℃∪■O﹂εQ。いマ8一︶、予備従業員代表者の資格を有する労働者に対する降格処分に関し、それが い限り、公序に関する法規定に違反するものであるとした事例︵oooo﹂oすミ﹂80。”qψむひ。。一マao。︶などがある。なお、 企業委員会の同意または労働監督官の許可なくなされたことは、当該労働者が重大な︿非行﹀︵ぼ5①αq.p<。︶を犯してはいな 後者の事例は、従業員代表に対する懲戒権行使の要件に関するものとして興味深いが、ここでは立入らない。 2 相当性の評価 以上のように、破棄院判例は、解雇以外の懲戒処分について一定の範囲での裁判所による審査の可能性を容認する ものの、個々の懲戒処分の相当性の間題については、一貫して消極的な態度をとり続けている。 まず比較的初期の判例として、裁判所による懲戒処分の相当性評価を肯定するかの如き表現を用いる破棄院判決が あった。それは次のように述べる。 ︵−︶ とするのに十分か否かを評価するのは、事実審裁判官の権限である。﹂ ﹁使用者が、その懲戒権によって労働者に対して出勤停止処分を科しうるとしても、主張にかかる異議が、科された制裁を正当 ︵2︶ ︵3︶ この判決は、一般に、破棄院が裁判所による懲戒処分の相当性評価を肯定した唯一の事例として位置づけられてい る。そのような評価は、右の判決内容を全体として読むならば疑問がないではないが、少なくともその文言上は、そ のような審査の可能性を示唆するものであった。 しかし右の判決は、その後の破棄院判決の展開を見る限り、全く孤立したものであった。すなわち、破棄院は、右 の判決後間もなくして、労働時間中の職揚集会開催を理由とする従業員代表者に対する出勤停止処分につき、原判決 466 懲戒処分法理の比較法的研究 U が当該労働者の︿非行﹀はそのような制裁を正当化するほど十分に重大なものではないとして損害賠償の請求を認容 したのに対し、労働者の︿非行﹀が存在する以上、使用者が正当にその労働者に科した制裁を無に帰することはでき ないとして、原判決を破棄したのである。そしてこのような破棄院の立場は、その後さらに、事実審裁判官が自己の ︵4︶ 評価を使用者のそれと置き換えることの禁止として定着することになる。 ︵5︶ このような意味で、破棄院判例の一つの転機となったのが、一九五九年一一月六日の判決であった。この判決にお いて破棄院は、原判決が制裁と︿非行﹀の間の不均衡を認め、実際になされた三〇日の出勤停止処分は一日にとどめ られるぺきであったとして、それを超える期間についての得ぺかりし賃金相当額の損害賠償の支払を使用者に命じた のに対し、﹁使用者は、争いのない︿非行﹀に対して、その適宜性と事業揚の規律を考慮し、当事者の法でおる従業 員規則に定められた限界の範囲内で制裁を科した﹂との認定を前提として、次のように述べて原判決を破棄した。 ﹁事実審裁判官は、企業の円滑な運営という利益において使用者により行使される懲戒権の目的の踊越︵象εロヨ。旨Φ薄︶を構成 する事実を指摘することなく、自己の評価を会社およぴ同意見の懲戒委員会のそれに置き換えることに帰藩したものである。﹂ このようにして破棄院は、懲戒事由である労働者の︿非行﹀の存在が確認され、しかも使用者が規則の定めに則っ て懲戒処分を行使する限り、懲戒権の目的の喩越のある揚合を除き、事実審裁判官が懲戒処分の相当性、すなわち制 裁とく非行Vの均衡性を評価することを明確に否定した。そのような事実審裁判官による評価は、右の事案のように 出勤停止処分期間の縮減をもたらす揚合のほか、戒告・謎責などのより軽い処分を相当と判断する揚合をも含み、そ ︵6︶ れを否定することは、その後の破棄院判決においても繰り返し判示され、確固たる判例となっていった。 ,ただし、このような破棄院の断固たる態度にもかかわらず、下級審判例の中には、裁判所が懲戒処分の相当性を判 断しうるとするものが少なくない。そのことは、つい最近に至るまで、右に掲げた判示と全く同一文言の理由によっ 467 一橋大学研究年報 法学研究 14 て原判決を破棄する破棄院判決があとを絶たないことからも窺われよう。 ︵7︶ ︵1︶ oooP凱甘一一■一〇鴇じ一、ρ型一3避目・刈ON♪Poo﹂3∋や零 ︵2︶995マ総避○巨8ヨo“O■○﹂8y℃﹄ごまた、本判決が、その後の破棄院判決とは異なり、当該処分が就業規則 に基づいてなされたか否かを問題としていないことから、それは、就業規則の定めの有無によって裁判所のコント・ールの範 旨だとする見解も存在した︵ω葺Pや鳶。。︶。しかし、本件において当該処分が就業規則の定めに基づかずになされたものか 囲を区別することを前提とするものであり、それが存在しない場合には、裁判官のコント・ールは完全なものとなるとする趣 が異なる旨を明言する判例も見当たらない。 否かは少なくとも判決文の上からは明らかではなく、また、そのほかに就業規則の有無によワて裁判所のコント・iルの範囲 ︵3︶本件は、従業員代表者︵原告︶が混乱を惹起するような印刷物を配布したこと理由とする出勤停止処分が問題となったも のであるが、原審は、原告が当該文書の作成、配布者であることの立証がなく、また、右文書の中で社名を用いていた.︶とに 支払を命じた原判決は相当であるとしたのである。仮にその場合に、原告が文書の作成・配布者である.︶との立証がないとい ついても悪意によるものではないと認定していたのであり、破棄院は、そのような認定の下では結果的に使用者に損害賠償の ︵4︶ ωoo●8﹄巳賢一〇象bU、ψ一8μやおい う点を重視するならば、それはむしろ労働者の︿非行﹀が存在しない揚合であろう。 ︵5︶ωo。・ひ9<﹂3檜︸・ρコ這αo・目=竜yqω﹂8ρや温本件は、従業員代表者である原告労働者が、他の従業 なお、本件では被告会社に懲戒委員会の制度が存在し、使用者は右処分に先立ちその諮問の手続を経ていた。 員に対し、会社の車庫管理者の措置に従わないようそそのかしたことを理由とする出勤停止処分が問題となったものである。 ︵6︶。。。ρ猛念ρま一こ■ρ雪まN﹂H、葭。ざu﹂§㌧やQ。倉ω。。﹂。暴冴ま魯u﹂。舞や§ぴ。9一。喜・ 一〇ひ9P一8ざoooヨヲ℃■軌ごωopo。一色﹂SρU﹂ONρ℃●刈刈9ω8●ω念ρ一零魯U・一〇V9一・客や倉ωop。αひp 一s鈎u、○﹂ξ9℃・ま押ωoρε婁<﹂。署”u﹂sざ一◎男。やひ押ω09No一三野6ヨu﹂sy一・勾・マ8N旧ωoρ嵩 昌o<し霜o。・U﹂鶏PH・男・マ89その他の判例につき、 9琶欝りお♪勺警裟Φ5℃﹄翼魯9参照。 468 懲戒処分法理の比較法的研究 H ︵7︶注︵6︶に掲げた判例は、いずれもこの趣旨のものである。 3 懲戒権の目的の喩越︵象8q旨oヨ○算︶ 破棄院は、裁判所による懲戒処分の相当性評価を否定するにあたって、多くの揚合に、事実審裁判官が、懲戒権の ︵1︶ 目的の喩越を構成する事実を指摘することなく、自己の評価を使用者のそれに置き換えたものであるとしていた。逆 にそのことは、懲戒権の目的の楡越が存在する限り、例外的に裁判所の審査が懲戒処分の相当性についても及ぴうる とする趣旨であることを推測せしめる。しかし実際には、破棄院による懲戒権の目的の喩越への言及は、それによっ て使用者の懲戒権を限界づけ、裁判所の審査対象を拡大するというよりは、むしろそれを構成する事実の摘示のない ことをもって、原判決破棄の理由とすることにその意義があった。ペリシエによれば、一九七九年までに懲戒権の瞼 越に言及する破棄院判例は二三件存在するが、そのうち二一件において懲戒権の蹴越が存在しないとされ、更にその うち二〇件が原審の判断を破棄したものであるという。単にこの数字だけを見ても、懲戒権の目的の喩越という概念 ︵2︶ が実際に果たす機能は明らかであろう。つまりそれは、使用者に対するよりは、むしろ事実審裁判官に対して、その 権限を制約するという役割を担うものであった。 ︵3︶ 破棄院判例における懲戒権喩越の観念の機能が以上のようなものである限り、その内容を破棄院判例のうえから具 体的に明らかにすることはできない。そこからはせいぜい、制裁と︿非行﹀の程度の不均衡、あるいは使用者による 懲戒処分選択における相当性の欠如といえども、それ自体としては懲戒権の喩越たりえないという、消極的な意味で の結論を導きうるにすぎない。 ︵4︶ このような中にあって、破棄院が懲戒権の喩越の存在を明確に認めたと思われる事例が一件だけ存在する。これは、 469 一橋大学研究年報 法学研究 14 工揚の暖房が不十分であることに起因するストライキに際し、職揚の立ち退きを拒否したことを理由に二人の従業員 代表者に対してのみ戒告の懲戒処分が科されたという事案に関するものであるが、破棄院は、使用者がそれらの者を 差別することによって懲戒権の目的を喩越したとして当該処分を無効とした原判決を、結果的に相当として支持した のである。また、それ以前にも、直接懲戒権の喩越には触れないものの、集団的示威行動に参加した従業員代表者に 対する出勤停止処分について、その者が右の行動の指導者ではなく、特別の責任も認められないのに、従業員代表者 のみを罰したことは、もっぱらそのような資格に基づく差別であり、それによって使用者は懲戒権を濫用したもので ︵5︶ あると判断した原判決を支持した破棄院判決があった。 これらの判断を見る限り、破棄院は、少なくとも従業員代表者という法律上特別に保護された地位にある者につい ては、もっぱらそのような資格に起因する差別的懲戒権行使を懲戒権の喩越︵もしくは濫用︶としてとらえる趣旨で あることが窺われるであろう。ただし、右の二つの破棄院判決においては、必ずしも明確に当該労働者の︿非行﹀の ︵6︶ 存在は認定されていないのであって、仮にその存在が明確に肯定される揚合にも、懲戒権の差別的行使が否定される ことになるのかについては疑問が残る。 ︵7︶ ところで、判例によって懲戒権の楡越が語られる揚合、それは直接的にはあくまで解雇以外の懲戒処分に関してで あった。それに対して、懲戒としての解雇については、判例︵少なくとも破棄院︶は、そもそもそれを懲戒権の行使 としてはとらえておらず、その目的の喩越も問題としていない。確かに、学説の一部には、解雇に関する一定の判例 ︵8︶ をも懲戒権の鍮越の観点からとらえようとするものもあるが、そのような判例においても、実際に間題とされている ︵9︶ のは、あくまで一般的な濫用解雇法理に基づくその成否である。 ︵−︶前掲一九五九年一一月六日破棄院判決の判示︵本節二2︶を参照。また、そこで引用したその後の破棄院判例でも全く同 470 懲戒処分法理の比較法的研究 皿 ℃睾ω巴oンミ駄ミ苫簡静℃。N馨卑9 のことが述べられている。 ︵2︶ ωopひ旨o︿ー這N♪U。一〇翠、一,押やN& 勺ひ一ぼ巴①きミ無§頓3℃,卜﹂まuOo70pU.oo■おooρでぐ一〇梓9 一 ︵3︶ 賦8<﹂鶏。。・U・ち郵一・幻・や舘o︶では、当該労働者に対する差別を特徴づけ、それだけで権限の蹄越を証明しう ただ、従業員代表者ではない通常の労働者に対する出勤停止処分が問題となった一九七八年一一月一五日の破棄院判決 ωopに一雪く ■ 一 8 N ㌧ ∪ , o o ー 這 ひ ざ や い 8 ︵4︶ ︵5︶ ︵6︶ ︵uワop 明 確 な 事 実 を 摘 示 し るよ うな て い な い と し て 、原判決を破棄している。しかし、このことをとらえて、破棄院が一般的に差別 の 蹴 越 の 内 る と は 速 断 Oろ いう 勺ひ=ω巴oきミ駄ミ譜聲や鴇O①け三頴一凶ω馬。一①さ 的懲 戒 権 行 使 を そ 容 と 解 し て い で き な い で。あ 工場内の平穏を保つ性格のものであったとされ、一九六七年判決では、当該労働者に特別の責任はないとされていた︵集 右の判例のうち、一九七四年判決では、当該労働者が従業員代表としてその揚に留まることは通例のことで望ましくもあ Oσの① ﹃< 暮 一 〇P ωo器oooρ凱昌o<。一Soo︾∪・一ξO、一。国●℃ー8一 ︵7︶ り、 行 動 そ の も の の 違 で な い ︶ 。 その限りでは、それらの判決において、懲戒権の喩越が、たとえ 団的 示戚 法 性 に つ い て は 明 らか ︵b雲邑3ミ賢§恥惨℃■ミ。。︶とは必ずしも言い難いようにも思われる。 労働者がく非行Vを犯した揚合でも、事実審裁判官に対して使用者の懲戒権行使にコント・ールを及ぼすことを可能にした ︵8︶ ω醤ミO匿男9一。﹃窪’やミP鳴&﹄’ρマN89εじ昌鼻や台o。 ︵ 1 V 懲戒としての解雇に関する審査 労働者の︿非行﹀の程度と解雇の相当性 471 ︵9︶90≡9や旨。。 三 1 一橋大学研究年報 法学研究 14 懲戒としてなされた解雇については、判例はまず労働者の︿非行﹀に関して、それ以外の懲戒処分の揚合とは異な り、単にその存否のみならず、その程度についても裁判所の審査が及ぴうることを認めている。破棄院判例によれば、 ﹁事実審裁判官は、単に︿非行﹀とされた事実の存在のみならず、使用者がそれに与えた重大性の程度、および協定 ︵2︶ や就業規則が法律上の強行規定に違反しないかどうかについて判断する権限を有する﹂。そして、事実審裁判所の認 定にかかる労働者の行為が︿非行﹀を構成し、その程度が重大か否かの判断は、単なる事実問題ではない法律問題と ︵3︶ して、最終的には破棄院の審査に服することになる。 しかし問題は、判例が︿非行﹀の重大性について裁判所の審査が及ぶとすることの意味である。すなわち、それは 決して労働者の︿非行﹀が懲戒処分を相当とする程度のものか否かという観点からの評価ではなく、あくまで、使用 者が法律上義務づけられた解雇予告や解雇に伴う諸手当を免れるための条件としての︿非行﹀の程度についての評価 ︵4︶ であった。たとえば、労働者は重大な︿非行﹀︵鼠暮Φαq声奉︶のある揚合を除いて解雇予告の権利を有するが︵労働 法典旧第一巻第二三条d、現行L一二二i六条以下︶、判例は、そのような法規定は強行規定であり、それに反する ような使用者による︿非行﹀の評価や就業規則等による定義づけは許されないとしたのである。同様のことが、解雇 補償手当︵L一二二ー九条︶に関する重大な︿非行﹀︵拭暮・σQβ<o︶、あるいは、ストライキを理由とする解雇︵L五 ︵5︶ 二一条︶や休暇補償手当︵L二二三−一三条︶に関する重度の︿非行﹀︵置暮28巳。︶についても問題となる。いず れにせよ、このような揚合に判例が労働者のく非行Vの性質や程度について評価を加えるのは、あくまでそれぞれの ︵6︶ 法規における法律効果の要件の存否という観点からであって、懲戒としての解雇の相当性という観点からではない。 ︵7︶ 判例によれぱ、解雇が労働者の軽度の︿非行﹀︵富9。一粛曾Φ︶を理由とする場合であっても解雇そのものは有効であ り、解雇が懲戒としてなされたという事実は、そのことに対して何らの影響も及ぼすものではない。 472 懲戒処分法理の比較法的研究 且 次に、右のような意味での重大な︿非行﹀の存在が認められる限り、それを理由に即時解雇を行使することが適当 か否かの評価は、使用者に委ねられることになる。使用者はそのことを予め就業規則に明示することも可能であり、 そのような揚合には、事実審裁判官は、即時解雇が過度のものであるとして解雇予告に代わる賠償金の支払を使用者 に命ずることはできない。破棄院はそのような判例を下した原判決を破棄するにあたり、﹁当事者間の法たる上記︵服 務︶規定の文一一、一ロに照らして、会社は職員の規律と安全という利益がその適用を必要とするか否かを理解する唯一の判 定者である以上、事実審裁判官は、自己の適宜性︵o電o詳自ま︶についての評価を会社のそれに置き換えたものであ ︵8v ︵9︶ る﹂.︶とをその理由としていた。同様のことは、即時解雇以外の通常の解雇についてもあてはまる。このようにして 使用者は、判例上、解雇権行使の適宜性の評価について排他的な権限を認められることに蕉肥・ の労働者の︿非行﹀の程度が異ならない揚合であっても、使用者がその一方との雇用関係を継続することが企業の利 判例のこのような態度は、解雇の差別的行使についての判断にも影響を及ぽしている。すなわち、破棄院は・二人 益であると考えるときは、両者に同一の制裁を科すこと義響けえ需のでは喪箆・晃・たとえ︿非行﹀ が同等であっても、他の要素を考慮することが許されるという事情の下では、多数の労働者のうち組合活動に従事し パむレ ていた一人のみを解雇しても、差別とは認められないとしているのである。ただし、最近の破棄院判例の中には、ス トライキ中の違法行為について、他の参加者との間に差異が認められないにもかかわらず、使用者が組合代表者およ び従業員代表者に対してのみ解雇手続をとったという事案において、使用者の差別的態度についての労働者側の主張 パど を是認したものがあり、先に指摘した法定従業員代表に対する解雇以外の懲戒処分に関する破棄院判例との関連でも、 今後の動向が注目される。 ︵1︶ 後述のように、解雇に関する法制度は、特に一九七三年の法改正によって大幅に修正された。ここで取り上げる判例は、 473 一橋大学研究年報 法学研究 14 ︵2︶。。。ρ舘鷺琶まpじ・ω﹂。頓。も・お。 主としてそれ以前のものである。 ︵4︶ 重大な︿非行﹀とは、一般に、たとえ一時的にせよ労働契約の継続を困難にし、解雇予告手当の喪失を正当化するほどの ︵3︶。・。ρN。・α・ρ一。鉾u﹂。ub・︸ω。§も。N鴛。ρい。8<・藝・u・髪も﹄ひあ。。・。。。:。upu・落も.ま ︿非行﹀と解される。Ohー象<Ro訪髪壁卑や399B。﹃一旨。ぎ℃﹄。。。 ︵5︶ 鼠昇①一8乱。は、h臣富αq声およりも一層重いく非行Vと解されている︵Rωo。・一〇。欲く・一〇αω・U・ω・一8“やいぎ〇四, 一〇目分を﹁重度の﹂︿非行﹀として区別した。なお、︿非行﹀の程度の訳語については、第六章第二節二1注︵−︶参照。 巨o身琴ぎや鵠09ε。このうちh讐$⑳βく①が一般に﹁重大な﹂︿非行﹀と訳されていることから、本稿では、hΦgδ。 ︵6︶ 破棄院によれば、労働者の重大な︿非行﹀の存否と使用者の諸手当支払義務の存否とは直結したものであり、その間に裁 判官の裁量の余地がはいり込む余地はない︵ooo。・ぐ泳。・這墨O・oo﹂o象・マ8押oD。。・N斜口一。く・一8鈎Uあ﹂89℃﹂象︶。 N軌03お蕊・U﹂鶏斜H・甲℃・b。b。一︶、︿非行﹀の程度に応じて手当の一部のみの支払を認めるア︼ともできない︵ω。。・一〇Φけ その結果、労働者の行為が重大な︿非行﹀を構成するものの、未だ諸手当を奪うほど重大ではないとすることはできず︵uっ。。。 訟ヨ巴一8ぎqoo﹂8y℃・8曾oo9・鴇03一8yU・一8yoDoヨ5マ8︶。この意味からも、解雇をめぐる︿非行﹀の 程度の裁判所による評価は、それに応じた事案の柔軟な処理を可能とするものではない。 ︵7︶Ω6馨・﹃言。犀も乙いω ︵8︶ oo8﹂Nき<﹂30。・qoo﹂oいPつ睾oもちろん、使用者が客観的に重大な︿非行﹀に該当しない行為を就業規則に即 約についても同様である︵ωo。﹄o。冒暑﹂Sρ旨O℃﹂So﹂一レa訟︶。ROρ梓曽一ρ−や鵠o 事解雇事由として定めても、それが裁判所を拘束することにはならない︵oo。ρ8鷺﹃一=3PU■堕這鉛マお。︶。労働協 ︵9︶ ωoρo。︷曾﹂8斜旨ρ℃﹂8N﹂一﹂ぎS就業規則に、遅刻について三回以上の戒告がなされたときは解雇する旨の定 めがある揚合に、それに従ってなされた解雇を濫用とした原判決が破棄されたものである。 ︵−o︶ 以上の判例のほかにも、事実審裁判官による判断の置き換えの禁止について語る破棄院判例は多い。たとえぱ、O鶴。。.9. 474 懲戒処分法理の比較法的研究 ∬ ﹃ひロ巳①Pミ曽く注一8ど一隆O■国一8廿=,旨ま曾oooo■ マ8ごooop卜o軌ooβ一Sい”U■這Nω、一。刃℃■卜oN一 ︵12︶ oooo.ひ一聲∼お認一旨ρ℃■む刈駆。■F旨区oo 一〇ヨ鶏ω一8伊∪。一8鈎や親O.ωoρ撃融<●6Nど∪◎ω■むN一讐 ︵11︶ oooρま泳P一800り切ミト∼ロ。畠O一Ω。勺坐置巴R一 ℃、ミO ︵13︶ oo8●刈欲<﹂So。、∪・oo■一〇団o。一マω8 3 解雇権濫用理論による制約 懲戒としての解雇に対する裁判所の審査の可能性は、以上のほか、解雇権濫用理論によって与えられてきた。この 理論は、古くから学説.判例によって形成され、展開されてきたものであるが、労働法典も旧第一巻第一編第二三条 で﹁契約当事者の一方の意思による契約の解除は損害賠償を惹起することがある。﹂と定め、その他若干の規定を置 いていた。解雇権濫用理論の内容や、右の労働法典規定の沿革とそれをめぐる学説・判例の状況については、既にわ ︵−︶ が国でも詳細な検討がなされているので、ここでは立ち入らない。ただ、特にその重要な結論のみを示すならば、ま ず、この揚合に間題となるのは、解雇に伴う使用者の帰貴事由︵宣暮①︶によって、労働者に不当な損害が生ぜしめら れたか否かである。すなわち、解雇が濫用とされるのは、使用者が悪意︵冒8暮一9ヨ巴菅。島。︶ないし害意︵言富〒 身冒一.Φ︶、または非難すぺき軽率︵一緯酵まげ醇目呂一Φ︶によって解雇を行った揚合、あるいは協定や規則上の手 ︵2V 続に違反した揚合に限られる。また、そのような濫用解雇の要件およびそれによって生じた損害額は、労働者側が立 ︵3︶ 証しなけれぱならないとするのが、判例の基本的な立揚である。しかも、解雇が濫用とされる場合にも、そのこと自 体は解雇の効力を左右するものではなく、単に使用者の損害賠償義務を生ぜしめるにすぎない。また、解雇が公序規 475 け一 一橋大学研究年報 法学研究 14 定に反し、無効とされる場合にも、結局は損害賠償の問題に還元される。判例によれば、使用者による労働者の復職 ︵4︶ ︵蚤暮oσq声江9︶は﹁為す債務﹂であり、民法典第一一四二条によりその不履行は損害賠償に変質するからである。 いずれにせよ、懲戒としてなされた解雇は、それ以外の解雇と同様、解雇権濫用の問題として、裁判所の審査の対 象となりうる。しかし、それによって労働者にもたらされる救済は、右に指摘したように、その立証およぴ救済内容 において制限的なものであるだけでなく、その要件においても著しく厳格なものであった。たとえば、解雇の理由が 不正確であること、解雇に先立って警告がなされなかったこと、あるいは弁明の機会が与えられなかったことなどは、 ︵5︶ ︵6︶ ︵7v いずれも単にそれだけでは、解雇が濫用とされるためには十分でない。解雇権濫用理論は、確かに懲戒としてなされ た解雇についても裁判所による審査の可能性を開くものではあるが、懲戒としての解雇である.︸とに特別の意義を認 めるものではなく、そのことによって解雇権濫用法理そのものに伴う限界性が克服されるのでもない。 ︵1︶ 第三章第二節二注︵−︶の文献のほか、小西國友﹁解雇の自由e﹂法学協会雑誌八六巻九号一〇四頁以下、野田進﹁フラ ンス解雇法改正の法理論的背景−学説を中心として﹂阪大法学一一八・一一九号二三頁を参照。 ︵3︶ω。。﹄8睾<﹂。郵uあ﹂。質℃る。。9ω8る曾6く﹂。卸uあ﹂。罫℃トニ§・ ︵2︶ 手続の問題については、次節四で若干の検討を加える。 ︵4︶ 破棄院は以前から、法定従業員代表の保護規定違反の解雇を無効とし、その揚合に使用者に対して復職を命じうる.︸とを 認めていたが、同時にその不履行は損害賠償に転化するとし︵ωo。し置口這命・U・む畠・℃・蟄90QoP刈幕o・お罫曼ω・ 一〇紹マまざoooρおヨ胃ω一〇墨PψG郵や轟=︶、それ以降の賃金請求権を否定していた︵ωoρ軌撃︻一一一8♪U.ω. 制︵鐘益暮。︶を伴う急速審理︵蚕①み︶による命令を容認するに至っている︵oo。。﹂ど・ぎお蚕O・φら認・や“a︶。.一の 一〇罫︾畠館ω9﹄ど・ぎ一。茎qω﹂8♪やひむ︶。ただし、その後破棄院は、法定従業員代表の復職について、罰金強 点にっいては、中村紘一﹁諸外国の不当労働行為制度㈹フランスー従業員代表およぴ組合代表の使用者による反組合的行為 476 懲戒処分法理の比較法的研究 H ︵5︶ ωoρo一ロ岸一8い”U・oo﹂獣溌やωo。ただし、具体的事情によっては濫用解雇の成立が認められることもある。ωoρo からの法的保護法制の発展﹂現代労働法講座7︹総合労働研究所・昭五七︺一〇五頁に詳しい紹介がある。 ヨp冨一89U。oo、一89や鳶ざoooρboω融く、一〇鴇、Pψ一3ざPNOoo 第三節 懲戒処分をめぐる主要間題に関する判例の概要 ︵7︶ ωoP三濠ρ一89U◆一8y℃■ミO ︵6︶匂りo。﹂o欲く﹂3Pいρ℃﹂。ひo﹂︻﹂富舘 一 序説 と、判例を契機として生ずる懲戒をめぐる個別的間題についての判例批判を中心として展開された。しかし、ここで 本章のはじめにも指摘したとおり、フランスにおける制度説登場以降の懲戒をめぐる議論は、制度説に対する批判 そのような判例のすべてを網羅的に取り上げることは困難であり、その必要性もない。以下では、特に判例による懲 戒理論の基本的性楕と、フランスにおける懲戒理論の問題状況を把握するうえで重要と思われる点について、破棄院 判例を中心に若干の検討を加えることにする。そのことは、最近のフランスにおける使用者の懲戒権に関する立法的 規制の背景とその意義を理解するためにも、不可欠の前提となると思われるからである。 二 懲戒処分の形態 懲戒処分の形態のうち、懲戒としての解雇については、判例はそれを強いて懲戒権の行使としては構成せず、解雇 を労働契約上の解約権としてとらえることを前提とする伝統的判例理論の枠内でそれを処理していることについては、 477 一橋大学研究年報 法学研究 14 既に指摘した。従って、解雇が懲戒処分として就業規則等に定められ、あるいはその趣旨で行使されることは、判例 にとって、解雇そのものの要件や適法性の評価について格別の意味を持つものではなく、懲戒解雇の概念自体もとり たてて問題とならない。また、わが国のように、退職金の不支給という効果との関連で、懲戒解雇の概念が問題とさ ︵1︶ れることもない。 解雇以外の懲戒処分形態で、判例上最も頻繁に現われるものが出勤停止処分である。この出勤停止処分をめぐって は、かつて下級審判例の中にそれ自体を違法とするものが現われ、それに呼応して、学説の間にも、それを違法とし、 ︵2︶ あるいはその要件を厳格に解そうとするものが多数見られた。しかし、それに対して破棄院は、出勤停止そのものの ︵3︶ 合法性を肯定する立揚を一貫して維持し続けた。その理由として、破棄院は、労働法典上の罰金規制規定は出勤停止 ︵4︶ 処分には適用されず、そのような規定によって使用者の内在的懲戒権が奪われるものではないことのほか、特にそれ が就業規則に定められる揚合について、就業規則が労働者を拘束するものであり、しかもそれが労働監督官の審査に ︵5︶ 服するものであることを挙げていた。破棄院の示すほとんど唯一の制約は、出勤停止処分の行使にあたってはその期 間が特定さるれことを要し、期間の定めのない出勤停止処分は、実質的に使用者による労働契約の解約すなわち解雇 となるということにすぎない。 ︵6︶ 味を持つことになろう。 ︵−︶ ただし、懲戒としての解雇か否かは、後述する労働協約や就業規則に基づく懲戒手続の適用範囲をめぐっては、重要な意 ︵2︶o。島。一乙。冥鼠.ぎヨ馨のα①5。。①ぎし。。欲<■重Pu●○,ゑ。もる9↓葺。一く・。。。ぎ①﹄い塁=。軌。弘ρ喝・ま9 Fまま一円ユ99︿●oo色⇒oふ隷く﹂3ρいρワG軌曾目おo卸O,犀8畦“ρ菊こピ帥ヨ一器帥口a℃畦日雷目oαぎ一, ℃一ぎ巴おg一p﹄弩厨冥&①一一8hβ君巴ωρ葡魯ミ、ミミ&題憂wミ暴麟這軌避<o一・ρマNo。g。。・ 478 懲戒処分法理の比較法的研究 n ︵3︶。pロ琶.畦・罫窪.×一。昌ω・,慮﹃一帥巨・.①書9霧・一3一う・・ζ・9一①二ゆβ蚕・畳ω3量如2。蟄う ︵4︶ω。ρN3ぐ﹃一=。軌。レ望。軌p篭軌器。pa量一鐸u,ωも歩や軌参。・。ρ譲二。ひ。もρコ馨窒 ω捧o。げ。斜言帥ロ﹃一。。・g巨器帥冨阜o,○、這頓。。いマ。。旧ξg−o器pやN鵠g幹 轟O ︵5︶ω。。・む︷①<﹂峯∪・まωも・箸る8。曽暴邑盗upω。ま軌も。出一 ︵6︶ω8一¢﹃﹂昌まどミニくも’ま。・﹄。§一Ro壁帥も﹂。・一 三 懲戒処分の対象 1 懲戒処分の対象 と し て の 労 働 者 の ︿ 非 行 ﹀ 破棄院は、特に懲戒権の性格に関して、それが﹁企業の円滑な運営﹂という利益において行使されるものであるこ とを繰り返し述ぺていた。そのことは、逆に﹁企業の利益﹂を害するような労働者の行為こそが懲戒処分の対象であ るとすることが、破棄院の理解であることを推測せしめるであろう。しかし、既に指摘したように・それは実際には 使用誘機撃正当化し、同時に事実審裁判官の審査権限を制限するための論拠として用い髭ているにす暮い のであって、懲戒処分の対象を画定し、限定づけるための基準としては、必ずしも機能していない。むしろ判例にお いて懲戒処分の対象として問題とされるものは、より一般的な労働者の︿非行﹀︵♂暮Φ︶である。 この労働者の︿非行﹀をめぐ・ては、こ鷲で曇態し薮の判禦藷えて孕しかし・そ砦を丹念に 精査したとしても、おそらくは懲戒処分の対象としての︿非行﹀の意義や内容的な限界を明らかにすることは、著し く困難であろう。それは、およそ次のような事情による。 479 一橋大学研究年報 法学研究 14 第一に・フランス法上の.、囲㊤暮①.、概念一般について妥当するその特異性である。このア︶と自体は、既に多くの論 ぞレ 者によって指摘されているところであるが、特に懲戒との関連で言えば、それはほとんど労働者の行為の違法性ある いは非難可能性と同義に用いられており、懲戒処分の対象となる行為を客観的に特定するための基準とは必ずしもな しえない。 第二に、判例が問題とするのは、多くの場合に労働者の一般的な︿非行﹀であり、たとえば制度説の主張するよう な、民事的︿非行﹀とは区別された意味での懲戒的︿非行﹀ではない。つまり判例は、懲戒処分の対象の評価につい て、必ずしも他の義務違反と区別されるような規律・秩序違反をその統一的基準としてはいないように思われる。.︸ のことは、懲戒としての解雇については、その懲戒という目的に特別の意義を認めない判例の立場からすれば当然の 帰結であ髭・そ殻外の懲戒処分についても、判例はしばしば使用者による事業揚の規律の配握ついて語るもの れはむしろ使用者側の帰責事由の存在を否定することに意味があり、懲戒処分の対象を積極的に画定するため のものである。 働者の︿非行﹀の存否および程度であって、それは懲戒処分の対象上の限界性評価とは、形式的にも実質的にも別個 ある。すなわち、その揚合に問題とされるものは、あくまで解雇に伴う諸手当ないし賠償金不支給の要件としての労 第四として、労働者の︿非行﹀が問題となる事例の多くが、解雇に関するものであるという事情を考慮する必要が パ レ ない範囲でのみ、それが否定されるというにすぎない。 判例にとって、労働者の規則・命令違反は原則として︿非行﹀を構成し、何らかの理由で使用者の規制権限が及びえ 第三に、労働者のく非行Vの存否の問題は、しばしば使用者側の権限の範囲の問題に置き換えられる。すなわち、 の基準としては用いられていない。 曙“ 480 懲戒処分法理の比較法的研究 H とにより、判例の理解と問題点を検討することにしたい。 そこで以下では、特に懲戒処分の対象の時間的.揚所的限界と、労働者の権利行使との関係の問題を取り上げるこ た。 ︵−︶ 実際に、﹁企業の円滑な運営﹂が妨げられていないことを直接の理由として懲戒権行使を否定した判例は見当たらなかっ ︵2︶ たとえば○雁出p。いO。ミ・&w亀鴨覧ミq&き℃舞腕6籍では、特に第四章および第六章で、懲戒事由およぴ解雇事由に関する 膨大な数の判例を分類.塾理している。その他、多数の判例を分類・整理した文献として、>註ρU塁一卑卜轟ミ黛ミ恥導誤き恥 §8ミミ馬魯㌣§禽き勺貧﹃む雛などがある。 ︵3︶ たとえば、第四章第二節一注︵1︶に掲げた文献を参照。 ︵4︶ ただし、.︸の.一とは、解雇に関する事案において規律違反が問題とならないことを意味するものではない。たとえば、監 oDOO’Oo賞口<,一〇α♪いO,℃。一〇ひやH<●N顛 督者による命令の拒否が企業の円滑な運営を害する規律違反行為であり、重大な︿非行﹀にあたるとした事例なども見られる。 ︵5︶。ζp﹃①図・ω。ρ曾。<・まp一・ρ型ま。,一H、三Nざω。ρ一u簿﹂。Pい○塑一還・目ひ§8 ︵6︶ たとえば使用者による労働条件変更をきたす命令について、それが労働契約条件の本質的変更をもたらすものか否かが問 題とされる.。訟。。﹄。。睾一=裟ヒ・。。・まひも■轟・。。。る9■8§﹂SNヒ﹂虜レ菊も■a舞 2 労働者の︿非行﹀の時間的・場所的限界 判例によれば、労働者の︿非行﹀は、たとえ休憩時間中や就労時間外であっても、広く企業内の行為について認め られる。たとえぱ、休憩時聞中に会社食堂で同僚を侮辱したことを理由とする出勤停止処分について、その行為が職 揚外.労働時間外になされたことを理由に不当とした原判決を破棄し、その食堂が使用者の管理下にあるか否か、そ う誉すれば当募響覆用者の震下にあるか票を嚢すべきである乞姦護判決が窺・索国の判例 481 一橋大学研究年報 法学研究 14 における施設管理権と同様の理解を示すものと言えようか。 ︵2︶ ︵3︶ このほかにも、企業施設内での労働者の多くの行為が、判例によってく非行Vにあたるとされる。たとえば、就業 規則による禁止に反して会社構内に印刷物を持ち込むこと、使用者の信用を害するような文書を配布するア︶と、労使 ︵4︶ ︵5︶ 間の協定に反する内容のビラ貼りなどが、いずれも解雇または懲戒処分を正当化する︿非行﹀にあたるとされている。 これに対して、労働時間外に、しかも企業外でなされた行為については、判例は一面でそれを︿非行﹀と認めるア︸ とに消極的である。たとえば、非番の日に会社の電車に乗り合わせ、運転手に話しかけたア︸とを理由とする出勤停止 ︵6︶ 処分につき、当該労働者が使用者の権威下になかったことの故に濫用とした事例がある。しかし、多くの判例は、た とえ労働時間外で企業外の行為であっても、一定の揚合には労働者の︿非行﹀と評価されうることを認めている。た ︵7︶ とえば、労働者の競業、企業秘密の漏洩などのほか、企業外での犯罪やその嫌疑などが特に問題となる。また、企業 ︵8︶ 外での企業の信信を毅損するような宣伝活動が、重大な︿非行﹀にあたるとされた事例などもある。ただし、これら の企業外行為に関する判例は、その大部分が解雇についての事案に関するものである点に留意する必要がある。つま り、そこでは、先に指摘したような意味での労働者のく非行Vの程度こそが問題とされているのであり、また、しば 確かに諸手当を伴わない解雇を相当とする︿非行﹀の存否とその内容や、濫用解雇成否の具体的事情は明らかにしう しば間題の重点が濫用解雇の要件としての使用者側の帰責性の存否に移行する。従って、それらの判例によっても、 ︵9︶ るとしても、それを直ちに懲戒処分の対象としての︿非行﹀の内容や限界の評価に結ぴ付けることはできない。 ︵1︶ ω8■8目卑誘一3ρ戸ψ一〇頓9や&檜ωoρ88∼一翫9qψち鴇・や象も同旨。 ︵2︶ uりoρ8象o﹂8どqψ這ひρマ鴇o本判決は、工揚施設内への新聞の持込みと配布を禁止する就業規則の定め自体は 労働者の表現の自由を侵害するものではないとし、新聞三部を工揚内に持込んだことを理由とする解雇について、使用者の悪 482 懲戒処分法理の比較法的研究 H 意が示されていないことの故に、濫用ではないとしたものである。同様に、会社の乗合バスに政治的示威行動参加の勧誘を内 破棄した判例︵oo。。■峯ま<・一8ざPoり﹂頚ざやおN︶もある。これらの事案を見ても、破棄院による解雇権濫用の判断基 容とするビラを持込んだア︶とを理由とする解雇につき、それがあまりに厳しいとして会社に損害賠償の支払を命じた原判決を 準がいかに厳格なも の で あ る か が 窺 わ れ る で あ ろ う 。 ︵3︶ oo。。■二。。“む鋼U﹂S勲や象溌U■oD・6鐸℃乙まなお、本件は、従業員代表者についての裁判上の契約解除請求 ︵4︶ω。ρ軌四丘=3♪∪薗。D﹂。頓♪や8。。 に関する事案であり、重大な︿非行﹀の存在が認められ、請求が認容されたものである。 ︵5︶ このような破棄院の傾向に対し、下級審判例の中には、労働者の企業内での諸活動が使用者に何らかの損害を生じない限 り、それを理由とする解雇は濫用であるとするなど︵9唱曽突、9房亀3℃昌山.ぎヨヨ①㎝号寄目聲ご琶∼む象ヤU。9 ︵6︶。。。ρ雪。。﹃這軌Pu,○﹂。α。も,旨。 一〇ひ♪やい翠︶、それと異なる判断を示すものが少なくない。 一﹂誤る一。一一①奉=解爵Hp冨<一・冒くひ。9の巴慧ヒ、○﹂。Nひも■暴忌①D−廊×幕一盆①﹃㌧8日Φ一も﹂誌卑9 ︵7︶RuΦの℃p図・憲。蔓・冨<一Φ霞賃署§婁一。き。一一①身団即剛麟忌①;。三昌&28の‘二。8鼻韓留冨く巴こ’ρ℃ー一。ひい■ ︵8︶ ωoρ一一〇。¢GN卜。りP堕一〇謡”やいO“ ︵9︶ このほか労働者の重大な︿非行﹀は、判例上、従業員代表者についての裁判上の労働契約解除に関しても問題とされてき Ω一・巨碁ρ曽︼三⇒這N避U、ψおN♪やまo。 たが、現在ではそのような特別に保護された労働者について裁判上の解除請求をなすこと自体が否定されている。90留φ 3 労働者の権利行使と懲戒処分ーストライキをめぐって 労働者の権利行使が︿非行﹀とは性格づけられないこと、また、 たとえ︿非行﹀が存在しても、それを理由とする 483 一橋大学研究年報 法学研究 14 ︵1V 懲戒処分が公序規定に反しえないことは当然である。しかし、判例による懲戒処分に関する基礎的理解を前提とする 限り、ここに一つの問題が生ずることになる。すなわち、権利の濫用的行使、または権利行使に附随する︿非行﹀と 懲戒処分の関係である。このことは、労働者のストライキ権をめぐって最も顕著に現われる。 パこ 労働者が適法なストライキを行った揚合、使用者はそれを理由に解雇または懲戒処分をなしえない。また、一九五 〇年法第四条︵現行L五二一ー一条︶により、労働者の重度の︿非行﹀︵置暮。H。仁肖α。︶がある揚合を除き、ストラ イキは労働契約を破棄しないとされた結果、それに至らない程度の︿非行﹀を理由として、使用者は解雇をなしえな いこととなっ︵混。しかし、それによっても、ストライキに際しての労働者の︿非行﹀を理由に、解雇以外のより軽度 の懲戒処分が科されうるかという問題は、依然解決されていない。 この点について、労働者に重度の︿非行﹀があり、従って佼用者が解雇を行うことも許される揚合に、いわばその ︵4︶ 減刑措置として、解雇よりも軽度の懲戒処分を行使しうることは、一般に認められている。問題は、労働者の︿非 行﹀がそれよりも軽い揚合である。学説の中には、この揚合について、重度の︿非行﹀が存在しない限り、解雇はも ︵5︶ ちろん・それ以外の懲戒処分も行使されえないとするものと、それに至らない程度の︿非行﹀については解雇以外の 懲戒処分が科されうるとするものがあった。これに対して判例は、これまでのところ必ずしも明確な態度を示しては パさレ いないが、若干の興味ある判決が下されている。 ︵7︶ これらの判決は、判例による就業規則の理解に関して既に取り上げたものであるが、まず一九六八年一二月一六日 の紘灘では、重度の︿非行﹀とは性格づけられないスト中の職揚滞留を理由とする出勤停止処分について、使用者は ストライキ期間中労働契約の履行が停止されるために就業規則規定を利用しえない乙とを理由にそれを否定し、次い ︵9︶ で一九七二年二月八日の判決では、スト不参加者の入揚を阻害し、労働の自由︵菩震叡OΦ一.p︿p旨。.︶を侵害したア︶ 484 懲戒処分法理の比較法的研究 ∬ とを理由とする出勤停止処分を肯定し、更に一九七二年七月四日の判決では、スト中の集会参加を理由とする戒告処 ︵10︶ 分につき、再び使用者が就業規則規定を利用しえないことを根拠にそれを否定した。これらの判決が、先の問題につ いてどのような立揚に立つのかについての評価は分かれているが、まず第二の判決について、判例上一般に労働の自 由侵害が重度の︿非行﹀に当たると解されていることからは、それを著しい︿非行﹀には至らない程度の︿非行﹀に ︵11︶ 対して解雇以外の懲戒処分行使の可能性を認めた趣旨と解することは困難であろう。それに対して、重度の︿非行﹀ ︵12︶ の不存在が確認された第一の判決、および、短期間のスト中の職揚集会を重度の︿非行﹀と明示しない限りで第三の 判決が、結果的に懲戒処分の効力を否定したことは、破棄院が重度の︿非行﹀のある揚合を除いて懲戒権の行使を認 めない趣旨であるとの理解を促す。しかし、右破棄院判決が、わざわざ使用者は就業規則を利用できないと述べてい ︵13︶ ることからは、正当なストライキ権行使によって労働契約の履行が停止する結果、その一部をなす就業規則も停止し、 従って使用者は懲戒権行使の相当性評価についての裁判所の審査を免れるために就業規則を援用しえず、裁判所の審 査権限は完全なものとなるという趣旨と解することも可能であろう。しかし、右破棄院判決が明示的には懲戒処分の ︵14︶ ︵15︶ 相当性を問題としていない以上、そのような解釈についても疑問は残る。 する破棄院判例の原則的立揚の、一つの限界性を示すものであるように思われる。つまり、ストライキによって使用 さて、以上のような判例の曖昧な態度は、懲戒処分の相当性についての裁判所による審査をあくまで拒否しようと 者の懲戒権が消失しないことを前提としながら、そのような原則を貫く限り、ストライキ権保障の効果は、単に重度 の︿非行﹀が存在しない揚合の解雇からの保護に限定されてしまうからである。その意味で、先の破棄院判決の判断 は、右のような原則そのものには触れないまま、同時にそのような不都合な結果を回避するための、いわば苦心の論 理構成であったのではあるまいか。 485 一橋大学研究年報 法学研究 14 ω凶壼ざトa鴨き魯マいO♪β陣器帥Uoξ︸や8簿 ω, ︵5︶ 486 ︵−︶ 公序規定に反する懲戒処分は、単に濫用的性格を帯びるだけでなく、無効である。たとえば、従業員代衷者の解雇保護規 定違反の解雇につきωoρo一三一・一〇鴇・qoo・一濃∋や呂、ストライキを理由とする懲戒処分につきoooρ8ヨ騨一一〇箪U・ ︵2︶ ただし、このことは厳密な意味でのストライキについてのみ認められるものであり、たとえば単なる情宣のための労働時 ○﹂涙o。いや舘一などを参照。 間中の集会︵ωoρま巨巴む蕊・quり・ちV冊マ綾︶や抗議のための集会︵uo8・ごぎ<﹂鶏、ごPψぢ試㌧℃﹄ま︶はスト ︵3︶邦語文献として、石崎政一郎﹁同盟罷業と労働契約﹂比較法雑誌一巻四号六二頁、菊谷達彌﹁フランス法における同盟罷 ライキとしての要件を欠き、法的保護の対象とはならない。9ωぎ亀・ぎ鷺きやマ一ま9幹い巳。。。帥甘目堕℃b。N卑。。・ 業と労働契約﹂九大法学七号二一頁参照。なお、重度の︿非行﹀を理由とする解雇につき、学説上はそれが懲戒権に基づくも のか労働契約上の解約権に基づくものかについて争いがあるが︵90。一田ざP鷺き釣つ8押Opヨ包唇。ぎ℃る象魯ヨ菊 また、重度の︿非行﹀に基づく解雇も無効ではなく、濫用とされるにすぎない︵9ωぎ亀いトa鴨きや℃﹄鴇︶。 谷達彌﹁争議行為と懲戒解雇ーフランス法の揚合﹂九大法学一三号四五頁︶、判例上は懲戒権の行使としてはとらえられず、 ︵ O 8 ■ 一 ・ 昌 一 〇 o幹 β仁90 しo 這ooρマ一8 4︶ o■ 盆 < ’一 ご い ρ勺 〇 ひ一 ﹃ 一N 。ω ひ玄 ω四く四江oき○訂o﹃︿簿一〇μmoqのuりoρま鳥ひρ一〇αQo、 U。oo、一8Pマω一〇〇 ωoo■ま念ρ一8Qo一〇,ω■這ひP℃・い一〇〇 前節三2参照。 ■oo欲<。一ミρ∪■一〇認”℃,aひ ρ高一9一,一SN曽いρ℃。ら蕊、=ー旨&“ Ohω言即ざトa鷺魯♪サトoNoooけω■ 一〇N曾=・一M轟α轟 ︵11︶ 頷諒の一ΦさZo器8霧ωo。■鼻一9一り一〇N9いρ型 ︵12︶ ︵13︶ ω曽く碑ざき209000ロoooooρoo欲く、一〇Vρ∪・一〇刈卜o層 ℃、ひ鴇 ︵10︶ ︵9︶ ︵8︶ ︵7︶ ︵6︶ uo 〇〇 uり 懲戒処分法理の比較法的研究 H ︵14︶ 頴一鰐一9魯も貰は、.一のような解釈も可能であることを指摘する。このような解釈は、破棄院が、不文の懲戒権につい ては裁判所の審査権限は完全なものであり、それは懲戒処分の相当性評価にも及ぶとする制度説の主張に依拠していること、 およぴ、上記の二判決において、事実審裁判官によるそのような相当性評価を破棄院が暗黙のうちに承認したことを前提とす れている。Oh閃R騨ロ9やひoogF℃●這oo9ω∴閃oβ霞“qψ一〇〇〇ρマ頃一 る。しかし、ストライキによる労働契約およぴ就業規則の完全な停止という理解については、近時、有力な批判がなげかけら ︵15︶ 更に第三の解釈も可能であろう。つまり、上記の二判決で問題となったいずれも短時間の職揚滞留および職揚集会は、ス トライキに随伴し、それと密接に結び付いたものであり、従ってそのような随伴行為に対する制裁は、実質的に適法なストラ イキ権行使そのものに向けられたものと解されたのではないかという理解である。そうだとすれば、就業規則について語る判 示部分は、単に、その揚合にも就業規則規定を援用して懲戒処分を正当化しようとする使用者側の主張を否定するための論拠 にすぎないことになる。 四 懲戒手続 第二章で指摘したように、フランスの私的企業において懲戒手続が定められることは従来必ずしも一般的なことで はないが、特に公共部門の企業を中心に、人事規程ないし就業規則に懲戒手続に関する規定、特に懲戒委員会の制度 が定められることが多く、また、一部の全国・地域協約にも、同様の規定や懲戒をめぐる紛争の段階的処理手続を定 めるものがある。このような懲戒手続をめぐっては、特に懲戒委員会手続に関して、規則ないし協約の解釈問題とし て、あるいは手続違反の懲戒処分の法的救済の問題として、裁判上争われることが少なくない。それに対して判例は、 畠︵1︶ 原則的には裁判所による広範な審査権限を容認してきた。 懲戒手続に関する裁判所の審査権限については、まず規則・協約上懲戒委員会への提訴が定められる揚合の裁判所 487 一橋大学研究年報 法学研究 14 の管轄権限の存否の問題として争われる。しかし判例は、そのような定めのいかんにかかわらず、裁判所の管轄権を 広く認めるという立揚を堅持してきた。すなわち、労働審判所の管轄権を定める労働法典旧第四巻第一条︵現行L五 一一ー一条︶は公序規定の性格を有し、協約や規則によってそれを制限したり、懲戒委員会などによって置き換える ことはできないとしたのである。その結果、判例は、そのような機関による懲戒措置の法的評価は裁判所を拘束する ︵2︶ ︵3︶ ものでないとし、また、協約や規則上懲戒委員会への提訴が定められる揚合にも、労働者はその手続を経ることなく、 ︵4︶ またはその手続の進行中であっても直接裁判所に出訴しうるとして、その訴願前置的機能を認めない。 このようにして判例は、裁判所の管轄権を前提として、懲戒手続の間題についても一応は審査可能性を容認するわ けであるが、実際にはそのことは、特に手続違反の効果と救済内容についての判例の態度によって、懲戒処分の手続 的保障の意義を大きく減殺する結果となっている。 労働協約や就業規則によって定められた懲戒手続を履践せず、または暇疵ある手続によって行使された懲戒処分は、 判例によれば、当然に濫用的性質を帯ぴることになる。判例はその揚合に、使用者の﹁悪意﹂や﹁非難すべき軽率﹂ ︵5︶ などをとりたてて問題としない。しかし、そのことは、確かに当該処分を濫用とし、使用者の損害賠償責任を惹起す ︵6V るものではあっても、その無効までをもたらすものではない。従って、労働者としては、手続違反の懲戒処分によっ ︵7︶ て生じた損害を立証しなければならず、それがなされない限り、結果的には何らの救済も得られないことになる。 このようにして、その違背に伴う効果においてその意義を制限された懲戒手続は、次のような判例の理解によって、 更にその意義を失うに至る。 まず第一に、懲戒処分が手続違反とされる揚合に賠償されるべき損害とは、使用者の手続違反によって直接生じた もの、ないしはそれと因果関係にあるものでなければならず、仮に労働者の側に労働契約の継続を不可能とするよう ︵8︶ 488 懲戒処分法理の比較法的研究 H な重大な︿非行﹀があるときは、そのような因果関係が存在しないものとして、救済が否定される。 ︵9︶ 第二に、懲戒手続に関する定めは、使用者が裁判所に対して、民法典第一一八四条に定める裁判上の契約解除請求 を妨げるものではない。これによって使用者は、はじめから懲戒手続を回避しながら労働者を解雇し、あるいは、手 ︵10︶ 続違反が争われた訴訟において、右の反訴請求を行なうことによって自己の貴任を免れるという可能性が開かれるこ とになる。 以上のように、判例は、懲戒手続について、その違反の効果と救済内容のみならず、その実際の履行の必要性につ いても消極的能度を維持することによって、その意義を極めて限定的なものとしたのであり、そのことが、近年にお ける立法的改革の一つの大きな焦点となるのである。 ︵−︶懲戒手続に関する判例の状況については、特に次の文献を参照。9夢ρマお簿ヨ騨⋮︸や&恥g。。こ三器陣一〇旦い ︵2︶ooop一〇〇。叶﹂濃。。﹄u齢oo﹂3P℃■N。。るopN轟o。梓■一8ρu■oo﹃一8ρやまい や一章oけω■UU①ぞ欝×萄ひ一厨巴Φき8goN一やま簿。。. されず︵ooo。、δ09﹂3。。も︾ミ’︶、また、そもそも懲戒手続に服すぺき制裁としての性格を有するか否かについても、裁 ︵3︶ たとえば、懲戒委員会が降格処分を相当としたのに反して使用者が解雇を行った揚合にも裁判所は同委員会の意見に拘束 ︵4︶oD。ρちヨ霧一3いも﹂拓oり。ρ峯目賀の這ヌu■oo﹂鶏ω”マ&。。 判所は懲戒委員会の判断とは別個に、独自の立揚から評価することができる︵ωoρ撃03一8ρ愚も㌣︶。 ︵5︶uりo。﹄ε雪<﹂3Pu甲o。■一。u。も,象N一ω。ρG嘗一ソ一3Po﹂3。㌧℃,蟄冷。。。。’q。g﹂8ρいρb■一8一﹂一, おO= ︵6︶ oりoo・No。ヨ霞ω一8ρqω﹂8ρや軌象は、協約に基づく懲戒委員会に構成上の暇疵がある揚合に、その意見に基づい て言渡された解雇は、たとえ使用者の詐欺的策動︵ヨ睾8≦①hβ区巳2器︶が主張されていない揚合であっても、濫用の性棺 を示すものであるという。 489 一橋大学研究年報 法学研究 14 ︵7︶ uうoρoヨ四閉一8一こ・Oマむ9一ダ9は、銀行の職員規程に基づく懲戒委員会手続の不履行に関して、この旨を明 り、その効果も一般の濫用的解雇と異ならない︵注︵5︶の判例参照︶。 言する。また、判例上しぱしば問題となる労働協約上の手続に反してなされた解雇も、判例上はあくまで濫用とされるのであ ︵8︶ oりoρ応。O嘗昌むひ9旨O■型6ま■Hく.=o。︸ωoo’ひす暑・一まざU■oo■む籍、マ鴇o。 ︵9︶ω8﹂い昌o<●一Soこ’ρ型一。No﹂<●ω三 ︵10︶ ωoρ賠ヨ碧u一8ρ一.ρ劉一89目噸一一Nま“ωoρ刈oo“一8♪∪,ω、一8U”マ一〇〇。 第四節判例の評価と批判 一 判例の基本的理解とその批判 以上で検討した懲戒処分に関する判例に対しては、まずその基本的理解をめぐって、多くの評価と批判が加えられ たが、そこで共通に指摘されたものは、判例における理論的一貫性の欠如であり、制度論的理解と契約論的理解の混 溺である。 破棄院が、一九四五年判決以降、使用者の﹁内在的懲戒権﹂について語り、たとえ労使間の事前の合意や明文規定 の存在しない揚合であっても、使用者はそれに基づいて懲戒処分を行使しうるとしたことは、確かにその限りでは制 ︵−﹀ 度説的理解を示したものと言えるであろう。仮にそのことが、判例が全面的に制度説に依拠したことを意味するので あれば、当然に右の﹁内在的懲戒権﹂は解雇を含む懲戒措置すべてに妥当するはずであり、また、それは裁判所によ る広範なコント・iルの可能性へと結び付くはずであった。ところがその後の判例の展開を見る限り、判例による制 ︵2︶ 度説への依拠の意味は、.こく限られたものであることが明らかとなる。第一に、判例のいう使用者の﹁内在的懲戒 490 懲戒処分法理の比較法的研究 H 権﹂とは、その語自体から推測される一般的内容とは裏腹に、実際にはもっぱら明文規定のない揚合の出勤停止処分 を根拠づけ、あるいはその一般的な合法性を補強するために持ち出されたにすぎない。懲戒処分の重要な一形態であ る解雇については、判例はあくまでそれを労働契約上の解約権によってとらえる伝統的な解雇法理の枠内で処理した のであり、それを懲戒権によって理論的に構成することもなかった。第二に、懲戒処分についての裁判所によるコン ト・iルも、極めて限定的なものであった。懲戒としての解雇が、あくまで使用者の解約権行使としての観点からの 限定的意味において裁判所の審査に服するとされただけでなく、それ以外の懲戒処分についても、それが少なくとも ︵3︶ 就業規則の定めの範囲内で行使される限り、その定めは当事者の法に代わる合意の内容として裁判官をも拘束し、裁 判所による審査は懲戒処分の相当性や適宜性の評価には及ばないとされたのである。そこでは確かに、懲戒権の目的 の喩越が一つの留保条件として述べられてはいる。しかし、そのことは、実際には裁判官による懲戒処分審査の可能 ︵4︶ 性を拡大するものではなく、むしろそれを制約するための論拠として機能するものであった。 このような判例の基本的理解に対しては、多くの学説によって、それは一方で懲戒を基礎づけるために契約を放棄 ︵5︶ し、他方で裁判官によるコント・ールを狭めるためにそれに立ち帰るものであるとの批判が加えられた。また、判例 による﹁内在的懲戒権﹂への言及は、単に、明文の規定が存在しない揚合であっても、法律によって罰金の手段を奪 われた使用者に対し、それと同等の柔軟性および効率を持つ制裁を自由に用いさせようとしたにすぎないとの指摘も ︵6︶ ︵7︶ なされた。かくして、破棄院が制度説、契約説のいずれの立揚に立っているかは明らかではないとし、あるいは、破 ︵8︶ 棄院の基本的立揚はかつての契約説にほかならないとの評価もなされることになる。 しかし、判例に加えられるべき批判は、単にその制度論的理解と契約論的理解の混濡にのみあるのではない。オー リエの言うように、たとえ懲戒権が契約に基づくものと解しても、裁判官がそれをコント・iルされた権利とするこ 491 一橋大学研究年報 法学研究 14 とを欲するのであれば、契約に基づく法としての就業規則規定の公序への適合性について、積極的にそのコントロー ルを広げるであろう。その意味では、判例における間題性の核心は、むしろ、使用者に対して企業運営についての絶 ︵9︶ 対的権限を承認し、可能な限り裁判所の介入を抑制しようとする判例の最も基本的な態度にこそある。そのことは、 判例による使用者権限の基礎が、種々の娩曲的表現にもかかわらず、まさに企業の所有権にあるとの評価を促すこと にもなる。 ︵n︶ ところで、右のような判例に対する批判は、一面において、制度説の持つ一つの実際的な限界性を示唆するもので あるように思われる。すなわち、制度説は使用者に対して内在的懲戒権を承認すると共に、それが厳格な理論的制約 に服するものであることを主張した。しかし、制度説がいかに懲戒権の制約を強調しようとも、それが実際に裁判所 による十分なコント・ールに服さない限り、制度説は単に契約法理による枠を越えて使用者の懲戒権を根拠づけ、使 用者の権限を拡大するための理論として機能するにすぎない。右に見た判例の展開は、まさにそのことを実証したと 言いうるであろう。 ︵1︶ Uロβp9∪・Oo。一睾9や命oo ︵2︶o。一畠ざ∪﹂899﹃。昌も●NN。一ξ96器p寒ミミ職醤讐ミ警之舞﹂8Nも■§ ︵3︶ このことが、民法典第一一三四条に依拠したものであること、および判例が一貫して就業規則を契約によってとらえる立 揚に立っていることについては既に指摘した。これに対し、就業規則に定めのない揚合またはそれを超えて懲戒処分の行使が を示していない。なお、前節二3参照。 なされた揚合の裁判所による審査の範囲については、そのような事案がまれであることもあって、判例は必ずしも明確な態度 ︵4︶ この点については、最近に至るまで下級審判例の中に破棄院の判断に抵抗するものが多数存在したことは既に指摘したが、 学説の中にも、︿非行﹀と制裁の不均衡はそれ自体が懲戒権の喩越であるとして、裁判所が積極的に均衡性の評価をすぺきこ 492 懲戒処分法理の比較法的研究 H とを主張するものが少なくない︵国三Pマ£9盟畠ざ写8簿3一。留蟹冥ε〇三〇畠年ひ箒。・雷9ぎ嵩色畳讐昌巴8壁器− ︵5︶ ○一一一〇びや一鵠 切暑p℃■a90島=o琶oゴO・○、一8ン℃、舘∋○=[¢き U。oo■一8ざマU8 使用者の権威行使を弱めることの故に、それに懐疑的な見解も存在した︵9琶勲ついS︶。 鳴&留の壁耳窃85巨。。窃qω■這NPやNミ︶。しかし一部には、そのような均衡性の評価自体が困難なものであること、 ︵6︶ 即臨①ン甘壁い勺oロ<oマ℃画ぼ凶ヨo鉱巴簿色80岳gユ窃 boおo昌器伊∪■ω■一〇〇〇ρサ高o叶ω■ OoぎpU◎ω●一〇〇〇ρやミO魯幹 ︵7︶ ︵8︶ O臣①びや一〇ごO昌三〇ロ一ト.馬ミ、魯篭鷺㌧的s融蝕、ぎ魯、恥㌧ や一軌㌧℃●89ω■ O臣Φ5U●ψ一8ざや8Nオーリエは、その限りでは、 契約か制度かは真の論点ではないという。 ︵10︶ ︵9︶ 二 固有の懲戒法理の不存在 判例における懲戒処分に関する基本的理解の一貫性の欠如は、具体的紛争処理に際しての、懲戒処分に固有の統一 的な法理的基盤の欠如となって現われる。もとより判例に対して学説に対すると同様の意味での懲戒法理を期待しえ ないことは当然であるが、懲戒処分の実際的意義や機能に則した統一的法理という観点の欠如は、しばしば個別的な 問題処理の妥当性についての疑間を惹起することになる。 このことは、解雇について最も顕著に現われる。判例によれば、懲戒としてなされた解雇もあくまで使用者の解約 権の行使としてとらえられ、その法的評価についても他の解雇の揚合と異なるものではない。その結果、そのような 解雇について懲戒権行使としての要件や限界性ははじめから問題となりえず、使用者は、労働契約上の解約権に基づ き、労働者のあらゆる︿非行﹀を理由に有効に解雇をなしうるのである。そしてこのように自由な解約権が承認され ︵1︶ 493 oo 一橋大学研究年報 法学研究 14 ることは、解雇以外の懲戒処分についても重要な意味を持つことになる。判例がそれらの懲戒処分についても裁判所 のコント・ールを極めて限定的に解していることは既に見たとおりであるが、解雇を含めた懲戒処分の統一的把握と それに基づく懲戒処分の相当性・均衡性の要請の欠如は、使用者が直ちに解雇という最も重大な措置に訴えることに よって、そのようなコントロールすら無意味にすることを可能にするからである。いずれにせよ、判例の認める自由 な解約権を前提とする限り、使用者は強いて懲戒権に拘泥する必要はない。その意味で、﹁懲戒権は、一方的な解約 ︵2︶ 権が消滅したときにはじめて出現しうるものである。﹂との指摘は、そのような判例の状況を端的に示すものであり、 ︵3︶ ましてや、契約法と区別された固有の懲戒法を語ることは無益ですらあった。 判例において特自の懲戒法理という視点が存在しないことは、このほかにも多くの具体的問題処理に対して影響を 及ぼすことになる。たとえば、懲戒処分の対象としての労働者の︿非行﹀の独自の性格やその範囲は不明確なままで あり、懲戒処分を限界づける機能をほとんど果たさない。また、懲戒手続に関しても、その現実的な意義と機能に則 した法的救済は否定される。このような点からしても、判例について固有の懲戒法を語りえないことは明らかであろ うo 以上のような判例の状況は、最近の行政裁判所による公務員の懲戒処分に関する判例と比較しても、際立った対照 を示すものである。すなわち、公務員の懲戒処分については、既にコンセイユ・デタ︵Oo9亀α.蝉緯︶は制裁と ︵4︶ ︿非行﹀の均衡性を評価する態度を示しているのであって、私的企業における懲戒処分に関する破棄院判例の状況は、 ︵5︶ それとの対比においても学説の批判を一層強めることになった。 ︵−︶確かに使用者は労働者の︿非行﹀の程度に応じて一定の手当の支払を義務づけられるほか、濫用解雇法理による制約を受 けるが、それが解雇の無効をきたすものではなく、すべて損害賠償の問題に還元されるものであること、また、その評価にお 494 懲戒処分法理の比較法的研究 ∬ ま甘一一■一〇Noo㌧ いて解雇の懲戒処分としての相当性・適宜性が問題とならないことは既に指摘したとおりである。その意味で、 使用者は、 定の制約を伴うとはいえ、懲戒の趣旨であると否とを問わず、自由な労働契約解消の権利を有していた。 ︵3︶u①。。℃貴、頴一誘醇﹂oe。N︸℃﹂o ︵2︶9馨昌琴遅ξ9−oの8る。Φ自‘℃■ミ。 ︵4︶ 9湧Φ凶一α.犀夢o首ロGNo。︾隷“§亀籍砺“魯睦§恥§G§動ミ馬織.簿ミ㌧GNo。りやN&¶Oo房。=α、団茸㌧ ︵5︶oり一畠ざ∪●ooし。N℃、℃・卜。Nω 淘ミ§篭魯防儀8駐§偽軋ミq§雛篶叙、禦ミ、一窯oo︸℃■O観 章六章 懲戒処分をめぐる立法的規制の展開 第一節 従前の法状態と立法的規制の要請 フランスにおける使用者の懲戒権限は、制度説を中心とした学説による懲戒法理の展開にもかかわらず、判例上は、 ︵1︶ ほとんど実質的な法的制約を伴わない放任状態に置かれてきた。このことは、特に以下の点において顕著に現われる。 第一に、比喩的意味での﹁罪刑法定主義﹂の不適用である。従来の判例によれば、使用者はたとえ明文の規定が存 在しない揚合であっても懲戒処分を行使できるのであり、また、懲戒事由としての労働者のく非行Vについても、明 確な評価基準や限界は存在しなかった。使用者はそれをほとんど一方的に決定しえたのである。 ︵2︶ 第二に、懲戒処分と︿非行﹀の間の比例原則の不存在である。判例は、一貫して懲戒処分の相当性評価の問題につ いての司法審査を拒み続け、その結果、使用者は広範な懲戒処分行使の自由を保持し、しばしば苛酷な懲戒処分が放 置されることになった。 495 一橋大学研究年報 法学研究 14 第三に、手続的保障の不完全さである。労働協約や就業規則による懲戒処分の手続的規制は決して一般的なもので はなく、しかもそのような規制についてさえ、違反についての救済はごく限られたものであり、使用者は一定の揚合 にはそれを回避することも可能であった。 さらに、このような判例の下においては、懲戒処分法理を論ずることの意義そのものが限られたものとならざるを えない。判例が使用者の自由な解雇権を前提としている限り、そこに独自の懲戒法理が妥当すべき余地のないことは 既に指摘したが、そのことを別としても、懲戒権の法理的制約といえども、結局は裁判所による積極的な司法審査に よって実現されるほかはない以上、そのような判例に対する批判もまた、懲戒処分法理の具体的内容以前の間題とし て展開されざるをえないからである。 ︵3︶ 以上のような使用者の懲戒権限をめぐる法状態の下で、大方の間題関心が次第にその立法的規制の要請へと移行し ていくことは、いわば当然の成り行きであった。そのことはしばしば、実質的な法的規制を受けないという意味で事 実上の権限にすぎない懲戒権︵娼2ぎ冒eの。首ぎ巴器︶から、法的規制を伴い、従って法的な権利としての懲戒﹁権﹂ ︵費o詳象豊喜轟一お︶への発展として説かれたが、それが具体的には右に指摘した判例状況の克服を意味することは ︵ 4 ︶ 明らかであろう。そしてこの立法的規制の要請は、一九七三年の解雇規制法により部分的に実現するところとなり、 更に一九八二年の法律によって、懲戒処分全般に拡張されることとなった。 ︵1︶ q,困<RPU,Oり隆一SP℃■ω9ω∴Oo冨Pqoo。一〇〇。ρ℃、旨9U①も賀鳶ひ一厨。q一①ン8ヨo卜∂一やNOo3∴ωo轟N芦℃酔二 ︵2︶ このことと関連して、判例上は、懲戒処分形態相互間の制裁としての段階性も、明確な形では存在しなかった。特に解雇 U皿℃o=<o一﹃ωo犀<oH巴コ<o話仁5α8岸色し。o首一一一蚤冒ρ∪,○。一〇〇〇押℃■&一①けω■ については、たとえそれが懲戒処分としてなされた場合であっても、判例上はあくまで労働契約に基づく解約権行使として処 496 懲戒処分法理の比較法的研究 H こなかった。 理されたのであり、懲戒処分としての一般的な要件や、他の懲戒処分形態との関連における相当性評価も、一切間題とされて ︵3︶ 制度説登揚以降のフランスにおける懲戒処分法理は、どちらかと言えば停滞し、必ずしも顕著な展開を示していないよう 第二節 一九七三年法による解雇規制 ︵4︶Ro弩毘岩量ξ。昌−o器・b①①3も。NNgo一一一gも﹂ま①訂, に思われるが、それは、制度説の影響力もさることながら、以上のような判例の状態にも大きな原因があると考えられる。 − 序説 期間の定めのない労働契約の解約に関する一九七三年七月二二日の法律︵現行労働法典L一二二ー四条以下︶およ ぴ同年八月一〇日のデクレ︵現行労働法典R一二二−一条以下︶は、それまでのフランス解雇法制に大幅な改革をも パ レ たらした。この改革は、特に雇用保障の観点から、労働組合の要求や国際的動向を背景として実現されたものである が、同時にそれは、使用者の懲戒権の間題に対しても直接・間接の影響を及ぼしうるものであった。右の法改正につ いては、既にわが国でも詳細な紹介.検討がなされているので、ここでは、本稿のテーマとの関連で必要な範囲で、 パこ その内容と意義および懲戒法理への影響について検討を加えるにとどめたい。 ︵−︶中村紘一﹁フランスにおける一九七三年七月一三日の法律による解雇法改革の研究﹂比較法学一〇巻一号九一頁以下参照。 ︵2︶中村.前掲論文のほか、保原喜志夫﹁フランスの解雇の法理に関する一考察﹂日本労働協会雑誌一八九号二頁、山口俊夫 日本労働法学会誌四三号一九〇頁、野田・前掲阪大法学一ニニ号一頁などを参照。 ﹁フランスの新しい解雇保護法ー解雇正当事由説の採用﹂日本労働法学会誌四二号一八八頁、同﹁フランスの新解雇保護法﹂ 497 一橋大学研究年報 法学研究 14 二 解雇法改正の内容とその意義 − 解雇正当事由の要請 一九七三年法による解雇法改正のなかで、ここでの関連で最も注目されるものは、期間の定めのない労働契約の揚 合の解雇について新たに一種の正当事由が必要とされ、しかもその評価が明確に裁判官の権限として規定されるに至 った点である。すなわち、使用者は、労働者による書面の要求に基づき、解雇の﹁現実的かつ強度の事由﹂ ︵冨o謡 一。ω8島3泳色霧魯器ユ①拐窃︶を開示する義務を負い︵L一二二ー一四ー二条︶、また、使用者の主張にかかる解雇 ︵−︶ ︵2︶ 乳知︶。しかし・改正法は﹁現実的かつ強度の事由﹂について一切の定義規定を置いておらず、その具体的な意義や 事由の﹁現実的かつ強度な﹂性格を評価する権限は、裁判官がこれを有するとされたのである︵L一二二−一四− 内容の解明は、すべて法解釈の手に委ねられることになった。ここでは、この点に関する主要な問題について触れる にとど め る 。 まず第一に、解雇事由が﹁現実的﹂なものであることが要請されることによって、理由のない解雇はもちろん、理 ︵4︶ 由が不正確な解雇やそれが口実にすぎない解雇も、その適法性を否定されることになるであろう。.一れによって、従 来、そのような揚合にも濫用解雇の成否のみを問題とし、使用者側の帰責事由が立証されない限りその成立を否定し ︵5︶ てきた判例が、もはや維持されえないことは明らかである。 第二に、解雇には﹁強度の事由﹂が要請され、それが裁判官の評価に服するとされたことにより、これまで、解雇 の相当性判断について、事実審裁判官が自己の評価を使用者のそれと置き換えることを禁止してきた判例は、その変 更を余儀なくされた。特に労働者の︿非行﹀を理由とする解雇について、たとえ労働者の軽度の︿非行﹀であっても ︵6︶ ︵7︶ 498 懲戒処分法理の比較法的研究 n 解雇を適法とするには十分であるとして、︿非行﹀の程度と制裁としての解雇の均衡性評価を拒否し、︿非行﹀の重大 性をもっぱら解雇に伴う諸手当の要件にのみかかわらしめてきた判例は否定され、裁判所は労働者の︿非行﹀が﹁強 度の事由﹂に該当するか否かという観点から、︿非行﹀と解雇の均衡性を評価しなければならないことになっ極︶。 しかし、問題はそのような﹁強度の事由﹂に該当する労働者の︿非行﹀、すなわち強度の︿非行﹀が、従来のく非 行Vの程度についての概念といかなる関係にあるのかである。この点については立法の当初から争いがあったが、現 在では学説の多くと判例は、それによって従来の重大な︿非行﹀と軽度の︿非行﹀の間に新たなカテゴリーが挿入さ れたと解している。それによれぱ、労働者の︿非行﹀は、その程度に従い、重度の︿非行﹀︵♂暮Φ一8a。︶、重大な ︵ 9 ︶ ︿非行﹀︵h帥目陣。σq門帥く。︶、強度の︿非行﹀︵塗暮①器ユ2器︶、軽度の︿非行﹀︵貯耳o一醤酵o︶の四段階に区分され、解雇 が適法とされるには、重大な︿非行﹀である必要はないが、軽度の︿非行﹀では足りないことになる。 いずれにせよ、一九七三年法による解雇法改正によって、裁判所は、労働者の︿非行﹀を理由としてなされる懲戒 としての解雇について、その︿非行﹀の重大性を﹁強度の事由﹂の観点から評価する権限を有し、またその義務を負 うア︶とになった。懲戒としての解雇と︿非行﹀との間の均衡性についてのコント・ールを拒否してきた判例は、根本 的な変更を余儀なくされたのである。 ︵1︶ 、.。蝕ロロ①︵、︶ωひ同凶。島。︵。。︶・.の訳語としては、﹁由々しき事由﹂︵山口・前掲論文︶、﹁重大な事由﹂︵中村・前掲論文︶、﹁著し より望ましいことではないが、..ω。幕長.、の語がこの後に触れるように労働者の︿非行﹀の程度を示すためにも用いられてお い事由﹂︵野田.前掲阪大法学一二二号︶など多様に訳出されている。一つの原語について多様な訳語が存在することはもと り、しかもそれが=︷費ロ一①一。一一﹃︵一〇..︸..h窪8σq田<。..マ..h窪3。り豊窪器..廿、、﹃雲3一粛曾。.、め順に段階的なものと理解されているこ とから、本稿ではそれらを強いて﹁重度のく非行V﹂、﹁重大な︿非行﹀﹂、﹁強度の︿非行﹀﹂、﹁軽度の︿非行﹀﹂として区分し、 499 一橋大学研究年報 法学研究 14 それに伴って、.畠島o器旨霧o..も﹁強度の事由﹂と訳出することにした。 ︵2︶ ただし、本条は、経済的理由による集団的解雇︵L一二二−一四−五条︶、通常一一人未満の労働者を雇用する使用者に よる解雇︵L一二二−一四−六条第一項︶、およぴ勤続一年未満の労働者の解雇︵L一二二ー一四−六条第二項︶には適用さ ︵3︶本条は、L一二二−一四ー二条と異なり、すぺての解雇について適用される。 れない。 ︵4︶ 学説上、現実的事由とは、﹁実在し、かつ明確な事由﹂︵譲誇の凶9℃﹂ま︶、あるいは虚偽の排除と具体的かつ客観的性格 を意味するもの︵国9冨脇亘客ρ一U①5ロo匡23欝耳o帥σ8低9自08霧ρU﹂鶏♪Oげ﹃o戸℃﹂8︶とされる。また、 それは、その存在が客観的に証明されることのできる事由であり、解雇の真の事由でなけれぱならないともされる︵控く段o、 留く彗9やα田︶。なお、中村・前掲論文=一七頁以下参照。 ︵5︶ξg−9雪窃o目Φ聾ρ寓姦o屋。9一一。窪。凶聾。暮帥賃p<。冨5一〇一倉冨宣=。梓一ミ辞qω﹂sQも﹂o∋ωo目。什。斤p U■一鶏♪O耳oF℃。一〇押bひ諒巴R︸や一署簿幹 ︵6︶ξ。㌣9色くω。目Φ聾pu■。。﹂ミいも■お。’やω。∋濯一匿。﹃も﹂。。。。①叶9 ︵7︶ ﹁強度の事由﹂は、一般に、労働者個入に関するものと、企業の組織活動に関するもの、すなわち経済的理由に関するも の︵経済的理由の解雇については、一九七五年に別個の立法がなされた。現行L⋮二−三条以下︶とに分類され、前者は ωop昌簿卑ρUー一S♪078戸や一ε9p さらに、労働者の肉体的不能や職業上の不適楕を理由とするものと、労働者の︿非行﹀を理由とするものに分けられる。R ︵8︶ 勺象。。巴①び℃■一8 ︵9︶詳しくは、中村・前掲論文二一二頁、野田・前掲阪大法学ご三号一三頁以下参照。 2 解雇手続の保障 一九七三年法による法改正のいま一 つの大きな特徴は、これまでもっぱら労働協約や就業規則に委ねられ、法律上 500 懲戒処分法理の比較法的研究 H はほとんど無視されてきた解雇手続に関しても、一定の保障を新設したことにある。 新たな法規定によれば、使用者はまず、解雇を企図した揚合には、決定に先立ち、呼ぴ出し︵8⇒く08ぎロ︶の目 ︵1︶ 的その他を記載した書留郵便によって当該労働者を呼び出さなければならない︵L一二二−一四条第一項︶。次に、 使用者は、呼ぴ出された労働者との間で話し合い︵窪貫魯窪︶を持たなければならない。その過程で、使用者は、企 図されている解雇の理由を示し、かつ労働者の意見を聴取する義務を負う︵L一二二ー一四条第一項︶。その際、労 働者は、自らの選択にかかる当該企業に所属する従業員一名を伴うことができる︵L二三ー一四条第二項︶。 右の話し合いによっても使用者が解雇の意思を捨てず、解雇を決定したときは、それを受領証付書留郵便によって ︵2︶ ︵3V 労働者に通知しなければならない︵L一二二−一四ー一条︶。また、使用者は、右の通知後、労働者による書面の要求 § ︵4︶ カ あったときは、解雇の﹁現実的かつ強度の理由﹂を開示する義務を負う︵L一二二ー一四ー二条︶。 ア︸のように、一九七三年法は、解雇手続に関して、特に労働者の意見聴取の機会の保障、その際の補佐人同行の許 ︵5V 容、および解雇理由開示の保障によって、労働者の地位の一定の改善をもたらした。それは、従来、労働協約や就業 規則によって部分的にしか保障されていなかった解雇手続をそれ以外の揚合にも拡張すると共に、次に述べる手続違 背に対する制裁と相侯って、解雇の手続的側面に新たな意義を認めようとするものである。 ︵−︶使用者は、その呼ぴ出しの目的が解雇であることを示さなければならないが、この段階では解雇の事由までを表示する必 要はない。 ︵2︶ この解雇通知は、呼ぴ出しの期間の後、まる一日を経過してはじめて発することができる︵L一二二−一四−一条第二 ︵3︶ この請求およぴそれに対する使用者の解雇事由の通知には、一定の時間的制約が付されている︵R一二二−三条参照︶。 項︶。一種の冷却期間を定めたものである。 501 一橋大学研究年報 法学研究 14 ︵4︶ この点に関して破棄院は、使用者が労働者の要求に答えないときは、現実的かつ強度の理由なしに解雇したものとみなさ れるとした︵uoo。■ま8梓﹂SgU﹂ミざ℃。ω茸︶。ただし、その後の破棄院判例においては、.︸のア一とが必ずしも厳格に解 されていないようである。Ω酢℃2一器ざきやOO9㎝;マNooO9幹 ︵5︶ 以上の手続的規制は、その適用範囲について一定の制約を伴っている。まず、解雇の通知を受領証付書留郵便でなすぺき ことの要請は、すべての解雇について妥当する。しかし、その他の手続的要請は、経済的理由による解雇︵L一二二ー一四ー 五条。これについ工はL三二一ー三条以下に別個の手続が定められている︶、常時一一人に満たない労働者を雇用する使用者 二者の制限の理由につき、中村・前掲論文一〇〇頁以下参照︶。なお、このような手続的保障を受けない労働者の解雇につい による解雇︵L一二二−一四ー六条第一項︶、勤続一年に満たない労働者の解雇︵同条第二項︶については適用されない︵後 ても﹁現実的かつ強度の事由﹂の存在は必要であり、訴訟によって争う.︼とも可能である。 3 違法解雇についての救済 以上の実体的・手続的規制に対する違反については、一定の救済手段が定められている。その内容は、解雇が実体 まず、解雇が﹁現実的かつ強度の事由﹂を欠く揚合については、﹁裁判所は、労働者が既得の利益を維持したまま 的規制と手続的規制のいずれに反してなされたかによって異なる。 ︵−︶ ︵2︶ 企業に復職︵聾三譜﹃蝕9︶することを提案することができる。当事者の一方がそれを拒否するときは、裁判所は労 働者に対して補償金︵冒号ヨ三ま︶を付与するものとする。﹂と定められた︵L一二二ー一四ー四条︶。 従来の判例は、解雇が濫用とされる揚合にも、従業員代表者などの一定の揚合を除き、解雇を無効とせず、また、 復職も命じて妄かつ︵撃し奪・濫用的解雇の法的効暑損害賠償のみであった.死七三年の駿晋よ.て、 新たに復職の可能性が明文上規定されるに至ったわけであるが、それは復職の﹁提案﹂にとどまり、しかもそれも裁 502 懲戒処分法理の比較法的研究 n 判官の裁量に委ねられるのであり、﹁現実的かつ強度の事由﹂が存在しない揚合に当然に復職が命じられるわけではな ︵4︶ い。そして、労使の一方がその提案を拒むときは、復職に代えて特別の補償金の支払が命じられるにすぎない。これ ︵5︶ によって、新法が復職の救済を定めたことの意義は、大幅に後退したものとなった。 なお、解雇の﹁現実的かつ強度の事由﹂の立証に関して、新法は、﹁裁判官は、当事者の提示する資料を参照し、 必要があれば有用と考えるすぺての証拠調ぺの後に、その心証を形成するものとする。﹂と定めた︵L一ニニー一 四ー三条︶。以前から多くの学説によって主張され、立法過程でも議論のあった立証責任の転換は実現しなかったも ︵6︶ ︵7︶ のの、右の規定によってそれまで使用者の帰貴事由の存在を立証しなければ法的救済を受けられなかった労働者の地 位が改善されたことは確かである。ただ、破棄院が、使用者が外見上﹁現実的かつ強度の事由﹂を主張したときは、 立証の責任は使用者には帰せられないと判断していることについては、学説の評価は分かれており、また、あらゆる ︵8︶ ︵9︶ 証拠調ぺによっても裁判官が十分な心証を得られない揚合に、それが労使いずれの不利益となるか、つまり﹁立証の 危険﹂の問題についても、見解が対立している。 ︵n︶ ︹11︶ ︵12︶ 次に、法定手続違反の解雇については、当該解雇が﹁現実的かつ強度の事由﹂に基づく揚合に限り、法定の解雇手 続の履行と一か月分の賃金額を超えない補償金の支払を義務づけられる︵L二一二ー一四−四条︶。しかし、右の事 由がない場合については、手続違反それ自体の救済は定められていない。また、右の救済に際して解雇事由の存否に ついての実質的審査がなされるのであれば、改めて手続それ自体の履行を命ずることの意義は、かなり限られたもの となろう。 ︵13︶ ︵−︶ この補償金は、解雇に先立つ六か月分の賃金額を下回ることはできず、場合によりL一二二ー九条に定める最低解雇補償 手当︵ぎ紆言三芯旨三目ロ巳号浮Φβ幕ヨ。算−二年以上勤続した労働者に対し、重大な︿非行﹀のある揚合を除き、勤続 503 一橋大学研究年報 法学研究 14 年数に応じて支払われる︶を害することなく支払われるものとされる︵L一二二ー一四−四条第一項後段︶。 ︵2︶法文上補償金の支払が定められるのは、裁判所が復職を提案し、当事者の一方がそれを拒否した揚合についてであり、逆 に裁判所が復職を提案しない揚合の扱いについては疑問が存在したが、破棄院が、L一二二−一四−四条の規定は﹁現実的か 象o。む試㌧U、這N9やbo5︶、 一応の結坐泪を見た。q﹃勺色一鴇貯きや鴇一9ω■ つ強度の事由﹂なしに解雇がなされ、しかも復職がなされなかったすぺての揚合に適用されると判示するに至り︵ωo。﹂o。 ︵3︶第五章第二節三3を参照。また、法定従業員代表については例外的に復職が命じられていたことについてもそこで指摘し ておいた。 ︵4︶ この補償金は、﹁現実的かつ強度の事由﹂なしに解雇を行った使用者に対する制裁としてだけでなく、労働者の被った損害 の補償としての性格をも有し、裁判官はその二重の性格を考慮してかなりの高額の補償金支払を命じうるとされる︵象房箒き とするようである。 や鴇軌9。り●︶が、判例はむしろ、労働者が被った損害が六か月分の賃金額を超えない限り、それ以上の補償金は得られない ︵5︶ 労使双方、特に使用者が復職を受け容れることは極めてまれである︵頴一誘一3℃﹂ま︶。また、﹁現実的かつ強度の事由﹂ に基づかない解雇も無効ではないのであり、従って、たとえ復職がなされても、労働者は補償金の支払はもちろん、解雇から 復職までの賃金の支払も得られないことになる︵ξo亭99葛8諾聾。︸Uあ■這ヌや89勺讐琶3や呂o。9ε。 ︵7︶ 中村・前掲論文一三二頁以下参照。 ︵6︶ 本条は、法定手続違反の問題についても適用される。 ︵8︶ ωoρ這一嘗ぐ、一鶏ざ∪,一〇Nooいや一総卑ρ ︵9︶ その危険性を強調するものとして、oD一冨ざい霧α§2ま切α.o箆お冥098ぎ募霧号す或身ご甘一一弾6ヌ∪・oD・ ︵m︶ 9’∪Φ評。。一〇さつ8ひ簿ω∴9ヨR曹一。ざ■鴇g−OmoF=。aこ℃●さ。NN。梓ω■ 一〇No。・や爲9幹異なる評価を示すものとして、り象毘8やN宝などがある。 ︵11︶ 判例によれば、法定手続に違反してなされた解雇も無効ではなく、使用者は当然に適法な手続が履行されるまでの間の賃 504 懲戒処分法理の比較法的研究 n ︵12︶ この手続違反についての救済は、先に指摘した手続規定の適用が除外される場合に妥当しないことはもちろんであるが、 金支払義務を負うことにはならない。R℃塾隆聲マ認u魯ω● 更に勤続二年未満の労働者についても適用されない︵L一二二−一四−六条第二項︶。この結果、勤続が一年以上で二年未満 ︵13︶ 頴冴旨きや鵠oなお、手続違反の解雇がなされた場合に、急速審理について管轄を有する大審裁判所が手続の履行また の労働者は、手続上の保障は受けながら、それについての特別の救済は得られないことになる。 は復職の仮処分を命ずることは、破棄院によって否定されている︵ωoρo欲<﹂SざU﹂Sざ℃・巽∋oooρ8互コお蚕 旨ρ悶Gご﹂一﹂2脇︶。ただし、学説からは強い批判が加えられている。 ︵1︶ 三 立法の懲戒法理への影響 さと不徹底さを伴うものであることは否定できない。とはいえ、それが従前のフランス解雇法制の抜本的改革であり、 一九七三年法による解雇法制の改革は、それ自体が一種の妥協の産物であり、制度的にも理論的にも多くの不完全 しかも労働者の︿非行﹀を理由とする懲戒的解雇を主要な規制対象とすることからは、解雇に関する実務や判例はも ちろん、懲戒法理に対しても、大きな影響を及ぼすことは確かである。 まず、解雇について新たに﹁現実的かつ強度の事由﹂が必要とされ、しかもその評価が裁判所の権限とされたこと により、これまで限られた意味でしか労働者の︿非行﹀の程度を問題としてこなかった判例は変更を余儀なくされ、 ﹁現実的かつ強度の事由﹂の存否という観点から、その程度について評価を加えなければならないことになった。学 説の中には、そのことをとらえて、懲戒としての解雇に関しては、制裁の︿非行﹀に対する適切さについての体系的 コント・ールがもたらされることになるとし、あるいは、これまで存在しなかった﹁懲戒法﹂が出現することになる ︵2︶ と指摘するものも見られた。学説上、懲戒権理論に基づいて繰り返し主張され、判例に対する最大の批判点でもあっ ︵3︶ 505 一橋大学研究年報 法学研究 14 た、懲戒処分における制裁と︿非行﹀の均衡性の要請は、こうして立法による解雇法改革を通じて、部分的にではあ るが、実現するに至っ た わ け で あ る 。 しかしながら、右にいう﹁現実的かつ強度の事由﹂の概念は、その内容自体が必ずしも明確ではないだけでなく、 それに基づく労働者の︵非行﹀の程度の評価も、決して懲戒処分としての相当性という観点からのみなすぺきことが ︵4︶ 強制されているわけではない。判例の対応いかんによっては、大方の期待とは全く異なる事態も生じうるものであっ た。事実、その後の破棄院は、一方で労働者の軽度の︿非行﹀について解雇の適法性を否定しながら、他方で新たな 観点から解雇の正当事由を拡大しようとしている。すなわち、破棄院は、解雇が労働者の行為を原因とする場合にも、 その︿非行﹀の程度を問題とするまでもなく、それによって労使間の信頼の喪失︵零濤o留8呂き8︶がもたらさ れたことをもって﹁現実的かつ強度の事由﹂とするには十分であるとして、解雇原因の主観的要素を重視する傾向を ︵5︶ 示して い る の で あ る 。 ︵ 6 ︶ 次に、一九七三年法による法改正によって新設された解雇手続は、確かに一面で懲戒手続の保障という性格をも有 している。しかし、この手続もあくまで最小限のものにとどまり、解雇の決定は、依然として使用者の単独の権限で ある。また、法定手続の適用対象および手続違反についての救済が限定的なものであることも、先に指摘したとおり である。新たな﹁懲戒法﹂の形成は、手続的観点からもその一歩を進めたものの、それもやはり不完全なままである。 ︵7︶ ところで、一九七三年法による実体的・手続的規制はあくまで解雇に関するものであり、解雇以外の懲戒処分につ いて直接的な影響を及ぼすものではない。その意味で、一九七三年の法改正以降、学説によって盛んに喧伝された ﹁懲戒法﹂もしくは法的意味での﹁懲戒権﹂の出現も、いわば使用者の自由な解雇権が否定されたことの裏返しにす ぎない。学説の中には、解雇法制の改革を契機として、裁判所が懲戒処分についての従来の態度の全面的な再検討を 506 懲戒処分法理の比較法的研究 H ︵8︶ 期待するものもあったが、それは現実のものとはならなかった。破棄院は、一九七三年法の適用下においても、出勤 ︵9︶ 停止処分について、︿非行﹀との均衡性のコント・ールを一貫して拒否したのである。 さらに、一九七三年法が特に解雇について他の懲戒処分と区別して法的規制を加えたことは、一方で、判例が解雇 以外の懲戒処分に対するコントロールを自制していることの不当性を際立たせると共に、他方で、懲戒的解雇とそれ 以外の懲戒処分を同一の法理の下に包摂して論ずることの理論的意義を、かえって後退させることにもなった。その ような法制度の下において中心的な間題となるものは、あくまで法律によって規制される解雇の概念規定と、それに ついての独自の法定要件の解釈であって、懲戒解雇それ自体についての懲戒処分に固有の要件や限界ではありえない 切ミ馬恥ミ§ミ貰辱黛∼亀黒∼魯§亀笥§恥ミー目oo隆一Soo、コロ日曹o。。忌且巴“卜aミ帆鴇亀ミ昏禽へ織塁ミ§竃恥§恥ミ勲U。ω・這ooど 新解雇法の運用状況や解釈論上の問題点の検討は、本稿の直接の目的ではないので、ここではその詳細には立ち入らない。 ■冤g−O器昌葛g需斤陣ρ∪・oり・一SρマおO ℃ひ冴巴①き℃●一2 中村・前掲論文九一頁以下参照。 からである。 ︵10︶ ︵−︶ ︵2︶ ︵3︶ ︵4︶ O︷■ oげ一一αq鉾一〇暴︶口 po﹃日巴一器甑83一一8目一〇go昇gの雲<①σq帥三①8ω喝oロ<o一屋αβ30hα、2賃o冥一も。p肉ミ魯恥§ミω秘9傘 口仁ヨO ﹃ Oω慧o巨引冒く自①き一臼ローΩ塁αρd房ぎ瑳①一一㊦≡ロのけβ凱gα瓢o昌象什α島一〇σp5ロoω︵昏o一け帥一、o日℃一〇一g費o津自窃 ︵5︶ んど・ぢ一鶏9望ψち団ざや8その要旨は次のようなものである。﹁会社とその技術助手との間の、その者の職務 G霜§ ミ 骨 § U 漸巴一〇Nり剛碧一の一窯oo”℃■一〇一 構成 す る 。 労 働 者 に 帰 せ ら れ る 非難 が ︿非行﹀を構成するか否かは、労働関係が維持されるために必要な相亙の信頼が両当事 の重 要 な 点に 価 の 明 白 な 不 一致 つ い て の 評 は 、 労働契約の通常の継続を困難にし、解雇を正当化する現実的かつ強度の事由を 者間 に は も はや 存 在 し な い 以 上 、 重要なことではない。﹂なお、この判決の意義については、ペリシエの評釈︵頷一﹃剛90■ψ 507 〇〇 一橋大学研究年報 法学研究 14 ︵6︶RΩ首貫≧巴P鍔隠§38罫嘗8饗二、昏覧。巻弩8諾匡εみ−色。琶軌。き器善一一9訂貧窪器象一凶8琶。目。鼻∼ 一。NN魎や蹟糞呂を参照。 U,一〇〇。一一〇冒9■℃、一8旧≧<霧。N一三8一窃ヤ■帥砂葺Φ︽の曾同①霧。︾魎o雲鴇qo一陣89一。ヨ。昇︸U■ρ這VPマ9冒く自9㌧甘馨− Ω即&Pい.oげ凝毬曾留一2臣審象。。。銭誘・∪・○﹂鴇ざ℃﹂呂また、ペリシエによれぱ、信頼の喪失に関する判例の多く は管理職員に関するものであるが、それ以外の労働者について適用される揚合もあり、前者については、労使間の評価の対立 やささいな︿非行﹀であっても、信頼の喪失として解雇の正当事由とされるのに対し、後者についてそれが認められるのは、 実際に契約関係の継続を困難にするような揚合か、信頼の喪失というよりもむしろ従業員相互間の著しい対立の揚合であると ︵7︶ この限定的な救済も、もちろん法定の手続に関するものであって、労働協約や就業規則に定められる手続について適用さ いう︵頴諒旨ン℃■一8︶。 ︵8︶ 困く震o、oo塁緯一〇ン刈①ε■りや一Nひ れるものではない。それらの手続違反についての救済は、従来の法状態がそのまま継続していると言える。 ︵9︶RωoρQ急ρ這鐸u﹂SgH.国も。9000pひ一き<﹂oNざu﹂o唱㌧一■押や爲るoρ賂。o﹂巨閣一〇Nぎq這ヨ目■ ︵−o︶ 解雇の概念をめぐっては、新法にいう解雇の概念規定に関して新たな解釈論上の間題が生じているほか、たとえば解雇と 国■や8N旧ωop頃き<、一〇回o。︸U。一ミP一■卑℃■じ。いO 労働者の退職との関係や、使用者による一方的な労働条件の変更が解雇に該当するか否か︵この問題については、野田進﹁労 働条件の変更と解雇ー契約論的構成の検討﹂︵未完︶阪大法学一二六号、一二八号に詳細な検討がある︶などの既存の問題 一8窪。一Φ日Φ耳①二〇ω霊庁吸o。。巨aΦ。。畠¢﹃壱盆﹃Φ2。o暮β陣αΦ賃p<pFU﹃¢一So。voDつ9国昏。“8毒p一巳瓢帥ユく①〇ニョ℃=, にも新たな影響を及ぽしている。9頴冴旨5︾u9。。・︸9日亀旨爵P岩マ9窪・=①識こや一翠9ε頴一一量9ro 鼠ご凶一一器”冒ひ。蜂oegけαo犀一6ユg︵一Φ一一8一一。凶。日o耳りO。ω,一〇〇。一’やNOざoop<緯剛g■即ヨo血38寓o昌導出舞酔巴①30g賃緯 黛賃畦巴一・qoo・60。ど℃・曽沖℃象裟9■島α9騨器口甜8一貫qoo・おQ。一”℃・80。それに対して、懲戒的解雇とそれ以外 の解雇の概念上の区別は、新法の下においては必ずしも重要な意味を持たない。懲戒としての解雇も、他の解雇と同様、あく 508 懲戒処分法理の比較法的研究 皿 まで新法による解雇規制に従って評価されるものである以上、その限りではそれを強いて懲戒権の行使として構成し、 他の懲 戒処分と同列に置いてその要件や限界を論ずる必要性や実益に乏しいからである。 第三節 一九八二年法による懲戒処分規制 一 懲戒処分の立法的規制の展開 − 一九七八年法による財産的制裁の禁止 前節において指摘したように、解雇に関する新たな立法的規制の導入は、逆に解雇に至らない懲戒処分の無規律状 態を一層顕著なものとした。このことは、フランス労働法制の中でも特にその後進性が指摘されてきた就業規則法制 の改革と並んで、次なる立法的規制の課題となったのである。そして、一九七八年には、労働大臣により、リベロを ︵1﹀ ︵2︶ 長とする就業規則問題検討委員会が設置され、また、労働界でも、たとえば労働総同盟︵cGT︶が、その第四〇回 ︵3︶ 大会において、就業規則の廃止と懲戒手続の保障を要求事項の一環として掲げた。 このような状況の下で、懲戒処分に対する立法的規制は、まず一九七八年七月一七日の法律によって部分的に実施 されることになった。すなわち、同法第五一条は、それまで労働法典L一二二i三九条以下に定められていた罰金の 例外的許可制を廃止し、それに代えて次のような規定を置いたのである。 L一二二−三九条 すべての使用者は、罰金またはその他の財産的制裁︵”目。且霧8き賃窃墨琴けご房忌2昆巴吋8︶によって、 就業規則規定に対する違反を罰することを禁止される。 ︵4︶ これによって、罰金その他の財産的制裁の行使は、法律上は例外なく禁止されることになった。ただし、懲戒処分 としての罰金は、既に一九三二年法による規制によって事実上消滅していたのであって、その限りでは、右の法改正 509 一橋大学研究年報 法学研究 14 が実務に与える影響はほとんどない。問題は、﹁その他の財産的制裁﹂の意味である。実務上、出勤停止や降絡など、 労働者に対して間接的に財産的損害をもたらす処分形態は広く普及しており、また、懲戒処分として明示されない場 合であっても、諸手当の不支給ないし減額、あるいは不就労に伴う賃金カットなどもしばしば行われている。右の規 定の解釈いかんによっては、そのような実務上の取扱に対して、大きな影響が及びうるわけである。 この問題については、これまでのところ必ずしも本格的な議論が展開されているわけではないが、その中で、破棄 ︵5︶ 院社会部は、右の法改正後も、出勤停止処分については一貫してその合法性を承認しており、また、特にストライキ に伴う賃金カットに関して、﹁使用者により支払われる報酬は、契約によって定められた通常の履行条件で提供され た労務に対するものでなければならず、意識的に不完全になされた労務についての賃金不払は、禁止された罰金では ない。﹂との判断を示している。しかし、他方で破棄院刑事部は、賃金の低下を伴う降格がL一二二ー三九条にいう ︵6︶ ︵7︶ 財産的制裁に当たるとしており、今後の動向が注目されるところである。 右の一九七八年法による改正は、このように、単に罰金その他の財産的制裁を禁止したものにすぎない。懲戒処分 ︵8︶ についての本格的な立法的規制は、社会党政権樹立後の一九八二年に至って、ようやく実現することになる。 ︵1︶ q、困くRρ一舞P20盆ωロ﹃一〇詰σq一①ヨΦ暮凶簿曾一窪ン∪・ψ一鶏Pや一 ︵2︶99ぎp霞窪誉9宝&。q一昏窪江忌幕目。二。宕薯嘗駐暑菅跨Φ亀瓢3。こ.。昌名冴poあ﹂。。。ρ℃﹂認 ︵3︶ぎ貯。おも訟費一ご垂Φ二鶏。。宕量昇良語屋ω馨窪§α、聾雪。馨凶8留箕。醇一9竃暑2.&巨募賃豊8。二① 唱5げ一一〇〇一島くo器8色愚o巴梓一〇房畠.oa﹃o曾o日oヨ5ロo、のoo団巴卑富o巴 ︵4︶ これに伴い、L一ニニー四〇条およぴL一二二−四二条は廃止され、L一二二ー四一条は、﹁﹂一二二−三九条規定に反 するすぺての規定は無効とする。﹂と修正された。なお、L一二二−三九条違反については罰則がある︵L一五二−一条︶。 ︵5︶ 出勤停止処分が労働法典の規制する罰金に該当しないことは、以前から破棄院の一貫した判例であった。第五章第三節二 510 懲戒処分法理の比較法的研究 H ︵6︶もoop8日曽の一〇NPu﹂ONP一’勾.や云O を参照。 ︵7︶ 9ぼレ。.α8這o。ど望Pむo。ρやb。o。oただし、本判決が賃金の低下を伴う降格を一般的に﹁財産的判裁﹂にあたると したものか否かについては疑問がある。判決文の上からは、当該降格が職務や責任の変更を伴わず、単に賃金の低下のみを惹 賃金減額が職務変更の間接的結果であるような本来の降格については妥当しないとの評価︵切ひβ且’20器859ぎ■塙.泳ρ 起するものであった︵少なくとも使用者がそれに反する主張をしなかった︶ことが窺われるからである。そのため、本判決は、 ︵8︶ 以上の一九七八年法のほかにも、懲戒処分の立法的規則の試みがなかったわけではない。たとえぱ、労働審判所に関する 一〇Q。ンq600bo︸H即マω=︶も見られる。 一九七九年一月一八日の法律の審議に際し、労働審判所は労働者が犯した︿非行﹀の重大性に比して不当または不均衡と判断 や一N一︶。 される懲戒処分を無効とし、または軽減する権限を有する旨の修正案が提案されたが、否決されている︵ρ旨。PU.oo・一〇〇。ρ 2 一九八二年法による懲戒処分規制の実現 私的企業における懲戒処分の立法的規制は、一九八一年のミッテラン社会党政権の誕生を契機に、ようやくにして、 しかし一気に実現することになった。それは、第一次、第二次モーロワ内閣の労働大臣オールーの強いイニシアチブ によるものであった。 ︵−︶ オールーは、一九八一年九月、大統領及び首相あてに、労働法において実現されるぺき諸改革に関する﹃労働者の 諸権利﹄と題する報告書を提出した。この報告書は、﹁国家における市民である労働者は、彼らの企業においても市民 であらねばない。﹂との理念の下に、労働者の諸権利の回復と拡大、労働集団︵としての企業︶の再構成、労働者代表 511 一橋大学研究年報 法学研究 14 すなわち﹁企業内における公的自由﹂の拡大の一環として、使用者の懲戒権の規制と就業規則法制の改革が謳われて 機関の強化、団体交渉の復活の四点を骨子とするものであったが、その中で、﹁企業内における市民権︵畠3、。目①$︶﹂、 ︵2V いた。報告書の内容は、その後四つの法案として議会に提出され、激しい議論の末、いわゆるオールー法として一九 ︵3︶ 八二年後半に相次いで制定の運びとなった。これらの法律は、従業員代表制度の改革や企業内団体交渉制度の確立、 ︵ 4 ︶ 労働者の企業内での意見表明権︵昏o詳α.雲冥。鋒8︶の保障など、フランスの労使関係および労働法に極めて重大 かつ大胆な変革をもたらすものであるが、懲戒処分に関する立法的規制もまた、その一環として、﹁企業内における ︵5︶ 労働者の自由﹂に関する一九八二年八月四日の法律第八二−六八九号によって、遂に実現を見るに至ったのである。 この法律の背景や審議経過、労使の対応などは、オールー法全体との関連でも、それ自体が重要な検討課題ではあ るが、ここでその詳細について立ち入っている余裕はないので、以下では、本稿が対象としてきたフランス懲戒処分 ︵6︶ ︵7︶ 法理との対比において、立法の内容と意義について検討を加えるにとどめる。 ︵−︶卜塁昏ミ魯ミミ鶯§§ミ⇔﹂ど窪目。鼻壁8写君ゆ器①這。。押R.、r①ω﹃ひ噛o琶。一..噂℃H①巨警①短岳g9田署o﹃貯>員o舞 ︵2︶報告書によれば、﹁すぺての市民に対して適用される公的自由は、生産という拘束と両立する限りにおいて、企業内に導 ∪。oD。一〇〇〇Nり昌ロ日母o愚曾凶巴一︸帥く注一臼覧℃■8雪9 巾巴鴇留費o淳3け田く曽二g自o置oり①。旨まωo。芭pZp耳。旨。一8b。O−N一一6<Φ一昌耳o一〇〇。ごO■堕這o。ρp一一巳曾o。。隠。一巴、 入されねぱならない。﹂という︵魯甲亀き︾oo︶。Ω,r.9賃Φ冥羅9一窃一ぎo昌傍℃虐⊆ゐ5伊Ooぎρ器幕一.霧8且豊9即聾9 ︵3︶懲戒権規制に関する法律案︵一九八二年二月四日に社会経済委員会に提出された立法草案およぴ同年三月三一日国会提出 、ビ①・りみ8畦ヨ$=、、︸や全No富。 の最終法律案︶の内容およびその批判については次の文献を参照。冒≦≡曾や8N9豆切魯90芭$9鼻色。。o堂ぎ巴﹃① 。梓98岩⋮①器魯屋一、窪胃8岳。自彗。。﹃﹃駄9ヨ。α窃昏o計α窃qp奉三①=富︵>暴一岩o含冥o隣ロo一〇一>旨o奏︶、Poo. 512 懲戒処分法理の比較法的研究 ∬ むo。ρ5ロヨ瓜H。の忌。一p一・、、■。。。み噛。﹃ヨ①ω一一..・や&ざギo蒼留弼誓畦一。議σQ一〇β窪二g害①ξ①二〇響o#αぎ苞ぎ巴﹃。︸即型 ︵4︶ これらの法律については、佐藤清﹁フランスにおける労働者権利の拡大ーオールi法の成立によせてー﹂季刊労働法 qoo・一〇〇。N・コロヨ母o。。葱o芭い..U8芽コoロく①磐図α窃需髪即三窪誘.、︾マ鴇99 ︵5︶本法は、就業規則およぴ懲戒権についての規制︵労働法典L一二二−三三条以下の改正︶と、労働者の意見表明権の創設 一二八号一四六頁に概説がある。 ︵労働法典L四六一−一条以下の新設︶を主要な内容とする。また、前者に関しては、一九八三年三月三日のデクレ第八三ー ︵6︶ ア︸の点については、佐藤.前掲論文のほか、森由人﹁フランス社会党政権下の労資関係ーオールー法に盛られた労働者 一六〇号によって、労働法典第二部の関連条項︵R一二二−一三条以下およぴその標題︶が修正された。 の権利ー﹂月刊社会党一九八三年一月号一一六頁、葉山滉﹁企業内の市民権ーフランス労働法典の大改正㊤﹂経済評論一 九八三年七月号七四頁、同﹁一二世紀の企業を求めてーフランス労働法典の大改正㊥﹂経済評論一九八三年八月号八四頁、 ︵7︶ なお、以上の立法に先立ち、一九八一年八月四日に恩赦に関する法律︵■o一⇒。o。γNま身轟8象這o。一宕﹃梓の算費ヨ菖隆。︶ 長部重康﹁、、、ッテラン政権の構造政策﹂長部編﹃現代フランス経済論﹄︹有斐閣・昭五八︺三二二頁以下を参照。 が制定されたが、これはその対象を、単に刑事罰や公務員などの法令に基づく懲戒処分︵公務員の懲戒処分を恩赦の対象とす ︶のみならず、一般の使用者による懲戒処分にも拡大し︵同法第一四条第一項︶、更に従業員代表者または組合代表者の職務 る︸︾とは、7︾れまでも見受けられたところである。Ω・Uo薯器oF[.鱒ヨ三経①自ヨ緯5冨色ωo凶覧ぎ巴βqむa︸Oξ昌■P 共産党議員の修正案に基づいて挿入されたものであるが、法文の意義が不明確なこともあって、多くの問題を惹起することに に関する行為の故に解雇された者の復職を定めている︵同条第二項︶点に大きな特色があった。これらの規定は、社会党およぴ 鳳Φ﹃・[、帥ヨ昌一ωユ①α①のの帥昌。ユ。pの岳の。菅一昌鉱﹃8鼠房一。。。。算話E。。①ω︵[o一身“8象一〇。。一yo■oo。一〇。。どやα09ωo轟N貫 なった。ただし、それはもっぱら条文の細かな解釈や技術的問題に関するものであるので、ここでは立ち入らない。R留<㌣ ℃p=一・■費一。一α.ρヨ昌凶ω菖。。二。℃。⋮oマ良ω。旦ぎ践﹃。冨#oロ巴魎幻■恒o,oD、這・。どや緯o切08g&い一〇嘗宝弩9び斜一〇凶コ。 oo一もいひα=命8窪這oo一℃o﹃伸騨算のヨ巳㎝餓ρ︾ρコ這oo一,r8斜α 513 ・。 一橋大学研究年報 法学研究 14 ︵−︶ 二 一九八二年法による懲戒処分規制の内容とその意義 − 就業規則と懲戒規定 一九八二年法は、まず、就業規則法制について注目すべき修正を加えた。すなわち、同法は、就業規則が使用者の パと 一方的作成にかかるという原則およぴ作成の条件については基本的に旧制度を維持したものの、その内容を、﹁企業 または事業場における安全衛生法規の適用手段﹂と﹁規律︵島毘嘗壽︶に関する一般的.常設的定め、およぴ特に使 ︵3︶ 用者がとりうる制裁の性質並びに段階﹂に限定し︵L一二二−三四条第一項︶、また、それは後述のL一二二−四一 条または労働協約から生ずる労働者の防御権に関する規定を置くものとした︵L一二二−三四条第二項︶。ア︶れによ って就業規則は、今後はもっぱら安全および規律に関する行為準則、およびその違反についての懲戒規定としての性 格を有し、従来就業規則に定められていたそれ以外の実質的な労働条件の問題は、労使間の交渉およぴ協約.協定に ︵4︶ 委ねられることになったわけである。 しかしながら、一九八二年法は、懲戒処分に関していわゆる罪刑法定主義の原則は明確な形では採用しなかった。 L一二二−三四条は、制裁の性質およぴ段階を就業規則に規定すぺきことを定めるものの、具体的な懲戒事由の列挙 には言及していないのである。立法の審議過程において、懲戒処分の対象を就業規則に定められた行為に限定すべき 旨の修正案が提案されたものの、結局否決されている。 ハさレ ︵1︶ Ω■ωo轟NF勺雲一、U5℃oロ︿oマ。。oロく段巴コ︿。屋巨昏o詫含の。豆ぎ巴﹃PU。○・一〇〇。ρマ轟お︸冒く自。き旨。塁,Ω四民9 H﹂.①×の8回80什一Φ8昌賃20甘ユ良o甑oロロo一αg℃o目<o一﹃α一のo首一ぎ巴お︾qoo,もooいー℃■鴇ご[冤op−O器90①βa、U口poロ<$ロ ω器o岱o島色ωo首言巴話pU.oo■一〇〇〇シ℃■象跡ω一αqεお菖p閃3鼠09■o﹃①σp一①ヨo耳ぎ貯ひユogα.o暮話鷲栃ρ菊・勺・qoo・一〇〇。斜 ω弩一。話αp一①ヨ窪二暮鋤一①5。二即急。no骨一ぎ・α睾の一.雪嘗6誹ρqむo。い一Ωく9・マざ悶①=ω巴のツ一8p[即濠夢三〇ロα①ω 514 懲戒処分法理の比較法的研究 H α仁℃。⋮。一目目。﹃量蕊。一、。曼。冤。=鷺レ。り﹂。・。ζき。為艮費5。琶量身§§×暑き尋喜艮。葺馨■ や鴇曾ω蒔8同①洋ρ■①切αQ弩p算一霧象・。。昼﹃巴﹃窃帥一.o暮器℃誹p即閏qψむo。N旨や零ごのo一目ρ切Φヨ碧“零8鼻Φ昌 目①ロけ即一﹃。計ロの一.。ロ斤﹃Φ℃﹃一・.①・pω・一。・Qいも・釜“<①旨p評巷訂①レ.婁爵σ・の幕葺αξ8<。一こ凶。・。凶℃一凶曇区Φ一ぎー ℃一〇図〇一﹄きUーω。這oo ρ 轟 o o ひ ︵2︶ 使用者の一方的行為としての就業規則制度が廃止されるぺきか否か、労使の集団的協定に置き換えられるぺきか否かにつ いては活発な議論があったが、一九八二年法は従来の制度を維持しつつ、その内容を限定し、法的規制の範囲を広げるという 方法をとった。政府の報告によれば、その無条件の廃止はかえって使用者の権限と恣意を強化する危険があるという︵ヵ響 ︵3︶ この﹁規律﹂という語の具体的な意味や内容については、新法は特に触れていない。このことは立法の審議過程でも問題 署。H酔窓﹃o・日。ロ梓巴戸>のm・ヨσ一①。口畳g巴o﹄。8昆o。。霧巴go邑言巴おαoむo。一−むo。ρコ。o。軍︸やo。︶。 ︵4︶ 以上のほか、今回の法改正により、就業規則は当該企業・事業揚に適用される労働協約およぴ集団協定に反する規定︵L となったものであるが、結局は意見の一致を見ずに終わった︵9ω9量ρqoり﹂Oo。甜や蟄N︶。 一二二−三五条第一項︶および性別等による差別規定︵同条第二項︶を含みえず、﹁従業員の権利およぴ自由に対し、遂行す ぺき職務によって正当化されず、追求される目的に相応しない制限を加えることはできない﹂︵同条第一項︶ことが明示され、 更に、労働監督官は﹁いつにても﹂L一二二ー三四条およびL一二二−三五条に反する規定の削除を求めうることになった 総O ︵L一二二ー三七条一項︶。Oい一畠包ヨ窪9>鼻oぎPい窃8昇3一霧α05一甜p一ま身吊屯①ヨ9一什ヨみユΦ日・U・ω・一〇〇。辞や また、従来、就業規則としての法的規則に服するか否かについての問題のあった服務規定︵ぎ伸窃号器署一8︶その他の文 ︵5︶ Ω・>剛5。隅一階ヨ。、一け昌。まひ℃貧ヌoo品三Pい○,象9冨㌻88この点に関して政府側は、一般法上の懲戒的︿非行﹀ 書は、一定の範囲で就業規則の付属規定とみなされ、就業規則と同一の規則に服することになった︵L一二二−三九条︶。 あることを指摘していた︵愚・ミこや88︶。 も制限的に定義づけられているわけではなく、しかもそれは多様な企業の独自の活動を考慮すべきより広い範囲に及ぶもので 515 一橋大学研究年報 法学研究 14 2 懲戒処分の形態と対象 6 ユ ω 懲戒処分の定義 一九八二年法は、労働法典第一巻第二編第二章第六節に、新たに第二款として﹁労働者の 5 L一二二−四〇条 制裁︵旨。ω雪&9︶とは、口頭の注意を除き、使用者により︿非行﹀と思料された労働者の挙動︵pα。一、。。。, 保護および懲戒権﹂の項目を設け、その冒頭に次のような懲戒処分の定義規定を置いた。 在、職務、経歴または報酬に影響を及ぼすものをいう。 目①幹︶に対して、使用者によってとられるすべての措置であって、直接的であると否とを問わず、労働者の企業における存 このよえ薪法は・公隻轡存奮・つに懲戒処分形態を齪的に列挙するのではなく、その理由およぴ効果 という二つの観点奮、ご≦般曽懲戒処分蓬彗けた.特に、右の条文のうち、﹁直接的であると否とを謂 ず﹂という文言は、後述するL一二二−四一条第二項との関連で、当初の立法草案に新たに付加されたものであるが、 これによって﹁制裁﹂の概念は、その効果の観点からは極めて広範なものとなった。その結果、法的規制の対象と パ レ しての﹁制裁﹂の具体的な範囲の評価においては、かえって、使用者が︿非行﹀と思料する挙動を理由としたか否か パゑ という主観的要素が、決定的な意味を有することになるように思われる。このことは、制裁の性質および段階を就業 規則に定めることが要請される︵L一二二−三四条、前述二−参照︶こと、および労働者の︿非行﹀についての定義 が存在しないこととも関連して、使用者によってとられる具体的措置の動機やその理由とされた労働者の行為の性質 をめぐって、新たな問題を惹起することになろう。 パさレ ⑧ 形態上の制限 懲戒処分の形態に関しては、特にL一二二−四二条が、﹁罰金またはその他の財産的制裁は 禁止される﹂と定める。これは、一九七八年法により改正された従来のL一二二ー三九条を引き継いだものであるが、 ハ レ 今回の改正によっても、﹁財産的制裁﹂がいかなるものを意味するのかについての指針は与えられておらず、今後に 懲戒処分法理の比較法的研究 H 問題を残すことになった。ただ、立法の審議過程において、この点に関して出勤停止処分が問題とされ、結局その禁 禁止された﹁財産的制裁﹂に当たらないと考えていたと解される。おそらく今後は、このような観点から、財産的損 止を求める修正意見が否決されたア︸とからは、少なくとも立法者は、間接的に財産的損失を生ずるにすぎない制裁は パァレ 失が直接的か否か、換一一一一・すれぱ、それが労働者の労務提供の性質や責任の程度に相応したものか否かが問題とされる 傾向が強まるであろう。 ︵8︶ 以上のほかには、新法は懲戒処分の形態に関して特に制限を置いていない。これまで問題とされてきた出勤停止処 すレ 分の期間の制限は、今回も実現しなかった。 團 対象上の制限 新法は、懲戒処分の定義に関して、それを﹁使用者により︿非行﹀と思料された労働者の挙 パリ 動に対してとられるすべての措置﹂とするものの、そのく非行Vの意義や内容については何ら具体的規定を置いてい ない.この雌っいて、新法の適用に関する労働大臣通達は、﹁契約関係の正常議往合致しないもの﹂を︿非行﹀ と解しているが、懲戒処分の対象としての︿非行﹀が契約履行上の︿非行﹀であるのか、それとも民事的︿非行﹀ β汁。。一く一一Φ︶や職業的︿非行﹀︵壁暮Φ冥08婁o目亀①︶とは区別された独自の懲戒的︿非行﹀︵富鼻。息㎝。苞冒鉱器︶ パど であるのかは、今後とも引き続き議論の対象とされることになろう。 について、次のような規定を新設した。 このように新法は、懲戒処分の対象について明確な一般的基準は示さなかったものの、特にその差別的行使の禁止 合活動または宗教的信条を理由に制裁を科され、もしくは解雇されることはできない。 L一二二−四五条 いかなる労働者も、その出生、性別、家族状況、民族もしくは国家もしくは種族への帰属、政治的意見、組 これと異なるすぺての定めは無効である。 517 (一 一橋大学研究年報 法学研究 14 ︵B︶ ただし、右の差別理由のうち組合活動については労働法典L四一二−二条により、それ以外の理由についても刑法 典第四一六条により、既に差別的取扱が禁止されており、しかも右規定の第二項が当該措置そのものではなく﹁定 め﹂を無効とするにすぎないことからも、右の規定の意義および効果については疑間が残る。 ︵耳︶ ︵巧︶ 凶 制裁と︿非行﹀の均衡性の要請 このように、一九八二年法は、懲戒処分の形態と対象について、その内容 を具体的に明示するものではないが、それらの関係については、一つの重要な原則をうち立てた。すなわち、懲戒処 分と、その理由となった労働者の︿非行﹀との間の均衡性の要請がそれである。後述のように、L二一二ー四三条は 懲戒処分に関する裁判所の広範な権限を定めたが︵4①参照︶、その中で特に、裁判所は﹁犯された︿非行﹀と均衡 しない制裁を無効とすることができる﹂ことを明言したのである。これによって、従来、懲戒処分についての審査対 ︵16︶ ︵17︶ 象をほとんど懲戒事由の存否と協約または規則上の手続違反の間題に限定し、懲戒処分の相当性の評価については一 貫して裁判所による審査を否定してきた判例が、根本的な変更を余儀なくされたことは明らかであろう。永年にわた って判例に対する最大の批判点でもあったこの問題は、ようやくにして立法的解決を見るに至ったわけである。 ︵−︶公務員の一般的身分に関する一九五九年四月一四日オルドナンス第三〇条参照。戒告から、年金の停止を伴う免職まで、 ︵2︶9<。言ぎ一U,oo﹂o。。い︸で﹂。。N 一〇段階の懲戒処分と、停職処分が定められている。 ︵3︶ Ω’oo蒔コoお洋ρ罰勺,U,oo らooρ℃■い鳶 するL一二二−四一条第二項の文言からは、そのような直接・間接の影響を伴わない﹁制裁﹂が存在するア︸とを前提とするよ ︵4︶ L一二二ー四〇条は、労働者の地位や報酬に直接・間接の影響を及ぼすすべての措置を﹁制裁﹂と定義づけながら、後述 うにも読みとれる。このことは、﹁直接的であると否とを間わず﹂という語句が事後的に右の両条に付加された.一とに伴う立 法上の齪麟とも言えるが、同時に、﹁制裁﹂の定義においてその影響すなわち効果の果たす意義自体についての疑問を生ぜし 518 懲戒処分法理の比較法的研究 H ︵5︶頴一﹃一9∪あ甲G。。ωも’蜜。。い<①⋮一po,ω﹂。。。いも﹂。。N めることになる︵勺ひ房巴3U■ψごoo鈎℃,頓鳶︶。 ︵6︶ ただし、旧規定の﹁就業規則規定の違反を罰するために﹂という語句は削除された。なお、禁止に違反する規定や定めが 無効とされること︵L=一二−四二条第二項、ただし、、.牲℃E鉢δ塁、、を..色巷8蕊98駐宅5什一9..に修正︶、およぴ罰則 規定︵L一五二ー 一 条 ︶ は 変 わ り な い 。 ︵7︶象一一切。。凶9u,。。■一。。。ωも己お<。巳目9uあ﹂。。。一もト。。刈 ︵8︶墨葺$uあ・一裟㌧℃﹄軌。訪曹。韓8るも甲oあ﹄。。。“。も﹂参ΩH琶騨。﹄。軌白魯嵩目貰切一。。。鈎ぎ量募 ︵9︶ 9<9巳劇qoD﹂oo。きや畠Nただし、懲戒処分とは区別された懲戒手続中の出勤停止処分の可能性が明示されたこと α.8讐。器9α9貧牙一〇ω一帥軌3訂巨3轟目舞這o。Nなお、本節一−を参照。 ︵10︶ L一二二−三四条が﹁規律﹂との関連で﹁制裁﹂の定めを就業規則の対象事項としていることからは、この揚合の︿非 につき、後述3㈲を参照。 行﹀とは規律違反を意味するように思われるが、新法はこの﹁規律﹂についてもその具体的な意味を明らかにしていない︵前 ︵11︶Ω§芭﹃①含嵩ヨ誤壽ωも︾ミ・曾幕§ω睾る雪9舞。﹄らピ。ω﹂§も薗篶 述二1注︵3︶参照︶。 ︵12︶ り雲ωも・凶9U、oり﹂Oo。。一℃,匁o。 ︵13︶ ア︺のほか、同じ一九八二年八月四日法により新設された労働者の意見表明権に基づく意見が、制裁または解雇の理由とな ︵14︶就業規規則が労働者の性別や信条を理由とする差別規定を含みえないことは、別にL=一二−三五条でも規定されている。 しえないことが規定されている︵L四六一−一条第二項︶。 ︵15︶ Oh■<自鉱PO■ω■這o。い℃マ阜o。V卑9 ︵16︶ 当初の立法草案は、この点について、﹁犯された︿非行﹀に比して明らかに均衡を失した制裁を無効とすることができる。﹂ と定めていたが、最終的な成文はそのような制約を除外し、裁判官に対してより広い均衡性評価の権限を認めるものとなった。 519 一橋大学研究年報 法学研究 14 ︵17︶ Oいω凶σQロo話窪P印℃■U●ω、一〇〇。N℃や零o。、甘<一三90・oo・おo。い・℃・匁O Oの 適用対象 一九八二年法の注目すべき特徴の一つは、懲戒処分行使について最小限の手続的規制を導入した 3 懲戒処分の行使および手続 ことにある。その内容は、基本的には一九七三年法による解雇手続に倣うものであるが、重要な点でそれを発展させ ている。すなわち、一九七三年法による解雇手続が、企業規模およぴ労働者の勤続年数により、その適用範囲を制限 されているのに対し、新たな懲戒手続はそのような制限を一切伴っておらず、しかもL一二二−一四−六条の規定に ︵−︶ ︵2︶ よって、L一二二−一四条およぴL一四二−一四ー二条に定められた手続規制に服しない解雇についても、新たな懲 戒手続規制が適用されることが明言されているのである︵L一二二−四一条第四項︶。特に小規模企業についても懲 ︵3︶ 戒手続規制を適用することに対しては、使用者側からの強い反対があったものの、結局受け容れられると.︸ろとはな らなかった。 図 意見聴取の機会の保障 制裁を行使しようとする使用者は、まず当該労働者を呼び出し、その釈明を聞かな けれぱならない︵L一二二ー四一条第二項、R一二二−一七条、R二一二ー一八条︶。呼び出しの通知は、会合の目的、 ︵4︶ 日時および揚所を記載した書面によってなされねばならない。その会合において、使用者は予定した制裁の理由を示 したうえで、労働者の釈明を聞かなけれぱならない。その際に労働者は、当該企業の従業員の中から選出した者一名 ︵5︶ を随伴することができる。 なお、以上の手続は、﹁予定された制裁が、直接的であると否とを間わず、労働者の企業における存在、職務、経歴 または報酬に影響を及ぽさない戒告その他類似の性質を有する制裁であるとき﹂には適用されない︵L一二二−四一 520 懲戒処分法理の比較法的研究 H 条第二項前段但書︶。ここにいう﹁直接的であると否とを問わず﹂の語は、当初の立法草案が﹁直接の﹂影響として ︵6︶ いたのに比ぺれば、適用除外の範囲を著しく狭める意味を持つものである。 また、L二一二ー四一条第三項は、労働者の挙動が即時出勤停止の暫定措置︵ヨ。の日Φ8房R轟8ぎ︶を不可欠と するときも、その挙動を理由とする確定的制裁は、右の手続が履践された後でなければ科されることができないと定 ︵7︶ めた。このような暫定的出勤停止処分の制度は、法定従業員代表の解雇に関して法律上定められ、それ以外にも判例 上認められてきたものであるが、これによって、懲戒手続についてもそれが可能であること、およぴその揚合にも確 ︵8︶ 定的な懲戒処分行使には法定手続の履践が必要なことが確認されたわけである。また、右の規定によって、そのよう な措置が﹁不可欠﹂︵冒&ぞ8舞三。︶か否かの観点から、その当否が判断されることになるであろうが、その間の賃 ︵9︶ 金に関しては定めがなく、今後に問題を残すことになった。 ㈹ 懲戒処分の通知および理由の開示 懲戒処分の手続に関するいま一つの重要な規制は、懲戒処分の書面の通 L一二二ー四一条第一項 いかなる制裁も、労働者が考慮された理由について同時にかつ書面で通知されるのでなけれぱ、科さ 知および理由の開示が義務づけられたことにある。 ︵P︶ れることができない。 この規定は、右の事情聴取手続とは異なり、すべての制裁について適用される。しかも懲戒処分の理由の開示は、噺 一九七三年法による解雇理由の開示の揚合とは異なり、労働者の請求とは関係なく、当然に懲戒処分の通知に記載さ れ なければならない。 ︵11︶ ︵⑫︶ なお、先の事情聴取手続の対象となる制裁については、右の通知は、会合の日からまる一日後およぴ一か月後まで の間になされなければならない︵L二一二−四一条第二項後段︶。一九七三年法による解雇規制が単に一日の冷却期 521 一橋大学研究年報 法学研究 14 ︵13︶ 間のみを定めていたのに比べて、懲戒処分行使の最長期限を明示した点でも、一定の改善を図ったものと言える。 叫 手続違反の制裁 以上のような形式に違反する制裁については、労働審判所はそれを無効とすることができ る︵L二一二−四三条第二項︶。しかし新法は、それ以上に、一九七三年法による解雇手続の揚合のような、手続の 事後的補完や金銭賠償については定めていない。そのため、使用者は改めて法定の形式性を備えることによって有効 に懲戒処分を行使しうるのか否か、あるいは手続違反を理由とする金銭賠償の可否や内容などは、今後に残された問 題である。また、右の規定は解雇については適用されない︵同条第三項︶ため、特に一九七三年法による解雇手続に 服さない解雇については、懲戒手続規制の適用は認められる︵L一二二ー四一条第四項︶ものの、その違反について の特別の制裁は存在しないことになる。 ︵耳︶ ︵15︶ ㈲ 免責・失効期間 このほか一九八二年法は、使用者による懲戒処分の行使に対して二つの観点から時間的な制 約を加えた。一つは、一種の時効期間であって、使用者は労働者の︿非行﹀とされる行為を知った日から二か月を超 えて、それだけでは︵29器ロ一︶懲戒責任追及を開始する理由とはなしえない。ただし、その行為が刑事訴追を受け ︵16︶ ︵17︶ たときは、この限りでない︵L一二二ー四四条第一項︶。第二は、既に行使された懲戒処分の失効期間であり、懲戒 ︵18V 責任の追及から三年を経過した制裁は、新たな制裁を補強するために援用されることはできない︵同条第二項︶。 ︵−︶ L一二二−一四ー六条第一項。前節二2注︵5︶参照。 ︵2︶懲戒手続規制の適用には、労働契約の期間の定めの有無や勤続年数も関係しない。 ただし、制裁形態による制限があるこ とは、ωで述ぺる。 ︵3︶卑琶。f一。男’■。﹃も宕洋>日o艮二①℃o一暮O。≦。αΦ切勺■客同こu’oo■一。。。ρ つまO.Oい<Φ昌三PU、ω,一〇〇〇い㌧マ “QQoQ 522 懲戒処分法理の比較法的研究 H ︵4︶ この通知は、受領証と引き換えに労働者に手渡されるか、書留郵便でなされねばならない︵R一二二ー一七条第二項︶。 ︵5︶ 通知から会合までの期間については定められていないが、労働者が補佐人を選定するなどの最小限の準備期間の保障は必 ︵6︶ これによって、たとえば戒告についても、それが繰り返されることによって出勤停止や解雇が科されるように定められて 要であろう︵ω哩δお辞P罰型豊uり,一〇〇。ρマωa︶。 いるときは、事情聴取の手続が義務的になるとされる︵ω一讐窮痒9刃型U・oo・むo。ρマQ&︶。 ︵8︶ ω09轟巽邑一SPq一SP一,幻■P乱9ωoρ認宣昌らNPq這Q。o㌧一.押うo。oそのような哲定的措置が認められ ︵7︶企業委員会委員につきL四三六−一条、従業員代表者につきL四二五ー一条、組合代表者につきL四一二ー一八条。 曽冒ぎ一SPU・Gooρ一■男■やooO る限り、その後にとられた最終的処分との間に二重処罰の問題は生じない。ωoρoo8<ー一So。いU﹂鶏Pい罰う80一ωoΩ ︵9︶ いくつかの立法解説は、使用者はその間の賃金支払義務を免れないとしている。Rω蒔8お洋ρ即型O■oD、Go。卜。’マ O轟禽く磐三PO、ω■一〇〇。い一℃■阜o。O ︵10︶ この通知の態様は、事情聴取のための通知の揚合︵前掲注︵4︶参照︶と同一である︵R一二二−一八条第二項︶。 ︵11︶ 一九七三年法では、解雇事由の書面による開示は労働者の書面の要求があってはじめてなされるぺきものとされ︵L一二 ︵12︶期間計算には初日を算入せず、期間満了日が土曜、日曜、休祭日のときは、次の平日に延期される︵R一ニニー一九条︶。 二−一四−二条︶、しかも企業規模と勤続年数による制限があった︵L一二二−一四ー六条︶。 ︵B︶ L一二二ー︸四−一条は、解雇の通知は呼ぴ出しの日からまる一日を置いて発送されねばならないとしていたが、いつま ω■一〇即ヨニ﹃gぎN。価自こマ奪一 でに発送すべきかについては定めがない。そのため、遅延した解雇通知が一つの問題とされていた。ρ頴一誘一9りo。一9 ︵U︶ ■図o㌣90p U ■ 一 〇 〇 。 い ㌧ Ω 員 8 、 や O ︵15︶注︵12︶参照 。 ︵16︶ これが、呼ぴ出し、事情聴取のための会合、制裁の通知のうちいずれを意味するのかについては問題がある。R甘ぐ⋮自 523 一橋大学研究年報 法学研究 14 ∪.ω●一〇〇。甜℃■鵠O ︵17︶ 逆に、労働者の新たな非行について、二か月以前の行為を補強のため援用することは可能であろう︵ω2欝“宣○﹂oo。ρ や&o。いΩ﹃2§お身旨目帥房むo。いも︾息も異なる見解として、ω蒔9器窪P勾・コqP這o。b・℃やいま︶。ただし、それが ︵18︶ ただし、制裁の記録そのものを除去することまでは要求されていない。 いつまで、またどのような条件の下で可能かは、間題が残る。 4 裁判所による審 査 ω 裁判所の審査権限 一九八二年によってもたらされた懲戒処分法制の改革のなかでも、特に重要な意味を持 つものが、裁判所の審査権限の拡大であろう。それは、単に新たな懲戒処分規制の実効性を確保するためのものであ るだけでなく、従来の判例を大幅に修正する意味を有しているからである。新法は、この点について次のような規定 を置いた。 L=三ー四三条第一項争いのあるときは、労働審判所が、とられた手続の適法性、およぴ労働者に帰せられる行為が制裁を 正当化する性質のものであるか否かを評価するものとする。︵後略︶ こ と が で き る 。 同条第二項 労働審判所は、形式にのっとらず、または正当化されず、または犯された︿非行﹀と均衡しない制裁を無効とする このように、懲戒処分に関する裁判所の審査権限は、単にその形式・手続上の適法性や、その理由となった労働者 の行為の存否や性質のみならず、︿非行﹀と処分の均衡性の問題についても及ぶことになった。このことの意義につ ︵−︶ いては既に指摘したが、そのほか、違法な懲戒処分の救済として、明確に﹁無効﹂を言渡す可能性が開かれたことも 524 懲戒処分法理の比較法的研究 H 注目される。一九七三年法による違法解雇の救済が金銭賠償にとどめられていたことと比較すれぱ、一つの前進と言 えるであろう。また、右の規定は、無効の救済を単に可能性として定めるにとどまり、その限りでは、無効以外の救 ︵2︶ 済、たとえば損害賠償の支払などに代えることもできるように読めるが、やはり無効とすることが立法の趣旨にかな うものであろう。 ︵3︶ ただし、右の規定は、解雇については適用されない︵L一二二−四三条第三項︶。つまり、一九八二年法は、解雇 についても、それが労働者の︿非行﹀を理由とする限りで一定の要件上、手続上の改善をもたらしたものの、それに ︵4︶ 対する救済に関しては、一九七三年法による状態をそのまま維持したわけである。これによって、今回の懲戒処分規 制の意義が大きく減殺されたことは確かであろう。 なお、裁判官が過重な制裁の引き下げを命ずることができるか否かについては、その旨の修正案が否決されたこと もあり、否定的に解されている。また、懲戒処分が手続違反または過重であることの故に無効とされた揚合に、使用 ︵5︶ 者は改めて手続を履行し、またはその程度を引き下げることによって再び懲戒処分を行使しうるか否かについては、 ︵6︶ 今のところ学説の見解は分かれている。 ③ 立証責任 一九八二年法は、懲戒処分をめぐる訴訟における立証責任の問題についても、重大な改革をもた らした。L一二二−四三条第一項は、右に引用した文言に続けて、次のように規定している。 L一二二−四三条第一項 ︵前略︶使用者は労働審判所に対して、制裁を行使するために考慮した諸要因を提示しなければなら と考えられるすぺての証拠手段を命じた後に、その心証を形成するものとする。疑わしいときは、労働者の利益となる。 ない。労働審判所は、それらの要因およぴ労働者によりその主張の証拠として提示される要因を審査し、必要なときは、有益 ここでは特に、第一次的な証拠資料の提示が使用者に義務づけられたこと、およぴ﹁疑わしきは被告人の利益に﹂ 525 一橋大学研究年報 法学研究 14 という刑事法上の原則と同一の原則が新たに導入された点が注目される。これによって、一九七三年法においては不 ︵7︶ ︵8︶ 完全なものにとどまった﹁立証責任の転換﹂は、懲戒処分に関する限りでは、明確な形で実現したわけである。今後 の判例における実際上の運用が注目される。 なお、右の規定もまた、解雇については適用されない︵L一二二−四三条第三項︶。この点でも、同じ懲戒処分で ありながら、解雇とそれ以外の懲戒処分形態の間には、明確な一線が画されることになった。 ︵9V ︵2︶<①目凶Fu。oo■這。。Q一℃■おo ︵−︶ 前掲2注︵16︶を参照。 ︵4︶従って、懲戒としての解雇もあくまで﹁現実的かつ強度の事由﹂の観点から評価されるにとどまり、たとえ︿非行﹀との ︵3︶く①目5qω■む。。ρやお9盟αqぎ聾貫刃型∪●ψち。。N旨℃し≒ 均衡性を欠き、法定手続に反する揚合であっても無効とはされない。また、解雇法上の手続規定による保護を受けない解雇に つき、前述3ωを参照。ただし、懲戒処分としての規制に違反した解雇が、解雇法上の救済にいかなる影響を及ぼすかという ︵5︶く①目芦qψ這。。ρやおo簿㎝,こ塁自30あレ。・。Q︾や睾ごωo養NFu.9這。。ρマa。 問題は残る。 ︵6︶ 手続およぴ制裁の選択における危険は使用者が負うことや、L一二二−四四条によりく非行Vの存在を知ってから二か月 一。。。ρや象。。︶と、無効の言渡し確定から改めて二か月の期間が開始するとして肯定的なもの︵く窪三PO・oo・一。。。ωもお一︶ 以降は懲戒貴任の追及はできないことの故に、否定的に解するもの︵切2器Fqρ這o。ρP轟$︸oo酋・o曇8・刃型U・oo・ ︵7︶ ﹁疑わしいときは、労働者の利益となる。﹂︵、、oo[巨3耳①ω昌ω巨。﹂一冥魯斤。霊絶豊①・.、︶という文言は、当初の立法草 が見られる。 ︵8︶9く窪巳P導oo・這。。ρやおご甘く蓉3qψむ。。き℃・監o解雇の立証責任の問題に関しては、前節二3を参照。 案にはなかったものであるが、共産党の修正案によって付加された。 526 懲戒処分法理の比較法的研究 H ︵9︶R<①⋮一pu,ω■一。。。Qも’お一.ξ96器pu﹂。。。Qも,。①訂, 三 国 九 八 二 年 法 の 問 題 点 と 懲 戒 処 分 法 理 へ の 影 響 以上のように、一九八二年法は、懲戒処分をめぐる旧来の法状態に根本的な変革をもたらした。その特色は、第一 に最小限の懲戒手続の保障、第二に懲戒処分の相当性︵制裁とく非行Vの均衡性︶の要請、第三に裁判所の審査権限 の拡大と立証責任の転換に要約されるであろう。これによって、これまで永年にわたって事実上の権限として放任さ れてきた使用者の懲戒権がはじめて本格的な法的規制を受けることになっただけでなく、懲戒処分の審査について一 貫して消極的な態度を維持してきた判例も、大幅な変更を迫られることになった。このことが、使用者の懲戒権に対 ︵−︶ する労働者の地位の改善とその保護にとって有する意義については、改めて指摘するまでもないであろう。 しかし、今回の法改正がそれ自体として少なからざる制度的、理論的欠陥ないしは問題点を伴うものであることは、 既にその内容に関連して言及したところであるが、より基本的な問題点としては次の点を指摘しうると思われる。 ︵2︶ まず、今回新たに導入された手続的規制はあくまで最小限のものにとどまり、公共部門の企業や一部の労働協約に 見られる懲戒委員会の制度は取り入れられず、従業員代表者や組合代表者の役割も明確にされなかった。また、使用 者は依然として一方的に就業規則による懲戒規定を制定しうるのであり、懲戒事由の限定的列挙も法の要請するとこ ろとはならなかった。従って、使用者は、新法の下においてもなお、排他的に懲戒規定を制定し、懲戒処分を行使し うるのであって、その限りでは、今回の法改正は、そのような使用者の懲戒権に対して新たな合法性の根拠を与えた ︵3︶ とも言える。ただし、一九八二年の一連の法改革は、他方で従業員代表制度の強化と企業レベルの団体交渉権の導入 ︵4︶ をもたらすものであり、それらとの関連でも、今後の労使関係の実態面での動向が注目される。 527 一橋大学研究年報 法学研究 14 次に、法制度上、懲戒法と解雇法の不完全な分離がもたらされたことが挙げられる。解雇は、確かにそれが労働者 8 のく非行Vを理由とする制裁である限りでは手続上・要件上の新たな規制に服するものの、それについての特別の救 5 済手段は定められておらず、あくまで従来の解雇法制の枠内での法的救済が可能であるにすぎない。このように、最 も重い制裁である解雇のみが他の制裁措置と区別され、異なる取扱を受けること自体が、一つの大きな制度的欠陥で あり、早急な立法的調整が要請されているゆえんでもある。 ︵5︶ 一方、今回の立法的改革は、今後のフランスにおける懲戒処分法理に対しても、重大な影響を与える.一とになろう。 今回の立法によって、従来の判例が多くの点で変更を余儀なくされることは既に指摘したが、恐らく今後の懲戒処分 をめぐる法的議論は、新法の解釈と、それに関する新たな判例を中心に展開されることになると思われる。その揚合 に注目されるのは、特に次の点である。 ︵6︶ まず、今回の法改正によっても、懲戒事由の事前の明示が要求されず、しかも懲戒処分の対象としての労働者の く非行Vが何ら定義づけられなかったこととの関連で、そのような︿非行﹀の法的性質や客観的限界性の問題が、改 めて重要な意味を持つことになろう。これを契機として、その前提としての懲戒権の法的根拠や性質にっいての議論 ︵7︶ が、再ぴ活性化する可能性もある。 ︵8︶ 次に、今回の法改正によって、裁判所の審査権限が拡大され、特に懲戒処分の相当性評価についてもそれが及ぶこ とになったが、そのことは、単に従来の判例の変更を要請するものであるだけでなく、懲戒処分法理が展開されるた めの理論的前提そのものを変更するという意味を有している。懲戒処分についての実質的な司法審査を拒むことによ って、懲戒法理の内容を論ずることそのものの実益すら乏しいものとしてきた従来の判例の障壁は除去され、今後は、 裁判所による広範な司法審査を前提として、懲戒処分法理のより具体的で実質的な内容についての議論が深められる 懲戒処分法理の比較法的研究 H ための条件が整えられることになったからである。 とはいえ、新たな懲戒法への対応は、いまようやく開始されたばかりである。特に判例の動向については、これま でそれが解雇および懲戒処分に関して示してきた態度に照らして、必ずしも予断を許さない。今回の立法がフランス ︵9︶ における懲戒処分法理にいかなる影響を与えるのか、果たしてそのことが全く新たな懲戒処分法理の形成をもたらす のか否かについての評価は、いずれにせよ今後の学説・判例の展開に侯たざるをえない。 ︵1︶ 一九八二年法によって、労働者の防御権が保障され、裁判所によるコントロールが認められたことをとらえて、懲戒﹁権﹂ O“冒く葭①﹃︸U,oo﹂Oo。ρ℃■鴇o。﹄隠ρぎ3︵刈︶ ︵、.費鼻..良巴喜昌幕︶の出現について語るものは多い。Ω■切8目ドU・9むo。即℃■“q曾■岩〒O器PU・一〇〇。いいOぼ9・や ︵3︶ この意味では、一九七三年法が使用者の一方的な労働契約解消権限を廃止しなかったのと同様、一九八二年法は使用者の ︵2︶ これらの規定と一九八二年法による手続規制との関係につき、く9三p曼ψち。。曾や高〇一99参照。 ︵4︶Ω■冒<⋮①さu。ω﹂。Q。甜℃。aN 懲戒権限︵℃2<o詫色。・。旦ぎ巴﹃。︶を完全に廃止するには至らなかった。9ω2器ダ∪■ρ這o。ρ℃・&ω ︵5︶Rωo琶N貫U。○●這。。Nや&。。3∴ξ86器目り∪し。。。ρ9﹃8も﹂9<。目5∪ーω﹂。。。い︸やおい為。・邑戸∪・ ︵6︶ 新法は、﹁使用者のとりうる制裁の性質およぴ段階﹂を就業規則の記載事項として要求するものの︵L一二二−三四条︶、 oo”一〇〇〇い㌧や軌ま9ω■ ︵7︶<。目旦口oo﹂o。。ρ℃・おN。嘉■ 懲戒事由を予め列挙すべきこと、懲戒処分の行使がそのような事由に限定されることまでは定めていない。 ︵8︶新法のいう︿非行﹀の意味について、既に異なる理解が現われていること︵ただし従来の議論の延長ではあるが︶につい ては、先に指摘した。 ︵9︶今後の判例が、行政法における法技術の影響を受ける可能性につき、冨く葭9U、oり﹂鵠辞℃■睾い9。。甲を参照。少なく 529 一橋大学研究年報 法学研究 14 530 とも、公務員法と労働法における懲戒処分法理の比較もしくは統一が、 今後の一つの課題となるであろう。そのための前提は、 一応整ったと言 え る 。 第七章 小 ︵2︶ このことの原因は、両国の法定従業員代表制度の内容およぴ沿革の差異に求められるであろう︵ドイツにおける沿革につ であるか否かをはじめから問題とせず、一貫して解雇権の行使であることを前提としている。 ︵−︶ ただし、有力な学説が懲戒としての解雇を懲戒権によって構成することを否定しているほか、判例はそれが懲戒権の行使 さることながら、むしろ学説と判例の間の古くからの相克を主要な軸として展開されてきたものであった。 使用者の権限の間題として位置づけられる。そしてこのようなフランスにおける懲戒権法理は、学説相互間の論争も 関連で論じられることはない。それは一般に、フランス労働法に特有の法的範晴である企業、およぴその一環である ︵ 2 ︶ においてもドイッに類似した法定従業員代表制度が存在するが、ドイツの揚合とは異なり、懲戒権の問題がそれとの た懲戒規定に基づいて懲戒処分が行使されるという点でも、その理論的前提はわが国と同一である。確かにフランス が国のそれと類似する。しかも、就業規則が法制度上は使用者の一方的制定にかかり、多くの揚合にそれに定められ じられるという点で、フランスにおける懲戒処分法理の性格は、既に検討したドイツの揚合とは異なり、明らかにわ きる包括的な権限としてとらえられるものであり、懲戒権それ自体について、法的根拠や要件、限界などの問題が論 ︵1︶ に関する法理として形成されてきた。この懲戒権の概念は、使用者が解雇を含む多様な懲戒処分を行使することので 定法上の規定が極めて乏しいという状態の下で、少なくとも一九三〇年代後半の制度説の出現以降、使用者の懲戒権 ω 懲戒処分法理の基本的特質 フランスにおける私的労使関係の懲戒処分をめぐる法理論は、それに関する実 括 懲戒処分法理の比較法的研究 H き、本稿第一部・法学研究B一九二頁以下、二三二頁以下、 三一七頁以下参照︶。フランスにおいては、企業委員会や従業員 代表者が懲戒処分の問題に関与すべき旨の定めは存在せず、 就業規則、従って懲戒規定の制定についても、単に意見を述ぺう るにすぎない。 図 懲戒権の法的性格・根拠 懲戒権の法的根拠に関する学説・判例は、契約説、制度説、およびそれらの折衷 説︵ただしその内容は多様︶に大別できる。このうちフランスの懲戒法理を特徴づけるものが制度説であり、最近で ︵1︶ は学説に関する限り折衷説的見解が有力となりつつあるが、なお制度説の影響は強く残っている。 ︵2︶ 制度説は、かつての通説・判例であった契約説に対する批判のうえに、いわゆる制度理論を企業の内部関係にも拡 張し、ドイツの労働関係理論にも依拠することによって、企業の長としての使用者の資格に内在する懲戒権を承認し、 それに基づいてフランスにおいてはじめて一つの体系的な懲戒権法理を形成した。それは、当時の学説・判例の状況、 およぴその後の懲戒処分法理の展開を見る限り、次のような積極的意義を有するものであった。 第一に、懲戒処分法理に集団的・組織的視点を導入し、伝統的な契約理論に基づく個別的把握を否定したことであ る。これによって、懲戒処分はその実態に則した統一的理論に服せしめられ、その共通の要件や懲戒処分相互間の関 連性︵制裁としての段階性、制裁と違反の均衡性︶を論ずる可能性が開かれることになった。第二に、制度説が懲戒 権を根拠づけるために持ち出した論拠である企業の共同の利益ないし目的や、使用者の企業運営に関する責任が、同 時に懲戒権を客観的に限界づけるための論拠ともされた点である。制度説は、懲戒権を制度としての企業に求めるこ とによって、契約理論によっては当然には導きえない懲戒権の客観的限界性を主張したのである。そしてこのような 懲戒権の限界に関する目的論的な解釈方法は、その後の懲戒法理の展開に対しても大きな影響を及ぼした。第三に、 そのような懲戒権の限界性について、裁判所による広範な司法審査を主張した点である。ただしこのことは、単に当 531 一橋大学研究年報 法学研究 14 時の判例に対する批判としてだけではなく、他方で制度説が主張した﹁不文の懲戒権﹂を正当化する論拠としての意 味をも有するものであった。 ︵3︶ このような制度説に対しては、企業の制度論的把握それ自体やそれを独自の法律関係とすること、企業の共同の利 益の優位などをめぐって多くの批判が加えられたが、そのほかにも、明文の懲戒規定が存在する場合に裁判所の介入 を限定するなど理論的に一貫しない点もあり、また契約法理との分離も不完全なままである。近年次第に折衷説的な 立揚が有力となり、制度説の中にも契約理論への傾倒が見られるが、それはおそらく、制度説の有する積極的意義を 認めながらも、その理論的欠陥を補い、契約法理との調和を図ろうとする試みと評しうるであろう。しかし同時に、 制度説出現以降の学説の展開を見る限り、たとえ懲戒権の法形式上の根拠を契約に求める立揚においても、特にその 限界を論ずるにあたっては、何らかの形で制度説の主張した企業および労働関係の集団的・組織的性格を考慮せざる をえないことを示している。それはある意味では、懲戒権理論における制度理論と契約理論の融合であり、懲戒権の 特質に則した契約という法形式の制度理論による実質化の傾向である。 一方、判例においては、一九四〇年代から五〇年代にかけて、﹁使用者の内在的懲戒権﹂に言及する破棄院判例が 相次いで現われ、明示の規定や合意が存在しない揚合にもその行使が認められたことにより、明らかに制度説の影響 が窺われた。しかし、そこでいう懲戒権とは主として出勤停止処分に関して述ぺられるものであり、解雇については、 あくまで従来どおりの契約理論を基礎とする解雇法理の枠内で処理され、懲戒権の行使としてはとらえられていない。 しかも一九六〇年代以降は、右の﹁内在的懲戒権﹂に代わって﹁企業の円滑な運営という利益において行使される懲 戒権﹂が破棄院判例における常套句となるが、それは懲戒権を根拠づけるものというよりは、むしろ事実審裁判官の 審査権限を制約するための論拠であった。すなわち、懲戒処分が少なくとも就業規則の制限内で行使される限り、そ 532 懲戒処分法理の比較法的研究 H れが相当性を欠くことの故にその適法性を否認することは、事実審裁判官が自己の評価を企業運営について責任を有 する使用者のそれに置き換えるものとして、厳に否定されたのである。それは、企業運営およびそのための諸権限の 行使について使用者こそが﹁唯一の判定者﹂であるとする判例の基本的理解と、同一の基盤に立つものであった。 このよう癒判例に対しては、使用者による恣意的な懲戒権行使を放任するものとして、学説によって強い批判が加 えられたが、一九八二年の立法的規制が実現するに至るまで、遂に変更されるところとはならなかった。 ︵1︶ フランスにおいては、わが国やかつてのドイツにおけるような、懲戒権の根拠を立法による国家の授権に求める見解は存 秩序や規律に関する一般的規定も一切存在しなかった︵制裁に関する定めが就業規則の記載事項とされることもなかった︶こ 在しない。これは、フランス法上、罰金の原則的禁止規定を除き、懲戒や制裁に関する規定はもちろん、企業や経営における とによるものと思われる。 ︵2︶ ただし、かつての契約説は罰金を中心として個々の懲戒処分を個別的に契約理論によって説明するものにとどまり、制度 ︵3︶ 制度説は、制度としての企業を法律および契約と並ぶ第三の法律関係形成の基礎としてとらえる。その限りでは、ドイッ 説の登揚以降の新たな契約説とは、その内容や性格において同列には論じえないものであった。 におけるナチス時代以降の多数説的理解と同一である。しかし、制度説にあっては、それによって経営協同体ないし経営団体 などの点で、ドイツにおける理論とは明確に異なる。 ではなく使用者の権限を基礎づけるものであること、解雇や出勤停止処分をも含む幅広い懲戒権を基礎づけるものであること 偶 懲戒処分の形態と対象 制度説によれば、懲戒処分は、労働者の規律違反に対する制裁として、使用者によ る契約上の制裁としての民事罰や企業の組織づけのための措置とは理論的に明確に区別される。しかし、実際にはそ れらはそれぞれの形態や効果のうえからは区別しえない揚合が多く、結局は使用者の動機いかんという主観的要素に よっていずれかの措置かを判断するほかはないという。そのため、懲戒処分の境界設定は、必然的に流動的なものと 533 一橋大学研究年報 法学研究 14 ならざるをえない。たとえば解雇は、それが労働者の規律違反を理由とする限りで懲戒権の行使としてとらえられ、 懲戒処分としての一般的要件や法的評価に服するというのであって、その意味では、解雇の懲戒権による構成は、ど ちらかと言えば事後的な性格づけの間題にすぎないものとなる。また、懲戒権の概念自体、予めその具体的な法的効 ︵1︶ 果を特定しうるものではなく、むしろ使用者が労働者に対して何らかの懲戒処分を加えることのできる一般的権能と いうにふさわしい。 同じことは、懲戒処分の対象についてもあてはまる。懲戒処分の対象は、規律上の︿非行﹀として、民事的く非 行Vや職業的︿非行﹀とは区別されるが、それはせいぜい労働者の規則違反や命令違反として理解されているにとど まり、また、一個の行為が同時にそれらの複数のく非行Vに当たることも認められているのであって、その具体的内 容を特定することは著しく困難である。むしろフランスの従来の議論を見る限り、個々の懲戒事由やその限界につい て立ち入って論じられること自体が必ずしも多くはなく、わが国やドイツのように、それを企業秩序や経営秩序の概 ︵2︶ 念と結ぴ付け、その意義や内容を間題とするという理論的関心も強くはないように思われる。 このような理論状況がもたらされた原因がどこにあるのかは必ずしも一概には言えないが、その一つとして従来の 判例の状態が挙げられよう。すなわち、判例においては、まず懲戒としてなされた解雇は、懲戒権の行使としてでは なくあくまで労働契約上の解雇権の行使としてとらえられ、解雇の自由を前提とする伝統的解雇法理の枠内で処理さ れた。そのため、そのような解雇の法的評価においてその理由が問題とされるのも、解雇権濫用の成否の一っの要素 として、または解雇に伴う諸手当の支給要件や解雇規則法規の除外要件としての労働者の一般的な︿非行﹀の存否. 程度に関してであって、それが特に懲戒としての解雇の事由たりうるか否か、懲戒としての解雇に相当するか否かと いう観点からの評価はなされない。また、解雇以外の懲戒処分についても、判例は、使用者こそが企業の円滑な運営 ︵3︶ 534 懲戒処分法理の比較法的研究 H についての責任を有することを理由に、使用者に対して懲戒処分の行使について大幅な裁量権を認め、労働者の︿非 行﹀が存在する限りで裁判所による懲戒処分の相当性評価を原則的に否定しており、この点でも懲戒処分の対象につ いての具体的評価基準や客観的限界が問題とされる余地は事実上存在しない。結局このような判例の状況の下におい ては、懲戒処分の限界を論ずるための前提そのものが制約されているわけであって、ひいてはそれを論ずることの実 益すら乏しいものとならざるを得ないのである。まさにこの点に、従来のフランス懲戒処分法理の最大の障壁とも言 う べ きものがあった。 ︵1︶ フランスでは、わが国のように退職金不支給との関連で懲戒解雇の概念が間題とされることはない。また、学説の中には 的な理解であるとは言えない。結局、懲戒解雇︵=88鰐冨暮9器ロ<o一岳ω。覚ぼ巴お︶という揚合の﹁懲戒﹂の語は特定の 労働者の重大な︿非行﹀を理由とする即時解雇を懲戒解雇としてとらえる見解もあるが︵たとえぱデュランなど︶、それが一般 ︵2︶ 制度説は、もともと懲戒権を企業運営についての使用者の貴任と企業の共同の利益・目的という概括的な根拠によってと 法的効果を意味するものではなく、むしろ労働者の︿非行﹀を理由に制裁としてなされる解雇を形容するものにすぎない。 らえるものであり、その対象を積極的に限定するための具体的基準を呈示するものではなかった。また、制度説に対する批判 については強い批判を加えるものの、やはりそのような基準は明確でない。 的学説においても、制度説があまりにも広範な企業運営についての責任とそのための権限行使の可能性を使用者に認めること ︵3︶ すなわち、解雇に関する限り、そこで問題とされる労働者の︿非行﹀はその性格において限定されておらず、判例にとっ て労働者の︿非行﹀が規律上のものか否かは重要な意味を持たないのである。また、フランス法上、︿非行﹀︵融耳o︶の概念 自体が一般に極めて広範なものであり、漠然としたものであることも指摘しておかねばならない。 倒 懲戒処分法理の限界 フランスにおけるこれまでの懲戒処分法理の展開は、その内容自体もさることながら、 懲戒処分法理そのものの存立基盤やその限界性についても、興味深い示唆を提供するものであるように思われる。 535 一橋大学研究年報 法学研究 14 うな使用者の自由な解雇権の承認を前提とする限り、そこに懲戒権の独自の存在意義を認める余地はないと一一一一口える。 5 第一に、解雇権と懲戒権、およびそれらの法理の間の関連である。すなわち、従前のフランスの判例に示されるよ 6 ヨ 金銭的制裁を除くすべての懲戒処分形態は解雇権によって説明し尽されうるのであり、使用者はその自由な解雇権を パこ 主張することによって、懲戒権行使に伴うあらゆる法的制約を免れうるからである。また、その限りでは、通常の解 雇権行使とは区別された懲戒解雇という独自の法的範疇が成立する余地もない。従って、法的な意味における懲戒権 の概念とその固有の法理の成立は、必然的に使用者の自由な解雇権の否認を前提とする。﹁懲戒権は、一方的な解約 ハ レ 権が消滅したときにはじめて出現しうるものである。﹂との指摘は、まさにそのことを端的に表現するものである。 その意味で、懲戒権は、自由な解雇権が否定されることによってはじめて、それが正当化されるための独自の根拠を 必要とするのである。 第二に、懲戒処分をめぐる司法審査にかかわる懲戒処分法理の限界性である。先に指摘したように、フランスの判 例が一貫して懲戒処分の相当性評価を拒否したことは、懲戒処分の限界性を論ずるための前提そのものを否定すると いう意味を有し、そのため学説による判例に対する批判は、懲戒法理の具体的内容以前の間題として展開されざるを えなかった。つまり、懲戒処分の法理的限界性自体が裁判所の広範な審査によって確保されざるをえないものである 以上、そのような判例の状態は、既にその前提において懲戒法理の展開を制約し、規定していたのである。その意味 で、フランスにおける懲戒法理の展開は、それ自体が常にそのような判例による制約を所与の条件とするものであり、 あくまでもそれとの関連において理解すぺきものであった。 フランスにおいては、一九八二年の法改正によって、新たに懲戒処分に関する立法的規制が整備されるに至った。 それは確かに、従来の立法上の空隙を埋め、労働者の地位を大幅に改善するものである点で積極的な意義を有するも 懲戒処分法理の比較法的研究 n のではあるが、同時にそのような立法が必要とされざるをえなかったこと自体、フランスにおける懲戒処分法理の限 界性を暗示するものであるように思われる。 ︵−︶このことは、制度説に立つデ、ランらによ.ても主張されているが、それは明らかに制度説の論旨と蒼する︵第四章第 三節四参照︶。 ︵2︶o昏㊦身奨\ξ86§る。aーも﹄這 537
© Copyright 2026