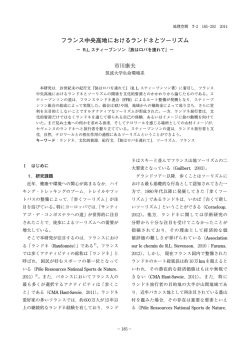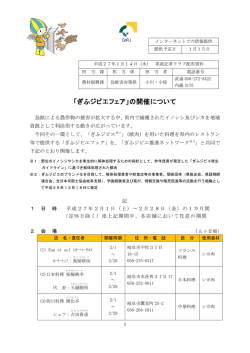はじめに 徳富蘇峰 将来の日本 緒言
はじめに 蘇峰の『将来の日本』は、明治維新のほぼ 20 年後、明治 19 年に発表された。明治維新の偉業 を賛美し、今後の日本社会の進路を軍備社会から経済(国富)社会へ、貴族社会から平民社会へ と、熱烈に説いたが、 残念ながら歴史はなお軍備社会へと驀進し、蘇峰の願望は、それから 60 年後の太平洋戦争の終結まで持ち越された。 しかし彼の簡明で直截的な論理は、一面素朴であるとしても、あの時代にこういう思想家を持った ことに、日本人は誇りを持って良いと思う。 原本はネット上の青空文庫で読めます。 徳富蘇峰 将来の日本 私は人情を重んずることを知り、自分を愛し、人を愛し、国を愛することを知り、真理の線路を走り、 正義を踏んで恐れないことを知った。これはすべて両親の教育のお蔭である。この冊子を著述した のも、両親の教育の結果が表われたものに過ぎない。私が著述を世に出すのは、これが最初であ る。これにより少しでも両親の老境を慰め、両親の笑顔を開く第一歩としたい。私は謹んでこの冊子 を愛しかつ尊敬する両親の膝下(ひざもと)に献ずる。 緒言 将来の日本という問題は、ついに私を駆り立て、この冊子を著述する動機となった。私は高尚深 奥な哲学者としてこの問題を論ずるのではない。また活発雄飛の政治家として説くのでもない。た だ忠実、真摯(しんし)な日本人の一人として、脳中に湧いて来るものを、はばからず、恐れず、吐 露したのみである。 私は強いて生産主義を取ろうとは思わない。しかしわが国の将来の情勢の赴くところ、その勢い 1 は止めることが出来ないと知る。私は単純な民主論者ではない。しかしすでに社会の生産の側面 が、一変して平民社会となるのは確実だと知る。私はどんな場合にも、どのような代価を払っても、 ただ平和論を唱える者ではない。しかしすでに日本社会が平民社会であれば、社会の運動は一転 して平和主義の運動となるのも間違いないと知る。私はもとより日本全体の利益と幸福を目的として 議論をする。しかしその議論の標準となるものはただ一軒の茅屋(ぼうおく)に住む人民である。な ぜなら、これらの人民の利益と幸福が進歩すれば、日本全体の利益と幸福が増進するのは論をま たないからである。 私の議論の原理はヨーロッパ諸学士の思想から生まれて来たものが少なくないが、これを事実に 適用して解釈するのは、まったく私自身の責任である。もし私の議論に不完全なものがあれば、どう か許してもらいたい。私は、辺鄙な土地で、相談する友もなく、参考の書に乏しく、ことに一ヵ月に足 らない短時間のうちにこの冊子を書いたからである。そしてこのように急いで出版できたのは、社友 諸氏が植字校正等の労を分ってくれたからである。私はここに明記してその労に感謝する。 将来の日本は実に多事の日本である。この冊子の論ずるところはただ概略に過ぎない。思うに国 会・外交・貿易・財政・兵備・地方制度・宗教・学問・教育・工芸・製造等に関し、論ずべき点は多々 ある。もし他日機会があれば、私は必ず本論の通則を細かに砕いて、開陳したいと思う。 私がこの冊子を著わしたのは、もともと同志の人に配りその批評を乞うためであった。しかし諸友 の懇切な勧めにより、ついに大胆にも、この冊子の運命を日本の現今の社会に委託することになっ た。この冊子が世間より冷遇されるも運命、厚遇されるも運命である。運命である以上、私は何も言 うことはない。 明治十九年十月十日 東京において 著者記 第一回 洪水の後には洪水あり(緒論) 2 「朕の後には洪水が起こるであろう。」とは、ルイ十五世が死に直面してフランスの将来を予言した 辞世である。今や洪水の時代はわが国にもやって来た。我らもまた波乱重々のうちに立っている。 もし人が来て私にわが国の将来を問うたら、私はどう答えたらいいのか。 人が常に知りたいと思うもの、それは「将来」である。ことにわが日本の将来は最大の関心事であ る。なぜなら現今の日本は、ノアの子孫が雑草のはびこるバベルの原野で、天に達する石塔を築こ うと企てた古えの文明から、北方蛮人の後継者が鉄と電気によって、ほとんど地球上の表面を一新 する近時の文明に至るまで、人類が記憶するいかなる時代にも比較出来ないほどの、一種奇怪な、 喜んでいいのか驚いていいのか分らない時代を迎えているからである。 変化というものは万物の大法則だから、わが国が昔の面目を一変したとしても、驚くにはあたらな い。しかし、その変化があまりに急で、かつその方向が意外な針路に向かって走っている点に関し ては、誰もが驚くであろう。かのドレーパー氏は情けないことに、「東洋文明の命運はただ墳墓があ るだけ」と放言したが、わが国の文明は、三十年前には気息えんえんとして前途の覚束ない旅行を していたにもかかわらず、不思議なことに、その針路を電光石火一変し、さらに急速な歩調でヨーロ ッパ文明の後を追走し、これと競争するまでの形勢となっている。これには日本人自身も訝(いぶか) りかつ祝うところであり、欧米人士も大きな関心を抱いている。 これは理由のないことではない。もし試みに、徳川将軍家斉公全盛のときに死んだ江戸の市民 を、今、墓の中より呼び起こし、銀座の中央に立たせるとする。街頭に並ぶ家屋、その店頭に陳列 する商品、街を往来する者、彼らが話し相談するもの、これを見た江戸の市民は、これが江戸かと 夢にも理解できないだろう。まるであの夢想兵衛が飄々として凧にまたがり、天外万里の異郷に漂 着した想いをするであろう。 今日の変化は退歩の変化ではなく、進歩の変化である。今日の戦場は最後の戦場ではなく、初 陣の戦場である。今日の門出は絶望の門出ではなく、希望の門出である。見るがよい。十一世紀ヨ ーロッパの暗黒時代はこのような境遇であったかと思われる封建社会を転覆したのは、ほんの十余 年の前である。十九世紀ヨーロッパの議院政治の制度の殻を破ると予想される国会の開設は、す でに四、五年の後に迫っている。奴隷に等しい平民はたちまちその階級を上り、主人であった士族 3 はたちまちその階級を下り、同じ位地に並ぼうとしている。昔、刀を持たない者は人にして人ではな い有様だったが、今は剣を帯びる者は常備兵と警官のほかにはない。昔、土足で蹂躙(じゅうりん) したキリシタンの十字架も、今はキリスト教としてそのもとに拝跪する者さえある。考えてもみよ。鎖国 の論から海関税全廃・自由貿易の論に至るまで、攘夷の説から内地雑居の説に至るまで、どれだ けの日数と時代を経過したのか。これを想い、あれを思えば夢か幻のようだ。「処世大夢のごとし」 の妙句もこの時代を評するためにあると言ってもよいくらいである。 このような大変化は私たちの耳目に触れる政治・社会・衣食住にとどまらない。さらに進んで形而 上の事柄を観察しても、道徳・信仰・交際・体面・思想等の標準はすべて一転してしまった。もしこ れを一々描写し、旧時のものと対照比較すれば、ずいぶん奇妙なこともあろう。ただ私たちは充分 にこれを観察できないのに苦しみ、たとえ観察できても、これを描写することができないので苦しむ。 今日の高令者で、封建時代の破壊から明治時代の今日に至るまでを経験した人は、邯鄲の夢、爛 柯の斧も大したことではないという心地がするであろう。要するに現今の時代は、枝が折れ幹が朽 ちて枯死する老樹が大風のために吹き折られたところに、その残株から一つの新芽が生まれ、雨 露がこれを潤(うるお)し、陽光がこれを育て、ついには雲を凌(しの)ぎ、天を衝(つ)く望みを抱く、 もっとも前途に希望ある時代となったのである。これは日本の変化というよりむしろ日本の復活再生 というのが正しい。なぜなら旧日本はすでに死に、今日生存するものは新日本だからである。 では日本の将来はどうか。将来の日本はどこに行くのか。政治家は日本政治の将来をあれこれ 心配し、商業家は商業の前途はと懸念する。学者なり、宗教家なり、現今の情勢を観察する者はあ わせてその将来を知ろうと必至である。それもやむを得ないが、社会は単分子の結晶体ではない。 実に異種異類、多様な分子の集合体であり、それが複雑であればあるほど自他の関係は細密とな るので、ただその一部を採って、ただちにその将来を占うのは難かしい。今日の政治社会はこうで あるから、将来の政治社会はこうなる、今日の経済社会はこうであるから、将来の経済社会はこうな ると断定することはできない。なぜなら将来の政治社会は、今日の政治社会によってのみ制せられ るものではなく、富の分配、知識の分配等によっても制せられるからである。経済社会の将来もまた 今日の経済社会によってのみ制せられるものではなく、あわせて政権の分配、知識の分配によって 4 も制せられるからである。 このように社会の分子はたがいに原動し、反動し、原因となり、結果となり、主因となり、主果とな り、客因となり、客果となり、その現象は千差万別、海浜の砂石もこれに及ばない。しかしたがいに 接触し、ともに連帯一致の運動をしているので、その一部の運動を知ろうとすれば勢い全体の運動 を知らなければならない。なぜなら全体の運動は各部の運動の協同によって支配されるように、各 部の運動はまた全体画一の運動により支配されるものだからである。 ゆえに日本将来の政治を知ろうとする者も、日本将来の経済を知ろうとする者も、そのほか宗教・ 学術・文学等を知ろうと欲するものも、みなその究明の範囲を全体に拡げなければならない。つまり わが国の社会に現出する将来のことを知ろうと欲するものは、その知ろうと欲することがいかなる点 にあっても、みなその究明の矛先を日本の将来という全局面に向けざるをえない。何人の思想もみ なこの中心点に向って帰着するのだ。 この問題は、ベルリンの権謀政治家が機会を掴もうと必死になり、ロンドンの哲学者が社会学の 材料を発見しようと推究し、ニューイングランドの宗教家が東洋の異教国にキリスト教を伝播しようと 思慮し、自由をアングロサクソン人の特有物とする学者が自由の恩恵は蒙古人種にも適用できるか と疑惑し、黄色人種の朋友と称する義侠の白人が日本の将来は果して独立国となるかを懸念し、 あるいはわが国在野の政治家が将来を思って困難な道を沈思黙考するところの根本問題である。 修業に集中して学窓に励む青年の書生も、机上に眠りを催すときには、忽然としてわが国の将来を 夢みることもあろう。あるいはみずから権威を誇る郷村の政治家も、僚友と炉辺に座るときには、あま りにも激しいわが国の変化の不思議に驚き、将来はどうなるかと談ずることもあろう。あるいはまた周 囲に人のない密室で、ひそかにわが国の将来を至誠をこらして上帝に祈る熱心なキリスト教徒もあ ろう。あるいはわが国の将来のあれこれを思い、天地眠る深夜にひとり熱い口惜し涙をふるう愛国 者もあろう。 このようにわが国の将来は、だれかれの差別なく、何人の脳裡にも必ず発現する問題である。そ してまた何人も、これを解釈するのに苦しむ問題である。私たちはこの問題をどのように解釈したら よいか。 5 過去は遠いとはいえ、古人の足跡は今なお残る。これを深く調べる必要がある。現今の世界は 錯雑とはいっても、私たちが現に耳目に触れるところのものは、知ることができる。しかし将来につ いては、ただ暗黒が眼前に横たわっているのを見るだけで、その中身を知ることはできない。しかも 今日の状況のもとではなおさらである。今は改革の時代だ。山中の人に向かって山の形状を問うて も、中流に浮かぶ人に川の形勢を問うても、改革の渦中にある人に改革の将来を問うても、決して 十分な答弁は得られない。なぜなら自分をその中においているからだ。この問題を問う者には、改 革の将来は改革であり、洪水の後は洪水だと答えるほかない。 過去のことは論評できる。現今のことは観察できる。しかし将来のことはどんなに達識炯眼(けい がん)の人でもただ推測するほかない。そして目下の情勢では推測することすら容易ではない。た とえ推測して苦言痛語を呈しても、なんの益もない。むしろエジプトの敗将でセイロン島の客となっ たアラビーパシャに習い、日本の将来はただ神が知るのみと答える方がましだ。誰もがそう思って いる。 しかしこのように重大な、私たちが微力を尽くしたとしてもほとんど徒労と思うほどの重大な問題に 向かって、大胆にも将来の推測を試みるのも、もっともな理由がある。将来の日本はどうなるかという 問題の中には、必ず将来の日本をどうするかという問題を含む。将来の日本がどうなるかは、もとよ り私たちのあずかり知るところではない。しかし将来の日本をどのように作り上げていくかの問題に ついては、私たちは一人の日本の国民として、平生忘れようと思っても忘れることはできない。この 問題は常に私たちを衝き動かして止まない。黙っていようと思っても黙っていられないのである。今 日において言えるだけのことは、遅疑せずに言っておこうと思う。私は胸襟を開き、直言直論しよう と思うのである。 ただし、この問題は種々の要素がたがいに関連し、決して分離することはできない。わが国の将 来はどうあるべきかは、人により希望するところが異なる。しかしその希望ははたして何より生じた希 望なのか。希望に価値があるのは、実行されるからである。もし実行されなければ、それは空望でし かない。億万の空望は一つの実行に及ばない。社会には社会必然の情勢があり、たとえ希望が千 万あっても、決してこの社会情勢を敵とすることは出来ない。したがって実行する価値があり実行で 6 きる希望であれば、その希望は必ず将来の情勢と一致する。将来の情勢を知るには、ただ将来を いかにするかによって決まるのである。 もし社会の情勢に抵抗できないと確信すれば、あらかじめ抵抗を断念するがよい。それは徒労だ から。たとえば天を仰いで石を投げるとする。いかに精神を集中して投げても、石は天外に飛び去 るものではない。一たび投げれば一たび地に落ち、百たび投げれば百たび地に落ちる。重力には 敵わないと判れば初めからなげないのがよい。私たちは決してわが国の将来に向かって架空の希 望を抱くものではない。ただ将来において必ず実行できる希望を持つのである。実行できる希望と は、社会の自然の情勢に従い、これを善導することである。つまりわが日本の将来をどうするかとい う抱負は、他国の干渉や妨害受けることなく、将来の日本を推測することにより定まる。 将来の姿とそれを実現する方法論の二つは、互いに関連する。第二の問題を解釈しようとすれば、 勢い第一の問題を推測せざるをえない。しかし私たちがこれに注目し、これを考え、かつこれを推 測してやまないのは、さらに一歩を進めてわが国の将来の経綸(治国済民の根本思想)を定めたい からである。改革の将来は改革である。であれば、その改革はどのような改革なのか。どのような改 革でなければならないのか。洪水の後には洪水がある。であればその洪水はどのような洪水なのか。 どのような洪水でなければならないのか。光陰は電気が鉄線を走るよりも速い。昨日は今日の昔で ある。一日また一日進まなければ、今日考える万里の将来も、たちまち他日の今日となってしまう。 私たちが今日、将来の日本を論ずるのは当然である。 第二回 一国の生活(総論) 人間はただ生活するためにだけこの世に出て来たのではなかろう。しかし、では最初の目的は何 かと問われたら、私も人も三尺の童子でもみな異口同音に生活するためと答えるほかあるまい。人 間が世界にあってしたいと思うことは千差万別だが、生命を持った以上、必ずまず生活の道を求め ざるをえない。首陽山にぜんまいを採ったのは伯夷・叔斉が生活を保つためで、箪食瓢飲(たんし ひょういん、粗末な食事)は顔回が生活を保つためだった。古代ギリシアのシニカル派哲学の開祖 7 アンチステネスは、精神の快楽と生活の快楽とは反するもので、まったく両立するものではないと、 つねに生活を敵視していた。にもかかわらず、彼が病んでまさに死の床にあるとき、かすかな声で 弟子に「この苦痛より脱れるすべはないか」と聞いた。弟子はたちまち短剣をひっさげ「これで救い ましょうか」と答えた。彼は驚いて「いやいや私は苦痛より脱れたい。生命より脱れたいとは思わん」 といった。生命は人である。生活があってこそ、その他の願望も生ずる。一国の目的もまた同じだ。 一国の最終目的は、モンテスキュー、バーク、スタイン、スペンサーの諸氏に聞いても満足な答は 得られないけれども、その最初の目的については、白蟻・蜜蜂の社会よりなお簡単質朴な太平洋 群島の野蛮国でも、精緻に発達した政治の機関を持つ欧米社会でも、国家である以上は一様に、 まず国民の生活を保つという一点に求めざるをえない。これは半文政治家でも容易に断言できるこ とである。一国はその生命があればこそ何事もその分に応じて行うことができる。もし生命がなけれ ば何事もなしえない。 したがって、将来の日本を論じようとすれば、まずわが国の将来はどんな手段によって生命を保 つかという問題を最初の着手としなければならない。一国の生活を保つ手段は二つある。一つは生 産機関、一つは軍事機関である。生産機関は国内の供給を行い、軍事機関は外部の妨害を防御 する。孔子がいう「食に足りて兵に足る」のがこれである。この二つの機関は必ずしも始めから職務 の区別はなく、社会の草創期においては未分化であった。たとえば無事の日には農夫となり、戦争 の日には兵士となり、国民も兵士も同一人であった。ただ従事した時の仕事にしたがって称号を異 にしたのだ。この場合は生産機関も、軍事機関も、同一である。この実例は、頼山陽が言ったように、 日本建国の始めはきわめて簡易な政治機構で、文武一体、国内挙げてみな兵とした。天皇が元帥 となり、大臣(おおおみ)・大連(おおむらじ)が副将となった。独立した将帥は置かなかった。武士 などという者はいなかった。私たちの王朝の歴史はこういうものであった。 しかし社会が進歩すると、人事はいよいよ繁多になり、勢い分業が行なわれていった。仕事の区 別が漸次増えて行き、戦争がつねに絶えないようになると、武備の機関はいよいよ拡大し、生産の 機関はいよいよ収縮していった。頼山陽が「光仁・桓武朝では軍事多事のため、宝亀年間に、冗兵 をはぶき百姓を豊かにした。弓馬の才ある者は、もっぱら武芸を習い徴発に応じた。脆弱な者はみ 8 な農業に就けた。こうして兵農はまったく分離した。」といったのはこういう事実であった。 軍備機構の勢いは一躍し、ただ外部の敵を防御するに止まらず、防御の性質は一変して攻略の 性質を帯び、ついに生産機構をもその中に取り込むに至った。 これに反し一国がもし平和主義に立つときは、生産機構はたちまち勢力を増長し、軍事機構は まったくその下に圧伏せられることもある。たとえばローマの初期には全国の人士はみな兵士となり、 みな農夫となり、生産・軍事は分離していなかった。ローマの有名の歴史家プリニーは「田地は大 将の手で耕され、その土壌は賞牌を得た農具によって開墾された。これを導く農夫はまた戦争にお いても功労があった。」と当時を語った。またマニオス・キネリオスという人物は、武勲輝き、威名が 四隣を圧した豪傑だったが、田園に帰り、茅屋(ぼうおく)に住み、僅かな田地を耕し、身を安んじて 暮らしていた。おりしも炉辺にすわって蕪を煮ていると、敵国の使者が来て、黄金を贈って取入ろう とした。彼は笑って言った「私はこんな食事で十分なのだ。黄金など不要。私には黄金を自分の懐 にするより、これを懐にする敵国を征服することが光栄だ」と。当時の兵すなわち農、農すなわち兵 であった事情がわかる。 しかし、近隣の諸種族との生存競争がいよいよ激しくなるに従い、市民はことごとく戦争を専業と し、農業はまったく奴隷の手に放任してしまった。これより軍備の機関はいよいよ発達し、防御の性 質は一変して攻略となり、ローマ兵の向かうところ天下に敵なく、カルタゴ、ギリシアを滅ぼし、エジ プト、シリア、パレスチナを侵略するに及んで、天下の富はことごとくローマに集まった。ただし、そ の蒐集した富は経済的に吸引する引力があって集めたものではなく、ただローマ人の腕力をもって 各地より掠奪したものであった。ローマの都が世界一だといっても、一つの特有産物があるでもなく、 ローマ人はただ略奪して来た金銀で、略奪された各国の産物を交易〔もしこれを交易ということがで きれば〕したのみである。ローマ人の諺にいう。「鉄を振う者は金を掴む」と。このようなローマ人は、 武備を固めて外敵を防ぎ、あるいは外敵を攻めて勝ったのではない。まったくその分取品により自 分たちの生活を保ったのだ。生産機関はローマにはなかったのである。 フェニキア国はそうでなかった。瘠せた、小さな国土にもかかわらず、生産機関が発達する環境 にあったので、国力の進歩は著しかった。なかでもツロの人民は航海の知識、製造の熟練、商業の 9 盛大を武器に、上古の歴史にその名を輝かせた。彼らはみずから地中海の帝王となり、その進取 の気象は一躍してヘラクレスの海峡を越え、ブリテン島に赴き、バルチック海に達した。至るところ の土人を得意先とし、至るところの土地を故郷とし、ついに地中海岸に設けた植民地は四十を越え た。私たちは『旧約聖書』でかつてのツロの繁昌を知ることができる。 「おおツロよ。お前は海に面してエーゲ海市民のために都市を築いた。お前はかつてこの町に はすべての物が揃っていると言った。お前の町は海の中心地にある。お前が建造する船は世界の 美を尽くしている。セニルの松を舟板とし、レバノンの柏香木を取って帆柱を作り、バシャンで採っ た果実で飲み物を作る。アッシリアの隊はキッチムの諸島で採った象牙でお前の椅子を作った。お 前の船帆にはエジプトの模様。お前の着る衣服はエリシヤ諸島より招来した青と紺の布だ。シドンと アルワダの住民はお前の舟子となった。ツロよ、お前の家の舵(かじ)取りは知者だ。彼とゲバルの 老練者はお前の舟を修復する名人だ。海に浮かぶ舟と舟子はみなお前の手下となって貿易を引 き受けている。」 実に盛んな活動であった。フェニキア人が商業によって征服した版図は、ローマ人が腕力で征服 した版図に比べても、劣ることはなかった。以上の実例を信ずるとすれば、生産と武備の二機関は 決して両立しうるものではない。彼が盛んであればこれが衰え、彼が滅びたらこれは興るのである。 人間の職業はその人の性質によって決まるが、人間の性質は職業により定まるものでもある。もち ろん職業を満足に成就したとしても、人間の目的はそれで終わるものではない。人間の高尚な目的 と卑近な生活上の職業はつねに離れず、解けない関係にある。人事万端といっても楼に上るときは 階段を踏む。一段上ればさらに一段を上り、一段下ればそれはさらに一段下る地歩となる。階と階 は相接し、節と節は相連なり、一つとして分離の運動はしない。したがって私は、卑近な職業と高尚 な職分は別物であると区別するような人とは、ともに語ることができないのである。 たとえばここに一人の武士と一人の商人があるとする。二人は兄弟でともに家庭の教育を同じくし、 学校の教育を同じくし、その二人の性情や行動は同じだとする。そして立身の過程でおのおの別 な職業についたとする。そして今ここに二人が一室に対坐したとする。二人はその趣味、その感情、 その嗜好、その思想が大きく異なるのを見て、茫然とするであろう。職業の性質はただちにその人 10 の性質に関係を及ぼすことがよく分る。これにとどまらず、職業の品格はただちにその人の品格を 定める。たとえば遊楼の主人も、伝道師も、芸妓も、女学校の博士も、経済的な見方をすれば、高 下の区別はつかないが、社会では経済的な見方ですべてを判定するわけにはいかない。職業は 生活のためという一面はあるが、不正な手段によって生活する者はその人がどう弁解しても、不正 な人物といわざるをえない。 国もまた同じである。生活のためにどのような職業につくかは、ただちにその国の性質にも品格に も、大きな関係を持つから、世間の識者ことに一代の創業者となる者は細心に考慮して、職業を選 ばなければならない。生産、軍備の二機関は単にその範囲中においてその勢力を振うにとどまら ず、あわせて社会万般に対し感化を及ぼすからだ。たとえば食物はただちに消化器官に刺激を及 ぼすが、そのあと血液となり、血管を流れて四肢五官脳髄に至るまで、つまり人の全体にその滋養 を及ぼす。社会の現象は一事一物すべてその感化を受けるのである。軍備機関の発達した国では、 政権は少数人の手に握られ、生産機構の発達した国では、政権は多数人民の手に分配される。一 方では人民は国家のためにあるとされ、他方では国家は人民のためにあるとされる。一方ではただ 国があるのみ、国家をほかにして人民はないとされ、他方では国の中にはただ人民あるのみ、人民 をほかにして国家はないとされる。一方の結合は強迫の結合であり、軍隊組織の精神により社会を 組織する。他方の結合は自由の結合であり、経済世界の法則により社会を結合する。一方の社会 ではただ主人と奴隷との二者だけで組織され、他方の社会では同胞兄弟によって組織される。一 方の富の分配は人為の分配により弱者はつねに泣き強者はつねに笑う。他方では富は自然の分 配にまかせ、人々はただ過去に下した種を今に収穫する。一方では、一、二の偉大な知者があっ ても千万の愚人があり、他方では偉大な知者はいなくても大きな愚者もいない。一方の権威はただ 命令があるだけで、人民を犠牲にして一国の体面を保つ。他方は人民に幸福を与えるために国家 の体面を保つ。一方では闘争が真面目(しんめんぼく)、他方では平和が真面目である。他人に損 をさせ自分を益するのは一方の方便であり、自分を益し他人をも益するのは他方の方便である。一 方の政略は他国を盗むか、他国より盗まれまいとするかの一点にあり、他方の政略は自国の独立 を保ち平和に交際することである。一方の法則は暴逆、他方の法則は正義である。一方の主義は 11 威力が権利であり、他方の主義は権利が威力である。要するに軍備機関の発達した社会は不平等 主義が支配するが、生産機関の発達した社会は平等主義が支配する。だから軍備社会の現象は すべて貴族的な現象であり、生産社会の現象はすべて平民的な現象である。 一国の生活を保つのはこの二つの機構であるが、この二つの機構が両立することはできない。二 つは国の政治・経済・知識・文学・社交、つまり一国の性質品格に一種特別の感化を及ぼす。世上 の識者はどちらの機構によりわが日本の将来の生活を保とうとするか。私たちの希望がここにあっ ても、社会情勢の趨勢があちらにあれば、私たちはどうすることもできない。ゆえに私たちがどちら を採るかという問題を解決しようとすれば、勢い一歩を進めて日本の将来の情勢はどちらに進むか 推測しなければならない。では何によって推測するか。第一に外部社会の四囲の状況。第二に社 会自然の大勢。第三に日本特有の条件。第四にわが国の現今の情勢。この四点である。もし私た ちの将来の希望が、これらの四問題と符合するならば、わが国の前途は実に頼もしい。不幸にも両 者が相反するなら、前途の吉凶を占うのに苦しむ。 第三回 腕力世界(第一 外部社会の四囲の状況。表面より論ず) この十九世紀では、四海の万国はみな日本の隣国である。そしてこれら隣国の状勢は、日本の 将来の命運を左右する一要素であることを記憶しなければならない。ではこれら隣国の状勢はどう か。これが今回講究する問題である。 十九世紀の今日は、実に絶望の時代である。眼を挙げて地球上の四隅を見てみよう。中でも世 界舞台においてもっとも豪胆活発な演劇者の中心であるヨーロッパ諸国を見てみよう。今日ほどひ どい道理の無力、薄弱がかつてあっただろうか。強者の権の流行が今日よりひどい時があっただろ うか。腕力主義の隆盛が今日よりひどい時代があっただろうか。昔の世界は野蛮人が腕力で開化 人を蹂躙(じゅうりん)した世界だった。今日の世界は開化人が暴虐により野蛮人を追い込む世界 になっている。 今日、蒸気・電気・鉄・石炭・ガラス等の大自然力により一大革命をなしとげ、世界の表面は一新 12 された。にもかかわらず、哲学・物理学・文学・美術等は実に百尺竿頭一歩を転じたにすぎない。か の便宜主義の統領であるベンサム氏が「最大無類の禍害」と呼んだ戦争は、いまだにその痕(あと) を社会に絶っていないではないか。ヨーロッパ諸国はみずからをキリスト教国と誇称するが、昔の賢 者が予言したように、牛羊とともに草を噛み、尾を垂れ、首をたらし、真の神の命に柔順な獅子では ない。ルイ・ナポレオンは「世界の歴史は戦争の歴史だ」といった。十九世紀の歴史は戦争の歴史 ではなかったか。次の表を一覧されたい。 ウィーン条約(一八一五年ヨーロッパ諸国とフランスとの講和条約)以来、戦争で死んだ者は三百 万人に達する。次にやや詳しく調べた数字挙げる。 年代 1828 戦争 戦死人 バルカン戦争 120,000 1830~1840 スペイン・ポルトガル二国相続戦争 1848 欧州革命 1854 クリミア戦争(同盟人) 60,000 155,000 (ロシア人) 1859 630,000 イタリア戦争(同盟人) 24,400 (オーストリア人) 38,700 1863~1865 合衆国南北戦争(北部) 206,000 (南部) 1866 160,000 375,000 普墺戦争 51,200 1867~1870 フランス・メキシコ戦争 65,000 1861~1867 ブラジル・パラグヮイ戦争 232,000 1870~1871 普仏戦争 290,000 1877~1877 露土戦争 20,000 合計 2,607,300 このほかフランスのアルジェリー戦争、イギリスのインドおよび南アフリカ戦争、スペインのモロッコ 13 戦争およびその他を合わせると僅か五十年間に戦死した者は三百万人を下らない。(マルホール 氏の『万国進歩の実況』による) シナの聖人は、「天下を得るのに人間は一人も殺してはならない。」と訓戒を垂れたが、ヨーロッパ の帝王宰相は、児戯にもひとしい名誉心を抱いて、僅か五十年間にこのように多数の無病息災、 血気まさに盛んな男児を、空しく虐殺した。ヴィクトル・ユーゴーが「血を流すは血を流すことだ。人 を殺すは人を殺すことだ。首切り役人の帽子を皇帝の冠に代えても、兇悪な殺人犯の性質には変 わりない。」といったのは、もっとも痛快な評であり、実に寒心に堪えない。しかも戦争はただ人を殺 すだけでなく、財貨をも殺す。孫子がいうには、「十万人の兵を起せば、出征は万里。百姓の費、 公家への礼など、日に千金を費やす。」これらの戦争でヨーロッパ諸国が徒費した財貨は巨額に上 る。私はヨーロッパ諸国がこれらの戦争により公債を増加した統計を見て、驚愕に堪えない。一八 二〇年より四八年に至る間は一七億二〇万ポンド(一年平均約六百万ポンド)を越えた。これがさ らに勢いを得て四八年以後の増加は実に驚くべきものがある。(一年平均約一億三〇〇〇万ポン ドの増加)。この出費の主な原因を次にあげる。(単位は千ポンド) 一八四八年 公債高 1,720,000 クリミア戦争 192,000 イタリア戦争 105,000 アメリカ南北戦 490,000 ブラジル、パラグァイ戦争 85,000 独墺戦争 90,000 仏独戦 370,000 露土戦争 210,000 軍器 1,607,000 鉄道・造船所・電信 総計 575,000 5,444,000 (マルホール氏『万国進歩の実況』) 14 ヨーロッパ大陸(イギリスを除く)は一八二〇年には一人平均三シリングの公債利子を払ったが、 一八八〇年にはほとんど四倍の十一シリングに上った。増加の理由は、ただ「575,000 千ポンド」を 鉄道・造船所・電信等のために消費したほか、みな無用な軍事に費消されたのである。 今を去ること一八〇〇年前オーグストス・シーザーがローマ帝王の位にあったとき、四境を守衛す る兵士は五十万人を出なかったが、今や当時ローマ帝国の一州一郡であったヨーロッパ諸国の常 備軍は、何人になっているか。次の表を見てもらいたい。 国 人口 常備兵 軍備兵 常備兵一人当人口 人口百人当兵数 英 35,241,482 189,252 636,951 186 2 露 100,372,553 502,738 2,080,918 200 3 独 45,234,061 445,392 2,650,000 102 7 仏 37,672,048 518,642 2,550,000 73 8 墺 37,786,346 271,833 1,026,130 139 3 伊 28,459,451 714,958 1,989,619 40 9 (『万国形勢総覧』) 私はかつてアダム・スミス氏の『富国論』を読み、「人口の百分の一以上の軍兵を養う国は衰亡を 招かざるをえない。これはヨーロッパの近代文明人の通論である。」との言を聞き、ひそかにそれは 至言だと感じた。しかし今やヨーロッパの現状はまったくこれに相違し、百分の一はおろか百分の 七を超える国もある。そしてヨーロッパ全体の兵数を概算すると、九五七万七千人を超える。これ一 直線に整列させると、長さは六〇一〇キロメートル(およそ一五三二里)になる。列を通過するには 快馬に鞭うって走っても十二日六時間かかり、急行列車で通過しても四日と十八時間を要すると聞 く。 また明治十七年八月の万国講和協会の調査によれば、ヨーロッパの軍備は平時において三九 〇万二千人、戦時においては一三八四万一千人に上るという。いずれの統計に従っても、このよう な巨大な兵備は十九世紀の一大奇観というほかない。その昔東洋の暴君、秦の始皇帝は石で万 里の長城を築いた。しかし今のヨーロッパの帝王宰相は人で万里の長城を築こうとする。なんと大 15 胆なことではないか。ヨーロッパの帝王宰相は何の必要があってこんな莫大な常備兵を養うのか。 私には理解できない。もしそれが必要だとすれば、私たちの社会は非常に険悪な証拠であり、必要 ないとすれば帝王宰相らはとてつもない道楽者なのだろう。ああこれもまた十九世紀の文明であろ うか。 このような常備軍はもちろん平時に代価なしで整えおくことはできない。とすればヨーロッパ諸国 の人民は、年々歳々どのくらいの軍費を負担しているだろか。かつて『毎日新聞』が掲載したロンド ンの万国仲裁平和協会が調査した一八八三年の報告書を見ると、墺・英・露・仏・独・伊六国の歳 出および軍費の割合は次のとおりである。 国 歳出(ポンド) 海陸軍費(ポンド) 歳出に占める割合(%) 墺 93,610,555 13,413,795 14 独 110,809,893 22,624,749 20 仏 136,137,607 33,730,783 25 英 89,004,456 31,420,755 35 伊 61,489,047 12,055,589 20 露 129,417,570 46,102,500 36 このほかに、軍備のために募集した国債もまた驚くべき額であり、これを合算すれば、二三〇億 二一五〇万ドルの巨額となる。利子を払うのに一〇億三七一五万九一七五ドルが必要である。イ ギリスでは三七億九〇〇〇万ドルの公債を発行し年々一億五六〇〇万ドルの利子を払っている。 ロシアの公債は三〇億一七五〇万ドルで年々一億五六〇〇万ドルの利子。フランスの公債は四 八億ドルで二億七二五〇万ドルの利子。ゲルマンの国債は一五億ドルで六七五〇万ドルの利子 をそれぞれ支払っている。 以上、ヨーロッパ諸国の軍備の状況を述べて来ると、ヨーロッパ人民の不幸を悲しまざるをえない。 たとえルイ・ナポレオンがセバストポールの戦いでロシアの攻撃を防いだとしても、フランスの人民 はそのためにいくらの利益を得ただろうか。たとえフランスに復讐したことでビスマルクの雄名が世 界に轟いたとしても、またモルトケの勲章に輝かしい光を添えたとしても、ゲルマンの人民はこのた 16 めにいくらの利益を得たか。パーマーストン、ビーコンスフィールド諸公がアフリカやアジアの諸蛮 族との間で綿々として無名の戦争を続け、イギリスの領土が幾分か増えたとして、イギリスの人民が 得たものは、失ったものを償うのに足りただろうか。近くはかのフェリー氏が安南事件について清国 と兵を構え、一万五千の兵士を失い、四三〇〇ポンドを消費し、おまけにクルペー提督が東京(と んきん=ベトナム北部)の海霧の中でインド洋の藻屑と消え、また英国内閣の命により、ゴードン将 軍がスーダンの熱砂で刀折れ矢尽き、命を砂漠に埋めてしまったのも、仏英の人民にとってどれだ けの愉快と幸福をもたらしたか。これを思えば、「一将功成って万骨枯れる」とシナ古代の詩人が詠 じたのも道理がある。かのジョン・ブライト氏が「私は清国戦争・クリミア戦争・アフガン戦争・ズール 戦争・エジプト戦争はすべて、決して得策ではないと論じてきた。思うに戦争によって金銭上の利 益を得た者、戦功により官位を進められ、爵位を得た者のほかは、少しでも思慮あるキリスト教信者 であればみな、その戦争の不正を非難するだろう。」と言ったのは、実に欧州人民の心事を描き出 した言葉といわざるをえない。 これを過去に照らし、現今に察すると、ヨーロッパ諸国の状勢は腕力主義の頂上に達したものとい わざるをえない。ここまで軍事機関が発達したのは、千古の歴史上例を見ないほどである。軍隊組 織の精神は単に武備の一点にとどまらず、その思想が社会の隅々に及ぶのは自然の理である。そ の事実は歴史が証明している。泰山に登らなければ天下の高さを知ることができない。黄河を見な ければ天下の深さを知ることができない。ベルリンで学ばなければ学問の英知を知ることができな いとして天下の書生が慕う哲学の楽園、高名な学者が輩出したゲルマン帝国ではあるが、その政 治ははたして人民の幸福を増進したであろうか。社会が完全な進歩を成就するまでは、いかなる社 会といえども空論世界の謗りを免れないが、天下万邦のなかで、ゲルマンのようにはなはだしい空 論世界はない。実にゲルマン人民のために嘆かわしい。ゲルマンの哲学・政治学・法学者中には 随分深奥精緻な議論をし、あるいは各国制度の得失を批評する人がいるが、その言うところ、説くと ころは、はたしてどれだけ国家の制度に反映しているか。私たちはスタイン(オーストリアの博士)の 千言の議論が、ビスマルクの一声にも値しないことを恐れる。 一八七〇年の普仏戦争後の、ゲルマン帝国の運動を見よ。かの鉄公ビスマルクの、いわゆる国 17 家社会主義つまり国家専制法がようやく社会の水面に頭角を現わし、七一年には、帝国議会は向 う三ヵ年間据置の軍事費を議決し、七四年には向う七ヵ年据置の軍費を議決し、同じく八〇年には さらに多額な軍費を同様に議決した。これすべてビスマルクの意向であり、議会の権力はたしてど こにあったのか。ピームが「議会に権力がないときは、ただ専制の器械となるに過ぎない。」といった が、これはゲルマン帝国の議会にもあてはまる。地方郡区の人民は力戦の武官を文官に選挙し、 自分たちの牧民官と仰がざるをえなかった。どんな高官大位の人も、いかに博学多識の大学校の 博士も、また中小学校の教師も、ことごとく一年間の兵役に就かなければならなかった。かの霊魂 世界を支配する僧侶さえも国家の威権のもとに圧服し、その宗門の規律にせよ、その制度にせよ、 その得度の方法にせよ、その一挙手一投足は国家すなわち政府の指令を仰がなければならなか った。ゲルマンは宗教改革の故郷である。あのローマ法王レオ第十世の暴威に抵抗し、赤手をふ るって起ちあがったマルチン・ルーテルは低地ゲルマンの氷山の中から出たのだ。しかして今やゲ ルマン政府の宗教に対する干渉はローマ法王よりもはなはだしい。ルーテルは地下でこれをなんと みるだろうか。 これ一つにとどまらず、経済世界もまた政府の干渉するところとなり、文明社会においてもっとも 活発な分配系である鉄道も、すでにその四分の三を帝国の官有鉄道とした。その他あるいは保護 税を盛んにし、利息制限法を再興し、日曜日の労作を抑制し、あるいは郵便法を拡充して銀行の 事務をも奪おうとする。またシナ戦国の政治家、商君の遺法である伍組を設けて、強制的に団結を 固め、あるいは国家保険法を設けて工匠の手足を縛ろうとする。またここ数年、社会党の結社の解 散二二四、新聞雑誌の発行差止め一八〇、書籍出版の禁止一三七を超えた。さらに本年一月二 十六日プロシア国国会においてビスマルク公はプロシア国の領分にあるポーランド人を放逐する 議案を発した。彼の運動の方向は明瞭である。要するにその運動は直接にも間接にもただ国家の 権力を増長し、個人の弱体化にある。帝国の権力はひたひたと蚕が桑の葉を食うように拡大し、今 やすでにほとんど食いつくしてしまっている。 人は常にいう。十九世紀の運動は自由主義の運動であると。しかし私は、ゲルマン帝国の運動 は専制主義の運動であると断言せざるをえない。私はゲルマン帝国といい、ゲルマン人民とはいわ 18 ない。なぜならただ国家があって人民がないからである。いわゆる「理論の天国、実際の地獄」とは この国のことである。 ロシアの場合はもっと厳しい。この国の惨状は、眼のある者はこれを見、耳ある者はこれを聞く必 要がある。これについては私があれこれ述べるより、一篇の詩を掲げれば充分であろう。この詩は 千余年前シナの詩人が時代を諷刺したもので、その沈鬱で悲壮な調子は今日のロシアの現状を 描写するにふさわしい。 「車馬は寂しく進み、歩兵は弓矢を腰につけている。老幼妻子走って見送り、咸陽橋には塵も 見えない。衣を引きずり足を摺り道を横切って泣く。泣声はただちに上って天に轟く。道傍の者が 行く人に問えば、行く人は常時行軍と答える。十五の年から北のかた河を防ぎ、四十になって西 のかた田を営む。さるとき村長が頭包みをくれて休暇をもらった。帰っては来たが、頭が白くなっ てまた辺を守るため出征する。辺地では流血が海水をなす。武皇は辺を平定してもなお満足しな い。君は生国山東の二百州、千村万邑に茨がはびこるのを見ないのだろうか。たとえ留守居の健 婦が鋤をとっても、雑草は四方にはびこる。また君は秦兵が苦戦に耐えるのを知らない。兵を駆 ること犬と鶏とに異ならない。長者が問うても、役夫はあえて恨みを述べない。今年の冬は、いま だに西域の兵を帰さない。官吏が租を出せと命じても、どの家の櫃(ひつ)も空である。男を生め ばろくなことはない。かえって女を生む方が良い。女を生めば嫁に行けるが、男を生めば戦死し て草の根元に横たわる。君は見ないのか、青海の辺境には白骨が野ざらしになっているのを。新 しい屍は恨み声を上げ古い屍は涙を流す。天は曇り雨は湿って寂しく響きわたる。」 世人よ。この詩を読んで東洋詩人得意の大言壮語としてはならない。実にロシアの残酷な状況は この巧妙な句でさえ充分には描写していない。もし疑う人があれば、どうか北海の寒風にさらされ、 寒山の氷雪を浴び、鉄鎖につながれ、シベリアの採鉱場で苦役する虚無党の罪人に聞いてもらい たい。ああ、このような有様はこの二国にとどまらない。オーストリーといい、イタリアといい、あるいは イギリス、フランスといい、みな幾分かはその臭味を帯びている。この二国はことにはなはだしいだ けである。私は今なお、かの平和主義の大立物ブライト氏が、去年六月にヨーロッパの現状を説い た一節を記憶している。 19 「今や財利はことごとく兵備のために使われ、人民の利益はもっとも忌み憎まれる外交政略という 妄想のために犠牲となる。国光国栄の妄想が優先し、一般人民の真実な利益を蹂躙している。ヨ ーロッパは恐ろしい一大変乱に陥る方向に進行していると考えざるをえない。兵備拡張は限度なく 堪えられるものではないから、おそらく人民は絶望に沈み、早晩帝王と帝王の名によって政権を握 る偽政治家を一掃することになるであろう。」 ヨーロッパの現状はこのとおりである。では、その将来はどうか。軍事機関がこのように発達したの は、過去に武力運動が過重であった結果だが、将来に関しては立場を変えて軍事機関が武力運 動の原因となるだろう。常備軍はもともと防御のために設けられたものだが、敵を防ぐ刀剣は一転し て敵を攻める刀剣となり、攻略の道具となる。当初の意図は平和を維持するためであっても、一変 して戦争の契機ともなる。その昔、果し合いというものが行なわれたのは、わが封建武士が双刀を 構えたときにもっとも盛んであったことを知れば、ヨーロッパの将来の果し合いも、莫大な常備軍が あるからこそ起るのだ。ヨーロッパ諸国の運動を支配する法律は、外観上万国公法だが、万国公法 というものはブライト氏が言ったように「習慣より成立した、複雑で矛盾に満ちた取決めであり、しか もその習慣はつねに強者の意のままに行なわれた習慣である」から、万国公法が首尾よく適用され たと言っても、それで天下の泰平を実現するには不十分である。しかも万国公法というものは各国 を支配する君主ではなく、かえって各国によって支配される奴隷のようなものだ。 またビスマルクが頼むのは万国公法ではなく、ただ鮮血と黒鉄である。ではヨーロッパ諸国の運 動を支配する法律ははたしてなにか。いうまでもなく、すでに習慣より成立した万国公法ではない。 またなんじの敵を愛し、なんじを呪うものを祝し、なんじを憎むものを善視し、なんじを虐待迫害する もののために祈祷する『新約聖書』でもないことはさらにはっきりしている。カーライルが言ったように、 「二人の人間の間に生ずる最後の問題は、自分が相手を殺すか、相手が自分を殺すかの一問題 である。」 私はさらに単刀直入にヨーロッパの現今の国際情勢について断言する。ヨーロッパ諸国の外交 政略は表面で隣国を愛し、裏で敵を憎むにとどまらない。また目に目を償い、歯で歯を償うにとどま らない。最後の問題はただ自国が相手の国を併呑するか、相手の国がわが国を併呑するかの一問 20 題に帰着する。この問題が現在の社会を支配すると知れば、その将来もまた知ることができる。欧 州の将来はどのように動いていくだろうか。 第四回 腕力世界 二(同上) 歴史の眼で観察すれば、アジア、ヨーロッパの二大陸は実に密着な関係を持つといわざるをえな い。東亜の山脈は波涛のように日本海からビスケイ湾(スペイン)まで連なっている。あるいは起き、 あるいは伏し、あるいは続き、あるいは絶え、不規則な折線をもって二大陸を南北に切っている。ま た中央アジアの大平原は茫として限りなく、はるかにゲルマン、オランダの中腹に連なっている。太 平洋の海岸より大西洋の海岸に至るまでおよそ六千マイルを超えるが、その高低はわずかに数百 尺の相違に過ぎない。東亜の大陸は海面上の高さ平均一一三〇フィート、西欧は平均六七一フィ ート程度である。かつ気候は温和で人体に適し、至るところ草は肥え泉は甘い。しかも長江大河が 横流し、自然の境界とはなっていない。 そうであれば欧亜の二大陸は千兵万馬が大運動する最好の戦場といわざるをえない。実にこの 地域は英雄が武を争った地である。未開の上古より十九世紀の今日に至るまで、人類の年代記は ただ各人種がこの二大陸を東西南北に往来漂泊した一つの事実にすぎない。欧亜古今の歴史は、 人種運動の歴史であったといっても過言ではなかろう。 そもそも今日のヨーロッパ人民の先祖は、中央アジアから西方に移住したものであり、上古の歴史 はむしろ東方の人種が西方に向かって旅行した歴史である。試みに見よ。ケルト人種が在来の土 人に対し、ラテン人種がケルト人種に対し、チュートン人種がラテンもしくはケルト人種に対し、スラ ブ人種がチュートン人種に対し、タタール人種がスラブ人種に対する運動はただ東より西に走り、 たがいにその足を追い、ついにヨーロッパ西岸の極端にあるスペイン人はさらに西進して大西洋を 越え、米州に達するに至った。これに反し、現今の歴史は実に人種が西方より東方に向かって運 動する歴史だといわざるをえない。 私は古今の歴史を通読してまことに奇異の感を受ける。人類がその歴史さえ記憶しない上古より 21 十三、四世紀に至るまで、ヨーロッパの歴史は多端とはいえ、あたかも隠々裡に一人の大将があっ て指揮したように、随意運動にもかかわらず、みな一定の規律のもとに東方より西方に向かって大 きく運動した(もちろんアレキサンダー大王の東征や十字軍は、西より東を征したが、これみな原動 ではなく反動であった。その反動は、東方より西方に向かって圧力を加えたから生じた。)。 しかし近世史の発端より今日に至るまでさらに大きな反動を起し、方向を一変した有様は、あた かも大将の一号令のもとに、千軍万馬みなその馬首を回し、新奇の運動を始めたように見える。遠 くは数千年、近くも数百年前先祖が出立し、流浪を始めた故郷に向かって各人種が旅行を始め、 ますます歩みを強める傾向にある。これは私たちがもっとも驚く事実である。 たとえばギリシアがトルコの束縛を脱して独立国となったり、イタリアがオーストリアの管轄を離れ て国体を新造したり、スペインがフランスに対し、フランスがドイツに対し、ドイツがオーストリアに対 し、イギリスがロシアに対し、ドイツがロシアに対し、ヨーロッパ諸国がトルコに対して矛先を向けたの は、みな西から東に向かう運動ではなかろうか。三百年前の政治地図と三百年後の政治地図を比 較すれば、必ず思いは半ばに達するであろう。 (註)たとえばトルコは一四五三年にコンスタンチノープルを取ってから、しだいに諸方の国土を併 合し、モンテネグロを除くバルカン半島の全体とペロポネソスと黒海およびアゾフ海の北岸はみなト ルコの手に属した。一七一一年のころトルコの領地は西はアドリア海およびダニューブ河に至り、東 はドニエステルおよびドニエープル等の地方に達し、ベッサラビヤ、クリミアその他の蒙古地方もト ルコ国の領分となった。ヨーロッパ大陸にあるトルコの所有地は一万五四五四平方英里となった。 ロシアを除いて欧州のいずれの国よりも多くの領地を有していた。しかしこの時より後ようやく衰運に 向かい、一七三九年に一時オーストリアに戦勝したことがあっても、その後次第に領地を失い、先 年ロシアと戦争を始めるころはわずかに九四五六平方英里の領地となった。しかもそのうち八九〇 二平方英里は諸公国に属し、これらはただ名義上トルコを宗主国と仰ぐのみでほとんど独立国に 等しい。ついでまたベルリン条約によりトルコは四五五八平方英里の土地を取り上げられたので、 一七〇〇年より一八七八年までの間にヨーロッパで一万〇六六六平方英里を失った。そのうち、八 九〇二平方英里はロシアに征服され、そのうちの四八一六平方英里は完全にロシアの領地となっ 22 た。 最近ではアイルランドが、多年イギリス人により奪われた自由の権と土地所有権を回復する機会 を得た(十九年四月八日のグラッドストン氏によるアイルランド自治案。同十六日の土地買上案)。 一千年前ローマ帝国を鉄蹄により破った戦争はチュートン人種・ラテン人種・ケルト人種・スラブ人 種の戦争であった。今日の戦争はどうか。アングロサクソン人種のイギリス人とスラブ人種のロシア 人との間の、ラテン人種のフランス人とチュートン人種のドイツ人との間の人種戦争ではなかろうか。 世界は人種が優勝劣敗を争う修羅場である。ローマ滅亡の歴史も人種の生存競争の歴史であった。 十九世紀文明の歴史もまた人種の生存競争の歴史である。異なるところは攻守の関係を逆転し、 その運動の方向を一転したことだ。 私は考える。ビスマルクの将来構想は、オーストリアをゲルマン連邦から外して東方に押しのけ、 バルカン諸小国を統合してダニューブに沿って東漸させ、サロニカをその首都とし、その結果ダニ ューブ大河をゲルマン帝国が黒海に出る大道とする。さらにコンスタンチノープルを手に唾して取 って、地中海の上辺に拠点を構え、十九世紀世界において一つの新らしい東ローマ帝国を建設す るにある。私はこれが正しいかどうか知らないが、目下の現状より見ればあえて推測ばかりとはいえ ない。ロシアはポーランドを滅ぼし、静々と西南に向かって長蛇の急坂を下るように運動したが、今 はゲルマン帝国がその進路を遮るので、猛虎が谷に隠れるように、一歩も動くことが出来ずにいる。 しかし南下の志は一日も忘れてはいない。ロシアがコンスタンチノープルに出たいと欲する計画は、 決して一朝一夕に生じたものではなく、また決して一朝一夕に放棄する筈がない。およそ十九世紀 の東ヨーロッパの運動は、多くはロシアのコンスタンチノープル進出の踏み石であった。ゆえにヨー ロッパ将来の問題はこの東ローマ帝国の旧首都がはたして誰の手に落ちるかの一点にあるといっ てもよい。ああこの旧都は決してタタール人種が永遠に所有すべきものではない。これに代わるも のはスラブ人種か、チュートン人種か。いずれにせよ四百年前回教徒により略奪された旧都は、ふ たたび旧主人のキリスト教徒の手に回復されるであろう。これはすでに歴史の眼中に彷彿と見える のである。 ヨーロッパ諸国は、緩めば両軍相攻め、迫ればまた相戦う勢いであり、とうてい単純な運動は起き 23 ない。その運動はヨーロッパのどこに起るだろうか。 物体はもっとも障害の少ない点に向かって運動する。これは自然の法則である。人種の運動もま ったくこの理に従う。昔は東に難く西に易しかった。これが古代において西方に運動が起った理由 である。今は西に難く東に易しい。これが今東方において運動がある理由だ。ここにおいて東方論 という大問題が初めて世界の年代記に生じた。かのロシアの西方の運動は一進一退、うっとうしさに 耐えず、ひとたび矛先を東に向けると、かつて征服されたタタール人を今は追い越して征服し、野 獣を郊原に追うように東へ進んだ。あたかも無人の境を走るように、一瀉(しゃ)千里たちまち中央ア ジアに蟠(わだかま)り、アフガンに隣りし、満州に接し、日本の北門を叩き、黒龍江上に東洋艦隊 を浮かべ、長白山頭に猛鷲の旗が翻る勢いとなった。 今を去ること二十五年前、徳川幕府の末年に、ロシアの軍艦が対馬に来て占領を企てた。幕府 はイギリスの力を借りてようやくその企てを拒んだことは、今なお世人の記憶に新しい。当時イギリス 公使として日本に駐在し、親しくこの件に関係したラザフォード・オルコック氏は、ロシアが再び対馬 に事を起そうとしているという風聞を聞いて、さきごろ「タイムズ」紙に次のように投書した。 「日本政府は近ごろロシアが対馬を狙っているという風説を聞いて憂慮しているようだ。先年私が 日本に在職中にあったことを回想すれば、このような風説は日本政府の心を痛めるに相違ない。ロ シア人民の性質、またその専制政治が他に異なるところをみると、いったん目指したことはつねに 固執し、長くその政略を変えない。ロシアの目指すところはコンスタンチノープルにしろ、ボスポラス 海峡にしろ、中央アジアおよびシナにしろ、または黒竜江および蒙古地方にしろ、ひとたびこれに 目をかけた以上は、どれほどの障害にあっても決して打ち棄てることはない。一時の都合により後 回しとすることもあるが、早晩時機を伺い、ふたたびこれを持ち出し、結局その目的を達するまでや めない。 対馬は朝鮮海峡の東辺にある無比の良地であり、その港は水深く海湾遠く内地に入り、気候は 温和、終年氷結の憂いなく、港門狭く容易に敵兵の侵入を防ぐ。兵略上、あたかも天然のセバスト ポールともいえる要港である。加えて平時には太平洋よりシナ海の貿易を支配し、事あるときは一 挙して朝鮮または北京に攻め入ることが出来る。ロシアにとっては、サハリン以北シベリヤの全地と 24 沿海一帯の領地とを合わせた領土にも勝る価値がある。先年欧米諸国が初めて日本と条約を結ん だのち、まもなくロシアがこれを取ろうとしたのを見ても、ロシアが深くこの島に望みをかけていること がわかる。」 霜を踏んで堅い氷が出来る。ああわが国の危機は目前にある。日本国民は眼孔を東洋の全局 面に注がねばならない。とはいえロシアが東洋に向かって野心を露わにしているにしても、すでに 東洋には一人の主人があることを忘れてはならない。それはだれかといえばイギリスである。イギリ スが東洋にもっとも勢威を振うのはインドを持っているからである。かのロシアは虎視眈々としてその 機会を待ち、インドをイギリスの手より奪おうとしている。最初の手段は、まずアフガニスタンを奪うこ とである。世界の運動は東洋に集まり、東洋の運動はインドに集まり、しかしてインドの運動はアフ ガニスタンに集まる。アフガニスタンこそはイギリスとロシアの争地である。イギリスがインドを守るに はアフガニスタンを守らざるをえない。ロシアがインドを攻めるには必ずここを攻めざるをえない。こ れが英露の間にアフガン争論がつねに絶えない理由である。この問題は東方論の一大争点である。 年来破裂したアフガニスタン境界論は、去年ソールズベリ侯内閣が姑息な手段で一時的に取り繕 ったが、なお噴火山上に噴火口を塞ぐようなもので、かえって将来の大噴火を予想させる。アフガ ニスタンのアミール・アブドゥル・ラーマンは、いまのところ表面は英国の巨僕のように見えるが、そ の実はロシアに心を寄せている。少し東方論に詳しい者はみな知っていることだ。彼は多年ロシア の域内に住み、久しく厚遇を受けたのだ。今やロシアの密使は続々と都のカブールに往来している。 両国の接触は一日の交情ではないことを知るべきである。私はかつて前のペルシア駐在合衆国公 使ベンジャミン氏がペルシアに関する東方論を読んだ際、次のような言葉を発見した。 『ロシアの政略と雄図は昨春(明治十八年)ロシア官吏の口から明快に公言された。彼が言うに は「あなたは東方の境界に関する曖昧模糊な巧言を信ずるな。たとえ誰がヘラート(アフガニスタン の西都)を取る必要なしと誓っても、これを信ずるな。たとえ私がこれを誓っても、あるいはツァー(皇 帝陛下)その人がこれを誓っても、信ずるな。私はヘラートを取らねばならない必要を感ずる。ゆえ にわが輩は早晩これを取るよ。」』 この言葉が確かなら、今日隠れている危険が破裂するのは決して遠くない。私はただ東天をにら 25 んで黒煙が上るのを待つのみである。 イギリスがインドを征服した歴史は、イギリスの罪悪の歴史であり、私があれこれ言う必要はない。 天下の人士、しかも本人のイギリス人ですら承認している。その他ホンコンにおいて、清国において、 日本において、あるいは昨年ビルマにおいて、やむをえず戦うのだと弁護はするが、やむをえない とは、他国を奪わざるをえないことがやむをえないのでないか。私はそのほかにやむをえない理由 を発見できない。その他イギリスが巨文島を、ロシアが済州島を、ゲルマンがマーシャル群島、カロ ライン島を、フランスが安南、台湾、福建を、彼等が何の権利によって占領したか分らない。ただ強 者の権をもって占領したというほか何一つの理由も分らない。 要するに東方論というものは、無残無慈悲なヨーロッパ人民により早晩併呑される運命を持った 憐れな東洋諸国が、いかなる人種、いかなる国により、いかなるときに併呑されるかの問題なのだ。 ビルマを見てみよ。面積はほとんどフランスの三分の二あり、三条の大河は悠然と沃野を横切り、も っとも森林資源に富み、石油・石炭・金属・宝石、ゴム・硫黄などが豊富で、三千万人の農夫がいそ しむ田地がある大国にもかかわらず、ただ未開で弱小という罪により、イギリスのために一朝にして 滅ぼされてしまった。世界に誰一人涙を流す者はなかった。私はキャンベルがポーランド滅亡を誦 した詩に慨嘆せざるを得ない。 「ああ歴史に書かれた血生臭い画図だ。 サルマシヤは罪なく滅亡した。 しかし泣く者とていない。 矛を揮って救う義侠の友もなく、 不運を憐れみ菩提を弔う慈悲ある敵もない。 村落の農夫が死んでも彼のために涙する者はある。 しかし堂々たる大国の死に、なぜ天下の人はみな冷たく看過し、知らないと装うのか。」 私は疑う。かの植物が動物のために生じたように、動物が人類のために生じたように、東洋は欧 州人のために生じたのではあるまいか、と。 私はかつて『神皇正統記』を読んで、次のような古い伝説に出会った。この伝説は、わが東洋の 26 現状によく適合している。 「出雲の簸(ひ)の川上というところに着いた。そこに翁(おきな)と姥(うば)が住んでおり、一人の 乙女をかきなでつつ泣いていた。素戔嗚尊(すさのおのみこと)は誰かと聞いた。『私はこの国の国 神(くにつかみ)です。脚摩乳(あしなずち)、手摩乳(てなずち)といいます。この少女はわが子で奇 稲田姫(くしなだひめ)といいます。先年八箇(やたり)の少女が八岐(やまた)の大蛇(おろち)のた めに呑まれ、今この子がまた呑まれるのです。』と言った。尊は『私に呉れないか。』と言われた。 『仰せの通りにいたします。』と答えたので、尊はこの乙女の姿を湯津(ゆづ)のつま櫛に変え、鬟 (みずら)に差し、八(やみおり)の酒を八つの槽(おけ)に盛って待った。はたしてかの大蛇がやっ て来た。八つの頭を八つの槽に入れて呑み、酔って寝たところを、尊は十握(とつか)の剣(つるぎ) をぬいて寸々(ずたずた)に切った。」 ああインドがすでに滅び、安南も滅び、ビルマもまたついで滅んだ。残る国もただ名義上の独立 国であり、早晩大蛇の腹中に葬られる運命を免れるかどうか。十九世紀の今日、八岐の大蛇はあっ ても素戔烏尊はいないのか。実に嘆かわしい時代である。ペルシアの前途はどうか。シナの前途は どうか。朝鮮の前途はどうか。そしてわが日本の前途はどうなるのか。目を見開いて前途を望めば、 雲行は急である。私は懸念に堪えない。思うに私はただ二十世紀の歴史に、その判決を待つほか ない。 第五回 平和世界 一(第一 外部社会四囲の境遇。裏面より論ず) ああ天下の乱れはいつの日に止むだろうか。私はヨーロッパの現今の形勢を見て実に嘆かわしく 思う。あのヨーロッパ諸国はこのような莫大な兵備をどう整えるのか。必ず莫大な経費を要するであ ろう。その莫大な経費はどこから得るか。必ず社会の富から集めるに違いない。すでにこの兵備が ある以上、この兵備を維持する富があるはずである。つまり表面の強大な武備は、ただちに裏面の 生産機関の膨脹を証明している。 コブデンは言う。「国王の命令は幸いなことだ。戦争というものは自らを廃滅せざるをえない性質 27 を包含しているから」と。戦争ほど高くつくものはないだろう。大きな戦争をしようと思えば、大きな代 価を出さざるをえない。大きな代価を得ようと思えば大いに生産機関を発達させなければならない。 そして生産機関と武備機関の両立はなかなか難しい。ひとたび生産機関が突進するときは、武備 機関は必ず一歩退かざるをえない。ふたたび一歩を突進するときには、さらにふたたび一歩を退か ざるをえない。まるで丸木橋を両岸から渡るように、たがいに接近するに従い、いよいよ両立できな くなる。 一進一退、一方が進んで目的の岸に達するとき、他方は退いて自分の岸に帰らねばならない。 笑うほかない。かの欧州の権謀政治家が、日夜兵備拡張に汲々として、かえってその兵備拡張の 手段となるものが兵備拡張の目的を遮断する大敵だということを忘れている。この十九世紀に武力 の運動を自由にする手段は、ただ富の勢力を増加するほかはない。そして富の勢力を増加する手 段は、武力を減ずるほかにはない。ゆえに帝王宰相らが武備拡張に従事すれば、人を斬ろうとして かえって短剣をおのれの首に突き付けるようなものだ。そうであれば、腕力主義の命運が尽きるの も遠いことではない。 現今の大勢から帰納すれば、欧州を支配する勢力は兵と富との二つの主義である。どちらがもっ とも大きな勢力を有するか。つまり兵が富を支配するか。富が兵を支配するか。これを突き詰めなく てはならない。十九世紀の世界は生産主義と武備主義との一大戦場であり、今日の時代はこの二 主義間の戦争の時代なのである。 この二つの機関は人間と同時に社会に生まれ、また同時に発達したが、異種雑類が互いに混合 し、近代に至るまでその区別ができなかった。試みに上古の歴史に散見する事実を見てみよう。孔 明が餉(しょう)に仇(きゅう)すと言い、鄭(亭)人が温の麦を刈るといい、イスラエル人が牧場を争う といい、高地のスコットランド人が低地のスコットランド人の牛羊穀物を奪うなどという史話があるが、 いずれも戦争の目的は生活の方便を争うことであった。コンスタンチン大帝以後天下の耳目に著明 な戦争は二八六戦あったという。その原因は、レッキー氏の説によれば、第一に宗教上の反目、第 二に経済上の実利の争い、第三は君権と民権の対立より生じたものである。交易の利益の争いは 近世に至るまで戦争の主要な原因であった。かつてスペイン人は、金銀に富む国があると聞けば、 28 全力で征服に向かったのである。 このように戦争とは一種の盗賊であり、交易というものもまた己れを益して他を損する一種の盗賊 である。これは古今普通の観念であり、交易をするとは盗賊となること、盗賊となるとは戦争をするこ とであった。交易と戦争の二つは、つねに盗賊という目的により連帯して起った。その極みとして、 近古の商人は戦争の主義をもって交易を行ない、近古の武士は商業の目的を達するために戦争 をする。商人は商業をもって戦争とし、武士は戦争をもって商業とする。兵と商はほとんど同一物で あり、ただ表裏の姿が異なるにすぎない。このような考え方は、ひとり世の凡庸政治家ばかりでなく、 モンテーニュ、ベーコン、あるいはフランス革命の張本人ともいえる炯眼(けいがん)なヴォルテール なども例外ではない。十八世紀中頃のイギリスの一流政治家チャタム侯ピットは、「フランスと戦端を 開いて仏領カナダを押領したのは、まったくイギリス人が貿易の利を専有するためだった。」と言っ た。あの経済学者セイ氏も、「この二百年間において、ヨーロッパの政治家が貿易上の利を争って 戦争に従事した期間はおよそ五十年を下らない」と言った。このような片寄った邪妄の主義ほど世 の禍いとなるものはない。人は好んで悪をするものではないから、このような禍害を社会に及ぼすの は、その行為を善とし、当を得たものと死ぬまで信じ込んでいるのだ。実に嘆かわしい。これら諸名 士までこうなのだから、世の俗輩が重金説・保護主義・専売主義等に心酔するのも当然だ。 勢いが極限まで進めば必ず変化する。欧州の政治家らが妄迷な政略により人民を苦しめ、国家 を悩まし、あの百姓に、「皆が集まって頭を悩まし、額をひそめて語り合う。わしらの王、わしらの宰 相は略奪を好む。なぜおれたちを困難の極に追い込むのか。父子は相見ず、兄弟妻子は離散し てしまった」といわせるほどの極点に追いつめた。しかし幸いにもヨーロッパの人民はここに初めて 経済世界の新主義を説法する救世主に出会ったのである。 貿易の主義と戦争の主義とは氷炭相容れない。戦争の主義は己れを利して他を損し、両者の利 害は決して両立しないが、貿易の主義はこれに反し、己れを利し、合わせて他を利し、両者の利益 は両立するとの一大真理を欧州諸国に向かって破天荒な説法をした者は、アダム・スミスその人で ある。もちろんイタリア、フランス、スコットランドなどで多数の学者が出て、氏の前後にこの説を唱え た者はあるが、氏の声ほど大きく遠国まで届いた者はない。一七七六年に初めて世界に出た氏の 29 一篇『国富論』は貿易世界の福音書であった。氏は言う、「各国の人民がそれぞれ貿易するとき、 他国の人民の繁栄を猜疑の眼で見、他国の利益は自国の損害とみなす。商業というものは個人間 と同じく、国家間にもおのずから自他の友愛、和睦の契機となるはずだが、かえって敵対、乖離の 大きな原因となる。古今往来、帝王宰相の飽くことを知らない功名心は、商業家・製造者の険悪な 猜疑心のようにヨーロッパの平安に害をもたらしてきた。」と。 氏はまた言う、「隣国の富は、戦争もしくは政略上の交渉においては我に危険を与えるが、通商、 貿易においては我に利益を与えてくれる。なるほど戦争となれば彼の富は我にまさる海陸軍の備 えを可能とする。しかし天下泰平、舟車往来の日には、我が物産貨物をその富によって高貴な価 で買ってくれる。景気のよい市場を与えてくれるのだ。富者は隣の貧人よりも隣の生産者のよい得 意先となるように、富み栄える隣国はよい得意先となってくれるのである。」 このように氏はヨーロッパ諸国に向って呼びかけた。光あれ。商業の太陽は車輪のように中天を 軋(きし)り上り、ついにヨーロッパの面目を一新するに至った。サー・ジェームス・マッキントッシュは 「文明諸国の立法のもっとも重要な点を直截(ちょくせつ)に、全体に、かつ元には戻れないほどに 変革を及ぼしたのは、おそらくこの一書であろう」と。この新主義は向かうところ敵なく、ヨーロッパ全 体を風靡(ふうび)し、山となく河となく、草も木もその威に従わないものなかった。頑固な帝王宰相 も、悪辣(あくらつ)な商人も、奸智にたける政略も、今はほとんど一掃し去る勢いであった。 この新主義の運動をさらに押し進める生産世界の新手段が出てきた。それはワット氏の蒸気機 関の発明であった(一七六九年)。自由貿易主義と蒸気機関とは雲竜相伴う勢いで、一つの必要 は一つの発明を生み、一つの発明はさらに一つの必要を生じ、進歩より進歩に進み、発明より発明 に移り、僅か五十年の間に、これらの大作用は突然に一つの新世界を宇宙に産んだのである。新 世界とはなにか。それが十九世紀の世界である。 今日の生産世界の現象を的確に理解しようとすれば、まず今日の運輸、通信機関の活動する有 様を観察するとよい。なぜなら百貨の離合集散はこの機関によって行われるので、生産会社にとっ て欠くことのできない手段だからである。以下、マルホール氏の『万国進歩の実況』から実態と数値 を引用してみよう。 30 第一 蒸気船の発明 汽船が出来てから航海は非常に便利になり、帆船がひとたび航海する間に汽船は三たび航海 する。たとえその船の数を増さなくても、貿易を実に便利にした。かつ汽船を使えば船舶と水夫を 大いに減らすことが出来る。これも有利な条件である。今もしすべて帆船を使うとなれば、必ず現状 より三万三〇〇〇隻、水夫五五万人を増さざるをえない。こうなれば産出者の利益は出ず、また消 費者を利することもなく、いたずらに物価の騰貴を招くであろう。現在の各国の船舶のトン数を挙げ ると次のようになる(単位は千トン)。 国名 汽船 風帆船 英国 3,363 5,807 合衆国 1,127 3,411 合計 9,170 4,538 スウェーデン・ノルウェー 206 2,003 2,209 98 1,292 1,390 ゲルマン 227 876 1,103 フランス 334 725 1,059 スペイン 175 565 740 オランダ 135 402 537 ロシア 106 392 498 ギリシア 7 427 434 オーストリア 81 339 420 南米 59 95 154 ポルトガル 83 146 229 6,001 16,480 22,481 イタリア 合計 第二 鉄道の発明 首を回して往時を顧みると、かの有名なスチブンソン氏の時代(思うに一八二〇年)より以降、工 31 業の発達は多く鉄道に集中し、もっとも著大な功を奏したことがわかる。スチブンソン氏がロンドンか らバーミンガムまでの線路を作ると、世人は大工事に驚き、あたかもチェオプスのピラミッドのように 思った。しかし近時築造する諸線路に比べれば、難易、大小ともに同日の論にはならない。ちなみ に、バーミンガムの線路はピラミッドの工事に要した労力の五割六分に過ぎなかった。ピラミッドは 十万の人夫を使って二十年を要したけれども、スチブンソン氏はこの工事にわずか二万人の人夫 を使ったに過ぎない。また期間も五年で落成した(スマイルス氏の言)。もう二、三の例を挙げてみよ う。近年の工事では、南米アンデス山よりペルーへわたるオーロル鉄道は海抜一万五六四六フィ ートである。この鉄道は六十三の隧道をアンデスの山中に通し、数多の橋梁を渓谷の間に架けた。 その高さと嶮(けわ)しさは岩石高くそびえるスイスのリギ鉄道に比べればやや劣る。リギ線は頂上 に達するまで僅か四英里(ルツェルン湖の水面より高さ四五〇〇フィート)だが、その間は巨巌突出 して牙のように峻厳である。また地下鉄でもっとも有名なロンドンのメトロポリタン鉄道は一ヤードで 六百ポンドの費用を要した。また地形の嶮しさではなく、高い費用を払ったのはニューヨークの高架 鉄道である。この鉄道は軌道を屋上に架け、諸人が雲集する繁昌地を進行し、あたかも空中を走る ように見える。これを利用する乗客は毎月二百万人を下らない。この事業を起こすには非常の出費 を要し、一英里およそ七万八〇〇〇ポンドの巨額であった。近時プロシア国ベルリン府の大博士シ ーメンス氏は電気を用いてこれと同様な線路の築造を企てた。 敷設してもっとも交通が便利になった最初のものは、一八二五年ストックトンよりダーリントン(イギリ ス)間の鉄道であろう。過去三十年間にイギリが世界各地で敷設した鉄道は十万英里に達し、その 費用は一八億ポンドの巨額に達する。諸大州に拡張した鉄道の景況を示そう。 年代 1830 年 1840 年 1850 年 1870 年 1880 年 ヨーロッパ 550 5,500 24,200 60,400 95,271 アメリカ 340 4,090 20,160 56,300 92,842 アフリカ ― ― 40 580 2,060 アジア ― ― ― 4,500 7,870 オーストラリア ― ― ― 1,300 3,980 32 合計 890 9,590 44,400 123,080 202,023 第三、電信機の発明 電信が世に行なわれようになったのは、そんなに遠いことではない。一八一六年にローナルズ君 がハンマースミスの試みた方法を改良したのち、クック氏およびホイートストン氏らが電信機通信の 免状を得たのは一八三七年で、これを翌々年初めて「グレイト・ウェスタン・レイルウェー」(汽車)に 用いた。しかし一八四八年になっても電信の設置を拒否していた路線が、一七〇〇英里もあった。 当時の人は女王の談話七百語が六十五分でロンドンからリバプールへ届いたのを見て驚嘆した。 また初めて電線を水底に敷設したのは一八五〇年ドーバー(イギリス)とカレイ(フランス)間の電線 である。そして今の海底電線の数は三三〇、長さ九万七六〇〇英里である。現在世界の陸上の電 信線路は次のとおり(音信数は千単位) 国名 英里 音信数 一英里当音信数 百人当音信数 ヨーロッパ 218,450 78,000 350 75 アメリカ 140,550 24,000 170 32 アジア 22,400 2,000 90 13 アフリカ 14,050 1,000 70 5 オーストラリア 25,700 4,000 160 150 421,150 109,000 260 9 合計 これに海底電線九万七五六八英里を加えると五一万八七〇〇有余英里となる。 第四、郵便法の進歩 どこの国でも、郵便物の数はその国の商業の盛衰と知識の進度を表わす。次に各国の一人当り の書状数を掲げて、十年間の進歩の跡を示す。 国名 一八六七年 一八七七年 英国 27 35 スイス 24 30 合衆国 15 19 33 オーストリア 13 18 ゲルマン 9 15 オランダ・ベルギー 9 14 10 10 フランス ノルウエー・スエーデン・デンマーク 7 9 オーストリア・ハンガリー 6 8 カナダ 6 8 スペイン・ポルトガル 4 5 イタリア 3 4 スペイン領アメリカ 1.5 2 ギリシア 1.5 2 ロシア 0.75 1 日本 1 1 第五、新聞紙の発行 次に掲げる表は世界各国の新聞創始の年代と、一八四〇年および現行の発行紙数ならびに年 間の新聞用紙使用量(トン)を示す。 国名 創始の年 一八四〇年 一八八〇年 年間消費高 英国 1622 493 1,836 合衆国 1704 830 6,432 フランス 1605 776 1,280 ゲルマン 1524 305 2,350 オーストリア 1550 132 876 92 ロシア 1714 204 318 72 75 376 40 オランダ・ベルギー 1757 34 168 525 134 244 スウェーデン、ノルウェー、デンマーク イタリア 1644 104 120 30 1562 210 1,124 38 1704 92 150 10 ― 54 230 17 スペイン、ポルトガル スイス スペイン領アメリカ 1728 98 850 20 カナダ 1765 88 340 20 西インド 1731 37 50 5 オーストラリア 1805 43 220 15 トルコ 1797 8 72 ペルシア 1838 2 ― 一 インド 1781 63 644 一 シナ 1880 4 一 30 アフリカ 1824 14 40 一 サンドウィッチ 1835 1 6 一 一 日本 ― ― 34 ― 合計 ― 3,633 17,348 1,460 現在の新聞紙の発行部数を挙げると合衆国は四百万部。英国は二百万部。その他諸国は合わ せて六百万部である。 以上諸々の発明と進歩は、互いに関連しながら動いていき、著大な変化を地球上にもたらした。 あの豪胆不敵なマゼランは、水平に明滅する南極星の微光を頼みに千古未航の大洋に乗出した。 驚喜の涙をそそぎながら、天が自分の雄志を試みる機会をこの大海洋に与えてくれたのを祝い、 太平洋の名付け親となった。当時、地球の一周には実に三年の歳月を要した。しかし彼が危険を 犯した行為は、もとより尋常一様の舟子のできることではなかった。歴史上の一人物マゼランだから 35 こそできたのだ。ある詩人が大洋は窮(きわ)めることができないと歌ったように、大洋を航海するの は天に上るより難しい現実であった。それが今では僅か八十日間で、船中に寝ながら地球を一周 出来る。ロンドンから自然の風力に頼る帆走船で喜望峰の荒れ海をしのぎ、カルカッタに達するに は、快走してもおよそ四ヵ月を要した。それが汽船の便を借りれば九十四日となり、スエズ運河開削 の大事業が一八六九年に成就した後は、カルカッタはおろか東洋の極にある日本にすら四十日内 外で達することができるようになった。あの天に達するピラミッドの大工事を成就し、万古の年代を 通じて他の人類を見下したエジプト人が、数千年前その労力と経験とを尽くしてもついに果たせな かったこの事業も、フランス人レセップス氏は片手を振って難なくこれを実現してしまった。その余 力を駆って、今はパナマ地峡の開削に従事している。 昔の人がこれを聞いたら何と言うだろうか。鉄道についても、前世紀の人は夢にも幻にも思い当 たらなかった。ニュートンが「将来あるいは一日五十里を快走する方便が発明されよう」と予言した のを評して、ヴォルテールは「世にそんな馬鹿げたことがあるものか」と大笑いした。だが今鉄道は この太平洋の岸頭から大西洋の岸頭までほとんど一週間かからずに着くではないか。電信の速さ については実に驚く。今や英京ロンドンから米国ニューヨークに至るまで三千余里の海底を、ただ の二分半で通信ができる。十分もあればその回答さえ聞くことができるという。スペンサー氏曰く、 「エディンバラの一市民が電信によってロンドンの一市民に通信する時間は、電信局に電信を依頼 し、電信局よりこれを受け取る時間を算入しても、なお僅かであり、この二市の間に動物が一列に並 び、その神経によって刺激を通ずる時間の四分の一よりさらに短い。」 社会の神経は動物よりも活発に動く。これは驚くべきことではなかろうか。これらの新発明は社会 の表面に一大刺激を与えたばかりか、社会を組織する一個人の感情にいちじるしく変動を与えた。 上林の秋雁に頼らなくても郵便は至るところに通信を可能にした。風に吹かれて故山を眺め泣く必 要はなく、世界はみなわが故郷だ。『古今集』や『唐詩選』の世界はこれらの発明のために失われ、 自然の境界はいよいよ消え、想像の帝国はいよいよ狭くなった。事務の勢力は日に日に長じて詩 人の勢力は日に日減じていく。詩人のためにはいささか気の毒だが、わが社会進歩の現象としてこ れを見れば、天に向かって感謝せざるをえない。これらの交通、通信機関は燎原の火のように、水 36 が低きに流れるように、政治的境界を日に日に侵食して経済的な領地としていった。実に現在のヨ ーロッパ諸国は、政治的に観察すれば種々の国体もあり、種々の人民もあり、種々の制度もあり、 たがいに睨み合い、お前がおれを斬れば、おれはお前を刺すという意気盛んな表情を見せてはい るが、経済の世界は、片寄らず、党派もなく、着実に各国、各民族を網羅して一つの連邦に向かっ ている。 マコーレーによれば、「中世の封建割拠時代の欧州諸国はただ一つのローマ教を信じ、唯一の 法王を戴く宗教上の連邦を組織していた。しかし十九世紀のヨーロッパは実に生産機関のために 一大共和国となった。」誠に愉快である。 ビスマルクは「愉快だね。今日初めてルイ十四世以来深い仇のあったフランスに復讐することが できた。」とい言い、フランスのガンベッタは「看よ、看よ。いつかお前に向かって、セダンの恥辱、パ リ城下の恥をそそがずにおくものか。」と言った。しかしこれは武装機関の支配する政治世界の妄 想にすぎない。経済世界においてはフランスもなく、ゲルマンもなく、また恩や仇もない。イギリス人 がいかに強情、高慢であっても、酔いを楽しむにはフランスの葡萄の美酒を汲まねばならない。ゲ ルマンがいかにフランスを仇としても、フランスの流麗艶美の文学はこれを賞し、書籍を買わずには いられないだろう。鉄を生ずる国は鉄を輸出したらよい。砂糖が必要な国は砂糖を輸入すればよい。 あの政治世界においては、ここは我の領地、あそこはお前の所有だとして、城を構え、鉄塁を築き、 実に窮屈な世界だが、実生活上は決してそうではない。経済の世界は平坦な大道を矢のように、 世界中を利のために行き、利のために来る。風のように来て、潮のように行く。物資は需用の求心 力があるところに集まり、供給の遠心力あるところから出ていく。世界はただ商利の大競争場であり、 物資の集散はただ商利の市場で行われる。例えば水道の蛇口は各人の所有を表すけれども、地 下の導管には水が相互に往来しているようなものだ。経済世界の眼で見れば、権謀政治家らが権 謀術数たがいに政略を交わし、経済世界の運動に抵抗するのは、漁村の児童が海浜に立って砂 石を拾い、波を遮ぎろうとするようなものだ。可憐の至りといわざるをえない。 交通、通信の機関がここまで発達した現在、これを利用する貿易はどれほど進歩したか。次の表 を見てもらいたい。過去五十年間に世界の貿易は八倍に増えているのだ。 37 国名 一八三〇年 英国 一八七八年 88,000 増加率 601,000 7.0 英国植民地 21,000 322,000 15.0 フランス 42,000 368,000 9.0 ゲルマン 39,000 319,000 8.0 30,000 275,000 9.0 合衆国 35,000 225,000 6.5 オーストリア 120,000 160,000 13.0 ロシア 24,000 128,000 5.5 南アメリカ 14,000 101,000 イタリア 11,000 98,000 9.0 66,000 8.0 39,000 3.5 15,000 85,000 6.0 350,000 2,787,000 オランダ・ベルギー スエーデン・ノルウエー 8,000 7.0 スペイン・ポルトガル 1,000 トルコおよび東方 合計 8.0 〔マルホール氏『万国進歩の実況』〕 次に製造面を見る。近世社会の進歩と工業生産の進歩はほとんど同一歩調をとっている。今ヨ ーロッパでは一二五〇万人の職工を雇用し、ますます盛んな生産をしているが、かつてのワーテル ロー戦争(一八一五年)当時は実に幼稚な姿だった。以後、製造工業が改良進歩した国は、必ず 繁栄をきわめている。次表は各国の製造工業の状況である(単位は千人、百万ポンド、ポンド)。 国名 職人数 英国 2,930 産出高 665 職工一人当り産出高 227 38 フランス 1,936 416 215 ゲルマン 2,781 286 103 ロシア 1,500 160 107 オーストリア 1,100 130 118 117 99 72 118 42 108 20 91 2,704 846 313 50 50 100 2,804 182 オランダ・ベルギー 1,180 スペイン・ポルトガル イタリア 610 390 スエーデン・ノルウエー 合衆国 植民地その他 合計 220 15,401 〔マルホール氏『万国進歩の実況』〕 ペンス氏は「一八三三年の綿糸製造高は一年に五十億里に達した。これは地球の表面を二十万 回廻り、地球太陽間を五十一回往復し、地球の太陽周回軌道を八回半廻る長さである。この木綿 布の一ヵ年の輸出高は赤道を十一回廻る量となり、一直線に張れば地球から月に届いて余りがあ る。」といった。五十三年前すでにこの数字である。今日ではさらに生産は拡大している。 こうした商業の進歩は交易上の現象にとどまらず、さらに一つの驚くべき現象を生んだ。それは 信用制度の発達である。信用制度は実に近世文明の一大事業であり、もしこれを前世期の人に話 せば、こんな奇怪な仕組は『アラビヤン・ナイト』の小説物語だと冷笑するだろう。この制度の奇抜な 仕組みは、今世紀の人でなければ決して理解出来ないだろう。いわゆる負債というものは一種の富 であり、社会には負債の売買により一種の商業を営む銀行というものがある。この信用機関が商業 世界で果たす役割は、蒸気機関が世界中に広がったように、絶大な働きをする。ダニエル・ウェブ スターは言った。「信用というものは近世商業の大立者である。これがあるため各国が富ます財産 は、全世界の鉱山より採取する金銀の幾千倍にもなるのだ。このために勤労を励まし、製造を盛ん にし、海外の通商を飛躍させ、各人民、各王国、あるいは各民族をたがいに交際させ、文明を伝播 39 したのだ。このために精鋭な陸海軍を整理し、兵数に依頼するばかりの暴力をなくした。このため国 家の勢力は、武力ではなく才知と富とその国に適した生産力などの基礎によって立たざるを得なく した。」 これは決して作者の誇張ではない。その実際を知ろうと思えば、世界信用の問屋ともいえるロン ドンのロンバード街に行けばよい。ヨーロッパの生活社会の進歩は私が喋々するまでもない。天下 の活眼の士はみなよく知っている。明治十五、六年のころパリに滞在した在野の政治家板垣退介 氏は、「私がフランスに滞在したとき、学者のアコラス氏を訪問した。氏は私に向かって、『あなたは ヨーロッパに来て事物を観察し、いかなる感想を持ったか』と問われたので、私は『ヨーロッパにいる 日がなお浅いので、詳細な事情はわからないが、日本で聞いていたとおりヨーロッパ哲学の進歩は 驚くほどである。今回私がもっとも驚いたものは二つある。その一は生活社会が大いに進歩したこと であり、その二は生活社会に比べて政治社会は大いに進歩していないことだ』と答えた。アコラス氏 は大いに私の言に賛成して言うには、『私もまた三日前に朋友と相談し、十九世紀において何にも っとも注意すべきかという問題を本にしたところだ。その内容は、欧州では生活社会は進歩したが、 政治社会は進歩していない、ゆえに十九世紀においてさらに改良すべきは政治社会なりというもの だ。あなたの観察はまことによくわがヨーロッパの現状を看破した。』と意外な賞讃を受けた。ヨーロ ッパの生活社会の進歩のありさまを観察すると、すべて財ある者、知ある者、力役者らが合同して 精巧広大な事業を興すので、衣食住をはじめ、農工商に至るまで、善を尽くし、美を尽くし、地方の 村落にも煙突が空を衝き、煙が天を覆う。また高層のビルが雲にそびえ、瓦が陽に輝く。そして富 豪の家屋がかしこに立ち、容貌優れ知的な人、衣服頭飾の華麗な人をあちこちに見る。一歩を進 めて観察すると、あるいは力役者の会社のもとで荷物を運搬する者、会社で為替手形により迅速な 売買をする者がある。道路は砥石のように平坦で自在に交通運搬し、水のない土地には運河を掘 って流水を通じ、まるで人力で自然を圧倒した景状である。 一方眼を転じて政治社会を見れば、一個人の自由に任すべきことでも、なお政治の干渉を免れ ないものがある。あるいは市町村の自治に任すべきことも、なお中央政府の牽制を受けるものがあ る。政党と称するもののなお私党の大弊を免れないものがある。たとえばフランスの下院において 40 貴族を放逐する決議をしたとか、イギリスの下院ではかのブラッドローが誓いを承諾しないため議院 に入ることを許さないといった児戯に類することがある。」 真にそのとおりだ。ヨーロッパでは、その昔は政治社会が生活社会を支配したが、今や生活社会 が進歩して逆に政治社会の進歩を促している。経済世界の交流が政治世界の割拠を打ち破り、生 産機構が武備機構を転覆するのは、早晩避けられない命運であろう。 第六回 平和世界 二(同上) 富は十九世紀の一大運動力である。兵力が政治世界を支配する力だとすれば、富は経済世界を 支配する力である。政治世界が経済世界の影響下にあることを知れば、兵力もまた富の支配を受 けることがわかる。兵力の影響が広大なことを知れば、兵力を支配する富がさらに広大な力を持っ ていることがわかる。十九世紀の世界は富が兵を支配する世界である。 ヨーロッパの歴史において常備軍の制度が始まったのは、富が兵力より一層強大となった結果で あるといわなければならない。なぜなら常備軍は全国皆兵の社会を一変して、全国の一部を兵とし、 その他多数の人民を他の殖産の事業に従事させ、いや、従事させなければならない必要が生じた からである。人民は自分の口を糊するにとどまらず、あわせてその厄介者の常備軍をも養わざるを 得なくなったのだ。 常備軍の創設と火器の発明とは、その時代を問えばほとんど同時であり、その関係を問えば実に 精妙不思議な因縁がある。この解説はしばらく他の議論に譲り、私はただ常備軍は火器によって成 り、火器は高価な経費によって成り立つものだと明言しておく。見よ、今日世界に君臨する大都も、 近世史の始めの頃は実に哀れな微少な存在であった。彼らはどのように封建豪族の強い収奪を免 れたか。ただ王政の大翼中に隠れたからである。 帝王はなぜ都市に自由の特許を与えたか。なぜ都市の自治権を放任したか。なぜ都市の味方と なりつねに保護したか。なぜ通商貿易を奨励しその進歩に加勢したか。他に理由はない。ただ租 税を得るためであった。簡単にいえば、常備軍を保つ費用を負担させるためであった。イギリス憲 41 法史を一読した人は知っているだろう。国王はなぜ都市の市民を国会に出席させたか。なぜ、また 何の必要があって国会を開設したか。何の必要があってもっとも大切な権利を惜しげなく市民に譲 ったか。それは唯一の必要、つまり兵備を維持するためであった。 このように生産機関は、始め武力を備える一手段として武備機関内で養成されたけれども、その 性質上、大きな自己発展力をもっていたので、一粒の種が春陽に乗じて生長するように、ついに空 中を舞う鳥も巣くうほどに成長したのである。帝王宰相らが後悔してもいまさらどうにもならない。たと えばイギリスではバジョット氏が言うように「ヘンリー八世の奴隷的な国会は一変してエリザベス女王 の不平的な国会となり、さらに一変してジェームス一世の激昂的な国会となり、またさらに一変して チャールス一世の謀叛的国会へと」生長した。今では神権説の主張者であるチャールス王も、やむ をえず製造人・職工・商業家・貿易者・農夫らに膝を屈し、その鼻息を伺う存在となってしまった。そ の原因は、ただ富の力が兵力を制したからである。 ヨーロッパでは野蛮人の乱入以後、ことに常備軍創始以後の歴史は、実に兵と富との消長、盛 衰の事実が充満しており、兵・富戦争史といってよいくらいだ。私はここまで読んでくると、まるで木 曽山中の旅客が、尺幅の天を眺めながら寂しい山中を踏破し、初めて碓氷峠の頂上に至り、そこ ではるばると関八州の平原を望むように、快活な気持になる。 上古において野蛮人が開化人を踏みにじったのはほかでもない。ただ腕力で富を制したのであ る。今日開化人が野蛮人を滅亡に追いつめるのはほかでもない。ただ富によって腕力を制すること ができるからである。実に今日の世界は富により兵を制する時代であり、「富はすなわち力なり」とは 今日の大勢を看破した警語といわざるをえない。アダム・スミス曰く、「近世の戦争は火器の莫大な 費用を支弁できる国民に有利に働いた。すなわち富んで文明な国民が、貧にして野蛮な人民に対 し勝利を占めた。上古においては富んで文明な国民は貧にして野蛮な人民の攻撃を防御するの に非常な困難を感じたけれども、近世においてはかえって貧にして野蛮な人民は富んで文明な人 民の侵入を防御するのにはなはだ困難を感じている。火器の発明は一見すれば禍害的なものであ るが、文明の拡張と維持のためには恩恵あるものといわざるをえない。」 そうであれば、私たちは知らねばならない。今日東洋諸国がヨーロッパ諸国に呑に込まれるのは、 42 我らが貧にして野蛮な国であり、彼らは富んで文明な国だからである。これは自然の理で、疑うこと はできない。 あのロシアは全地球の二十六分の一、または全陸地の七分の一を占め、八五〇万平方マイルの 領土を持っている。しかし今古無比の大帝国にもかかわらず、そしてまた兵力強大で、欧州列国を 蹂躙するに足る兵馬をもっているにもかかわらず、その勢力を欧州で伸ばすことが出来ず、東亜に おいても思うほどの成果を得ていない。その理由は、イギリスの抑制力のためだ。そしてイギリスは なぜ抑制力を持っているのか。世界の海上を支配する海軍があるためか。そうではない。イギリスが 海上の王になっているのは海軍ではなく、商船があるためである。マルホール氏は「一八七七年に 諸国の港湾に出入りする船舶の合計は、一億二三九万トンだが、各国の船舶は四九一五万トンに 過ぎず、残りの五三二四万トンはすべてイギリスの商船である」という。イギリスはこの莫大な商船を 何の必要があって所有するか。隆盛な商業があるからだ。実にイギリスの仲買商は全世界の五割 三分余りの多数を占めている。英人ポーター氏は「イギリスにもし熟練した製造能力がなかったなら、 ナポレオンとの戦いに勝算はなかった」という。イギリスがロシアを抑制する力はここにあるのだ。そ してイギリスが世界に覇を唱え、世界の最強国ロシアを押え込んでいるのは、ロンバード街に貨幣 市場があるからだ。ニューカッスルの造船所あるからだ。マンチェスターに綿花製造所、シェフィー ルドに鉄器製造所があり、ロンドンに帆柱が乱立する港湾があるからだ。これらの製造所の煙突が 吐き出す万丈の黒煙は、敵の来襲を知らせるのろし台のように、ロシアの野心を閉じ込めている。 いかにロシアが人民に鞭を振い、血を絞っても、限りある資金では限りない経費を賄うことが出来な い。策が窮し術が尽き、最後の手段は自国の不信用を世界に広告する高利の公債をロンバード街 で募集せざるをえないのだ。あのゴブデン氏はイギリス人に向って「金をロシアに貸すのは噴火山 上に財産を置くようなものだ」と忠告したように、ロシアはもっとも不安な得意者だから、金利はことさ ら高くなる。イギリスがロシアを凌駕する理由は富であり、ロシアがイギリスに凌駕されるのは富の不 足による。では富と兵とは今日の世界においてどちらが大きいか。この答えは知者にまかせるほか ないが、私は富の力は兵より強く、兵の力は富に及ばないと考える。理由は、今日の世界において は兵は富によって維持することができるが、富は兵によって維持することができないからである。 43 考えてもみよう。もし今日、兵の力が強くて富を支配することができれば、ビスマルクは苦労して 十九世紀のライカルガスとなり、鉄銭を鋳造し、貿易を禁じ、港湾を鎖し、関門を設けて往来を遮り、 世界のほかにさらに一つの新世界を作り、天地のうちさらに一つの新天地を開き、ゲルマン帝国を 近世のスパルタとし、思うままに武備の機関を強大なものにしなかっただろうか。そうすれば一国を 挙げて城とすることも出来た。人民を挙げて兵とすることも出来た。訓練のために盗賊を公許するこ とも出来た。演習のためといって奴隷を襲撃させることも出来た。将来兵士となる見込みない虚弱な 子供は葬ってもよかった。 しかしビスマルクはこういう得意技をせず、なにを苦しんで不得意なソロンを学ぼうとしたのか。な ぜ大略奪家の資格に加えて商業家の性質を合わせ持とうとしたのか。なぜドイツの製鉄事業をベ ルギーやイギリスと競争し、青銅器や燈火器をオランダ、ベルギー、スペイン、イタリアの市場にお いてフランスの製品と匹敵させようとし、また近来東洋ことに日本・シナの貿易市場において東洋の 旧主人イギリスを圧倒しようと企てたのか。彼が経済的自然の境界を超越して政治上もしくは兵略 上の手段を取ったにせよ、彼の目的が貿易者の善意ではなく陰険な外交家の分子を含むにせよ、 なぜ彼はこのような事業を経営する必要を感じたのか。私はこれを怪しまざるを得ない。 しかし少しも怪しむことはない。これがいわゆる十九世紀の大勢だからである。富の実力、つまり 富でなければ兵備を保つことが出来ないという要請が、外交政略家の真相を持つビスマルクに貿 易者の仮面を被らせたのである。私はゲルマン人民の前途に一筋の微光があるのを見て祝わずに はいられない。人の国を奪うために貿易するのも貿易、人を殺すために貿易するのも貿易である。 収奪の心をもって貿易するのも堯舜の心をもって貿易するのも、貿易はすなわち貿易である。貿易 の太陽がひとたびゲルマン帝国の中心を照らすときには、彼が奇々怪々な魔術により幻出した武 備という妖星は光を失うのは当然である。去年九月八日の『ドイツ官報』は「我々は十余年前まで戦 勝しなければ得られないと信じていたものを、今や産業の功によって得るという幸運に達した」と書 いた。ドイツ国民も今それを悟っただろうか。あのビスマルクの強引、執拗さもなお十九世紀の大勢 の中では泥中にもがくようなものだった。ましてビスマルクにならおうとする者、ビスマルクにあたいし 44 ない人には出来ないことだ。世の凡庸な政治家よ、願わくは眼を転じて汝の後頭を顧みよ。 一見すればヨーロッパは腕力の世界だが、少し観察すると裏面にはさらに富の世界があるのがわ かる。兵と富とは二つの大勢力であり、「日月並びかかって天地を照らす」ありさまだ。しかしさらに 精密に観察すると、兵の太陽はいかにも輝かしいが、夕映えすでに西山に入ろうとする絶望的なも のである。一方富の太陽は紅輪鮮やかで、まさに中天に躍り上ろうとする希望に満ちている。しかし さらに一層の思考を凝らすと、兵の絶望的な光輝も、富の希望的な光輝を反映して瞬時に幻出し たものである。これをたとえると、月はもともと光輝のないもので、ただ太陽の光輝に反映して美妙の 光を放つように見える。月の光は太陽の光のだ。もし太陽の光がなければ月光などはない。今日兵 に勢力があるのは富の勢力を借りているからだ。もし富の勢力がなければ、兵の勢力とて別に見る ものはないであろう。世の活眼家はこの道理をたやすく承認してほしい。昔武備のために存在した 生産は、今日一変して生産のために存在する武備となった。目的は一変して手段となり、手段は一 変して目的となった。君と臣は主僕の位地を逆転した。汗を流し骨を折り、武士に奉じた商人農夫 を保護するために、ワーテルローの豪傑ウェリントンのような大将軍も、トラファルガーの英雄ネルソ ンのような水師提督も、血戦奮闘してくれた。我々は天理人道のために大いに祝いたい。 今日、兵備というものは単に生産を保護する必要品にとどまらず、生産機関の勢力を天下に広告 する贅沢品となっている。これは奇異な現象といわなければならない。たとえば徳川時代は、天下 泰平、戦火を見ず、寸鉄を用いなかったので、戦国時代の必要品であった刀剣は一変して贅沢品 となった。豪商や高級武士が正宗の太刀、兼定の短刀、その鍔(つば)、小柄といい、黄金を装い宝 玉をちりばめ、意気揚々と市中を横行するとき、道傍の人が皆あっぱれ貴人だと指さし語るのを見 て得意となったように、欧州諸国においてもクルップ砲といい、アームストロングといい、甲鉄艦とい い、水雷火船といい、すべて国光を輝かす一種の装飾品であり、「わが国にはこんな軍備があるぞ」 と他国に誇示するに過ぎない。要するに戦争というものは、多くは軍備の戦争であって、実際に戦 端を開く前に勝敗が決まってしまう。その理由は、富の多少が勝敗を決めるからである。だからこそ、 富は十九世紀を支配する一大勢力といわれるのである。 45 第七回 平和世界 三(同上) こうして富と兵とは決して同一の主義ではない。戦争を支配する主義は、商業を支配する主義で はない。たとえ二個の山岳が出会い、併行の二線が出会ったとしても、二個の主義は決して合体す るものではない。この事実を証明したのは、富が兵に向かっておさめた第二の大勝利であった。 人間は主我的な動物である。私は決してベンサム氏の宗教に随喜して実利主義を主張するもの ではないが、人間を支配する主な力は何物かと問われれば、躊躇なく自愛心だと答える。一個人を 支配する主な勢力が自愛心だとすれば、この一個人により組織された一国を支配する主な勢力も また一国の自愛心である。一人であっても、一国であっても、自愛心すなわち利己心によって支配 される一つの動物であると知れば、彼我の利益が両立しない場合は、決して自分を損して他を益 することはしない。 いかにキリスト教の感化が広大無辺であっても、いかに仏法の功徳がたくさんあっても、キリストの 愛も釈迦の憐れみも、自家の利益と他の利益と競争する限りは、火中に油を投げるように、かえっ てますます焔の勢いを加えるに過ぎない。そして上古から近世に至るまで、世人はみなもっとも身 に適切な、直接に必要な貿易の利益は彼我両立しないものと妄想していた。この妄想が各人の頭 脳と社会に隅なく存在する間は、どんなに博愛の説教をしても、道傍の石地蔵に向かって話をする ように、聞く人はもとより説く人さえも心中では決して心服しなかったことは当然であろう。しかし貿易 の法則は彼我の利益を並立することにあり、貿易の法則はすなわち人情の法則、宗教の法則、愛 情の法則なのである。この万古の真理を喝破し、俗耳を驚かせたのはアダム・スミスその人であった。 そしてこの法則を実行する作用を発明したのがジェームズ・ワットであった。もし国家を破り、社会を 滅ぼし、百姓(ひゃくせい)の力をそぎ、百姓の財を強奪し、人の父を殺し、子を孤児にし、乱政虐刑 をふるい、もって天下を壟断する人を英雄豪傑とするなら、ナポレオン、ビスマルク、ゴルチャコフら はそういう人であった。もし襤褸(ぼろ)をまとうものに身体に合った新衣を与え、半ばは土を食う貧民 に肉を与え、雨露霜雪が侵す茅舎(ぼうしゃ)を一変して愉快な家宅とし、万国の怨恨を一変して友 愛の情とし、兵気が消え、日月かがやく希望を前途に生み、社会の結合は強迫の結合を頼まずに 46 随意の結合を頼み、随意の結合は利益の結合であり、利益の結合はすなわち愛情の結合だという 一大真理の燈火を世界に与えた人を、世界の尊敬と敬慕に値する大人とするなら、スミス、ワットの 二氏がそうであろう。社会の変革は決して一個人の力にのみ頼ることはできない。しかし一個人の 力により十九世紀の新世界を創造することに尽力し、かつその功労があった人は誰かと問われたら、 ただちにこの二氏を挙げねばなるまい。わが十九世紀文明の世界は、金冠を戴く帝王よりも、三台 に坐る宰相よりも、華麗な言辞を用いる文人才子よりも、人民の偶像として雄弁を振う国会議員より も、活溌老練な商業家よりも、敬虔な宗教家よりも、この二氏に負うところが多いといわざるをえない。 今日の世界はスコットランド山中の二人の寒儒の手により作られた世界である。二氏は世界の大恩 人であり無冠の帝王である。願わくはわが現今の人民よ、将来の人民となる青年よ、少しはナポレ オン、ビスマルクを嘆美する熱情を一転して、この二恩人を嘆美せよ。 近時の世界において真正の平和主義はスミス氏より出たといわざるをえない。もとより氏の以前に 平和主義を講じた人物は大勢いる。しかしそれはただの空論であった。つまり快楽主義を敵として、 苦痛主義を本尊とし、世情に反し、人情に逆らい、名利を求めて奔走する人々に向かって、ストイッ クな哲学者になるよう求め、苦行の釈尊や、面壁九年のダルマ大師を見習えという迂闊(うかつ)で 苛酷な空論ばかりだった。その結果、一方で平和主義を講じ、一方で闘争主義が流行した。議論 はただの議論であり、実際は別に実際だから、いかに熱弁をふるっても空言は世に迎えられない。 しかしスミス氏は、平和というものは自家の利益を犠牲とした平和ではなく、自家の利益を得るため の平和だと唱えたのだ。これにより初めて実際に行動を伴う平和主義が生まれ、滔々(とうとう)と江 河が流れるように、防ぐことのできない勢いとなった。平和主義は一つの極楽浄土であるが、上古 の平和を得ようとすれば、仏者のいう剣山をよじ登らなければならない。極楽に入るには剣山によじ 登る苦痛を経なければ駄目だと言われれば、何人も逡巡せざるを得ない。しかしスミス氏が出てか らは、なんの苦もなく、いわゆる剣山もなく、三途(さんず)の川もなく、足音高く平和の極楽に達す ることができる。陶朱公は術を用いて、釈迦の住む極楽に旅行する道を教えた。この門がひとたび 開けば、誰もが喜んでここに入ろうとする。平和の主義は静かに勢力を社会の中心に広げているの だ。 47 戦争によって商業をするより、商業によって商業をするのが本来の姿だ。貿易の主義は平和の主 義である。したがって富がますます増えるにともない平和主義がいよいよ進歩するのは当然である。 たとえば一昨年の清仏の開戦に際し、上海在留の外国人らが平和を欲するあまりに、資金を出し 合って二国の争いを調停しようとした。これは決して両国民が塗炭に苦しむ状況を見るに忍びず行 なった道徳上の行為ではない。事情を知らない眼で見れば、ほとんど理由もなく因縁もなく、他人 の不機嫌を気に病むように、意味のない怪事にみえるかもしれないが、決してそうではない。彼ら外 国商人は多少の出金の苦痛を忍んでも、戦争のために取引上大きな損害をこうむらないよう企てた のだ。利己の一念が外国の人民に関係ない二国の和睦を計画させたのだ。私はこのように世のい わゆる慈善家・道徳家・博愛家の誠心から出ずに、かえって利に汲々とする商人より出たことを見て、 理論というものが実に価値なく、価値ある理論は人間の自愛心とは一致しないものであると知った。 平和主義と自愛主義とは、富と兵の関係とは違って決して敵対の主義ではなく一致協同する主義 なのだ。戦争に敵するものは平和主義にあらず、むしろ利己主義である。平和主義というものは、た だ利己主義を母体として生長したもので、利己主義と一致して初めてその力を発揮できるのだ。私 は戦争主義がこの意外の大敵である利己主義に味方したことを悲しみ、平和主義がこの意外に勢 力がある利己主義の助力を得たことを祝いたい。腕力主義を支える恐るべき大敵は、実にこの利己 主義である。ただこの利己主義である。今日に至るまで腕力主義が社会に横行した理由は、利己 主義と一致したからである。つまり利己主義が勢力を貸したのだ。しかし今や人を損っても自分の 利にはならない、自分を利するには人を利することだという主義が社会に勢力を有するようになった。 今となっては誰が腕力主義の味方となるものか。見よ見よ、今日心中に天下の泰平を祈らない者は ただ二、三の権謀政治家、貪る狼のような帝王宰相、もしくは無主義な二、三の陸海軍人など、もっ とも少ない少数にとどまることを。これらの人々が今なお幾分かの勢力を社会に有するようであるが、 それはただ過去の因果よりしてやむをえないので、これから長くは続かないであろう。今日の世界 では一個人が平和主義を唱えるばかりでなく、一部の階級の人々が平和主義を唱えるばかりでな く、一国を挙げて平和主義を唱えるものがあるのだ。その国はどこにあるのか。それは我らの東隣、 北米連邦である。 48 明治十七年八月十四日開設の万国講和協会で米人ブラウン氏は次のような演説をした。 「わが合衆国政府は人口五千万を有するが、平時にはわずか二万五〇〇〇人の常備軍で足り るとしている。これはわが国独立以来、兵乱が少なかったためである。この百年余りの間に外国と兵 を交えたのは一八一二年(イギリスとの役)および一八四六年(メキシコとの役)の二回しかない。そ の間、スペイン・フランス・ロシア・メキシコその他の諸国より購入して領土に編入した土地は、諸君 の熟知するようにきわめて大きく、人口もまた三百万より五千万に増加した。このように国土いよいよ 広く人民いよいよ多くなったのは、みな平和主義によるもので、一民一土も兵力で征略することはな かった。ヨーロッパでつねに欠かせない常備軍は、わが国では内、秩序を保ち、外、国威を発揮す るために必要を感じない。南北戦争は四年にまたがり、地を荒し、命を害し、言うに忍びない惨状を 呈したが、私はこれによりますます常備軍が不必要になったと確信する。この内乱で南北双方が募 集した兵は無慮百五十万を下らなかったが、乱が終息したのち数年を出ずに、おのおのその常業 に戻り、兵員は僅かな定数に落ち着いた。常に大兵を抱えていれば、ともするとこれを使おうとして、 乱を収めるはずのものがかえって乱を開くなど、昔からその例は多い。まことに嘆かわしいことだ。」 私はこの発言を聞いて不思議に思う。ヨーロッパの強国がたがいに虎視眈々と剣先を削り、地球 の表面には一日も戦火が絶えなく、一日も砲声を聞かない時がない今日、どうすればこの国がこの ように光栄を保ちつつ、国体を維持できるのか。北米連邦は、まるで刀剣を振り回し銃砲を打ち合う 修羅の巷(ちまた)の中で、悠然として平服を着、脱刀して横行濶歩する者のようにみえる。この傍 若無人の挙動は、誰もが驚かざるを得ないだろう。この国はなんの頼むところがあってこんな大胆な 挙動をするのだろうか。他の強国はなんの恐れがあってこの世界第一の富栄な国に、ローマがカ ルタゴを襲い、アレキサンダー大帝がツロを手に入れたように、一獲千金を狙って奇襲をかけない のだろう。この問題を了解すれば、必らず十九世紀世界の真面目を了解できる。 今日、各国が何より欲するものは富であり、何より恐れるものも富である。今日の世界は富の世界 である。かの北米連邦は富により成り立つ国体であり、世界第一の富を持つ国である。世界の大盗 賊もこの国の富を奪うことは出来ない。もし苛酷な批評家の眼で観察するなら、この北米連邦とて決 して敬服することばかりではあるまい。しかしこの国の持つ国家・制度・文物の美に対しては敬服せ 49 ざるをえない。平民主義の政治は一隅の発達にとどまらず、平民的活気が全社会に充満している。 国家の大経綸ばかりか、日常生活上注意をひかないほどの些細なことでも、解剖すればすべて平 民的分子により組織されているのだ。要するに一国を挙げて徹頭徹尾、平民的分子の結晶体とも いえる一大現象に対しては、ただ賛美するほかない。トクビル氏はいう。「アメリカ人が身を挺し危険 を踏み商業に従事するのを見ると、フランス人の軍陣における行動のようだ。フランス人は征略のた めにこれを用い、アメリカ人は廉価のためにこれを用いる。アメリカ人の活溌な気象は、世界におい てもっとも廉価、かつもつとも快速な貿易者とした。」 「今やアメリカ人が掲げる華々しい旗は、世界 の至るところの人々に尊敬される力を持っている。思うに数年足らずの間に、恐怖を感じるほどの巨 大さになるにちがいない。この国民が商業に発揮する熱心さと、商業にとって有利な自然の便益 (良い港湾に富むなど)および今日までに成就した功績について考えると、早晩この国が地球上第 一の海上の覇権者となることは間違いない。かのローマ人が世界を征服するために生まれ出たよう に、この国民は海上を支配するために生まれ出たのだ。」 その昔ローマ人は鉄を振るって金をつかんだ。しかし今やアメリカ人は金をつかんで鉄を振るって いる。これは二国の相違にとどまらず、二国によって代表される時代の相違である。上古の時勢は 腕力が富を制する時勢であった。近世の時勢は富が腕力を制する時勢となった。富は単に腕力を ばかりか、腕力の子孫である涙、血、怨恨、闘争、嫉妬をも制する。強が弱を圧し、暴が正に勝つ 状況、その他疾病・飢饉・放火・盗賊などを一掃する希望は、我々の眼前に横たわっているのだ。 イギリスの自由貿易の大先達であるコブデン氏の説を聞いてみよう。 「かの生活上の利益は、自由貿易主義が全勝したことによって人類が得たものの一部分に過ぎ ない。試みに遠大の眼を開けば、重力の法則が宇宙を支配するように、自由貿易主義は道義の世 界において、人類を一か所に吸引し、種族・宗教・国語などの反目敵視を脱却し、人類を無極の平 和の靭帯により一致させる。 さらに一層の遠大の眼を開けば、私は次のように推測し、夢想する。はるかな将来、すなわち千 年余りの後に、この主義の全勝の結果は何を実現しているだろうか。私は、世界の表面は一変して おり、今日流行するものとはまったく趣を異にする政府の組織が採用されていると信ずる。私はか 50 の帝国が領土を拡張し、威力を拡げ、雄壮な陸軍を設け、偉大な海軍を備え、人の生命を斬殺し、 勤労の報酬である財産を滅失するための武器を備える願欲と熱望とは、必ず雲散霧消すると信ず る。私はもし人類が一家族となり、たがいにその同胞とともに自由にその勤労の結果を貿易する日 が来れば、このような凶器は無用となり、さらにこれを用うる必要はなくなると信ずる。」 私はこの言葉が夢想ではないことを希望し、かつ信ずる。なぜなら今日の世界経済の現象はこの 言葉が空望ではないことを保証しているかららだ。近世の歴史は兵と富との戦争史だった。しかし 十九世紀の時代は富が兵に向かって大勝利を得、かつ得ようとしている時代である。ヨーロッパの 将来の歴史には、必ずかの帝王宰相らが慌てふためく一大革命が起こるだろう。そしてその革命は、 商業主義が腕力主義に向かって抗抵を試み、連戦連勝してついに最後の目的を達する一大革命 であろう。ああわが同胞人民よ。記憶せよ。わが国の四隣の状況はこのような有様なのだ。 第八回 平民主義の運動 一(第二 社会自然の大勢より論ず) 天地は万物の宿、光陰は百代の旅客である。そしてこの光陰の大潮流とともに世界の表面に現 われる人事の現象は、おのずから運動し変転していく。その変動はおのずから社会自然の大勢の ために支配されるのである。 たとえば上古の光彩にあふれ、世界の舞台を賑わせた貴族の現象は今どこにあるか。その大半 はすでに没落し、視聴の世界を去り、すでに記憶の世界に入ったではないか。そしてわずかに生 存するものも、やつれ果て、すでに片足を墓中に投じているではないか。これに反し平民的な現象 は、あたかも一夜のうちに富士の高山が地面より突出したように、十九世紀の世界に高くそびえて いる。貴族的な現象はすでに去り、平民的な現象が今来来ようとしている。これは歴史上の一大事 実だ。すでに事実となっている以上、必ずその理由があるのだ。 そもそも社会を組織する分子は、多種多様であるから、その運動も決して単純な法則のみで支配 されているのではない。したがって私は生産、武備の二機関の消長盛衰をあえて唯一の原因とは しないが、もしこれらの現象がどのような過程で生長して来たかと問われれば、私は猶予なく次のよ 51 うに答える。 かの貴族的な現象は武備機関の進歩した過程で生じたもので、平民的な現象は生産機関が隆 盛となる過程で生じた、と。上古の歴史に貴族的現象があったのは決して不思議ではない。なぜな らそのような条件がそなわっていたから。近世の歴史に平民的現象が起ったのは決して不思議で はない。なぜならそのような条件がそなわっていたから。 自由の意志を持つ動物はすべて、必要の前には必ずその首を垂れなければならない。上古にお いて武備機関を設けざるをえない必要は、他の一種の異様異彩な貴族的現象を生まざるをえない 必要があったのだ。では何の必要があって上古には武備機関を設けざるをえなかったのか。人間 社会が進歩する必要があったためである。優勝劣敗の妙理を活用して、優等の人種と優等の組織 により、社会を支配する必要があったからである。 世界文明の微光は兵の運動とともに始まり、武備の機関が進歩するに従い社会はいよいよその 歩を進めた。両者は常に並行し、轡(くつわ)を並べ、袂(たもと)を連ねて運動してきた。私は断言 する。文明は実に武力の胎内より生まれたものである、と。文明世界の人類を文明の民らしくしよう と思えば、自由が必要なように、野蛮世界の民を文明の民に進めようと思えば、抑圧というものが必 要である。野蛮世界の民を意のままに放任すれば文明の運動は断念するほかない。目的は一つ だが、手段はこのように異ならざるを得ない。それは人民の位置に差がある以上はやむをえないの だ。 偉大な帝国はどのように完成したか。器械技術はどうして発明できたか。屈強な体格を有する人 民はどうして社会を支配することができたか。どのようにして緻密な法律を作ったか。複雑な政治社 会の機関はどのように発達してきたか。人類の社会が蜂の巣より高等なものになったのは、みな腕 力運動の結果である。今日のいわゆる文明世界に向かって、未開野蛮の人民が一歩を踏み出した 要因は何か。それは他でもない。ニムロデや、秦の始皇帝、ロムルス、メネス、ライカルガスのような 人々が社会に出たからこそだ。もしこれらの人がいなかったら、今日の社会は依然として太古の社 会のままであり、人民はただタタールの原野に野獣を追い、アラビアの砂漠にラクダを駆る人民で あろう。これらの暴君ないし圧制者は、社会進化の大恩人といわざるをえない。上古の世界におい 52 てつとに自治の制度を適用し、平民的現象により社会を支配した国体はないことはなかった。たと えばカルタゴやアテネ、あるいは地中海の沿岸に輝いたツロ、ギリシアの諸植民地などは、自由の 光輝を上古の社会に放った。しかし小魚は大魚の餌となり、小敵は大敵の捕虜となり、ついに近傍 の腕力国の腹を肥やす食物となったのだ。この理由は何か。時機を得ず、境遇に適応できず、社 会全体の進歩と調和を得られなかったからだ。上古の歴史に平民社会を見れば、あたかも万緑草 中紅一点を望むように、愉快とも珍奇とも思われるが、とうてい可憐な悲しい歴史に過ぎない。ロー マがカルタゴを滅ぼしたはスキピオの功業ではないのだ。カルタゴが滅びたのはハンニバルの罪で もない。アテネがスパルタのために屈辱をなめたのもペロポネソスの一戦に帰することはできない。 彼らが滅びた理由は平民的な社会であったからだ。あるいは平民的社会の罪というよりその時節に 不適合な社会だったからだ。その時代に威力をたくましくしたのは貴族的社会であったからだ。ある いは貴族的社会の功徳というより、その時節に適応した貴族的社会であったからだ。武備の世界に は貴族的社会が最もよく妥当する。生産の世界では平民的社会が最もよく力を発揮できる。これは 自然の理である。 しかし光陰の潮流は奔走していく。武備の機関は社会の進化とともに役割を果たし、社会が変化 を遂げるときには武備の機関も一歩を転じないわけにはいかない。白雪が天地に満ち、一面銀世 界の日には、春風百花を仰ぐ好時節を夢想するのは難しいが、地球が回り軌道を走れば、いずれ この時節はやってくる。そのようにわが世界の歴史も、日月の潮流とともについにこの意外な境遇に 会う運命となった。今や中古の武備の時代から一変して生産の時代となり、貴族の社会は一変して 平民の社会となろうとする一大過渡期に来ている。そして近世の歴史はすでに半ばその目的を成 就しているのだ。生産の機関が武備の機関の中心から出たように、近世の平民的現象は多くは中 古の貴族的現象の中から生まれた。武備機関の衰亡と貴族社会の凋落、生産機関の興隆と平民 社会の勃起とは、つねに一連の運動をしており、その中には言葉で表現できない妙理が存在する。 これは社会の大勢に通じた人にはよく感じ取ることが出来よう。イギリスほど平民主義が秩序よく進 歩した国はない。実にイギリスの社会変遷の実例は、ヨーロッパ社会一般の模範である。イギリスは なぜこんなにすみやかに封建のしがらみを脱し、こんなに早く帝王と宗教の専制を脱し、妄想迷信 53 の世界から脱したか。また、いかにしてその政治の自由を得、いかにしてその社交の自由を得、い かにしてその思想・議論・良心の自由を得たのか。古今の学者の答は複雑で長いものであろうが、 ただ一つの要因を挙げてくれといえば、どの学者も口を揃えて、富の蓄積と言うだろう。商業の進歩 と、平民主義の進歩とは、決して別ものではない。時には例外の現象もあろうが、密接に動いていく。 そうでなければ二者の存在は決して確としたものではなかっただろう。これを疑うならイギリス憲法史 を一読すればよい。 ああ造物主の用意は周到懇切である。彼は抑圧された人生に幸福を与えるときは、必ず事前に 抑圧を与えた。主みずから与えたのではない。社会の境遇が当時の人類に抑圧を忍受する必然 性を与えたのだ。人類が自由を必要とするときには、造物主はまた自由を与えた。主は直接与えた のではなく、人類の境遇を一変して、抑圧を忍受しない社会状況を与えたのだ。上古の社会で武 備機関が増長したのは、近世の社会で生産機関を増長するためであった。上古の社会に貴族的 社会が流行したのは、近世の社会を平民的社会とするためであった。我らの先祖が抑圧をこうむっ たのは、我らが抑圧をこうむらないためであった。いいかえれば我らに自由を与えるためであった。 自由の世界つまり平民的社会は、ルソーが夢想したような質朴野蛮の社会では決して行なわれ ない。人類の性質が従順、穏和、結合、協力の道を知り、自愛と他愛の関係を知り、社会の威力を 体得し、その社会が恒久に耐える身体であることが必要である。深い知力と将来を見通す知識をも っていなければならない。感情面で主我的利己的な運動を制限する種々の法制や習慣法が支配 していなければならない。このように進歩した社会となって、初めて人為の結合が止んで自然の結 合が生じ、人為の必要が止んで天然の必要が生じ、強迫専制的運動が止んで自由な運動ができ る。林園に野鳥を馴らして飼おうとすれば、まずは籠に収めなければならない。籠は決して野鳥の 目的の地ではないが、林園のうちに高飛朗吟しようとすれば、必ずまずはこの窮屈な籠の中の苦を 忍受しなければならない。そうしなければ決して馴れた親しめる鳥にはならない。世界は造物主の 林園である。人類はその中の野鳥である。この鳥が幽谷を出て林園を愉快に飛ぼうと思えば、まず 貴族社会の籠の中に入る必要があったのだ。上古の貴族的社会は人類を教育して自由の天性を 全うする一つの学校であったことは、人類が幾千年を経過した今日、その過去の足跡を回顧するこ 54 とによって、ようやくその深意を理解できたのだ。火中に蓮花を咲かせ、茨の棘のうちから葡萄を収 穫し、不自由の中から自由を生ずる不思議な手段は、驚嘆せざるをえない。人間の狭少な心で考 えれば、この不自由な学校に在る日月があまりに長かったと疑う者があるかもしれないが、時を無と し、宇宙を家とする上帝の眼光より見れば、一秒の時間にも価しないだろう。造化が一歩を転ずる のに、人生幾千年を経過するかを知らない。ああ宇宙は大きく広い。 第九回 平民主義の運動 二(同上) 平民主義の運動は政治世界にもっとも著明に表われる。狂乱怒涛が海に押し寄せるように、平民 主義が政治世界に侵入し、貴族の堤防は一時に壊滅の様相を示した。アメリカの独立戦争、フラン ス革命、ギリシアやイタリアの独立、イギリスの憲法改正と非穀物条例運動などは、十目の目はすべ て一致するだろう。一八六五年、ブライト氏はバーミンガムで議院改正案に関しつぎのような演説を した。 「国家の危禍として警戒しなければならないのは平民主義ではなく、むしろ平民の正常な請求と 権利に敵対する執政者・執権者である。その名称は彼みずから王党と称し、民権党ともいうが、そ の正体は保守である。この党派こそ実に我々が戦わなければならない真の国家の大危禍である。 彼らは河流を防ぐだろう。奔水を逆流させようとするだろう。しかしいったん水勢が激昂氾濫すれば、 しかも氾濫が眼前に迫っている今、よほどこの愚劣な政略を聡明な政略に代えなければ、たちまち 堤防は決壊する。揚々として平民主義を鎮圧したと安心すれば、たちまち一致団結した人民の猛 志がこれを一掃するだろう。どうか眼を挙げてヨーロッパの表面を見てほしい。まだ代議制度を採用 しない国はただ二国、ロシア、トルコの二国あるのみ。ロシアは他のヨーロッパ諸国とともに静かに 自由の域に進んでいる。そして代議政体はイタリア、オーストリア、またあるいはほとんどゲルマン諸 連邦において、また北方の諸国、ベルギー、オランダ、フランス、ポルトガル、スペインに発見できる ではないか。 平民主義は今日の政治世界の一大勢力である。我々は平民主義がどこから来て、どこに行くかを 55 知らない。しかしその威力、気力が高揚し、ほとんど天地に満ちる勢いであることは、つねに目撃し 驚嘆するところだ。その気運は、貧賤な農夫・雇人・職人に権利を持たせる嘆願書となり、柔美な婦 女に参政権を与えることを迫る公訴状となり、鬼神を泣かせるほどの檄文となり、飛天より来た雄壮 な演説となる。このため俄然として一つの大平民国が興り、したがって忽然として一つの大貴族国 が滅ぶ。一個の市民がたちまち世界万国の尊敬を受ける大統領となり、朕はすなわち国家なりと誇 言した大皇帝の子孫も他国にのがれて天涯の孤客となる。しかしあまりに激高すると、天狗が地に 落ちて雷のような声を出す虚無党の爆裂弾となる。これを等閑に付すと、火星をも飛ばす社会党の 猛烈手段となり、その行方は混沌として人を惑わす。なぜこんな状況を招くのか。それは、彼ら平民 主義者が生産上すでに得たものを、さらに政治上に拡大したいからである。商業においては、購買 者と販売者、つまり権利者と義務者があるだけだ。ゆえに彼らはこれを政治上に及ぼし、政治上の 関係をもただ権利義務の関係により支配したいと欲するのだ。生産の場で彼らを使役し、運動させ るものは、自然の生理である。ゆえに彼らは政治においても自然の生理が命令者であることを望む のだ。生活上の最大権威者は正義である。ゆえに政治上の最大権威者もただ正義であることを願 うのだ。要するに生産上において彼らは自由、平等、自然である。ゆえに政治上においても自由、 平等、自然であることを欲する。人は利害がもっとも切な点にもっとも痛痒(つうよう)を感ずる。生活 上の利害は直接の利害だ。人類はまず生活上において安心立命の地位を得た。政治上の利害は 間接的であった。しかし直接の利害において自己を確立できれば、次にもっとも心を悩ますものは 必ず間接の利害である。直接の利害ある間は間接の利害であったが、その先は間接の利害も一変 して直接の利害となる。青は藍より出て藍よりも青い。平民主義は生産機関の中から生まれ、その 勢力は拡大の一途である。今日、政治の上で平民主義が流行するのも当然であろう。今日の社会 を維持するのは平民主義以外にない。今日の平民主義は社会の元気の素である。貴族社会が武 備主義よって立たざるをえなかったように、生産世界は平民主義によって立たざるをえないのだ。こ こに一つの必要というものがある。必要の向かうところ天下に敵はない。今日天下に平民主義の敵 がないのも当然であろう。世の平民主義の敵対者は、モンテスキューやルソーたちの鼓舞扇動によ るものだと恨めしく不平を訴えるが、そうであろうか。この二氏は議論に少々傷があるにしても、世の 56 知者を超えて新しい考えを示した。その豪胆さと卓識はまことに不世出の人物である。二人の思想 が人民の実利実益と相反するか、もしくは無関係であれば、二人の一声が天地をつんざく大革命 を生みはしなかった。人民は政治上においてこそ平民主義の中身を理解しなかったが、生活上に おいてはすでに実行していた。二氏は空中の楼閣を示して人民を教唆したのではない。人民は実 際上の事実を観察し、帰納し、演繹(えんえき)して、一片の議論を作ったのみである。釈迦はもとよ り慈善家であるが、釈迦の前に人類の慈善を行なうものは幾千人もいた。この二氏はもとより平民 的な政論家だが、二氏が説法する以前に大勢の人民が事実上平民主義を実行していたのである。 国家は人民が組織した一大有機体である。したがって平民主義の分子は国家とともに国家のうち に生まれたのは疑いない。しかしそれがまだ十分に発達しないのはなぜか。その時節がまだ到来し ないからだ。その条件がまだ整わないからだ。しかし今やすでにその機会を得た。二氏がいなくて も状況は調ってきたが、二氏のような案内者があれば進展は余計早くなる。 今日のヨーロッパ各国の平民主義運動は、かつて東洋の偽英雄が変幻自在に大風呂敷を広げ て、万一の成功を目論んだような博奕的な閑事業ではない。人民の利害存亡に大関係を有するも のだ。ヨーロッパの世界は平民の世界である。ゆえに租を食らい、税を飲み、他人の血を絞って自 家の口腹肉欲を満足するような生活をするものではない。それならなんの暇があって自分に関係の ない政治の世界に無用の心配をするか。文明の世界は多忙の世界だ。閑をつぶすのに苦しんで いるのだろうか。そうではない。平民主義者が憤発激昂、みずから進んでやまない理由は、頭上に 禍福安危の応報が落ちる恐れがあるからだ。ゆえにヨーロッパの平民主義は二、三人の学者が尽 力してたまたま得た産物ではない。ヴィクトル・ユーゴー氏は言った。『今や、フランスが経過しなけ ればならない危機の最中に、率直に問う者がある。誰がこのような危機を作り出したか、我々は誰を 罰したらよいか』というのだ。ヨーロッパの狼狽者はフランスに原因があるという。フランスの狼狽者は パリに原因があるという。パリの狼狽者は出版の自由が原因だという。しかし活眼精識の人は、罪は 出版の自由になく、パリにもフランスにもなく、深く人間頭脳のうちにあると答える。」 私もまた次のように言いたい。もし今日の平民主義の罪人を問うなら、それは民の実利実益にあ る。つまり人民自身にあると。上古に平民主義の政治がおこなわれなかったのは、ただ国家があっ 57 て人民がなかったからだ。今日平民主義が流行する理由は、まず人民があって、国家は人民のた めに設けられたからである。しかし平民主義は今日世界に十分行き渡り、完全に実行されていると はいえない。その理由にはいろいろな説がある。 原因と結果の法則が宇宙の万物を支配する間は、人間といえども、社会といえども、決して部分 的にせよ過去の抑圧を免れることはできない。過去のヨーロッパ世界は貴族的な世界であった。し たがって今日たとえいかにその抑圧を逃れようとしても、幾分かはこれを受忍せざるをえない。現在 の社会が産れる前にすでに指定された一つの命運であった。スペンサー氏が冷静に指摘したよう に、学校教育で一週の六日間はアキレス(トロイ戦争の勇将)を英雄として崇拝し、七日目(日曜日) にはキリストを親愛せよと教え、公館で行われる饗応では今なお国会のために祝杯を傾けず、かえ ってまず陸海軍の人のために祝杯を傾けるような習慣はなぜ生じたか。傲慢で片寄った不健全な 愛国心はなぜ生じたか。門閥を尊び、旧慣を重んずる風習はどのように生じたか。人間の関係は権 利義務ではなく、主人と奴隷だという妄想はどうして生まれたか。官吏を鬼神のように尊び、武勲の ほかには勲業などないとの迷妄はどうして生じたか。なにゆえに政府を万能かつ無尽蔵の権威者と 信じ、国家の威力は天体の運動さえ止めるほどの効用があると信じ、常備軍は国家に欠くことがで きないものと信じ、外国とは政治上の交渉をせざるをえないと信じ、権利は腕力によらなければ伸 張できないと信ずるのだろう。なぜ今日の世界をもっとも悩ます一国の記憶、つまり隣国への復讐 の念が生じたか。見よ。なぜプロシアとフランスの二国はつねに宣戦中の休戦のような有様なのか。 過去の遺恨があるからだ。なぜアイルランドとイギリスの関係は今日に至るまで鎮圧令を布いている か。強迫による結合が過去に行なわれて、まだその跡を絶てないからだ。人民は決して今日の帝 王宰相らの政略に感心服従しない。色を正し、言を高くして彼らを非難し、排斥する者は数多い。 しかしなおその雲霧は青天を望むのを妨げている。この世界をまだ快活な世界としていないのは、 過去の抑圧が残っているからだ。過去というものは最大の圧制者なのだ。だから今日のヨーロッパ では過去のヨーロッパと現今のヨーロッパがつねに争い、新旧二分子が不調和のまま格闘している。 例えばイギリスの政党間の争いは、原因が多々あるにしても、重な原因は過去の分子と現今の分 子、武備機関の境遇に生じた貴族的現象と生産機関の境遇に生じた平民的現象との間の戦争と 58 いわざるをえない。一方は与えまいとし、他方は取ろうとする。争いが生じないわけがない。十九世 紀のイギリス政治の実態は実にこの二分子間の争いである。あの奇男子ビーコンスフィールド侯が 神出鬼没の政略を採り、ヨーロッパ政治の大舞台で驚き怪しむような言動を演ずるのはこの旧分子 の力である。あのコブデン、ブライトの二氏が、古今の政治演劇中にいまだかつて見ない、あのシェ イクスピアの怜悧な脳中にも浮かばなかった新趣向・新脚色の技を演じたのはこの新分子の力であ る。反対者たちはこの二氏を、民政の胎内から出て来た近世のグラッカス(ローマの民権家ティベリ ウス、ガイウスの兄弟)と呼んだ。グラッドストン氏は一世の豪傑ではあったが、エジプトとの葛藤、ス ーダンの遠征など思いを遂げられなかったのは過去の抑圧があったからである。彼の政敵のビー コンスフィールド侯が種を撒いた禍機を氏は受け継いで解決した。しかし保守党が今日でも若干の 勢力をイギリス政界の一隅に保っているのは、旧分子の力であり、これを扶植したビーコンスフィー ルド侯の力である。ソールズベリがよく罵る、チャーチルの危険な傾向は弱敵ではないが、グラッド ストン氏の眼中より見れば子ども扱いである。妨げになる連中ではない。しかしグラッドストン氏はコ ブデン、ブライト諸氏が主張する純粋潔白な平民的政治家では断然ない。かえって氏が月夜に一 鶏を盗むような姑息な手段を取らざるを得なかった理由は何か。墓の中に大敵があるためだ。あの ウェストミンスターの憂鬱な墓の中に沈黙している一個の死人は、かえって議院内に立ち腕をねじ って弁ずる多くの生きた人間よりも氏の進路を妨害している。私は『三国志』を読み、死んだ孔明が 生きている仲達を走らす一節に至り、ひそかにその奇談に驚いた。だが今図らずも眼前に同じこと を見るとは。 第十回 平民主義の運動 三(同上) とはいっても過去はすでに過去である。長続きはしないだろう。今日、武備の機関と貴族的現象 はすでに宇宙に出生した目的を達した。彼らの事業はすでに成就した。彼らの功績はすでに結果 を得た。彼らはわが社会と人民とをこの位置とこの時節に伴って来たのだ。もはやこの世は彼らを 必要としない。人は問うかもしれない。そうであれば彼らはどうして潔く最後を遂げないのかと。造化 59 はなぜこんな無用の長物を空間の世界に漂わせているのか。種々の説がある。遠くを旅する客が 烈風肌を裂き積雪脛を没する山中を過ぎるときには、必ず綿衣を重ねなければならない。このとき このところでは、綿衣ほど必要なものはない。しかし春色爛漫な平原広野に出たときは、これほど不 必要な厄介者はない。そうであればなぜ綿衣を脱がないのか。人心が習慣を纏(まと)うのは綿衣 で身を纏うよりもはなはだしい。これを知れば過去の抑圧の激しさもまた知らねばならない。しかしど んな過去の抑圧であっても、人類の自愛心の敵にはなれない。人に自愛心があるのは物に重力が あるのと同じだ。物体はつねに降下するものだが、軽快なガスの作用を借りる軽気球は空中を飛揚 することもある。しかしこれは例外であって、軽気球といえどもその作用が終わればたちまち重力の 権威のもとに降服せざるをえない。また人為の仮設の作用のために自愛心の活動が制減されること もあろうが、これまた例外であって、いかなる威武、いかなる尊厳、いかなる富貴、いかなる誘惑・迷 妄・偏僻・陋習であっても、自愛心の矛先には抵抗出来ない。自愛心の向かうところ天下に敵はな い。黒雲が日光を覆うとも太陽は依然として雲間に存在する。いつかは完全な姿を現わす。私はこ れを信ずる。十九世紀社会の大烈風は、上古に垂天の雲のように重く垂れさがった貴族的な大木 を抜き去った。すでに抜き去ったのだ。たとい暫くは緑の色を変えないかもしれないが、すでに死ん だ材木だ。生きた樹木ではない。そうなのだ。それが長続きするはずはないのだ。ミル氏は言う。 「わがイギリスがすでに制度を変革した理由、もしくはまさに大変革をしようとする理由は、哲学者の 力によるものではない。近時、勃然として勢力を増長した社会の多数人民の利益と願望の力がある からだ」と。平民主義の勢力が強くなるのは、人民の利益・願望が鼓動者となるからである。貴族主 義の衰微するのは人民の利益・願欲が反対者となるからである。現在のイギリスの貴族的な外交政 略、権謀術策の政略は、マンチェスター派のコブデン、ブライト諸氏が攻撃するばかりではない。始 めに諸氏が唱えた白雪陽春の格調は、高遠すぎて賛同する人は少なかったが、その主義は人民 の実利実情に沿うもの、いや、実利実情に基づいたものだったから、賛同者は激増している。 〔註〕スペンサー、ベインらの哲学家を始めジヨン・モーリー、フレデリック・ハリソンその他有名な議 員紳士らが非侵略同盟を結成し、去る十五年二月二十二日ロンドンのウェストミンスター・パレス・ホ テルで発会式を行なった。会の目的は、従来のイギリスがややもすれば武威を外国に振い、侵略 60 主義に訴えることを憂い、その弊を改めて四海みな兄弟の交わりをしようという趣旨である。その手 段として一はイギリスの政略に注目する。二に外交政略には議院の主導権を拡大する。三に外国 人に対して圧抑的手段を施した外交家を免職する。四にイギリス国民保護には兵力を用うるも可な りとの主義に一定の制限を課す。五に外人と接するには正道を旨とし、蛮民といえども暴力的所為 を禁止する。六に戦争はなるべく和談仲裁し、または万国公法の改良により防止する。七に人民の 繁栄は、文明諸国との平和、野蛮諸国との無紛争によることを社会公衆に示す。 これはイギリスだけにとどまらず、ヨーロッパ諸国にすべて妥当する。その実例の一つとして、一八 八四年(明治十七年)に開かれた万国仲裁講和協会第四会議の記事を次に掲載する。 「万国仲裁講和協会はスイスのベルンにおいて、該大学校五十年祭の当日すなわち八月四日、 かねて約定したとおり国会議場で総会を開いた。会長のスイス連邦参議院議官ルーコンネットは開 会の祝詞の中で『戦争は人世中もっとも恐ろしい害悪だ。葡萄樹を犯すバフイロツキセラ虫、人間 を襲うコレラ病よりも激しい害悪を社会にもたらす。戦争は必ずしも紛争を解決する手段ではない。 なぜなら戦争が終わっても紛争が依然として解けないこともあるからだ。列国の紛争を調和するに は仲裁の手段が最も適切である。仲裁によれば、一国の兵備は単に国内の平和を維持し、外に向 かってその国の独立を確保する程度にとどめることができる」と述べた。ルーコンネットはまた『我ら がこの協会を結成したのは、有名なブルンチュリーの遺志を継いだもので、博士の功労を追謝せ ずにはいられない』といった。イギリスの委員長ワトソン・ブラットは、会の趣旨をますます拡げるため 会員を増加を望んだ。フランスの委員はフランス憲法改正案の討議のため代議士として国会に出 席するので本会には欠席した。この協会の発展のためには、各国の都市に支部を設け、百方力を 尽くしてますます世論を喚起し、各国の国会および政府にその影響を与えなければならない。この 事業は実に重大かつ至難である。なぜならこの事業は数千年の慣習を破り、軍務に従事する人々 の利益を損うからである。しかし、だからといって志を曲げるわけにはいかない。ただ懸命に努力す れば、正は邪に勝つの理にたがうことなく、ついにその目的は達する時があろう。イギリスの委員は 一八八二年のブラッセル会議以来一回も欠席せず、列国間に紛争が起こりかねない時も、その機 を失わなかった。つねに書面をもってこれを調停しようと務めた。現にスエズ運河とエジプトの事件 61 では、イギリス委員はフランス委員と目下協議中である。またイギリス委員は諸国に向かいその主義 を宣布した。そして職工などからおびただしい賛成者を得た。この日ビュルテンブルグ枢密議官の ドイツ国会代議士フォン・ビューレルは『全ドイツ国民は均しく平和を好む。しかし今兵備を減少でき ないのは、各国の国民がドイツ国民に反する挙動を往々にして取るからだ。私はドイツ国会に兵力 削減の建議を提出した。初めは一人の同意者もなかったが、その後四十名の議員の賛成者を得 た。』と述べた。万国平和の主義により仲裁講和協会に賛同し、近時新たに入会した人々は次のと おりである。 ルイス・アップルトン(イギリス委員の書記) フヒフセル婦人(ロンドン) (この婦人は、今日各国が競って兵備を盛んにするのは婦女たちの罪だ。なぜなら万国の婦 女が一致協力して抵抗すれば必ず戦争の源を絶つことが出来、自然に兵備は不要となる、と いう。) ベーロー・エスローオ(パリ府) 元老院議官アルフヒーリー・ドソステグノー(ローマ) ステルン(ブカレスト) ル・モンニエー(パリ) カール・フォン・ベルゲン(ストックホルム) バイエルン(コペンハーゲン) リュ・ウェンタール(ベルリン) ミヘーリス(フライブルグ) もしヨーロッパ政治の前途はどうかと問われれば、我々はただちに大西洋の向う岸にある一大平 民国を指して答える。『ただこの国のようになることだ』と。実に北米合衆国は平民主義運動の先導 者であり、この国の人民は造物主の選民である。世界の人民に向かって将来の命運を定める目標 となっている。梅の花が雪中に開くのは一陽来復を報せるためではないか。今日の世界にこのよう な社会が生まれたのは、将来の政治の変動を予知し、準備をうながしているのだ。遅速こそあれ、 62 十九世紀の大勢力に敵対して揚々と勢力を拡大するするゲルマンやロシアではあるが、一度はか のポンペイの都府がヴェスビアス山の大噴火のため一夜のうちに地中に埋没したように、今日の現 象が意外にも地球上の表面より消え去る一大奇事が将来の歴史に残るかもしれない。これを我わ れは今日より断言する。我々はこの二国の皇帝宰相らが、この危険に対処する準備を今からはじめ るよう祈る。 このように平民主義の運動は政治の世界を一変するにとどまらず、宗教上、経済上、文学上、学 芸上、技術上、あるいは人類の社交上にも、その感情、思想、議論の上にも、その他人事の現象の あらゆる場面に及ぶ。あたかも地球の表面に空気の充満しないところがないように、至るところ、触 れるところ、化合し結晶していく。これを縦割りし横断しても、その経線といい、その緯線といい、み な平民的現象でないものはない。ただ政治においては、著明ではあるが一斑の印があるのみだ。 なぜ政治の世界では平民主義が遅れを取っているのか。私はこの理由を詳しく解説しようと思うが、 残念ながら紙面に余裕がない。 英国急進党の名士モーリー氏はいう。「近世の社会は平民的にせよ、貴族的にせよ、社交・宗 教・政治上の大変革の道を進まざるをえない。このことは実に苦患であり、危険であるが、しかし今 日の大勢である。政府を分離し、これを一種特別の物とみなして、今日の雄大深遠な平民主義勢 力の感化を受けないとすることはできない。西欧の文明は着実にこの道を進んで、新舞台に出て来 たのだ。政府の体裁のようなものはその一小部分に過ぎない。」と。 私はこの人の活眼に敬服する。私はこの言が適切なことに感心する。ヨーロッパの大勢は全くこの 通りなのだ。 要するに人類が記憶しない千万年の過去はだれも知らない。人類の想像のとどかない千万年の 未来もまた、誰も知らない。しかし人間の理解と想像力との域内にある一幅の人類旅行の図を見つ めると、人類は正々堂々と一定の目的に向かって、一定の順序を踏みながら進んでいる。あたかも 精鋭なフランスの常備兵がナポレオンの号令に従い行軍するように、朝セーヌの河を渡り、夕には アルプスの雪嶺を超え、鉄馬風に嘶(いなな)き、雄剣氷に没する地を踏み、今すでにトスカナの原 野に達し、緑樹の林、和鳴の鳥、柳暗花明の村落に達しているのだ。かつてアルプスの雪嶺をよじ 63 登ったのは、今トスカナの沃野に達するためだった。武備世界に入ったのは生産世界の世界に達 するためだった。貴族的現象が社会に生じたのは平民的現象が社会に生ずるためだった。人類が 不自由の世界に囚人となったのは、人類が自由の郷里に到達するためだった。そして今や人類の 旅行は、この郷里に達する寸前にある。いわゆる時節到来の日だ。人類の歩調がいっそう快活に なっているのは、論をまたない。人力では天体の運動を遮(さえぎ)ることが出来ないように、誰も人 類の運動を遮ることはできないのだ。四時の循環を人為の力で支配することが出来ないように、人 類の運命の循環を人為の力で支配することもまた出来ない。人類はロビンソン・クルーソーのように 絶海の孤島に偶然漂泊したものではない。必ずその目的があるのだ。幾千年前チグリス、ユーフラ テスの河畔に簡易な社会を造ったとき以来、今日の境遇に入り、今日の社会に至る一つの運命を、 あらかじめ造物主より指示されていたのである。造物主は、人類の先祖が征途に上り一歩を進めた ときには、その子孫である十九世紀の人類が必ずここに達するよう予定されていたのだ。そして人 類は、すべての川が海に流れ込むように、運命のときを迎えている。今や平民主義の運動は火のよ うに、雷のように地球の表面を快走し、生産力と富の必要は人民を駆り、社会を駆り、いかなる人類 をもいかなる国体をもことごとく平民的な世界に押し出そうとしている。これが十九世紀の大勢であり、 この勢いに従うものは栄え、勢いに逆らうものは滅ぶ。 第十一回 天然の商業国(第三 わが国特有の条件より論ずる) 全体の条件は必ず一部の条件を支配する。全面の環境は必ず一局の環境を支配する。したがっ て日本特有の条件と環境は、世界一般の条件と環境によって支配されるのも当然である。 読者はすでに記憶されているだろうが、今日の世界の環境は富の環境であり、今日の世界の条 件は平民主義が大勢である。我々はこの事実から、わが日本の将来は商業国となり、また商業国と ならなければならないと断言できる。とはいえゲルマンやロシアのように、その国に固有な一種特別 の事情があるため、容易に全体の大勢に従い、全体の環境に入り、全体と共同一致の運動が出来 ない場合もある。日本にもはたして特別の事情があるかどうか。この点はわが国の置かれた状況を 64 観察するのに先だち、思考を要する点である。 今日の世界の大勢に抗し、武備により一国の生活を維持する国は、必ず過去のやむをえない事 情があるからだ。その事情のもっとも主なものは、 〔第一〕内部の結合が薄弱であり、強いて威力を借りなければならない事情である。内部の結合が 弱く、ややもすれば分裂の傾向を生ずる原因はいくつかある。人種を異にしその性情行動がおの ずから氷炭相容れない場合。腕力により征服されたにもかかわらず、かつて独立国であった記憶と 遺風が残り、恥を忍びながら心中に報復の念が去らない場合。征服者にとっても鉄火のもとに鎮圧 しなければ枕を高くして寝られない場合。宗教・言語・風俗が異なり、商業上の利益が反する場合。 あるいはその国の面積があまりに広いため政治家の随意の結合が困難で、ややもすれば分解の 恐れがある場合。またあるいは政府が国民の実情実利を代表することができず、不満の爆発を恐 れてやむをえず武力により国を維持しなければならない場合などである。たとえばオーストリアとハ ンガリーのケースは人種・国体の異なるため。トルコとセルビア・ルーマニア、英国とアイルランドの ケースは、人種・国体・風俗・言語・宗教が異なるためである。ロシアでは一つは領土があまりに広 大で、ことに人民と政府が互いに反目しているためである。アメリカの南北戦争は南北の利益が相 反したためである。ゲルマン連邦が今日強迫的な結合を取らざるをえないのは、兵略上の結合だ からだ。 〔第二〕外国社会からの刺激。過去に二国間で争い、いわゆる歴史的な記憶が残る場合は、我が 彼に報復すれば、彼も必ず我に報復するから、相互に睨(にら)み合い、武備機関を発達させる。 また強大かつ武備的の国と境界を接する場合は、つねに厳戒しなければならない。これを怠れば たちまち蛇に呑まれてしまう。ことに地理上、兵略上の要地である国はもっとも武備に注力しなけれ ばならない。なぜなら万邦、万人、みな涎(よだれ)を流し牙を磨いて呑みこむ機会を待っており、 少しでも乗ずる隙があればたちまち国を失ってしまうからである。こういう場合は万々やむをえず、 泣き泣き、たとえ一国の身代を使いつくしても武備の用意を果たさねばならない。 ドイツとフランスの関係は歴史的記憶があるためだ。ロシアとドイツの関係は犬牙接するためだ。 イタリアはローマ帝国没落以来群雄鹿を追い、千兵万馬が駆けまわり、欲望をたくましくしたからだ。 65 我が日本にはこうしたやむをえない事情があるだろうか。日本は唯一の国体、唯一の人種、唯一の 風俗、唯一の言語である。その結合は利益の結合であり、兵略上の結合ではないから利害が反す るものはない。宗教は今日に至るまでほとんど政治家の注意をひくほどの現象には進んでいない。 たとえ将来キリスト教の勢力が増大しても、このために一国の一致を、強固にすることがあっても散 漫にすることはなかろう。国土は二万四七九四方里にすぎないから、凡庸な政治家でも掌上に運 転することができる。 では外部の事情はどうか。四方八面大海の広がりを見るのみだ。三十年前まで鎖国の政略を採 っていたので、歴史的記憶として存在するものはない。国土が美であっても、イタリアのように単騎 長駆してただちに城下を奪われる心配はない。わが国を商業国とするのを妨げる事情はないのだ。 もし外部の事情がつねに我が国に向かって反対の運動を与えるにしても、武備的政略の障碍には なっても、商業上の発達を強く促す契機となるであろう。要するにわが国は自然の結合により自然 の国体が出来たものだから、国を治める方略とて別にないのだ。ただただ自然の傾向により、水の 下流に就くように治めればよい。 わが国はこのように自然の境遇に入り、自然の運動をするうえで一つの妨害物をも発見しないば かりか、さらに一歩を転じて考えると、非常に有利な条件があると判る。次にこれを説いてみよう。 〔第一〕気候。造物主は、日本人を配置するのにもっとも便宜な温帯の地を与えた。日本人民 は、氷山雪屋のうちに住むエスキモーのように鯨油を飲み、アザラシの肉を食べ、寒気と戦うために この世に生活するものではない。また、アラビア人のように一木一草も自由豊美な生長をしない熱 砂の中で、駝鳥の伴侶となり、駱駝の主人となり、沙漠より出て沙漠に入る生活をしなくてよい。また 草木禽獣の得意の世界ともいえるアマゾン河流地方のように、どんなに斧をふるっても森々とした 高草大木は人を圧して侵し、猛獣毒蛇が人に迫り来る地に生活する運命をも持ち合わせていない。 わが国の気候は寒温の適度を得、空気は乾湿まことに程よい。そのため人間の生活に必要かつ有 益な動植物は豊かに繁殖し、住民も遺憾なく天賦の能力を開発する便宜がある。 〔第二〕地味。モーゼはカナンの地を指して蜂蜜と牛乳の流れ溢れる国だと言った。しかしわが 国は生糸と茶の湧き出る土地である。日本の桑園と生糸の産出高は次のとおりである。 66 日本の輸出貿易品の首位を占める生糸の根元といえる桑園の面積は、十一万一七四町三反三 畝(明治十四年の調査)で、桑葉の収穫高は、二億四五八一万一六六九貫目である。一反歩につ き平均二二三貫目にあたる。養蚕は原紙一枚の養育に桑葉二百貫目を要するので、一二二万九 五〇八石の繭が取れ、九八万三二四六貫六八〇匁すなわち六一四万五二九二斤の生糸を製造 できる。一方全国の養蚕家の数は明治十五年の調査で七五万二五〇三戸であるから、一戸につ き桑園は一反四畝一九歩、桑葉は三二六貫八〇〇匁、製糸は八斤強の平均にあたるという。(十 九年四月八日『中外物価新報』) そして生糸の外国への輸出高は、 生糸 十五年 二、八八四、〇六八斤 一六、二三二、一五〇円 十六年 三、一二一、九七五斤 一六、一八二、五五〇円 蚕および絹類総計 十五年 一九、三七七、八〇〇円 十六年 一八、六七八、六一五円 (『第四統計年鑑』) これに続いてもっとも有益な産物は茶であり、その輸出高は、 茶 十五年 二三、五八九、〇九八斤 六、八五八、七六三円 十六年 二四、一四一、七三七斤 五、九七六、五九五円 茶類および胡椒合計 十五年 十六年 七、〇三三、三八〇円 六、一一一、九三九円 (『第四統計年鑑』) 茶畠の面積は、明治十四年の各府県の調査統計によると四万二〇二三町九反に達する。 要約すると、明治十六年の輸出の総計は二八九八万三九三二円で、うち二四七九万〇五五四 67 円は生糸・茶の諸類だから、取りも直さずこの二品はわが国輸出のほとんど六分の五を占める特有 の産物なのだ。全国の耕地は、国土面積の約十二パーセント四五〇万七四七四町四反四畝一六 歩を占めるので、かの桑と茶の耕地を合わせた一五万二一九八町二反三畝歩は、全耕地の三十 分の一を出ない。私は希望する。もし今日より、いかなる場合でも決して国民生活の必要を他国に 仰ぐべきではないという封建世界の固陋な悪習を去り、天地広大、四海兄弟、天の時に従い、地の 利に随い、分業の便益を世界を通じて適用する自由貿易主義に即し、わが国を挙げて養蚕の世 界、生糸の故郷に育てていきたい。日本の耕地は山腹水涯に至るまで、ことごとく桑園茶園に適す るので、わが国の繁栄は大いに期待できる。 ウールジー氏は「土地の肥痩(ひそう)は人民の職業を制約し、人民の職業はその国の政治を制 約する」という。そのとおりである。わが国の地味はわが国民を生産者とし、生産者の職業は国を平 民国にもっていくのである。 〔第三〕地勢。頼山陽は言った。「私はかつて国内を歴遊し、山河の起伏を見て考えた。地脈は 東北より来て、西に向って徐々に小さくなっていく。これを人身にたとえると、陸奥、出羽は首、甲斐、 信濃は背である。関東八州と東海諸国は胸腹、そして京畿は腰と臀(しり)。山陽南海より西は股と 脛(すね)である」と。この比喩が当を得ているかどうかは別にして、日本の地形はもっとも変化に富 む。東北より西南に向かって一匹のトンボのように延びている。山岳は秀で、河海は内外をめぐるか ら、風土もおのずから適度の変化を得、このため社会生産の発達を刺激する。地勢の変化は上古 のギリシアを文明の先鞭者とした。今日わが国の前途を疑うものはないだろう。さらにわが国民は一 つの記憶に注意しなければならない。それは日本が島国であることだ。ギルバート氏は『古代商業 史』につぎのように論じている。「島国が商業の便を得ているのは、たいていの場合大陸諸国よりは るかに大きい。なぜなら島というものは、その面積に比べ大陸諸国よりもはるかに長い海岸線を有し、 気候は温和で、四時の変化はるかに少ないのが通例だから、商業活動が気候のために阻害される うれいがない。また海は天然の城・砦(とりで)となるので、外敵の危難が少ない。したがって兵籍に 編入する人口の割合は少なくて済む。また他国との通商は必ず海によって行なわざるをえないの で、国民は知らず識らず海上の習慣を得、造船、航海の研究ははるかに大陸諸国をしのぐ。国民 68 は海上の戦争においてもさらに多くの熟練と勇気とをもつようになる。古代の歴史においてクレタ、 ロードスおよびキプロスの諸島はおのおのその商業をもって世にその名を著わしたのだ。 島には海によって諸国間に貿易を営む便宜がある。大陸の諸国では内国貿易も道路と運河の 手段を使わざるをえないが、島地では沿海貿易で済む。国内各地の間の貨物の交易は、時と金を はるかに節約できる。」 この言葉は実に至れり尽くせりではないか。私が付け加えることは何もない。 〔第四〕位置。試みに地図を開いて見よ。わが国はどんな位置にあるか。東洋の極東に位置し ている。領土は狭く各国を雄視するには足りないが、その位置の便利さから見て、将来東洋貿易の 中心となりうることを考えれば、決して遺憾とするには当らない。体格が小であっても、才知抜群の 人は偉男子を制することが出来る。昔から商業国は必ずしも大国に限らない。ギリシアのアテネ、フ ェニキアのツロ、オランダ、ベルギー、あるいはイギリス、いずれもその面積は日本と均しいか、二分 の一、三分の一以下である。にもかかわらず百貨の集散するところとなったのは、良い位置をしめ ていたからだ。長い袖はよく舞い、多い銭はよく買うという。人は山野にあるものは必ず猟し、河海 にあるものは必ず漁し、市町にあるものは必ず売る。それと同じように、天然の位置は必ず日本を 東洋貿易の中心市場とする。日本国民はこの好機を躊躇なく、遅疑なく、捕らえなくてはならない。 首を転じて四囲の光景を見よ。西方には一衣帯水を隔てて世界に無類な大帝国のシナと相対して いる。南方には南洋群島を控えてオーストラリアと連なる。北方の国境千島はシベリアの岬カムチャ ツカを望み、呼べば答えるように迫っている。シナは本国だけでも百五十余万平方マイルの面積を 有し、人口四億になんなんとする。その豊かな富はヨーロッパ人が常に恐れ、うらやみ、獲ろうとして やまない。 オーストラリアは新国ではあるが、それだけに将来わが国との貿易は大いに希望が持てる。金鉱 に富み、石炭に富み、牛羊は村々に広く散り、眼界一望砂糖の天地、小麦の世界、今や歴然と頭 角を現わしている。シベリア地方はオーストラリアとは比較できないが、日本の得意客であることは 決して争えない。そして日本の最大の得意先は、太平洋の向岸の北米合衆国だ。今日我が輸出 品の重なものは生糸であり、その主な輸出先は北米合衆国である。実にアメリカと日本とは商業上 69 の関係において唇歯助けあう好兄弟なのだ。しかもこれにとどまらず、あのレセップス氏が計画する パナマ地峡の開削が、氏の計画どおり一八八九年に完成し、二つの大洋が連絡すれば、四百余 年前コロンブスの脳中に浮かび出た大西洋を直航してジパングリー〔日本〕に達する夢が実現する。 そうなれば太平洋はもちろん大西洋の両岸に対立する各都府の港湾より、あるいは地中海沿岸の 市邑(しゆう)よりジブラルタルの海峡を通り、日本の港湾まで、大西太平の二大洋を通じて一線の 船橋を渡すことになる。わが国はたとえ好まなくても、天然の好位置は日本を駆って商業国とせざる をえない。旧来の陋習を破り、天地の公道に基づき、上下心を一にし、武備拡張の主義を断然廃 棄し、商業国となるのだ。私がかつて『自由道徳および儒教主義』の小冊子(明治十七年十二月) で論じたように、わが制度を自由の制度とし、財政を整理し、信用を厚くし、国民の所有権を安全に し、百般の職業を解放して国民の自由に任せ、干渉保護の跡を削り、大いにわが港湾を整備し、 大いに関税を減らし、全国を開いて外国人の内地雑居を公許し、来るものは拒まず、往くものは追 わず、外国の人民も、外国の資本も、外国の貨物をも、自由に注入できるようにすれば、百工が興 隆し、まるで霜や雪に押えられていた草花が春風にあってたちまち芽を発するように、疑いなく繁栄 の好時節を迎えるであろう。 そうであれば、耕やす者はみな野に出、商人はみな市に出、旅人はみな機会を求めて出ていこ うとする。日本はたちまち太平洋中の一埠頭となり、東洋の大都会となり、万国商業の問屋となり、 数万の煙突は煙を吐いて天を暗くするだろう。雲のような高楼、林のような帆柱は、鑿(のみ)や鎚 の建設音、蒸気機関の響き、車馬の行き交う声とともに相和して、晴天白日のもとに雷鳴を聞く活 況をみせるだろう。まことに愉快ではないか。 ジョセフ・クック氏は言った。「日本は小さい国だが舵(かじ)のようなものだ。東洋の大船を動かす のはこの舵以外にはない」と。非常に道理のある言葉である。以上の理由に相違がなければ、わが 国は天然の商業国となる条件があるといわざるをえない。しかしここに一つの疑問がある。それは、 わが国民がはたして商業家の資格を持っているかどうかの問題である。 日本の国民は軍隊世界のうちに生長した国民だから、現時点では商業家となる資格をもっていな い。しかしこの障害は決して商業家の資格を否定するものではない。日本人が初めから商業家・生 70 産家になれない運命を持っているわけではない。なぜなら封建時代の習慣は、国民をもっとも無益 で活力のない人物にしてしまったからだ。習慣によって養成された性質は、また習慣により変更す ることができる。一つの境遇によって制せられた性格は、また他の境遇によって制することができる。 わが封建の士族は維新の大変動のために永世の家禄を失い、自力で食べなければならなくなった。 しかして今日士族で餓死した者はほとんどまれである。境遇の変更とその刺激は、相伴ってわが士 族に迫り、彼らを生産者に変えていったではないか。武士が生産者となり得るなら、わが武士国を 商業国に変えるのも困難ではない。 前に述べたように、わが国は世界の状況によって支配され、世界の大勢により支配せられ、しかも その支配を妨害する事情は一つもない。かえってこれを強化する日本特有の自然条件に支配され ている。そして一方では是非とも世界万国と対立して一国の生活を維持しなければならないという 必要に支配されている。これらの必要はたちまち日本人の資格を一変して、純然たる商人・貿易 者・職工・資本家・事業者に変えていかねばならない。いかにやさしい春風には動じない岩石とい えども、この切迫な勢いのためには変化を迫られる。敏捷で融通変化、境遇に従い、事情に従い、 適応力に富む点では世界に評判高い日本人が、変化に対応出来ないはずはない。 日本の先祖は、決して徳川封建末路の国民のように遅鈍でしかも軟弱、深窓の婦女子然とした人 間ではなかった。我らが誇りかつ羨むほどの、活発でしかも大胆な気象に富んでいた。 たとえば大友宗麟(そうりん)、蒲生氏郷(がもううじさと)、伊達政宗は、使節をローマに遣わした。 わが緑髪黒瞳の日本人は、すでに十六世紀の終りに、ローマ大帝国の結構壮麗な旧都で、各国 の貴紳と法王の膝下に近接し、壮厳神聖な儀式にあずかってセントピーターの寺院の祭壇の傍ま で進んだではないか。ことに伊達政宗が「邪法が国を迷わし、口に唱えてやまない。蛮国を征伐し たいがまだ実現していない。雄途に就く翼がはばたく日はいつ来るか。万里から吹く風が待ち遠し い」という詩を贈って送り出した支倉常長の一行は、一六一四年(慶長十九年)に太平洋を一直線 に航海してメキシコに着き、スペインをへてついにローマに達した。太平洋航海の最初の航海者を マゼラン(一五二〇年)とするなら、第二の航海者はわが支倉常長である。ああわが日本人は千古 の豪傑マゼラン以後の第一人者として豪勇無双な航海をしたのだ。これにとどまらず、シナ海・イン 71 ド洋の沿岸、西海の群島諸方に日本の商船は時々往来し、冒険者たちはあるいは植民をし、ある いはその地方の重要な権力者となった。私が云わなくても、識者は誰でも知っていることだ。このよ うに日本で通商航海の道が進歩したとき、貿易の真理と主義が微光を放ちはじめたのである。慶長 年間わが商舶が安南に赴いたとき、当時の有名な儒者で徳川時代文学の開山であった藤原惺窩 は、船中の規約を作って与え、こう言った。 「交易とは、自分に無い物を求め、利益を得ることである。人に害を与えて自分が得をすることで はない。双方が利を得れば、利が小ないといっても効果は大となる。双方が利を得なければ、大き な利といっても効果は小さい。利とは、義の双方の合致である。だから、『欲の深い商人は儲けが少 なく、廉潔な商人はかえって儲けが多い。』といわれるのだ。」 もしこの勢いを保ち、途中で挫折しなければ、日本人が商業者となる資格があるかどうかの議論 や、日本は天然の商業国だろうかという問題は解消する。論より証拠、今日の日本国民はみな生ま れながら炯眼(けいがん)活溌な貿易者となり、生まれながら波涛をものともしない健児となるであろ う。これを思いあれを想えば、封建の創業者徳川家康の政策はまことに遺憾であった。しかしこれ はただ一時の妄想であって、過去を咎めるべきではない。封建時代を過ごした事実は、決して日本 人が貿易者・航海者の資格を昔から持っていなかったのではないと、証明しているのだ。今日それ を疑うのは、人為による抑制があったからである。もしこれを除去し、自由な活動にまかせれば、日 本国民は他人の鼓舞、作為を待たずに、あの先祖のように、否、あの先祖よりさらに一層進歩した 生産者・商業家となるのは、決して疑いない。 第十二回 過去の日本 一(第四 わが国の現今の形勢より論ずる) わが国の少年学生は、講堂で教師からスパルタの話を聞くと、奇妙な国風に驚嘆して舌を巻くが、 われらの父祖の日本は、スパルタのように、いやスパルタよりも一層緻密、周到に軍隊組織の行き 届いた武備社会であったことを知っているだろうか。 現在の日本の状勢を論ずるには、まずこの父祖の社会に関し述べておく必要がある。 72 徳川封建社会の前に封建社会はなかった。徳川封建社会ののちに封建社会があるはずはない。 我らの父祖の社会は宇宙の歴史の中でも空前絶後の現象であった。なぜなら徹頭徹尾、社会の 生命と元気は武力ただ一つであって、天上天下およそ社会の空気の触れるところには、武力精神 が充満していた。まるで今日の常備軍制を全国民に及ぼし、今日の常備兵営を全国に拡充したよ うなものだった。全国みな兵営、全国民がみな兵士であり、兵士の使役する夫卒であった。当時の 武士は、今日の常備兵であった。異なる点は常備兵がある期限中兵士の義務を負担するものだが、 武士は生まれてから死ぬまで、一家の主人から家族まで、先祖から子孫まで、兵士の義務を負担 していた。当時の武士日常生活で常に双刀を横たえていたのは、今日の常備兵が銃を肩にし、剣 を腰にしているのと同じだったのだ。幼少から老大に至るまで、武芸に従事したのも、今日の常備 兵が操練演習に従事するのと同じであった。旅行の自由がなく、ただある免許を得てある期限に近 国を往来したのは、今日の常備兵が水曜・日曜の休暇に、門限まで兵営の外に出られるのと同じ だった。家にいて行儀正しく武器を調えていたのは、今日の常備兵が営中にあるようなもので、城 の太鼓を聴き、起臥進退したのは、今日の常備兵がラッパの合図により起臥進退するのと同じだっ た。武芸の認定状がえられないため家名が断絶したのは、今日徴兵の募集に際し体格が劣るため 不合格となるようなものだった。足軽から家老に、家老から城主に、城主から征夷大将軍に上った が、今は兵卒から下士・上士・佐官・将官に上っていく。こうして全国に充満した武士と、武士を統 制する高等武士(封建諸侯)はどんな生活をしていたか。彼らは一日といえども鋤を手にしたことは なかった。一日といえども算盤を握ったことはなかった。ではどのように生活を支えたのだろうか。他 に彼らの生活を支えるものがあったのだ。当時の農工商はみなこの武士と高等武士に必需品を供 給するために生存していたのだ。今日においても常備兵は自分では労作しない。すべて全国人民 に養われている。今日と封建時代と趣きが異なるのは、ただ一つ、常備軍は人民を保護し、人民の 生産を保護するために存在するが、当時の人民はこの武士および高等武士を養うために存在した 点である。このように人民は唯一の供給者であったから、供給目的を達するためには、労力も労力 の結果である財産も、あるいは二つとない生命をも、擲(なげう)ち捨てなければならなかった。当時 の分配方式は、今日全国に十二旅団あり、六師団あり、これを統制する陸軍本部があるように、三 73 百の城下において実行され、江戸が統制したのである。三百の城下は武士の小団結の地であり、 江戸はその大団結の地であった。このように武士は高等武士を追って集まり、供給者は武士を追っ て集まり、諸々の貨物は供給者を追って集まったので、一つ城下には必ず一つの町が出来た。全 国の大城下の江戸が今日の東京に比ベて劣らない繁栄を誇ったのも不思議ではない。私は各地 の封建城下を訪れるたびに、寂しげな空堀、破屋、秋草のはびこるのを見て、過去の社会の遺形 を知る。私は士族が城門を囲んで住み、商工業者が士族屋敷を囲んで住むのを見て、当時の富の 求心力は武士族にあったと実感する。 武士階層はどのようにして富の求心力を得たか。それは彼らが富の消費者だったからだ。どうし て消費者となることが出来たか。それは彼らが人を所有し、あわせて人の所有をも所有する主人だ ったからだ。彼らは決して市民と交易をするのではなく、ただ一方で横領した富を一方の貨物と交 換するのみであった。武備の世界では、この種の交換がわずかに行なわれただけで、真正の交易 は決して行なわれなかった。なぜならその世界には二種の階級しかなく、一はただの消費者で一 はただの生産者だったから。消費者は徹頭徹尾、ただ愉快に安楽に貨物を再生の見込みない地 に向かって消費するのみであり、生産者は徹頭徹尾、ただ終生骨を折り、汗を流して生産の業に従 事するのみ。封建時代の農工商は自分の生活を保つために労役するのではなかった。他人の驕 奢(きょうしゃ)助けるために労役したのだ。つまり彼らは生活のために労役したのではなく、労役す るために生活した。こうして一地方の富は城下に集まり、全地方の富は江戸に集まり、社会の富は 武士と高等武士のもとに集まった。主人の豪華はその奴隷の貧乏を意味し、城下の繁栄は田舎の 衰微を意味し、首府の富栄は地方の困窮を意味した。 このように軍隊組織の社会では、経済上の自然分配の法則を排除して、人為の分配法を採用せ ざるをえない。人為の分配は不平等主義によって行なわれる。不平等主義がひとたび横行すれば 当然に貴族的社会が現出し、怪しげな社会慣行が生じて来るのも論をまたない。 経済世界の自然分配の法則に従えば、全国、全社会、全国民を挙げてすべてを生産者とし、消 費者としなければならない。何人も生産者は必ず同時に消費者であり、消費者は必ずまた生産者 でなければならない。そして消費する額の多少は必ずその生産の多少と等しく、消費の多い者はま 74 た生産も多く、生産の少ない者はまた消費も少なく、原因結果の関係は緊密に行なわれる。勤勉し て富を生ずる者は葡萄の美酒、夜光の杯、花下の遊楽、月夜の船などの快楽を、自然の結果とし て買うことが出来る。怠惰で放逸な者は悪衣悪食、他人には恥かしめられ、自分には不愉快を感じ、 終生意気が上がらない。このような差があっても、天を恨むことは出来ない。人を恨むこともできな い。自業自得、みずから種をまき、みずからその実を収穫するのは自然の約束だからだ。しかし人 為の分配法はまったくこれと反対で、労者はつねに労し、楽者の苦痛を癒し、楽者はつねに楽して 労者の快楽を奪う。これほど不平等主義のはなはだしいものはない。これほど不正義のはなはだし いものはない。これを忍ぶことができたら、ほかに忍べないものはなかろう。徳川氏の天下二六〇余 年の長い歳月、武士はもちろん、被害者の農工商の人民すら、一人として正義の回復に向かって 天理人道の保護を叫んだ者がなかったのはなぜだろう。私は実に不思議に思う。 このような現象は尋常普通のものではない。社会の表面に表われる現象は、その裏面の精神を 反射するもの、つまり鏡である。エジプトの巨大なピラミッド、シナの万里の長城のような大工事が今 日残るのは、上古の二国において貴族社会がもっとも発達した証拠である。この時代に、このような 国で、このような大規模な工事が出来たのは、決して偶然ではない。ただ百姓の力を疲弊し百姓の 財を費消し、全国人民の肝脳を搾(しぼ)って成就したものだ。この二大事業は、いかに大きいとい っても、長い歴史の上では上古の圧制の記念碑に過ぎない。一国の貧富は全国人民の富の総合 値である。あの貴族社会は全体よりすれば非常に貧国にもかかわらず、その社会の表面はかえっ て平民的な富国よりも壮麗雄大・光彩華やかに見えるのはなぜだろうか。全国の富を人為の手段 により一部に集めたからだ。貴族が美麗な衣服をまとったのは、全国民を裸体としたからだ。美酒を 飲み、美味い肉に飽いたのは、全国民に土を食らい、水を飲ませたからだ。家にいては美姫を擁し て楼閣に住み、外に出れば肥馬にまたがり、軽車を乗り回す。これに従う雲のような全国民は、風 に吹きさらされ、雨に濡れ、父子兄弟妻子は離散し、泥地に転び倒れた。貴族世界の第一義は他 を損して己(おの)れを利する一点にあった。他を泣かせるのは己れが笑うためだ。他を転倒させた のは己れが舞うためだ。他を泣かせたのは己れが歌うためだ。己れの飽食のためには他の股を割 いて食わざるをえない。己れの淫欲を満足させるには他の子女や妻をも強奪せざるをえない。己れ 75 の怒りに触れれば他を斬殺せざるをえない。いうまでもなく己れの生命を維持するためには、他の 一命を遅疑なく要求する。他の生命すら断ち葬る。人を斬るのに草を切るように声を聞かない。正 義はどこに、公道はどこに、平和はどこに、権利はどこに、法律はどこにあったのだろうか。ただ暴 逆が正義、不公平が公道、闘争が平和、威力が権利、滅法が法律であった。このような社会を私は 大野蛮、大圧制の社会というのだ。このような武備機関が膨脹したのは自然の結果である。だから この悪因果を憎んで、なお全国を兵隊組織の社会を目指すのは、酔った人間に酒を強いるに等し い。間違ってはいけない。世人は美術がわが国に進歩したのを見て、わが国の光栄とする。しかし これは誇ってよいものだろうか。わが国のような貧国がなぜ身代に不釣合な高尚の美術を生んだか。 ただ貴族的な需要があったからだ。この需要はなぜ生じたか。平民の窮乏があったからだ。封建貴 族は、ある意味では無限の富源をもっていた。生活の必要には不相応な富をもっていた。そこから たちまち需要を生じ、その需要から奇妙不可思議な現象が生じた。緞子(どんす)・綸子(りんず)・ 綾・錦などの精巧な織物を製造したのは、襤褸(ぼろ)さえ纏(まと)えなかった国民があったからだ。 九谷焼の豪華な器を製造したのは、貧乏徳利さえ持てなかった国民があったからだ。梨子(なし) 地の金蒔絵や漆器等を製造したのは、破れた膳や椀さえ持てなかった国民がいたからだ。友禅染 や縫箔が製造されたのは、紅花染の綿衣すら着れなかった国民がいたからこそだ。金銀・赤銅・象 牙などの奇想な細工が行なわれたのは、国民が鍋釜さえ持てず、包丁を歯牙に代え、箸を手指に 代え、燈火を月光に代えたからだ。日光の廟の壮厳雄麗、金碧が目をくらまし、今日なお世界各国 の喝采を博しているのは、わが国民が一切れの墓田も、三尺の石塔をも持たず、親の菩提(ぼだい) すら弔うことが出来なかったからだ。これらの美術品は、実に封建時代の国民の苦痛と怨恨を子孫 の我々に説明し、記憶せよと命じている。よって生れたゆえんを考えず、ただ漫然として見るのは、 祖父の心を知るものとはいえない。むしろ識者の笑いを招くであろう。 戦国時代の三河武士は、勇猛、朴訥(ぼくとつ)、死を恐れないことでは右に出るものがなかった。 白刃を踏み、水火をものともせず、あのクロムウェルの三千の鉄騎をしのぐ力を持っていた。しかし この三河武士は封建の治世になってどう変貌したか。寛政時代の賢相松平越中守が旗本八万の 武士に向かって厳しく論じた文を読むと、実に嘆かわしい思いがする。 76 「我々の先祖の多くは東照宮に仕え奉り、数度の戦場に身を砕き、骨を粉にして働いた。その勲 功により知行があてがわれ、今に至るまで、身を安楽にし、妻子を扶助し、諸人から御旗本と敬わ れている。これみな先祖の勲功によるものである。しかるに先祖の恩を忘れ、あてがわれた知行を 自身の物と心得、百姓を虐げ、恩恵の心なくややもすれば課役を申しつけるなどは、正しい心とは いえない。このような不行跡は、若年より学問をせず、何事をもわきまえず育ったからである。…… たとえば古来よりの楽しみとして和歌を詠み、蹴鞠・茶道・あるいは連歌・俳諧・碁・将棋などの遊び があるのに、今は旗本に似合わない三味線・浄瑠璃を語り、こうじては川原者の真似をする輩(や から)も間々ある。これらは本妻を持たず、召使の女に家内を治めさせているので軽々しくなり、不 相応な者に奥深く出入りを許し取締りが不十分である。身の恥を思わず、わがままな行ないは、お のずから勝手不如意となる。武芸を鍛えず、益もない金銀を費やし、これを償うため多くは筋違い の娘を金銀の持参目当てに貰い、身分の軽い者の子を金によって養女とし、娘とするから、自然に 家内を取り乱す。天和年間の法制により養子は同姓より致すと決めたのは、筋目を正す目的である。 身分あるものが以後養子あるいは娘取りをするときは、縁金という慣行を停止し、姓を正し、婚姻の 時節を延ばさず取り結ぶようにせよ。身分不相応な婚姻により、金銀の用意がなく漫然と時節を送 っておれば、男女の道はおのずから正しくない方に向かう。これを深く考え、家長はよくよく心をつ け、婚姻を願い出るときには吟味を尽さなければならない。婚礼の時節を外し、年若い面々が遊所 に入り込み不相応の遊び事をすれば、風俗は乱れ、衣服などに着ける家紋を略し、夜行のときの 提灯の印を替え、云々。」 事態はここまで衰えてきた。いかに賢相が苦心して祖宗の天下に戻ろうとしても無理であった。軍 隊組織の制度は、決して永久に武士の活発質朴な本来の真面目を維持できない。先祖は赤手を ふるって四海を圧倒したローマ人も、その子孫はたちまち北夷蛮人の鉄蹄に蹂躙されたではない か。このような現象が武備社会に起るのは、けっして怪しいことではない。なぜなら、武士というもの は人民の租を食らい、税を着るものだからだ。いかに贅沢をしても自分は損をしない。玉杯を作る のも、象牙の箸を作るのも、銀の橋を庭の池に架けるのも、自分の懐には関係ない。白砂糖で築山 の白雪を装うこともできた。悪因を結べば善果が来、善因を結べば悪果が来る、という。食を一汁一 77 菜に限り、服を綿衣に限れば、その結果はただ生活の不愉快を感ずるのみ。そんな倹約は自分に とって何の利益もない。酒池肉林の楽しみはただ生活の愉快を感ずる。そんな贅沢をしても自分に は何の損害もない。一方では無限の権利者があり、一方には無限の義務者がある。しかもその主 人には奴隷を厚遇せよという。全く愚かなことだ。武士あるいは高等武士は、無限の権威を持つ無 責任の皇帝だった。取っても尽きず、汲んでも涸(か)れない財源を持っていた。たとえ涸れても自 分には決して痛くもない財源を持っていた。これを持っている以上無駄にすることはない。私は断 言する。武備の社会は必ず武士つまり主人を驕奢に導く。文弱に導く。なぜなら彼らは自分の労力 により生活するものではないから。彼らは生活の必要以上の富を持ち、富を消費する道に苦しむ。 両者の間に不自然な需用が生じざるをえない。一方で生活に不必要な富を持てば、必ず他方では 富者に奉ずるために生活に必要な富すら持てない者が生まれる。一方に不自然な需要が生ずれ ば、他方には不自然な供給が生ずるのは論をまたない。田口卯吉氏は『日本開化の性質』の小冊 子で親切にこの道理を説明した。その一節を次に掲げよう。 「このように人民の頭上に累積する諸侯大夫は、労作して産を得ることはまったくなかった。すべ て人民の労作したものを自分のものとしたのだ。彼らは一人の妻で足りるとしなかった。さらに妾を 求めた。もし社会の人がみな富人なら、その求めに応ずる者はないだろう。貧困に陥っていた人民 は、妾を求める者に喜んでその子女を供する者があった。これが社会に妾というものがあるゆえん だ。彼らは妾を得てなお足りるとしなかったから、娼家に遊んだ。社会の貧しい者は、彼らのために 子女を提供し娼婦とした。これが社会に娼婦というものがあるゆえんだ。娼婦があってもまだ楽しみ を満たせず、さらに絃妓を求めた。社会には貧者があり、子女を絃妓として提供した。絃妓という者 が社会に出たゆえんだ。すでに絃妓があるのにかかわらず、なお次に幇間を求めた。貧困な者は 盗賊や乞食に甘んじたが、幇間にもおちぶれた。ここに幇間という者が社会に生まれた。以上のよ うな社会相の変化はみな貴族的な需要がもたらしたものである。」 巨石が崖から転げ落ち、積水が絶壁より流れ落ちる。いくら腕力に誇る者も、その勢いを制するこ とはできない。ローマ社会が文弱に赴くときは、老カトーがこれを怒り、叱咤し、鞭を振っても、止め ようがなかった。徳川社会が驕奢に流れると、松平越中守や水野越前守が涙を流して怒り、苦慮痛 78 心してもどうにもならなかった。彼らが嘆息するような現象が生じたのは富の分配が正当に行われな かったからだ。富の分配が正当に行われなかったのは、社会組織が不完全だったからだ。因果の 大法則は人力で止めようとしても決して出来るものではない。世の政治家たちはなぜ本来の法則に 戻ろうとしないのだろうか。 第十三回 過去の日本 二(同上) 徳川時代のような武備機関の膨脹した国では、いかに平和であっても、いかに人口が増えても、 いかに物産が興隆し、いかに農工商の生産者が勤労しても、決して全国の富が蓄積し、全国民の 生活程度が進歩することはない。なぜなら年々産出する富は、年々軍備に供され、つまり武士およ び高等武士を養い、彼らの贅沢ために消費されるからだ。年々歳々このような不生産的消費に富 を投ずるのは、貨物を水底に投げるのと同類で、再生の見込みはない。これが徳川氏の天下二六 〇余年、太平が続いたにもかかわらず、日本が依然として野蛮な貧乏国にとどまった理由である。 武備の立法者の眼中には、兵略上の思想が唯一あるのみ。城下の位置を定めるには、山を絶ち、 谷による天険を選び、道路や城門を築造するにも、ただ攻守の便宜より判断を下す。関所を設けて 物流を監視し、行政の区域を定め人民を統制するにも、すべて軍備の都合による。農工商の事業 に干渉するが、それも独立した生産事業の育成としてではなく、ただ武備の目的を達する一手段 一作用として干渉する。もちろん経済上の真理は夢にも脳中に浮かばず、ただ隣国との開戦や籠 城のときに備えて、必要な糧食、資材を平生から調達して置くのが目的である。封建領主が第一に 奨励したのは農業で、ことに奨励したのは穀物の生産である。封建制の局外にいた学者頼山陽で すら、封建立法者の策に籠絡され、農を尊び、商を賤しむ議論をした。遺憾なことであった。 これに続いて武器調度の類、あるいはその領主の逸楽のための贅沢品も、すべて領地内で作ら せた。今日では、南極洋の裏、北斗星のかたわら、あるいは熱沙の広がる赤道直下、およそ舟車の 及ぶところ、太陽の照らすところ、空気の通ずるところ、人類の住むところを挙げて人類の需要を満 たす供給地となるのだが、わが封建社会では、日本国を限って唯一の経済世界とした。まことに窮 79 屈至極であった。さらにこの狭い日本国には三百の領主があり、その領内はみな一つの兵営であり、 その中の人民は決して自由な行動は許されなかったので、わが封建の経済世界は取りも直さずこ の一領地内で行われた。つまり日本の面積の三百分の一の平均八十方里余が一世界一天地であ った。この豆粒大の天地で、僅かな人民により、職業を分担させ、産出を求めたのである。こんな社 会で適切な分業が行なわれるはずがない。損を去り利に就く経済が行われるはずがない。天の時 を得、地の利を得、人の和を得、自然の傾向に従い、自然の職業に従事することが出来ようはずが ない。このような封建領地の状態が老子の言う至治の世なのだろうか。 〔註〕老子曰く。「至治の極は、隣国と平和を保ち互いに鶏や犬の声を聞く。民は領内で衣食に満 足し、習慣を守り、仕事を楽しむ。老死に至るまで隣国とは往来しない。」 ああこれが封建政治の最良の世界であった。これは我々の希望であったろうか。封建の社会では、 生産者である人民は、みずから鍛工となって耕具を作り、みずから農夫となって耕し、みずから料 理人となって調理し、近海を航行するときはみずから舟大工となり、みずから水夫とならねばならな かった。家を建てるにも、みずから木挽・大工・石工・左官となったロビンソン・クルーソーを学ばざる をえなかった。これでは生活世界の進歩は望めない。わが封建社会の人民は、このような不自由で 窮屈の世界に住み、さらに幾層倍の不自由で窮屈な世界に住んだ可憐な孤囚であった。しかし我 らはなにゆえに悠々としてこれに安んじていたのか。それには理由があった。それは隣国が敵であ ったからだ。昔、北条氏は塩を甲斐には売らなかった。武田氏は困った。このままでは死ぬほかな い。このとき唯一の兵略は塩の欠乏なく籠城の目的を達することであった。十指を失うこともいとわ ず、他を顧みるいとまもなかった。徳川氏の天下は元亀、天正の時代から出て来た。多事の日に積 み重ねてきた慣例格式は、無事の日にもそのまま慣例格式となった。 このようにわが封建の世界では、隣国を敵とした理由は何であったか。武備社会の本質からそれ を必要としたからだ。武備の社会というものは、隣国を奪おうとするか、奪われまいとするかのほか には政略がない。その手段は、攻守の相違があったにしても、隣国を敵とする一点に帰着する。長 蛇が急坂を下るように進撃し、あるいは猛虎が洞窟を背にするように退守するにしても、頼みとする のはただ自家の領地である。つまり割拠の主義は武備社会の主義なのである。徳川氏が鎖国政策 80 を取り、諸侯らが鎖藩政策を取ったのも、同じ考えから出たものだ。封建武士らが「北の客はよく来 てくれた。何で報いようか。弾丸や硝薬を使うのは恥だ。客がなお従わなければ、宝刀を彼の頭に 加えよう」の軍歌を歌って、互いに隙を伺ったのももっともなことだ。 私はかの保護貿易というものは封建社会の遺物であり、したがって干渉主義というものも封建社 会の目的を達するために欠くことが出来なかったと考える。封建社会では寸地もその領主の所有で あり、一夫もその主人の臣であった。武備の版図は立錐(りっすい)の余地なく全局に膨脹した。目 を挙げて経済世界のありさまを見れば、秋風寂しく吹く荒野に、黄面痩骨の鬼と見間違えるような 老若男女が鋤を揮い、機を織るのを見る。彼らが従事する職業はもとより自由の職業ではない。ち ょうど士官が兵士を指揮するように、無慈悲で残忍な官吏が鞭を振い、強迫し、なんの容赦もしな い。なんの会釈もない。苛政は虎よりも猛(たけ)し、とは実にこの時代のありさまであった。無邪気 で質朴な農夫らは一体どんな感情をもっていたのだろう。東洋の詩人は歌って言った。「麦はお上 に収め終わり、絹は機(はた)の上にある。お勤めが出来てやれやれだ。口に入れ身に着けるもの があれば十分だ。城に仔牛を収めなくて済めば、これほど有り難いことはない。田家に衣食厚薄は ない。都会を見なくても楽に過ごせるに越したことはない」と。農民の情はこういうもので、まことに哀 れであった。商業においても決して純然たる商業は行なわれなかった。ミル氏はいう。「このような社 会には二種の商人があった。穀物の調達と、貨幣の調達である。穀物の調達は生産者より穀物を 直接に購買せず、政府の代官をつうじて購買した。代官は租税を作物により取り立て、首府、つまり 帝王、文武の官吏、兵士およびこれらの人々の需要を満たす工人の集まるところの首府に運送す る務めを果たし、商人がそれを実行した。貨幣の調達は、不幸な農夫が天災によりあるいは苛税に より、困窮に瀕するとき、生活を保ち、耕作を継続させるために金を貸し付け、次の収穫において高 利を付けて回収した。また政府もしくは政府の歳入の一部を有する人々に大量に貸し付け、政府 の収税官による返済の保証を得た、あるいは土地を抵当に取り、その土地が産み出す税額で回収 した。商人は抵当を持つ間、返済の支払いが終わるまでの間、政府権力の大きな部分をみずから 握り、発動した。これらの商人は、政府の歳入となる一国の産物について采配する地位を保った。 政府の歳入から彼らの資本は利潤を得たのだ。政府の歳入こそ彼らの固有の資金の源泉であっ 81 た。」 この言葉は、わが封建時代の商業世界の実相をうまく描写している。江戸大阪はなぜ繁栄したか。 そして繁栄の分子は誰であったか。あれこれ考えると必ずある人物に行き当たる。商業もまた軍務 の一部であった。商人もまた官吏の一人であった。そこには専売特許の弊習が必ず行なわれる。 私はかつて『貿易備考』を読んで、わが封建時代の商業世界は実に専売特許の世界だとわかった。 あの問屋というものは政府と特別の契約を結び、冥賀金(みょうがきん)を上納し、株式を得て公開 競争の道を絶ち、専門商業の利益を独占したのだ。 〔註〕江戸には十組問屋があり、専売の特例を得たうえ、菱垣廻船、積荷仲間と連合した。さらに仲 間株式を定め総員一九九五名に株札を付与し、定員のほかには新規加入を許さなかった。もし組 合中破産、廃業の者があれば、組合がその株式を保管し、適当の者を選んで補った。その問屋に 属さない者には産地よりの直買を禁じて、組合仲間を保護した。冥加金の額は旧制以来変更なか った。ここでさらに六十五組の新連合が団結し、菱垣廻船積荷仲間が結成された。〔『貿易備考』〕 彼らの規律、統制の周到、厳密なことは、ドイツ、フランスの常備軍も及ばなかっただろう。 これで富の増進が望めただろうか。私にはもう一つ観察した事柄がある。封建時代にはなぜ遺伝 血統を尊び、門閥を重んじたのか。軍隊組織には必要不可欠だったからだ。軍隊組織というものは 強迫の組織だ。勇者ひとりが進むを得ず、怯者はひとりとても退くを得ない。軍隊の結合は圧制の 結合である。知者が知を伸ばし、愚者が愚を現わすことはできない。軍隊の組織に知愚なく勇怯も ない。ただ一切一様一定の規律のもとに運動しなければならない。だから愚者も長く職にある者は 知者を支配する。知者も職にある期間が短い者は愚者に支配される。軍隊世界の進路は「ただ先 着」の効があるのみ。我、彼より後れて立てばいかに努力し功を挙げても決して彼に追いつけない。 追い越すなどは論外だ。今日各国陸海軍の軍制を一覧すれば、わが封建時代に世襲が行なわれ た真理がわかる。なぜなら陸海軍の制度は、先着の功績(爵位・勲章・年金)をその人一代に限り、 あるいはその子と寡婦に限るが、わが封建社会はこれを拡げてその末世末代にまで及ぼしたので ある。徳川治世の貴族は、先祖を尋ねれば人民に功徳があったかどうか決して保証はできないが、 元亀天正の時代から群雄鹿を逐う戦国時代に多く賤徒より起こり、手に唾して州郡を横領した人々 82 だから知勇抜群であったことは承認できる。しかしその子孫はなんの功績があり、なんの才知があ って、こんなに多くの才俊豪傑に飢えの声を上げさせ、数多くの憂世慨時の人物を世間に埋もれさ せ、領内の百姓の肝脳を絞ったのか。なぜ他人の血と涙を自分の愉快にかえたのか。ただ先着の 一つがあったからだ。つまり父祖の余沢があったからだ。財産家の子孫といえども不肖ならば窮民 となる。しかし封建君主はいかに不肖、柔弱、狂暴、贅沢であっても、決して窮民とはならない。そ して封建の人民は、いかに雄才、豪胆の人物でもほとんど青雲の道は遮断されていた。天上天下 千万里、昇ろうとしても登れず、下ろうとしても下れなかった理由は何か。軍隊組織の精神により社 会を維持したからだ。武備社会の末路においては、特性であった美風善俗は跡を絶つたが、固有 な悪習毒気は増長はしても決して減ずることはなかった。どんな時代にあっても、軍隊社会がある 限り、あるいはその世界が表面から消えた後でも、その禍はいつまでも残るものだ。 血統と門閥を重んずること、以上のとおりであった。封建社会は造化力と人為を借りて奇戯を演ず る舞台であったといってもよい。当時、医者で診察や薬の調合が出来ない者があった。剣術の師範 で竹刀を振れない者があった。教授で句読点を知らない者があった。祐筆で紙面に書けず、画師 で絵具を使えない者があった。あるいは加減乗除を知らない算術家、度量衡の目を知らない商人、 監察できない監察、取締りのできない取締、勘定を知らない勘定方、奉行のできない奉行があった。 こんな有様だから、十六歳の元老、八歳の征夷大将軍があっても不思議ではない。 〔註〕太宰春台氏の『経済録』政篇に、「日本においては、諸道の学者や技芸家の多くは家の専門 とし、代々国家に仕えて俸禄を手にした。ゆえに芸術は徐々に衰え、名手の誕生はまれになった。 また事によっては家業も衰え、士人でありながら学ばない者があった。これは専門制度の欠点であ る。専門とは一家を立てその業を子孫に伝えることであった」とある。 このような世襲の弊習は、封建武士の一部のみではなく、社会の隅々まで及んだ。そのため奇々 怪々、表裏反覆・名実相違の現象を生み出した。中央の部分で行なわれるものは、何事も四隅ま で及ぶのは自然の理であり、私は決してこれを怪しまない。 封建の社会では、有形の現象ばかりでなく、無形の現象においても、その真面目を発揮した。た とえば封建社会の道徳は、天真爛漫、自然のうちに修養し、自由のうちに規法のある、愛し親しむ 83 ものではなかった。逆に式にこだわった死物の道徳であった。今日存在する浄瑠璃や院本(まるほ ん)などは、実に封建思想の産物であり、その時代の真相を写し出した明鏡である。 〔註〕「これかか様、士(さむらい)の子という者は、ひもじい目をするのが忠義じゃ。またたべるときに は毒でもなんとも思わず食うものじゃと、言わしゃったので、わしはいつまでも堪(こら)えている。そ のかわり忠義をしてしまったら、早くままを食わしてや。それまでは明日までも、いつまでも、こうして きっと居てお膝へ手をついて待っております。お腹(なか)がすいてもひもじゅうはない、なんともな い」と。皺顔つくり涙は出ても、幼な心に褒められたさがいっぱいで、私は泣きはせんわいと、額を 撫でて泣顔を隠す心は、さすがに名に負う武士の子である。〔伽羅千代萩(めいぼくせんだいは ぎ)〕 切腹して君に殉ずる忠臣。身を売って父母を養う孝子。利に営々とする商人の中で利を好まない 者。名に汲々とする君子の中で名を欲しない者。封建の道徳世界は牛鬼蛇神、ほとんど我々が想 像できないものであった。しかしこれもやむをえない。軍隊組織の中では決して避けられない結果 である。軍隊組織の元気はただ従順である。従順の極は自然の反動作用を抑制し、人為の作用を 強制する。立とうとするときに立ち、坐ろうとするときに坐り、言おうとするときに言い、黙ろうとすると きに黙り、苦痛を苦痛として避け、快楽を快楽として受け入れるなら、軍隊の組織は成立しない。軍 隊を完全に組織するには、苦痛を快楽とし、快楽を苦痛とし、毒を薬となし、苦を甘としなければな らないのである。 封建社会には一個の人民はない。つまり人民のために設けた社会ではなく、社会のために、いや むしろ領主およびその臣族の武士のために設けられた人民である。人民を保護するために官吏が あるのではない。官吏に奉仕するために人民があるのだ。人民なくして人民の事業があるはずはな い。事業なくして人民が不自由な手足を伸ばせるはずがない。政府のほかに力を振う余地は残っ ていない。だから、善人も、悪人も、賢者も、愚者も、治国平天下の志ある人も、巧言令色の人も、 少しでも志のある者は、唯一官途に就く道を求めざるを得ない。封建社会では官途の価値は異常 に高い。この道を上らなければ、いかに優れた人物もただ草木と同じように朽ち果ててしまう。しか しこの道に入るのは、駱駝(らくだ)が針の孔を通るよりも難しい。憐れなことではないか。 84 要するに封建社会においては、上、征夷大将軍より、下、庄屋に至るまで、みな一様に上に向か って無限の奴隷であり、下に向かって無限の主人であった。社会の位置は唯一の鉛直線であり、 何人といえども、何時といえども、決して同じ地位に立つことはなかった。いかなる場合にも、その関 係はみな上下の関係であった。これこそ軍隊の組織において緊要なものである。兵卒が下士官と 同列になり、下士官が上士と同列になり、上士が佐官将官と同列になれば一日として軍隊組織は 成り立たない。わが封建社会ではこの軍律を全体の関係に及ぼし、父子の関係も夫婦の関係も兄 弟の関係も、朋友の関係もこれで律した。複雑な政事軍務などはもちろん、隣里郷党・交際・冠婚・ 葬祭・花見・遊山等の細事に至るまでみな一様に、この不変の軍律で支配した。不平等の極め付 きであった。どの立法者もこんな偏屈、不都合を生ずるとは夢にも思わなかっただろうが、これは避 けられない結果だった。父が仇を討てば子は報復を受ける。やむをえないことだ。 軍隊政治の可否を知ろうと思えば、わが封建社会を見ればよい。この社会こそ武備機関が遺憾な く、完全に発達したものであった。これを公平に観察すれば、その利益もその禍害も解る。わが封 建社会は、我らの父祖が苦痛と怨恨とをもって我らに問いかけた、軍隊政治の利害を判断せよとい う一つの問題提起である。我々はこれを軽々しく見過ごしてはならない。 第十四回 現今の日本 一(同上) 現在の日本に立って現在の日本を論じようとすると、馬に対してその馬を説き、山に向ってその山 を弁ずると同じで、ほとんど無用の議論となる。しかしどうしても言っておきたいことがある。なぜなら 現今の状況をつまびらかにしておかないと、将来の命運が考えられないからである。 私は徳川政府の転覆を少しも不思議とは思わない。なぜなら、昨日は東周、今日は秦。咸陽(か んよう)の煙火、洛陽の塵。どの貴族社会も、一度はその実力が傾く非運に遭逢するのは必然であ った。政府の転覆とともに合わせて社会の全体を転覆し、政府の改革とともに同じく社会の全面を 改革し、その改革の猛烈な勢いは、止めようとしても止まるものではない。この事実は東洋の歴史に 豊富な実例を残す。シナ二十四朝の革命、新井白石が王代九変、武家五変と節目した我が国の 85 改革、これらはみな朱三・王八・大頭公・猿面郎などがたがいに秘技を演じたものだが、演ずる人が 異っただけで、舞台は同様の舞台であった。戯曲も同様の戯曲であった。東洋の改革史は陳腐、 常套、読んでおもしろくない。 ただ明治維新の歴史については、雄勁、複雑、人意を超越し、人を一唱三嘆させるものがある。 わが維新の大改革は、内外の衝動が一時に抱合し、外圧と内迫が一種の壮観、奇状を呈したから だと、私は断言する。くわしく言えば、世界の大勢が我が人心に警鐘を鳴らし、その必至必然の圧 力に迫られて、ついに意外の大事業をなしとげたのだ。未来永劫いまだかつて見ない、いまだかつ て聴かない、いまだ脳中に浮かばなかった新奇新鮮な戯曲を演じたのだ。傍観者であった国民が 意外に思ったのみでなく、演技者であった愛国義勇の維新改革の先達も意外と思ったに違いない。 歴史上、新日本開拓のきっかけを作ったペルリ氏が当時の将軍に奉った書状を見ると、 「鎖国という国法は一国独自の取決めであり、今は万国ともに通商をしない国はどこにもない。万国 の例に従って、通商を始めるのが貴国のためにもなる。」 この一節を熟読すれば、維新改革の難題はみな解くことができる。ナイルの下流に大洪水が起き たのはアビシニアの山中に大雨があったからだ。日本は改革前までは空に浮かぶ一片の雲も見な かった。大地に落ちる一点の滴(しずく)も見なかった。しかし忽然として政府はもちろん旧世界を一 掃するような大洪水がやってきた。これは決して魔術のせいではない。ただただ世界風潮の大波乱 があったからだ。維新改革の先達は玉石ともに焼かれることを恐れ、右顧左眄(うこさべん)したにも かかわらず、必迫の圧力をもってこの大波乱を乗り切った。一つの改革はさらに他の改革を生み、 一つの転覆はさらに他の転覆を誘い、止めようとしても止まらず、休もうとしても休めず、ついに今日 においてほとんど例のないほどの改革が行なわれたのである。 寛政の改革以来、日本の改革家は何回か流れをせきとめようとしたが、改革の猛勢はこれを受け 入れず、転々としたあげく、ついに慶応三年徳川内府は大政を返上し、中興の事業は完成したと 思われた。しかし、戊申の大変動となり、太政官の制度を定めてまずは雨降って地固まったと人々 が安心したにもかかわらず、さらに諸藩の版籍奉還となり、その勢いは一転して廃藩置県という未 曾有の大改革を行う英断となった。このような推移は当時の改革家の胸中にあらかじめあったとは 86 思えない。これが臨機応変の処置だったのか、とにかく日本は武備社会を一変して生産社会とし、 貴族社会を一変して平民社会とする大基礎を築いた。当時の詔勅条例を見ると、意気は鮮烈、精 神は活発であり、人は当時の風雲を懐かしく思うであろう。「広く世界の形勢を考察する」といい、 「近来世界は大いに開け、各国は四方に雄飛する時代に、ひとり日本のみが世界の形勢に疎く旧 守を固守し一新の効を謀らないわけにはいかない」といい、「万里の波濤を開拓し、国威を四方に 示し、国富を安泰にする」といい、あるいは「願わくは大活眼大英断により、万民がともに一心協力、 公明正大の道理に従い、万世にわたって恥じず、万国に臨んで恥じない大根柢を建てなければな らない」という。これらはみな先達の諸子が黙々のうちに当時の世界情勢により支配されたことを物 語っている。当時の大勢はあたかもアラビアの砂漠に現われた白雲紅火の円柱が、方向に迷った イスラエル人を誘導したように、維新の事業を誘導し、千里一送して今日の新日本に到着した。改 革先達の諸氏はもとより稀に見る人物であったが、活眼卓識の点では、横井小楠翁の右に出る者 はなかった。翁は大政奉還に際し越前老公につぎのような建白書を献呈した。 一、幕廷が悔悟され、誠心を発せられたのは、まことに恐悦の至りです。四藩は一日も早く上京し て、誠心から朝廷の補佐、助言をすれば、皇国の治平の根本を確立することが出来ます。公 が東京に滞在され、正義の人々を登用し、とりわけ某殿を重用し、心底から庇護されるよう、こ れが私の第一のこい願うところであります。 一、同志の諸侯は早速に上京されてはいかが。ひとまず重役を派遣される向きも多いでしょう。新 政の初めは特に慎重を期し、四藩のうちどなたでも上京のうえは大赦の大号令を仰せ出さ れたい。ただし、朝廷も反省、自責され、天下一統、人心の洗濯をされるよう請い願います。 一、一大変革の時節ですから議事院を創設するのがもっとも至当と考えます。上院は公武で構 成し下院は広く天下の人才を集める。 一、四藩がまず執政職につき、その余は諸侯の中から賢名の聞こえる人物を選んで、追々に登 用する。 一、皇国の政府が立つうえは、金穀の用度を一日も欠かせない。勘定局を建て(この人選はこと に大切です)、差し当り五百万両くらいの紙幣を発行して皇国政府の官印を押し通用させる 87 必要があります。 一、皇国中の知行には、一万石につき百石を課し、政府の年貢米とする。ただし幕府が辞職 すれば莫大な用度が省かれ、諸侯が参勤をやめ江戸を引払えばこれまた莫大な削減が 出来る。十分一の年貢米は当然で、紙幣はこの年貢米より取り収めることとする。 一、刑法局を創設する。 一、海軍局を兵庫に建てる。関東諸侯の軍艦を取集め、十万石以上の大名に高に応じ、人数 を定めて、兵士を出させる。西洋より航海士と指揮官を雇い受けて伝習させ、年々艦数を 増し、熟練すれば、人心一致、士気興隆、万国の勢力と並ぶことができる。総督は大名の うちからその器に当る能力のある人に命じ、それ以下の士官は関東諸藩の熟練の士を登 用する。すべての設備はまず勘定局より費用を出し、外国貿易が盛んになれば諸港の関 税を当てる。この費用は莫大だから、貨財運用の妙は議事院中の能力ある人物を選んで 任せる。 一、兵庫開港期日は迫っている。国体の名分が改正されたので、旧来の条約は妥当しない。 随時改正し公明正大百年不変の条約を定めねばならない。ただおそらくは事件によって は困難が予想される。後日の大悔とならないよう公平な交渉をしなければならない。 一、外国に貿易商法の学問がある。世界の産物の有無をしらべ、物価の高下を明らかにして 広く万国に通商し、さらにまた商社を作り互いに交易する。欧米人はこのような熟練をもっ てわが拙劣の人に対するから、ほとんど大人と小児のようなもの。六年余りの三港の交易 は、彼らが大利を得たわけで、日本に一人の富商も生まれず、彼らはすべて大富の商人 となった。この現実をみれば、これまでの交易は明らかにわが国の大損です。これは要す るに日本から外国に乗り出さなかった弊害であり、すぐにも改める必要があります。西洋で は露・英・仏・米・蘭の五国、漢土には天津、上海、広東の三港に日本商館を設け、内地 では商社を作り、兵庫港なら五畿内、四国、南海道の大名はいうに及ばず、商人百姓で も望みによってはその社に入れ、一致協力しともに船を仕立てて海外に乗り出し交易す べきです。他の三港も同じです。ただみだりに出入を禁じ、必らずその港の税関の承認を 88 受け、行く先の日本商館へ連絡する。帰帆も同様です。こうすれば自然に商法に熟し、利 を得ることは明らかです。内地も自然に彼らの奸計をのがれ、公平な交易が実現するでし ょう。これはもっとも重要な案件であり、すみやかに決定されることを望みます。 一、外国への公使、外交担当者ならびに諸鎮台等の役人は、将軍が辞職されても諸侯の長で あることに変わりないから一人は旗本から選び、その他は下院中より選挙するのが良い。 一、大小の監察官や側用人等の類は無用であり廃止。記録布告などは下院ですればよい。こう すれば政事は簡素化できます。 一、各国に公使を送り国体の改正を布告する。 上記の事項はただいまの急務と存じます。学校を初め御改政の諸事は詳しく存じませんが、 政府の基本が確立してからのことと存じます。以上、至急に書き記しましたので、不都合な点も ございましょうが、献言申し上げた次第です。以上。」 私はこれを一読して実に翁の規模遠大、まことに改革の率先者として恥じないと感じた。しかし翁 の眼中にすらなお封建の制度は残滓が残っている。そうであればいったい誰がこの軍隊組織の社 会を転覆したのだろうか。清の学者趙翼(ちょうよく)が言ったように、人情が旧習に狎(な)れている あいだに、天意は新局を用意していると知った者が天下の大勢を動かしたのではなかろうか。 私は維新の歴史を読むとき、一つとしてその事業が尋常の原因より出て尋常の結果に入ったもの を見ない。前提と結論が通常の関係を持つ例を見ないのだ。幕府に抵抗し、一戦して倒したのは 薩長二藩だから、二藩が幕府の跡を継ぎ東西の二大将軍となるのが普通に思える。しかしこの二 藩は率先して藩籍奉還の議を唱え別の方向に進んだ。これはなぜか。維新の大功臣は問わなくて も西郷・木戸・大久保の諸氏だとわかる。これら諸氏が廃藩置県の議を主張煽動したのはなぜか。 維新の改革は一方の武士が他方の武士に対して勝を制した武士の改革である。しかるに武士が武 士の権を殺(そ)ぎ、特例を奪い、特許を剥(は)ぎ、家禄を没収し、生命と頼んだ刀剣さえ禁じてし まった。これはなぜか。人は哲学者でないから、わざわざ功を求めない者はない。だが維新改革に 功のあった諸藩諸氏は電撃雷撃の死地に立ち、万死一生の途を出入し、端なくこれを成就したに もかかわらず、功を誇らなかった。維新を天下に及ぼし公明正大の政略を採った理由は何だった 89 か。必ず理由があるはずだ。 表面から観察すれば、これらの転換は煙火を不要とする天使の事業であり、とうてい濁世煩悩界 の人間のする事業ではない。これらの諸氏の行動はほとんど情欲を超越した天人かと疑うほどであ る。しかし裏面を観察すれば決して怪しむに足りない。なぜならやむをえない必然の勢いがあった からだ。必然の勢いに圧迫されるときは何人といえども哲学者となり、聖人となる。これは維新改革 の諸氏ばかりではない。 維新の諸先達もまた人である。胸中には一点の名利の心がなかったとはいえまい。およそ人生の 事業においては多少の賭博的分子を帯びるものだ。その分子の多少に従い、危険の性質を帯び るものだ。そして人生の事業は政治の改革より賭博的なものである。その危険もまた大きいと知らな ければならない。したがってこの苦難の世界に奔走して幸いに目的を成就できればこれほどの喜 びはない。思うところ、願うところを必ず成し遂げる、これがわが東洋の改革家すべての信念であっ た。しかし維新先達の諸公はなぜこの快活豪胆な東洋流の英雄を学ばず、かえって謹厳端正な米 国の創業者の実例にならったか。これは実にやむを得ない事情があったからだ。世界の生産的な 条件と平民主義の大勢がわが幕府を駆り、わが井伊大老を駆り、わが水戸烈公・藤田東湖を駆り、 わが佐久間、吉田諸氏を駆り、わが梁川星巌を駆り、わが横井小楠翁を駆り、会津桑名を駆り、越 前公を駆り、薩長二藩を駆り、西郷・木戸・大久保諸氏を駆り、佐幕勤王、攘夷開港を問わず、無 謀の暴挙にせよ、活眼の信念にせよ、因縁もなく、関係もなく、個々分離・自家撞着の事業をばす べて大鍋のうちに溶解し圧搾して、当時の英俊豪傑や竜顛虎倒の分子を尋ねる跡もなく、唯一の 新日本という固結体を製出したのだ。この新日本こそ私たちが住む現在の日本である。 第十五回 現今の日本 二(同上) どの時代においても、現在は必ず過去の分子と未来の分子とが衝突し、格闘する戦場である。こ れが真実なら、日本の現今においてもっとも真実といわなければならない。過去の世界と未来の世 界は決して同一の世界ではないが、その進歩を秩序のうちに保つ社会においてはその距離は短 90 い。前岸に出没する人影は後岸に立つ人の眼に容易に見える。現時の日本について、私はかつ て『第十九世紀日本の青年及びその教育』の小冊子においてつぎのように論じた。 「維新改革の大波乱により、わが青年と老人との距離は数千万里の外に拡大した。西欧の開化 史を見るとあの北狄の蛮人が鉄剣快馬をふるって、ローマ帝国を襲い、ついに封建割拠の勢いを 招いて、君主・臣僕の制度を欧州全土に及ぼして以来、十九世紀の今日に至るまで、おおよそ四、 五百年の星霜を重ねた。その間歩々一歩を転じ、層々一層を上り、知らず識らず今日に至った。こ の着実な進歩に反し、わが国においてはこの数百年の長程を一瞬一息のうちに駆け抜けたのであ る。このため数百年前の封建の残余と数百年後の文明の分子が同一の時代において、同一の社 会において、肩を並べ袂を連ねて、生活するという奇異な現象を生じてしまった。 だから現在の日本は、封建時代の先天の日本と、明治時代の後天の日本との大激闘の戦場とな っている。もし偶像を破壊し合わせてその偶像を拝する迷信を破壊し、家屋を焼失し合わせて家屋 に住む人の習慣・偏癖を焼き尽し、制度を転覆し合わせてその制度を維持した固陋な観念を転覆 し、社会を改革し合わせて会の精神・元気をも改革することが出来れば、社会の改革は掌を返すよ りも容易であろう。しかしこのような哲学者の奇石は決して社会自然の理において存在しない。今日 のわが清新爽快な日本の新天地においてなお旧分子が陰々裏に跋扈(ばっこ)しているのも理由 のないことではない。東方に日が出てなお燈を点じ、天下公衆に向かって妄言を吹聴する者は論 ずるに足らないが、天下の広居に立ち、改進の音頭を取らねばならない人が、なお旧い日本に支 配されているのはなぜだろう。 今日、政治社会を支配する主な精神は何物か。封建の遺習ではないか。つまり土地偏着の割拠 主義ではないか。封建社会は忽然として倒れた。我々はただ記憶の世界に向かってこの事実を確 かめることが出来る。しかし封建社会の精神は依然として山のように屹立しているではないか。今日 なお封建割拠の結合のほかには政治上の結合を見ることができない。封建勲閥のほかに真正の政 治上の権勢を見ることが出来ない。封建感情のほかに真正の政治上の感情を見ることが出来ない。 今の権威ある政治家の脳中には、不幸にも日本全体の社会と国民を網羅する思想が欠乏しており、 一地方一団結の勢力をもって天下を支配するような思想が多い。まことに嘆かわしいことだ。 91 官吏に登用されることにこれほど価値のある国は、世界にない。朝野の差別はまるで極楽と地獄 の相違だ。九天の上、九地の下、その差異は千万里を超える。どんな人物でもひとたび官吏にな れば、あたかも竜門に上ったように、意気揚々、大きな顔をする。世人が官吏に接する時は生き神 に仕えるように、慇懃(いんぎん)に恭しく頭を下げる。昔ローマの英雄シーザーがスペインの知事 に任ぜられたとき、「ローマにおいて第二流の人物であるより、むしろスペインにおいて第一流の人 物でありたい」といった。もし私が今日のありさまを評するなら、「イギリスにおいてグラッドストンにな るより、日本において書記官になりたい」という。思うに世界万国いずれを取っても、日本の官吏市 場のような好景気を有する国はない。したがって、民間に学士・事業家・率先者が少ないのは不思 議でない。能力ある者が民間に足をとどめようとしても、決して能力を発揮する余地がないからだ。 民間の境遇は天下有為の人士を追って、ことごとく政府の範囲内に入れてしまった。私は信ずる。 民間の人々の位地、境遇を政府の官吏と同等同地位にしなければ、決して官途熱望者を一変して、 民間の事業家に育てることはできないと。しかしこの弊習も偶然ではない。封建時代の遺物なので ある。 眼を転じて現今の経済世界を観察すれば、いまだかつて独立独行、政治社会の牽制を超脱した 純粋な経済活動は行われていない。たとえば日本銀行の貨幣市場における、日本鉄道会社の鉄 道事業における、日本郵船会社の航海事業における、事業としては頭角を表わしているが、要する にみな政府の余力により、政府の余光を借りて繁栄を装っているに過ぎない。その他、この二十年 間、国民の耳目に輝かしい土木築造、採鉱、あるいは農工商の改良、これみな明治政府の事業で ある。民間の有志者がたまたま独立の営業を始めれば、多くは途中で種々の口実を設け、政府の 保護を仰ぎ、その干渉を好んで迎えるありさまだ。かの三府五港はもちろん、各都府において紳商 と称し、商業世界の会社を組織した人々を見よ。それら人々はいまだ一人として政府と密接な関係 を持たない人があろうか。その事業は一事として政府と縁故のない事業があろうか。私はいまだに その例を見ない。中古の歴史を見ると欧州の土地はことごとく封建君主の所有であった。たまたま 自由所有主があれば、それを封建君主に献じ、その臣民として借地したのだ。今や日本の経済世 界はこれに似ている。もし人が私に向かって今日の有名なわが国の紳商は封建時代の官吏の一 92 部でもあった御用達とどれだけ相違があるかと問えば、私は相違点を挙げるのに苦しむ。 政治においても、経済上においても、媚(こび)を示し、へつらいを言い、自分で幇間(ほうかん)と 認める者は、深く責める必要もないが、朋友とも味方とも思い、頼もしい人々と信ずる自由の弁護者、 民権の率先者、天下の志士と任じ悲憤慷慨(ひふんこうがい)やむことのない正義諸君子の挙動に は、敬服できないものがある。 これらの諸君子は純粋な急進自由の率先者だから、政治上の意見・議論・運動・行為は徹底的 に自由主義に始終することが、志士の真面目である。退いてその内面を省みると、なるほど自由主 義は自由主義に相違ないとしても、日本の一種特別の自由主義である。江南の橘(たちばな)も江 北に移せば枳殻(からたち)になるという諺(ことわざ)どおり、アングロサクソンの自由主義も日本に 移せばその性質を一変し、日本流もしくは封建的な自由主義といわざるを得ない変化をする。それ は、かの諸君子が平生は単純な自由民権の主義を論弁するにもかかわらず、隣国に事あればたち まち「なぜすみやかに長白山頭の雲を踏み破って四百余州を蹂躙(じゅうりん)しないか」などという。 外戦をひとたび開けば、政府の権力はいよいよ増大する。政府の権力がいよいよ増大すれば、人 民の権力はいよいよ減退せざるを得ない。武備機関がいよいよ膨脹すれば、生産機関はいよいよ 収縮せざるを得ない。常備軍の威勢が飛んで天を圧するとき、人民の権利は舞って地に落ちる。か の諸君子はこういうことを思うのか思わないのか。人民の利害安寧を児戯と見なし、ただただ開戦 論を主張するばかりか、実行に移すため義援金を募り、従軍を志願し、あるいは激烈粗暴な檄文を 発し、過激で無謀な行動をする。絶えて自省することなく、かえって志士の本来と考えているのは、 おかしなことだ。そして傍観者も、これを排斥せず、かえって喝采し鼓舞する。不思議なことだ。 私はクエーカー宗徒でもなく、ウィリアム・ペン氏の考えに従うものでもない。だから事情を論ぜず、 場合を問わず、外戦をすべて否定するものではない。ただ、一国の正義と体面が平和の談判によ って確保できないという場合、万々やむをえない場合、つまり仁がすたれ義が尽きる場合に、初め て外戦に訴えるべきである。ゆえに私は、ナポレオンの侵略主義とワシントンの自由主義とは決して 両立しないと信ずる。しかしかの諸君子は平生ワシントンの自由主義を信奉するにもかかわらず、 事件が起こればナポレオンの戦争主義に転じ、一人で両様の人物を兼ねようとする。私はこれを実 93 に不可解に思う。 このように、平生自由の朋友と自任する諸君が豹変し、主義を複数にする。自由が口をきくなら、 天下に友は無いと泣くだろう。日本では自由主義がいまだ真価を発揮せず、全社会を挙げて全国 津々浦々を自由の帝国とし、全人民を挙げて自由の人民とするに至っていない。自由主義の率先 者も、隠秘な脳中は依然として封建の頑民に過ぎない。 今日本に流行する国権論、武備拡張主義も、要するに新奇な道理の外套を被ってはいるが、み な陳腐な封建社会の旧主義の変相に過ぎない。政治の問題は事実の問題である。政治上の経験 は、化学家が元素の試験をするような、容易で廉価な経験ではない。世上往々政治を一つの愛玩 物とし、その経験を煙火のように愉快なものとし、その問題を詩人の花鳥風月、小説家の人情の変 態と同一に思い、滑稽な変化を放言高論して、愚妄無識の人民をたぶらかす者もある。私は国家 のために非常に残念に思う。 黒竜江上の朔風に旗を翻し、呉山の第一峰に馬を立て、自分をアレキサンダー大帝、チムールと 任ずるのは、愉快は愉快だが、はたしてこのような壮図、雄略は実行できるものかどうか。論者は本 当にこれを実行出来ると思っているのだろうか。もし実行できないと知りながら大言を発しているなら、 人を欺き、天を欺きかつ自からを欺くものだ。真に実行しようとおもっているのなら、いかに無謀な匹 夫、黒旋風李逵(りき)でもその無謀には驚くだろう。論者は梁山泊の世界を求めて向かうべきであ ろう。記憶せよ、今日は十九世紀の文明自由の世界であることを。 昔、武骨な武士がいた。かつて『曽我物語』を読み、曽我兄弟が父の仇(かたき)をうった痛快な 段にくると、膝を叩いて「ああ一度は父の仇をうってみたいな」と思う。ある論者もこの類である。実際 に行なえないことを思い、実際に行なってはならないことを口にするのは、詩人・小説家の役割だ。 政治上の世界は広大無辺ではあるが、このような奇怪な妄想説の実行は許されない。また一種の 論者は「今日では内に一尺の民権を伸ばすより、外に一寸の国権を広めるべきだ。武がなければ 国は立たない。兵がなければ国を保てない。今は優勝劣敗の世界なのだ」という。しかし国家の目 的はどこにあるか。国家はなんのために組織されるか。リーバー、ウールジー、ミル、スペンサー、 誰一人として国家の目的は個人を保護するにあると説かない者はない。私は決して政治学の講義 94 をするつもりはない。論者が少しみずから省察すればよいのだ。いかに国権を拡張し、外国を侵略 したとしても、人民の権利を侵害すれば、国家の目的はどこにあるか。古来より世の圧制君主が民 権を抑圧するために国権拡張に従事した例は数多い。論者はこのような例を喜ぶのか。論者はナ ポレオン第三世のような人を帝王と仰ぐのが本望なのか。つまり圧制残忍なヨーロッパの、籠絡の 巧みな帝王の臣民となりたいのか。今日の世界を周末秦初の七雄の時代と同視するのは、もっとも 迂遠皮相な見方といわざるをえない。もちろん私は今日を黄金の世界とは思わないが、睡眠の社 会とも信じない。優勝劣敗の大法則は、昔時のように、いや昔日より一層快活・周密に行なわれるこ とを信ずる。しかし優勝劣敗なるものは、ただ兵力の多小によるものではない。文明社会がまだ出 来ず、文明の利器が社会に出て来ないときには、優勝劣敗はただ簡単な腕力の一作用で判断で きたが、今日文明の利器が燦然として社会を支配するときには、腕力も一分子に相違ないとしても、 これを唯一の分子とも、重要な分子とも思えない。むしろ富と知力とがもっとも恐るべき、もっとも勢 力ある分子だと信ずる。すなわち優勝劣敗の大法則は、野蛮で貧乏な国体や人種をすべて呑滅し、 文明にして富める国の餌食にすると信ずる。ゆえに日本の国権の不振を嘆き、国威の揚がらない のを嘆き、独立は長くないと嘆ずる者は、ただ一つ、遅疑なく日本を文明かつ豊かな富の国としな ければならない。 ある論者は言う。「国は富まなければならない。兵も強くしなければならない。富国強兵は決して 分離できない。この二者はつねに相伴い、いまだかつて一日も乖離したことはない。わが国も公平、 一様に両者を伸ばさなければならない。両者の軽重・前後・緩急を論ずる必要はない」と。この論は 穏当、着実な感じがして俗人を惑わすが、静かに考えると一種の詭弁である。国が富めば兵を強く できる。なぜなら、たとえ過多な常備軍がなくても、その国の人民は独立自治、国家と個人の自由 のために戦うだろう。武器も精緻な妙品を整えるだろう。しかし逆に兵が強ければ国を富ますことが できるだろうか。今日の世界は富により兵を支配できるが、兵により富を支配する世界ではない。も し論者の言うように、富は兵を支配するゆえに兵もまた富を支配するというなら、世界は山を含むゆ えに山を指してこれが世界だというようなものだ。犬は動物だから動物は犬、人も、猫も、鼠もまた犬 なりといえるだろうか。世にこんな奇怪な論法はない。武備と生産の二主義は決して両立するもの 95 でないと、私は繰り返し述べた。だが論者は、一方において冗官を廃し不急の土木を止め、地税を 減らせと、かの舜が歴山の野に鋤を持ってたたずみ、天に向かって号泣したように嘆訴するが、一 方では陸海軍を拡張せよと勧告するのはなぜか。陸海軍を何によって拡張するかといえば、租税 を増加するほかない。一方で増加を促し、一方では減少を促す。たとえ政府の諸公が神通自在の 大能力を持っていても、出来ることではない。東去西来の二舟がともに順風に乗ることは、全知全 能の神にも不可能だろう。論者は誤っている。 あるいは言う。「一国の光栄を維持するには兵備に依らざるを得ない。雄大精細な兵備を持つの は、ただちに外国に向かって開戦を挑むためではない。また一国の独立に差支えがあるからでもな い。ただ数百の兵営を国中に設け、三里の城、七里の郭、飛ぶ鳥も越えることができない堅固な砦 (とりで)を築き、砲台を設け、数十艘の甲鉄艦が旭日の旗を五大州各地の港湾に翻がえすためで ある。世界万邦に向かってわが日本を知らせ、わが日本を侮(あなど)れない国と知らせ、わが日本 を尊敬せよと知らせるのは、愉快ではないか」と。私もそれを愉快と思わないではない。しかし論者 の言うように、兵備を一つの驕奢品とするなら、私は容易にその論に賛成できない。驕奢品は必要 品の需用を満たしたのちに作るべきだ。茅屋に住んで大門高塀を作る者はいない。飢餓に瀕して 肉・葡萄酒を買う者はない。一国の生活すら満足に維持できずに国威を輝かし、外人の尊敬を博 すのは不可能だ。まして武備を驕奢品と考えるなら、もっとも無駄な乱費を費やした代物ではない か。驕奢品は必要品ののちに作り、高価な驕奢品は安価な驕奢品ののちに作るのは経済的自然 の順序である。論者は法外にもこれを転倒しようというのか。「武士は食わねど高楊枝」とは封建武 士の気風をうがつ諺だが、論者は日本を貧乏武士にしようとするのか。ああ論者もまた封建武士の 子孫なのだ。 要するに今日のわが国は実に新旧日本の戦場である。政治・宗教・文学・教育・学問・生活・感 情・思想などすべての面で衝突している。国の立場で観察しても、一国の戦争はつねに新旧二主 義の戦争である。一地方の立場で観察し、これを一家の立場で観察し、一身の立場で観察しても、 みな同じである。二つの主義の戦争は、ペルシア古代の神学者の解説のように、二つの敵対する 神が広大に広がり、巨大な物体のうえにも、細密な極微分子のうちにも、ともに存在し、ともに触れ 96 合い、ともに戦うのだ。とすればこの戦争の終局はどんなものか。 武備主義と貴族社会により我が国の生活を保ち、万国と対立するなら、日本の固有なしかも得意 な軍隊組織を転覆する必要はなかった。維新の大改革は不要であった。世界の形勢を洞察し、武 備主義を一変して生産主義とし、貴族社会を一変して平民社会とする端緒を開く必要はなかった。 今日の復古論者が言うように素晴らしい維新の功業はどこへ行ってしまったのか。私はかつて維新 の際の幕府の参謀原仲寧(ちゅうねい)の言を聴き、実に思いを新たにする。 「私が上京してから三年がたつ。変化は百出。ほとんど人力のよくするところではない。病床に臥 して深くその理由を考えると、天地の間には自然の大勢があることを始めて知る。人間の知らない 間に循環し、潜航、黙移つねに人意の外に表われる。その時に処し、その局に当たり、人知に及ば ないもの、知っても制御出来ないものがある。当然俗士とともに談ずることが出来ない。天は末永く 喜びを与えてくれたのである。」 天下の大勢は、幕府がまだ倒れず、封建社会がその勢力を維持し、鎖国の堤防がなお存在した ときですら、知り得なかったこと、あるいは知っていても制御できなかったものがあったのだ。しかも 今や天破れ、地驚き、洪水は天に漲(みなぎ)り、山となく、川となく、城となく、市となく舞い狂う今 日、この世界の大勢に抵抗できるだろうか。 世界の気運は躍動してやまないものだ。天下の大勢は光陰の潮流とともに動いてやまないものだ。 ゆえに二十年前日本を刺激した天下の大勢は、今日はさらに倍の勢力で刺激している。二十年前 維持できなかった武備主義・貴族社会は、今日さらに一層維持できなくなっている。上流でせき止 めることが出来ない水勢は下流ではなおさらせき止められない。二十年前の大勢はそのまま今日 の大勢だ。二十年前の困難はそのまま今日の困難だ。昔日の改革の時代は今日でも続いている。 にもかかわらず、わが国の人士は小成に安んじ、小庸に馴染み、事業は終わった、余生は天も許 すだろう、楽しむに限ると謡う者もある。しかし彼の脳中の魔鬼は跳梁し、復古の事業を行なおうと 暗躍しているのだ。ああ日本人よ満足するなかれ。改革の事業はまだ半分も成就していない。旧日 本はすでに去ったと思うなかれ。今日の社会を支配する重要な部分は、すべてこれ旧日本の分子 である。もしこれを疑うなら、どうかあなたの脳中の魔鬼に問うてみよ。 97 第十六回 将来の日本(結論) 私が将来の日本を論ずるのはやむをえない必然である。私は現今の日本社会のありさまを観察 して、これを論ずる必要を感じた。日本の将来はどうあるべきか。どうするべきか。どうなってはいけ ないか。将来の日本はもとより多事ではあるが、第一の急務は一国の生活を維持することだと述べ た。そしてその生活の手段はいくつもあろうが、要するに武備、生産の二主義にあると述べ、その手 段の相違は一国の気風・品格・制度・文物・政治・経済・教育・文明等に大いに関係があると述べた。 次に私は一歩を進め、わが国の生活は何の主義により維持すべきかの問題を解説しようとした。私 は速断せず、まずこれを世界の境遇を質(ただ)した。そして世界の境遇は実に生産主義であると 発見した。ついでこれを天下の大勢に質したところ、天下の大勢は実に平民主義であると発見した。 私はさらに眼孔をわが国に転じて観察したところ、わが国の現今の境遇はもっとも生産的な境遇に 適し、わが国の現今の形勢はもっとも平民主義が大勢であると発見した。つまりわが国の現今の状 勢はこれらの境遇勢力の重囲のうちにあることを発見した。こうしてわが国の将来を予測する材料 は完備した。私はこの材料を詳しく考究したのはもっとも公明正大であったと信ずる。この材料によ りわが国の将来を占ったのは、決して妄想迷説ではないと信ずる。 ではわが国の将来はいかになるべきか。私は断言する、生産国となるべしと。生産機関の発達す る必然の理に従い、自然の結果として平民社会となるべしと。私はたとえ日本国民が一挙手・一投 足の労を取らなくても、現今の洪水はわが国を駆り立ててここに向かわせると信ずる。たとえ剣を振 るい、矛を突いてこの洪水に対抗しようとしても、洪水の勢いは一層激しい力で襲ってくると信ずる。 自然の勢いには適度がなく、忠実な味方も、憎い敵も、みな大流の中に呑みこみ、あらゆるものを その目的を達する利器としてしまう。イギリスの革命を成し遂げた者はミルトン、ハンプデン、ピムな どばかりではない。チャールス王自身が最大の張本人であった。維新の改革を煽動した者は佐久 間・吉田・西郷などばかりではない。あの井伊大老も、また一人の発起者といわざるをえない。運動 を助ける者もこの勢いのために制せられて一つの利器となり、抗する者もこの勢いのために制せら 98 れて一つの利器となった。人力ではどうすることも出来ないと知れば、どうすることも出来ないことを 最良の手段としなければならないのだ。 将来の日本はこの自然の大勢に従い、これを善導する他に方法はない。故人は言った。「達人の 知は明らかだ。すべて天地の勢に従う」と。そのとおりで、ただ天地の勢いに従うほかはない。 私はもとより世の一書生に過ぎず、天下の何人に向かって何の求めることなく、何の不平もない。 何を苦しみ好んで、悲奮慷慨、洛陽の少年に倣うことがあろうか。私は世間の流れに従って諸公と ともに中興の天地を喜び、その恩沢に浴する安楽を知ってはいる。また、朝変暮改、雲が漂い風が 吹くように、ただ世情に媚び世論に雷同する安逸を知ってはいる。剣によって千里を横行し、その 主義の邪正を問わず、その手段の善悪を論ぜず、むやみに剣を振う快活さを知ってはいる。世に 容れられるためには他人の思うように思い、他人の言うように言い、他人の行なうように行なうのが 得策だと知ってはいる。しかし私は天を欺(あざむ)き、人を欺き、かつ自分を欺くことは好まない。 たとえ自分を欺こうとしても、愛国心を抱く一方の私が、先輩に対し内心に恥じるであろう。これが私 が不肖を顧みず、筆を持ち紙を重ねて意見を述べた理由である。 ブライト氏が言うには、「私は信ずる。徳義の基礎によって立つのでなければ、国民の永久不滅 な隆盛繁栄は決して望めない、と。私は強大な武備には全く関心がない。私が意を注ぎ、つねに忘 れることができないのは、私がともに生活する国民の境遇である。思うに大英国において、私のよう に帝冠および王政を不敬の言葉で語る者はいないであろう。しかし国民多数の愉快・満足・幸福の 公平な分配がなければ、輝く金冠・勲章も、強大な武備も、広大な植民地も、雄大な帝国も、私の 眼中には一本の剛毛に過ぎない。立派な宮殿・楼閣・城・公堂・会館も、国民とは関係がない。国 民というものは、いかなる国においても茅屋のうちに住むものだ。ゆえにもし国の憲法の恩光がこの 茅屋のうちに輝き、立法の美、卓絶な政治がこの茅屋のうちに住む人民の感情と境遇に適合しな いなら、一本の毫毛にも及ばない。」 私の考えは上記のとおりだ。私は皇室の尊栄と安寧が保たれ、国家が隆盛であり、政府が強力で あることを望む。これを望む至情は天下の人士に遅れないと信ずる。しかし国民というものは茅屋の うちに住むものであり、この国民が安寧と自由と幸福を欠くときは、国家は一日も存在することがで 99 きないと信ずる。茅屋のうちに住む国民にこの恩沢を与えるには、わが社会を生産的な社会とし、 その必然の結果として平民的な社会にしなければならないと信ずる。つまり、わが国が平和主義を 採り、商業国となり平民国となれば、わが国家の存在を保ち、皇室の尊栄も、国家の威勢も、強固 な政府も、将来の豊かな社会も維持することができる。国家の将来の大経綸は、ただこの一手段を 実践するにあると信ずる。余がこう信ずるからには、黙っていることはできない。たとえ世間が私に罪 を着せようとしても、私は甘んじてその罪を受ける。なぜなら私の心事は、早晩必ず天下に白日のも とに認められる時が来ると信ずるからだ。ただ恐れることは、もしわが国が世界の大勢に従うことを 遅らせば、かの青い目の人種が波濤のようにわが国に侵入し、日本国民を海島に駆逐し、国土に はアリアン人種の一大商業国の平民社会を見るかもしれない。これを防ぐには、願わくは神速雄断、 維新大改革の猛勢を百尺竿頭の外に一転せよ。欧米人の出来ることが出来なければ、欧米人は 日本人に代ってするだろう。このときになって苦言痛語を発しても遅いのである。 100
© Copyright 2026