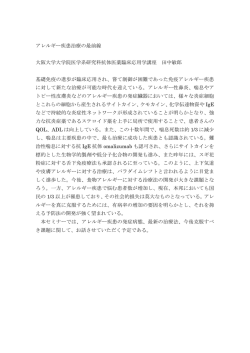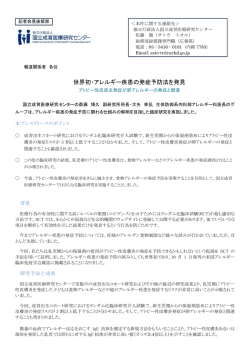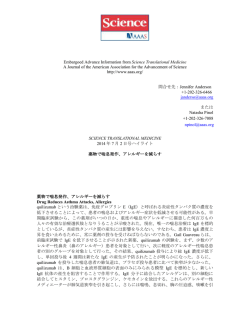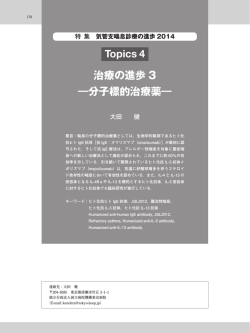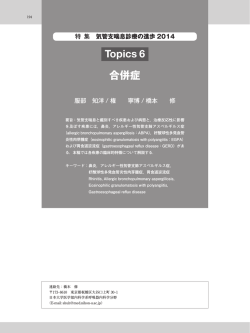巻頭言アレルギー疾患考 石田 央
1 アレルギー疾患考 石 最近の学校保健の動向をみると明らかに児童・ 生徒の疾病構造は変化して来ている。公衆衛生の 向上によって寄生虫、細菌、ウイルスなどの感染 症は激減した。しかし反比例するように花粉症、 喘息、アレルギー、自己免疫疾患、発達障害など 新たな疾病が増加して来ている。発達障害に見ら れるように昔から存在していたとも思われるが新 しい概念の発見により注目されて来た疾患もあ る。寄生虫疾患とアレルギー疾患のように、一方 の減少と他方の増加があたかも関連しているよう にも見える疾患もある。アレルギー疾患は学校保 健では最も重要な疾患に成りつつある。世界的に は国や地域別に差はあるものの、アレルギー疾患 や喘息の流行が始まったのは1960年代のことであ り、その後この流れは1980年代に加速し、2000年 代前半にピークに達して以来そのままの状態が続 いている。我が国でも同様の傾向が見られる。一 方寄生虫疾患は東京都予防医学協会の報告による と、東京都内の児童・生徒の糞便検査法(鞭虫、 回虫、横川吸虫、鈎虫等)での寄生率は1948年 72%であったものが次第に減り続け1970年代には 0~ 0.2%で推移し、ついに2003年糞便法は一定 の成果が見られたとして終了している。ピンテー プ法による蟯虫卵検査もその寄生率は1956年の 35.3%をピークに2011年には0.2%となっている。 一方アレルギー疾患に対してはその有病率を経年 的に追跡したものは少ないが、 西日本疫学調査 (11 県の小学児童の疫学調査)では気管支喘息、アト ピー性皮膚炎、アレルギー性鼻炎、アレルギー性 結膜炎、スギ花粉症の合計有病率は22.98%(1992 年)、24.52%(2002年) 、30.28%(2012年)と増 加傾向を示している。寄生虫疾患の有病率の低下 とアレルギー疾患の増加の間に何らかの相関があ るのであろうか?関係説と無関係説が存在し、公 衆衛生学的にも免疫学的にも数十年来の論争と なっている。関係有りとする説は「衛生仮説」と 呼ばれ、 「自己免疫疾患の発症率が先進工業国で 田 央 増加しているのは小児期の感染症の低下による」 という説である。これを支持するものとして、 2004年ドイツ医科学チームの乳幼児期におけるエ ンドトキシンの曝露量が以後の花粉症や喘息の発 症に密接に関係しているとの報告やその他の傍 証、著書、TV 放送も存在する。例をあげれば「寄 生虫無き病(モイセズ・ベラスケス・マノフ著、 赤根洋子訳、文芸春秋) 、 「原始人健康学(藤田絋 一郞著、新潮選書) 」などである。その中で藤田 は自らがインドネシアのブル島に赴き調査した結 果、住民のほぼ100%に回虫卵が発見され、鞭虫 (90%以上) 、鉤虫(60%以上)の卵も高率に発 見された事、アトピー性皮膚炎、喘息、花粉症、 結膜炎などアレルギー疾患に罹患している者は皆 無に近かった事、さらに住民の血清 IgE 抗体が いずれも高値を示した事を報告している。旧東ド イツの子どもと西ドイツの子どもを比べた場合、 東ドイツの子どもにはアレルギー疾患が少なく、 高血清 IgE 抗体を示したとの報告もある(IgE 抗 体が高いのにアレルギー疾患が少ないという結果 の解釈は専門書に譲る) 。この他自らを鉤虫に感 染させ、その結果花粉症が治ったという報告や南 米アマゾンのジャングルに住む寄生虫だらけのチ マネ族という部族には自己免疫疾患やアレルギー 疾患は存在しないという報告など数々の傍証が報 告されている。一方において我が国でブタ回虫の 幼虫移行症が多発した際、感染群ではスギ花粉症 に対して2倍、アレルギー性鼻炎に対して3倍の 頻度で有病率、IgE 抗体の保有率が高かったと言 う報告もある。このようにみてくると、寄生虫感 染がアレルギー疾患を直接抑制するという話はい ささか乱暴の感も否定できない。もし 「衛生仮説」 が真実とすれば、 「不潔が清潔に勝る」という公 衆衛生学上の一種のパラダイムシフトともいえる のである。 (県医理事) 新潟県医師会報 H26.12 № 777
© Copyright 2026