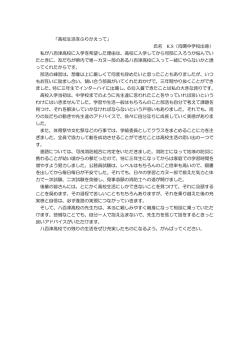邪神に転生したら配下の魔王軍がさっそく滅亡し
邪神に転生したら配下の魔王軍がさっそく滅亡しそうなんだが、どうすればいいんだろうか 蝉川夏哉/逢坂十七年蝉 タテ書き小説ネット Byヒナプロジェクト http://pdfnovels.net/ 注意事項 このPDFファイルは﹁小説家になろう﹂で掲載中の小説を﹁タ テ書き小説ネット﹂のシステムが自動的にPDF化させたものです。 この小説の著作権は小説の作者にあります。そのため、作者また は﹁小説家になろう﹂および﹁タテ書き小説ネット﹂を運営するヒ ナプロジェクトに無断でこのPDFファイル及び小説を、引用の範 囲を超える形で転載、改変、再配布、販売することを一切禁止致し ます。小説の紹介や個人用途での印刷および保存はご自由にどうぞ。 ︻小説タイトル︼ 邪神に転生したら配下の魔王軍がさっそく滅亡しそうなんだが、 どうすればいいんだろうか ︻Nコード︼ N6415BC ︻作者名︼ 蝉川夏哉/逢坂十七年蝉 ︻あらすじ︼ 牡蠣にあたって死んだ平乃凡太は生前の徳不足で天国に入れない。 しょうがないんで徳を前借りして異世界で邪神として転生させて貰 うことになるのだが、転生した先がこれまた難儀なところで⋮⋮ ︵2012年9月5日前後に、作品の一部をダイジェスト化しまし た︶ 1 第1章ダイジェスト版︵前書き︶ ※書籍化に伴い、ダイジェストにてお送りいたします。 2 第1章ダイジェスト版 牡蠣、という食べ物がある。 海のミルクとも言われる濃厚な味わいのそれは滋味豊かで、煮て も焼いてもフライにしても旨い。 だが一番の食べ方といえば、何と言っても“生”だ。 世の中の多くの人は勘違いしているが、スーパーで販売している “生食用”の牡蠣は“加熱用”の牡蠣よりも新鮮だというわけでは ない。生でも食べられるように体内にある毒素を排出させる為、長 時間断食させた牡蠣なのだ。痩せた“生食用”とありのままの“加 熱用”。どちらが旨いかは、考えるまでもない。 という話がまことしやかに流れると、当たり前のように“加熱用 ”を生で食べる人間が現れる。生で食ったら危険だから、“加熱用 ”と書いてあるのにわざわざ生で食うのだ。 当然、あたる。最悪の場合、死に到る。 そんな阿呆は滅多にはいないが、稀にいる。 つまり、俺のことだ。 ○ ﹁あなた、このままじゃ地獄に堕ちますねぇ﹂ ねっとりとした口調で目の前のオバサンが指摘する。 ここは“あの世”だ。 正確に言うと“あの世の入り口”らしいが、死後の世界であるこ とに変わりはない。 三途の川も何もなく、あるのは雲を突く超巨大な閉じた扉と前に 3 並ぶ役所群、そしてその門前町だけだ。何とも味気のないところで あるが、まぁこれがあの世というならあの世なんだろう。 そのあの世の入り口で俺が何をしているかと言えば、転入手続き なのだ。 ﹁⋮⋮そこを何とか、まかりませんかね?﹂ ﹁さっきから何度も説明してるでしょう、平乃凡太さん? あなた の考課だと、逆立ちしたって天国には潜り込めないんですよ﹂ 言いながら手にしたA4一枚の考課表とやらをばしばしと叩く。 これに生前一切の徳と不徳が記されているというのだから驚きだ。 ﹁﹃無実のカエルを爆竹で爆死させた罪﹄、﹃想いを寄せられてい ることに気付いていたにも拘らず相手の面相が気に入らないという 理由で手酷くイタズラした罪﹄、﹃ジャパニーズレストランで生け 簀から鯖を出して〆させたのに結局一口も食べなかった罪﹄⋮⋮﹂ 何とも情けない行状が次々と挙げられていく。 このオバサンと向かい合っているのは役所の相談コーナーみたい に隣とはパーテーションで区切られているだけなので、恐らく丸聞 こえだろう。随分と恥ずかしい。 ﹁観念して、転生したらどうですか?﹂ ﹁でも、せっかく死んだんだしなぁ⋮⋮﹂ 正直なところ、この二十四年間はあまり楽しい人生ではなかった。 現世への未練も読み続けていた週刊漫画の続きが気になることく らいしかない。それならばもう、ここでゴネて天国に潜り込んでし まおうという肚だったのだが、どうにも認められないらしい。 4 ﹁仮に転生するとして、どんなのがあるんです? 出来れば、日本 で﹂ ﹁日本で、ですか⋮⋮﹂ ﹁はい。続きが気になる漫画とかあるんで。出来れば社長の息子と か﹂ ﹁そうですねぇ、この考課で日本となりますと⋮⋮ ヤンバルホオ ヒゲコウモリですとか、オオダイガハラサンショウウオとかウジヒ メセトトビケラとかになりますね﹂ ﹁えーっと、何ですって?﹂ ﹁ヤンバルホオヒゲコウモリ、オオダイガハラサンショウウオ、ウ ジヒメセトトビケラですね﹂ ﹁人間ですらない?﹂ ﹁ヤンバルホオヒゲコウモリは哺乳類ですよ?﹂ 想像は俺の予想を遥かに下回っている。これは、非常にマズい。 転生するのがどれもレッドデータブックに載ってそうなマイナー 生き物というのも辛い。 転生したは良い物の、童貞で一生を終えるのがほぼ確定ではない か。 ﹁えっと、日本に限らなければどうなります?﹂ ﹁日本に限らなければ、ということは地球にも拘りませんか?﹂ ﹁え?﹂ ﹁地球外にも範囲を広げます?﹂ このオバサンは何を言っているんだろう、と思った所ではたと気 が付いた。地球外にも生き物がいるのなら、その魂もここに来るの だろう。なるほど、一つ賢くなった。 5 ﹁地球外でも異次元でも異世界でも、何でもいいです。ちょっとで も条件が良ければ﹂ ﹁あら、そうならそうと言ってくれればいいのに。ちょうどいい物 件があるんですよ﹂ ﹁ちょうどいい物件?﹂ ﹁ええ、異世界の邪神に一柱、空きが出てましてね﹂ ○ 風が、吹いている。 <廃太子>ドラクゥは馬上から自分の押し込められた大地を見つ めた。 長い黒髪に鮮血のように紅い瞳。そして、乳白色の一本角。 この魔界に一〇八人いる魔王の一人である。 武略、智略共に秀でた自分がこんな辺境に半ば追放されたことが、 未だに信じられない。 辺境。 正に、辺境であった。 大地は森林に深く覆われ、大海に浮かぶ島のように峻険な山が生 えている。 魔物は凶暴で、文明の痕跡は少ない。 ︵⋮⋮こんな処に︶ こんな処に、放逐された。 原因は負け戦だった。 近年勢力を増した<北の覇王>ことザーディシュの軍に敗れたの だ。たった一度の敗北だったが、ドラクゥはそれで全てを失った。 自分には、運がなかったのだ。そう言い聞かせる。 6 運とはつまり、邪神の加護であった。 ドラクゥは、生まれてこの方、邪神を信じたりはしていない。 邪神に縋るなど、弱き者のすることだと唾棄してきた。 それが、こんな風に弱気になるとは。 ︵つまり余も、弱き者の仲間入りということか︶ そう思えば自然と笑いがこみ上げてくる。自嘲だ。 ︵そうだ、いっそ余だけの邪神を想ってはどうだろうか︶ 自分だけの邪神。 縋る為の神ではなく、ただ祈る為だけの神。 強くなくても良い。自分と共に在る邪神だ。 そういう信仰の形が、在っても良いだろう。 ドラクゥは、目を閉じた。 邪神に捧げる祈りなど、片句も知らない。 ただ、我流で祈りを捧げてみる。 ︵邪神よ、邪神よ、余だけの邪神よ。願わくば、余と共に⋮⋮︶ その時、ドラクゥの背後で大きな爆発音がした。 ドラクゥが振り返ると、そこには。 ○ ﹁あいたたた⋮⋮﹂ いきなり落っことされて俺は盛大に尻餅をついた。 転生、というにはいささか乱暴である。記憶も見た目もそのまま だし。 あるのは神様としてちょっとした奇跡を起こす力と⋮⋮ 借金だ。 7 邪神になるまでは良かったのだが、実は転生する為の徳すら足り なかったので前借したのだ。 邪神として勤め上げて晴れて天国でぐうたら生活を送る為には、 邪神として信仰を集め、借金を完済してさらに天国に入るのに必要 なだけの徳を集めなければならない。 その額合計してざっと五億六千万カルマ。現代日本人の平均生涯 所“徳”が二億七千万カルマというから、およそ人生二回分である。 どうやったら効果的に徳が貯まる、とか、そういう話は教えて貰 えなかった。 とにかく信仰を集めていけば何とかなるに違いない。俺の勘がそ う言っている。 自慢ではないが、RPGでもシミュレーションでも取扱説明書を 読む前にプレイする男だ。行き詰ってから読む為の取扱説明書もな い世界だが、その辺は先輩邪神か何かをつかまえて聞いて行けばい い。 転生していきなり、﹁○○の奇跡を使うには200カルマを消費 して∼﹂だの、﹁効果的にカルマを貯めるにはヨイドレ沼の奥地に 棲むレッサードラゴンを倒さねばならない﹂とか﹁神様にもランク があって、最初はブロンズからはじまり∼﹂みたいな話で頭を一杯 にしたくないのだ。 邪神ライフをエンジョイしつつ、軽くゆるーくカルマを貯めるの がこの人生での大目標だ。 なに、邪“神”というくらいだから、それくらいなんとかなるだ ろう。 そんなことを考えながら腰をさすっていると、こちらを覗きこん でいるドえらい美男子と目があった。 8 ﹁⋮⋮貴方さまが、私の崇めるべき邪神か?﹂ ○ ﹁⋮⋮貴方さまが、私の崇めるべき邪神か?﹂ 口に出してから、ドラクゥは恥じた。 邪神がその御姿を容易に現すはずがない。大方、この辺りに住ま う魔族だろう。 戦の経験も無さそうな、緊張感のない表情をしている。 邪神が世界に顕現することは決して有り得ない話ではない。 初代の大魔王に王杓を授けたのも邪神であったし、大森林の奥に は邪神が憩う湖もあるという。 しかし言い伝えられる邪神の姿は、名状し難きものや屈強な肉体 として知られている。 よもやこんなに弱そうな男が邪神であるはずがない。 ︵しかし、そう言えば、余が願ったのも強くない邪神であったか︶ とは言え、まさか邪神が。 ﹁あ、はい。はじめまして、邪神です﹂ ○ 言ってしまってから、しまったなと反省する。 邪神というものはもう少し殺伐としていないといけないのではな いだろうか。 何と言うかこう、“はらわたを喰い尽す”ようなアグレッシブさ が必要な気がする。 9 最初が肝心とも言うし、フレンドリーな邪神より、頼れる感じの 強面な邪神を演出した方が良い。 そこで俺は、敢えて言い直すことにした。 ﹁コホン。左様、我が、邪神だ﹂ すると目の前の黒髪の美男子はズボンが汚れるのも構わずに地面 に片膝をつけ、こちらに深々と礼をするではないか。目測で二メー トル近くあるイケメンにこういう風にされると、悪い気はしない。 いずこ ﹁知らぬことといえ失礼を。何処の邪神とは知らねども、まずは非 礼をお詫び申し上げます。私はこの辺土一帯を新たに任せられるこ ととなった魔王で、ライノンの子ドラクゥ。<廃太子>ドラクゥと 申す者にございます。以後、お見知りおきを﹂ おいおい、魔王か。やはり言い直して正解だった。 邪神が魔王に舐められてはイカン。ちゃんと跪いているというこ とは、とりあえずは成功だ。 しかしこういう場合、これからどうしたらいいのだろう。 時代劇みたいにやればいいのか? おもて ﹁うむ、面をあげよ﹂ ﹁はっ﹂ ﹁⋮⋮ところで一つ尋ねるが、ここは何処だ?﹂ ﹁ここ、にございますか? ここは魔界の西のはずれ、蛮王領の一 つ、<ジョナンの赤い森>にございます。邪神さまはこちらを治め ておられるのではないのですか?﹂ と、ドラクゥという名前のイケメンはこちらを不思議そうに見つ 10 める。 それもそうか。 邪神がどういうものかいまいちよく分かっていないけど、普通は 自分の治めている所とかに出てくるものなのか。 営業だって自分の担当する地域があるもんな。邪神にもそういう のがあるに違いない。 ﹁実は我は邪神としてまだ生まれついたばかりなのだ﹂ ﹁ほう、生まれついたばかりと。それならばその御姿にも得心いた しました。邪神も私や普通の魔族のように成長して行くものなので すね﹂ ﹁御姿?﹂ ﹁ええ、邪神としては、少し小さくていらっしゃる。私も邪神に御 目に掛かる栄に浴したのは初めてのことですが、伝承にある邪神が たは皆巨大だと聞いておりましたので﹂ む、しまったな。 実はあの世のオバサンにも﹁巨大化しなくていいの?﹂とか聞か れていたんだった。 素うどんみたいな“素転生”でも言語関係とかは邪神基本セット に入ってるらしいんだけど、“巨大化”だとか“闇の衣”とかそう いうのは別売りになっていて、それぞれカルマが要るみたいなのだ。 巨大化で四〇〇万カルマくらいだったと思うが、さっさと借金返 済したい俺としては見送りを決めたのだが。少々早計だったかもし れない。今にして思えば、五億も借金がある身で、四〇〇万くらい 屁でもないような気がしてくる。 前世で平乃凡太やってた頃に付き合いのあった印刷屋の親爺さん なんかも、一億ン千万の借金を拵えてからの方が夜遊びも派手にや ってたしな。意外と金銭感覚なんてこんなもんなんだろう。 11 ﹁うむ、実はそうなのだ。我も信仰を集めれば、次第に大きくなる だろう﹂ ﹁御意にございます﹂ ○ どうやら、邪神は邪神でも見習いのそれらしい。 言葉を交わしてみてドラクゥはこの無角の邪神のことをそう判断 した。 聞けば、まだ邪神として生まれついたばかりなのだという。 ︵それもそうだ。たった今、余が崇めようと想い定めた邪神なのだ から︶ 生まれたばかりの、邪神。 これはドラクゥにとっての瑞兆だ。 何も示すこともなく、ただ照覧する邪神。 それこそが、ドラクゥの求めたものだった。崇めるが、祈り、縋 らない。そういう関係を、この邪神となら築けるかもしれない。 ○ このドラクゥという俺の信者は何だかとっても忠実そうなんで安 心した。 “邪神”と来て“魔王”というくらいだから、おっかない奴が信 者第一号だったらどうしようかと不安だったけれど、このドラクゥ は良い奴だ。ちゃんと話は聞くし。 ここが魔界のはずれだ、っていうことはドラクゥの説明で分かっ た。 田舎だから、多分魔族も純朴だろう。いや、勘だけど。 カルマがどうやったら集まるかは知らないが、俺の優れたゲーマ 12 ーとしての勘は、邪神としての信仰を集めればいいんじゃないかと 囁いている。 この田舎をさっさとこのドラクゥが掌握し、俺が信仰を集めれば 後は寝て暮らせばいいだけという寸法になる。素晴らしきかな、俺 の人生設計。 ﹁ところでドラクゥよ、もう一つ尋ねたいのだが﹂ ﹁何なりと、邪神さま﹂ ﹁お主の率いる部下は、どれくらいの数がいるのだろうか﹂ 何と言っても魔王だからな。一万二万はいるだろう。十万とかい ると嬉しいな。 アイドルグループでも十万くらいはファンを動員するんだから、 魔王ならそれくらい配下がいても何もおかしい所は無い。 ﹁そうですね、今はざっと二〇〇と言ったところでしょうか﹂ ﹁二〇〇⋮⋮?﹂ ﹁はい、このドラクゥの率いる魔王軍は、戦闘員だけですと概ね二 〇〇になります﹂ 俺は、自分の中で何かがガラガラと音を立てて崩れるのを感じた。 ○ 二〇〇、二〇〇か。 俺はドラクゥから聞いた魔王軍の規模にちょっとがっかりしてい た。 魔王軍なのに、二〇〇。 高校の時のクラスが四〇人だったから、アレの五倍。 全員の顔と名前が一致するくらいしかいないじゃないか。慶永さ 13 ん、元気かな。 <廃太子>なんて格好のいい二つ名を持っているからにはもっと 強大な軍勢を持っているのかと思ったというのに。 三国志とか信長の野望をやりこんだこの俺に言わせて貰うと、二 〇〇なんて兵力では何も出来ない。 あのテルモピレーの戦いでも三〇〇人は兵士がいたのに。 二〇〇の戦力で一体どうしようというのか。 ﹁あの⋮⋮ 邪神さま、どうかなさいましたか?﹂ ○ ﹁うん? ああ、我を崇める魔王の麾下としてはいささか数が少な いように思えてな﹂ ドラクゥは密かに歯噛みした。 そうだ。少ない。精鋭はそのほとんどを<北の覇王>との戦いで 失い、今や手元にあるのは敗残兵だ。そうでなければ、武略にも智 略にも秀でた自分が邪神などを崇めてみようかという気など起こす はずがないのだ。 ﹁はい、邪神さま。先だって大きな戦がございまして。余の軍は敵 に敗れ、その数を大きく減じたのでございます。今この辺境の地に 在るのも、その負け戦の故にございまして﹂ ﹁なるほどな。ちなみに、敗れた相手と言うのはどの程度の兵力を 持っておったのか?﹂ ﹁およそ、二十四万﹂ ﹁二十⋮⋮ 四万か﹂ ﹁対する我が陣営は連合を組み、十九万﹂ 14 そう、十九万だ。ドラクゥの集めた戦力は、数の上では敵に五万 劣るとはいえ、地の利もある。 運さえあれば、負ける戦ではなかった。 ﹁それが、今や二〇〇か﹂ ﹁左様にございます﹂ ﹁⋮⋮厳しいな﹂ ﹁はい﹂ 何が厳しいな、だ。 邪神は邪神らしく祀られていればいい。戦は魔族の領分だ。照覧 し、運だけ与えさせしてくれれば何も文句は無いのだ。どうせ生ま れたばかりの邪神になど、大した期待はしていない。 ﹁なるほど、な﹂ ﹁邪神さまはなにも御心配めさるな。これでも私は武略においては 少々心得がありましてな。我が身くらいは守れます。二〇〇の兵も いずれは一〇倍にも増やして見せましょう﹂ ○ ﹁一〇倍?﹂ ﹁はい、一〇倍の二千もいれば、当面の安全は保たれます﹂ 二千か。二千、な。 でも相手が二十四万もいるとなると、二千ぽっちじゃどうにもな らんだろう。 どうしようもないくらいボロボロだった頃の劉備でももうちょっ と兵力持ってたんじゃないかな。 15 しかし、この世界ってどれくらいの文明レベルなんだろうか。 二十万からの戦力を動員できるとなると、中国だったら三国志の 赤壁の曹操くらい。日本だったら関ヶ原の両軍合わせても十六万五 千でちょっと足りない。ヨーロッパは詳しくないからなぁ。いずれ にせよ、それくらいを動員できる人口がいて、そいつらとその家族 を食わせるだけの食糧生産はあるんだろう。 その辺はおいおい調べるとして。 一つ気になることがある。 ﹁何か御不審な点でも?﹂ ﹁ああ、その二千で身を守ることが出来たとしても⋮⋮﹂ ﹁出来たとしても?﹂ ﹁⋮⋮天下を狙うにはどうかな、と思ってな﹂ ☆ 邪神として転生した平乃凡太。しかし、今のところ唯一の信者で ある魔王ドラクゥは、たった二〇〇の兵しか従えていなかった。 早速滅亡しそうな魔王軍だが、﹃三国志﹄や﹃信長の野望﹄が大 好きな平乃はこの状況を愉しんでさえいた。邪神として神界へ向か う平乃。 その頃一方、ドラクゥにはゴブリンの魔王、<千里眼>のベナン の魔手が忍び寄っていた⋮⋮ 16 第2章ダイジェスト版 雨は上がったが、代わりに霧が出てきた。 <廃太子>ドラクゥは兵をまとめ、街道脇の廃城で身体を休めて いる。 廃城と言っても、さほど大きくはない。ル・ガンの兵三〇〇を合 わせて五〇〇に膨れ上がった全ての戦力を収容することは出来なか った。それでも交代で夜露に濡れずに仮眠を取れる、ということの 意味は小さくはない。火にも、当たることが出来る。この城の元の 主は、薪の蓄えまでは持って行く余裕がなかったようだ。 ﹁邪神さま、先ほどは有難うございました﹂ 盆に見立てた皮盾に、供え物としてのパンと葡萄酒を乗せる。 給仕の役は、邪神官であるエリィナだ。 ル・ガンも呼んだのだが、兵たちと共に居たいということで席を 外している。邪神との対面に畏怖を感じているのかも知れなかった。 ﹁いや、我もドラクゥが的確に合わせてくれたので助かった﹂ 言いながら温めた葡萄酒を啜る邪神は、まるでそこらにいる魔人 のようにも見える。 黒髪に、黒い瞳。来ている服は異国風だが、そこからは邪神らし い威圧感は、無い。 それでもドラクゥがこの邪神を信じるつもりになったのは、彼の くつわ 邪神が行動として<廃太子>ドラクゥを助けてくれたからだ。これ は、魔族と邪神の関わりとしては異例と言っていい。 邪神は、与えるが同時に奪うものでもある。まるで轡を並べる戦 友のように、共に飯を食う邪神などドラクゥは聞いたことがなかっ 17 た。 ﹁さてエリィナ。汝の説明でおおよその状況は掴めたが、改めて整 理させて欲しい﹂ ﹁はい、邪神さま﹂ ○ 俺はエリィナという少女から教えて貰った情報を頭の中で整理し た。 このエリィナ、燃えるような赤い髪をポニーテールに束ねた少女 で、大人しい。さっきから話している限りでは、頭の回転もかなり 速い。俺が分かるところ、分からないところを即座に判断して、必 要なところには十分な説明と注釈を入れてくれる。 かなりざっくりした理解だが、今の状況を分かりやすくする方が 先決だ。 ﹁まず、今は戦乱の時代だ﹂ ドラクゥとエリィナが同時に頷く。本当の兄弟ではないらしいが、 こういう仕草はよく似ていた。 親同士が義兄弟だ、というだけでなく一緒に育ったのだろう。 ﹁そして、ドラクゥはその渦中にいる。理由は、魔王の中でも大魔 王の血を引いているから﹂ ﹁はい。先代大魔王陛下は、私の祖父に当たります﹂ ここまでは、いい。ここから先が少しややこしいのだ。 ﹁大魔王“家”の血を引く男子は、今のところ三人いる。<廃太子 18 >ドラクゥ、<法皇>リホルカン、そして<皇太子>レニス。この レニスを、<北の覇王>は擁立しようとしている﹂ 言っててこんがらがりそうになってきたが、つまり問題になるの はドラクゥとレニスの二人だけ。リホルカンとかいうドラクゥの叔 父さんはあまり話に絡んでこないらしい。 ﹁レニスは女系、つまり私の叔母の子に当たります。父親も大魔王 “家”の王統に連なっているが、血は薄い﹂ ﹁正統性で言えばドラクゥが勝る、ということか﹂ ﹁はい﹂ 絶対の権力者である大魔王が、後継を指名せずに死んだ。 そこで普通であれば直系であるドラクゥが跡を継ぐべきところを、 <北の覇王>ザーディシュが横槍を入れてきた。曰く、ドラクゥで はなくレニスが大魔王となるべきである。 このザーディシュ、やり方が老獪だ。 実際、かなりの高齢らしい。 改革の意思が強いドラクゥに反感を持っている先代大魔王の側近 たちを抱き込み、先代大魔王の遺書を“発見”したんだそうだ。歴 史によくあるパターンである。 ﹁そこで国を二分しての大決戦⋮⋮ とはならなかったわけだ﹂ ﹁ええ、そうなのです﹂ ﹁あの忌々しい魔王どもめ⋮⋮﹂ この魔界には、一〇八もの魔王がいる。ことになっている。 どうもエリィナに聞くところによると、数は時代によって変わる らしい。今は大体一〇〇より少し少ない程度。その魔王たちが、め いめいに独立したというのだ。 19 ﹁元々大魔王陛下が絶対的な権力を持つことに不満を持つ魔王さま 方は多かったのです﹂ ﹁“魔王”を名乗り、それと認められる者の多くが氏族や部族の代 表者。魔族として言葉を操るとはいえ、一皮剥けば敵同士だった先 祖の記憶が蘇るのでしょう﹂ アメリカ以上の多民族国家、というわけだ。 さっきの戦いにしても、魔人、ゴブリン、コボルト、ホブゴブリ ンが入り乱れての戦いだったことを考えれば、どれだけ色々な種類 の魔族がいるかがよく分かる。この辺りの感覚って、多分現代日本 に育った俺には共有できない感覚なんだろうな。すぐに“みんな仲 良く”とか思ってしまうのだが。 ﹁つまり、ドラクゥが天下を取るには一〇〇人の魔王を片っ端から 殴りつけて行けばいいわけだな?﹂ ﹁平たく言えばそうなります。他の魔王の傘下に入っている魔王も おりますから、一〇〇よりは少なくて済むでしょうが﹂ 俺は敢えてふざけた解を導いたが、それほど簡単なことでもない だろう。 例えば、大魔王の都。こういう拠点を抑えることも大事になる。 <皇太子>の身柄も抑えねばならないに違いない。 こちらの手勢は、増えたとはいえ五〇〇程度しかいないのだ。 ﹁五〇〇で、二十四万か﹂ ﹁畏れながら邪神さま、五五〇に増えましてございます﹂ ぼろ 俺の呟きに答えたのは、ル・ガンだった。 霧に濡れた毛を襤褸布で拭いている。 20 ﹁ドラクゥ殿下が討った傭兵団の敗残兵を纏めておりました。ゴブ リンとコボルトの混成ですが、ひとまず、五〇。軽傷の者も混じっ ておりますので、小荷駄か徴発辺りにしか使えませんが﹂ 小荷駄、という言葉の意味がよく分からなかったのでエリィナに そっと尋ねる。 どうやら、食料や水を運ぶ輸送部隊のことらしい。 ﹁なるほど。邪神である我が言うのもなんだが幸先が良いではない か、ル・ガン﹂ ﹁邪神さまのお陰にございますな﹂ 片頬のホブゴブリンはガハハと豪快に笑う。 こうしてみるとなかなか愛嬌のある顔立ちだ。 ﹁おお、そう言えば﹂ 大事なことを忘れるところだった。 ドラクゥに向き直り、俺は神界でのことを掻い摘んで説明する。 ﹁<北の覇王>を守護する邪神、ですか?﹂ ﹁そうだ。長い黒髪の邪神で⋮⋮﹂ そこまで言ったところで、ドラクゥが身を乗り出してくる。 ﹁その者、異国風の装いに、見慣れぬ長柄の武器を持っておりませ んでしたか?﹂ ﹁ん、袴と方天画戟、だな。確かにこちらの世界には無いかもしれ んが﹂ 21 ドラクゥは大きく息を吸い、吐いた。 気を落ちつけているのだろう。 ﹁邪神さま、私はこれまで他の邪神を見たことがない、と申しまし たな?﹂ ﹁ああ、確かにそう言った﹂ まみ ﹁あれは、勘違いにございました。その<黒髪姫>とやら、戦場で 見えております﹂ ﹁ほう﹂ 相槌を打ちながら、俺は背中を嫌な汗が伝うのを感じていた。 俺もこんなに姿を現すのはまずいと思うが、他にも同じようなこ とをしている邪神がいたのか。 しかし、たった一人の邪神である。 戦場に出たからといってどれだけのことが出来るだろう。 俺なら、なにも出来ない。精々が雷を背負って説得くらいのもの だ。 ﹁<黒髪姫>は、化け物です。正に、一騎当千。あの女一人の為に、 私の軍は敗れたと言っていい﹂ ○ 足りない。 おかしい、全然足りない。 慌てて自分の服をバタバタとまさぐる俺の姿を、エリィナが不思 議そうに見つめている。 細い人差し指を唇に当ててちょこんと首をかしげる仕草がとても 22 愛らしい。愛らしいが、今はそれどころではない。 カルマ ﹁畏れながら邪神さま、何かお探しでしょうか?﹂ ﹁おぉ、エリィナ。実は、我の徳が覚えていたよりも少なくなって いるのだ﹂ ﹁はぁ⋮⋮ 徳、ですか﹂ 神界で服を買った時はまだ四〇万くらいは余っていたはずなのだ カルマ が、今では三十五万くらいしかない。 ちなみに徳はお札みたいして保存しておくことも出来て大変便利 である。小銭もある。俺は小市民なんでこの形にして保存していた のだが⋮⋮ ﹁あ﹂ その時俺はとんでもないことに気付いてしまった。 ひょっとして。 ○ それまで穏やかだった空が俄かに掻き曇り、天が轟き始める。 大粒の雨が一つ滴ったかと思うと、それは一気に濁流のような豪 雨になった。 横殴りの雨が廃城の苔むした壁面を容赦なく叩きつける。 ﹁一体何事だっ!﹂ 慌てて飛び出してきたドラクゥは、城の前で呆然と天を見詰める 邪神の姿を発見した。 まるで妻を寝取られた男のような呆け具合だ。 23 ﹁じゃ、邪神さま?﹂ ﹁あ、ああ、ドラクゥか﹂ がっくりと肩を落としたまま、邪神はひらひらと手を振って廃城 の中に入っていく。 煤けた背中に掛けるべき言葉を、ドラクゥは持たなかった。 ○ 原因が分かった。 実験前、俺の財布には三十五万四千三百十七カルマ入っていたの だ。 それが“大切なことを言う”為に雷雲を呼んだ途端にみるみる減 り始め、今では三十万ちょっとしか入っていない。つまり、一回雷 雲を呼ぶだけで五万カルマは飛んでいくという寸法だ。 これはますます節約をしないといけない。しないといけないんだ が。 ﹁邪神さま、お供え物でございます﹂ ﹁あ、ああ﹂ これも問題なのだ。と言っても支出側でなく、収入側の問題だが。 エリィナの差し出すパンを受け取る。受け取るのだが、モノとし てのパンは盆の上にそのまま残る。 俺がお供え物として頂くのは、お供えされたパンの“意味”なん だそうだ。エリィナの説明によるとこの世界と重なり合う形で存在 する邪神の世界の側にあるパンを、俺は貰っているらしい。深い。 で、俺が食べるのは邪神の世界側のパン。残った物質世界側のパ ンはどうなるかというと。 24 ﹁⋮⋮邪神さま、これ、美味しくないです﹂ エリィナが眉根を寄せ、うへぇと舌を出す。が、俺の前だと気付 いてさっと元に戻した。 可愛いなぁ、もう。 つまり、お供えされたパンの“意味”は美味しさとかそういうも ののことだろう。 お供えものとして提供されたパンの物質界側をエリィナに食べて 貰ったのだが、御覧の有様だ。 栄養分もなくなっているかもしれない。 となると、残念だが俺の計画していた第一弾の計画は崩れ去る。 計画は、こうだ。 ドラクゥの軍が入手する兵糧を一度全て俺にお供えさせる。 それの“意味”を俺は神界で売り捌き、兵糧自体はドラクゥに普 通に使用させていく。この方法が使えるのなら、何の問題もない。 ドラクゥが勢力を増せば増すほど俺は手に入れられる兵糧が増え、 それを売り捌いてカルマを入手できるという素晴らしい計画だった のだ。 それが、崩れた。 味のしないパンだけを食べて戦争をさせることはできない。そこ まで俺は悪逆非道な邪神ではない。 第一そんなことでは戦いに勝てないだろう。士気も上がらないし。 見たところ、ドラクゥの兵もル・ガンの兵も士気はそれなりに高 い。というよりも、士気に頼らざるを得ないのが実情だ。 近現代的な操典にそった訓練方法というものが無い時代では、こ 25 れもまたしょうがない。 というよりも、“誰でも人が簡単に殺せる”兵器である銃が出て くるまでは、将軍個人の武勇とカリスマ、それに従う兵の士気が大 切になる。 士気を上げるには、カリスマ、規律、旨い飯が大切だ。 旨い飯、温かい寝床。それがなければ戦うものも戦えない。 それを取り上げてしまえば、負けることは目に見えている。勝て たとしても、長くは続かないだろう。 俺にせめて個人的な武勇があれば。 ⋮⋮そう、<黒髪姫>のように。 ○ ﹁<黒髪姫>は、化け物です。正に、一騎当千。あの女一人の為に、 私の軍は敗れたと言っていい﹂ ドラクゥは、遠い目をした。 目の前にありありと戦場の砂塵が浮かび上がる。 その女は、赤い馬に乗っていた。 いや、魔界には肌の赤い馬などいない。神獣か、珍しい魔獣の類 だろう。 ﹁あの女が現れたのは、戦の中盤でした。私の指揮する連合軍は竜 翼の陣で挟み込もうとする敵軍に対し、竜鱗の陣形を組んで抗して いたのです﹂ 竜翼の陣は数の多い側が数の少ない敵を両側から反包囲する陣形、 竜鱗の陣は部隊を小さく分けて竜翼の陣に対抗する為の陣形だ。大 軍同士の戦いというのは、却って基本に立ち返ることが多い。 26 ﹁連合軍は、寄せ集めとしては破格の勇猛さで敵の攻撃を退け続け ました。両翼からの攻撃に耐えながら、機を見て敵の中央を食い破 ろうとしていた。そこに、あの女が現れた﹂ ドラクゥの口調に、激憤が混じる。 相手がまだ魔族であれば自らの力量不足と納得出来ていたものが、 相手が邪神となれば話が違う。 とっかん ﹁赤い馬に乗ったあの女は、単騎駈けで我が軍の先陣に吶喊し、蹂 躙したのです﹂ ﹁⋮⋮赤い馬、そこまでやるか﹂ 邪神が、何か呟く。邪神同士にしか分からない何かがあるのだろ うか。 ﹁先陣を崩された我が軍は、最終的に敗れました﹂ 数の上では相手の方が五万多いのだ。 それも、全てがドラクゥに忠実というわけでもない。ここの武勇 を活かす為の竜鱗の陣だが、裏を返せば個々の武勇にしか頼れなか ったとも言えるのだ。 ﹁さて、しかし﹂ 頼みの綱の邪神は、唸るばかりだった。 それもそうだ。相手の<黒髪姫>なる邪神がどの程度かは分から ないが、こちらの邪神はまだ邪神として生まれついたばかりなのだ。 場を、重い雰囲気が支配する。 が、沈黙を破ったのは意外にもル・ガンだった。 27 ﹁黒髪の女武将の話は聞いておりましたが、よもやそれほどとは。 しかし、何です。今日明日にその<黒髪姫>とやり合うわけでもあ りません。今は、今日明日のことを考えましょう﹂ それもそうだ。 そもそも<黒髪姫>と雌雄を決するところにまでドラクゥの軍を 大きく出来るのか。 まずは、一手。 ﹁その件については、余に腹案がある﹂ ☆ 数で勝るベナンと戦うため、様々な策を弄するドラクゥ。 山賊紛いの略奪に流言飛語。 ベナンの甥、ゴブリンシャーマンのリ・グダンが率いる隊と対峙 するドラクゥ。一方で平乃は、ゴブリンが命を奪われるのを見ても じんざい さほど心を動かされない自分自身に、違和感を覚えていた。 邪神として未熟な自分をサポートしてくれる神材を探す為に再び 神界を訪れる平乃。そこで待っていたのは、高校時代の先輩である 慶永佐織との、思いもかけない再会だった。 28 第3章ダイジェスト版 ﹁まずは再会を祝して﹂ ﹁乾杯﹂ 酒を旨いと感じたのは久しぶりだった。 接待とヤケ酒のせいで、俺の舌はアルコールに拒否反応を示すよ うになっていたんだが。 よしなが 呑む相手が良い、ということだろう。 慶永さんと俺は斡旋所の裏手にある小さな構えの焼き鳥屋を選ん だ。まだ陽は高いが、ちらほらと客の姿もある。慶永さんによると、 ここのつくねがなかなかイケるらしい。 ﹁しっかし、ヒラボンが邪神とはなぁ﹂ ﹁さっきもそれ、言いましたよ﹂ ﹁そうだったっけ﹂ 言いながら慶永さんは芋焼酎を一気に呷る。豪快な飲みっぷりだ。 そういえば高校時代から部室に一升瓶を隠すような酒豪だった。 俺の方はと言えば、ハイボールをちびりちびりとやっている。つ くねも旨いが、鳥皮もなかなか。 カルマ ﹁神さまやってた経験から言わせて貰うと、やっぱり邪神は辛いな﹂ ﹁そうですかね﹂ カルマ ﹁そりゃそうだ。だって、信仰集めたって徳が貯まらないんだから さ。神階に応じて貰える給料なんて雀の涙だかんね。ちなみにヒラ しょうそいのげ ボン、今の神階は?﹂ ﹁えーっと、少初位下だったかな﹂ 29 そこで慶永さんの目がジト目になる。 手にしたコップをテーブルに叩きつけるように置き、そのまま俺 をヘッドロックしてきた。 柔らかい、石鹸の香りが鼻をくすぐる。とか言っている場合では ない。身体こそ小さいが、相手は慶永さんだ。技を掛けられた瞬間 にギブしないととんでもないことになる。 ﹁ヒラボン、お前、まだ名前も貰ってないのか!﹂ ﹁ギブギブ、って名前ですか?﹂ ﹁そ、名前だ名前。神さまにも名前ってあるだろ。アマテラスオオ ミカミとかコノハナサクヤヒメとかククリヒメノカミとか﹂ ﹁ああ、ありますね﹂ そう言えば、転生してからこっち、ずっと“邪神さま”だ。 ドラクゥもエリィナもその辺りには無頓着なんだろうか。 平乃凡太、でも不便はないのだが。 しょうそいのじょう ﹁名前が付くだけで少初位上にはなる。話はそこからだ﹂ ﹁え、そんなに簡単に位って上がるんですか?﹂ ﹁簡単なのはここまでだ。ここから先は信者数だのなんだのと、変 な基準が一杯ある﹂ しかし、ということはさっき面接に来た<氷結山脈のキノコ>さ んは俺よりも神階が上だったのか。 ちょっぴりショックだ。 ﹁最初はただ給料が上がるだけだけどな、従五位下以上になると、 会議に出られるようになる﹂ ﹁会議?﹂ ﹁ヒラボンなら“邪神会議”、な。店員さん、これおかわりー﹂ 30 相変わらず、この小さな体のどこに入るのかと思うほどの量をこ の人は食べる。それも旨そうに。 青白く半透明な店員さんが持ってきてくれた芋焼酎を片手に、慶 永さんの説明は続く。 ﹁邪神会議みたいな会議っていうのは、大体が神さま同士の利益調 整だな。基本的に神さまなんて滅多に下界に介入しないのが建前だ けど、例えばどこかの部族が滅びそう、とかになってくると話が違 う。そこを担当してる神さまが失職しちゃうからね。だから、そう いう事態が成るべく起きないように会議をして巧く調整するように なっている﹂ ﹁へぇ、談合みたいですね﹂ ﹁言葉は悪いけど、まぁそういうことだな。それで上手く回る面も あるし、それを嫌う奴もいる﹂ 深いな。前世ではどちらかと言えば談合に携わる側だったけど、 こちらの世界ではどうなるか。そもそも従五位下というのがどれほ ど偉いか分からないので、そこまで到達するだけで大変そうだ。 ﹁ところでヒラボン、君は何の魔王の担当の邪神なんだ?﹂ ﹁何だと思います?﹂ ﹁んー そうだなぁ、草食スライムとか、泥啜りとか、沼ゴブリン とかそういう感じじゃないかな﹂ ﹁実は﹂ ﹁実は?﹂ ﹁魔人の魔王なんです﹂ 次の瞬間、慶永さんが芋焼酎を盛大に噴き出した。汚い。 31 酷い笑いようで、そのまま引っくり返りそうなほどだ。 ﹁いや、失敬、ヒラボンが魔人の魔王担当とは恐れ入った。そうか そうか。意外にいいマスターに巡り合えたんじゃないか、私は﹂ 咽ながら謝る慶永さんの為に背中をさすってやりながら、水を頼 む。 そんなに意外なのだろうか。 カルマ ﹁そういうのはな、ヒラボン。徳が余って余って仕方がない神がや る役だぞ。例えば邪神セットに三億ぐらい注ぎ込むような、そうい う酔狂な奴がだな﹂ ﹁⋮⋮俺の邪神セット、五億くらいです﹂ 今度こそ本当に、慶永さんは引っくり返った。 ○ 口の端から、鮮血混じりの泡が漏れている。 怒りの咆哮を上げ続けた喉は潰れ、声も出ない。 リ・グダンは、敗残の兵を率いて北へと逃げていた。 森の道は、優しくない。 まるでリ・グダンを責め苛むように入り組み、根を張り、月影さ えも隠す。 火を放ったことに対する神罰のようだ。 兵は次々と脱落し、残っているのは傭兵の一部だけだ。それも、 傭兵隊長を失って行く当ての無い連中だけで、常備兵と目端の利く 傭兵は森の中に溶けるようにしてリ・グダンの元を去っている。 32 まさしく、敗軍だ。 負けた。 僅かな兵しか抱えていなかったはずの<廃太子>に、魔王ベナン が敗れたのだ。 その場にリ・グダンは駆け付けることすら出来なかった。アルナ ハ落城の知らせを伝えに来た伝令のゴブリンも、リ・グダンの部隊 への合流は、拒んだ。曖昧な笑みを浮かべながら去っていく後ろ姿 に、リ・グダンは怨みすらも抱かなかった。 何もかも失ってしまったのだ。 地位も名誉も名声も力も。当てどなく北上しながら、目指す場所 に一つの目星もない。 巣の無い鳥は飢え死にするか力尽きるまで飛ぶしかないだろう。 いっそこのまま山賊になるのもいいかもしれない。 賊の討伐に出て、そのまま賊になる。出来過ぎた冗談だった。 今にして思えば、巧妙な罠だったのだ。 自分のことを知恵者だと信じていたリ・グダンにとって、これは 耐え難い屈辱だった。 “砦にリ・グダンの隊を引きつけている間に、後方を攻撃する” という敵の策は、読み切っていたと言っていい。問題は、その規模 だった。 まさか後方も後方、アルナハ城市を直接攻撃するなど、リ・グダ ンには思いもよらない。 いや、脳裏に浮かびはしたのだ。ベナンもその可能性を指摘して いた。だが、それは頭の片隅に追いやってしまえるほど可能性の少 ない、大胆な策だった。とても寡兵で行う作戦ではない。 奇策。なるほど、奇策だ。 33 リ・グダンが森に火を放ったように、<廃太子>は望む場所に兵 を召喚した。それだけのことだ。 天運、としか言いようの無い力にドラクゥは護られているのだろ うか。 がか 一つでもボタンを掛け違えば、全てが水泡に帰すであろう危険な 策。それを何の躊躇いもなく選択できるのは、やはり神憑りではな いか。 ︵ドラクゥは、邪神の加護を享けているのかもしれない︶ 突如、リ・グダンは天啓を得た。 そうだ、邪神だ。そうであれば合点も良く。ドラクゥには、邪神 が憑いている。 巧妙な罠、というのは言い換えれば常に綱渡りなのだ。その危地 を邪神の加護で補う。であればあれほどの果断にも説明がつく。卑 怯な魔人め。何が<廃太子>だ。何が武略と知略の天才だ。 とんだペテンではないか。 自分が邪神の加護を得られなかった、という屈辱はまるで無い。 むしろ、リ・グダンにも邪神の加護があるのであるのではないか。 この敗北ですら何かの糧であり、迂遠な計画の途上にあるとは考え ぬかる られないか。 泥濘みを踏みしめる足に、生気が戻る。 そうだ、これは邪神の課した試練だ。 “邪神は信者を試す”という。ならば、リ・グダンはその試練に 耐え抜いた。生き延びた。 これは惨めな敗走ではなく、栄光への道程である。 リ・グダンの口元が、緩む。 自然と笑みが零れるのを隠し切ることが出来ない。 34 邪神、邪神、邪神。 これからは邪神の望む通りに生きよう。ドラクゥよりも、さらに 随神の精神を高めるのだ。そうすれば、負けることはない。如何に 相手が魔人で王族であったとしても、能力として優れているのはこ のリ・グダンの方なのだ。そこに邪神の加護が同程度加われば、負 ける要素は無い。 漏らした忍び笑いが哄笑に変わるのに時間は掛らなかった。 喉一杯に鉄錆びた味が広がるのも構わずに、リ・グダンは天に向 かって笑う。 傍らを行く敗残の傭兵が奇妙なものでも見るような視線を向けて いることすら、気にならない。 その時、天から一筋の光がリ・グダンの眼前を照らす。 それこそ正しく、リ・グダンの待ち望んだものに、違いなかった。 ○ ﹁一カルマっていうのは、一人の一般人が一日信仰を捧げた時に発 生する徳なんだよ﹂ ﹁ほう﹂ 焼き鳥屋を出た俺と慶永さんは公園のベンチで寛いでいる。 <神界の太陽>担当の神さまが<神界の月>担当の神さまにバト ンタッチし、辺りはすっかり夜だ。 薄闇の公園は静かで、人影もあまりない。噴水の水音が遠くに聞 こえるだけだ。 こうしているとまるでデートのようだが、会話の内容は堅いこと この上ない。 35 今まで避けて来た“この世界の常識”をやはり学ばねばならない ようだ。 ﹁熱心な信者、例えば僧侶や神官みたいな信者がいると、もう少し 効率はよくなる。こういう聖職者自身の祈りは二∼三カルマになる こともあるし、他の信者に神の教えを伝えることで雑念を除いて、 クリアなカルマを得ることが出来るようになるのさ﹂ ﹁ほうほう﹂ 聖職者、ということは俺にとっては邪神官のエリィナみたいな人 のことだな。 赤毛の女の子、という印象しかなかったが、結構重要な役どころ らしい。 カルマ ﹁この徳が神界では通貨として扱われているんだが、実はもっと重 要な使い方がある﹂ ﹁邪神基本セットを使う時に消費する?﹂ ことわり ﹁なんだ、知ってるんじゃないか。そうだ。正確に言うと、神の奇 跡を起こす際に必要になる。例えば農耕の神が特定の畑を自然の理 に逆らって豊作にしたり、逆に不作にしたりするのにも、カルマは 消費される﹂ ああ、それで納得できた。 人々の信仰で神界にカルマが流入するなら、いずれは凄まじいイ ンフレになるはずだ。奇跡によって消費されるなら、それでカルマ の流通量のバランスが取られているのだろう。この辺りはブラック 企業とはいえ商社に勤めていたから、何となく分かる。 ﹁平和な時に祈りを捧げるのは聖職者だけだが、戦争や疫病、飢饉 が発生すると民衆は神頼みをするようになる。そうすると神々の得 36 るカルマの量が増え、奇跡も起こしやすくなる、という寸法だな。 これを皮肉って、“神の見えざる手”と言うそうだ﹂ 慶永さんがドヤ顔で言い放つが、あまり面白くない。 昔から慶永さんの渾身のギャグは受けないと決まっているのだ。 ぎこちない愛想笑いを浮かべておくが、ちょっと可哀そうだった。 ﹁さて、ここからは仮説になる﹂ ﹁仮説、ですか?﹂ ﹁まず、この世界の住人、つまり下界の人間や魔族も、転生者だな ?﹂ ﹁そうですね、多分﹂ あの世での転生について考えるとそれはほとんど間違いないよう に思う。 全ての者が転生者だとするならば、この世界の生き物だけ違うと 考えるのは道理に合わない。 ﹁同じように転生したのなら、何故魔族の信仰からはカルマを得ら れないのか﹂ ﹁ああ、それは確かに﹂ ﹁とはいえこれも実は経験則で、魔族からカルマを得た邪神がこれ までにいなかった、というだけなのかもしれない。が、よく分から ない。とにかく、人間や他の種族、キノコからでさえもカルマを得 られるのに、魔族から得られないのはなぜか﹂ そこはとても重要な問題だ。 原因が分かってもどうしようもないのだが、腑に落ちないと気持 ちが悪い。 37 ﹁多分、あれは“修羅道”なんじゃないかな﹂ ﹁シュラドウ、ですか?﹂ ﹁そう、仏教における六道輪廻の一つなんだがな。ずーっと戦い続 けることを定められているんだ﹂ 流石は寺の娘。難しいことをよく知っている。 ﹁地獄みたいなもんですかね?﹂ ﹁地獄とはまた違う。むしろ、ずっと上等だ。天道、人間道に次ぐ。 悪い業を背負ってはいるが、悪人ではない者が修羅道に生まれる﹂ ﹁業が深い、って奴ですか﹂ ﹁そういうことだな。で、ここからが仮説の核心﹂ ﹁ふむ﹂ ﹁ヒラボンがカルマの借金を返さないと天国に行けないように、彼 らもまた、悪業を取り除かないと天国なり極楽なりに行けないので はないか。そしてその浄化に、カルマが消費されているのではない か、ということなんだよ﹂ うん、つまり、どういうことだ? ﹁例えば、カルマを大福だとする﹂ ﹁大福﹂ ﹁祈りを捧げると、不思議なことに大福が一個、出来る。普通の人 は神に祈りを捧げるときに、大福を持って行く。ここまではいいな ?﹂ ﹁はい﹂ ﹁ところが、魔族の家には腹をすかせた子どもがいる。大福をいく ら食っても満腹にならない。だから、祈る時に大福が出来たとして も、それを神さまに持って行くことが、出来ない﹂ 38 ﹁ふむふむ﹂ さっきから相槌しか打っていないが、言わんとすることは分かる。 その業とかなんとかいう奴を取り除く為に、自分の徳を消費して いるから、信仰しても邪神にはカルマが集まらない、ということか。 ﹁こう考えると、何となく辻褄が合うんだ﹂ ﹁単に徳が足りないだけってことはないんですかね?﹂ ﹁それだとヒラボンも魔族になっているはずだろう﹂ ﹁ああ、そういえばそうか﹂ 徳が足りなくて魔族になるなら、確かに俺が魔族にならないのは おかしい。 なるほどな。 ﹁そういえば先輩はどうして神さまなんてやってるんです? 徳も 高そうなのに﹂ ﹁そりゃそうだろう。天国なんてつまらなそうだからな。暇なのは 嫌いなんだ。たっぷり楽しませてくれよ、マイマスター﹂ ○ 命を、拾った。 酒盃を傾けながら、ルクシュナはそう思っている。 アルナハ城市の夜は、意外なほどに賑やかだった。土壁の酒場に は宵も深まっているというのに多くの客がいる。豚肉と、酒。これ だけしか出ない安酒場だったが、今はそれで十分だった。 ﹁ルクシュナ、呑め、呑め﹂ 39 差し向いにはタイバンカの姿がある。 “死んでくれ”と言った負い目からか、今日の払いは全て持って どぶろく くれるという。そうとなれば遠慮するルクシュナではない。元より、 もちごめ 食事よりも酒が好きと言う男なのだ。 欠け茶碗に並々と注がれた酒は糯米を醸した濁酒で、かなりきつ い。が、ルクシュナはそれを水のように呑めるのだった。 ﹁旨いな﹂ ﹁ああ、旨い。勝利の美酒、という奴だ﹂ 勝った、という実感と共に心地よい酔いが身体に回っていく。 安酒でも、美酒は美酒だ。 何度目かの乾杯を経て、漸く周囲に目を向ける余裕も出てきた。 アルナハは、魔界南西の辺境としては十分に大きな城市の内に入 る。人口は三万と公称しているが、実際にはさらに五千は多いはず だ。これに周辺の村々の人口を加えれば、かなりの数になる。 その多くはコボルト属の魔族で、この酒場も事実、そういった者 で多くが占められていた。とは言え、流石に南国である。魔都周辺 でルクシャナら二人の見慣れたコボルトと比べ、このアルナハに住 まう者たちは随分と短毛だ。ひょっとすると、種自体が異なるのか もしれない。 皆、陽気に酌み交わしているところを見ると、負けたという意識 は希薄なのだろう。 タイバンカの碗に酒を注ぎ足してやりながら、ルクシュナが尋ね た。 ﹁ベナンはあまり良い統治者ではなかった、のかな﹂ ﹁見る限り、そのようだな。これだけコボルトが多いのに、ベナン 40 の側近はほとんどがゴブリン属だ﹂ ﹁では我らが<廃太子>さまは解放者という訳か﹂ ﹁さてな。期待が大きければしくじった時の反動も大きいからな﹂ ドラクゥは配下に行政官を持たない。 であれば新たに雇い入れる必要があるが、ベナンの配下をそのま ま引き継ぐ訳にも行かなかった。彼らは多くがベナンの親族で占め られており、恨みもまだ癒えない。そして何より、住民の大多数を 占める短毛コボルトの反対が大きかった。 そのせいもあって、占領から三日経つというのに新しい人事はま だ発表されていないのだ。 ﹁しかし、統治は難しいだろうな﹂ ﹁ここだけの問題ではないがな。国全体が、荒れている﹂ 先代大魔王の崩御からまだ数年しかたっていないのに、魔界はす っかり乱れていた。 中央に集められることになっている租税は滞り、大魔王府は魔都 周辺に自らが禁じた荘園を作って糊口を凌ぐ始末だ。 ちょうさん では地方が豊かになったかと言って、そういうこともない。相変 わらず取り立てられる重税に耐えかねて、魔族の逃散が続いている。 部族単位で逃げ出して、適当な魔王の用人として荘園を耕すのだ。 その収穫も多くは庇護を約束した魔王が取り立てる。 つまりは虐げられるのはいつもの如く下々の民なのだ。 たび重なる戦乱に軍役として壮年の男を取られ、地方は見る見る うちに疲弊している。 それはこのアルナハ城市とその周辺についても例外ではない。 ベナンの後釜としてこの城市を治めるドラクゥは、難しい舵取り を迫られるのは間違いなかった。 41 ﹁それにしても、邪神さまよ﹂ ﹁おぉ、邪神さまだ﹂ 戦の最中に姿を消した邪神が、帰って来ていた。 軍中の者は顔を見知っており、親しみを覚えている者も多い。顕 現した邪神、というのは魔界の歴史から見てもあまり多くはないし、 そのほとんどが伝説の濃い霧の中だ。実際に見えるとなれば、崇め る者も現れる。 その邪神を讃える為に、早速神殿までが建てられようとしている のだ。 ﹁ルクシュナ。ここだけの話だが、今回の戦、随分と危なかったと 思う﹂ ﹁お前もそう思うか?﹂ タイバンカが、答える代わりに碗の中身を干す。 <廃太子>ドラクゥを戦の名手とするのはむしろ外部の評判であ り、率いられる身としてはその采配の危うさが身に沁みている。も っと大きな盤面で戦うべき人なのだ。才気が走り過ぎ、今回のよう な小部隊を取り回す時にはどうしても策を弄し過ぎる。 当たれば必殺、外れれば敗北。そういう賢しらな部分が、どうし ても目立つのだ。 ﹁五千までの兵を率いるなら、あの戦い方も在り得る。が、こうい うやり口に慣れて貰っては、な﹂ ﹁王器を見せつける、そんな戦い方こそが似合う方なのだが﹂ その危うさを、邪神が補っている。 邪神の与えた天運だけが勝敗を決したわけでもないのだが、そう 42 いう要素はある、と二人は見ていた。 そう思えば、自然と感謝の念も湧いてくる。 ﹁邪神さまとドラクゥさまに﹂ ﹁邪神さまとドラクゥさまに﹂ 碗が、打ち合わせられる。 酒場の喧騒は、まだまだ続きそうだった。 ☆ ベナンを倒し、アルナハを手中に収めたドラクゥ。 平乃改め邪神ヒラノを崇める邪神殿も建設し、腐敗の蔓延る城市 の改革に乗り出す。 人材を集め、領地を接する異種族“泥啜り”に外交使節を派遣し、 生き残る為の策を次々と打ち出して行く。 その頃ヒラノは慶永さんの誘いでジョナンの赤い森の奥へと探索 に出掛ける。 そこで待っていたのは⋮⋮ 43 第4章ダイジェスト版 門前に、もう一つの街が出来ていた。 行商人たちが荷を運び、城市に入らず勝手にそこで荷を解いてし まうのだ。物があれば、人も来る。たちまち辺りは賑わい始め、乱 雑な区画割りで露店らしきものが建ち並び始める。 街道税を廃したからだった。 魔界の南西の端ではあるが、アルナハはこの辺りでも有数の大き さを持つ城市だ。街道に掛る税が無くなれば、自然と人も物も金も 集まるようになる。この辺りには城市にも成りきれない小さな集落 はいくらでもあった。それらの結節点として、アルナハは機能しつ つある。 ドラクゥは城門の上からその様子を見て、目を細めた。 内心穏やかではない。ラ・バナンの税制改革の失敗、とも言える からだ。街道税を廃して入市税を取ることに定めたのに、人も物も 市に入らないのであればそれは税収がなくなるのと同じことだった。 とは言え、感心もしている。 辺境の一城市に過ぎないアルナハで街道税を廃しただけで、これ だけの人々が集まるのだ。活き活きと物を売り買いする人々の姿に、 ドラクゥは魔都の大市場の姿を重ねる。あそこの喧騒はここの比で はない。民の力強さと逞しさを感じる。民は疲れているが、生き抜 く為の場を与えてやれば、これほどまでに輝くのだ。 全ては、税と法と魔王が問題なのだ、とドラクゥは考えるように なっている。 大魔王の孫として魔都にいた時には、見えなかったことだ。王家 の血の威光は地に墜ち、あるいは悪用されている。魔王がそれぞれ の領地で権勢を振るうことは止められないが、苦しむのは民なのだ。 44 それでいい、とは<廃太子>ドラクゥは思えない。 この魔界は、長く惰眠を貪り続けたのだろう。扉の蝶つがいが軋 むように、色々な所に不備が出始めている。古いものを有り難がる 風潮が、その傾向に拍車をかけていた。 一度、ドラクゥは大魔城の奥で“初代大魔王の剣”なるものを見 たことがある。恐らく、贋作であろう。五千年も前の話なのだ。そ の五千年、というのも本当かどうか疑わしい。その時代、まだ魔族 には文字すらなかったようなのだから、確かめようもない。 正絹の袱紗に包まれたそれは最早剣の原型を留めておらず、ただ の鉄錆の塊にしか見えなかった。 ︵あれがつまり、今の魔界の姿なのだ︶ 自嘲気味に思うのは、己が欺きようもないくらいに古いものへの 愛着を感じているからだ。 そうでないのなら、魔界の統治など力のあるもの︱︱つまりは、 <北の覇王>︱︱に委ねてしまえばいいのだと諦めることが出来る。 <北の覇王>と<皇太子>、この二人と戦い続けねばならないとド ラクゥが思うのは、民のことよりも何よりも、まずは自分の懐古趣 味が原因なのかもしれない。 ﹁ドラクゥさま﹂ 振り返ると、ラ・バナンがいた。 憔悴しきり、目の下に隈が濃い。それもそうだろう。眼前に広が る盛況な市からは、全く税収が入らないとドラクゥは聞いている。 苛立ちもするだろう。が、心なしか今朝見たときよりは顔色が良い。 ﹁どうした、ラ・バナン。嬉しそうだが﹂ 45 ﹁行商人どもを取り纏めることに成功いたしました。区画ごとに、 出店税を支払わせます﹂ ﹁ほう﹂ 出店税、というのは聞き慣れない法律だ。 法源はなんだ、と聞きかけてドラクゥは口を噤む。新法について、 ラ・バナンに一任していた。 魔族には﹁古き法は善き法なり﹂という考えが根強い。上古の昔、 第八代大魔王の定めた欽定律令との派生諸法辺りを法の根拠とする のが、法を作る上での流行りだった。 つまり、実態に即していない。 法律の条文の見た目の美しさを優先する為に要項を付けたしたり、 長々と注意事項を書いた後に、﹁但しこれは適用しない﹂とやった りする。これでは民が法に何かを期待することなどあり得ない。 だからこそ、ドラクゥはラ・バナンの瑞々しい才能に望みを託し ている。 ﹁よく行商人が納得したな﹂ ﹁した、というよりも向こうから申し出てきたようなところがあり ます。彼らは街道税を嫌いますので﹂ ﹁ああ﹂ 街道税は、ほとんど野放図になっている。 城市の魔王だけが徴収するのではない。小さな砦に拠った豪族や 小部族、酋長、竜までさまざまだ。それら全てに街道税を払うなど、 行商人に儲けを出すなというのと同じことだった。 ﹁奴ら、ドラクゥさまにあと二、三は城市を支配して貰いたいと﹂ ﹁ほう﹂ ﹁二つ三つの城市の間で街道税が無くなれば、商いはもっと上手く 46 行く、と考えているようです﹂ ﹁それは、そうだろうな﹂ だが、難しい。 南のバァル・ゴナン、東のキリ・シュシュツ、どちらも容易には 落とせそうにない。 治めているのが泥啜りとリザードマンなのだ。となれば、後は北 に進むしかない。 ﹁<淫妖姫>、か⋮⋮ 余はあれが苦手なのだがな﹂ ○ 花園は良い香りに満ちていた。 辺境には似合わない。赤い森の中にそこだけ華やかなここは、< 淫妖姫>の所有する庭園だ。水準でいえば、魔都の薔薇園にも匹敵 すると言われている。色とりどりの花が丹精され、庭園の中には小 さな小川までが走っていた。 アルナハの北、パザンの城市である。 ジョナンの赤い森の北限に当たるこの辺りには、珍しい花が多い。 常緑のものと、一年で枯れるものが混在している。育て方にさえ 気をつければ、温暖だが乾燥した魔都よりもよほど多くの種類の花 々を育てることが出来た。 花園も、その特長を最大限に活かすように造園されている。地上 の楽園の如し、と評されるほどだ。 その中心に、東屋がある。白大理石造りの落ち着いた雰囲気のそ れは、<淫妖姫>に気に入られた者しか立ち入れぬ、一種の聖域で あった。 47 リ・グダンはそこで、茶を啜っていた。まるで賓客の扱いである。 対面には<淫妖姫>その人の姿があった。 ﹁<廃太子>の実力はそれほどか﹂ 美しい、といえばこれほど美しい魔王もいない。 まさに、見るもの全てを魅了する美姫である。リ・グダンの目に は、<淫妖姫>パルミナが絶世のゴブリンシャーマンの美女に“見 えて”いた。他の者にはまた、違うように見えているだろう。 つまり、<淫妖姫>とはそういう種族の魔族なのだ。 ﹁ええ、恐るべき策謀を秘めた男です。我が先代、ベナンは奴の謀 略に破れたと言っても良いでしょう。手勢が少ない、と侮るべきで はない﹂ ﹁謀略、か。先代のベナン殿は惜しいことをした﹂ 先代のベナン、ということばをリ・グダンは強調する。 魔王を、継いでいた。 もちろん、正規の手続きを踏んだわけではない。あくまで暫定の 魔王位である。それでも<淫妖姫>パルミナがその魔王位を認める ような発言をするのは、アルナハへの介入の意図があるからだろう。 上手くしてリ・グダンが本当に魔王としてアルナハ城市に凱旋する ことになれば、そこに対するパルミナの発言力は増さざるを得ない。 全ては、駆け引きだ。 この駆け引きで、リ・グダンはパルミナから既に相当な額の資金 を借り受けていた。それらは傭兵の雇用とその兵糧に充てられる。 全くの空証文だった。 48 ﹁しかしリ・グダン殿、本当にお前さまに金を預ければ、この庭園 は敵に踏み荒らされずに済むのであろうな?﹂ ﹁それは、間違いなく。我が邪神に誓って﹂ つまり、傭兵なのだ。 リ・グダンという傭兵隊長を雇い、金を払って傭兵隊を編成する。 それがパルミナの狙いだ。魔王の名を名乗りながら、パルミナの種 族は手練手管に頼り過ぎ、実際の戦闘にはまるで疎い。だからこそ 手先が必要で、それがたまたま窮鳥として懐に飛び込んできたリ・ グダンだった、ということなのだ。 それで良い、とリ・グダンは思っている。 そう思えるだけの強かさを、森の中での逃避行は彼に与えてくれ ていた。 名より、実を取る。するとその実を担保に、また名が手に入る。 虚像であっても構わないのだ。いずれ、何かは付いてくる。城市か もしれないし、魔王という位なのかもしれない。いずれにせよ、大 人しくしているだけでは決して手に入らないものを、リ・グダンは 手に入れようとしている。 その為ならば、<淫妖姫>の靴を舐めることなど、何ほどのこと もない。 ﹁して、どのような策であの<廃太子>に当たるつもりなのかの﹂ ﹁策とも言えぬ策ですが、ああいう相手には愚直な方法しか通用し ないでしょう﹂ そう言ってリ・グダンが懐から取り出した物に、パルミナは目を 細める。 アルナハ城市周辺の、絵図面だった。正確に描かれたものであれ ば、千金に当たる。 49 視線に気付きながらも、リ・グダンは気にせずに説明をはじめた。 ﹁北から流れるこの川は、アルナハの西を通って南に下ります。ラ ウ川、と言いますが、これを使おうと﹂ ﹁水の手を断つのか? 金がかかる策よな﹂ ﹁いえ、そうではありません。アルナハは井戸の多い城市ですし、 この川を堰き止めてもあまり意味は無いでしょう。西側から攻める のであれば水濠代わり使われて厄介ではありますが、その点は特に 問題は無い。北からでも東からでも攻める術はあります﹂ ﹁ふむ。城攻めか﹂ ﹁ええ、城攻めです﹂ ﹁数に勝るとはいえリ・グダン殿は、戦巧者である<廃太子>の守 る城を落とすことが出来るのかえ?﹂ ﹁出来ない、でしょうな﹂ 鼻で嗤う。 そう、これがリ・グダンの得た最大の財産だった。 自信に目を曇らせずに、敵と相手の力量を、計る。率直に言って、 今のリ・グダンではドラクゥに勝てる気がしないのだ。 ﹁それでは駄目ではないか﹂ ﹁ええ、駄目です。このリ・グダンでは、倒せません﹂ ﹁ならば⋮⋮﹂ ﹁ですから、ラウ川を使います﹂ パルミナの言葉をさえぎり、リ・グダンは絵図の南端を指で叩い た。そこには流れ込むラウ川と共に、バァル・ゴナンの文字が見え る。 ﹁泥啜りです。奴らにアルナハを攻めさせ、ドラクゥを誘い出し、 50 その隙に火事場泥棒と洒落込むのです。なかなか素敵でしょう﹂ ﹁ああ、素敵じゃな。実に素敵じゃ﹂ <淫妖姫>がその二つ名に相応しい艶然とした笑みを浮かべた。 そのままリ・グダンの手に柔らかな手指を絡めてくる。 わらわ ﹁素晴らしい、素晴らしいぞ、リ・グダン殿。その意気じゃ。城市 を得た暁には、お前さまが魔王に就けるように妾が運動してやろう。 実に良い﹂ 絡まる指を、リ・グダンは冷ややかに見つめる。 見えている指の形と、肌を這いまわる物の形が、違う。 ひんやりとした触感はどこまで甘やかで、蠱惑的で、官能的だ。 労わるように包み込み、誘うように離れていく。その技は、五本 指の生き物には出来ない芸当だった。 ︵⋮⋮スライムの、化け物め︶ パルミナは、“シェイプシフター”という種族の魔王だ。 とろける軟体の身体と強力な幻術を操り、見るもの全てを魅了す る。スライムやミミックと言った種族の、頂点に立つ一人だった。 ︵こうやって人を籠絡し、自分の手を汚さずに勢力圏を広げるつも りか︶ こんな辺境に<淫妖姫>が追いやられているのも、無理はない。 中央に置いておくにはあまりに危険な魔王だからだ。そのパルミナ を、リ・グダンは利用してやるつもりでいる。 ︵待っていろ、ドラクゥ。借りは必ず、返してやる︶ 51 ☆ ドラクゥへの恨みに突き動かされたリ・グダンは<淫妖姫>パル ミナと手を結んだ。 手段を選ばずドラクゥを陥れようとするリ・グダンとパルミナの 策謀に、ドラクゥは有効な手を打つことが出来ないでいた。 手掛かりを元に乾坤一擲の出撃を決意するドラクゥ。彼はそこで、 邪神に見放された人熊の一族と出会う。 カルマ 一方、神界に赴いたヒラノは、ドラクゥの為、いずれは人界に進 出することを考えて徳を集める為に一計を案じることになる。 52 第5章∼第6章ダイジェスト版 五二〇。 集まった兵は、それで全てだった。 魔人、ゴブリン、コボルト、そして人熊。こんな混成部隊も珍し い。 森の中に拓けた小村の広場で、ドラクゥは兵たちを引見していた。 広場の中心に据えられた大きな石の上に立ち、兵たちを見遣る。 腹が立つほどに空は晴れ渡っていた。もし天が今のドラクゥの気 持ちを汲んでくれるのなら、雷雨か、少なくとも豪雨でなければな らないだろう。 この短時間でよくぞ集まったという想いと、それでも足りないと いう想いの両方がドラクゥの中にある。 情報が、集まりつつあった。 人熊を集めたダッダは、後続が集まるまでの時間を使ってパザン 周辺の様子を探っていたのだ。狩人としての能を最大限に活かした 働きだった。 ﹁タイバンカ、敵の数は二五〇〇を超えるそうだ﹂ ﹁大した数です。しかし、所詮は統率のとれない傭兵の群れだ。数 が仇になることもある﹂ ﹁そうだな﹂ タイバンカらしい強がりだ。 統率のとれない、ということではこちらも負けず劣らずなのだ。 中核となるべきドラクゥ直卒の二〇〇はともかくとして、後は農 民、町人、行商人、人熊の狩人の寄り合い所帯で、それぞれに小隊 長すら定まっていない。 53 留守をしていればいいものを何故かタイバンカに付いてきたラ・ バナンが今、編制を勧めている。書面の上で部隊を編制し、実際に 人数を分けて編成するのだ。この男は、とにかくそういう仕事が好 きなようだった。 状況は、悪い。 が、勝機がないわけでもなかった。 ﹁この戦、どう見るタイバンカ﹂ ﹁さて、巧くすれば勝てるのではないですかな﹂ ﹁相手は二五〇〇、こちらは五〇〇。随分とお寒い限りだぞ﹂ ﹁まともに当たれば、脅威でしょうね﹂ やはり、タイバンカには戦術眼がある。 何人かいた二〇人長の中から特に厚遇したのは、この才を伸ばし てやろうと思ったからだった。ドラクゥには、手駒がない。いない のなら、育てるしかなかった。 ﹁今回の作戦の目標は、毒庫とやらが解放されるのを阻止すること です。何も二五〇〇を向こうに回して大立ち回りを演じる必要はな い﹂ ﹁そう、その通りだ。そして、毒庫の場所もほぼ判明していると言 っていい﹂ 毒庫は川沿いにない。これはダッダの調べで明らかだった。 パザンから少し離れた窪地に建ち並んでいる土倉がどうにも怪し い、というのがドラクゥとダッダの共通した見解だ。ここからラウ 川の支流に向けて、大きな樋が大急ぎで作られている。 ﹁リ・グダンを誘引し、その隙に毒庫を燃やす。それしかないでし 54 ょう﹂ ﹁どういう毒があるのか、分からない。燃やすと危険かもしれんぞ﹂ ﹁魔王パルミナもそれを踏まえて毒庫を人里離れた窪地に置いたの でしょう。パザンまでは毒は届かないか、影響は少ないのではない でしょうか﹂ ﹁確かにその通りだ。あの女は、慎重だ﹂ パルミナの顔が、脳裏に浮かぶ。 いや、顔だけではない。声も、吐息の香りさえも、ドラクゥには ありありと思い出すことが出来た。 ﹁出来ればあの女狐の首を斬り落としてやりたいところだが﹂ ﹁そこまでの余裕はありませんよ。それにあの女はシェイプシフタ ーです。首など落としてもまた生えてきましょう。灰すら残らぬよ うに焼くしかありません﹂ タイバンカらしからぬ冗談だ。 横で帳面と睨みあっていたラ・バナンも苦笑している。如何なシ ェイプシフターとはいえ、首が落ちれば、死ぬ。最も、パルミナは 首だけになっても生きていそうではあったが。 ﹁さて、残る問題は、役割です﹂ ﹁役割、か﹂ 常識的に考えれば、隠密行動に長けたダッダたち人熊を土倉の破 壊に向かわせるべきだろう。その間、ドラクゥは数が少ないことを 逆手にとって、リ・グダン率いる二五〇〇を翻弄する。 だが、その決断をドラクゥは下すことが出来ない。 ﹁殿様、我々に死に場所を与えて頂けるそうで、有り難いことです﹂ 55 ﹁ほんに、ほんに﹂ 集まって来た人熊は、五〇人ほどだ。 ダッダの話によれば森の奥にはもっと多くの人熊が隠れ住んでい るそうだが、急な呼集に応えられたのはこれだけだったという。 皆、死に場所を求めていた。 元は、城詰めの常備兵なのだ。 それが身分を剥奪され、追いやられるようにして森の中で狩人を している。耐え難い屈辱であろうことは、容易に想像がついた。 ﹁殿様、我らが死んで罪を雪げば、きっと邪神さまは帰って来て下 さるんです。ですから、何とぞ今回の戦で華々しく散らせて下せぇ﹂ ﹁足止めでも捨て駒でも、なんでもやります。お願ぇします、殿様﹂ 毒庫の破壊も、危険である。 危険ではあるが、人熊たちの求める戦場ではない。 ドラクゥ自身は、これからの覇業にこの人熊たちの力を借りたい と強く思っているが、一人の男として、彼ら自身が抱える悲嘆も理 解していた。 誇りもなく、名誉もなく、過去の栄光に押し潰されそうになりな がら生きる生は、牢獄のようだろう。ドラクゥ自身が、そうだった。 今、ドラクゥはこうして立てているのは、神の恩寵あったればこそ だ。 その神にも見放された人熊たちに、何を言ってやればいいのか。 死ね。 戦って、死ね。 惨たらしく、死ね。 56 それこそが、彼らの望む言葉ではないのか。 そしてドラクゥはその言葉を掛けてやることも出来るのではない か。 しかし。 ○ ﹁ダッダ、お前に頼みがある﹂ ﹁頼みなどと、殿様。殿様は一言、仰って下さい。死ね、とそれで 我らは、死ねます﹂ ﹁いや、違う。お前に頼みたいのは、毒庫の破壊だ﹂ ダッダが、黙った。 見る間に顔に血が昇り、犬歯が剥き出しになる。それはまるで獣 の表情だ。 ﹁殿様、殿様、殿様!﹂ ﹁お前たちの気持ちは、よく分かる。よく分かるが、これは必要な ことだ﹂ ﹁畏れながら、殿様は何も分かっていない。ここにいる五〇の同胞 が、何の為に集まったか、分かっていない。家族と今生の別れを済 ませて集まった意味が、何も分かっていない!﹂ 悲痛な、叫びだった。 それを見て、人熊たちだけでなく、他の兵たちも色めき立つ。 ﹁分かった、ダッダ﹂ ﹁では?﹂ ﹁神意を、問おうではないか﹂ 57 神意。 そう、神意だ。 彼らは、神に見放されたことを嘆いている。 その悲嘆を晴らせるのは、また神しかいないのだ。 ドラクゥは、自らの差し料をダッダに下げ渡す。 ﹁この剣で、この岩を斬ってみよ﹂ ﹁この岩を、でございますか?﹂ ﹁そうだ﹂ 岩は、ドラクゥの立っていたそれだ。 大きい。 大人の一〇人も乗れるであろうそれを、剣で斬れるはずもない。 ﹁畏れながら殿様、如何に莫迦力の我ら人熊とはいえ、この岩は斬 れません﹂ ﹁だろうな、斬れれば、神意だ﹂ 斬れるはずがない。 人熊たちが、どよめいた。 神意を、量る。運命を占う。 神に見放された後に、ついぞそんな機会は人熊たちには訪れなか った。 それを、今、再び行う。 ﹁分かりました。神意であれば、従わざるを得ません﹂ ダッダの表情が、静まる。 両手で剣を構え、大きく頭上に振りかぶった。 58 ﹁鋭っ﹂ 裂帛の気合いと共に、振り下ろす。 その瞬間、天が轟いた。 ○ 岩が、割れている。 正に晴天の霹靂だった。 ダッダが剣を振り下ろした瞬間、雷が岩を撃ったのだ。 ﹁まさか、しかし⋮⋮﹂ 呆然とするダッダに、ドラクゥは優しく声をかける。 ﹁邪神はお前たちを見放してなどいない。神意は示された﹂ 静寂が、割れる。 人熊たちは歓声を上げ、泣いていた。 心地よいどよめきの中で、ドラクゥは空に崇める邪神の姿を見い 出していた。 ○ これ以上もなく巧く行った。 俺が<雷>で撃った岩は、綺麗に割れている。 59 思わず、安堵の溜息が出て来た。 練習なしのぶっつけ本番。タイミングが合ったから良いようなも のの、失敗していたら大恥を掻くところだ。前世から試験でも体力 測定でも本番に強いタイプだったけど、本当に、上手く行って良か った。 ﹁お見事だね、マスター﹂ ねぎらいの言葉を掛けながら、慶永さんがタオルで汗を拭いてく れる。 自分でも気付かなかったが、緊張で汗をかいていたらしい。 ﹁奇跡の使い方としては満点だね。立派な邪神さましてるじゃない﹂ ﹁立派な邪神、ね﹂ 立派な、邪神。 邪神の立派って何だろうという考えを、必死に振り払う。 今は考えるより他に、するべきことがある。 ﹁ほら、ドラクゥもこっちを見てるよ﹂ 確かに一瞬、ドラクゥと目が合った。 透明化しているはずだが、見えるんだろうか。 俺は、ゆっくりとドラクゥの側に降り立った。もちろん、姿は隠 したままだ。 ﹁ドラクゥ、我の声が聞こえるか﹂ ﹁やはり、邪神さまでしたか。<邪神の雷>、ありがとうございま す﹂ 60 <邪神の雷>? 何だか知らない間に勝手に名前が付いて、しかも恰好良くなって るぞ⋮⋮ そういえば今はカルマがたっぷりあるから気にしてなかったけど、 また五万使っちゃったんだな。節約、節約。 ﹁いや、それはよい。邪神とは、そういうものだ﹂ ﹁そう仰って頂けると有り難く思います。ところで、申し上げたい ことがあるのですが﹂ ﹁ここでは目に付くな。森の中へ入ろうか﹂ ○ 森の中は鳥と虫の声で五月蠅いくらいだった。 俺が姿を現すと、ドラクゥは膝を折り恭しい態度で礼をしてくる。 ﹁まずはこの危急存亡の時に再び降臨頂き、かたじけなく存じます﹂ ﹁よい、我とドラクゥの間柄ではないか。我はドラクゥの邪神、ド ラクゥは我の一の信者。それで、良い﹂ ﹁はい﹂ 演技ではなく、本当にそう思い始めていることに気付いて、俺は ちょっと驚いた。 最初でこそドラクゥの天下統一を横から眺めていよう、と思って いいただけだったのだが、変われば変わるものだ。 少しの間、離れていたからだろうか。それとも、ドラクゥが俺の 為に神殿まで立ててくれたからだろうか。 ﹁ところで、話したいこととは? 随分と物騒なことになっている ようだが﹂ 61 ﹁はっ、実は﹂ ドラクゥの話は持って回っていたので、俺なりに整理する。 アルナハの魔王だったベナンの甥、リ・グダンというゴブリンシ ャーマンが、パザンという街の魔王と結託して川に毒を流そうとし ている。その毒が流されると、川下の泥啜り、という種族がアルナ ハを攻めてくるかもしれない。 それを阻止する為、今からドラクゥたちはパザンの街の近くにあ る毒庫とやらを攻撃しなければならない、ということか。 あの熊みたいな連中は人熊という種族だ、ということも分かった。 ﹁そこで、畏れ多くも邪神ヒラノさまにお願いしたいことがあるの です﹂ ﹁申してみよ﹂ さて、どう来る。 <邪神の雷>で毒庫を燃やしてくれ、とかかな。 それとも、敵の二五〇〇の大軍の兵糧を全て腐らせてくれ、とか。 今の俺なら、ちょっとカルマを持ってるから色々出来るのだ。 ﹁邪神を、邪神を探して来て欲しいのです﹂ ﹁何?﹂ ﹁人熊族の邪神です。彼らの王が祭祀を誤ったが為に、姿を隠され たと。このようなことをお願いするのは筋ではないと承知しており ますが、何分、私の力の及ぶところではなく⋮⋮﹂ おいおい何を言ってるんだ、この魔王は。 危急存亡の時じゃなかったのか。 たった五〇の人熊に、毒庫を襲わせるんだろう? 62 たった五〇〇弱の兵力で、二五〇〇の敵を引きつけないといけな いんだろう? 毒が川に流されるのを、阻止しないといけないんだろう? それがどうして、人熊を、たった五〇人仲間に加わっただけの人 熊の、いるかいないかも分からない邪神を探してくれ、なんて言う んだ? 死にたいのか? 助かりたくないのか? 勝ちたくないのか? それが本当に、今すべき願いなのか。 ﹁それで、良いのか﹂ ﹁はい。お願い致します﹂ ﹁見つからぬかもしれぬぞ﹂ ﹁ならばそれが、人熊の種族としての運命でしょう﹂ ﹁我は、お主の邪神だ。この危急の時に、他に願うことがあるので はないか﹂ ﹁いいえ﹂ ドラクゥが、顔を上げる。 その表情は、どこか晴れやかだ。 ﹁人熊を見て、余は考えたのです。余は、恵まれている、と。邪神 に照覧頂けている、と﹂ 照覧。誰かに、見て貰えている、ということ。 それは、そんなに嬉しいものなのか。 俺自身、誰かに見て貰っていたことがないから、分からない。 63 ﹁魔族の世のことは、魔族の為すべきことです。神意は、あるでし ょう。それは運命として受け容れます。しかしそれに頼るようには なりたくない。為せることを試さず、為せざることを夢想する。そ れは、大魔王を志すべき者の道ではない﹂ ﹁それは、厳しい道だ﹂ ﹁分かっております。それでも、私は、悔いたくない﹂ 言葉が、痛い。 今、気が付いた。 俺は邪神でドラクゥはその信者だけど、中身としてはドラクゥの 方が優れているのだ。 邪神、という立場で、敬語も使われて、俺は、浮かれていたんだ。 恥ずかしかった。 とてつもなく、恥ずかしかった。 恥ずかしさが顔に出そうになるのを、必死に抑える。 ﹁ドラクゥよ。お前の覚悟、よく分かった﹂ ﹁はっ﹂ ﹁人熊の邪神は、出来得る限りの事はしよう﹂ ﹁有難うございます﹂ ﹁それが、お主の選んだ道なのだな﹂ ﹁はい﹂ 分かった。 これが、ドラクゥなのだ。 俺は頷くと、天に舞い上がった。慶永さんも、付いてくる。 ﹁慶永さん、聞いててくれました?﹂ 64 ﹁もちろん。人探しならぬ邪神探し、って奴だね﹂ ﹁そう。手伝って、くれますよね?﹂ ﹁あったり前じゃない﹂ ○ 織物は絹だった。 手ざわりも良く、染めも上手くいっている。染料が良いのだろう。 難しい青が綺麗に発色していた。 パルミナは、満足気に吐息を漏らす。 ﹁よい出来だ。これなら間違いなく、優れた産品となる﹂ ﹁お褒めに与り、光栄です﹂ ここは<淫妖姫>の私室だ。 薫りの良い香が焚き込められ、調度も全てが美しい。配置と光源 にまで拘って、それは均整の取れた一つの総合芸術と言って良い。 文机の上に置かれた薬箱までが彫金に彩られている。 立ち入りを許される者は少ないが、この魔人の御用商人は選ばれ た男の一人だった。 きんす ﹁都を追われてこの辺境じゃ。慰みに、と思うてお主に金子をたっ ぷり撒いておいた甲斐が有ったというもの。こういう見事な織物を、 もっともっと作っておくれ﹂ ﹁かしこまりました、魔王さま﹂ ﹁魔王などとまた仰々しい。この部屋に二人しかおらぬ時は、特に 差し許す。“パルミナさま”で良い﹂ ﹁有り難き幸せにございます、パルミナさま﹂ その言葉が合図になったかのように、パルミナが商人にしな垂れ 65 かかる。 <淫妖姫>の二つ名そのままに、その動きは、ねっとりと淫靡だ。 吐息が絡まるほどに頬を寄せ、パルミナは男に尋ねる。 ﹁ところで、リ・グダンの様子はどうかの﹂ ﹁上手くやっているようです。集めた人数も、二五〇〇を超えまし たようですよ﹂ ﹁傭兵を二五〇〇、な。実際に使えるのはどの程度になるかの﹂ ﹁と、仰いますと?﹂ ﹁良い、こちらの話じゃ﹂ 思索を邪魔されぬように男の口を情熱的に塞ぎながら、パルミナ は打算する。 今回の行軍、リ・グダンは水が使えないことを承知しているはず だった。木桶の注文が殺到していることでも明らかだ。 傭兵が多くなれば、小荷駄も多くなる。ここに水を持っての行軍 となれば、馬も要る。その飼い葉も。 台車でも使うことが出来れば多少は軽減できるのだろうが、パザ ンとアルナハを結ぶ街道はあちこちで泥濘んでいて、その用に適さ ない。 パルミナとベナンが疎遠だったから、ということもある。交通の 便が良いということは裏返せば侵攻しやすい、ということにも繋が るのだ。 人足が足りない分は、傭兵自身に水を運ばせなければならないだ ろう。行軍は、自然と遅くなる。あるいは一部の傭兵は戦意を喪失 して戦闘力自体を失うかもしれない。 それにしても、木桶だ。 窪地の土倉から川へと続く樋も合わせて、随分な量の材木が動い ていた。 66 全て、パルミナの持ち物である。 城市の改築に合わせて村々から供出させた木材を、パルミナは盛 大に放出していた。 リ・グダンは金を借りると恐縮していたが、払われた金は色々な 道を通ってパルミナの元に帰ってくるようになっている。 傭兵の支払いがかなりの額になるが、先払いは半金だけというの が仕来たりになっている。死ねば、残りの半金は払わなくていい。 出来れば全滅して欲しい、とすら<淫妖姫>は思っている。 つまりは、政治なのだ。 リ・グダンに傭兵を集めさせたのも、莫迦なベナンが従軍した< 北の覇王>との戦いの後始末、という側面がある。 アルナハの先代魔王ベナンが決戦に備えて集めた傭兵は、この辺 りで山賊と化していた。しょうがない。故郷を離れて傭兵となった 者は、元の鞘に収まることは出来ないのだ。戦働きの機会がなけれ ば、略奪するしかない。 そういうあぶれ者を、リ・グダンに集めさせる。 出来れば、磨り潰して欲しい。そうなれば、パザンは平和になる。 ︵どっちが勝つだろうか︶ 男の薄い胸板に指を這わせながら、パルミナの思考はここにない。 リ・グダンか、ドラクゥか。 理性は、リ・グダンを推す。手駒の数が違うのだ。ケンタウロス の騎兵まで雇い入れ、今のリ・グダンの兵力はちょっとした城市を 攻め落とせる規模にまで膨れ上がっている。 対するドラクゥは、どうか。 リ・グダンの策に気付くことが出来るかどうかが、一点。気付け たとして、それに対応出来るかが一点。対応したとして、効果的な 策が打てるかが一点。 67 考えれば考えるほど、リ・グダンが有利に思えてくる。 だが、<淫妖姫>パルミナの胸に滾る“女”は、そうは言ってい ない。 かつて魔都の社交界で出会い、言葉を交わしたあの愛らしい男児 のことを、高く評価しているのだ。 情だろうか。 莫迦莫迦しい。<淫妖姫>が、情にほだされる筈がない。 女の嗅覚、とでもいうべきものが<廃太子>を推しているのだ。 そう、自分で信じ込もうとしている。 おこ それでも、この胸の奥に燻ぶる熾りのような感情は、何だろうか。 あの男児を征服したいという願望だろうか。 どう成長しているだろう。 パルミナは歴代の大魔王を毛嫌いしていたが、彼らの美貌だけは 高く評価していた。 <廃太子>は、大魔王家の血筋が濃い。 きっと、美しく成長しているはずだった。 男の首筋をきつく吸い、パルミナは腕の間をするりと抜けた。 もう、そんな気分ではなくなっている。 極上の美酒を想いながら、安酒で喉を焼く趣味を<淫妖姫>は持 ち合わせていない。 ﹁パルミナ、さま?﹂ ﹁続きは、戦が終わってからたっぷりと、な﹂ それだけ言うと手を優雅に振り、事の終わりを告げる。茫然とし た商人は、いそいそと服装の乱れを直し始めた。恋愛には駆け引き も必要なのだ。 68 無様に退室する商人の後ろ姿を見送りながら、パルミナは自分の 中に押し隠しきれない昂ぶりがあるのを感じていた。 ﹁そうだ、物語はいつも偶然に彩られているものじゃ﹂ 思いつきに、自然と笑みがこぼれた。 手元の鈴で、召使いを呼びつける。 ﹁お呼びですか﹂ ﹁うむ、リ・グダンからはまだ土倉を解放しろとは言ってきておる まいな?﹂ ﹁はい。金に糸目をつけずに集め過ぎたことが却って弊害になって いるようです。糧食、小荷駄、それに水。全ての支度が後手後手に なっております﹂ ﹁で、あろうな。分を過ぎた兵は扱えぬ﹂ 分相応不相応というよりも、子飼いの家臣団がいないことの問題 だろう。 所詮魔族は上位者の声の届く範囲でしか戦えない。それはおおよ そ二〇〇人が限界で、それ以上を纏める為にはさらに上位の人間を 置く必要がある。そういう部下を、リ・グダンは持っていない。 兵站、つまりは補給物資をどう融通するかさえ、自分が口を挟ま なければならないはずだ。 それは負担になり、頭の切れを鈍らせる。 圧倒的に不利なドラクゥに、少しでも加勢してやろう。 最上は、共倒れだ。 どちらが勝っても構わないが、精々どちらにも恩を売っておいて やるとしよう。 そう思うと、胸が躍る。 69 ﹁よし、明朝にでも土倉の中身を放ってやれ﹂ ﹁まだ、樋は完全ではございませんが?﹂ ﹁構わん。今でも川に流れ込みはするのであろう﹂ ﹁しかし、一部は途中で垂れ流しになります﹂ ﹁良い。無駄にはなるがな﹂ <淫妖姫>の表情は、獰猛な肉食獣のように歪んでいる。 胸を満たすのは、喜悦であった。 権謀と術策。 種の本質にまで、その歓びは刷り込まれている。 ﹁さぁ、支度も整わぬ内に舞台の幕は開けてしまったぞ。役者たち は、どう踊るかのぉ?﹂ ○ 森の中を駆けるのに、ダッダは明かりを必要としなかった。 人熊は、夜行性ではない。夜目が利くのは、邪神からの賜りもの なのだという。 邪神。 そう、邪神だ。 ダッダは、下された神意を噛み締めている。 剣を振り下ろした瞬間、雷が岩を撃った。つまりその瞬間、ダッ ダは神話に関わったのだ。 ししむら それは、人熊がまだ世界から爪弾きにされていないということの 証しでもあった。 この世界は、神に満ちている。 森の神、夜の神、病の神、風の神、炉の神、蜂の神、肉の神。 70 魔族が魔族として決めることなど、ほんの僅かに過ぎない。魔族 の生活の周囲には神が、邪神が溢れていて、世界の秩序を形作って いる。 だが、人熊にだけ、神がない。種族を見守る邪神がいないのだ。 それはこの世界に人熊の居場所がない、ということそのものでも ある。 世界、宇宙を構成する調和の中に、人熊の席が、無い。 蟻にも、蝶にも、鳥にも、鹿にも神は在る。 見上げる天の隅まで無限に広がるこの広漠とした世界の連なりの 中で、人熊だけが孤独なのだ。 ダッダの父は、邪神官だった。 謹厳実直を絵に描いたような父だったが、厳しさの中に優しさも 滲ませる、そんな父だ。 王が祭祀を怠り、邪神の声が聞こえなくなった直後、父は自ら命 を断った。 怠惰な王を諌める為ではない。 恐怖だ。 死を選ぶ前日、父は泣いていた。 ﹁ダッダよ、人熊は、世界から弾き出される。死ぬよりも恐ろしい ことが待っている。孤独だ﹂ ﹁孤独は死より恐ろしいものなのでしょうか﹂ ﹁恐ろしい。それは、無だ。光も音も香りも触れるものもない魂の 牢獄で永劫の時を過ごすことを想ってみよ。それには、死という終 わりすらないのだぞ。死んでなお、救済がない。これは、恐怖だ﹂ 魂の孤独を恐れて、死に逃げる。 正確に言えば、孤独に悩む生を続けて行くことに怯えたのだろう。 ダッダはそれを、悪いことだとは思わなかった。 71 父の立場に在れば、ダッダも同じことをしたかもしれない。邪神 官とは邪神と人熊の紐帯として生きるのだ。人一倍、邪神のぬくも りを感じる位置にいたのだ。邪神の恩寵の喪失に鋭敏になるのも頷 ける。 間も無く、城市が奪われた。 忌まわしきシェイプシフターの連中に、だ。 当てどなく放り出された時、自死を選んだ父を臆病者と誹った連 中も、初めて事の重大さに気が付いた。森での生活は、厳しく、辛 い。 多くの同胞が命を落とす中で、怠惰な王もまた、死んだ。贅沢に 慣れ切った身体が、変化に耐えられなかったのだろう。 若者の取り纏めをしていたダッダも葬儀に参列したが、式には献 花すらない。統べる民に衷心から見送られることすらなく、王の死 は孤独だった。 ﹁孤独、か﹂ 邪神との繋がりを求め、人熊は健気なまでに一途だ。 狩りの獲物は必ず一番いい部分を捧げた。いつ、戻っていらっし ゃっても良いように、と粗末ながらも邪神殿を森の中に建てさえも した。 それでも癒されない孤独に、人熊は耐えねばならない。永劫に。 そう信じて生きて来たのだ。 それが、覆された。 ダッダの手の内には、今もなお岩を“斬った”時の感触がある。 これは、神話だ。 末代までも語り継がれるべき、神話だ。 いつ死んでも良い、と思う。同時に、この感動を子々孫々に伝え 72 て行かなければならない、とも。 ﹁ダッダ、もうすぐだ﹂ ﹁ああ﹂ 脇を走る仲間が、ダッダに注意を促す。 森は、もうすぐ終わる。そこからはなだらかな下りになっていて、 身を隠すものが少ない。一度、森の端で様子を窺う手筈になってい た。 木々が、切れる。 視界が、開けた。 ダッダの視線の先に、“毒庫”が現れる。大きい。 漆喰で塗り固めた土倉が五つ、月明かりに照らされている。周囲 には柵があり、所々で篝火を背に見張りが立っていた。人数は、決 して多くない。偵察に来た時はまだ未完成だった樋が、ほとんど出 来上っていた。馬も、繋がれている。何かの動きが近いのかも知れ なかった。 急がねばならない。 五〇人の仲間を振り返り、頷く。それだけで、覚悟は通じるのだ。 厳しい森の生活も、まるで無駄ではなかった。 音もなく坂道を駆け下りた。 人熊の足の裏は、音を立てぬよう、獲物に気付かれぬように柔ら かくなっている。 十人一組、五つの隊に分かれ、土倉に近付く。 遮るものは、何もないのだ。相手からは、見られているに違いな い。 見張りの何人かが、慌てたように動き出す。 73 だが、遅い。 つんざ 仲間に合図を、送る。 次の瞬間、耳を劈くような咆哮が轟いた。 人熊の全力の咆哮だ。不意を突かれ、怯まぬ者はいない。 自身も肚に力を入れて雄叫びを上げながら、ダッダは華奢な柵を 力任せに引き倒した。木で作られたそれは、人熊の膂力の前にあま りにも無力だ。 ﹁火だ!﹂ 背中に背負った樽を、力任せに漆喰の壁に投げつける。入ってい るのは、油だった。 隊の一人が火口箱を取り出し、火を付ける。 炎が毒庫を舐めるように広がった。 ダッダは、布で口を覆う。仲間も同様に、煙を吸わないように身 を低く屈めた。毒庫を焼いて、毒が出ないはずがない、という配慮 だった。 他の土倉からも、火の手が上がる。 ﹁ダッダ、拙い、一番奥だ!﹂ 仲間の声が聞こえた時には、もう駆け出していた。 一番奥の土倉を目指した隊が、しくじったのだ。 五つの蔵に、五つの隊。誰も、失敗できない。失敗できないが、 その可能性は常にある。全てを破壊しなければならない。それも一 つ一つを完全に破壊する必要があるのだ。 途中、別の隊から予備の樽を受け取る。 燃え盛る土倉の脇を抜け、樋を潜り抜けようとした所でダッダは 信じられないものを見た。 74 ︵莫迦な、もう、毒が流れている︶ それは月明かりの下でもはっきりとそれと分かるほどに青い液体 だった。 一番奥の土倉から分かれ出た樋を、粘性のある液がゆっくりと流 れて行く。既にかなりの量が、流れているのだろう。液の先端は見 えない。 暗闇を流れる川のように、毒が。 迷いは、無かった。 樋を支える柱に、ダッダは渾身の力で体当たりする。 木材が悲鳴を上げる。木と木と継ぐ木釘が、弾け飛ぶ。 もう一度。もう一度。 柱が歪み、樋が傾ぐ。 四度目にぶつかった時、柱が割れた。 樋が、倒れる。 ダッダは、自分が、どろりとした物を浴びたことを、確かに、感 じた。 ○ 神界の横丁を歩きながら、俺は途方に暮れていた。 ドラクゥには絶対に見つけて来ると約束したものの、どうやって この広い広い神界からたった一柱の邪神を見つけ出せばいいのか。 焦りばかりが募ってくる。 夕暮れに差し掛かった街に、ぽつぽつと明かりが灯り始めた。 こういう所はアナクロで、影の薄い神さまが一つ一つ付けて回っ ているらしい。電気とかないのかな。奇跡で代用しているのかもし 75 れない。 手分けして探す、ということで慶永さんとは別行動中だった。 日が暮れたら前につくねを食べた焼き鳥屋で集合することになっ ている。 今はその焼き鳥屋に向かう道すがら、人熊の神を探しているのだ が。闇雲に歩いても、全く見つかりそうな気配がない。 神界が広すぎるのがよろしくなかった。 慶永さんの説明によると、この神界はこの世界における最大の神 界なのだという。 他にも小さな神界がいくつかあるが、それはひどく小さな仲良し グループが自分たちの為に創って維持している物だったり、恐ろし く偏屈な神さまが自分一人で閉じ籠っている物がほとんだという。 そういうわけなので、広い広い下界、つまりは魔界と人界を合わ せた広大な領域を担当する神さまのかなりの部分がここで生活して いるというのだ。広くて当たり前である。 このどこかに、人熊の邪神がいる可能性が高い、ということだ。 神界の形を大まかに言うと、巨大な円形の盆のような土台の上に、 正方形の街区が乗っている。 街区の中心部にふた回り小さな正方形があり、ここが中心区画。 最初に神界を訪れた時に見た、巨大な神殿やお寺や神社なんかは、 この中心区画にそびえている。街区のどこにいても見えるほどに大 きい。 この造りは、何となく好きになれない。 地図が、整い過ぎているのである。 Simcityで遊ぶ時もわざと歪な街を作って遊ぶ、というの が俺のポリシーなのだ。意味はないが。 76 全体の形が整っているから、と言うわけでもないのだろうが、今 歩いている道も含めてかなり印象がバラバラで面白い。軒を連ねる 店は多国籍というより多世界籍だし、道路の舗装一つとってもショ ッキングピンクのアスファルトで舗装されている所なんかがあった りする。目が痛い。 だが、今は神探しが先決だ。 呑気に遊んでいる場合ではない。 そもそも、どんな顔なんだろうか。 せめてそれだけでも聞いてくれば全然違ったんだろうが、うっか りしていた。 実は、名前だけは分かっている。<左>のエドワード、という。 前世の経験から、何となく役所に行けばヒントがありそうだと思っ たので駄目元で役所に問い合わせたら教えてくれたのだ。が、そこ しょうそいのじょう でも顔までは分からなかった。 ついでに、少初位上にも昇格した。特に何か変わったわけでもな いのだが。 この時間になると、どこから湧いて出たのか横丁は人で一杯だ。 会社帰り、というわけでもないのだろう。みんなマルクント屋で 遊んだり、遊び疲れたような顔をしている。これから夜の街に出て 一杯ひっかけるのだろうか。 この中から、<左>のエドワードを探さないといけない。 まさか神隠しになんか遭っていないだろうな。そう考えると、背 中がゾクリとする。俺も、神隠しに遭わないとは限らないのだ。 しかし、見渡す限りの神、神、神、熊、神である。 なかなか見つからない。 ⋮⋮熊? 77 それは、熊だった。 いや、確かに熊であることは間違いない。間違いないのだけれど も。 ゆうに全長三メートルはあろうかという巨大な“ぬいぐるみ”が 人ごみを縫うようにして歩いて行く。 胸に白い斑紋が三日月を描いているところを見ると、あれはツキ ノワグマのぬいぐるみだ。 速い。 訓練されたサラリーマンがラッシュタイムの駅で乗り換えるが如 きスピードで、軽やかに進む。 ﹁あ、ちょっと、待って下さい!﹂ 声をかけたが、この人ごみに紛れて聞こえなかったらしい。 ふらりと角を曲がったかと思うと、見えなくなってしまった。慌 てて追いかけるが、姿が見えない。 どこかの店に入ってしまったのだろうか。 <左>のエドワードかどうかは分からないが、とにかく、熊だっ た。 これは、大きな収穫である ○ ﹁と、いうことがあったんですよ﹂ ﹁なるほどね。多分、それでビンゴだよ﹂ 言いながら慶永さんは呑み屋のテーブルに角型2号の茶封筒の中 身をひっくり返した。 中から出て来たのは、写真だ。 78 写っているのは、熊のぬいぐるみ。さっき見たのと同一神物で間 違いない。 ﹁これが、<左>のエドワードの写真。人熊の邪神だけど最近は遙 任中。二つ名は、左利きだから﹂ ﹁左利きだからっていうだけで二つ名になるんですか?﹂ ﹁なっちゃうのよね、これが﹂ そう言って慶永さんは一枚の写真を摘みあげる。 そこには、雄々しくファイティングポーズを決める熊のぬいぐる みが写されていた。 ﹁下界に降りない原因も分かった。このエドワード氏、現在最長記 録連続防衛の奇跡禁止無差別格闘技のディフェンディングチャンピ オンさんやってんのよ﹂ ﹁え﹂ ﹁つまり、格闘家。それも最強クラスの﹂ 道理であの巨体で身のこなし、というわけだ。 でも、見つかったのなら話が早い。 ﹁じゃ、早く交渉して下界に連れ帰りましょうよ﹂ ﹁そういう訳にもいかないのよね﹂ ﹁何でですか?﹂ ﹁ヒラボン、腕に自信はある?﹂ ﹁慶永さんも知ってるでしょ。俺が喧嘩弱いの﹂ ﹁私もそっち方面にはあんまり自信がないしなぁ﹂ ﹁腕っ節が何か関係あるんですか?﹂ 慶永さんが、ビールの並々と注がれたジョッキを、一気に飲み干 79 した。 ﹁彼、挑戦者に負けない限りは下界に降りないっていう誓いを立て てるのよね﹂ 46、右と最中と支配人︵A面︶ 二秒。 たった二秒で、目の前の挑戦者は吹っ飛ばされた。 右の一振りである。 漫画的に放物線を描いて飛んでいくでもなく、鈍い音と共にリン グに叩きつけられる姿が生々しい。 全長三メートルの熊のぬいぐるみ、<左>のエドワード氏はやは り強かった。それも、かなり。 ﹁見れば何か対策が浮かぶかもしれない、と思いましたけど。こり ゃ無理ですね﹂ ﹁マスターじゃ無理だね、こりゃ。圧倒的じゃないか﹂ 俺と慶永さんは闘技場を訪れていた。 人熊の邪神、<左>のエドワード氏を下界に連れ戻す為である。 奇跡禁止無差別格闘技、というからどれほどのものかと思ったが、 試合内容は随分あっさりしていた。 相撲とプロレスが一緒になったようなリングの上で、エドワード 氏が雄叫びをあげているのだが、周りは完全に白けている。拍手も ない。それもそうだ。ディフェンディングチャンピオンの防衛戦が、 たった一撃の横薙ぎで決まってしまったら、面白くもくそもないだ ろう。 ﹁しかも、右ですよね﹂ ﹁うん。“黄金の左”も出ないんじゃ、見に来てもなぁという感じ 80 なんだろうね﹂ エドワード氏は最長記録の連続防衛中。多分、強過ぎるんだ。 こんなに圧倒的で、魅せ方も心得ない試合をしていたんじゃ、ど んどん人気はなくなっていく。これじゃ他の選手とか運営とも上手 く行ってないんではなかろうか。 せめてこう、一度は<左>の名に恥じない左の一撃を決める、と か、胸を貸すつもりで挑戦者を実戦で育ててやるとか、そういう要 素は欲しい。 八百長をやれ、と言っているわけじゃなくて、魅せ方の問題だ。 振り返って観客席を見る。 一番前、かぶり付きで見ていたのは俺たち二人だけで、後は後ろ の方にまばらに客がいるだけだ。 酔っ払った爺さん、あくびをする猫、いちゃつくカップル。神さ まもいろいろである。 ここに入る時チケットを買ったのだが、一柱で二〇〇〇カルマ、 自由席のみだった。S席だの二階指定席だとのというチケットも昔 はあったみたいなのだが、横線を引いて消されている。この人気の 無さでは確かにS席に七〇〇〇カルマも払う奴はいないだろう。ち ょっと高過ぎる。 ﹁で、マスター、どうする? この状況じゃ、エドワード氏が負け るのを待っておくっていうのはちょっと難しいんじゃないかな﹂ ﹁それは論外ですね。そもそもまともに試合が成立するような相手 を呼ぶファイトマネーもないんじゃないかな、ここ﹂ ﹁そういうものなの? チャンピオンが強いからそれに挑戦! っ ていう雰囲気でもなさそうだけど﹂ ﹁そういう雰囲気じゃないですね。多分、興行として失敗してるん だと思いますよ﹂ 81 まるで地方のうらぶれたプロレス団体の本拠地の平日を見ている 気分である。 こういうところで防衛され続けるチャンピオンの座に、果たして 意味はあるのだろうか。 そんなことをぼんやり考えていると、向こうから老人が一人近付 いてきた。 恰好からすると、支配人か何かだろう。 ﹁お客さん方、偉く熱心にエド公の試合を見てらっしゃいましたが、 ファンの方ですかね﹂ ﹁ええっと、まぁ、ちょっと違うんですが﹂ ﹁まぁ、そういうのは何でもいいんだ。あのエド公を、何とか負け させてやる知恵はねぇかな﹂ ﹁え?﹂ ○ 奥の支配人室に通して貰ったが、随分と侘び寂びを感じさせる有 り様だった。 デスクはスチール。ソファの皮は破れ、中からスポンジとバネが はみ出している。壁に掛る“一意専心”の額が、空しい。 ﹁悪いね、ちょっと、珈琲切らしててさ﹂ ﹁お構いなく﹂ ﹁お構いなくー﹂ 出て来たのは湯呑に注がれた野菜ジュースとお茶請けだった。慶 永さんはさっそく小さい最中の包みを開けている。俺もこっそりオ ブラートに包まれたゼリーを手元に確保しておく。これは、緑が旨 82 い。 ﹁で、エド公の試合を見てどう思った?﹂ ﹁一言で言うと、華がありませんね。あっさり決着をつけ過ぎだ﹂ ﹁そうだな。他には?﹂ 慶永さんと顔を見合わせる。 他にもも何も、それが全てなのだ。 ﹁他にって言っても⋮⋮ 短すぎて﹂ ﹁そうだよ、それなんだよ、それが全てなんだ﹂ 支配人が力なく俯く。なで肩から、言いようのない悲哀が立ち上 っている。 ﹁エド公はな、それはそれは強ぇんだよ。滅茶苦茶に強ぇ。それこ そ、男のオレが惚れこむほどにな。だが、強過ぎるんだ。相手がい ねぇ。相手がいねぇのに、あいつと来たら毎日毎日修行修行だ。衰 える気配もまるでねぇ。挑戦者は、瞬殺。今じゃもう物好き以外に は試合を挑んできもしねぇ﹂ ﹁はぁ﹂ ﹁オレもな、エド公に注意したんだ。“お前の強さを分かって貰う 為には、魅せ方も大事だ”ってな。そしたらあいつ、“ボク、八百 長は嫌なんです”だよ? あの図体でボク、だぜ?﹂ 一人称が、ボク。 なんというアンバランス。まぁ、ぬいぐるみだからボク、でも良 いような気もする。三メートルだけど。 ﹁手加減しろ、とは言わないさ。勝負だからな。それは分かる。そ 83 れは分かるんだが、何というかこう、思いやりというか、段取りと いうかがだなぁ﹂ ﹁仰る通りで﹂ 強過ぎて融通が利かない格闘家、というのも興行主にとってはや りにくいのかもしれない。 もちろんそれも魅せ方なんだろうけど。 そして慶永さんはお茶請けを食べ過ぎである。もう少し遠慮して 欲しい。 ﹁なぁ、何か良い知恵はないかな。エド公を、負けさせたいんだ。 そうすれば、あいつも分かってくれると思う﹂ 支配人が身を乗り出す。 そうは言っても、相手は最強である。最強を倒すというのは、無 茶だ。 ﹁分かりました!﹂ 声は、隣から聞こえて来た。 慶永さんだ。 ﹁私たちが、何とかしましょう!﹂ 慶永さんの目が爛々と燃えている。 しまった。この人は、こういう逆境が大好きな人だった。 47、ヒトとモノとカネ︵A面︶ 支配人の部屋を後にした俺たちは神界の商店街をぶらつきながら 作戦を練っていた。こうして歩いていると前世と変わらないような 84 気がするが、直立二足歩行するワニや膝下くらいの身長のドラゴン、 全身鎧を着た蛸、二センチくらいのおっさんたちによる大名行列な んかが買い物客に混じっていると、やっぱりここは神界だな、と実 感する。 ﹁安請け合いしちゃいましたけど、何か考えはあるんですか﹂ ﹁それを考えるのが、マスターの仕事だろうに﹂ 屋台で買ったタコ焼きを頬張りながら慶永さんが宣言する。 この辺りの丸投げ感は、前世でもかわりはない。 指揮官である慶永さんが目標を定め、実行部隊である俺が動く。 これが囲碁将棋部の流儀だった。役割分担としては、まぁ上手く行 っていた方だと思う。慶永さんも実際にどう動くかというアイデア を出したりするのだが、その通りにやると碌でもないことになった りする。 ヒラボン、と呼ばれていた高校一年の頃、俺は随分と慶永さんに 振り回されたものだ。たった一年だけなのに、妙に思い出が多い。 ﹁どちらにせよ、<左>のエドワード氏に下界に降りて貰う為には、 負けて貰わないといけないわけだしね﹂ ﹁それはそうです﹂ エドワード氏に負けて貰うには、彼よりも強い相手を当てるしか ない。 そもそもあれだけ強いのだ。エドワード氏に勝てる相手がいるか どうかが疑問だが、いたとしても、その相手を呼ぶ為のファイトマ ネーが不足していた。ただで戦ってくれる酔狂はいないだろう。 支配人が軍資金として出してくれると約束してくれたのはたった の三〇万カルマ。もちろん、後払いである。これでどうしろという のか。 85 ﹁ヒト、モノ、カネ。どれもこれも何にもなしか﹂ ヒトはこの場合、強い挑戦者。モノは勝つ為の仕掛け。カネはフ ァイトマネーなどなど。どれもこれも全くない。何か一つでもあれ ばそこから話を転がして行くことは出来るのだろうが、現状がこれ では不安極まりない。 ﹁マスターは何でも難しく考えるねぇ﹂ ﹁そうですかね﹂ ﹁難しく考えずに、マスターが得意な方法でやればいいんじゃない の?﹂ ﹁得意な方法、ですか﹂ ○ ﹁で、またこれですか﹂ ﹁今回は意味合いが少し違うけどね﹂ 百畳くらいある和室。 碁盤。 そして目の前にはニヤニヤと笑いを浮かべる神々。 ここは、以前俺が荒らしに荒らしたマルクント屋だった。 ﹁兄ちゃん、しばらくぶりやのぉ﹂ ﹁儂ら、兄ちゃんのこと随分と待っとったんやでぇ﹂ ﹁今度は前みたいに勝ち逃げさせへんからな﹂ 何故か怒りのあまり関西弁になっている老神たちを前に、正座し て愛想笑いを浮かべる。 86 まずい。 非常に、まずい。 俺の長い賭け碁生活での経験から、この状況は非常にまずいとい うことは明らかだ。お年寄りがこの状態に入ると、基本的に帰らせ て貰えなくなる。こちらは一人、相手は複数。体力的に俺の方が不 利なのは明らかだった。 ﹁しかし兄ちゃん、強い強いと思ってはいたけど、<戦女神>の直 弟子だったのか﹂ ﹁道理で強い筈だわな﹂ ﹁儂らも直接指導して貰ったことなんかないのにの﹂ 後ろで立っている慶永さんが愛想笑いを浮かべ、手までヒラヒラ と振っている。 慶永さんが碁を神界に伝道した、というのは本当らしい。らしい と言えばらしいのだが、どうしてまた神界で囲碁なんて教えようと 思ったんだろうか。不思議だ。 ﹁で、今日も一局お願いしたいんですが、よろしいでしょうか﹂ 紳士的に尋ねる俺に、暇を持て余した神々は実に愉しそうな笑み を浮かべる。 ﹁もちろんじゃとも。一局と言わず、百局でも千局でも﹂ ﹁ここにおる連中は時間だけは余っておるからの。何局でも相手す るぞ﹂ ﹁もちろん、カルマは賭けるがな﹂ そこで俺ははたと気が付いた。 賭けるカルマがないのだ。 87 いや、正確には八〇〇万ほど持っている。持ってはいるのだが、 これは違う。これは、俺のカルマだ。今回は、エドワード氏を倒す カルマ 為の仕事の一環としてここに来ている。 ということは、自前の徳を積むのはどうにも憚られた。 ﹁どうした兄ちゃん。儂らから巻き上げたカルマはもう使っちまっ たか?﹂ ﹁おいおい、こんなに早くか﹂ ﹁若いって素晴らしいなぁ、おい﹂ 好き勝手に老神が囃したてるが、さてどうしたものか。 と思った時、慶永さんがずいと一歩踏み出した。 ﹁今回はちょっと変わった趣向で打って貰いたいと思います﹂ ﹁変わった趣向?﹂ ﹁そう、変わった趣向﹂ いつものようにニヤリと笑いを浮かべた慶永さんは手早く俺の前 に碁盤をもう一つ並べた。 まさか、この展開は。 ﹁二面打ち、って言えば分かりますよね﹂ 集まったギャラリーがざわめき始めた。 当たり前だ。賭け碁で二面打ち。いくらなんでもここにいる真剣 師たちを馬鹿にしている。 が、慶永さんの挑発は止まらない。 ﹁置きたければ、石を置いても良いですよ。それでも、この邪神ヒ ラノは勝ちますから﹂ 88 勘弁してくれ。真剣師相手に置き石だって? 二面打ちなんていう在り得ない条件を出して、その上にハンデま で付けてやるというのはもう、侮辱以外の何物でもない。 俺が勝つとか負けるとかそういう話ではなかった。相手のプライ ドの問題だ。 ﹁⋮⋮儂らは一向に構わんよ?﹂ ﹁その代わり、相応のモンを賭けて貰えるんじゃろうな﹂ ﹁そうそう。遊びじゃないんだからの﹂ 老神たちの目が妖しく光る。 そりゃそうだ。真剣師たちの場を散々に荒らして、その上にこん な口上。叩き出されても文句は言えない。 慶永さんはと見てみれば、満面の笑みを浮かべている。 ﹁賭けるのは、私よ﹂ は? 親指を立て男気溢れる仕草で自分の胸元を示している。 ﹁私と一晩、一緒に過ごす権利を賭けます。そっちはカルマを積ん でね﹂ いや。 いやいやいやいや。 この人は何を言っているだろう。さっき食べたタコ焼きの中に脳 を侵食する寄生虫でも入っていたんだろうか。 賭け碁に、しかも二面打ちに、自分を賭ける。 いくら俺でも真剣勝負の二面打ちだ。負けることだってある、か 89 もしれない。 そんな勝負に自分を賭けるなんて、絶対にどうかしている。 青い顔をしている俺の耳元に慶永さんは顔を近づけ、そっと囁く。 ﹁信じてるよ、ヒラボン﹂ 顔が引きつる。 血の気が引く。 背中を嫌な汗が伝う。 相手の爺さんたちはニヤニヤと下卑た笑いを浮かべながら慶永さ んを舐めるように見つめている。 負けられない。 絶対に、負けられない。 惚れた女が賭かっているのだ。負けられる筈が、ない。 ☆ 慶永佐織をチップとした賭け碁は佳境を迎えていた。そこに現れ る見目麗しい一人の少女。 彼女こそ、マルクント屋全てを束ねる<賭博神>フォン・マルク ントだった。 エドワードを負けさせるため、興行に助力を願う平乃。 その頃ドラクゥは人熊の部隊に毒庫の破壊を委ね、悲愴ともいえ る覚悟でリ・グダンの軍を迎え撃っていた。 運命が交錯し、新たなる神話の風がここに、吹き始める。 90 第一章ダイジェスト版 黒い。 壁も、床も、天井までも、全てが黒い。 この部屋を設計した者は、どういう意図でこの配色にしたのだろ うか、とザーディシュは考えてみる。 威圧感、孤独感、全能感。 全てが正解で、全てが誤っているようにも思える。 魔都にそびえる大魔城の奥深く、“黒曜の間”で<北の覇王>は 倦怠を愉しんでいた。 この間は、大魔王を支えるべき四天王の一人一人に与えられた部 屋の一つだ。ザーディシュが覇王位に就いた時から、この部屋の主 は彼一人だった。 任地である北にいることが多かったが、最近は魔都に戻ると常に この部屋にいる。 老いた、とは思わない。 トロル族の特徴である長命と不老によって、ザーディシュの肉体 は七十三という歳を重ねてなお、鋼の強靭さを保っていた。 浅黒い肌、錆色の髪、黒曜の角。細身だが、弱々しさは全く感じ はくはつき られない、武人としての容貌を、ザーディシュは誇りにしている。 ﹁こちらに居られましたか﹂ 闇が揺らぐ。 漆黒に満ちた部屋に不似合いな、白。 <北の覇王>ザーディシュの懐刀として知られる、<白髪姫>ラ コイト・デル・アーダだ。 91 ﹁ラコイトか。何か、起こったか﹂ ﹁いえ、特には。北から戻られた、と窺いましたので挨拶に﹂ ラコイトは、トロル族とオーク族のハーフだった。 トロルであるザーディシュも長身だが、ラコイトは女だてらにそ れよりも少し高い。名の通りの白に近い銀髪を長く伸ばし、その姿 は見る者の目を奪う。少し広めの額と知的な眼鏡と合わせ、彼女が 率いる官僚団からの人気は高かった。 もちろん、美しいだけでザーディシュの懐刀は勤まらない。<北 の覇王>が任地と魔都とを行き来する二重生活を営むことが出来る のも、ラコイトが魔都で大魔王府に睨みを利かせているからだった。 ﹁苦労を掛けるな、ラコイトよ﹂ ﹁それは構いません。構いませんが、そろそろ次の大魔王を即位さ せて頂きたい﹂ 国が、持たなくなっている。 ラコイトは言外にそう訴えていた。 魔界、という“領域”と大魔王の統べる“国”はほとんど同じ意 味を持つ。大魔王の支配に従わない化外の民はいても、あくまでも 少数に留まる。 広大な国土、膨大な人口、莫大な富。それら全てが、大魔王とい う一人の魔族を中心に渦巻いている。それが、魔界の在り方だった。 中心のない渦は存在しない。今の魔界は、まさに分裂寸前にまで追 い詰められていた。 ﹁<皇太子>を、か﹂ ﹁はい。お飾りの大魔王でも、いなければ国が﹂ ﹁時だ。時が満ちておらんよ﹂ ﹁そうでしょうか。大魔王府の連中も一部が頑張っているようです 92 が﹂ <廃太子>ドラクゥの廃位は成功したが、大魔王府の文官たちは 頭が固い。女系である<皇太子>レニスの即位には二の足を踏んで いる。 下らないことだ。 王統が絶えたことは、何度もある。その度に史書をいじり、正統 性を喧伝してきたのもまた、大魔王府だったのだ。今更前例にひと つ加えることに、何の躊躇いがあるというのだろうか。 ﹁群臣など捨ておけ。儂の懸念は、他にある﹂ ﹁では、賊ですか﹂ ﹁賊でもない。賊は確かに問題ではあるが﹂ 魔都周辺の賊の跋扈は、目に余る水準に達している。 原因は、税だ。 魔都周辺の民は、絞り取られるだけの税を絞り取られ、賊に堕ち ている。地方からの税が届かなくなっているのだ。各地に散らばる 大魔王の直轄領の税を、近隣の魔王が奪っている。これは由々しき 問題だが、直轄領の代官自身が自分の身の安全の為に税を魔王たち に献納している例すらあるという。 こうてい ﹁群臣でも賊でもない、となると<蝗帝>か夜魔族、ですか﹂ ﹁それこそ問題にもならんな﹂ ﹁では﹂ ﹁<廃太子>、だ﹂ 南に放逐した筈の<廃太子>が、アルナハを得ていた。 93 ただ得た、というだけではない。アルナハに拠っていたゴブリン の魔王を討っての、正式な支配だ。あれだけの大敗から、普通はす ぐに立ち直れるものではない。 ﹁<千里眼>のベナンの甥が復仇に動きましたが、引き分けたとの ことです。糸を引いたのは、またパルミナです﹂ ﹁聞いている。邪神が顕現した、という噂もある﹂ ﹁莫迦莫迦しいことです。神代でもないでしょうに﹂ ﹁︱︱ああ、そうだな﹂ こくびゃくにき 黒髪姫の素性は、秘中の秘だった。 まさかラコイトも自分自身と“黒白二姫”と持て囃される<黒髪 姫>の正体が邪神だとは思ってはいまい。 ﹁ともかく、大魔王の即位の件、御一考をお願い致します。私で支 えるにも、限度がありますので﹂ ﹁分かった。検討しよう﹂ 嵐のように捲し立て、<白髪姫>は去って行った。 ザーディシュは天井を仰ぎ、瞑目する。 大魔王。 そう、大魔王だ。 どうするべきか。答えは、出ているはずなのだ。だが、迷いもあ る。 ﹁<廃太子>ドラクゥ、か﹂ 老いは、感じない。 だが、疲れは抜けにくくなっていた。 自分で動くことも出来るが、それには疾風迅雷の速さが必要とな 94 る。 本来であれば繊細さを求められる仕事だが、ザーディシュは誰か に任せることを考えるようになっていた。 ﹁そういえば、ベナンの甥、というのがいたな﹂ 南に、一石を投じる。 それもなるべく、手間のかからない方法で。 答えは、意外にも簡単に見つかった。 ﹁座興としては、面白いか﹂ 呟いて、ザーディシュは部屋を見渡す。 ﹁大魔城に、空き部屋があるのもよくないからな﹂ それは、素麺だった。 日本の夏に馴染みの深い、あれである。 ﹁ソウメン、召し上がらないのかしら?﹂ 小首を傾げながら、フォン・マルクント嬢はつるりと旨そうに素 麺を啜る。 ガラスの鉢に、たっぷりの素麺。からり、と浮かべられた氷が揺 れる。 転生して、邪神になって、なんで素麺を食べているのか。理解に 苦しむ。 風鈴の音、扇風機。蚊取り線香まである。 95 これは、夏だ。日本の。 ﹁神さまになると、不便がないから困りますわね﹂ ﹁はぁ﹂ 畳敷きに、卓袱台。 濡れ縁の外には朝顔まで咲いている。 なのに、不快な暑さは感じない。俺が、邪神だからだ。 暑さ、寒さ、空腹、眠さ。もろもろ全てを、俺は転生の時に無く してしまったらしい。 ﹁あんなに嫌いだった暑さを、ときどき懐かしく思ってしまいます。 それでこんな部屋を設えさせましたの﹂ マルクント嬢の別宅の一つにある“夏の間”に俺は一人で招かれ ていた。 促されるように素麺を啜る。口の中に出汁の味が広がり涼やかな 麺の食感が心地よい。気が付けば、三口四口と口に運んでいる。 ﹁食べながら、お聞きなさい﹂ うちわを扇ぎながらたそがれるマルクント嬢は、浴衣姿だ。金髪 美少女にも、浴衣は似合う。濃紺の生地に、淡い紫の朝顔が一輪。 襟元から除く肌の白が眩しい。 ﹁︱︱貴方、随分と下界で好き勝手やっているようですわね﹂ 単刀直入だった。 危うく素麺を噴き出しそうになるのを、鍛え抜かれた自制心で堪 える。 96 リ・グダンとの戦いから、大体一ヶ月が経っていた。 確かに、邪神としての領分を越えて俺は下界で好き勝手にやって いる、と思う。 ﹁ほとんど常時顕現して、姿も見られ放題。落雷を始めとした奇跡 も躊躇なく使う。はっきり言って、傍若無人な振る舞いですわね﹂ ﹁仰る通りで﹂ こういう時に下手な言い訳はしない方が良い。だって、実際にや っていることだしな。 でも、譲るつもりはない。 俺は、ドラクゥを見守ると決めたのだ。 ﹁本来であれば、何らかのペナルティを課すべきなのでしょうね﹂ ﹁神が神を裁く、ということですか﹂ ﹁神も邪神も複数いれば社会になります。お互いに気まずい思いを しない為のルールは必要でしょう。あなたはその辺りに随分と無頓 着なようですけれど﹂ ﹁慶永さんの関係者ですから﹂ ﹁︱︱そう言われてしまうと何も言えなくなるのが辛いところです わね﹂ 実際は、違う。 慶永さんは、俺がドラクゥの前に姿を現わしたり、必要以上に関 わったりすることを嫌う。何かの理由があるのだろう。 ただ、ルールに無頓着、というか確信犯的に自分の正しいと思う ことをしようとするのは、慶永さん譲りということで間違いない。 前世で一緒に過ごした高校時代の一年間、慶永さんには色々と教え て貰ったものである。 97 ﹁それはともかくとして、私は貴方に一つ貸しがあります。覚えて いますか﹂ ﹁⋮⋮賭け碁の件、ですよね﹂ ﹁ええ。その貸しを、早速ですが清算しようと思うのです﹂ 借りを返せ、と来ましたか。 先にこっちが拙いことをしているというのを指摘した後だ。難問 を押し付けられるんではなかろうか。慶永さんを同席させない、と いうのもそういう理由だろう。 ﹁内容にもよりますね﹂ ﹁選り好み、出来る立場だとお思いですか?﹂ ﹁少初位の身の上です。出来ること、出来ないことがありますから ね﹂ 俺の答えに、マルクント嬢はやわらかく微笑んだ。 合格、ということだろう。安請け合いする奴には任せられない仕 事ということだろうか。となるとますます難易度が高いような気が する。 ﹁そういう所、嫌いではありませんよ﹂ ﹁それは有り難いお話です﹂ ﹁貴方がヨシナガの一派でなければ、私の部下に迎えたいくらい﹂ ﹁それはご容赦願います。慶永さんには冗談では通じない﹂ ﹁あら大した自信。私の知る限り、ヨシナガはよほど気に入ったも のでないと執着しない性分だと思いましたが﹂ ﹁こう見えて、前世からの仲ですから﹂ 明らかに会話を愉しんでいる。 見た目は少女だが、中身は相当な狸だ。迂闊な答え一つで弱みを 98 握られることにもなりかねない。慎重に、軽妙に。言質を取られな いように選びながら、相手の言葉の白刃を躱していく。 ﹁まぁ、そういうことにしておきましょうか。ところで﹂ ﹁はい﹂ ﹁貴方にお願いしたいのは、この子です﹂ ○ ﹁それで、預かって来た、と﹂ ﹁はい﹂ 慶永さんに、俺は正座させられている。 アルナハにある、俺の為の邪神殿の、一番奥で、だ。恥ずかしい。 エリィナたち邪神官たちは見て見ぬふりをして仕事をしてくれて いるが、時々肩が震えているのが見える。絶対、笑っているのだ。 頑なに顕現しない慶永さんのせいで、俺は何だか誰もいない空中 に向かってペコペコしているように見えるだろう。それは確かに滑 稽だ。 ﹁しかし、<賭博神>が、ね﹂ 慶永さんの視線の先には、居心地悪そうに少年が座っている。 灰色の髪に青い瞳。歳の頃は十四、五くらいか。まるで執事か何 かのようなフォーマルな服装に身を包んでいる。何とも陰気な顔を した少年だ。 これが、マルクント嬢からの“預かりもの”だった。 ﹁神さまを預かってくる、なんて前代未聞だよ? それも格上の﹂ 99 ﹁それを言ったら今の俺より格下な神さまなんてほとんどいません よ﹂ ﹁開き直るなよ、みっともない。と、そんなことより君だ﹂ ﹁え、あ、僕ですか﹂ ﹁そう、君だ。オイレンシュピーゲル。<賭博神>がマスターに預 けてきた、ということは何かしらの問題を抱えているんだろう?﹂ 流石慶永さん。回りくどい聞き方は一切しない。 オイレンシュピーゲル、という名前の少年神は、助けを求めるよ うに視線をこちらに向けて来る。が、俺は小さく首を振った。この 少年がどんな問題を抱えているかは、俺としても知っておかなけれ ばならない。 ﹁えっと、あの、僕はですね、ワーボルト、という土地で神さまを しているんですが﹂ ﹁うん﹂ ワーボルト、というのは確かジョナンの森の西、川を越えた向こ う側の地名だ。 ドラクゥの支配地域と、隣接していると言えなくもない。 ﹁実はその、言いにくいんですが⋮⋮﹂ ﹁どうした?﹂ ﹁⋮⋮魔族に、攻めて来て貰いたいんです﹂ 槌音が響いている。 アルナハの城壁は、大幅に拡張されつつあった。 魔界に於いて都市とは城壁に囲まれた領域のことであり、アルナ 100 ハの市街もまた、壁に囲まれている。ドラクゥと文官筆頭のラ・バ ナンの見立てでは、この城壁の範囲が手狭になっていることが大き な問題だった。 ﹁アルナハを訪れる行商人の数はさらに増えております。それに、 民も﹂ ﹁これまでの方法では収容しきれない、ということか﹂ ﹁単純な広さの問題もそうですが、出店場所を巡る些細な交渉の失 敗で行商人同士が衝突する事例が増えているようでして。裁定を行 う人間を置く必要があります﹂ ﹁お前にその権限を与える、というわけには行かないのか﹂ ﹁畏れながら、既に私の手に余る状況になっています﹂ 文官として優秀なラ・バナンの仕事は日に日に増えている。 問題は、人材だった。 ドラクゥは先の戦いでリ・グダンに敗北を喫している。敵が邪神 を呼んだとはいえ、負けは負けだ。だが、あの戦いの結果は民には 違って見えているらしい。勝利、とは言わないまでも、アルナハに 被害を受けることなく、敵の攻勢を頓挫させたという見方だ。 それは、ある意味では正しい。 ゴナン 南の堅き者との盟約も、良い材料だ。 ルクシュナの功績でゴナンたちがドラクゥと同盟を結ぶことに同 意したお陰で、アルナハは後背の憂いを立つことが出来ている。 目聡い行商人たちがアルナハに目を付けるのも、無理はない。周 辺に溢れる土地を捨てた民たちも流入し、アルナハは俄かに活気づ いていた。 それを上手く差配する人材が、足りないのだ。 文官だけでない。 101 武官も、兵も、何もかもが足りない。 <青>のダッダをはじめとした人熊を臣下に迎えてなお、まだ足 りないのだ。 ﹁当てはないのか﹂ ﹁父の頃の旧臣団には、もう﹂ ﹁他でも良い。質の悪いのも困るが、今は数が必要だ﹂ ﹁それでしたら、ドラクゥ様の方が﹂ ﹁ふむ﹂ 魔都からドラクゥの旧臣を呼ぶ、ということは、考えていた。 既に手紙も送ってはいる。 だが、応じる者がいるかどうかは不透明だった。 城市一つを手に入れたとはいえ、ドラクゥは今や辺境に割拠する 魔王の一人に過ぎない。中央にいれば、魔王ならずとも得られる富 や名声は自然と大きくなるものだ。果たして、誰か一人でもこちら に来てくれるのか。 ﹁地道に探すしかない、ということか。この際だ、行商人や市井の 者からも取り立てねば﹂ ﹁それでしたら、心当たりがあります﹂ ○ ﹁豚、ですな﹂ クォンは開口一番、そう言った。 アルナハの居館でドラクゥは早速、ラ・バナンの推挙した人物と 会っている。 クォン・ヴェルバニアス。ラ・バナンの見つけてきた、コボルト 102 の冒険商人だ。元、と言った方がいいかもしれない。成長の早いコ ボルトにあって、四〇と言うのは既に老境に差し掛かっていると見 て良い。 アルナハを中心に西や北へと隊商を率いてきたが、その財を息子 に譲り渡しての仕官だ。 ﹁豚は既にアルナハでも飼っている。あれはあれで旨いな﹂ ドラクゥは答えながら、豚肉の味を思い出していた。魔都のある 北では、豚よりも羊の肉が上等とされる。ドラクゥ自身、羊以外の 肉を食べたのは<北の覇王>に敗れて以降のことだった。 ﹁数を、もっと飼えばよろしい。これからアルナハの人口は増えま す。米だけでは﹂ ﹁飼うというが、城市の中は手狭だ。豚に割くだけの広さはあるま い﹂ ﹁そこで、森の恵みを使うのです﹂ 冒険商人であるクォンは、“渡河者”でもある。 河を渡り、人の世界を見てきた。魔界にしかないもの、逆に人界 にしかないもの。それを商うことは、胆力は要るが実入りも大きい。 “渡河者”は、人の世界を見ているだけに見聞もまた、広かった。 ﹁人族は、森に豚を放します。森の恵みを食べて豚は育ち、肉質も 良い﹂ ﹁それで、管理はどうする﹂ ﹁しません。村々で放し飼いにされた豚は、共有の財産です。秋に なれば絞め、肉にする。燻製にして冬の食糧とするのです﹂ ﹁アルナハに冬は無いぞ﹂ ﹁それはまさに好都合ではありませんか。必要な時に、必要なだけ 103 獲ればいい﹂ なるほど、見聞があるというのは確かだ。 まだ計画としては雑だが、その辺りは追々詰めれば良い。 犬が立ったような見かけのコボルトは、弱々しい魔族として知ら れている。このクォンは少し毛色が違うようだ。巧く使えば、化け るかもしれない。 ﹁クォン・ヴェルバニアスと言ったか。商人として功績があるそう だな。文官として、その力を発揮して貰おう﹂ ﹁お待ちください、ドラクゥ様。私は、文官としてではなく武官と して遇して頂きたい﹂ ﹁武官、と。軍での経験はあるのか?﹂ ﹁若い頃、軍役に﹂ ﹁では指揮の経験は?﹂ ﹁ありませんな﹂ ﹁⋮⋮それでは武官というのは難しい﹂ ﹁自信が、あります﹂ クォンの目はまっすぐだ。 コボルト属の中でもヨーク氏族に属する老人を、どう遇するか。 悩みどころではある。 今は、一人でも多く計数の出来る文官が欲しい時期だ。しかし、 進んで仕官しようという者の気持ちを挫くのも、本意ではない。 ﹁無給でも、結構。武官の末席に加えては頂けませんか﹂ ﹁そういうわけにもいくまい﹂ ﹁ではせめて、訓練の指図などをさせて下さい﹂ 熱意がある。 104 ここまでの訴えを、ドラクゥは退けることが出来なかった。 ﹁分かった、クォン。お前を武官として召し抱えよう。但し、条件 がある﹂ ﹁何でしょうか﹂ ﹁武官としての仕事の空いている時間は、文官の補佐をするように﹂ クォンが、跪く。 ﹁心得ましてございます﹂ ○ 当たりもあれば、外れもあるのが世の常だ。 ドラクゥはこの日、ラ・バナンの推挙によって参上した者たちと 引見したが、召し抱えられる者と召し抱えられない者は半々といっ た所だった。 ラ・バナンが、敢えて取り混ぜて推薦しているという感覚もある。 どういう人材を勧めるべきか、思考錯誤しているのかもしれない。 事実、ドラクゥの趣味は変わっていた。クォンのように、少し尖っ た者を好む。 ありきたりな人材を取り揃えても、勝てない。 そういう想いがドラクゥを突き動かしている。 タイバンカにせよ、ルクシュナにせよ、ダッダにせよ、皆、尖っ ていた。もちろん、ラ・バナンも、だ。こういう人材を適材適所で 扱えてこその、王道だと思っている。 だが、本当に必要な人材には、なかなか巡り合えない。 人数だけは増える家臣団を見て、いつしかドラクゥは自分が焦っ ていることに気付き始めていた。 105 情報。 武官でも文官でもなく、情報を扱う者が必要だった。 アルナハという僻地に身を置きながらも、中央に通じる必要があ る。そうしなければ、取り残されてしまうだろう。 たとえば<淫妖姫>は魔都に多くの間者を放ち、パザンに居なが らにして政争の機微を把握している。それと同じか、少し劣る程度 の情報が、ドラクゥには必要だった。 そして、出会いはある晩、唐突に訪れた。 手酌で酒を呑むことが多くなっていた。 肴は、月だ。たまに簡単な料理などを用意させる。 アルナハの濁り酒を呑みながら、ドラクゥはこれからの事を考え ていた。 自分のこと。 家臣のこと。 邪神のこと。 そして、国のこと。 考えれば考えるほどに、焦りと無力感が募って行く。 何故悩むのか、と馬鹿馬鹿しく思うこともあった。 ゴナン 例えば、アルナハを治める魔王として自立するという道も、ある。 堅き者との同盟が成立した今、このアルナハを魔都から直接攻める のは、非常に困難だ。軍を送るには遠過ぎる。今の立場でいえば、 恵まれた立地とも言えた。 逆に言えば、ドラクゥもまた魔都に遠い。 ドラクゥがまだ魔都にいた頃、アルナハなど地図の端としてしか 認識していなかった。 106 そんな場所から、天地を窺う。 大それた野望だ。 ドラクゥに流れる大魔王の血のせい、と言えるかもしれない。 それは誇りであり、立場であり、武器でもある。 ただ 国が、乱れていた。 それを糺すには、力だけでは足りない。もし力だけで収まるので あれば、<北の覇王>ザーディシュで事足りるのだ。 魔界は複雑で、混沌としている。 多くの民、多くの神、多くの習俗、多くの伝説。 大魔王家はそれを緩やかに束ねる要石であり、無くてはならない ものとして魔界に君臨してきた。それが最も正しい方法であるかは、 ドラクゥには分からない。或いは、全ての種族から立てた魔王によ る合議、といった方法もあるのかもしれない。 だが、今求められている形は、大魔王による統治だ。 長きにわたり慣れ親しんだ魔界の形に、戻す。 それが出来るのは、ドラクゥしかいない。 大魔王家の血脈に連なる男子は、二人。一人はドラクゥで、もう 一人は叔父だ。叔父は既に出家しているので、継承権は無い。 今<皇太子>を名乗っているレニスは、女系だった。 大魔王の血を男系で引き、継承権を持つのはドラクゥだけだ。 ドラクゥが大魔王に就かねば、魔界は瓦解する。 酒を、注ぎ足した。 数百とも一千を超えるとも言われる諸族と大魔王家の関わりは、 妥協と脅迫の歴史だ。 多くの者は、制度としての魔界に組み込まれている。それでも、 辺境の者は大魔王家、或いは大魔王個人との契約を結び、魔界は成 り立つ。 107 代替わりの度に、辺境の各部族は契約を新たにする為に部族の若 者を魔都に送るのだ。 ひどく素朴で、非効率的な方法だとドラクゥは思う。 中心に大魔王がいて、その周りに諸部族がいる。それが、魔界と いう形になる。大魔王の不在が魔界を混乱させているのも、これが 原因だった。 早く、という焦りがある。 力を蓄え、魔都に凱旋し、大魔王に就かねばならない。 それが、ドラクゥの為すべきことだ、と。 その一方で、魔界が大きくうねり始めているのも、感じる。 <北の覇王>ザーディシュがいつまで経っても<皇太子>レニス を大魔王に就けないことで、魔界はかつての混沌に戻ろうとしてい る。 混沌は一事で、強さと知恵と勇気を備えた者が、全く新しい大魔 王家に代わるものを打ち立てるかもしれない。そういうものをこそ、 民は待っているのかもしれない。 ﹁浮かない顔をしておいでですね﹂ どこから声を掛けられたのか、分からなかった。 右か、左か。 油断なく手元に剣を引き寄せ、気配を探る。 ﹁これは失礼を﹂ 声の主は、意外な所から姿を現した。天井だ。 青い肌に、黒い目。ダークエルフと呼ばれる種族だった。 ﹁ダークエルフ、か。余も会うのは初めてだ﹂ 108 ﹁御尊顔を拝し、恐悦至極に存じます﹂ 天井から軽業のように降り立ったダークエルフはドラクゥに平伏 する。その身のこなしは、何かの舞踊のように優雅だ。 ﹁拙者、ダークエルフ族のシュノンと申す者。主上より命を賜りた く、参上致しました﹂ ﹁シュノン、か。祖父より名を聞いたことがある﹂ ﹁有り難き御言葉。ただそれは、拙者の先代に当たるシュノンかと﹂ 主上、という呼び方が気になった。 本来は臣下が大魔王を呼ぶ時にだけ許される尊称だ。 ダークエルフ、というのは諸族の中でも特別な扱いをされる。 そもそも、出自が魔界ではない。 遥かに西、人界の奥深くでエルフとの争いに敗れた者たちの末裔 だ。 それを十数代前の大魔王が、拾った。 以来、彼らは大魔王に忠実に尽くす種族として知られている。そ の彼らが、大魔王に使うべき尊称を他者に使うだろうか。 ﹁シュノンよ、先ほどお前は余の事を“主上”と呼んだな﹂ ﹁はい、畏れながら、そのように﹂ ﹁何故だ﹂ ﹁我らダークエルフの忠誠は、大魔王の血脈にこそ捧げられており ますれば﹂ ﹁⋮⋮答えになっていないぞ、シュノン﹂ 言いながら、ドラクゥは察していた。 つまりダークエルフは、ドラクゥに賭けた、ということだろう。 109 ﹁畏れながら主上。今や大魔王の血を引く正統な後継者は、主上を 置いて他におられません。なれば、拙者が主上を主上とお呼びする ことに、なんの障害もございません﹂ ﹁そうも行くまい。余は未だ即位しておらぬ﹂ ﹁では、即位の意思はお有りになられる、ということでよろしいで しょうか﹂ ああ、なるほど。 それを確かめる意味もあったのか。確かに、<北の覇王>に対し て大敗を喫して以降、ドラクゥの野心の向きは誰に対しても明らか にされていない。 天下、という言葉を部下や邪神に対して使いはしたが、それは内 向きの事だ。 外から見れば、怪しく動いているようにしか見えなかっただろう。 ﹁ああ、その通りだ。余には社稷を継ぐ意思と覚悟がある﹂ ﹁それを聞いて安心致しました。主上、拙者たちの忠誠をお容れ下 さい﹂ ﹁よかろう﹂ ﹁有り難き幸せ﹂ 仰々しく頷く。 好機、というより他ない。 ダークエルフは諜報に長け、大魔王の耳目として魔界の維持に貢 献してきた種族だ。彼らを抱えることは、今後に大きな助けとなる。 ﹁ではシュノン、早速だが、魔都の様子が知りたい﹂ ﹁畏まりましてございます﹂ 二人の密談は、夜遅くまで続いた。 110 ☆ アルナハの地盤固めを着々と進めるドラクゥに、義理の妹のよう に育ったエリィナから連絡が入る。 邪神ヒラノが、悩んでいるというのだ。 客人神であるオイレンシュピーゲルと、親しい間柄である女神ヨ シナガに難しいお願いを頼まれている様子だという。 その内容は、ドラクゥの軍による人界への侵攻。 今はドラクゥにとっても大切な時期で、おいそれと軍を動かすこ とは出来ない。それを知っているヒラノは反対をしてくれているら しいのだ。 これまで助けて貰ったヒラノに対する礼の意味も込めて、ドラク ゥはこの人界侵攻を自分の方からヒラノに提案するのであった。 111 第二章ダイジェスト版 地平線を見たのは、はじめてだと思う。 風が走り、草が揺れる。 見渡す限りの大草原と天空の境目を、モンゴルの辺りでは天境線 と呼ぶんではなかったか。こんな絶景を自分自身の目で見ることな んて、絶対に無いと思っていた。 西へ向かって、ただただ緑の大地が広がっている。北には雄大な 山々と大きな森林。 これが、人界か。 魔界とは、随分違う。空が明るいのだ。眼下に野生の馬の群れが 走っている。 まずは、人を探さないといけない。人を探して、“聖堂”の実態 を見極める。 慶永さんの敵、“聖堂”。 ⋮⋮見極められたとして、俺は、どうするつもりなんだろう。 そんなことを考えながら飛んでいると、草原で、何かが光った。 槍の穂先だ。 誰かが、槍で戦っている。相手は、ゴブリンだ。 小柄な人間の槍使いが舞うように攻撃する度に、囲むゴブリンが 一体、また一体と脱落していく。 強い。 強いが、あまりにも多勢に無勢だ。二〇以上いるゴブリンに、次 第に押し込まれるように追い詰められている。逃げようにも、辺り は隠れるものなど何もない草原だ。簡単に回り込まれるだろう。 槍使いがじりじりと追い詰められていく。俺が見つける前から戦 い続けているのだろう。既に肩で息をしはじめている。もう、あま り持たないだろう。 112 助けるか? 今なら、まだ間に合う。 そう思った時には、身体がもう動いていた。 介入し過ぎだとか、相手のゴブリンがドラクゥの配下かもしれな いということが脳裏を過るが、知ったことか。 姿を消したまま地上に降り、意識を集中する。 辺りは急に暗くなり、雷鳴が轟き始めた。オクリ神との戦いで負 カルマ けてから練習を重ねた結果、最初から<雷>を使うよりも、<天候 操作>で雷雲を呼びだしてからの方が徳の消費量が少ないことが分 かったのだ。 ﹁⋮⋮<雷>!﹂ 蒼白い電光が、ゴブリンの集団の真ん中に突き刺さる。 当てはしない。戦意さえ奪えば、それでいいのだ。 ﹁なんだこれはっ? うろたえるな!﹂ リーダー格が必死に吼えるが、突然の雷にゴブリン達は浮足立っ ている。 もう一発。 今度は混乱を収拾しようとしているリーダーの足元に狙いを定め、 放つ。寸分違わず足元を雷撃に射抜かれ、ゴブリンは絶叫した。 散り散りに逃げながら、雷雲に向かって雑言を投げつける。 ﹁ヒラノだ! 邪神ヒラノだ!﹂ ﹁逃げろ! ヒラノはゴブリンを祟るぞ!﹂ 酷い言われようである。 とは言え、確かに俺を崇めるドラクゥはゴブリンの魔王を倒した。 113 ゴブリンからすればそういう風に見られてもしょうがないのかもし れない。 全てに好かれようとすると、結局誰からも好かれない、という奴 だ。出来ることなら俺はともかくドラクゥには敵を増やしたくは無 いのだが。 ○ 雨に濡れた草原に、槍使いが平伏している。 姿は見えていないはずなのに、ちゃんと俺の方を向いているのが 不思議だ。ひょっとして、見えているのだろうか。 いずこ ﹁何処の神とは存じ上げませんが、この度の御助勢、まことに畏れ 入ります﹂ 微かに甘さの残る声。 これは⋮⋮女だ。 どうして女、いや体格からして女の子がこんなところで一人でゴ ブリンと戦っているんだ。 それに、あの槍裁き。本当はここで声を掛けずに立ち去るべきな んだろうが、ついつい好奇心の方が勝ってしまう。 ﹁面を上げよ﹂ 短く刈り上げた柔らかそうな草色の髪、勝気そうな大きい瞳、健 康的な乳白色の肌。まだまだ幼さの残る、それは少女だった。 どうして少女がこんなところで一人でゴブリンと戦っていたのか。 少し迷い、俺はぼんやりとした影の形で姿を現すことにした。こ ういう芸当も慶永さんに教えて貰っておいて正解だった。 114 ﹁少女よ、何故お主はゴブリンと戦っていたのだ﹂ ﹁畏れながらお答え致します。それは私、ルロ・バンテンが戦士の 一族に連なる者だからです。近頃、村の近くにゴブリンが流れ着き 略奪や家畜泥棒、しまいには村から若い娘を生贄に出せと脅迫する などと目に余るので、私が退治にしに行くのです﹂ ﹁たった一人で、か﹂ ﹁村を出た時は男衆が何人かいましたが、夜の間にはぐれてしまい ました﹂ ﹁なるほどな。これからどうするつもりだ。村に引き返すのか?﹂ ﹁いいえ。既に戦士である私がゴブリンの住処に向かっていること とっかん は知れてしまったでしょう。村に戻って体制を立て直す猶予はあり ません。このまま、吶喊あるのみです﹂ ふむ。見るからに純朴そうな少女だ。いや、思い込みが激しいと いうべきか。 多分、これは騙されている。本人は戦士の一族だか何かで腕に自 信もあり、ゴブリン退治に出掛けたつもりなんだろうが、実のとこ ろ村人は生贄として送りだしたんではなかろうか。 この様子だと、村に引き返すつもりもまるでなさそうだ。たった 一人でゴブリンに挑むとなれば、末路は考えるまでもない。 見捨てて“聖堂”を探すという道もあるのだろうが、それはどう にも気が引ける。一度助けてしまったのだから、責任は持たないと いけない、という気がするのだ。 ﹁それにしても、雷を操るとはさぞかし名のある神さまなのでしょ うか﹂ ﹁ああ、我が名はヒラノ、という﹂ ﹁ヒラノ様、ですね。近頃は“聖堂”の所為で神々が姿を現される ことも少なく、我々は心細く思っております﹂ 115 そう言うとルロは跪いたまま、俺に向かって祈りを捧げ始めた。 あまね ﹁天と地に遍く神々に感謝を捧げます。今日、この日に大いなる雷 神ヒラノ様を巡り合わせて下さったことを﹂ 祈りの言葉が、心に沁み込んでくる。 カルマ 温かい心地良さがお腹の奥から全身に広がり、力が漲ってきた。 これが、徳か。 今まで魔族の信者しかいなかったから知らなかった。これは、な かなか⋮⋮いや、かなり良いものだ。 ﹁ヒラノ様、このルロ・バンテン。ヒラノ様に帰依させて頂きたく 存じます。よろしいでしょうか﹂ ﹁ああ、特にさし許す﹂ 雨が止み、雲の合間から光が差し始めた。 これは意外に、幸先が良いかもしれない。 ルロは焚き火の準備をすると慣れた手つきで干し肉を炙り始めた。 俺の知らない間に、夕日は傾きつつある。 良い香りが辺りに漂う。革袋の水筒から手鍋に中身を移し、これ も火に掛けた。動物の乳のようだ。そこにパンの切れ端を加え、即 席のシチューを拵えるつもりらしい。 お腹の空かないはずの邪神の身体でも、美味そうな匂いに食欲が 刺激される。 さっきの戦いでルロの馬が逃げてしまったので、ここで野宿をす る破目になった。 草原にまばらに生えている灌木の一本を今日の宿に決め、手際良 116 く支度を進めていく。 ﹁ヒラノ様、お供え物です。粗末なもので申し訳ございません﹂ そう言ってルロが差し出したシチューと干し肉は、お世辞抜きに 美味かった。シチューには適度なとろみがあり、少し塩味のきつい 干し肉とよく合う。 ﹁美味いな。塩の味が効いている﹂ ﹁お褒めに預かり光栄です。ルロたちの先祖が、塩の原の近くに村 を作ってくれたお陰です﹂ “塩の原”というと塩水を湛えた湖が干上がったものだろうか。 アメリカのデス・ヴァレーにそういうものがあったのを思い出す。 海が近くなければ、塩は貴重品だ。そういえばアルナハでは結構な 値段で塩が売られていた。これはひょっとすると、重要な交易品に なるかもしれない。聖堂を見極めに来ただけだったが、これは良い 情報だ。 この情報を活かす為にも、ルロという少女には生きていて貰わね ばならない。 ﹁ところで、明日戦いに行くゴブリンというのは?﹂ ﹁はい。少し前にこの辺りに流れ着いたようで、数はよく分かりま せん。村に略奪に来る時は、大体二〇から三〇くらいです﹂ ﹁今日襲ってきた連中と、同じか?﹂ ﹁ゴブリンの顔の見かけは付きませんが、多分、同じだと思います﹂ ゴブリンの集落のようなものがあるとして、全員を略奪に出撃さ せるだろうか。防禦にも兵を割いていたと考えると、少なくとも五 〇程度のゴブリンがいることになる。どう考えても、少女一人では 117 倒せる数ではない。 ﹁勝てる、と思うか﹂ ﹁はい。雷神ヒラノ様が付いておられますし、私にはこの槍がござ います﹂ ルロは立て掛けていた槍を手に取り立ち上がる。息を、吸って、 吐く。すると槍の周りを小さな青い粒子が舞い始めた。空気に甘さ な が混じる。この感じは、<ジョナンの赤い森>の霧に近い。 カルマ ﹁徳、か﹂ ﹁<風神の槍>、という銘の槍です。戦士の一族に代々受け継がれ てきた秘宝で、強い風の力を宿しています。つむじ風も起こせるん ですよ﹂ ﹁⋮⋮よく持ち出せたな﹂ ﹁はい。ルロは大戦士長バンテンの直系だからです。村にはもう、 ルロより血の濃い戦士は残っていません﹂ てっきりこのルロという少女は体よく騙されてゴブリンの生贄に されたんだと思っていたが、案外強いのだろうか。それにしても、 たった一人で五〇のゴブリンを倒せるとは信じていないと思うのだ が。 ﹁何か、作戦はあるのか?﹂ ﹁いいえ、ルロ一人ですから。乗り込んで、ぶちのめします﹂ ﹁それは随分と頼もしいことだな﹂ 苦笑しながら答えるが、実際にはそう簡単には行かないだろう。 碁で言えば、みすみす取られる為の石を打つようなものだ。ルロが 強いのは昼間の戦闘を見れば分かるが、逆に言えば数で押し包まれ 118 ては勝てないことも分かっている。 雷撃を使えば簡単に追い散らせることは分かっているが、相手は カルマ 俺の事を畏れ、警戒していた。逃げられ隠れられることを考えると、 かなり厄介だ。それに、出来ることなら徳の節約もしたい。 何か、策が必要だ。 考えながら焚き火に枝をくべる俺の横顔を、ルロが物珍しそうに 見ている。 ﹁どうかしたか?﹂ ﹁い、いえ、その、大変失礼なのですが、ヒラノ様が、まるで、普 通の人間のように見えまして﹂ ﹁そうか。ルロの知る神は我とは違う姿をしているのか?﹂ ﹁ルロはいつも神様方を身近に感じてきましたが、こうしてお会い するのははじめてです﹂ ﹁なるほどな。人に似ている、か﹂ ﹁はい。ルロもヒラノ様が雷で助けて下さらなかったら、その⋮⋮﹂ ﹁ただの人間と、間違えていた?﹂ ルロが躊躇いがちに頷き、続ける。 ﹁この辺りは旅人が少なくありません。ヒラノ様の黒髪も、珍しい ですが目立つ程では﹂ ﹁旅人、な﹂ その時、俺の頭に閃くものがあった。 ○ ﹁貴様、どこから来た?﹂ 119 縄で縛られた俺は、ゴブリンシャーマンの前に引き出された。ま だ若い。リ・グダンとどこか似た雰囲気のあるシャーマンだ。 ここはゴブリンの集落の中心にある、粗末なテントだった。いや、 集落というのは言い過ぎかもしれない。これは単なるキャンプだ。 偵察した限りでは女子供はいないし、男たちはみんな薄汚れていた。 どうやらここは、リ・グダンの軍勢から脱落した敗残兵が落ち延び てきた場所らしい。 ﹁えぇ、西の方からです。人間の集落を探していたら、迷ってしま いまして﹂ 精一杯怯えた風を装いながら、俺は捕虜の演技をする。 ブラック企業の元営業としては、これくらいの腹芸はお手の物だ。 ルロの荷物から使い古されたマントなんかを借りて、変装もばっち りだった。 ﹁人間の集落だと? ここから少し西に行った所にあっただろう﹂ ﹁はい、あるにはあったのですが⋮⋮凄い数の兵隊が集まっていて、 入れて貰えなかったのです﹂ ﹁凄い数の、兵士だと?﹂ 俺の情報に、ゴブリン達が色めき慌て始める。 もちろん、ハッタリだ。 彼らが一番恐れるのは、人間が組織だった討伐軍を編成すること だろう。この村にはおおよそ五〇のゴブリン兵が逃げ込んでいるが、 命からがら逃げてきた兵では士気も低く、装備も貧弱だ。 近くの村に大した備えがなければ襲うことも出来るが、数を揃え た軍隊が出てくれば抗する手段は、ない。 ﹁どれくらいの数だ、言え!﹂ 120 ﹁え、えっと、二〇〇より一杯でした﹂ ﹁二〇〇か⋮⋮むぅ﹂ ゴブリンシャーマンが黙り込む。 二〇〇と戦って無事で済むはずがない。そう判断する筈だ。戦意 があれば戦うという選択肢もあるのだろうが、今の彼らにはそれが 一番欠けている。 ﹁⋮⋮一端、身を隠すか﹂ 決断は、予想した通りのものだった。ゴブリンシャーマンは手近 に控えていた部下を呼び付けると、矢継ぎ早に指示を出す。北に広 がる森の中に、拠点を移すというのだ。 ﹁お頭、この人間はどう致します?﹂ 年嵩のゴブリンの問いに、シャーマンは気味の悪い笑みを浮かべ た。 ﹁生きたまま、連れていくさ。大事な大事な非常食だからな﹂ 邪神の身体なので食われることは無いとはいえ、何とも物騒なこ とをいう奴である。俺なんて食べてもそんなに美味しくないと思う のだが。 ○ キャンプから北の森へ向かうには、小高い二つの丘の間を抜ける のが近道だ。この道を通らなければ、かなりの遠回りをしなければ ならない。ゴブリン達は慌てているのか、斥候も出さずに丘の間の 121 隘路に歩を進める。 と、先頭のゴブリンが立ち止まった。行軍の列を塞ぐように、誰 かが立っている。 ﹁退けっ、人間の小娘! 死にたくないならな!﹂ ま みこと もち つじかぜ たま ゴブリンたちはギャアギャアと叫びながら、手槍を構え始めだ。 かみづま だが、目の前の少女、ルロ・バンテンに慌てた様子は無い。 あまつくに ﹁天津國に神留り坐す、風の神リルフィスの命以て、辻風を呼び給 え﹂ ルロが唱えると、構えた槍の周りに青い光が渦巻きながら集まっ て行く。ゴブリンがその様子に驚いている内に、俺はこっそりと縄 を抜けて丘の上に脱出する。全ては、打ち合わせの通りだ。 ﹁出でよ、神の旋風!﹂ 少女の者とも思われぬ大音声でルロが叫ぶとともに、凝集した光 の粒が激しく明滅しながら突風へと姿を変える。 地面に転がった石が礫となり、ゴブリンの隊列に殺到する。いや、 それがなくても立ってはいられない。必死に身を縮めて伏せている が、目すら開けていられないだろう。 ﹁吹き、飛べぇぇぇぇぇぇぇっ!﹂ ルロが裂帛の気合で、大きな魚を釣り上げるように槍の穂先を持 ち上げる。すると旋風の向きが変わり、ゴブリン達を巻き込んだま まで上空へ吹き荒ぶ。 これはもう、竜巻だ。 122 正直、ルロの槍に秘められた力がこれほどのものだとは思わなか った。 餌食となったゴブリン達の姿は、もう見えない。生きては、いな いだろう。 力を使い果たしたように、ルロが槍を取り落とし、そのまま地面 にへたり込む。 俺は慌てて彼女を支えに向かった。 ﹁⋮⋮ヒラノ様、やりました。ルロは、ルロは、ゴブリンを一匹残 らず退治しました﹂ ﹁ああ、そうだな。よくやった﹂ ﹁良かった、神様に褒めて貰えた⋮⋮これで⋮⋮﹂ ﹁これで?﹂ ﹁⋮⋮これで、“聖堂”の神官になってしまった父も、赦されるで しょうか?﹂ 物が動き始めている。 北のパザンや南のバァル・ゴナン、さらには東のキリ・シュシュ ツからの荷物がアルナハに再び流れ込みつつあった。市には商品が 並び、それを求めて人が集まる。するとそこに需要が生まれ、また 近隣から商品が流入するのだ。それは、良い傾向だった。 賊の討伐が、一定の成果を上げている。捕らえた賊に土地を貸し てやるという策が当たった。 今は賊に身をやつしているとはいえ、元は皆農民なのだ。土に親 しんで生きてきた者たちの両手に開墾用の斧や鍬を与えてやれば、 剣に持ち替える必要はなくなる。 123 ドラクゥは、その分忙しくなっていた。 食事さえも執務室で摂る。 決裁をしなければならない事柄は以前よりも増えていたし、何よ りもラ・バナンの“病臥”が響いていた。アルナハの街はまだまだ 拡大を続けており、それだけに闇雲に署名をするというわけにはい かない。不明な点があれば担当する部下を呼び出し、説明を受ける。 そこに新しい基準や枠組みが必要であれば、ドラクゥ自身が方針を 示してやった。 何かを創り出しているという充実感は、ある。同時にこれだけの 仕事をラ・バナンに押し付けていたのだ、という感慨もあった。 部下を育てなければならない。これは、切迫した問題だった。 策略の為、ラ・バナンにはもう少し自宅で療養を続けて貰う必要 がある。ドラクゥはその為に、一人の若者に自分の仕事を積極的に 見せるようにしていた。 ﹁シュリシア、任せていた検算はどうだ﹂ ﹁はい。小職の検算した結果、先程出ていた誤差は単純な計算の間 違いというよりも支出の細目の間違いだったようです。間違いを犯 した者の上司に、教育を再度行うように伝えます﹂ 打てば、響く。 ドラクゥが目を掛けているシュリシアというリザードマンの若者 は頭が良い。数字に明るい、記憶力が良い、というだけでなく、物 事の全体を捉える能力を持っている。これは訓練で身に着くという よりも才能によるところの大きい領分だ。ラ・バナンとはまた違っ た意味で官吏に向いている。 元は、奴隷階級の出だという。 奴隷と一口にいってもリザードマンの身分階級は複雑で、外から 124 見ても簡単には理解は出来ない。シュリシアは奴隷の身でありなが ら読み書きの教育も受けている。 魔界の南部には、リザードマンが多い。 今後はこのシュリシアのように、使える人材はどんな出自からで も陣営に加えるというのがドラクゥの方針だった。 ﹁シュリシア、次の仕事はなんだ?﹂ ﹁はい、地元の有力者からの進物の検分にございます。それが終わ れば、少し遅いですが昼食を﹂ ﹁つまらん仕事だな﹂ ﹁それでしたら小職が目録だけ作って後ほどお渡し致しましょうか﹂ ﹁⋮⋮よい。これも仕事だ﹂ 昼食の誘惑を堪えながら、ドラクゥは進物を運び込むようにシュ リシアに促す。 賊の出没は皮肉なことに、ドラクゥの権威を高めていた。 自力でリ・グダンの賊軍を打ち払えない豪族や領主にとって、今 よしみ では“アルナハのドラクゥ”といえば一種の庇護者として受け容れ られつつある。進んで誼を通じようと考える者も増えて来ていた。 この現象にドラクゥは満足していたが、問題がないわけでもない。 きた 友誼を結ぼうと考える者が次から次へと使者をアルナハに送って くるせいで、日程の調整に支障を来すほどになったのだ。ただでさ え決裁せねばならない事項の増えているドラクゥには頭の痛い問題 だった。 そこで、とくに重要だとドラクゥの判断した相手以外にはエリィ ナがドラクゥの代理として謁見を受けている。新興の邪神、<雷鳴 >のヒラノの邪神官長という肩書きは今や辺土ではそれだけの影響 力を持っているのだ。 シュリシアの指図で、部屋に次々と荷物が運び込まれて来た。 125 書記官が贈り主の名を読み上げ、ドラクゥが一つ一つを検分して いく。 ドラクゥに会えないとなれば、代わりに進物、いや貢ぎ物に力を 入れる者が現れるのは当然の成り行きだった。金穀にはじまり、刀 剣、鎧などの武具、壺や書画といった芸術品に到るまで贈られるも ワイン のの幅は広い。魔界南方では手に入りにくい筈の北方の産品である 葡萄酒などもあり、贈り主たちの気魄が伝わってくるようだ。 ﹁シュリシア、その箱はなんだ?﹂ ドラクゥの目に留まったのは、進物の中でも一際大きな箱だった。 箱自体にも金が掛かっている。その堅さで加工の難しいベルガン ヒノキ材を丁寧に削り出し、木目を際立たせるように細工まで施す 念の入れ様だ。 ﹁随分と厳重に封がしてあります﹂ ﹁誰からの進物だ?﹂ コボルトの書記官は小さく首を振った。予定にない進物だという。 ﹁いかが致しましょう、ドラクゥ様﹂ ﹁誰にでも手違いはある。開けて、中身を確認するとしよう﹂ かなけ 人数が集められ、道具で木釘が抜かれていく。金気を使わずに献 納品を梱包するという方法は、本来は大魔王家に対して行われる古 い作法だった。ドラクゥでさえ、書見でその存在を知っているだけ だ。 ﹁ドラクゥ様、間も無く開きます。中に賊が入っているやも知れま せん。念の為、小職の後ろに﹂ 126 いにしえ ﹁良い。賊であれば古の作法まで守って、これだけ手の込んだ真似 はするまい。それに、自分の身くらいは自分で守れる﹂ ﹁はい、失礼致しました﹂ そう言って、ドラクゥは柄頭に手を添える。 <破神の剣>はオクリ神との戦いで喪ってしまった。今の剣は鍛 造の上質品だがまだ腰の重さの違いに慣れない。 ﹁では、開きます﹂ シュリシアが合図をし、蓋が慎重に外される。 箱は巧妙な仕組みが施されており、上蓋が外れると共に四方の壁 も倒れるようになっていた。 ゆっくりと壁面が引き倒される。 その中に入っていたものの美しさに、ドラクゥは思わず息を呑ん だ。 ドラゴン 濃紺の流れるような長髪と、そこから聳える一対の象牙のような 角。 柔らかそうな白磁の肌に、怜悧な瞳。 上背のある肢体を包む衣装には見事な竜の刺繍が施されている。 その姿は静かな威厳に包まれ、見る者に畏怖さえ与えるような美 しさを湛えていた。 ドラゴン・ハーフ ﹁⋮⋮竜裔族、だと﹂ ドラゴン ドラクゥをして、始めて見る。 天翔ける竜の血脈を引くと自称するこの種族は、その性質も竜族 に似て長命だが子が少ない。それ故に、ほとんど現存していないと いうのが魔界での常識だった。 127 シュリシアに目を向けると、酷く戸惑いながらも跪いている。自 ドラゴン・ハーフ らも竜の血を伝えると名乗るリザードマン族にとって、より色濃い 空の覇者の血を持つ竜裔族は、崇敬の対象でさえあった。 ドラゴン・ハーフ 視線を竜裔族の娘に戻す。 気高い雰囲気を纏った少女はしかし、絶対の支配者に対するよう に優雅に腰を折った。 わたくし ﹁突然の訪問、平にご容赦下され。私はラーナ。ラーナ・エンデル ケ・ガ・クランシュファイルと申します。主上の側妾の端に加えて 頂きたく、こうして忍んで参りました﹂ ☆ ルロの故郷、戦士の一族の村へと向かうヒラノ。 その途中、ヒラノは奇妙な二人組に出会う。 借金の取り立てである。 邪神になる為に膨大な徳を前借したヒラノに返済を迫る彼らから、 ヒラノは唯一神が予想外に大きな力を持っていることを知るのであ った。 一方、ドラクゥは<淫妖姫>パルミナとの熾烈な謀略合戦に巻き 込まれつつあった。 賊徒を率いるリ・グダンも加わり、アルナハ周辺は再び戦乱の渦 に巻き込まれようとしている。 128 第三章ダイジェスト版 東に大きく迂回する進撃路を選らんだ。 ほとんどリザードマンの領域と言っていい道を、リ・グダン率い る元傭兵二〇〇〇が進んでいく。賊徒は連れていない。隠密裏の軍 事行動に、錬度の低い山賊紛いの連中を同道することは出来ない。 狭い道を使った行軍だ。元より伴えるのは二〇〇〇から三〇〇〇が 限界で、それ以上の軍を会戦に投入したければ分進合撃をしなけれ ばならないのが定石だ。 だが、今回に限ってリ・グダンは配下の賊徒たちと合撃するつも りはなかった。それよりも彼らには彼らに似つかわしい任務がある。 略奪だ。 こちらの戦力が減っている、と錯覚させる為にリ・グダンは苦心 して賊徒の略奪件数を調整し続けていた。多く奪い過ぎたら減らし、 減ったと見せかけて裏を掻き、分捕った食料を賊都カタニアに少し ずつ蓄えて、長距離の軍事行動が可能なまでに準備を整えたのだ。 その分、配下の賊徒は飢えている。略奪品を上納させられ、彼ら の苛立ちは痛いほどに伝わってきた。それを解き放つ。引き絞られ た矢は、放たれるしかない。暴力の奔流となってドラクゥの勢力圏 に雪崩れ込む賊徒の数は、おおよそ四〇〇〇。これだけの数を支え きれる兵を出してしまえば、アルナハは空城になる。 練りに練った作戦だった。 拠って立つ大城市を持たぬリ・グダンにとって、ドラクゥの首を 取るには策が不可欠だ。その為には、民に泣いて貰うことも厭わな い。ドラクゥを今度こそ叩き潰すには、非情さも必要だった。 ﹁カルティア、首尾はどうか﹂ 129 ﹁万事順調です。ドラクゥが民に優しいことが幸いしました﹂ 副官であるハーピィのカルティアには荷駄の全てを統括させてい る。その任務には“糧食の調達”、つまりは略奪も含まれていた。 賊徒に派手に暴れさせるのは目晦ましと同時にこちらでの略奪の印 象を薄める狙いもある。 軍隊というものは、存在するだけで厄介なものだ。 一日に三食。切り詰めて二食にしても、それが三日四日と続けば 戦闘力が低下する。筋肉に鎧われた兵士の肉体は常に滋養を求め、 胃袋はいつも空っぽだ。言わば軍隊という巨大な生き物が暴食の限 りを尽くすと言い変えてもいい。収穫の時期なら田畑から刈り取り ながら、そうでない時には村々を荒らしながら軍隊は進んでいく。 少なくとも、カルティアの育った魔界北部ではそれが当たり前の姿 だった。 うそぶ ﹁村々の蔵には米が蓄えられております。“火急の場合に備えて” と嘯いておりましたのが﹂ ﹁村が略奪されるよりも“火急の場合”があるとも思えんな﹂ リ・グダンは忍び笑いを漏らす。 付き従う二〇〇〇の兵は皆、眼が爛々としていた。賊徒などと呼 ばれながら、辛い逼塞生活を共に過ごしてきた部下たちだ。ドラク ゥの首級を上げ、何としても報いてやりたい。その為には、必勝を 期す必要がある。 必勝。そう、必勝だ。 あの<淫妖姫>の下らない策も、今は利用してやる。返す刀であ の“毒婦”の首も落としてやらねばならないが、今は眼前のドラク ゥのことに集中せねばならない。 130 カルティアにもサーフォートにも明かしていないが、今回の出兵 にはパルミナの陰からの支援があった。賊徒が集めてきた糧食や物 資では足りない部分については、パルミナに用立てて貰ったのだ。 輸卒を束ねるカルティアなら、恐らくは気付いているだろう。 だが、<淫妖姫>パルミナの支援はそれだけではない。ドラクゥ に美姫を献じ、それに毒を盛らせるというのだ。遅行性の、毒殺と 気付かれにくい毒だという。 ドラクゥは、これを見抜く。それはほとんど確信ともいえる予感 だ。こんな毒程度でくたばる<廃太子>ではない。逆にドラクゥは 策にかかった振りをする。これもほぼ間違いがない。その上で、味 方さえ欺く為の流言蜚語さえ使ってみせるはずだ。そんなことは、 お互いに読み切っている。 だがそこに、隙が出来る。 敵の将全員が、<廃太子>ドラクゥなのではない。主が病に倒れ たと聞けば、浮足立つ者も出るだろう。その、あるかなしかの隙を 突く。その為の精兵二〇〇〇であり、その為の囮の賊徒四〇〇〇だ。 邪神オクリもご照覧あれ。これぞ鉄壁の策であり、必勝の策だ。 道は緩やかに南下を続けていたが、不意に西に折れる。 このまま西進すれば、アルナハの北に出ることが出来る道だ。リ・ グダンの軍は夜魔のサーフォート率いる前衛五〇〇を先頭に、粛々 と行程を消化していく。 ﹁伝令! リ・グダン様、目の前に川がございます!﹂ サーフォートからの伝令がリ・グダンの元に駆けてきたのは、正 午を少し過ぎた時分だった。森の昼は蒸し暑く、伝令も汗を拭いな 131 がらの報告だ。 ﹁川、か。渡れそうか﹂ ﹁はっ。底は浅く流れもそれ程ではないのですが、ところどころ深 い所がございます。サーフォート様は半時もあれば安全な渡渉点を 見極められる、と﹂ 森の中の川は、しばしば流れを変える。そこに生えていた木は緩 やかに根が腐り、枯れてしまうのだが、その時に根の張っていたと ころに空洞が生じることがあった。それと知らずに足を取られると 助からないこともある。そういう危険のない道をサーフォートは探 ろうというのだろう。 ﹁分かった。サーフォートにはそのまま調査を続けるように伝えろ。 それと、全軍に大休止を取らせる。日の出から歩き詰めだったから な。ここで弁当を使う﹂ 二〇〇〇の傭兵に、弛緩した空気が流れる。今回の攻勢が秘密裏 のものであることは一兵卒に到るまで徹底していた。慌てず、しか し急いで。この背反した命令は士気の高い部隊であっても極度の緊 張を強いる。それが、緩んだ。 二人目の伝令がリ・グダンの元に辿り着いたのは、大休止の命令 が全部隊に行き渡った正にその瞬間だった。 ﹁伝令! 舟に載った敵部隊が川を南下してきました! 総数は不 明! 現在、サーフォート様が交戦中です!!﹂ 考えるより早く、身体は動いていた。 132 腰に佩いた剣を抜き放ち、<青>のダッダは舟から飛び降りる。 茫然とした顔でこちらを見るのは、武装した夜魔の軍勢だ。味方で はない。であるならば、敵だ。リ・グダンの手勢か。 裂帛の気合と共に、先頭の一人を斬り飛ばす。返り血が、青い毛 皮を朱に染めた。 ﹁野郎ども、舟から下りろ! 人熊、突撃!!﹂ 咆哮にも似たダッダの号令に合わせ、配下の人熊二〇〇が一斉に 舟から飛び出す。 大森林を縦断する小さな道と川とが交差する地点で敵と鉢合わせ したのは全くの偶然だった。こういう遭遇戦の場合、混乱からどれ だけ速やかに立ち直るかが勝敗を分ける。今のところ人熊は、機先 を制することが出来たようだ。 ﹁押せぃ! 押しまくれっ!﹂ 手近な敵に剣を突き立てながら、ダッダは二〇〇の兵で敵の隊列 を押し返していく。 難しく考えるまでもなく、これは喧嘩と同じだ。出会い頭に相手 の鼻先を殴りつけ、戦意を喪失させる。それが最良の手段で、ダッ ダはそれを軍としてやるだけだ。 道の幅は狭い。敵がどれだけの兵力を擁していようとこの広さで は自由に兵を動かすことできないはずだ。つまりは敵の大半を遊兵 の状態にしておくことが出来る。逆に、押し込んでしまわなければ ダッダの方が危うい。手勢は僅かに二〇〇で、しかも後背には浅い とはいえ川を背負っている。夜魔は魔界でも精強な種族として有名 だ。ここで押し戻されると、立て直すのは難しい。 一人、また一人。混乱から立ち直る前に、殺とれるだけ殺とって 133 おく。 ドラクゥが病に倒れたという知らせを受け、ダッダはアルナハに 退く途中だった。ル・ガンと協力し、アルナハの守備を固める。ド ラクゥが指揮を執れない隙を突いて、リ・グダンかパルミナが攻め て来ないとも限らないからだ。 それが、思いもかけずこんなところで敵と出くわした。随分と出 来過ぎた話だ。 ﹁⋮⋮こいつも、ヒラノ様とエドワード様の加護か、ねッと﹂ 後ずさる夜魔の首を刎ねながら、ダッダはその手に神意の感触を 思い出す。倒すべき敵がいて、自分は剣を持っている。全てはそれ で説明が付く。これは邪神の意志であり、ダッダの役割は敵を討つ ことだ。 剣を持つ者、戦斧を持つ者、棒を持つ者。部下はどいつもこいつ も血に飢えた良い面構えをしている。森に散っていた人熊族を結集 し、ダッダはそれを精兵に鍛え上げていた。 ﹁人熊ァ、前へッ!﹂ ﹁人熊、前へ!!﹂ 鬨を上げ、一歩進む。脆い。血飛沫が舞い、さらに一歩進む。率 先垂範。人熊の英雄、<青>のダッダは隊の最前列で後続の同族に 殺しの手本を余すことなく見せつける。 また、一歩。今度は少し抵抗がある。目を細めれば、隊列の後ろ で指揮を飛ばす夜魔が見えた。この隊の将だろう。アルナハへの土 産に、一つ首級を挙げてやろうか。 と同時に、ダッダの中の冷めた部分は潮時も測っている。夜魔の 後ろには槍を構えたオークが隊伍を組んでいるのが見えた。これは 134 大軍だ。少なくとも、一〇〇〇、多ければその倍。先陣の夜魔をど れだけ磨り潰したところでそれではダッダの自己満足にしかならな い。 ﹁人熊ァ、前へッ!﹂ ﹁人熊、前へ!!﹂ もう一度、敵を押し込む。そして相手の押し返す力をいなすよう にして、ダッダは半歩下がり、剣で相手の膝下を斬りつけた。蹈鞴 を踏む夜魔に圧し掛かるようにして後続の敵が倒れ込む。 ﹁野郎ども、舟へ! 舟へ!﹂ まるでそれが最初から既定の行動であったかのように、ダッダは 速やかに兵を退いた。戦いは、全てが呼吸だということをダッダは 肌で感じている。それは死地を越えた時に身に付けた感覚だ。乱戦 に縺れ込めば夜魔族相手と言えどもっと被害を与えることは出来る。 だが、今はそれをするべき時ではない。一発殴って、後は勝ち逃げ する。 退却も思ったよりは手間取らない。押し込んでおいたお陰で、整 然と下がる広さの余裕はある。敵将がダッダを悪罵しているようだ ったが、知ったことではない。戦争は、力量が拮抗していても運で 全てが引っくり返る。今回はたまたま、ダッダの方が幸運の尻尾を 捕まえることが出来ただけなのだ。 部下が全員舟に乗り込んだことを確認して、ダッダも舟に飛び乗 る。散々威嚇しておいたお陰で、追ってくる気配はまるでない。そ の気があっても、こちらは川下りだ。並の足で追いつけるものでも なかった。 135 ﹁しかし、こいつは厄介なことになったな。ル・ガンの旦那の予想 が当たったってわけだ﹂ リ・グダンが動くということは、目標はアルナハしかない。この 舟足なら十分に先に辿り着くが、この部隊だけが敵ということもな いだろう。別働隊がアルハナを既に包囲しているかもしれないのだ。 ﹁急げ、アルナハに戻るぞ!﹂ 水夫をしている<堅き者ゴナン>が頷く。十人ずつ人熊を載せた 二〇艙の平底船は、アルナハに向けて速度を上げた。 ☆ 人族としてははじめての信者となったらルロを連れ、ヒラノは彼 女の暮らす戦士の一族の村を訪れる。 しかしそこは“聖堂”との戦いの気配に包まれていた。 そこでヒラノは槍の名手であり、村に唯一残った<風の神>リル フィスと知り合うことになる。 136 第四章ダイジェスト版 襲撃者たちは、ごく普通の行商人の格好をしていた。 まだ朝靄に包まれているアルナハ政庁に闖入してきた賊の数は、 十七。多くはないが、決して少なくもない。音もなく門の守衛に忍 び寄って喉首を掻き切る手管は、シェイプシフターのそれだ。 本来であれば一〇を超える賊の侵入を許したとあっては防禦の責 任者であるシュリシアの監督責任が問われる。が、相手は変幻自在 のシェイプシフター族である。容貌に体格はおろか声音に雰囲気ま で他人に似せられるとあっては、並の守衛ではその正体を見破るこ とは不可能だ。 防禦する側の注意が最も散漫になる払暁の時間だ。<淫妖姫>パ ルミナ子飼いの暗殺者たちは流石と思える迅速さで政庁の正門から 中へと侵入した。狙うは病に伏せるドラクゥの首級ただ一つ。 しかしその様子をダークエルフのシュノンは二階の踊り場からは っきりと見つめていた。 ﹁放てっ!﹂ シュノンの号令一下、ダークエルフの放った矢がシェイプシフタ ーに降り注ぐ。黒装束に身を包んだ青い肌の狩人たちは、皆が弓の 名手だ。エルフ族にこそ勝ちを譲るものの、それ以外の種族には決 こわゆみ して負けないという自負がある。鍛え抜かれたダークエルフの膂力 を恃まねば引くことすらできない強弓の一撃は重く、シェイプシフ ターを刺し貫いて後ろの床にまで突き刺さる。 スライム だが敵はシェイプシフターだ。 軟体種族に名を連ねる彼らは、射抜かれた矢をものともしないか 137 スライム のように身体の形を変え、床に縫い付けられた状態から復帰する。 低級な軟体であればごく普通の動きであるが、高等な身体の構造 を模倣するようになったシェイプシフターにとって、ありえない形 に身体を作り変えるには激しい痛みが伴うことをシュノンは知って いた。 それでも一切の躊躇なく身体の変形を、それも無言でしてのける 敵の練度は高い。 ﹁放てっ!﹂ こわゆみ 部下の放つ強弓が再び唸りを上げ、哀れな襲撃者たちの影を床に 縫いつける。めりめりと音を立て、変形し切れない骨を剥き出しに しながら、シェイプシフターは声を上げずに再びそこから抜け出そ うとした。 ﹁放てっ!﹂ 間髪入れずに、シュノンは三度手を振り下ろす。容赦も呵責もな い。 これは、私闘だった。 本来ならばアルナハの政庁にまで敵を引きずり込まなくても、ド ラクゥの暗殺は阻止できる。だが敢えてそれをするようにシュノン が進言したのは、復讐の為だ。 ﹁放てっ!﹂ 政庁の石畳に敷かれた赤い絨緞に、シェイプシフターの青い体液 が滲み始める。変態が追い付かなくなって来ているのだ。それでも 苦悶の声ひとつ漏らさないシェイプシフターたちを見て、シュノン は仄暗い愉悦を感じている。 138 ダークエルフは、大魔王の影となって種の命脈を保ってきた。そ の忠誠は絶対で、命さえも簡単に捧げる慣わしだ。情報収集、妨害 工作、そして暗殺。負わされる任務には危険が付き物だが、最大の 敵はいつもシェイプシフターだった。 シュノンの一族にしても、父と兄、二人の妹がシェイプシフター の手に掛かっている。もちろんダークエルフもシェイプシフターを 殺しているが、そういう問題ではない。同数殺せば同数の死者が慰 められるわけではない。 誇り高きダークエルフが故地を追われ、苦しいながらも漸く手に シェイプシフター 入れた仕事を邪魔する不倶戴天の敵。姿形さえ定まらない不気味な 生き物は、いつしかダークエルフという種全体の怨敵となっていた。 ﹁放てっ!﹂ 既にまともな形を保てなくなったシェイプシフターに念の為にも う一射加え、控えていた部下に手で合図を送る。目の細かい麻袋に ぐずぐずに崩れたシェイプシフターを押し込み、口を厳重に閉じて 油で焼くのだ。あの変幻自在の生き物を確実に屠るには、そういう 原始的なやり方が、最も確実だった。 袋に詰められそうになったところで、一際身体の大きな一体が咆 哮を上げる。恐らくは隊長格だろう。だが、何も出来はしない。既 に勝負は付いたのだ。いや、今日、この時間にここを襲うというこ とをシュノンが知り得た時点で、勝負は疾うについていた。 ﹁呪われろ!﹂ シェイプシフターが叫ぶ。声帯を形作っていた部分も崩れている のだろう。耳障りで、嫌悪感を引き起こす唸り声だ。 139 ﹁呪われろ、ダークエルフ!﹂ ﹁その言葉、そっくりそのままお前に返すぞ、シェイプシフター﹂ いつもは努めて無表情に徹しているシュノンの口元が、微かに綻 ぼろ ぶ。これは復讐だ。誰の魂も慰められない復讐だが、それすらも奴 らの魂を冒涜する意味では好ましい。何の対価もなく、ただ襤褸の ように燃やされる。それがあの気色悪い軟体生物には相応しい末路 なのだ。 ﹁ダークエルフ、お前たちは<廃太子>を大魔王にするつもりだろ う﹂ ﹁ああ、そうするつもりだ。その為になら、なんでもする。誰の命 でも奪う﹂ その言葉を聞いて、シェイプシフターが嗤ったような気がした。 いや、気がしただけだ。笑顔など判別出来るほどに、奴の顔は残っ てはいない。 ﹁ああ、ダークエルフよ。お前たちに呪いあれ。既に手は青い血で 汚された。我らの血で、汚された。シェイプシフターの<毒庫>に な。お前たちは殺すぞ。際限なくな。殺して殺して、それでも殺し 足りなくなって⋮⋮﹂ ﹁黙らせろ!﹂ 麻袋の口が、閉じられる。 外に運び出される袋を、シュノンは振り返らなかった。仮病を使 っているドラクゥに、結果を報告しなければならない。 だが、あの気味の悪い声だけはシュノンの耳にこびりついていた。 140 ラーナの手伝いで鎧を身に着けていると、誰かが寝室の戸を敲い た。 この瞬間、ドラクゥに訪いを入れる人物は一人しかいない。入室 を許可すると、思った通り現れたのはダークエルフのシュノンだっ た。いつもは感情を読み取ることの難しい青白い顔に、どことなく 喜色が浮かんで見える。忠実な密偵頭がこのような表情をするのを、 ドラクゥは初めて見た気がした。 ﹁首尾は?﹂ 短く尋ねる。シュノンも、頷くだけだ。 それで全てが分かる。完璧主義のこの部下は、失敗の細部は語っ ても成功を誇張することはしない。政庁に侵入した賊を退治した、 というそれだけが伝わればいいと考えているのだろう。そしてそれ はドラクゥの趣味にも合っていた。 シェイプシフターの暗殺者を殺させたのは、日頃の奉仕への褒美 でもある。本来であれば、こんな汚れ仕事は密偵の行うものではな い。故郷というものを持たず忠誠心のみを拠り所にするダークエル フに対して、ドラクゥは報いる術をあまり多く持っていないのだ。 殺せば、怨みが生まれる。怨まれれば、また殺される。 それが積み重なると、澄んだ水のように穏やかで冷たくあるべき 心に、濁りが生じることもあるだろう。そのことをドラクゥは、幼 い頃に叔父のリホルカンから聞かされた。 当時のドラクゥには叔父が何を言っているのかよく理解出来なか ったが、今なら分かる気がする。いつもとは異なり、シュノンの瞳 には肉食のけものに似た、微かな光が宿っているのだ。この光が熱 量を帯び、いずれは心を沸騰させるのかもしれない。 141 掛ける言葉が見つからず、ドラクゥは無為に手を伸ばした。指先 が、何かに触れる。見るとそれは、武骨な装飾の小刀だった。アル ナハ周辺の豪族が献じてきたものの一つで、シュリシアの見立てで は結構な業物であるという。手に取ってみると、ずしりと心地よい 重さがある。 ﹁シュノン、大儀である。この小刀を褒美に取らせる﹂ 一瞬、シュノンの顔に戸惑いが生じたようにドラクゥには見て取 れた。 失敗した。 ダークエルフは、物欲を以って大魔王の血脈に仕えているわけで はない。御恩に対する奉公という一般的な紐帯を超えたところに、 その忠義の神髄はあるのだ。ダークエルフがどのような大功を収め ても、ドラクゥの掛けるべき言葉は﹁大儀﹂のただ一言。 その冷淡とも言えるほどに“当たり前”の関係が、ダークエルフ にとっての言わば特権的な地位を約束しているのだ。労に対して物 で報いるのは、彼らに対してのみ、最大の下策となる。 そうは言っても、これは王の言葉だ。 ダークエルフにとって王の言葉は“鶏は卵に返らず”と良い、決 して換言を促してはいけない定めになっている。今ここでドラクゥ が言を翻さなければ、それはシュノンとの関係性を一度に変えてし まうことになりかねない。 ﹁シュノン⋮⋮﹂ ﹁︱︱謹んで、頂戴致します﹂ 一瞬、遅かった。 シュノンは恭しく頭を下げ、押し戴くようにして小刀を受け取る。 142 どことなしに声音が硬いような気がするが、その表情はドラクゥか らは見えない。 ﹁では畏れながら主上、拙者はこれより埋葬の手筈を整えねばなり ませんので、これにて失礼致します。任務の為仕方ないとはいえ、 あたら守衛の命を犠牲にしました。せめて、陽当たりの良い場所に 葬ってやろうと思います﹂ ﹁ああ、そうしてやってくれ、シュノン。それが手向けになるだろ う﹂ 表情を読ませぬまま、ダークエルフの頭領は音もなく寝室を後に した。 自分の迂闊さを呪うように、ドラクゥは手を強く握りしめる。爪 が掌に食い込む痛みがなければ、絶叫してしまいそうだ。 王は王たる血を以って王であるのではない。それに加えて、王器 を持たなければならないのだ。王器とは即ち、受け容れること。自 分の持つものを部下に分け与えるときに、誰からも不満の出ないよ うに裁量することの出来る徳のことだ。 欲する者には与え、欲しない者には与えない。与えるだけでなく、 奪うことも、与えないことも、王器には必要となる。 シュノンは、ダークエルフは何故<廃太子>と蔑まれるドラクゥ を主上と仰ぐ気になったのか。叔父のリホルカンでもなく、<北の 覇王>の支援を受けたレニスでもなく、このドラクゥを選んだのは、 何故か。 それは二人を含めた余人に王器なく、ドラクゥにそれがあると感 じ取ったからではなかったか。だからこそ、彼らは最初からドラク ゥを﹁主上﹂と呼んだのではなかったか。 143 胃の腑を、後悔が締め付ける。 王は、孤独だ。 全てを自身の判断で、自身の責任でしなければならない。そこに は弁明など出来ない、崇高な責任だけがある。 せめて。せめて今、あの頼りない邪神が傍にいてくれたらどうだ っただろうか。決して強く叱責はしないだろう。ドラクゥの前では 精一杯偉そうにして見せてくれているが、あの邪神の本質はそこに はない。共に歩むことだ。 その邪神が今ここにいないことさえも、自分の決断の故だ。 王とは、なんと孤独なのだろう。 ﹁⋮⋮主上﹂ シュノンが部屋にいる間、一言も発さなかったラーナが近くに寄 り添って来る。そして、握りしめたままの拳を、そっと両の掌で包 み込んだ。 ﹁主上、主上が何をお考えなのか、私には分かりません。分かるこ とが出来るとも思い上がりません﹂ ﹁⋮⋮﹂ ドラゴン・ハーフ 続きを、待つ。が、ラーナはそれきり何も言わない。 竜裔族の美姫は、ただ優しくドラクゥの手を握り締めるだけだ。 だがそれが、今のドラクゥには、一番有難かった。 部下を二人連れている。 シェリシアはドラクゥに事態を報告するだけさえ、護衛を連れて くるような男だった。そのことについてドラクゥは良いとも悪いと も思わない。ただ、慎重で用心深いのであればそれは伸ばすべき美 144 徳である、と思うだけだ。 鎧の付け直しを手伝わせたラーナはまだ傍にいて、ドラクゥの額 の汗を拭っている。シュリシアの視線が、一瞬、そちらに向けられ た。 ﹁ドラクゥ様、お加減はよろしいのでしょうか﹂ ﹁ああ、心配をかけたな、シュリシア﹂ ﹁いえ、小職は本分を尽くしたまでです。しかし、もう起き上がっ て大丈夫なのですか﹂ ﹁元より仮病だ、問題ない﹂ 縦に長いシュリシアの瞳孔が、少し開いたように見える。リザー ドマンの表情は、それ以外の種からは非常に分かりづらい。彼ら自 身に言わせればとても表情豊かなのだというが、ドラクゥには今の シュリシアの考えていることは読み取れなかった。 ﹁仮病、ですか。しかし﹂ ﹁毒を盛られた、ということにしたかった。<淫妖姫>パルミナは 余を毒によって暗殺しようとしていたのでな﹂ ﹁謀略に掛かったふりをなされた、ということでしょうか﹂ 問われて、ドラクゥは目を細める。違う、そうではない。そうで はないのだ。 ﹁あのパルミナのことだ。この程度の策で余を陥れることが出来る などとは考えておるまい。言わば、相手は戸を敲いてきたのだ﹂ “これから仕掛けますよ”というパルミナの問いかけ。それに対し てドラクゥは“いつでもおいで下さい。歓迎します”と返答した。 そういうことだ。 145 ﹁では、毒はどうやって﹂ ﹁ここにいるラーナが持ってきたのよ﹂ ﹁では何故、処罰されないのです。ドラクゥ様のお命を狙ったので あれば、世が世なら大逆の罪です﹂ シュリシアの怒りも、もっともだ。暗殺者を罰しないばかりか、 親しく寝室にまで招いている。これでは法の秩序が保てない。 ﹁挑戦状を届けてくれた使者だからな、無碍に扱うことは出来まい ? それともシュリシアは余に使者を斬るような汚名を被って欲し いのか﹂ 苦笑を浮かべドラクゥは逆に問い返す。シュリシアは恐縮して黙 り込んでしまった。 パルミナには、後がない。 毒を使い、策を弄し、暗殺者も使った。舞台裏から操ることの出 来る駒はまだまだ抱えているのだろうが、今度は彼女に時間切れが 迫っている。 リ・グダンだ。 時に同盟者として、時に裏切り者としてリ・グダンと接してきた <淫妖姫>は、あのゴブリンシャーマンが<蛮王>の位に就いたと き、その下風に立たされる。自由気ままに権謀術策を操るパルミナ にとって、それは自身の絵を描く画板を狭められるようなものだ。 これで、最後だろう。 いけ好かない相手であったが、ここで勝っても負けても大人しく ならざるを得ない。こちらが有利なわけではないが、圧倒的に不利 だという訳でもない。こちらは自分の勢力と命が掛け金だが、パル ミナはリ・グダンをも掛け金にしている。金額は大きくなるが、乾 146 坤一擲の勝負をするには、覚悟が足りない。 ﹁さあ、シュリシア。戦の支度だ。どこまで済んでいる? お前の ことだから、準備は万端なのだろう﹂ ﹁は、はい。小職の判断で出来得る所までは、全て終えております。 後は﹂ ﹁後、余は何に許可を出せばよい?﹂ ﹁は、ラ・バナン殿の周囲に集まっている者たちの処遇について﹂ ラ・バナンは病臥していることになっている。 これも策だ。継承の権利がある<蛮王>の位に含みを持っている、 と内外に示してドラクゥに対する不満分子を集めようというものだ った。 しかしそれももう良い。 ドラクゥはラ・バナンを担ぎ上げようとした叛徒の捕縛と放逐を 命じようとした。 ﹁その必要はございません﹂ 声のした方を見る。軍装に身を包んだ、ラ・バナンが立っている。 いくらか疲れた様子をしているが、病を偽って休職を始めたころ と変わらぬ様子だ。 ﹁私を担ぎ上げようと集まった者たちは、全て城市から放逐しまし た﹂ きっぱりと報告するラ・バナンの姿に、逆に慌てたのはほとんど 顔を合わせたことのないシュリシアの方だった。 ﹁しかし、叛徒、いえ、放逐対象の中にはラ・バナン殿と近しい親 147 族の方もおられたはず。敢えて貴方がそれを指示すれば﹂ ﹁恨みを買う、ですか。それがどうしたというのです。私は、私の 父を討ったドラクゥ様に見出されて今の職に就いている。自らこれ と決めた忠義を、それを弁えぬ親類縁者の為に曲げることは出来ま せん﹂ ラ・バナンはそう言ってドラクゥの前に跪く。 ﹁臣ラ・バナン、ただいまドラクゥ様の幕下に帰参致しました。お 許し願えますか﹂ 見誤っていた、とドラクゥは思った。 何が休職前と変わらぬ様子か。今のラ・バナンは、正に忠義の臣 として帰ってきている。仕事の喧騒から離れ、自らを見つめ直す時 間が、まだ若さと危うさの残っていたこの能吏の心情を昇華させた のだろう。 ﹁許す。ラ・バナン。では早速、余の首席幕僚として思う所を述べ よ﹂ ﹁御意にございます﹂ 伝令はドラクゥの直筆の書状を携えていた。 アルナハに戻る途上の道である。シュリシアからのドラクゥ不予 の報せを受けたル・ガンは森の中の道を迅速に南下しつつあった。 伝令は行軍中のル・ガンと上手く行き当たることが出来た格好だ。 すれ違いになる可能性も考えれば、幸運だとさえ言えた。書状が敵 に奪われることも考えてか、内容は完結極まるものだ。 ﹁“ル・ガンに命ずる。麾下の部隊を纏めてアルナハへ急ぎ帰還せ 148 よ”、か﹂ 予想通り、何かが起きている。ル・ガンは、片頬だけで笑った。 自分でも、何故笑みが零れたのか分からない。武人としての、本能 かもしれない。 ル・ガンは裏切り者だ。ゴブリンの魔王ベナンに背き、<廃太子 >ドラクゥに従った。その理由は何だったか。武人として名を成す ためではなかった。 ならば、今がその時だ。 ル・ガンは考える。敵は、誰か。 <蛮王>の地位に色気を見せたラ・バナンか。それとも順当にリ・ グダンか。そのどちらにせよ、裏でパルミナが動いていることは考 えられた。 急がねばならない。兵士の状態にも気を使わねばならないが、こ の場合は速さを優先した。疲労のない兵士が遅れて到着するよりも、 まずはアルナハに兵を入れねばならない。 ル・ガンの手元に五〇〇。<青>のダッダの下に二〇〇。アルナ ハ城市には一五〇〇の兵を入れてある。が、籠城するにせよ、野戦 で決するにせよ、兵は少しでも多い方が良い。 五〇〇の隊を全て載せるには舟が足りない。ル・ガンは当面要る だけの荷物を兵に持たせ、残りの食糧や物資は舟で運ばせることに した。こうすることで兵の負担が軽くなり、普段よりも長く速く掛 けさせることが出来る。 ﹁誰か、足の速い者を呼べ﹂ 行軍しながら<片頬>のル・ガンは長駆できる者を一〇人、選抜 149 した。皆、森で育った者たちだ。土地鑑もある。条件に合えば、種 族や門地は考慮しなかった。 ﹁お前たちには、隊に先行して途中にある村々へ急げ﹂ ﹁そこで何をすれば良いんでしょうか﹂ 一番年若いゴブリンが尋ねる。まだ少年と言っても通じそうな、 良い目をした兵だ。 ﹁長に倉を開けさせる。その米で、握り飯を予め握らせるように頼 め﹂ ﹁握り飯、ですか﹂ ほしいい ル・ガンの隊は、食糧のほとんどを舟で先に運んでいる。携行し ほと ている食糧と言えば、糒だ。一度炊いた米を天日で干したこの保存 食は、食べる前に水で潤びさせる必要がある。 今のル・ガンには、その時間すらも惜しい。村に足の速い者を先 発させるのは、隊が到着してから米を炊く時間さえも節約したいか らだった。 ﹁渋るようなら、<片頬>のル・ガンの名義で借り上げると言え。 さ、行け!﹂ 実際には、そうはならないだろう。賊の討伐を通じて、アルナハ 周辺の人々はドラクゥの軍、特にル・ガンには好意的だ。喜んで、 とは行かぬまでも食糧の提供には応じてくれるはずだ。 ﹁さ、全軍、急ぐぞ! 落伍者はなるべく出すな!﹂ ル・ガンの号令で部隊の足が再び速まる。ほとんど、駆け足に近 150 い。森の道は足がとられるが、これまで続けた賊徒の討伐で皆、歩 き慣れている。 この場合、五〇〇という兵士の数も逆に幸いした。これ以上の兵 を率いていれば、森の中の細い道では身動きが取れなくなっていた だろう。仮に整然とした行軍が出来たとして、その動きは今よりも 遅くならざるを得ない。軍隊は数を増せばますほど、統一の取れた 動きはしにくくなる。 予想した通り、途中の村は快く倉を解放してくれた。食糧の供出 だけでなく、自ら武器を取ってル・ガンの部隊に加わろうとする若 者さえいる。そういった者もル・ガンは受け容れ、隊の中段に置い た。前段に置けば隊の足が遅くなり、後段に置けば落伍するからだ。 自分でも意外なことに、ル・ガンはこういう工夫を考えることが 苦にならない。これまではベナンの下で指示されるがままにしか戦 をしてこなかった。気になる個所や、工夫を加えたい所があっても、 それは許されなかったのだ。 今は、違う。 自分の創意で、自分の戦が出来る。これだけの裁量を与えてくれ るドラクゥに、ル・ガンは感謝した。 斥候がその集団を見つけたのは、アルナハにまでもうあと僅かと いう地点だった。武装さえしていない五〇人ほどのゴブリンの一団 が、城市から離れていくというのである。 妙だ。 やま 戦から逃れる、というのであればもっと多くの脱出者がいてもい い。それが、たったの五〇。家財すら持たずに逃げ出すのは、疚し いことのある者か、街を追われた者に違いない。 151 そしてその疑念は、一団の中にリュ・ギロクの姿を見たと斥候が 報告したことで確信に変わった。リュ・ギロクは魔王ベナンの弟で、 リ・グダンの父だ。つまり、ラ・バナンの叔父に当たる。病に伏せ ったラ・バナンに近付いていたゴブリンたちの顔役でもある。 ﹁⋮⋮アルナハで既に何かが起こった、ということか﹂ ラ・バナンが決起したのか、逆にラ・バナンが取り巻きを放逐し たのか。 いずれにせよ、あれは敵だ。 ル・ガンは武人の直感でそう判断した。 ﹁前段の隊はあの集団を追い散らせ! 深追いはするな。適当に追 撃してやれ!﹂ 我ながら意地の悪い指示だと自嘲する。 自分を蔑んだ魔王ベナンの親類を少し苛めたところで何かが癒さ れるものでもない。溜飲を下げる為の、ちょっとした悪戯のような ものだ。 首級を五つほど挙げ、ル・ガンはアルナハに凱旋した。 いなな 馬が嘶いた。 鞍上のパルミナが目を凝らすと、森の奥に乱れて潰走するゴブリ ンが見える。最初から隊伍を成していないのかもしれない。軍装ど ころか平服に身を包んだゴブリンの一団は、這う這うの体で当て所 なく進んでいる。 リュ・ギロクだ。 152 放っておいた仕掛けを、また一つドラクゥが見破った、というこ とになる。<淫妖姫>パルミナはアルナハ攻略に向けて幾重にも策 を張り巡らせてきたが、これまでにそのいくつかは見破られている。 ﹁暗殺も⋮⋮ま、成功してはおらんだろうな﹂ 風向きは変わっていた。 全てはダークエルフがあの<廃太子>の下に付いたことが原因だ。 歴代の大魔王の下で技を磨いたあの一党は、シェイプシフターの手 ことごと の内を知り尽くしている。ドラクゥに対するものも、リ・グダンに 対するものも、謀略の悉くに邪魔をされた。 鷹のように抜け目なく、蛇のように執拗に。 ダークエルフの間諜はいつもそのようにして敵対者を妨害し、大 魔王家を守り抜いてきた。いや、今も彼らは大魔王家を守っている つもりなのだろう。それは即ち血筋であり、つまりドラクゥのこと を意味する。 ☆ “聖堂”と戦士の一族の対立を逆手に取り、魔族と戦士の一族の 連携を模索するヒラノ。 ここで彼らと手を組むことが出来れば、ドラクゥ陣営で不足しが ちな塩と馬を大量に入手することが出来る。 相互の不信をヒラノは何とか乗り越えていく。 その頃アルナハではリ・グダンの軍が本格的な侵攻を開始してい た。 その陰に蠢く<淫妖姫>パルミナ。彼女は裏の裏をかき、自ら兵 を率いてアルナハに迫りつつあった。 153 狙うはドラクゥの首一つ。 策謀に長けた女魔王との熾烈な戦いの末、パルミナは自分の意外 な真意に気付くのであった。 154 第五章ダイジェスト版 塹壕、という技術自体は前世の地球ではそれほど目新しいもので もない。 ヨーロッパでは対要塞戦で中世後期から既に使用されている。要 するに自分が隠れられるように穴を掘り、敵からは狙いにくく、こ ちら側は座ったりしゃがんだりしなくても銃が撃てるようにすると いう工夫だ。これが爆発的に広まるのは機関銃の威力が広く知られ るようになった日露戦争以降、特に第一次世界大戦でのことである。 その塹壕を、“聖堂”軍は野戦でも好んで使うと聞いて、俺は最 初疑問に思った。 どうすれば戦場に即座に塹壕を掘ることが出来るのか。 “戦士の一族”は騎馬隊を持っている。敵が準備している間に奇 襲を掛けたり、後方に回り込むことだって出来るんではないか、と 思っていたのだ。 理由は、あまり見たくない“姿”をしていた。 ﹁⋮⋮マスターは、始めて見るんだっけ?﹂ ﹁あんまり見たくない光景ですね、こりゃ﹂ 空を飛んで偵察に出た俺と慶永さんの眼下で、“聖堂”軍が塹壕 を掘っている。より正確に言えば、穴を“掘らせて”いるというこ とになるだろう。 そこにいるのは、うすぼんやりとした姿の、“神々”だった。 ﹁“聖堂”では唯一神以外の神は存在を認められない。だから、あ の神たちは、“天使”なんて呼ばれてる。神格を剥奪され、存在す 155 カルマ るのにギリギリ必要な徳だけ配給されてね﹂ ﹁⋮⋮酷いな﹂ ﹁これが“聖堂”のやり方。信者の中でも特に忠実な者には“加護 ”なんて言って“天使”を使役させるの。“天使”の姿は人間には 見えないから、その信者は神から力を授かったように錯覚する﹂ ﹁そしてそれが、唯一神への信仰に繋がるってことか﹂ はらわたが煮えくり返るような怒りが湧いてくる一方で、俺の頭 の冷静な部分は感心もしていた。信者を奪い、信仰を奪って無力化 した神々を、“天使”として隷属化させ、再利用する。許し難い冒 涜だが、仕組みとしては確かに優れている、と思う。 決して真似をしようとは思わない種類の考えだが、確かにこの方 法なら最初さえ上手く行けば後は際限なく勢力を拡大していけるは ずだ。もちろん、類似の方法やこれに代わる方法を思い付く競争相 手がいなければ、という条件は付くが。 ど れんど ﹁武器は、弩って言うんだっけ? そういうのはマスターのが詳し いでしょ?﹂ ﹁ただの弩弓なら良かったんですがね⋮⋮どうにもこうにも、連弩 みたいです﹂ ﹁連弩? それって、弩とは何か違うの?﹂ ﹁ええ、弩も連弩も中国で昔使われてたんですが、連弩は連射が可 能です﹂ 連弩や弩は機械弓と呼ばれる武器の一種で、普通の弓と違って機 械的に矢を発射する。色々なメリット、デメリットがあるが、最大 のものは訓練が必要ない、ということだ。 日本の大河ドラマで武士の日常シーンでは弓の練習をしているこ とが多いが、これは弓が絶え間ない訓練を必要とする武器だからで ある。それに対して機械弓である弩や連弩は、遥かに扱いやすい。 156 初歩的な使い方さえ教えてやればその辺りから連れてきた農民でも 一端の戦力として数えることが出来るのだ。 この連弩を塹壕から撃つというのは、確かに正面から向かってく る騎馬隊に対しては有効な戦術だろう。見れば“聖堂”軍は単純な 横一文字の塹壕ではなく、W形に塹壕を掘っている。こういう形に 掘られてしまうと、例えどの方向から騎馬突撃を仕掛けても、死角 というものがない。 ﹁厄介、ですね﹂ 慶永さんが無言で頷く。視線の先にいるのは、“聖堂”に使役さ れる“天使”だ。 俺は幸運にも今こうして邪神だけでなく神としてここにいるわけ だが、もしどこかで一歩道を間違えていたら、ああやって“聖堂” に奴隷のように働かされていたかもしれない。 “聖堂”の軍と戦うのは、魔族と“戦士の一族”だ。 俺たちの敵は、人間の作った“聖堂”という組織ではなく、“聖 堂”そのもの、つまりは唯一神ということになる。 ただ、復讐に燃える慶永さんには悪いが、今のままの俺たちでは カルマ 唯一神の作ったこの仕組みに勝つことは絶対に出来ない。この世界 の神々にとって徳が全ての力の源泉である以上、それを集める力の カルマ 差が極大化してしまうとそれを覆すことが出来なくなる。 徳を持った神はその徳を使って奇蹟を起こし、より簡単に信者を 得ることが出来てしまう。前世での金と一緒だ。一の金を二にする よりも一〇〇の金を一〇一に、さらに言えば一〇〇〇の金を一〇〇 一に殖やす方が、圧倒的に簡単なのだ。 157 背中の後ろから、鬨の声が聞こえる。“戦士の一族”だ。 今はただ、目の前の戦いに集中しなければならない。でも、唯一 神との戦いについては、いつか必ず正面から向き合わなければなら なくなる。それはルロの為でもあり、ドラクゥの為でもあり、慶永 さんの為でもある。 この世界に転生した時に漠然と抱いていた、気楽に神様ライフを 過ごそうというなんていう気分はもうとっくに消えていた。 ごく自然に、慶永さんの手を握る。 びくりとした硬直の後、慶永さんは俺の手を柔らかく握り返して くれた。 ﹁マスター⋮⋮この戦いが終わったら﹂ ﹁何、慶永さん?﹂ 心臓が、一度高鳴る。 ﹁⋮⋮あの、ルロって娘のこと、ちゃんと説明して貰うからね?﹂ 中央に槍兵を置き、脇を騎兵で固める。 オーソドックスだが、基本を押さえた良い陣形だ、と思う。前世 で軍人だったわけではなく、単なるサラリーマンだった俺が言うの も変な話ではあるのだが。 “戦士の一族”というくらいだから、草原に暮らす氏族主体の塊 に分かれた突撃を想像していたので、整然と戦列を組む様には少し 驚かされた。てっきり、モンゴルの騎馬民族のように騎兵主体で騎 射を中心とした戦術を組み立てているのかと思っていたのだが。 長さが三メートル以上もある槍は、重い。密集陣形を作るには十 158 分な訓練が必要となる。よくよく考えてみれば、彼らの先祖は魔軍 の侵攻に対する守りとしてこの地域に入植した戦士たちだったはず だ。そうなれば、機動性に富んで侵攻や略奪に適している騎兵だけ でなく、こういった重厚な守りが敷ける戦術も必要だったのかもし れない。 俺は<風の神>リルフィスと一緒に空から戦場を眺めている。慶 永さんと、ついでにオイレンシュピーゲルには魔軍の方を見て貰っ ていた。いざという時、どちらにも二人いないと連絡役がいなくな るからだ。リルフィスとオイレンシュピーゲルのペアを提案したの だが、これは二人とも渋った。顔も見たくない、ということだろう。 しかし、なかなかしっかりした陣形だ。 この様子を見る限り、ゴブリンに怯えてルロを生贄に出した、と いう俺の考えは間違っていたのだ、と思う。明確に、ルロが邪魔だ ったとしか考えられない。 族長の孫娘という立場と、裏切り者の娘、という立場が難しかっ たのだろうか。 そう言えば、一つ不思議なことがある。 地上で槍を構えたり騎乗している“戦士の一族”は、ほとんど例 外なく赤い髪をしているのだ。族長も当然、赤い。では何故、ルロ の髪は緑なのだろうか。 ちらりと俺の横で腕組みをしている<風の神>を盗み見る。今ま であまり気にしていなかったが、このリルフィスも髪は緑だ。まさ か。 ﹁⋮⋮リルフィスさん、戦いの前に一つ聞いておきたいことがある んだけど﹂ ﹁何だヒラノ、水臭い。オレとお前さんは戦友みたいなもんだ。何 159 でも聞いてくれ﹂ 戦場の空気に酔っているのか、リルフィスが豪快に笑う。こうい う笑い方をする神が、いや、だからこそなんだろうか。 ﹁その、ルロっていう娘のことなんだけど⋮⋮﹂ ﹁ああ、アレは助かった。本当に助かった。恩に着るよ、ヒラノ。 まさかオレ自身が助けるわけにもいかんしなぁ。いや、お前が神の 姿を人間に晒していることを皮肉ってるわけじゃないんだぜ? そ ういう勇気も時には必要だっていうことを、オレは分かっている。 とにかく、いずれこの礼は何かの形でさせて貰うからな﹂ ﹁いや、礼とかはどうでもいいんだけど⋮⋮なんであの娘は生贄み たいなことをさせられてたんです?﹂ 俺の問いかけに、一瞬リルフィスが怯む。やはり、何かあるのだ。 ここでもう一押し。営業マンだった時の経験値が俺に囁きかける。 あと一押しで、リルフィスは落ちるはずだ。 ﹁あの娘の父親が“聖堂”の神官をやっている、というだけじゃな い気がするんだけど﹂ ﹁あーなんだ、その、直接の原因は、あいつの父親が寝返ったこと で合ってる。合ってはいるんだが⋮⋮﹂ ﹁戦友みたいなもんなんでしょ? なんでそこだけお茶を濁すんで す?﹂ リルフィスが、黙る。 眼下では、ゆっくりと近付く“戦士の一族”に痺れを切らした“ 聖堂”の軍の一部が連弩を射かけ始めた。前進する槍兵の先頭はま だ、弩の射程に入ってさえいない。威嚇なのか、練度の低い兵が混 じっているのか。 160 それでも俺が無言で横顔を見つめ続けていると、観念したように リルフィスがぽつりと呟いた。 ﹁⋮⋮娘なんだ﹂ ﹁えっ?﹂ ﹁ルロ・バンテンはな、オレの娘なんだよ﹂ ﹁娘、って、えっ?﹂ ﹁娘だよ、娘。オレの子ども﹂ ﹁神さまって、そんな、人間と子ども作れるんですか?﹂ 多分今の俺は凄く間抜けな面をしているだろう。リルフィスがそ れを見て肩をすくめる。 ﹁出来る、なんて知らなかったんだよ﹂ 軽い口調で言っているつもりなのだろうが、その響きは重い。も し本当にルロ・バンテンがリルフィスの娘だとすれば、色々と合点 がいってしまう。 ﹁じゃあ、ルロの父親が“聖堂”に寝返ったのは﹂ ﹁⋮⋮おう、そうだ。オレの所為だよ﹂ 槍兵隊が“聖堂”軍の連弩の射程にまで肉薄する。 つが ここから先は、損害を覚悟しないと一歩も踏み込めない。弩の連 射速度は、異様に速く見える。複数の矢を番える連弩は装填に時間 がかかるのが普通なのだが、塹壕の中に補給隊の人夫を収容して弩 の準備に従事させているらしい。 161 ﹁赤毛の綺麗な女だった。どちらかというとグラマーなタイプが流 行るこの氏族では珍しく、スレンダーな美人でな﹂ 俺は、相槌も打てなかった。想像していなかった、と言えば嘘に なるが、実際に本人の口から聞くと腹の底に響くような衝撃がある。 神と人が、子どもを作ることが出来る、というのはなかなか重い。 ﹁ヒラノ、お前さんがどこから転生して来たのか知らないが、ギリ シャ神話くらいは知ってるんじゃないかのか? ゼウスとかアポロ ンとか﹂ ﹁詳しくはありませんが﹂ ﹁知ってるだけでいい。あの神話のキモは、神婚譚だ。神が人と交 わり、子孫を残す。神の子は特別な力を授かり、その子孫はギリシ ャの各王族へと血を繋げる。あの半島の有力者たちが、自分たちの 高貴さの水源として神話を創り出した、という風にも考えられる﹂ ﹁それと同じことをした、と?﹂ ﹁違うな。結果としては何かしらの意味があるのかもしれんが、こ とに到った原因は純粋な愛情だよ﹂ 突撃が始まった。 この技術水準で考えられる恐らく最も濃密な弾幕の中を、“戦士 の一族”は蛮声を上げながら突っ込んでいく。空から見ると、無数 の小さな生き物が敵の陣という獲物に殺到しているように見える。 ﹁ヒラノ、さっき言ったな。お前さんが神の姿を人の前に晒すこと を否定しない、と。アレはな、オレも随分やっていたからなんだ﹂ カルマ リルフィスは静かな声でそう言うと掌を“聖堂”軍の少し手前に 向けて突き出した。空気中に甘い徳が漲っていくのが分かる。瞬き 162 をするほどの僅かな時間、放たれた矢を烈風が襲った。リルフィス の奇蹟だ。 ﹁生身の兵士たちに交じって暴れたこともある。ルロに授けた槍を 持ってな。流石にあの時は他の神々にえらく叱られたが﹂ ﹁そりゃそうでしょう﹂ ﹁お前さんが言えた口か? 与えている影響で言うなら、お前さん のが余程酷いぞ﹂ 苦笑しながらリルフィスは二度、三度と奇蹟を起こす。弩は飛距 離も命中率も弓より優れているが、安定性は悪い。<風の神>の呼 “戦士の一族”がそれを見逃すはずもない。一気呵 んだ気まぐれな烈風によって、弾幕は目に見えて密度を失っている。 戦慣れした 成に敵陣への距離を縮め、塹壕の前に設えられた馬防柵を力任せに 引き倒す。 ﹁一回だけの、過ちだ。いや、回数なんて関係ないな。それで、ル ロを授かった。不思議なもんでな、ヒラノ。どんな風にして生まれ た子にでも、愛着というのは湧いてしまう。特に、ルロの場合は、 オレと同じ髪の色をしていたからな。だが、それがまずかった﹂ 襲い掛かる戦士の群れに、塹壕から槍が突き出される。“聖堂” の主力は、弩から槍に持ち替えたらしい。“戦士の一族”の持つ長 槍は集団戦でこそ圧倒的な力を発揮するが、下から突き上げられる ような戦技に対しては取り回しが不向きだった。 ﹁キュリオスは⋮⋮ああ、キュリオスというのは長の息子で、ルロ の母親の夫なんだが、酷く絶望してな。元々がルロの母親は別の氏 族の出身だったのを、キュリオスが一目惚れして貰い受けて来たん だが、長く子を授からなかったからな﹂ 163 ﹁⋮⋮それはまた、なんとも﹂ 間の悪い、というかなんというか。寝取り寝取られというのはい つの時代、どこの世界でも厄介事の種だ。しかも相手が部族の崇め る神となれば、握った拳の振り下ろし先もない。キュリオス、とい うルロの父親の不幸は想像を絶するものがある。 ﹁困惑したんだろうな。暫くは酒浸りの生活を続けていたが、ある 日狩りから帰って来なかった。気が付けば“聖堂”の神官様、って わけだ﹂ 乱戦になりつつある地上の一点を、リルフィスはそっと指差す。 そこでは赤い髪を振り乱しながら、“聖堂”の戦士が両手にそれぞ れ短槍を持って奮迅の戦いを繰り広げていた。 ﹁あいつだよ、あれが、キュリオスだ。キュリオス・バンテン﹂ ﹁あれが、ルロの﹂ ﹁そう、ルロの母親の旦那で、ルロの母親を殺した仇でもある﹂ ﹁⋮⋮えっ﹂ リルフィスの口元には、凄絶な笑みが浮かべられている。 ﹁ルロの祖父はな、好き好んでルロを魔族の人質に出したんじゃね ぇ。この場に居たら、ルロはキュリオスを討ちに行こうとするだろ うからな。そしてそうなれば⋮⋮﹂ ﹁そうなれば﹂ ﹁ルロは、死ぬ﹂ 混戦は乱戦になり、二つの軍は絡まりあったまま徐々に動き始め 164 た。“戦士の一族”が、ゆっくりと押されつつある。塹壕から這い 上がりながら、“聖堂”軍はしっかりとした歩調で戦士たちを一歩、 また一歩と後退させていた。 先頭には赤髪のキュリオス・バンテンが立ち、かつての同胞を追 い散らしている。鬼気迫る、というのはこういうのをいうのだろう。 確かに人間離れした強さだ。 ﹁そんなに、キュリオスは強いんですか?﹂ ﹁キュリオスは、“加護持ち”だ。ルロでは、いや、普通の人間で は勝てない。絶対にな﹂ そう言ってリルフィスが顎をしゃくる。よく見ると縦横無尽に暴 れまわるキュリオスの肩に、青白い何かが見えた。神、いや天使と いうべきか。神格を失った神を“聖堂”はこういう風に使っている のか。 りょりょく ﹁天使を使って、個人の戦闘力を高めている。膂力を上げたり、動 体視力を良くしたり。一つ一つは小さな効果でも、戦場ではほんの 僅かな差が命拾いに繋がる﹂ ﹁英雄、みたいな?﹂ イミテーション ﹁英雄とは巧い言い方だな。そう、キュリオスは英雄だ。元からの 素質もあったが、加護を得てさらに強くなった。模造品の英雄と言 った所だろうな﹂ キュリオスの短槍がまた、一人倒した。返り血を浴びながら戦う 姿は、まるで獣のようにも見える。 ﹁キュリオスは“聖堂”にとって異教からの改宗者だからな。あい つが武勲を上げて“聖堂”がそれに報いる、というのは格好の宣伝 になる。他の異教徒たちが唯一神に帰依するのを邪魔する心理的な 165 ハードルを下げることにつながるからな﹂ ﹁自分たちも聖堂に重く用いられるかもしれない、と考えるだろう ってことですか﹂ ﹁少なくとも邪険にされない、という見本にはなるだろうさ。“聖 堂”はその辺りの懐柔や鎮撫に随分と心を砕いている。前世でのヴ ァチカンを参考にしてるんだろうが、組織の運営は驚異的に巧い。 が、少しばかり急いで勢力を広げ過ぎているからな。内情では綻び もあるのかもしれん﹂ ﹁綻び、ですか﹂ カルマ ﹁そこを突く、っていうのは中々難しいと思うぞ。何と言っても唯 一神の持っている徳は莫大だ。並の小細工だと見破られる前に踏み 砕かれちまう﹂ ﹁俺は、まだ何も﹂ ﹁目が言ってるさ。お前さんはあの<戦女神>ヨシナガの関係者な んだろう? 同じ目をしてる﹂ リルフィスの言う<戦女神>という言葉に、少し胸がざわめく。 自分の知らない慶永さんがいる、というのは何だか不思議な気分 だ。もちろん、慶永さんの全てを知っているなんて自惚れるつもり さちゅうじょう ゆうめいじん はない。それでも、他の人が知っている慶永さんなら、自分も知り たいと思ってしまう。 じゅしいのげ ﹁あの、<戦女神>っていうのは⋮⋮﹂ じんぼう ﹁従四位下左中将、<戦女神>ヨシナガと言えば、有名神だな﹂ ﹁従四位って、かなり偉いんじゃ⋮⋮﹂ ﹁神階で神の偉さが決まるわけじゃないが、ヨシナガは神望もあっ たしな。賭博神たち若い連中でつるんで色々やってたよ﹂ ﹁色々って、例えば﹂ 身を乗り出しそうになる俺を遮るように、リルフィスの声音が沈 166 む。 ﹁っと暢気にこんな話をしている場合でも無くなったな﹂ ﹁えっ﹂ 天使だ。 天使が三体、“聖堂”の軍を離れてこちらに上ってくる。手に抜 き身の剣を提げている所を見ると、友好的な話をしに来たとも思え ない。ぎらついた敵意を隠そうともせず、こちらに向かってくる姿 は、天使というよりも悪魔に近い。 ﹁ヒラノ。お前さん、戦いの経験は?﹂ ﹁⋮⋮残念ながら﹂ ﹁そうか。なら、重要なお役目だ。⋮⋮<戦女神>呼んで来い﹂ ﹁でも、そうなるとリルフィスさんが一対三に﹂ ﹁足手纏いだ、というのを婉曲的かつ文学的に表現して言ってやっ てるんだ。それくらい察しろ﹂ そこで言葉を打ち切り、虚空から槍を取り出す。パンプアップし た背中の筋肉が盛り上がる。“戦士の一族”の神、というだけあっ て、迫力が凄い。 ﹁行け、ヒラノ。愚図愚図するな﹂ ﹁はい。リルフィスさん、御武運を!﹂ ﹁⋮⋮武運を祈られるべき神が戦うんだ。その願いは、誰が聞いて くれるんだろうな﹂ ﹁さぁ、それは⋮⋮﹂ ﹁ともかく、行け!﹂ 背中を押され、俺は飛んだ。身体が軽いのは、最後にリルフィス 167 カルマ が少し徳を分けてくれたからだろうか。目指すのは、慶永さんのい る魔軍の陣だ。 ☆ 強固な陣で固めた“聖堂軍”を引きずり出す為に犠牲をいとわず 突撃する戦士の一族。敵の油断を突くように、魔軍の兵が殺到する。 アルナハが陥落あと一歩という苦境に陥った時、思わぬ増援が現 れ、形勢は逆転した。 二つの戦い、二つの勝利。 敗走するリ・グダンを敢えて追撃せず、ドラクゥはある重大な決 断を下す。 168 第一章ダイジェスト版 巨大、というより他ない。 とくとう はくぜん 大魔王府からやって来た老人は、ドラクゥよりも頭三つほど大き かった。オーク族である。禿頭に床まで届く長い髯。<白髯>のダ じい ーモルトと言えば、魔界で知らぬ者の無い老臣だった。 ﹁久しいな、爺﹂ ﹁ご無沙汰をしております、ドラクゥ殿﹂ 様付けでも、主上でもない。ダーモルトのドラクゥに対する呼び かけは、あくまでも“ドラクゥ殿”であった。今でこそ顕職に就い ていないとはいえ、ダーモルトは大魔王府の所属であり、ドラクゥ をその主としてまだ認めていないからだ。 アルナハ政庁の謁見の間で対峙する二人の立ち位置は、対等だっ た。 お互いに、立ったままで相手を直視している。 大魔王府からの“勅使”を迎える魔王は、本来下座に就かねばな らない。だが、ドラクゥは既に大魔王へ即位することを内外に公表 していた。 大魔王を名乗る者と、大魔王の名代。 本来であれば同時に存立することのない立場の二人の関係は、自 はくはつき 然と同等にならざるを得ない。 ﹁ラコイトは、<白髪姫>は壮健か﹂ ﹁ドラクゥ殿に気に掛けて頂いて曾孫も喜ぶでしょう。今は大魔王 府で<北の覇王>との連絡係のようなことをやっております﹂ ドラクゥとは不倶戴天の敵である<北の覇王>ザーディシュの腹 心、ラコイトはこのダーモルト翁の実の曾孫に当たる。その巨躯に 似合わず調整型の優れた官吏であるダーモルトの血を最も色濃く受 け継いでいるのが、<白髪姫>ラコイトだった。 ﹁ザーディシュ、な。あの老人もいつまで権力に固執するのか﹂ 169 ﹁はは、耳が痛うございますな﹂ ﹁爺、そなたのことを言ったのではない。<北の覇王>のことを言 ったのだ﹂ ドラクゥ即位の報は、既に魔界全土に広まっている。 辺境のアルナハは瞬く間に人々の話題の中心となった。これまで 位置すら知られていなかったような城市に無数の使節、密偵、そし て商人たちが詰めかけている。既に城市を取り巻く陶壁の周囲にも 市が立ち、宿泊用の天幕が軒を連ねていた。 既に<北の覇王>もいくつもの手を打って来ている。その一つが、 ことほ ドラクゥと近しい間柄であったダーモルトの派遣だった。 ﹁⋮⋮爺、そなたは余の大魔王就任を言祝ぐつもりはないのだな﹂ なんぴと あた ﹁そうは申しません。ドラクゥ殿は正しく大魔王の系譜に連なる御 方。手順を踏みさえして頂ければ、魔界に於いて何人も侵すこと能 わざる至尊の位に就くことに何も含むところはございません﹂ しゃしょく まつ あまね みいつ ﹁大魔王府の司る儀式を経なければ大魔王には即位できない、とい てんじんちぎ う訳だな﹂ ばんこ ﹁天神地祇と社稷とを祀り、遍く魔界にその御稜威を広められる御 方である大魔王に就く為には、盤古より定められた儀式をこなして 頂くのが定めにございます﹂ 恭しく頭を下げて見せながら、ダーモルトの目は笑っていない。 つまりはまだ時期が早いとこの老爺はドラクゥを嗜めているのだ。 ドラクゥ率いるアルナハ陣営の兵士は驚くべき勢いで増えている。 近隣の小豪族がドラクゥに帰順を申し入れてきているのだ。魔王の 中にも、ドラクゥに秋波を送る者は少なからずいる。それらの中か ら、本当に信用に足る者だけを選り分ける形で、ドラクゥは陣営の 強化を急いでいた。 数だけで言えば一万は十分に集められる。ラ・バナンの見立てで は無理をすれば、もう五〇〇〇用意することも不可能ではない。そ してそれはこれからも増えていくだろう。 落ち延びてきた時の兵力二〇〇から考えれば大きな進歩とも言え 170 るが、まだ一万しかいないのだという気持ちも強い。 倒すべき<北の覇王>は、最大で二十四万の兵力を動員できる。 これはほぼ間違いのない数字だった。以前、<廃太子>ドラクゥと の決戦に動員してきた数である。状況によっては、この数はさらに 増える可能性もあった。戦術で覆すことの出来る数ではない。 ダーモルトは、それを訴えている。 せんしょう 今、ドラクゥが大魔王に即位したと正式に宣言すれば、大魔王府 はそれを“僭称”と見做さなければならない。そうなれば<北の覇 王>も彼の下で働く<白髪姫>も嬉々として近隣の魔王にドラクゥ 討伐を依頼する使者を送るだろう。 その愚を避けろ、という忠告はドラクゥにとっても理解できるこ とだ。 せめて、大魔王府の中にもう少し味方を作る。或いは<北の覇王 >の後背を脅かす同盟者を手に入れる。それまで待てないのか、と いう想いはドラクゥも共有していた。 ﹁儀式は簡素に執り行う。累代の大魔王には申し訳ないが、祖廟す らまだ手にしていないからな。出来ることは自ずと限られてくる﹂ ﹁正しき儀式無しに正しき即位は有り得ません。祖霊にも邪神にも 申し訳が立ちますまい﹂ ﹁今、魔界は乱れに乱れている。それを放置することこそが最大の 不義であろう﹂ ﹁⋮⋮大魔王府としてはとても認められません﹂ ドラクゥは傍らにあった杯の中身を干した。 喉が渇いたわけではない。緊張を隠す為だ。今からダーモルトに 言わねばならない事はそれだけの意味がある。 言ってしまったが最後、決して後戻りはできない。 ﹁ダーモルト・デル・アーダよ﹂ ﹁はい、ドラクゥ殿﹂ ﹁大魔王は、いつから大魔王府の承認なしに即位出来なくなったの だ?﹂ 171 はっきりとダーモルトが息を呑むのが分かった。 これは、ドラクゥから大魔王府への決別宣言に他ならない。 ほひつ ﹁ドラクゥ殿、それは⋮⋮﹂ ﹁大魔王府は、大魔王を輔弼するものだ。大魔王の即位に関する一 切の権限は、大魔王ただ一人に帰属するはずだ。違うか﹂ 五千年も王統が続けば、大魔王家からも無能は出る。 その無能を補う為とは言え、時を追うごとに大魔王府の権限は拡 大され、その力はついには大魔王自身さえ上回ることがあるのは事 実だ。それを、ドラクゥは痛罵している。 ﹁余の血は最も古く、しかして余の王権は最も新しい﹂ その言葉を合図に、ラ・バナンがダーモルトの前に進み出た。 手には一枚の涜皮紙を捧げ持っている。 ﹁ダーモルト。これが余の“宰相”であるラ・バナンだ﹂ 紹介され、ラ・バナンが深々と頭を下げて見せる。 大魔王府に於いて非常時に置かれる臨時最高職だ。ドラクゥは、 大魔王府に諮らずにラ・バナンに新たな官職を授けると宣言したこ とになる。 ﹁ドラクゥ殿、それは、つまり、大魔王府が魔界に二つ存在するこ とになりますぞ﹂ ﹁二つではないぞ、ダーモルト。“正しい大魔王府”とは大魔王を 輔弼するものを指すのだ﹂ ダーモルトが、再度頭を下げた。 最早、ドラクゥとの間には一言の言葉もない。ラ・バナンの捧げ 持つ絶縁状を受け取り、ダーモルトは踵を返した。 ドラクゥを<廃太子>と貶めた大魔王府の中に在って最大の親ド ラクゥ派であったダーモルトと袂を分かったことで、アルナハの立 場はより鮮明に魔界の諸侯の目に映るようになった。 新大魔王、立つ。 魔界に、大きな嵐が訪れようとしていた。 172 せんそ ドラクゥ践祚の報は瞬く間に魔界全土に轟き渡った。 <廃太子>が大魔王位を継ぐ。その事に対しては批難の声はあま り聞こえなかった。血筋から言えば、ドラクゥしかいない。誰もが 知っていることだった。 大魔王家の血を引く男子で現在生存しているのは三人。 <皇太子>レニス、<法皇>リホルカン、そして<廃太子>ドラ クゥだ。 出家して神職となっているドラクゥの叔父リホルカンも、女系で しか血を伝えていないレニスも、大魔王位を継ぐことは出来ない。 もし継ぐことができたとしても、継承順位はドラクゥよりも下にな る。 問題なのは、時期だ。 今のドラクゥは精々が魔界の南東部、ジョナンの赤い森に城市を 一つ所有しているに過ぎない。新たなる大魔王の拠って立つ領土と しては、いささか小さい。せめて南方の全てを併呑してから動きが あるだろうと考えていた物見高い魔王たちにとって、性急とも言え るドラクゥの即位は驚きを以って迎えられた。 ﹁その結果が、この有り様という訳だ﹂ アルナハ政庁の窓から外を見遣りながら、ドラクゥは小さく溜息 を漏らした。 眼下に広がる市街の街路という街路を埋めるように、旅人の群れ が歩き回っている。大魔王即位の式典に招いた者も中には混じって いるが、それだけではない。新大魔王を一目見ようとやって来た者 や、そういった連中に物を売りつけようとする行商人たちがほとん どだ。 拡張が進んでいるとはいえ元がさほど大きくないアルナハ城市の 容量を明らかに超す人数がこの街に滞在している。式典が行われる 五日後までには、さらにこの数は膨れ上がるはずだった。 既にリザードマンの文官であるシュリシアの計らいで陶壁の外に 大小の天幕が張られ、旅人たちの休養所として開放されている。長 173 旅を経てここまでやって来た民をむざむざ夜露に濡らす様な趣味を ドラクゥは持ち合わせていない。 ﹁既に魔王やそれに準じる来賓の方々も幾名か到着されております﹂ そう報告するのは、<蛮王>兼宰相に任じられたばかりのゴブリ とくひし ンシャーマン、ラ・バナンだ。 彼の差し出す涜皮紙に書き連ねられているのは、主にアルナハか トレント アルラウネ らそれほど遠くない場所に拠点を持つ魔王や豪族たちだった。 ﹁樹精属に花妖属の魔王か。珍しいな﹂ ﹁普段は外界の事には不干渉ですが、大魔王の即位式典には必ず出 ヤモリ 席しているとのことです。後は、リザードマンの諸部族代表として 家守族の魔王、ルーア殿がお見えです﹂ ﹁リザードマンか。よく代表を出したな﹂ ﹁代表という形ですが、恐らくはルーア殿の独断でしょう。家守族 しょうた はリザードマン五氏族の中でも最も弱く、数の少ない氏族です。我 々に庇護を求めてくるのかもしれません﹂ ﹁なるほどな。そういうことか﹂ くち アルナハの東、キリ・シュシュツの城市を中心とする広大な沼沢 地に暮らすリザードマンたちは、氏族やもっと小さな単位に分かれ て互いに争いを続けている。時に多くの戦死者を出すこの内紛とも りんじ 言うべき小競り合いに歴代の大魔王は心を痛め、幾度となく調停を 申し入れた。 しかしリザードマンたちは形の上では停戦命令の綸旨を推し頂き ながら、すぐに再び戦いをはじめてしまうのだ。 ﹁戦いこそがリザードマンの本性、と余に仕えたリザードマンの剣 士が話していたな﹂ ﹁彼らの宗教観は独特です。邪神に対する信仰を持たない﹂ ﹁ああ、そうらしいな。輪廻を信じているのだったか﹂ 死ねば魂はまた別の者として生を享ける。 古い信仰の形だ。今ではもう、リザードマンにしか残っていない。 魔界に暮らす多くの者にとって死とは完全なる終着点であり、そこ 174 より先には無しかないと考えられている。 トカゲ ヘビ ワニ カメ ヤモリ だが、リザードマンは違った。彼らリザードマンを構成する五つ の氏族、つまり蜥蜴、蛇、鰐、亀、家守はそれぞれ連関しており、 輪廻を繰り返しながら魂は五つの氏族を渡り歩いているのだという。 そして五つの氏族全てで目覚ましい武勲を挙げた者の魂は竜に召 され、天上の世界で永遠の安らぎをえるらしい。彼ら独特の、彼ら にしか通用しない信仰の形だ。 ﹁武勲を挙げる為に必要とは言え、飽きもせず戦い続ける強靭さに は恐れ入ります﹂ ﹁だが、意外に内政も上手い。シュリシアを見ただろう。あれで奴 隷階級の出身だ﹂ シュリシアは、拾い物だった、 戦いで死ぬことを生きる目的とする戦士階級のリザードマンは、 戦場以外で死ぬことを極端に恐れる。飢餓や疫病など以ての外だ。 となれば自然と内政にも力を入れざるを得なくなる。 だから奴隷階級に文字を教え、自分たち戦士階級は何不自由なく 戦争に明け暮れるのだ。 ﹁そのリザードマンたちを、配下に加えたいと﹂ ﹁ああ、あれだけの精強な兵力が、内にだけ向かっているのはどう にも惜しいのでな﹂ ﹁ごもっとも。文字の読める奴隷階級をこちらで登用すれば、文官 不足にも歯止めがかかります﹂ 兵と文官の不足を一挙に補うことが出来る。それはとても魅力的 な話だ。 今のアルナハは人材不足に見舞われていた。これから新生大魔王 としてドラクゥが即位するに当たり、最大の不安要因になっている。 これを解消することが出来れば、<北の覇王>と事を構える準備に も大いに弾みがつく。 大魔王位に就いたとしても、<北の覇王>からの圧力を跳ね返せ るだけの実力を手に入れねば、それは絵に描いた宝玉に過ぎない。 175 こけむ ﹁⋮⋮それに、<苔生した甲羅>キリックを放置しておくのは危険 だ﹂ 先の戦いで屠ったシェイプシフターの魔王<淫妖姫>パルミナは ドラクゥの暗殺を企てていた。 陰謀に長けた彼女はドラクゥに美姫を送り込み、毒を盛ろうとし たのだ。その方法を調べる過程で、リザードマン属の中でも亀氏族 を束ねるキリックの名が挙がっていた。 パルミナに利用されていただけなのか。それとも、主体的に策謀 に加担したのか。それがはっきりとしない以上、リザードマンに何 の対策もせずに背中を見せることは出来ない。 みいつ あまね ﹁その為にも、此度の即位式典は何としても成功させねばなりませ んな﹂ 至尊の座に就いたドラクゥの御稜威を魔界に遍く広める。 ドラクゥが大魔王であるということを最大限に利用しなければな らない。 ﹁後、五日か﹂ 見るともなしに、ドラクゥは西の空を見つめる。 邪神がもうすぐそこまで帰ってきている気がした。 ﹁ところで、余は可能な限り儀式は簡素に執り行うように伝えたは とくひし ずだが﹂ 涜皮紙の束をドラクゥは執務机に投げ出した。 机の上には同じような書類が無造作に散らばっている。そのほと んどは請求書や見積書の類いだ。 式典に際して予想される支出の額はかなり大きい。叱責混じりの 問いかけに宰相ラ・バナンは何も答えず小さく頭を下げた。これか らまだ増えるということだ。 衣装や食材にはじまり、政庁の修繕費に馬丁の賃金。果ては旅で 疲れた貴人の足を洗う木桶まで。細目は様々だが、全て大魔王即位 式に必要なものばかりだ。 176 大魔王即位の式典は単なる儀式としても、外交的な示威としても 仇や疎かにはできなかった。 今のドラクゥには領地も兵力も財力もない。あるのはただ、大魔 王としての権威のみ。式典とは魔界の民草と支配層にそのことを印 象付ける大切な舞台なのだ。 それだけに用意すべき物の質は自然と高くなり、購う為に必要な 金子の量は否が応でも増えざるを得なかった。 ﹁これではアルナハの金穀蔵の床が見えてしまうな﹂ ﹁資金不足はしばらく続くでしょう。ですが主上が大魔王にお就き になれば、交易も捗るはずです﹂ 本当にそうなるか、ドラクゥは微かに疑問を抱いている。 宰相に任じたラ・バナンは内政についての才を遺憾なく発揮して いるが、どうしても理に偏るところがある。元は学者のようなこと をしていた男だから、無理もない。癖のようなものだ。 現実と、理論。 二つは重なり合っているようで、僅かにずれている。そのあるか なしかの差異に直面した時、ラ・バナンは悩みながらも理の方を優 先する。それは悪いことではない。文官の頂点に立つ者としては、 その方が良いとさえ言えた。 侍女の淹れた湯冷ましの椀に口を付けながら、ドラクゥは黙考す る。 大魔王の座に就いただけで財政が劇的に改善されるということが あるのだろうか。 もちろん、今までよりは良くなるだろう。地方に城市を一つ持つ 魔王という立場と、魔界全土に号令を発する大魔王の地位とでは意 味合いが大きく異なってくる。 金山や銀山を領有すれば、貨幣を鋳造することもできた。 本来であれば大魔王府と各四天王にのみ許された特権だが、ドラ クゥの配下には名目だけとは言え、<蛮王>と<竜王>がいる。今 はまだ領地に鉱山地帯を有してはいないが、優先的に制圧すべき目 177 標に加えるべきだった。 だが今のところ、状況がすぐに改善するとは思えないのだ。 先程ラ・バナンに手渡された来賓の一覧には、魔王の名が少ない。 魔界に一〇八いるとされる魔王の中で、ただ純粋に大魔王としての ドラクゥに恭順の意を示そうというものはまだ、ほとんどいないと いうことだ。 それは仕方がない。 魔都はまだ<北の覇王>に押さえられたままで、大魔王府とも袂 を分かった。今のドラクゥには本当に名目しかないのだ。ここから 雄飛するには、力や領土、そして何よりも兵力といった実が必要だ った。 この式典を成功させ、内外に力を示す。 そこで得られた声望を元に、一気に実力を伸ばさなければならな いのだ。 ﹁その為にも、まずは金か﹂ 誰にともなくドラクゥが呟く。 アルナハは決して貧しい城市ではない。 以前にここを治めていたゴブリンシャーマンの魔王の時代と比べ ると、状況は格段によくなっている。 簡素で分かり易い税制。適切に行われる裁判と周知された法律。 市場や街道の整備にもドラクゥは心を砕いていた。 人が集まりやすくなれば、そこに商いが生まれる。僅かな期間で アルナハは辺境でも有数の商業都市に生まれ変わりつつあった。 城市一つとしては十分に潤っているのだ。しかしそこから大魔王 としてのドラクゥを支えるだけの収益までは、確保できていない。 そんなことは魔都でさえ不可能だ。 繁栄した一城市程度の富の集積では支えきれない程の金穀が大魔 王には必要となる。大魔王府とはそもそも、大魔王家の保有する莫 大な資産と、巨額の支出を管理する家産管財人だったという話さえ ある。 178 今のドラクゥは必要な経費の多くを富裕な商人からの借款で賄っ ている。純粋な好意と、将来に向けた投資のつもりだろう。利子が それほど高くないのは大魔王への顔つなぎのつもりなのかもしれな い。 重税を掛ける気なかった。 まつりごと 民に平穏をもたらすために践祚するのだ。その民から血の一滴ま で搾り取るような政などをしていては、折角ドラクゥに集まった期 待も容易に怨嗟へと置き換わる。 民を虐げずに、金を得る方法が必要だ。 ただの貴金属の塊にどこまで縛られなければならないのか。 先代大魔王である祖父も、その父も、財政には苦労をしていた。 魔界を統べる絶対者であるはずの大魔王が、金貨銀貨の多寡如きに 一喜一憂せねばならないのはどうにもおかしかった。 そんなことを考えていると、不意に目の前の虚空が揺らいだ。 ﹁資金の心配なら、何とかしてやれると思う﹂ † † † 邪神ヒラノが人界から持ち帰った塩で、ドラクゥは財政的に一息 つくことができる見通しが立った。 大魔王即位と、アルナハ周辺の地盤固めに邁進するドラクゥ。 妖鳥族の魔王フィルモウやゴブリンの傭兵隊長ロ・ドゥルガンを 配下に加え、リザードマン領と北方の両面をにらんだ策を展開する。 その一方、体調不良で神界の病院に担ぎ込まれたヒラノは、自分 が査問会議に掛けられそうになっていることを知るのだった⋮⋮ 179 第二章ダイジェスト版 ﹁マスター、おまたせー﹂ 慶永さんが藪医院に戻って来たのは日も沈みかけた夕方のことだ った。手に紙袋を二つ下げている。 厚手のフードマントを羽織るという大して意味があるとも思えな い変装を解きながら、こっちにその紙袋の一つを投げて寄越した。 見たことのないブランドロゴだが、重さからして中身は服だろう。 今まで節約で安い服を着回していたから、神界で高い服なんか買っ たことが無い。どの程度の価格帯のものかは、袋からではさっぱり 分からなかった。 ﹁流石にその格好じゃまずいから、さっさと着替えて﹂ たかいびき そう言うと自分ももう一つの紙袋を下げて処置室の方に引っ込ん でしまう。酒に呑まれて高鼾をかいている藪先生に背を向け、俺は 慎重に紙袋の封を切った。 中に入ったのは、スーツ一着とネクタイに革靴、ベルトと革財布 というビジネスマン一式セットだ。 単なる吊るし売りではない。気合いの入った仕立ては素晴らしい 着心地で、身体にフィットするのが分かる。前世ではついに最後ま でペラペラの既製品しか着ることが無かったが、それとはまるで別 次元だ。 スーツに詳しくない俺でも知っているダンヒルやエルメネジルド・ ゼニア、ブリオーニやアルマーニを着たらこんな風なんだろうか。 ネクタイの色目もスーツに合っていて、気取ったところが無い。品 のあるコーディネートだ。 靴にベルト、財布も全部一級品。全部着替えて医院の大きな姿見 の前に立つと、まるで別人のような俺が映っている。 ﹁思ったより似合ってるじゃん﹂ 声を掛けられて振り返ると、そこには落ち着いた雰囲気のイブニ 180 ングドレスに身を包んだ慶永さんがいた。袖口を大胆にカットした デザインのドレスは、慶永さんの健康的な肢体によく映える。いつ カルマ もの茶目っ気溢れる表情は影を潜め、まるでどこかの御令嬢のよう だ。 ﹁この服、どうしたんですか?﹂ ﹁買った﹂ ﹁いやまぁ、そりゃ盗んだわけじゃないでしょうけど、徳とか、サ イズとか⋮⋮﹂ 慶永さんに信者はいない。 元々は人界で戦女神をしていた慶永さんだが、“聖堂”との戦い カルマ に敗れて信者は全て滅びるか奪われてしまったはずだ。信者がいな ければ徳は貯まらない。神界から給付される僅かばかりの収入では いずれ生計が成り立たなくなるはずだ。 それなのに、どうやって慶永さんはこれだけの服を調達したのだ ゆうめいじん ろう。決して安くはないはずだ。 ﹁私、これでもちょっとした有名神だかんね。昔馴染みに頼めばこ れくらいは融通も利かせてくれるってもんよ﹂ ﹁そんなもんですか﹂ ﹁そんなもん、そんなもん。細かいことは気にしなくていいの。後、 神界では良い服って特殊な素材で作られてるから、身体のサイズに 合わせて勝手に伸縮してくれるから。便利でしょ﹂ ﹁ほぉ、そいつは便利ですね﹂ 一度買ってしまえば体型が変わってもそのまま着られるという訳 か。良いものをずっと使いたいという人には天国のような場所だな。 まぁ、神界だから天国みたいなものかもしれないけれど。 でもそれだと服飾店が成り立たないような気もする。一度買って しまえばほぼ半永久的に長持ちするなら、買い替える必要がないか らだ。 前世でブラック商社に勤めていた癖でついついそんなことを考え ていると、慶永さんに額をこつんと叩かれた。 181 カルマ ﹁心配しなくても服はちゃんと売れるよ。徳持ってる神さまにして みりゃ、着道楽に食道楽、飲み道楽くらいしかすることないんだか ら﹂ なるほど。永遠にも等しい時間を、何の苦痛もなしに生きていか なければならないのだ。そういう娯楽に比重が置かれるのも無理は たち ないことだろう。俺が以前、賭け碁で結構な額を稼げたのも神さま たちが賭博にのめり込んでいたからだ。 ﹁それにしてもよく考えてることが分かりましたね﹂ ﹁ヒラボンは昔から気にしなくてもいいことばっかり気にする性質 だったからなぁ﹂ にんまりと笑いながら慶永さんが腕を絡めてくる。 ﹁さ、マスター。今日はしっかりとエスコートして貰いますからね﹂ ﹁え、エスコートぉ?﹂ 木を隠すなら森、というのは元々チェスタトンというイギリスの 作家が書いた小説の一説を元にしているらしい。もちろん、俺はそ んな本読んだことはない。そんな暇があったら歴史シュミレーショ ンゲームをする時間に充てていた。 ではなぜそんなことを知っているかというと、取引先の上得意に 英米文学科を卒業した人がいて、一時期毎晩のようにキャバクラで そのオッサンの英文学講座を拝聴することになったからである。 逃亡中であるはずの俺は慶永さんに促されるままに夜の神界を歩 いていた。 木を隠すなら森、神さまを隠すなら神さまの中、と言えば大した 策略家のようだが、実は内心気が気ではない。準備も整わない内に 会議に引っ張り出されるのは御免だった。 ひと ﹁慶永さん、これ、大丈夫なんですかね?﹂ ﹁大丈夫大丈夫。こんな神通りの多い所で紳士淑女を拉致するみた いな無粋な真似、流石のガーフィンケルでも出来っこないって﹂ ﹁紳士淑女、ねぇ﹂ 確かにフォーマルスーツに身を包んだ俺と慶永さんは紳士淑女に 182 見えなくもない。見えなくもないが、どうやら周りの人々の目には 余程奇異に映っているのか、さっきから好奇の視線が痛かった。 幻想的な淡い光で照らし出される夜の街には着飾った神さまたち が思い思いに歩き回っていてとても賑やかだ。往来にはざっかけな い夜店が出ているかと思えば、通りを一つ跨げば落ち着いた石畳の 道がほのかな幻燈に照らし出されていたりする。 ﹁ここはね、年がら年中がお祭りみたいなものなのさ﹂ 夜店のりんご飴を物欲しそうに眺めながら慶永さんが呟く。イブ ねだ ニングドレスで焼きそばやわたあめには齧り付けないと判断したの か、強請って来ない。強請っては来ないもののそれでもやはり気に はなるらしく、汁なしフォーとシシカバブの屋台の辺りで視線を彷 徨わせていた。 俺の方と言えばどこかから監視されていないかと周囲の気配を探 るのに忙しくてそれどころではない。実際、尾行もついているんで はないだろうか。これだけの混み合っていると誰が誰だか分からな い。 ﹁そういえば慶永さん、これからどこに行くんですか? そろそろ 教えて貰えません?﹂ ﹁ああ、まだ言ってなかったっけ。マスター、なんか食べたいと思 わない?﹂ ﹁そりゃまぁ、ずっと病院で寝てましたからそろそろ何か腹に詰め たいですけど﹂ 邪神に転生してからは、空腹という感覚が無い。ただ漫然と、何 か食べたいと思うことがあるだけだ。それも堪えられない物ではな く、どちらかといえば味覚を楽しませたい欲求という意味合いの方 が強い。 食べることが最上級の気分になるのは事実ではあるので、確かに 何か食べたい気分ではある。 問題は人に追われている状態で、しかもこんなフォーマルな格好 に身を包んで目立たない食道なんかが存在するのかどうか、という 183 ことなのだが。 ﹁じゃ、あそこに行こう﹂ 気持ちのいい笑顔を浮かべた慶永さんが指差した先には、煌びや かに彩られた超高層の高級ホテルの輝きがあった。 ﹁い、<戦女神>様ですか⋮⋮﹂ その名前が出た瞬間、辺りの雰囲気が明らかに変わった。 ついさっきまでは半身に構えていた女神が慌てて姿勢を正し、一 礼してから何処かに走っていく。こちらから見て死角になる植え込 みの陰に隠れていた別の用心棒たちも姿を現し、慶永さんの方に深 々と頭を下げた。次々と警備の神が出てきて整列するので、パーテ ィ会場前のホールはあっという間にヤクザの出所祝いのような状態 になってしまった。 整然と並ぶ神々からは先程とは打って変わって、最上級の敬意が 感じられる。それもこれも、<戦女神>としての慶永さんの名声の なせる技なのだろう。 ﹁⋮⋮慶永さん、すっごいネームバリューですね﹂ 俺が肘で突いて小声で尋ねると慶永さんはむふんと自慢げに胸を 張る。 ﹁まぁね。このパーティの主催者とはちょっとした仲でさ﹂ ﹁昔のお仲間ですか?﹂ ﹁ま、そんな処﹂ 慶永さんは前世の頃から仲間を作るのが妙に上手い。ほとんど才 能と言っていいほどのカリスマで、初対面の相手ともさっさと仲良 くなれてしまうのが本当に羨ましかったことを覚えている。 多分、こっちに転生してからもあちらこちらに仲間を作って来た のだろう。もちろん、竹を割ったような性格だから、フォン・マル クントのように敵も作っているんだろうが。 ﹁それよりもマスター、ここから先は何を言われてもニコニコ笑っ て、上手く合わせて頂戴﹂ ﹁了解、了解。万事お任せしますよ﹂ 184 ﹁素直で結構、大変よろしい。ま、私に任しておきなって﹂ ﹁期待してます﹂ 実際、俺の方には不安はない。 こう言って請け負った時の慶永さんに任せて失敗したことはない のだ。何だか城南大学附属高校時代に戻った気がして、自然と頬が 緩む。 ﹁ちゃんと舞台は整えてあげる。そこで何をするかはマスターの自 由だからね。さ、来たよ﹂ 扉の両側に立った女神が勿体ぶった所作で引き開けていく。 パーティ会場から零れる光でホールが眩く照らし出された。その 光の洪水の中から、虎の背に跨った一柱の女神がゆっくりと進み出 てくる。 現われたのは、鞣した革のように艶やかな褐色の肌を持つ美しい 女神だ。インド風の民族衣装に身を包み、悠然と微笑む姿はインド の宗教画から抜け出してきたようにも見える。 ⋮⋮ただ一点、身長を除いて。 ﹁よ、チビのカーンティ、元気してた?﹂ ﹁チビは余計なのじゃ、<戦女神>!﹂ 器用に虎の背中で飛び跳ねて見せるカーンティという女神は、と ても小さい。少女の様に幼いという意味ではなく、等身はそのまま に縮尺だけ小さくなっている。身長は丁度俺の膝くらいだ。これも 神さま基本セットの効果なんだろう。 それにしても慶永さんにからかわれたのが余程悔しかったのか顔 を真っ赤にしているカーンティは最初の印象とは違って大変可愛ら しいのだが、いきなり責任者を怒らせてしまって大丈夫なんだろう か。 周りの警護の神さまたちが何も反応していない所を見ると、これ が当たり前の光景なのかもしれない。 マスター ﹁ところで<戦女神>よ、そっちの若いのは?﹂ ﹁ああ、これが私の主神﹂ 185 ﹁どうも、はじめまして。ヒラノです﹂ マスター 営業スマイルを浮かべてさっと右手を差し出すと、カーンティは 口元に笑みを浮かべて俺の人差し指を握り返した。 ﹁<豊穣>のカーンティじゃ、よろしくな。お主の主神、ヨシナガ には夫婦ともども世話になっておる﹂ マスター と、そこで慶永さんが口を挟む。 ﹁違う違う、カーンティ。主神は、こっちのヒラノ様。属神が私。 分かる?﹂ ﹁何の冗談を言っておる? <戦女神>ヨシナガじゃぞ? それを お前、こんな若い神が属神として従えるなどと、そんなこと聞いた ことも⋮⋮﹂ だがそこでカーンティも俺と慶永さんが真面目な顔をしているこ とに気付いたらしい。 マスター ﹁⋮⋮まさか、冗句ではないのか?﹂ ﹁うん。正真正銘、ヒラノ様が主神で、私が属神だよ﹂ ﹁なんとまぁ⋮⋮あの、じゃじゃ馬<戦女神>をなぁ⋮⋮﹂ カーンティは余程驚いたのか小さな口をパクパクさせて何か呟い ている。 ﹁でさ、カーンティ。今日は旦那の方に用があるんだけど﹂ ﹁生憎じゃが、うちのダーリンは用事でな。今外出しておる﹂ ﹁あっそ。じゃあ、ちょっと呼んでくれない? パーティに参加し ながら待たせて貰うからさ﹂ これだけのホテルでパーティを主催する神様と、慶永さんは一体 どういう関係なんだろうか。しかも外出先から呼び戻せとまで言い 放っている。自分が営業だった頃、社長の知人だとかいう地方議員 を接待したことがあるけれど、それでもここまで無茶なことは言わ なかったと思う。 それでも周囲に立っている警備の表情からは、慶永さんがあまり 無茶なことを言っているという風には読み取れない。そうすること が当たり前、というようにさえ見える。 186 ない あ ﹁ま、そう言うと思ったわ。誰か、<戦女神>とそのお連れ様を案 内せい。それと、一番いい酒を用意して持って行ってやれ﹂ ﹁ありがと、カーンティ﹂ ﹁他ならぬ<戦女神>の頼みじゃ。無碍にすることなど出来るわけ が無かろう。お主がおらんかったらこんなところでパーティなんて 開けんかったんじゃなからな﹂ ﹁いやいや、まぁそれほどでもあるかな﹂ 感謝されて満更でもなさそうな慶永さんをエスコートし、俺はパ ーティ会場に足を踏み入れた。 空が高い。 目の前に広がっていたのは、ホテルのパーティ会場とは思えない 光景だった。 美しい水を湛えた湖にはボートが浮かび、その周囲には緑豊かな 雑木林が広がっている。天には鳥が歌い、木漏れ日を浴びて走り回 る栗鼠の姿さえ見えた。ちょうどイギリスの湖水地方のような景色 の中で、神々が思い思いに酒を酌み交わしたり食べ物を摘まんだり している。 ﹁どう、ちょっと驚いたでしょ?﹂ 悪戯っぽく微笑む慶永さんに俺は言葉を返すことすらできない。 ホテルの中に、外がある。神界だから何でもありだということは 頭では理解していても、実際に目の当たりにすると衝撃はなかなか のものだ。 ﹁この会場はホテルの中でも特別。主催者の思う通りの景観に設定 できるんだってさ﹂ ﹁すっごいですね⋮⋮これ﹂ カルマ バーチャルリアリティではない。本物の自然をホテルの中に作り 出す。土の匂いまで再現したこの空間は、一体どれほどの徳で維持 カルマ されているのだろう。森全体に人除けの結界を張っていたジョナン 翁も凄かったが、こちらは想像もつかない。 この美しい景観を創り出すために使われている徳を有効に使えば、 187 どれだけ多くのルロのような人々を救うことが出来るんだろうか。 ﹁そう言えばマスター、体調はもう大丈夫?﹂ ﹁ああ、もう大丈夫ですよ、多分﹂ まだ本調子という訳ではないが、パーティ会場に入ってから身体 の重さや倦怠感も随分と楽になった。多分、という言葉に慶永さん の目つきが一瞬険しくなったのは、俺が自分の体調をあまり顧みず に無茶な事ばかりするからだろう。 ﹁ま、今日の所は信じてあげましょ。でも、食事とかは私が取って マスター 来てあげるから﹂ 主神はどこか適当に座っておいて、と言われたので大人しく東屋 の椅子に腰を下ろす。ここは空気も澄んでいて本当に居心地がいい。 目に映る範囲だけで百柱ほどの神々がパーティに参加しているよう ようにん だが、皆のびのびと寛いでいるのがよく分かる。 以前、慶永さんから神々の遙任の話を聞いた。 神として任された自分の仕事は属神に全て任せ、神界で面白おか しく暮らす神々のことだ。きっとここで社交に興じているのも、そ ういう神々なんだろう。 夜会服に身を包んで近くで談笑している女神たちの表情からは、 何か生業を持っている者の顔に必ずある、日々の疲れのようなもの が一切見えない。 ﹁お待たせ! さ、一緒に食べよ﹂ 慶永さんが持ってきたのは、サンドイッチや冷製パスタ、生ハム、 赤身魚のカルパッチョなんかの立食パーティの定番メニューだった。 邪神に転生してから食欲とはとんと縁がなくなったのだが、それで も美味しいものを食べたいという気持ちだけは変わっていない。 勧められるままにパクつくと、どれもこれも流石に美味い。思わ ず急いで食べ過ぎて、慶永さんに水を汲んできてもらう羽目になっ た。 ﹁マスターったら慌て過ぎ。そんなにがっつかなくても取りに行っ たらまだまだあるんだから﹂ 188 ﹁いやぁ、前世では接待以外ではこんな料理食べたこともないから、 ついつい﹂ 頭を掻きながら照れ笑いを浮かべる俺を見つめる慶永さんの顔が 一瞬だけ哀しげに歪んだのは黄の所為だったのだろうか。 カーンティの部下が持ってきてくれた極上の赤ワインにも舌鼓を 打ちながら、俺は慶永さんの持ってきてくれる料理を次々に食べた。 カリッカリに揚がった牛肉のカツレツや絶妙な焼き加減のロース トビーフ。結局、前世は一度も口にする機会の無かった北京ダック も食べてみたが、期待した程には美味いものでもなかったと思う。 それよりはとろとろに煮込まれた豚の角煮を挟んだ饅頭の方が、俺 の好みだ。 邪神になって良かったと思うことは、腹が膨れることがないとい うことだった。古代ローマ人は美食を愉しむ為に食べた端から鳥の 羽根で喉の奥をくすぐって全部出してしまっていたというが、そん なことをする必要もない。 病み上がりの俺を気遣ってくれているのか、慶永さんはどんどん 料理を運んできてくれる。それが嬉しくて俺はどんどん料理の皿を 空にしていった。 気が付くと、いつの間にかパーティの参加者の注意がこちらに向 いている。はっきりとこちらを見るような無粋な奴はいないが、明 らかにこちらを窺う気配があった。 ﹁マスター、視線を合わしちゃ駄目。挨拶や自己紹介も、こっちか らはしちゃ駄目だから﹂ 栗おこわを頬張りながら慶永さんが小声で警告してくれる。小さ な口に一生懸命詰め込もうとしている所は、小動物のようでかわい い。 ﹁⋮⋮どういうことなんです?﹂ ﹁男も女もね、少々ミステリアスなくらいが噂の的になるもんなの﹂ ﹁話の筋が、さっぱり話が読めません﹂ ﹁⋮⋮暫く姿を消して可愛い女の子が、誰も見たことも聞いたこと 189 もないボーイフレンドを連れていたら皆はどう思う?﹂ ﹁ああ、なるほど﹂ 漸く、慶永さんの策が読めた。 これは、俺の名声を上手く上げる為の宣伝戦だったというわけだ。 暫く社交界に姿を現さなかった女神が、見も知らぬ神の世話を焼 いている。それもあのヨシナガが、だ。パーティに現を抜かす暇を しょうそいのじょう 持て余した神々にとって、これは格好の噂の種になるだろう。 単なる少初位上の位に過ぎない邪神の俺が、曲がりなりにも名前 を売るためにはこういう搦め手から攻めるのが一番いいと慶永さん は判断したのだろう。 仮に徒手空拳で査問会なり証人喚問なりに呼ばれたとして、神界 での知名度のあるなしは扱いに多少の影響を与えるに違いない。そ れも、恐らくはいい方向に。 東屋の周りにはさっきよりももっと神々が集まり始めている。 何をするわけでもない。こちらを見るともなしに見ながら神々が こそこそと何か噂をしているだけだ。それをぼんやりと眺めながら ワインのグラスを傾けるのは、ちょっと得難い優越感がある。 瓶が空になったので次の酒を何にしようか考えていると、最早人 だかりのようになっていた神々がさっと左右に割れた。モーセの割 った紅海のように道を開けた神々の間を通って来たのは、タキシー ドに身を包んだ上背のある紳士風の男だった。 灰色の髪に鋭い鳶色の目を持つその男は、慶永さんの前に来ると 地面に膝を突き、深々と頭を下げた。 ﹁大変お待たせを致しまして申し訳ございません、<戦乙女>の姐 御﹂ ﹁ユーリィ、久しぶり。そんなに畏まらなくていいよ﹂ 顔を上げ、ユーリィと呼ばれた神が立ち上がる。 ﹁マスター、紹介するね。この色男はユーリィ。カーンティの旦那 で、夜魔族の邪神だ﹂ ﹁夜魔族の、邪神⋮⋮﹂ 190 夜魔族と言えば魔界の北方、魔都近くに暮らす魔族だったはずだ。 詳しいことは知らないが、ドラクゥの宿敵である<北の覇王>ザ ーディシュに抵抗を続ける種族だとエリィナから聞いたことがある。 元々はトロール族と同じ祖先から枝分かれした種族だというが、角 がない為に永く迫害されてきたらしい。 その夜魔族に崇められる邪神が、目の前にいる。 ﹁⋮⋮失礼だが姐御、こちらの男性のことをお伺いしても?﹂ ﹁ユーリィ、こちらにおわすのは私の主神マスターで、ヒラノ様。 邪神よ。覚えておいてね﹂ 主神、という言葉を聞いた途端、ユーリィは俺に向かって深々と 頭を下げた。 ﹁ヒラノさん、私はユーリィ・コンスタンティノヴィチ・ロボコフ スキー。紹介に与あずかった通り、夜魔族の邪神だ。<戦女神>の 姐御のお陰で随分と神がましくさせて貰った。姐御の主神であるア ンタにも相応の敬意を払わせて貰うとしよう﹂ ﹁ユーリィ、頭を上げてよ。今日は食事とちょっとしたお願いに来 ただけなんだから﹂ ﹁いやしかし、大恩ある姐御の主神相手だ。万に一つの粗相もあっ ちゃならねぇ﹂ ユーリィの口調や鋭い眼光、それに威圧感はまるで大きな組の若 頭といった風格だ。 ヤクザしかりマフィアしかり、こういう気質かたぎの人は疑似血 縁的な上下関係をとても重んじることが多い。それも、外から見る と一件理解しがたい法則性に基づいた関係を、だ。昔慶永さんに世 話になったというこのユーリィという邪神の中で、俺は今のところ 彼自身より上位に置かれることになっているらしい。 ﹁ユーリィさん、今後ともよろしく﹂ 俺が握手の為に手を差し出すと、ユーリィはほんの一瞬だけ目の 奥に戸惑いの色を覗かせたが、すぐにがっしりと握り返してきた。 骨太の掌は大きく、全てを掴みとってしまいそうに力強い。 191 ﹁こちらの方こそ、よろしくお願いします﹂ 射抜く様な眼光で、ユーリィは俺を見つめた。俺が何者か、未だ に計りかねているのだろう。<戦女神>の主神であるのに、無名。 神界全体に顔が利くであろうユーリィさえも知らない顔だ。警戒八 分に興味が二分。ここで自分の素姓を喋ってもいいのだが、慶永さ んからは﹁合わせて﹂と事前にアドバイスを受けている。対面して すぐに自己紹介しなければならないのなら、慶永さんの方から誘導 があるはずだ。 郷に入っては郷に従え。ここは慶永さんに全てを委ねることにし て、俺はユーリィにワインを勧めた。 ﹁なるほど。ガーフィンケル爺さんに追われているってわけですか﹂ ﹁そうなのよね。査問会でも証人喚問でもうちのマスターに疾しい ところは無いから出ることは出るんだけど、事前の準備もなしにと いうのは例もないことだしね﹂ 酒を酌み交わしながら久闊を叙す慶永さんとユーリィの間で簡単 な事情の説明が行われている。オレはその間、生ハムを食べたり集 まって来た女神たちに曖昧な笑みを浮かべたりするのが大きな仕事 だ。 ﹁姐御は相変わらず人使いが荒いな。その辺りの始末を私にやれっ ていうんですか﹂ ﹁無理にとは言わないよ。ここに来たのもたまたま今日アンタがパ ーティを開いてるって聞いたからだし﹂ 嘘だろう。ドレスを調達してきた慶永さんは、してやったりとい う表情を浮かべていた。最善のタイミングでユーリィがパーティを 開いていたということだ。頼る相手は他にもいるのだろうが、ユー リィに頼むのが最良、ということなんだろう。 ﹁分かりましたよ、他ならぬ姐御の頼みだ。お請けしましょう。フ ォン・マルクントの時の借りもある﹂ ﹁あの賭場、全部マルクントに取り返されちゃったらしいじゃない﹂ ﹁ハコだけですよ。顧客も金主もそっくりこっちに頂きました。あ 192 の金髪縦ロールのお嬢が今まで散々暴利を貪ってましたからね。お 客さんたちには感謝されたくらいです。お陰で随分と良い目を見さ せて貰いましたよ﹂ なるほど。慶永さんはライバルであるフォン・マルクントの手か ら賭場を奪い取ったことがあったらしいのだが、それを任せたのが このユーリィだったということか。確かに儲けの大きな賭場の支配 権を融通して貰えたのなら、頭が上がらないのも無理のないことか もしれない。 ﹁いいでしょう。このユーリィ・コンスタンティノヴィチ・ロボコ フスキーの名にかけて、お二人を絶対安全な場所で匿いましょう﹂ ﹁絶対安全な場所とは大きく出たね。今の神界でガーフィンケルの 手が届かない場所なんてそんなにないと思うんだけど﹂ ﹁御心配には及びませんや。ヒラノさんにも姐御にも、絶対に手出 しは出来ません﹂ ﹁もったいぶらずに教えてよ。どこに匿ってくれるつもりなの?﹂ ユーリィは口元に小さく笑みを浮かべると、懐から葉巻を取り出 し斜めに咥えた。流れるような手つきでマッチを擦ると、ゆらりと 紫煙が湖水の空に立ち上る。 ﹁議事堂です。神界大会議場の議員控室。あの中になら、たとえガ ーフィンケルと言えども手出しは出来ません﹂ † † † 神界の中心から遥かに地下、議事堂へと誘われたヒラノが見たの は巨大な方舟であった。 そこでガーフィンケルに対する対策を練るヒラノ。 何故この世界ではある種の技術の開発が厳重に禁止されているの だろうか。ヒラノは徐々に革新に近付いていく。 その頃、即位式を控えたアルナハにも不穏な空気が漂っていた。 193 存在を秘すべきダークエルフのシュノンの扱いを巡って、小さな 諍いが起きようとしている。ドラクゥの真意はどこにあるのか。 194 第三章ダイジェスト版 陽が欠けた。 それまでいつも通り何ともなかった青空が俄かに昏くなり、天を 仰ぐと太陽が欠けていたのだ。アルナハ政庁の執務室から、ドラク ゥはその様子を見ていた。 丸い陽に黒く一回り小さな円が重なり、一瞬だけ夜のようになる。 そして再び陽は元通りの姿に戻った。 脇に控えたラーナがドラクゥに恭しく頭を垂れる。 ﹁おめでとうございます、主上﹂ ﹁日蝕、か。話には聞いていたが、余も見るのは初めてだ﹂ ﹁今回の日蝕は一度陽光が全て遮られておりますので、特に珍しい ことほ 皆既日食というものでしょう。伝承によれば天運の拓ける最上級の 瑞兆だと言われております。明日の主上の即位を天も寿いでいるの でしょう﹂ 上手く考えたものだ。心の底から、ドラクゥはこの美姫に感心し ていた。即位式の日取りを決めたのは、このラーナとラ・バナンの 二人だ。コボルト族のクォンも相談に乗ったらしいとは聞いている。 式の前日に日蝕が訪れるように、日程を調節したのだろう。 珍しい出来事ではあるが、事前に起こる日付が分かっていればこ う言うことも出来るようになる。ドラクゥは帝王学の一環として天 文の初歩を習い修めているが、知識のないものには驚天動地の出来 事に違いない。今頃はアルナハ市中でこの事が瑞兆だと広められて いるはずだ。 暦日に関する知識は大魔王府の管掌する秘事とされ、星辰の動き と共にその資料は魔都の宝物殿に厳重に保管されている。星を読む ドラゴンハーフ 役目を与えられた種族のみが閲読できるものだったはずだが、恐ら くは竜裔族にどこかの段階で漏れ伝えられた物が残っていたのだろ う。 195 それを利用する手管が、上手い。 ラ・バナンの発案ではないはずだ。宰相として非常に優秀な男だ が、その発想は今あるものを改良するといった種類の才能だった。 遥かに飛躍して、全く新しい種類の着想を得ることにはあまり向い ていない。 であれば、ラーナのしたことなのだろう。 はかりごと 民心の掌握の為に、天象までを道具として用いる。かつての敵手 であったパルミナの操る陰謀とは違った種類の謀を、ラーナは自然 体で行うことが出来るようだった。 女でなく男に生まれていれば、一廉の文官として名を成したのか もしれない。 ラーナの淹れた茶を啜る。 本来であればこんな仕事は侍女にやらせるべきことだったが、ラ ーナは自分でやると言って聞かなかった。ドラクゥも最初は渋った ものの、今では済し崩しに許している。 茶が、美味いのだ。訓練を積んだ侍女でもなかなか出せないほん の僅かな風味を、ラーナは引き出すことが出来た。 ﹁いよいよ、明日ですね﹂ ﹁ああ、明日だな﹂ 明日の式典で、ドラクゥは正式に<大魔王>に就任する。 祖父である先代大魔王が隠れてから長く空位の続いた至尊の座に、 漸く主が定まるのだ。 それで何かが変わるわけではない。到達点ではなく、出発点なの だ。その事をドラクゥはよく知っている。 躊躇いは無い。 生まれた時からドラクゥは大魔王になることを周囲に望まれた子 供であったし、祖父より前に父が倒れた時に仮定はほぼ確定に変わ った。覚悟なら、疾うの昔に済ませているのだ。 今までドラクゥが大魔王に就けなかったのは、ひとえに<北の覇 王>ザーディシュの策動があったからだった。大魔王府の重臣たち 196 を抱き込みドラクゥを<廃太子>へと貶め、南の辺境へ放逐したの は、全てあの老人の差し金だ。 だが、不思議と今のドラクゥにそれを恨む気持ちは無かった。 当然抱くべき怒りの火は今も胸の中に燻っている。犯した罪に対 する償いもさせねばならないという気持ちは時に眠りを妨げるほど に強い。 ただ、結果として良かったと思うこともある。 もしあのまま先代の後を継いでいたとしたら、自分は平凡か、或 まつりごと いは暗愚な大魔王として列王記に名を残すことになったかもしれな い。少なくとも、今ここにいるドラクゥよりも良い政が出来たとは 思えないのだ。 それは繰り返し考えてきたことだった。 どういう大魔王になるべきなのか。誰かに望まれているというこ とではなく、ライノンの子ドラクゥが、どう在りたいのかという問 題だ。 邪神ヒラノの照覧を受けて、何ら恥ずべきことのない大魔王。そ れが、今のドラクゥの理想だ。 その為には、しなければならないことを一つずつ解決していかな ければならない。 空虚な言葉で目標を飾るのではなく、大魔王として行う決裁の一 わだかま つ一つで、ドラクゥは自分の目指す大魔王の姿、自分の目指す魔界 の姿を伝えなければならないと思っていた。 ﹁ラーナ、済まないが少し席を外してくれないか﹂ ﹁畏まりました、主上﹂ 一人きりになった部屋で、ドラクゥは天井を仰ぐ。心の中に蟠っ ているものを、解決しなければならない。もっと早くにするべきこ とだったが、まだ遅きに失したというわけではないはずだ。 立ち上がると、ドラクゥは手ずから二人分の茶を淹れた。 これまで一度としてやったことのないことだ。自然、手際は悪い。 少し零れた茶を拭き取ってから、ドラクゥは天井に向かって声を掛 197 けた。 ﹁シュノン、話がある。入れ﹂ シュノンの表情は、いつにも増して読めなかった。 静かに怒っている。そんな風にドラクゥの目には映った。ただ、 立っているだけで部屋が肌寒くなるような雰囲気はこれまでに見せ たことのないものだ。 ﹁シュノン、話がある。少し長くなると思う﹂ 普段通り片膝を立てて跪くダークエルフに、ドラクゥは椅子を勧 めた。 ドラクゥ以前にアルナハを支配していたゴブリンシャーマンの魔 王が購わせた、高価な椅子だ。 大魔王の執務机と相対する椅子に座ることが許されるのは、本来 ならば魔王か高位の文官武官に限られる。少なくともドラクゥの知 る限りダークエルフがその席を許されたことは無かったはずだ。 ﹁シュノン、座れ﹂ 動こうとしないシュノンに、ドラクゥはもう一度同じ言葉を掛け た。ゆっくりと立ち上がり、シュノンはドラクゥと向かい合うよう に腰を掛ける。表情は、やはり読めない。 無言で茶を勧めるが、それにもやはり手を付けなかった。 風があるのか、窓の外から葉擦れの音が聞こえる。 ドラクゥは何も言わず自分の茶碗に口を付けた。美味くは無い。 いや、どちらかと言えば、不味い部類に入るだろう。何しろ、自分 で茶を淹れたことなどこれが初めてなのだ。見様見真似でやっては みたが、失敗だったようだ。 ﹁⋮⋮主上、お話とは﹂ ﹁ああ、知っての通り、即位式のことだ。式典に、シュノンの席を 設けさせている﹂ 即位式はもう明日に迫っている。その式典に何故ダークエルフの 頭領であるシュノンの席を設けるのか、ドラクゥは今までシュノン に説明できずにいた。 198 ﹁⋮⋮畏れながら、今からでも席次を変えて頂くことは出来ません か。席は空席にしておくとは言え、やはりダークエルフは表の場に その名を出すべきではないように思います﹂ ﹁それは出来ない相談だ、シュノン。ラ・バナンもあれで随分と骨 を折っている。急な変更は難しいだろう。仮に出来たとしても、余 はそなたの席を今から取り上げるつもりは毛頭ない﹂ 取り上げるという表現に、俯き加減だったシュノンの顔が微かに 上がる。 ﹁主上、取り上げるなどと。ダークエルフは影の者です。いるのか いないのか定かでない時にこそ、<大魔王の手>、<大魔王の耳> は最大の力を発揮する。それを喧伝するというのは畏れ多くも歴代 の大魔王様方のいずれもなさらなかったことです﹂ ﹁つまり、触れずにそっとしておけ、と﹂ ﹁そうは申しておりません。ダークエルフは主上の道具。その道具 に式典の席などという栄誉をお授けになるのは過去に例が無い、と﹂ ダークエルフの忠義の形は独特だ。時には命さえ捧げる苛烈な奉 公に対して、大魔王の血族は何一つ彼らに報いることが無い。財貨 も土地も役職も、この青白い肌を持つ者達に与えようとする大魔王 は一人たりともいなかった。 その扱いこそが、最大の褒美なのだ。打算や物欲に拠らず、ただ 大魔王とダークエルフの紐帯がある。臣従の仕方が、他の種族のそ れとは全く異なっているからこそ、ダークエルフはその地位を得た のだ。そうでなければ人界から河を超えてやって来た外様の種族が、 これほどまでに深く大魔王の信頼を得ることは出来ない。 ﹁余もそう思っていた。ダークエルフの忠義には何も報いる必要は ない。何も下賜しないことこそが最大の報酬であると﹂ ﹁仰る通りです。そのようにしてダークエルフは大魔王家の慈悲を 頂いてきたと聞いております﹂ ﹁⋮⋮余は、それをこそ改めたいのだ﹂ 少し温くなった茶に手を伸ばしながら絞り出すようにドラクゥは 199 呟いた。 † † † ダークエルフが報酬を拒む理由。その真実は、無償の忠義を捧げ るためではなかった。 二〇〇〇年の昔、ダークエルフの祖先が主である大魔王を殺した 報いなのだ。 それを改める。ドラクゥの決意は固く、ついにはダークエルフを 長く縛り付けて来た古の戒めは解かれた。 そして即位の日。ヒラノの力を借りた強大な雷の魔法によって開 会が彩られ、ドラクゥは大魔王へと即位する。 一方、神界ではヒラノが<知恵者の神>ガーフィンケルの訪問を 受けていた。 神界でも古く力のある神であるガーフィンケルの口から、技術開 発と信仰に関する秘密を聞かされるヒラノ。しかしその時、ヒラノ の身体は再び力を失い、気を失ってしまうのだった⋮⋮ 200 第四章ダイジェスト版 目が覚めると、俺はベッドで横になっていた。 柔らかなパステルカラーの色調で統一された部屋はどうやら病室 らしい。ぼんやりと見上げる天上では、カモメに似た鳥の形の照明 がゆっくりと円弧を描くように飛んでいる。 どうやら、また倒れたようだ。 思い返す限りでは、一回目の時とは比べ物にならない虚脱感だっ た。目の前でぶっ倒れられて、あのガーフィンケルという老人もさ ぞかし驚いたことだろう。何だか話していて腹の立つ奴だったから、 ちょっと驚かせることが出来たならまぁ良しとしたい。 今は大分と快復しているのか、身体に疲れは残っていないようだ。 試しに伸びをしようとした所で、腕に何か重さを感じる。固定でも されているのかと見てみると、慶永さんがだらしない顔で眠ってい た。 ﹁起こしてやりなさんなよ、アンタを心配してずっと付き添ってた ンじゃから﹂ 声を掛けて来たのは、藪先生だ。パイプ丸椅子に腰かけてワンカ ップの酒を呷っている。こちらにまで酒臭さが漂ってきそうなほど、 顔が赤い。 ﹁藪先生、診に来て下さったんですか﹂ ﹁お嬢の頼みじゃ断れンだろう。本当は往診なンかしておらンのだ が⋮⋮﹂ 言うなり、先生はこっちにカルテを投げて寄越してきた。 ﹁ドイツ語で書いてあるが、神様セットの有難い恩恵で読めるじゃ ろ。自分の症状くらいは把握しておいた方が良いぞ﹂ ﹁あ、ありがとうございます﹂ 確かに読める。患者の氏名や身長体重なんかの下に、たった一言 “急性貧徳”と書いてあった。 201 カルマ ﹁⋮⋮なんです、この“貧徳”って? 貧血の親戚ですか?﹂ ﹁阿呆。徳不足じゃよ、徳不足﹂ ﹁え、でも俺、徳はそれなりに持ってますよ?﹂ そう言って財布の中を確認すると、確かにちょっと減っている。 ﹁所持している徳ではなく、神としての身体を形作っている徳から ごっそり抜けおちたンじゃろ。それによって眩暈や虚脱感、倦怠感 などの諸症状が引き起こされる﹂ ﹁はぁ、なるほど。で、原因は何なんですか?﹂ 聞いている限りでは、貧血のような症状だし、ありふれた病気の ような気がする。であれば原因もすぐに分かるに違いない。病室に いない所を見るとガーフィンケルは帰ったようだが、まだまだしな ければならないことはいっぱいある。こんな所で寝ている暇などこ れっぽっちもないのだ。 しかし、藪先生の返答は思いもよらないものだった。 ﹁分からン﹂ ﹁え? 分からん、って。でも、病名は分かっているんですよね?﹂ ﹁病名は分かっているが、原因は分からン。邪神に多くある病気だ ということは分かっているが、普通の神様で罹ってる奴は見たこと がないな。どちらかと言えば病名というより症候群というべきもン じゃな﹂ ﹁そんな無責任な﹂ カルマ ﹁無責任と言われようが、そもそも症例が少ない上に、相手が邪神 じゃろ? 徳の回復手段がほとんどないもンで、病気が快方に向か カルマ わなければさっさとアガリを選ンで次の世界に転生するなり、天国 に行くなりするからな﹂ そう言えば、邪神は信者からの徳が得られない。これは邪神だか らというよりも、信者である魔族や魔物の方に理由があるらしいの だが、詳しいことは分からない。ともかく、回復手段がないならさ っさと次の転生を選ぶというのは確かに合理的な判断だという気が する。 202 ﹁でも、治った邪神もいるんでしょう?﹂ ﹁さて、儂は寡聞にして聞いたことが無いな。とは言え、神界は広 いし歴史もある。過去にはそう言うことがあったかもしれンな。自 然治癒に任せて見るというのも一つの手じゃろう﹂ ﹁自然治癒以外の方法としては?﹂ 先生は無造作に往診鞄の中に手を突っ込むと、遮光の為に褐色硝 子を使った小さな小瓶を取り出した。貼ってあるラベルの文字は遠 くて読めないが、何だか禍々しい感じのする小瓶だ。 ﹁さっさと死ぬことだ。今ここで黙ってアガリを迎えて次の神生を 愉しむのも、それほど悪い選択肢じゃなかろうよ﹂ ﹁それは困ります!﹂ まだ眠ったままの慶永さんの手を握り、気が付けば俺は思わず大 きな声を出していた。 ﹁この世界で、まだまだやらないといけないことがある。そう簡単 にほいほい転生をするほど、俺は安い男じゃないつもりです﹂ ﹁気炎を吐くのは大変結構じゃが、そうなると色々と大変だ﹂ ﹁どう大変なんです?﹂ ﹁食い扶持を稼ぎ続けにゃならンということじゃよ。次に発作が起 こった時、今と同じ程度の貧徳で済むのか、それとももっともっと 徳が失われるのか。その予測はさっぱりつかン。その度にお前さン は徳を補充しなければならン。お嬢がさっきまでしてくれていたよ うに、な﹂ そうか。今身体が軽いのは、慶永さんが徳を分けてくれていたか らだったということなのか。 ﹁⋮⋮このまま、発作が起こらないという可能性は?﹂ ﹁最初に病院に担ぎ込まれた一回だけで終わっていれば、その可能 性もあったじゃろうな。だが、二回目がこれだけ短時間の間しか置 かずに起こったことを考えれば、当然三度目も覚悟しておくべきな ンじゃないかね?﹂ 先生の言う通りだ。ここで何の根拠もなく発作が起こらないこと 203 を信じるよりも、次の発作が起こることを前提として動くべきだ。 徳の補充と、原因の究明。そして、治療法を探さなければならない。 これらを全て、急いで行わなければならないのだ。 ﹁分かりました。原因の究明と治療法の調査を、手伝って頂けます か?﹂ ﹁それは構わンが⋮⋮ お前さンはその前にしなけりゃならンこと があるじゃろう?﹂ ﹁何ですか?﹂ ﹁⋮⋮大会議じゃよ。お前さンの眠っている三日の間に、喚問の決 議が通った。明日はいよいよ大会議じゃ﹂ 大会議場について一言で説明すると、青空の下に鎮座する巨大な 擂り鉢ということになる。 世界の管理区画を兼ねる方舟の甲板にぽっかりと空いた擂り鉢状 の空間。巨大な金魚鉢の口を開いて形を整えたような透明な傾斜に、 広さ四畳半ほどの議席が星の数ほど浮遊している。そこに天神、地 祇、それに邪神たちがそれぞれ着席していた。 会則によればここに参加できるのは従五位以上の神々に限られる はずだが、それでも数は多い。見渡す限り神神神と、まるで神様の バーゲンセールだ。議席は擂り鉢の斜面に沿うようにゆっくりと周 回していて、まるで太陽を中心に回る無数の天体のような軌道を描 いている。 ﹁⋮⋮しかしマスター、本当にこんなことして大丈夫なのかね?﹂ 証人喚問はまだ始まっていない。 では何故、喚問されるべき証人である俺が大会議場に侵入できて いるかと言えば、それは慶永さんの議席に潜り込んでいるからだっ た。 慶永さんの神階は従四位下。当然この場にいて何の不思議もない。 ﹁大丈夫ですよ。大会議の会則にも“属神と主神は同じ議席に就く ことが出来る”という規定がありますから。この条項のどこにも、 主神が属神の議席を使ってはいけないという文言は無い﹂ 204 ﹁それって、詭弁なんじゃない?﹂ ﹁過去に問題になったことがあれば補足や訂正の条項があってもお かしくないはずですが、この部分については何もありませんでした。 思い付いたのは俺たちが初めてか、前にやった連中は気付かれもし てないってことです﹂ そもそも、こんなことをする神様自体がほとんどいないんだろう という気はする。従五位以上の神であれば誰にでも分け隔てなく参 加権のある会議だ。よくよく目を凝らしてみれば、議席には空いて いる席も目立つ。 会則によれば用意される議席の数は参加資格のある神の数に応じ て変化することになっているので、空いている席は単純に欠席して いるだけだ。大会議で話し合われる内容が多岐にわたることは議事 録を読んだから知っているが、確かに何を置いても参加すべしとい うような内容でもない。 まして、従五位にもならない駆け出しの神々にとっては、世界の 運行や神々の弾劾に関わるような会議は、それこそ無縁というもの だろう。 それでもこの大会議が重視されているのは、ここが高位の神々に とって大切な政治的駆け引きの場だからに他ならない。 今回の証人喚問も本当の所、俺たちはおまけでオイレンシュピー ゲルと引き合わせたマルクントの方が本命に違いない。あれだけ徳 を貯め込んでいるのだ。敵も少なくはないはずだ。 擂り鉢の底に一際大きな十畳ほどの議長席が浮かび上がってきた。 それを取り巻くように、大会議の重鎮たちの議席も浮かんでくる。 その中の一つに、俺は見知った顔を見出した。ガーフィンケルだ。 以前会った時と同じく、腹が立つほど仕立ての良いスーツを見事に 着こなし、白髪を撫でつけた老人がそこに座っている。 議長席に座っているのは細身のガーフィンケルとは対照的に肉付 きの良い中年の神で、頭にイギリス貴族風のかつらを身に付けてい る。そういう時代から転生して来たのだろうか、全体的ないでたち 205 もシックに纏まっていて、気品が溢れている。 ﹁それではこれより、臨時大会議を開始する﹂ 議長の宣言に、集まった神々は拍手で応えた。今日の大会議は臨 時、つまりは証人喚問とそれに関連する議題の為だけに召集された 会議だ。ここに集まっているのは皆、会議が好きな連中か、何かし らの利害関係があるということなのだろう。 ﹁早速ではあるが、証人として少初位上、邪神ヒラノを証人として ⋮⋮﹂ ﹁少々お待ちください!﹂ 議長の言葉を遮ったのは、俺の横に立つ慶永さんだ。俺が渡した カンペには見向きもせず、真っ直ぐに議長を見つめている。 ﹁⋮⋮<戦女神>ヨシナガか。当大会議場で見かけるのは随分久し ぶりだと思ったが。何か発言しなければならないことがあるのかね﹂ ﹁はい。大会議会則第三〇一条二項に基づき、当大会議にオブザー バーを招聘したいと考えます。条項の発動に必要な五柱の神々の署 名は、既に事務局に提出しております﹂ 大会議の会則には、従五位上以上の神階の神々五柱の推薦があれ ば、特別にこの場にオブザーバーを招くことを許すということが記 載されている。 ﹁⋮⋮確かに事務局は受理しているな。認めよう。それでそのオブ ザーバーとは﹂ ﹁はい、私の主神、邪神ヒラノです﹂ 慶永さんに名前を呼ばれると同時に俺は立ち上がった。 おぉ、というどよめきが大会議場に満ちる。無理もない。従五位 未満の神で証人喚問される当の本人が、オブザーバーとして大会議 に参加するなど前代未聞の事だろう。俺が目覚めてからたったの一 日で五柱の信頼できる賛同者を集めてくれた慶永さんの人気に感謝 するしかない。 ﹁分かった。では、邪神ヒラノが今回の大会議のオブザーバーとし て参加することを会則第三〇一条二項に基づいて許可する﹂ 206 従五位未満の神、つまり俺の場合は大会議での発言権が認められ ない。証人喚問に証人として呼び出されると、質問に答える形でし か発言が認められないのだ。そうなるとサンドバッグと一緒で、い いように殴られるということになる。 ただ、オブザーバーとなれば話は違う。この枠で会議に参加した 者は、議決権こそないものの発言権は従五位以上の神々と同等に扱 われる。何か反撃しようと思えば、この最低でもオブザーバーにな っておく必要があったのだ。 ﹁証人本人がオブザーバーというのも極めて異例のことではあるな。 しかし、会則は会則だ。邪神ヒラノには会則に基づいて、従五位以 上の神々と同じく大会議での発言権が賦与される。この権利に基づ いて当大会議内においてなされた発言について、邪神ヒラノは会議 城外でその責任について問われることはない。その点について問題 はないか?﹂ ﹁はい、ございません﹂ その点は予習済みだ。発言の権利はオブザーバーであっても保障 されている。ここでの俺の動きが、これから先の“聖堂”との戦い で大きな意味を持ってくることは間違いない。 一瞬、ガーフィンケルと視線が合った。あの老人は、苦虫を噛み 潰したような顔でこちらを見上げている。あの日、俺にもっと釘を 刺しておくつもりだったのだろう。 技術は、解放する。せめて、禁止技術以外の伝授については解禁 させなければならない。 それが俺の、勝利条件だ。 ﹁さて、それでは早速、少初位上、邪神ヒラノを証人として⋮⋮﹂ ﹁⋮⋮少々お待ち頂けますか?﹂ 再び議長の進行を遮ったのは、どこかで聞いたことのある声だっ た。 凛として、力強い声。 その声の持ち主は擂り鉢の底、大会議場の入り口から静かに歩い 207 て入って来た。 桜色の袴。身の丈以上の方天画戟。そして、長い黒髪。 ﹁<黒髪姫>⋮⋮﹂ ドラクゥの宿敵、<北の覇王>ザーディシュを担当する女邪神は、 まるで煉獄のそこから神々を睥睨するかのように冷たい瞳で大会議 場を舐め回す。それは背筋の凍りつくような威圧感を持った視線だ った。 † † † カルマ 大会議に突如現れた<黒髪姫>は、顕現して夜魔族の軍勢を一蹴 したという違反行為を自ら報告する。 そして、その罪を購うだけの莫大な額の徳を罰金としてその場で 払って見せるのだった。 一方、魔界ではドラクゥから東征軍を任された妖鳥属のフィルモ ウがリザードマン領との境界へと軍を進める。対する亀族の魔王キ リックの背後では、神界を裏切ったオイレンシュピーゲルの影が見 え隠れしていた⋮⋮ 208 第五章ダイジェスト版 始まった、ということが気配で分かる。 キリックの切り札である“戦車”七〇輌が、フィルモウの先鋒を 塞ぐ格好でぶつかったのだ。不整地でも走り抜けられるように車輪 に細工を施した俥は一輌で二十五の兵を運ぶことができた。鈍重だ が打たれ強い亀族の戦士がこれで一気に一七五〇、前線に現われる ことになるのだ。 特別にあつらえた“戦車”に乗って、キリックは前線にまで押し 出していた。 屋根に蓋が付いていて、そこから戦場の様子を覗くことができる ような工夫がしてある。霧は晴れかかっていたが、もう問題はない。 “戦車”は既に前線に到達しているのだ。 矢が放たれ始めた。キリックの戦術では、こうなってしまうとも う一方的になる。相手の矢は、こちらに当たらないからだ。 兵を運んだ“戦車”は壁として使うことができる。銅板を貼り付 けた側面には細い溝のような窓が刻んであり、その狭間から矢を射 るのだ。敵に腹を見せる形で“戦車”を並べれば、それは簡易の砦 のようになって敵の進撃を食い止めることになる。 泥濘の多いこの湿地帯で行軍の頭を止められれば、指揮官は混乱 せざるをえない。特に、目の前のフィルモウの隊は酷い慌てぶりだ。 戦う者と空に逃げる者、後ろに退こうとする者が入り乱れている。 そこに“戦車”から容赦なく矢が射掛けられるのだ。 ﹁⋮⋮あの鳥、さては逃げようとしていたな﹂ 分進合撃をする場合、指揮官は各個撃破を最も恐れる。フィルモ ウもそれを恐れていたのだろう。目の前で“戦車”と対峙する敵は、 ほとんどが妖鳥族で編成されている。いざとなれば空を飛んで逃げ るつもりで予め指示を出していたに違いない。 ﹁敵は随分と腰の定まらない戦いをしているようだね﹂ 209 そんなことを考えていると、キリックの傍らから“声”が聞こえ た。 傲岸不遜で知られるキリックが、慌てて“声”の方に膝を折る。 ﹁これはオイレンシュピーゲル様、わざわざ戦場までようこそお越 し下さいました﹂ ﹁面白い戦が見られるかと思ったが⋮⋮これは少し残念だな。あま りにも一方的過ぎる﹂ ﹁勝ち戦とはそういうものにございます﹂ キリックに“声”が聞こえるようになったのは、随分昔のことだ。 最初は信じるつもりもなかったが、“声”のお告げはことごとく有 用で、値打ちのあるものだった。まだ魔王ですらなかったキリック が多くの武勲を上げられたのも、お告げの声に助けられてのことだ。 “声”の主は、時々変わった。主が名乗ったわけではない。だが、 声の調子や癖、話す内容が別人のように変わるのだ。リザードマン の行政官のように、任期があるのだろうとキリックは思っていたが、 当たらずとも遠からじといったところだろう。 オイレンシュピーゲルと名乗る“声”の主がやって来たのは、つ い最近のことだ。 初めて自分から名を名乗った“声”の主だったが、その他のこと についても異例尽くしだった。 ﹁この勝利も、オイレンシュピーゲル様のお陰です﹂ ﹁いや、君たち亀族の強い魂のなせる業だよ。まさかこれほど短期 間にゴムを実用化するとはボクも思っていなかった﹂ ゴムというのは、オイレンシュピーゲルのもたらした奇蹟の一つ だ。“戦車”の車輪が黒いのは、全てこのゴムを使っているからだ った。キリ・シュシュツの近くで産する樹木の皮に傷を付けるとそ こから粘性の高い樹液が採れる。それを加工し、成形して空気を入 れることで不整地でも問題なく走ることの出来る車輪を作ることが 出来るのだ。 ﹁俥を使った戦術は亀族も昔から持っておりましたが、不整地では 210 動きが遅いことが悩みでした。オイレンシュピーゲル様があのよう な知恵を授けて下さったから、こうやってお申し付けにも従うこと ができます﹂ ﹁別に申し付けたわけではない。そうなれば良いと思っただけだ﹂ ドラクゥに兵を貸さないという方針はもちろんキリックの本心で ある。だが、同時にオイレンシュピーゲルの願いでもあった。理由 は分からないが、大魔王ドラクゥが力を付けることをこの“声”の 主は快く思っていないようなのだ。 “戦車”の外では妖鳥族がゆっくりと退き始め、やがてそれは潰走 に変わった。 ここに来て初めて、キリックは脇の小路に伏せた部隊に奇襲の命 を下す。戦果が稼げるのは、追討戦だけだ。真面目に向き合ってい る間に相手を削ろうとすれば、双方の被害が大きくなり過ぎる。 ﹁おめでとう、キリック。少し拍子抜けするが、あっさり勝てたよ うだな﹂ ﹁まだ三分の一です。北と南にまだ敵がいる﹂ ﹁だが、混乱は感染するものだろう?﹂ オイレンシュピーゲルの声音は、明らかに愉しんでいる者のそれ だった。戦争を誰よりもこよなく愛することを自負するキリックで さえ持ち合わせていない、狂気の響きがそこには籠っている。 ﹁⋮⋮それでオイレンシュピーゲル様、例の件は考えて頂けました でしょうか﹂ ﹁例の件? 何の事だったかな﹂ ﹁輪廻の、その、私の輪廻の件についてです﹂ リザードマンは、輪廻する。キリックだけでなく、それはほぼ全 てのリザードマンに共通する信仰だ。これまでキリックは亀族の魔 王として様々な“声”の主の要望を叶えてきた。時にそれは亀族や キリック自身の利益に反することもあったが、それでも頑なに言い つけは守り続けてきたのは、“声”の主が輪廻転生に手心を加える ことが出来ると信じたからこそだ。 211 ﹁ああ、輪廻の件か。当然だよ、キリック。君は次の転生で⋮⋮竜 になれる﹂ ﹁ほ、本当ですか!﹂ ﹁当たり前だ。ボクが君に嘘をついて一体何になるというんだい?﹂ ﹁ありがとうございます、ありがとうございます!﹂ 喜びの声に、喘息に似た音が混じる。永く生き過ぎたキリックの 身体は、既に限界を迎えつつあった。だが、次の転生で竜になれる。 その確証は、キリックの心を軽くした。 ﹁オイレンシュピーゲル様、このキリック、もう何も怖くありませ ん﹂ ﹁それは良かった。ならば是非、ドラクゥの軍を追い払ってくれ。 この沼地をリザードマンの聖地として守り抜くことこそが、君の今 生の役割なのだから﹂ ﹁はい、お任せ下さい!﹂ 伝令に“戦車”の後退を伝える。壊乱した敵の掃討は、亀族では ない他のリザードマンの奴隷兵に任せておけばいい。主力を一度キ リ・シュシュツに退き、もう一度同じ攻撃を南の隊にも仕掛けるの だ。 部下に指示を出しながら、キリックは“戦車”の中の気配を探る。 現れた時と同じように、オイレンシュピーゲルは音も立てずにこ こから去ったようだった。 支え切れなくなったのは、決して妖鳥族が弱いからではない。 泥の中を這い回るようにして退きながら、フィルモウは恨めしげ に東を睨む。事前に将兵に伝えていた撤退の命令と、フィルモウの 抗戦の命令が混乱を引き起こしたのだ。何かあれば南北を進む味方 と合流しろという命令は、あの黒い車輪の俥が戦場に現れるまでは 有効だった。 212 亀族の歩みは鈍重だ。フィルモウ率いる妖鳥族が退いてしまえす れば、亀族の主力はここに取り残される。そのはずだった。南北に 分かれた一五〇〇ずつの二つの軍は、そのまま前進を続けて守りの 薄くなったキリ・シュシュツを挟撃できる。 だが、あの俥だ。 素早く兵を動かすことのできるあの俥があれば、亀族は南北の隊 にも同じ攻撃を仕掛けることが可能になる。伏兵とあの俥の組み合 わせは、亀族の地の利を何倍も高めているのだ。対策はあるのだろ うが、今打てる手はほとんどない。新しい戦術にぶつかった時は、 誰しもこうなってしまうものなのだろうか。 また、敵が矢を射かけてきた。二〇〇〇に近い本数の矢が空を埋 める。 亀族の矢は、最初から狙いを定めては放っていないようだ。射撃 に耐え切れなくなった妖鳥族の兵士が飛ぶと、それが当たって撃ち 落とされる。狙って当てるのではなく、面を埋めるように撃たれて しまうと、如何な妖鳥族といえど躱すのは難しい。 ﹁纏まるな! 西へ向かって走れ!﹂ 自分が間違っていたと、フィルモウは思わなかった。あそこで退 くことだけは、絶対にしてはならない。魔王として、責任ある立場 の者として、退いてはならない局面はある。ただ、今の状況はその 賭けに負けたというだけなのだ。 相手の裏を掻くのが戦争ならば、今回は<苔生した甲羅>のキリ ックに随分と上手く手玉に取られてしまったということになる。い や、勝手に自分だけで踊っていただけなのかもしれないとフィルモ ウは自嘲した。相手は、戦争を生活の一部とするリザードマンでは ないか。生半な気持ちで当たれば、敗れるのは当然の帰結だったの かもしれない。 目の前で、若い兵が死んだ。流れ矢に当たった。矢は、頭に突き 立っている。助からないことは、すぐに見て取れた。少し軌道が違 っていれば、死んでいたのはフィルモウだったはずだ。 213 まだ、生きねばならない。この戦況を、立て直す。それが、命じ た者の責任だ。 潰走に近い状態だが、それでも踏み止まる兵はいる。 高い機動力と空中戦で敵を翻弄する妖鳥族にとって防禦は一番の 不得手だが、それでも短槍を構え、退く味方を支援しようとしてい るのだ。 ﹁お前たちも、退けっ﹂ ﹁フィルモウ様はどうかお先に。後から参ります!﹂ そう言いながら部下を率いて逆方向に走って行ったのは、フィル モウが数合わせの為に従軍させていた軍官僚だった。普段は馬に食 べさせる秣の量を帳面に付けているような男だ。一万の兵を集め、 大魔王の威を示す為には、妖鳥族の軍人であれば根こそぎ全て連れ てくる必要があった。そんな男まで、フィルモウはこの戦で使い潰 さなくてはならない。 振り返ると、黒い車輪の俥がゆっくりと後退していくのが見える。 代わりに前に押し出してきたのは、リザードマンの奴隷兵だ。 飛んで移動することを考えて、弓も短弓しか装備させなかったこ とが裏目に出ていた。今の子の軍では、あの俥に貼ってある銅板を 撃ち抜いて中の射手を殺すことはできないことは、もう誰もが理解 している。 兵が、俥に突っ込むのがフィルモウにははっきりと見えた。 周りの俥や亀族から、矢が降り注ぐ。敵の注意がそちらに向いて いるだけ、敗残兵が逃げる距離が稼げるのだ。ほんの少しの時間、 フィルモウは全力で走った。再び矢が降り注ぎ始めれば、泥の中を 這いずり回らなければならない。自慢の美しい羽根は、見るも無残 に汚れていた。 葦の茂みに身を隠し、フィルモウは小さく息を整える。 旗本衆はいつの間にか散り散りになっていて、ほとんど残っては いない。完全なる潰走だった。もしここで亀族が引き返したとして も、その期を逃さずに逆撃に転じるだけの余裕はない。 214 亀族はどこまで追撃してくるつもりなのか。兵を退くどころか、 更に圧し込んでくる気配もある。 ロ・ドゥルガンの動きが気になるが、この様子だと一旦、西の丘 にまで引き返しているのかもしれない。フィルモウを犠牲にしてキ リ・シュシュツに肉薄するという手もあるが、万が一他のリザード マンが敵に回れば、占領したばかりの城市では守りきれない。 いずれにしても、この戦いは負けだ。 今は一刻も早く、そして一人でも多くの兵をあの丘まで引き揚げ させなければならない。 ただ、フィルモウには一つだけ気がかりなことがあった。 ﹁⋮⋮リザードマンが、あの丘を西に越えないと誰が決めた?﹂ 最悪の事態を考えると、頭がきりきりと痛む。 敵が丘を越えてジョナンの赤い森に侵入するようなことがあれば。 後は、クォンとかいうあのコボルト族の老軍監が少しでも気の回 る男であることに望みをつなぐしかない。中央の隊が敗走している ことは伝令で伝わっているはずだ。せめてアルナハに救援の要請を 出してくれていればいいのだが。そう思いながら、フィルモウはま た走り始めた。 西の丘は、もうすぐ近くに見えている。 † † † 死を恐れず、むしろ転生の為に積極的に死地へと臨むリザードマ ンの兵たちの前に、フィルモウの軍は次第に追い詰められていく。 その頃ヒラノは、気絶するほどの自身の体調不良の原因が、信者 による魔法の行使で徳が不足しているからだということに気付く。 だが、その事を伝える前にドラクゥに夜魔族が<黒髪姫>に撃退 されたことを伝えなければならない。意外なことに、その時救いの 手を差し伸べてくれたのはかつての敵、オクリ神だった。 215 第六章ダイジェスト版 馬蹄の響きと共に、西から暗雲が立ち込めていく。 今にも降り出しそうな空模様に、低く雷鳴が轟きはじめた。フィ ルモウが目を凝らすと、丘の稜線からゆっくりと旗印が姿を現す。 ﹁あれは⋮⋮大邪神旗? 莫迦な、邪神官長のエリィナ様が御出馬 されたということか!﹂ 戦場に翩翻と翻るのは稲妻を象った大邪神旗、邪神官長エリィナ の旗印だ。 <大魔王>ドラクゥの義妹エリィナは邪神ヒラノに仕える邪神官長 の職にある。本来であれば邪神殿から動くことすら稀な立場だ。そ れが増援を率いて戦場に赴くなど、前代未聞だ。 ﹁増援の数は⋮⋮おおよそ、五〇〇! 内、一〇〇は騎乗の邪神官 です!﹂ ﹁有難い、無論のこと有難いのだが、たったの五〇〇では⋮⋮﹂ 遅かった。全てが遅かったのだ。 フィルモウは歯噛みし、自分の太腿を叩いた。エリィナの到着が もう少し早ければ。あるいは、フィルモウ麾下の部隊がもう少し持 ち堪えていたならば。 翻る大邪神旗と大魔王ドラクゥの義妹であるエリィナの着陣は味 方の士気を大いに高め、一気に盛り返す機会があったかもしれない。 しかし全ては遅きに失したのだ。今更五〇〇の兵、それも非戦闘 員を一〇〇も含んだ増援が駆け付けたところで、一体何の助けにな るというのか。 感謝と恨みがましさの綯い交ぜになった表情で増援を見つめるフ ィルモウの前を、エリィナが颯爽と駆け抜ける。その瞬間、フィル モウにエリィナが向けた表情は、一点の悲愴さにも侵されていない、 可憐で凛々しい微笑だった。 陣の中央に陣取ったエリィナは鞍上のまま、部下の邪神官たちに 216 号令をかける。 ﹁邪神官隊、戦闘詠唱開始!﹂ ﹁邪神官隊、戦闘詠唱開始!﹂ まじな 部下が復唱し、邪神に捧げる祝詞が読み上げられはじめた。力あ る言葉、今では魔族で使う者もない古い古い呪いの言の葉で編まれ た、邪神ヒラノを讃える祝詞だ。 古歌にも一家言あるフィルモウには分かるが、恐ろしく精密に押 韻と韻律に気を配った、当代稀に見る出来の祝詞だった。 ﹁あれをまさか、エリィナ様ご自身が?﹂ 疑念を呟くフィルモウの眼前で、“奇蹟”が発動し始める。西か らエリィナが増援と共に率いてきた雷雲はリザードマンの直上に移 動し、更にその雲底が低くなった。見れば、雹混じりの激しい大粒 マナ の雨が敵陣に降り注ぎ始めている。 詠唱によって魔那がエリィナの指先に凝集し、眩い光を放ち始め た。 ﹁大いなる邪神ヒラノよ、今こそ我に力を貸し与えたまえ、<雷撃 >!﹂ エリィナの喊声と共に指先の光芒が迸り、雷雲に吸い込まれる。 辺りが昼のように明るくなり、次いで耳を劈く轟音がフィルモウの 身体を直撃した。 魔法だ。今では使う者さえ少なくなった、太古の叡智。魔族が魔 族である証左。 奇蹟の顕現である激しい雷が、幾条もの閃光となってリザードマ ン達の陣に殺到している。 ﹁な、何だこれは⋮⋮﹂ ﹁魔法です。邪神ヒラノ様の御力を借りた﹂ エリィナに続いて部下の邪神官たちの雷も敵陣に撃ち込まれ始め た。 それまでこちらの陣に向かって攻撃を続けていたリザードマンた ちは完全に混乱に陥り、逃げ惑っている。算を乱して逃げ惑う姿は、 217 とてもさっきまで対峙していたリザードマンと同じ者たちだとは思 えない。 混乱が混乱を呼び、敵が潰走を始めるまでにそれほど長い時間は かからなかった。 ﹁凄まじい威力だな⋮⋮﹂ 思わず呟くフィルモウにエリィナがそっと微笑みかける。 ﹁強い力です。それだけに、使い方を誤らないようにしないと﹂ ﹁救援、ありがとうございます、エリィナ様﹂ ﹁お味方を見殺しにはできません。いざという時は、邪神官を率い て救援に向かうべきだというのが、北へ向かう主上のご命令でした﹂ ドラクゥは、この事を読んでいた。いや、ここまでの損害を蒙る ことまで予見できていたかは分からないが、少なくとも危機に備え ていた。その事がフィルモウを恐縮させる。 ﹁しかしこれだけの力だ。救援を頂いてこのようなことを尋ねるの も妙だが、北での戦い⋮⋮ああ、つまりパザンの接収などではなく、 <北の覇王>との対峙に役立てた方が良かったのでは?﹂ ﹁一時的にはそうかもしれません。ただ、主上はそれを望まれませ んでした﹂ ﹁何故です? ザーディシュは、強い。全ての力を結集して事に当 たるべきでは?﹂ フィルモウの知る限り、大魔王府を掌握する<北の覇王>ザーデ ィシュの動員力は二十四万に達する。アルナハの総兵力が二万であ ることを考えれば、比べることさえ莫迦莫迦しい差だ。 ドラクゥの即位で多少の離反はあったにせよ、それでも二〇万を 急に割り込むとも考えにくかった。ドラクゥが大魔王の正統な光景 を名乗るのと同じように、ザーディシュが庇護する皇太子レニスも また、継承権を主張し続けているからだ。 ﹁仮に魔法の力で敵を屈服させてしまえば、その後もずっと魔法を 使って政敵や民を圧し続けなければならないからです。それは、王 道ではないと主上は仰いました﹂ 218 ﹁王道⋮⋮﹂ ﹁はい、主上は王道をもって魔界を新たに統治されるおつもりなの です﹂ 血だ。 そう思った時には、口から零れ落ちた物は俺の掌を赤く染めてい た。 ドラクゥのいるパザン接収軍に送ってもらう途中だ。掌で受けき れなかった血が、オクリ神の白い背中を少し赤に染めた。 身体が冷たい。断続的に身体の芯から熱が奪われていくのが分か る。 耐えられないほどの頭痛と悪寒、それに虚脱感に襲われ、俺はそ のまま柔らかな毛皮の上に倒れ込んだ。 ﹁ちょっと、マスター! 大丈夫?!﹂ ﹁エリィナたちが魔法を使ったみたいです。それも特にでっかい奴﹂ 慌てた慶永さんが俺の背中を擦るが、ここはオクリ神の上だ。他 にできる看病もない。 前回、前々回は分からなかったが、今回はこうなることが分かっ ていたからか、誰がどのあたりで魔法を使ったのかが漠然と分かる。 ﹁どうする若人、大魔王のところではなく、その魔法を使った者の 所に行くか?﹂ ﹁⋮⋮いえ、オクリ様、このままでお願いします﹂ ﹁マスター!﹂ 慶永さんの悲痛な声に胸が痛む。 確かに、これ以上使われると意識を保っていられるかどうかも怪 しい。それくらい、今回の虚脱感は凄まじい。前回と同じか、もっ と強力な魔法を使ったんだろう。 旅人の神だけあって風を切って進むオクリ神は本当に速い。 219 あっという間にあの長い長い大空洞を通り抜け、神界に到達した。 ここはいま夜らしく、喀血の時に出た涙で煌びやかな夜景が滲んで 見える。 ﹁自慢ではないが、儂は旅人の神だ。脚は速いぞ。一度医者に診て 貰ってからでも、十分遅れは取り返せるのではないか?﹂ ﹁いえ、このままで﹂ 額に浮かぶ脂汗を慶永さんが黙って拭ってくれた。 それに微笑み返すだけの空元気さえ、今は湧いてこない。温かい 狼の背中に倒れ込んだまま、俺は回らない頭で考える。 エリィナが魔法を使ったのはアルナハの東だ。つまり敵は<北の 覇王>ザーディシュではない。 雷撃の魔法をどういう局面で使用したのかはっきりとは分からな いが、これだけ強力に、かつ連続して使ったなら、戦局は一旦安定 するはずだ。 ここで相手がザーディシュなら、あるいは<黒髪姫>のような規 格外の相手になら、エリィナたちもさらに連続して魔法を使おうと するかもしれないが、今の所そうする気配もない。 だったら今は、ドラクゥの所へ向かうべきだ。 一刻も早く、ドラクゥたちを止めなければならない。 ﹁ねぇマスター、私ちょっと考えたんだけど⋮⋮﹂ ﹁駄目です﹂ ﹁⋮⋮私まだ、何も言ってない﹂ ﹁慶永さんの事だから、ドラクゥの所かエリィナの所、どちらか一 方に自分が要って時間を短縮したいって言うんでしょ?﹂ ﹁う、鋭い﹂ ﹁それは駄目です。慶永さんにメッセンジャーをさせることはでき ない﹂ それについては俺も考えたのだ。折角二人いるんだから、手分け をすれば時間は大幅に短縮できる。でもこの方法は、俺にとって絶 対に使うことのできないものだった。 220 ﹁何でよ、マスター。その方が速く済むじゃない!﹂ ﹁⋮⋮どちらに行くにしても。慶永さんが顕現しないといけないか らですよ﹂ ﹁え、なんで?﹂ ﹁だってドラクゥもエリィナも、慶永さんの声を聞いたことなんて ほとんどないでしょ﹂ ﹁あ、ああ、そういえばそうだわ⋮⋮﹂ 姿さえ現せばドラクゥやエリィナに俺からの使いだと信じさせる 方法はいくらでもあるだろう。 だが、今の状況で慶永さんを顕現させることはできない。 ﹁証人喚問は終わったわけじゃない。単なる猶予中です。ガーフィ ンケルの爺さんにも目を付けられている。そんな状況で顕現すると いう危険を冒すのは、俺だけで十分です﹂ ﹁何言ってるの! 私はマスターの、ヒラボンの属神で、だから一 蓮托生で⋮⋮﹂ ﹁属神なんですよね、だったら主神からの命令です。危ない橋は渡 らないでください﹂ ﹁ぐっ、でも⋮⋮﹂ ﹁呵々、これは<戦女神>の負けだな。属神は主神に従うべきだ﹂ それまで傍観を決め込んでいたオクリ神からも助け舟が入り、慶 永さんは諦めたようだ。 俺の方をを恨めしそうに睨む目が、少し怖い。 慶永さんは気付いていないみたいだけど、工夫をすれば声だけで も俺の使者だと認識させる方法はいくらでもある。俺しか知らない はずのことを伝えたり、奇蹟との組み合わせで信憑性を高めたりす る方法だってあるはずだ。 でも俺は、それをさせたくなかった。 魔界の空は、寒い。身体を撫でる風は、身を切るような冷たさだ。 ひょっとすると俺は、さっきから続く身体の辛さに少し参ってしま っているのかもしれない。 221 慶永さんに、傍にいて欲しい。このまま消えて行ってしまうかも しれない時に、慶永さんだけがどこかに行ってしまうことに、耐え られないほどの寂しさを感じてしまったのだ。 ﹁マスター、死んじゃ駄目だよ﹂ 俺に徳を送り込みながら、慶永さんが力なく微笑む。 気のせいかもしれないが、その目じりにはうっすらと涙が溜まっ ている、ような気がする。 駄目だ、もう、力が入らない。 瞼がどんどん重くなり、開けていられなくなる。 ﹁ごめん、慶永さん。少し、寝る。着いたら⋮⋮起こ⋮⋮し、て﹂ 一万の軍の動きとしては、少し速過ぎるとドラクゥは思った。 予定していたよりも、随分先に軍を進めている。 将帥としてのドラクゥは一〇万を超える軍も五〇〇〇を下回る軍 も率いたことがあるが、その間である万単位の規模を指揮した経験 がない。 可能な限り速やかにパザンを接収するように命じたのはドラクゥ だ。しかし、これほどの速さで軍が移動できるというのは考えても みなかった。 シュリシアが行軍の奉行を務めている。戦闘の指揮とは一切関わ りなく、糧秣や武具の輸送、進む道の選定などを担当する役職だ。 輸卒の隊長を束ねる程度の職位だと思って設置を許可したが、思 わぬ効果が出ているということになる。これほどの速さで動いてい るのに、今のところ水も食料も不足している様子はない。 ﹁予定しているよりも、随分と速く進んでいるようだな﹂ ﹁輸卒を切り離しておりますから。戦闘に関わる部隊だけであれば、 この程度の速さで行軍することは可能でしょう﹂ リザードマンの奴隷階級から拾い上げた官僚であるシュリシアは 222 ドラクゥの問いに少し得意げに応えた。少し鼻に掛けるところはあ るが、時折目を見張るような工夫をすることがある。 ﹁輸卒を切り離して、水や糧秣はどうやって確保している?﹂ ﹁ご心配には及びません。途中の村々にございます﹂ ﹁よもや、掠奪をしているわけではあるまいな﹂ ドラクゥは掠奪を嫌う。そのことは既に南方の全域に広まってい た。豪族の一部が大魔王陣営に加わったのも、掠奪を含めた無法を 軍が働かない姿勢に靡いたからだ。 軍によって奪い尽くされた土地では流民が発生し、その先数年に わたって収入が回復しない。それだけに、掠奪をする軍に対する民 や豪族の憎しみは大きかった。 ﹁今回の侵攻は主上の即位式後に行われることが分かっておりまし たので、行軍が予定される道程に必要な分の糧食を先に運び込んで おきました﹂ ﹁その糧食はどこから調達した?﹂ ﹁先に派遣されているダッダ殿と協力して、パザンで買い付けまし た﹂ パザンの接収がどのように進むかは、ドラクゥにとっても未知数 だ。 直前の支配者であったシェイプシフターにとってパザンは故地で はなく、その前の城市の主であった人熊族の多くは森に落ち延びて いる。 頑強な抵抗に遭う可能性もあれば、ドラクゥ率いる接収軍をあっ さりと解放者として受け入れる可能性もあった。 場合によっては、包囲しての攻城戦も覚悟しなければならない、 とドラクゥは考えている。 だが、パザンにあまり時間を掛けることはできなかった。 北へ向けての今回の遠征の本来の趣旨は<北の覇王>ザーディシ ュに対しての示威であり、遠交近攻の策によって同盟を結んだ夜魔 族に対する側面支援の意味もある。 223 パザンを如何に素早く陥落させるか。 それが目下最大の懸案である状況で、籠城を長引かせる最大の要 素である敵の備蓄食料を、買い付けによって大幅に奪うことができ たのは大きな意味があった。 ﹁巧妙だな、シュリシア。しかし飢えた敵は死に物狂いで抵抗する のではないか?﹂ ﹁それについては、パザンにほど近い丘陵に買い付けた備蓄食料の 余剰分を密かに保管しております。畏れながら、主上の寛大な御心 をパザンの民に示される際にお使い頂ければよろしいかと﹂ ﹁なるほど、そちらも手を打ってあるということか﹂ 兵糧攻めにした上で、食糧を配って民の歓心を得る。 やり口が少々賢しいとドラクゥは思ったが、背に腹は代えられな い。 今回の遠征の真の敵が、あの<北の覇王>ザーディシュである以 上、ドラクゥの思いもよらない手段でこちらの手を潰しにかかる可 能性は十二分にあった。 ザーディシュの軍に対抗することのできる切り札は、リザードマ ンとの交渉が難航した時の為にアルナハに拘置してある。エリィナ の邪神官隊だ。あれを北で使うつもりは、今のドラクゥにはなかっ た。 ﹁シュリシア、リザードマンは余に兵を供すると思うか?﹂ ﹁まず無理でしょう。家守族辺りが恭順しても、大沼沢の出入り口 はキリ・シュシュツです。あの執念深い<苔生した甲羅>のキリッ クに心境の変化でもない限りは、リザードマンの兵は氏族単位で西 へ出ることができません﹂ ﹁西へは、な。では東へはどうだ﹂ ドラクゥの問いにシュリシアは怪訝な表情を浮かべる。表情の読 みにくいリザードマンだが、最近漸く、どういう表情かなのかがド ラクゥにも理解できるようになってきた。 ﹁東、ということは<東の冥王>の領域への侵攻も考えておられる 224 ということですか?﹂ ﹁可能性としては考え得る。大沼沢と内海に阻まれて陸路であの地 域に攻め込むことはできないが、リザードマンの一部か全部を仲間 に引き入れることができれば、あの地にも兵を送ることは可能にな る﹂ ﹁しかし、何もありません﹂ <東の冥王>の領地には、何もない。 そこにはただ広漠とした荒野が広がっているだけだ。その中央に は初代大魔王の眠る巨大な墳墓があり、代々の<東の冥王>がその 墓守を務めている。 ﹁何もないというのは、為政者の考え方だ。確かにあの地には目に 見える利益は無い。だが、そこに民はいる。そこにも、新しい魔界 というものを広めていきたいのだ﹂ ﹁そういうことでしたか﹂ ザーディシュは、強い。 あの老獪で精強な男に勝つためには、ドラクゥは持っているもの だけを振り絞っても勝てる見込みは全くない。持っていないもの、 これまで誰も手を付けようとしなかったものにも、手を付けなけれ ばならなくなるだろう。 いずれにせよ、パザンとその後のことが済んでの話だ。 パザンを取り囲むように配置されている支城の一つが、微かに聳 えているのが見えた。 ひだのかみ つまらないことになった、と飛騨守は口の中だけで呟いた。 大森林を貫く街道には人の気配が全くない。約束ではこの辺りに まで運べばいいということだったが、背中の上で気絶したように突 っ伏す若造と、その隣で眠りこけるその属神とを放り出せるほどに 飛騨守は無責任ではなかった。 225 送ると決めた相手は、必ず目的地に送り届ける。その義理堅さが、 飛騨守という名の他に“オクリの神”などという別名を頂いた理由 だった。 地面に降り立ち、匂いを嗅ぐ。 踏みしめられた雑草の香りがまだ強い。軍勢が通り過ぎてそれほ ど時間は経っていないようだ。数は、一万ほどだろうか。長い間こ の世界で邪神をやっていると、そういうことも自然と分かるように なってくる。 邪神になってより鋭敏になった嗅覚は、数ヶ月、さらには数年前 の残りがさえ嗅ぎ分けることができた。数千数万の匂いを鼻腔で愉 しみながら、自分に必要な情報だけを拾っていく。その中に自分の 香りを見つけ、飛騨守は漸くここがどこであるのかに思い当たった。 ﹁なんだ、随分と皮肉な場所に送らせるものだな、この若造は﹂ <ジョナンの赤い森>の中、パザンとアルナハを結ぶ街道の中間 点だ。 ここでかつて飛騨守は信者であるゴブリン・シャーマンに久方ぶ りに呼び出され、背中の上で眠る邪神ヒラノと対峙した。<戦女神 >と再会したのも、この場所だ。 今思い返しても初神者らしからぬ生意気な若造だったが、不思議 と嫌いにはならなかった。 誰かに似ているような気もしたが、誰に似ているのかは記憶の靄 の中に埋もれて思い返すことができない。眠っている時間が、長過 ぎたのだ。一〇〇年単位の睡眠を断続的に繰り返しているのは、起 きていても渇いた気持ちが満たされることはないからだ。 226 つまらないことになった、と飛騨守はまた口の中だけで呟く。 口癖のようになってしまっているが、今となってはつまらないこ とになってしまったから口癖になったのか、それとも繰り返し同じ ことを呟くから周りの全てがつまらないことになったのか、判然と しなくなっていた。 奇蹟を使えば、それだけ徳が減る。徳が減れば、来世に障る、と いうことを飛騨守は漠然としか知らなかった。この世界の仕組みと いうものに、あまり関心は無い。 ただ、前世で白い狼として山や谷の主をやっていた頃と同じく、 危険な匂いのすることには近づかなかった。それが生き延びる上で 一番大切な知恵だと飛騨守は知っている。 一つ大きなことを自分に禁じると、その周りにまた小さな禁じる べきことができる。それをまた禁じることで、また小さな禁じるべ きことが現われた。 それを野生の動物のように忠実に守ることは飛騨守の事を守った が、自分に禁じることを繰り返すとゆっくりと自分のやれることが 減っていくのだ。 ﹁⋮⋮それに引き替え、お主は随分と自由そうだな﹂ 背中の上のヒラノに飛騨守はそっと語りかける。隣で眠る<戦女 神>が眠っているのは、徳を送り込むのに疲れたのだろう。 他の神と同調して徳を送るのは繊細な調整の必要となる奇蹟だ。 <戦女神>ほどの遣い手であっても、困憊するのは無理もない。 二人分の重みを背に、若さだろうかと飛騨守は考える。 飛騨守にも、血気に逸る時期があった。但しそれは、前世の狼で あった頃のことだ。 227 今の飛騨守にない、熱を背中の二人は持っている。そんな気がし た。あるいは、飛騨守が悩まされ続けている渇きを潤すものも、あ るいは。 ﹁信者の為に、走る。面白い若造だ﹂ 信者に何かをしてやっても、見返りはない。 人族やエルフ族と違い、魔族の信仰は徳を生まないということは 邪神にとっては常識だ。飛騨守にとって、“信者の為に自分を犠牲 にしてまで何かをしてやる”というのは自分に禁じたことの一つだ った。 大会議に睨まれやすい顕現など、信者からの余程の強い願いに応 える場合でなければしない。 それをこの若造、邪神ヒラノは事もなげにやって見せる。 ﹁⋮⋮本当に、面白い小僧だ﹂ 危険なこと、すべきでないことを自分に禁じていった結果飛騨守 に残されたのは、誰かを送ることだけだった。<道を守る者>など という大した仇名を貰っているが、その役割さえも本気で行うこと は稀になっている。 ﹁着いたの?﹂ まだ眠そうな<戦女神>の声が背中から聞こえる。戦争では滅法 強い女神だというが、寝起きは単なる姿相応の人間の小娘と大して 変わらない。 ﹁いや、まだだ。もうすぐ着く﹂ ﹁そ﹂ ﹁若造は⋮⋮ヒラノとかいう邪神は起こさないのか?﹂ ﹁貧徳になんてなったことないけど、辛そうだったから。着くまで は寝せておいてあげるつもり﹂ なるほど、よくできた女房だ、と飛騨守は思った。 <戦女神>に直接言えば怒られそうな気がするが、それでも実態は “つがい”のようなものなのだろう。今は違ったとしても、遅かれ 228 早かれそうなる。そういう雰囲気が、今の<戦女神>の気遣いから は感じられた。 ﹁<戦女神>、しっかり掴まれ。ここからは、飛ばすぞ﹂ ﹁はい、お願いします!﹂ 全身に徳を漲らせ、飛騨守は大きく一声吼えた。 森が揺れ、天に轟く。 この仕事が終わったら、あのリ・グダンとかいうゴブリン・シャ ーマンを探してみよう。そんなことを、飛騨守はぼんやりと考えな がら、地を蹴った。 夢を見ていた。 走る夢だ。長い道を、ただひたすらに走る。 道は商店街で、自然公園で、会社の裏のドブ川沿いの道で、アル ナハで、魔界だった。 何で走っているのかは覚えていない。思い出す気力さえも、太腿 を前に動かす為に使う。 走って、走って、走って、走る。ここが夢だと分かっている明晰 夢なのに、空を飛んだり、一瞬で目的に着いたりすることはない。 鈍っていた大腿筋に血が通い、毛細血管が押し広げられる痒みに 似た感覚が襲ってくる。 喉の奥底から錆っぽい金属臭が這い上がってきて、口の中に血の 味が広がる。 それでも、走った。 人混みの中を、木漏れ日の芝生を、薄汚れたアスファルトの道を、 賑やかな人々の中を、そして、<ジョナンの赤い森>の樹々の間を。 額に滲む汗を拭う。 濡れた左手の甲を見ると、そこだけ薄っすらと透けて見えた。俺 の存在そのものが失われたような薄さで、向こう側が透けている。 徳が足りていないんだな、とぼんやり分かった。 229 徳が足りないと、俺は死ぬ。いや、死ぬか、それよりももっと恐 ろしい目に遭う。少なくとも、天国に行くことはできない。そうい う意味のことを、誰かに言われたような気がする。 そんなことを考えながら、足を前に出す。 ﹁踵を先に付けると、足が前に出るよ﹂ いつの間にか、慶永さんが隣を走っていた。 夢の中の慶永さんはまだ高校生で、俺の先輩で、高校の夏服を着 ている。現実の慶永さんも姿は同じだけれども、決定的に何かが違 う気がする。それが四〇〇年の重みということだろうか。 そこまで考えて、俺は不思議なことに気が付いた。 現実って、なんだ。今が夢の中だということは分かっている。そ れはつまり眠っているということで、起きている時があるというこ とだ。起きている時の俺は⋮⋮ ﹁邪神だよ、ヒラボン。起きている時は、ヒラボンは邪神なの。そ して、私のマスター﹂ そうだ。慶永さんに教えられて思い出した。俺は邪神だ。邪神だ った。 生牡蠣にあたって死んで、生まれ変わったのだ。邪神に。 その邪神の俺が、何で走っているんだろう。 森の道が小汚いビルの廊下に変わる。段ボールの積み上がった廊 下には見覚えがある。血反吐を吐きそうになりながら務めた職場の 廊下だ。 毎朝、ここを通るのが嫌で嫌で堪らなかった。何度も無断欠勤し ようとして、結局は毎日通ったのだ。土日もほとんど出勤した。祝 日なんている小洒落たものは高校卒業と同時に俺のカレンダーから は抜けて消え落ちてしまっていた。 その廊下を走り抜け、つきあたりのドアを開けると懐かしい場所 に出た。 高校の、囲碁将棋部の部室だ。夕陽の射す部屋には高校の制服を 着た俺と慶永さんが盤を挟んで向き合っている。 230 この光景には見覚えがあった。百回近くも対局した中で、一番記 憶に残っている対局だ。 ﹁この対局、負けた方が勝った方の言うことを一つだけ聞く、って ことで良いんだね?﹂ 盤面を前に座るブレザー姿の慶永さんが俺に尋ねる。もちろん、 走っている俺ではなく、記憶の中の俺にだ。 ﹁それで良いですよ。でも慶永さん、本当にいいんですか?﹂ 記憶の中の俺が、少し緊張した表情で慶永さんに聞いた。 この時点で、俺の慶永さんに対する勝率は一〇割。一度たりとも 負けたことはなかった。 ﹁良いって言ってるじゃん。武士に二言は無い﹂ ﹁慶永さん、いつの間に武士になったんですか?﹂ ﹁可憐でいたいけな女子高生をつかまえて武士とは何だ武士とは﹂ いつも通りの軽口。いつも通りの冗句。いつも通りの掛け合い。 この幸せな時間が、ずっと続くと思っていた。 対局が終われば、俺は慶永さんに交際を申し込む、はずだったの に。 石を置く音が、静かな部屋に妙に大きく響く。 遠くから吹奏楽部の演奏が微かに聞こえてくるが、曲名は分から なかった。 俺は、走り続けている。踵を先に付け、太腿を動かし、腕を大き く振った。それでも、目の前に映る光景は何一つ変わらない。 盤上では、勝負が思わぬ方向に進んでいる。 この結末は、見たくない。そう思えば思うほど、ただの教室がど んどん大きく、扉が遠くなる。まるで粘り気の強い水飴の中を進ん でいるように、俺の身体は動かない。 記憶の中の俺は、見るも無残に動揺していた。 その息苦しさが伝染したかのように、俺も胸が苦しくなる。 絶対に負けない。勝って慶永さんに告白する。そのはずだったの に。 231 パチリ、と最後に慶永さんが石を置いた所で、急に体が軽くなっ た。 部室は元の大きさに戻り、扉にも手が届く。慌てて部屋を出なが ら、俺は背中で慶永さんの勝鬨を聞いた。 あの後、慶永さんにわざと負けたんじゃないかと随分叱られたよ うな気がする。 俺はまた、森の中を走っていた。 見覚えがある。<ジョナンの赤い森>だ。 アルナハと、パザンの間。リ・グダンと戦った場所だった。 ﹁若造、走れ! 急げ!﹂ いつの間にか、俺の隣をオクリ神も走っている。 慶永さんと、オクリ神。この二人がいれば、絶対に間に合う。間 に合わせてみせる。 間に合う? 何に? 森の出口が近付く。樹々の間から、光が漏れている。 そうだ、俺が走っているのは。 ﹁ドラクゥ!﹂ 俺は、自分自身の叫びで、目を覚ました。 ﹁ちょうど良い頃合いで目覚めたな、若造﹂ 夢から醒めたばかりの俺をオクリ神はそう言って嗤った。 いつの間にか日が暮れている。オクリ神が佇んでいるのは、軍営 のど真ん中だった。 旗印は大魔王の親率を示す大魔王旗。 ここは、ドラクゥの陣だ。広大な大森林が終わり北に向けて開け た荒れ地に、一万ほどの兵が滞陣している。アルナハの郊外でも見 掛けた色とりどりの天幕が、篝火に照らされて並んでいた。 ﹁指定された場所に軍がいなかったからな。お節介とも思ったが、 ここまで運んで来た﹂ ﹁ありがとうございます、助かりました。でも、言った場所にドラ クゥがいなかったなら、起こしてくれれば良かったのに﹂ 232 ﹁二人とも気持ちよさそうに眠っていた。どうせ北に進軍している ことは匂いで分かっていたことでもあるしな﹂ 二人とも、と聞いて俺は横で眠っている慶永さんの寝顔を見る。 オクリ神の白い毛皮の上で、慶永さんはすやすやと気持ちの良さそ うな寝息を立てていた。確かにこれは起こしづらい。 それにしても、妙に照れくさいのはさっきあんな夢を見たせいだ ろうか。 あの夕陽の対局の後、慶永さんは俺になんて命令したんだろう。 どういうわけか、よく覚えていない。 ﹁慶永さん、起きて。着きましたよ﹂ 張りのある頬をぺちぺちと叩くと、んむぅと眠そうな声を上げて 慶永さんは薄っすらと瞼を開いた。心なしか疲れて見えるのは、ま た俺に徳を送り込んでくれていたんだろう。 慶永さんは欠伸をすると、大きく伸びを一回した。 ﹁おはよ、ヒラボン。もう夜だけど﹂ ﹁おはようございます、慶永さん。もう夜ですけど﹂ 間抜けな挨拶を済ませると俺と慶永さんはオクリ神の背中から飛 び降りた。まだ体が本調子じゃない。立ちくらみを起こしそうにな るが、何とか慶永さんに無様な姿は見せずに済んだ。 オクリ神は俺たちが下りたのを確認すると、まるで犬のように全 身を一度大きく震わせる。 ﹁では確かに送り届けたぞ﹂ ﹁飛んでいる途中に発作に襲われることを考えると、とても一人で はここまで飛んでこられませんでしたから﹂ ﹁実際、途中でへたり込んでおったしな﹂ オクリ神がまた、口角を上げて笑う。 最初に対峙した時のような怖さは、もうない。 ﹁それでは儂はそろそろ行くぞ。行きたい所もあるしな﹂ ﹁行きたい所、ですか?﹂ ﹁会いたい奴、と言い換えてもいいかもしれぬ。いずれにせよ若造、 233 次に会う時はまた敵同士ということになるだろう﹂ ﹁⋮⋮お手柔らかにお願いします﹂ リ・グダンに会いに行くつもりだということは、すぐに分かった。 最後の言葉を聞いてくれたのかどうか、オクリ神は四本の肢でし っかりと大地を蹴ると、星の瞬く夜空に躍り上がる。そして俺たち に向かって一声遠吠えを上げると、北へ向かって走り去っていった。 その速さはさすがで、邪神の視力でもすぐに豆粒ほどになり、やが て見えなくなる。 ﹁⋮⋮行っちゃったね。まさか力を貸してくれるとは思わなかった けど﹂ ﹁本当に。でも、おかげでここまで来られた﹂ まだ足元がふらつく俺を、慶永さんが支えてくれる。 二人とも顕現していないので、周りにいる兵士たちはまるで気に もしていない。一〇や二〇の塊に分かれて、飯炊きの焚火を囲んで いる中を、俺は慶永さんに肩を貸してもらいながらドラクゥを探す。 立ち上る煙の向こうに見えるのは、パザンを防禦する支城の一つ だ。 城市を守る防禦構造物が城壁しか存在しないアルナハと違い、パ ザンの周辺にはいくつもの支城が設置されていた。 街道を扼する形に配置された支城は単独でも十分に手強いが、相 互に連携を取ることでその威力を最大限に発揮する。確か、元は人 熊族の王が整備した鉄壁の守りだったはずだ。 それでも、支城を見据えて野営をするドラクゥ軍の兵士たちには 余裕がある。 支城が守るべきパザンには既に主としての魔王、<淫妖姫>パル ミナがいないからだ。この支城を抜き、素早くパザンを接収してし まおうと部隊の士気は高い。 そして、パザンを占領した後、この軍はさらに北へ向かう。 ﹁⋮⋮北に進軍させちゃ駄目だ。ドラクゥを、止めないと﹂ オクリ神の背中でたっぷり寝たはずなのに、まだ身体が重い。 234 もっとも、睡眠を取ったからといって邪神が回復するわけでもな いのだろうが、気分の問題だ。全身の筋肉が萎えてしまったかのよ うに、まるで力が入らなかった。 ﹁マスター、大丈夫? 少し休む?﹂ ﹁大丈夫ですよ、それよりも早くドラクゥを探さないと﹂ 目星は付いている。陣の奥まった所、周りより一段高くなった場 所に一つだけ大きな天幕が設置してあった。あれが恐らく、ドラク ゥの本陣だ。 一歩一歩、足元を確かめるように進む。慶永さんが身体を支えて くれている側がほのかに温かいのは、こっそりと徳を送ってくれて いるからだろう。 全身の鎧を黒く染めた親衛隊の間を潜り抜け、俺は漸く本陣に辿 り着いた。 邪神の身体なのに、息が上がっている。 慶永さんには気付かれないようにしたかったが、さっきからまた 俺は断続的な発作に襲われていた。エリィナが、また魔法を使って いるらしい。インフルエンザで四十一度の熱が出た時よりも、まだ ふらふらする。 ﹁いた⋮⋮ドラクゥだ﹂ ドラクゥは蝋燭の灯りで涜皮紙の束に目を通している所だった。 つい最近、顔を見たばかりのはずなのに、なんだかとても懐かし い気がする。ドラクゥに、伝えなければならない。たった一言で良 い。ドラクゥの横顔を見ながら、俺は残る気力を振り絞って顕現し ようとする。 その瞬間、俺の中で、何かが折れる音が聞こえた。 † † † 東征軍の軍監、クォンはキリックを確実に倒す為、特大の雷撃の 235 目印に自らなることを決意する。 使うのは、かつて人界で錬金術師に託された“火精の秘薬”、つ まり黒色火薬だった。 最後の最後で対峙し、互いの心情をぶつけ合うクォンとキリック。 激しい雷撃がキリックを撃ったとき、クォンはその閃光の中に天 に昇る竜の姿を見た。 その頃、ドラクゥは大天幕の中でヨシナガの嗚咽を聞く。 ヒラノが倒れた。しかも、その原因はドラクゥが使用を命じた魔 法によってであるという。 激しく動揺するドラクゥ。 ヒラノを助けるには、魔族ではなく人の信者が必要となる。悔恨 に打ちひしがれるドラクゥは、信じるヒラノを何としても助けるこ とを誓うのだった。 236 第一章 ダイジェスト版 署名を、書き損じた。 筆先が走り、字体が僅かに崩れてしまっている。ドラクゥにとっ てはじめてのことだ。 獣脂の蝋燭の灯りに照らして字体を確認してみるが、やはり崩れ ている。横に御璽が捺されていたとしても、これでは正式の命令書 として使うことはできない。大魔王の署名には、それだけの精確さ が求められのだ。 執務室に部下を近侍させていなかったことにドラクゥは安堵した。 何気ない所作の一つ一つさえ上手くいかないほどに、ドラクゥは平 静さを欠いている。このような姿を、部下に見せるわけにはいかな い。 不調の原因は、分かり切っていた。邪神だ。 邪神ヒラノが倒れて、既に二日が経っていた。 容態は、芳しくない。 原因は信仰の不足によるのだという。信者が魔法を使うと邪神の 持つ信仰、徳が消費される。徳が不足すれば、邪神は力を失い衰弱 するのだという。 ドラクゥはこれまでそういう話を一度も聞いたことがなかった。 書物で読んだ記憶もない。邪神官であれば何か知っているのかもし れないが、今回の遠征には同行させていなかった。 魔族に肉体の限界があるように、邪神にもまた限界がある。そう 言われてみればそうなのだろうという気がするが、今のドラクゥに とってはただままならない苛立ちだけを募らせる悩みの種でしかな い。 邪神ヒラノを快復させる為には、徳が必要だ。 一つには信者による魔法の使用を止めること。そしてもう一つに はヒラノに徳が集まるようにすることだ。但しその徳の源になる信 237 仰は、魔族のそれではなく人族のものでなければならないという。 魔族にヒラノ信仰を広める方法なら、いくつもある。だが、人族 相手に広めるとなると取り得る手段は限られてくる。 ドラクゥは、机上の小刀を手に取った。 書き損じの署名を削り、新たに書き直さねばならない。書類に使 う涜皮紙は厚く、こういうことをすることができた。 本来であれば署名の書き換えは手続き上の問題を産むが、今は新 たに書類の書き直しを命じる時間さえ惜しい。 しなければならない仕事が山積している。 ドラクゥ率いる一万の軍はほぼ大過なくパザン市を掌中に収める ことに成功していた。 城市の北方にある支城の一つがまだ頑迷に抵抗を続けているが、 一両日中には陥ちるはずだと寄せ手を任せてある<青>のダッダの 報告にはある。 かつての宿敵<淫妖姫>パルミナの支配下にあった城市だが、今 は空き城だ。この城市を、一刻も早く自領に組み込まなければなら ない。 パザンは<ジョナンの赤い森>の北限にある。魔界の他の地域か らドラクゥの基盤である魔界南部へ向かうには、リザードマンの沼 地かこのパザンを経由するしかない。ここをしっかりと押さえれば、 南部を完全に切り取ることができるのだ。 まずは魔界の南を切り取る。そこから北上して、魔都を窺う。 その支度が整う前に<北の覇王>ザーディシュが攻めてくるので あれば、このパザン市が最前線になるはずだ。それまでに住民を慰 撫し、大魔王の民としなければならない。口で言えばたった一言だ が、それが難しかった。しかも、掛けられる時は有限なのだ。 加えて、邪神ヒラノのことがある。 人族に、邪神を信仰させなければならない。 魔族と同じように、人族も色々な神を信じている。そういう話は、 新たに将として迎え入れたクォンから聞かされていた。 238 その信仰の中に、何とかしてヒラノへのものも紛れ込ませること はできないか。そのことをドラクゥはずっと考えていた。 ヒラノは、ドラクゥの邪神だ。だが同時に雷の邪神としての側面 もある。 これは義妹のエリィナと相談して、邪神殿でもそのように祀るよ うにしてあった。 同じようなかたちで、ヒラノの属性を広げることはできないだろ うか。そのようなことが可能なのかは分からなかったが、試してみ る価値はあるだろう。このまま座視していれば、あの気の良さそう な邪神は消滅してしまうかもしれないのだ。 ﹁ッ!﹂ 左の人差指を、浅く切った。 考え事をしながら涜皮紙を削るものではない。玉になって滲む血 を、ドラクゥは口に含む。痛みはそれほどでもない。だが、切った 角度が悪かったのか血はすぐには止まりそうもない。 政務への集中を欠いていたのだから自業自得だと自嘲しつつ、ド ラクゥは机上の置き鈴を鳴らした。手当てが必要だとも思わなかっ たが、後でラ・バナン辺りに見つかると過剰に心配されるのが億劫 だ。 ﹁主上、お召しになられましたか﹂ 扉の側に控えていたのだろう。間を置かずに入って来たのは、ド ラクゥの側室でもある竜裔族のラーナだった。 ﹁ラーナか。すまん、少し指を切ってしまってな﹂ ﹁ああ、主上。それはいけません。拝見致します﹂ そう言って傍に歩み寄ると、ラーナはドラクゥの指先を躊躇うこ となく口に含んだ。温かさと女の舌先の感触を束の間愉しんでいる と、気付けば傷の痛みは消え去っていた。 ﹁ご無礼を致しました、主上﹂ ﹁いや、良い。これも竜裔族の力か﹂ ﹁はい。竜の裔の血、唾液、体液には治癒の効果がございます﹂ 239 ラーナの唇から離れた指先を二度、三度屈伸してみる。痛みも傷 も、嘘のように消え去っていた。 ﹁大したものだな、竜裔の血は﹂ ﹁このようなことでしかお役に立てず、心苦しい限りです﹂ 言いながら俯いてみせるラーナの頬を、ドラクゥはそっと掌で撫 でる。 ﹁ラーナには助けられている。これからも、余を支えて欲しい﹂ ﹁畏まりましてございます﹂ ﹁早速だが、ラーナの知恵を一つ借りたい﹂ ﹁⋮⋮ヒラノ様のことにございますね﹂ ﹁ああ、そうだ﹂ ラーナの答えは、明快だった。 ﹁城市を築きましょう﹂ 机上にある魔界の地図の一点を、ラーナが指差す。それはドラク ゥの思いもよらない場所だった。 ﹁そこは、河だ﹂ ﹁はい、主上。魔界と人界を隔てる河の中洲と両岸とに、一個の城 市を築きます﹂ ﹁そこに人を住まわせる、ということか﹂ ﹁魔も人も、住まわせます。ここに城市を築けば、塩も馬も米も、 これまでより格段に運びやすくなるはずです﹂ 邪神ヒラノの助けで、今やドラクゥの陣営は人界との初歩的な交 易を始めることができている。それを本格的なものにする為にも、 この場所に城市を築くことは意義があるようにドラクゥには聞こえ た。 ﹁そこに人が住まうようになれば、ヒラノ様を信じる者も現われる か﹂ ﹁畏れながら、ヒラノ様を商いの神として祀ることも考えても良い かもしれません﹂ ﹁商いの神、か﹂ 240 ﹁ええ、塩の柱を持ち返りアルナハに商いの道筋を付けられたのは 他ならぬヒラノ様です。人族が他の商売の神を勧進するより前に、 この城市ではヒラノ様を祀るように邪神殿も建立してしまえば﹂ ﹁なるほどな。しかしそんなことができるのだろうか﹂ ﹁試してみる価値は、あると存じます﹂ 恭しく頭を垂れて見せるラーナの頭に、ドラクゥはゆっくりとそ の掌を載せる。 ﹁よし、やってみよう。パザンを掌握し、北への備えをしながらと いうことになるが﹂ ﹁微力を尽くします﹂ ラーナの声には、決意が感じられた。 何ができるのかは分からないが、今はただ動いていたい。ドラク ゥは、そう思った。 とにかく、早く終わらせてしまいたい。<青>のダッダは自分の 掌に何度も拳を打ち付けながら、眼前に聳える砦を見上げた。 パザン市の接収自体は、快勝と言っても良い。呆気ないと感じた ほどだ。問題は、たった一つ残ったこの砦だった。小高い丘の上に 築かれた石造りの砦は<淫妖姫>パルミナの統治時代のもので、堅 牢な造りになっている。 パルミナが北からの侵攻を恐れていたということはこの砦を見れ ばよく分かった。 魔界南部を覆う広壮な森林地帯はパザンを境にして終わり、ここ より北は見渡す限りの草原地帯、<西の獣王>の領域となる。 パザンがまだ人熊族の物だった頃、南下して掠奪を働く獣王の騎 兵は大きな脅威として捉えられていた。小競り合いはしばしば流血 の事態にも発展している。 その騎兵に備えるためパルミナは市の北に防衛線として幾つかの 砦を設置した。ダッダが手を焼いているのはその最後の一つだ。 砦を攻囲する兵の士気は、低くない。人熊族にとってパザンは故 241 郷だ。この砦を陥としさえすれば、かつて奪われた物が戻ってくる。 そう思えば意気の高まるのも自然なことだ。 しかし、どうにも攻め切れない。 頑健な抵抗があるわけではないのだ。ただ、手応えがなかった。 ダッダには、本格的な城攻めの経験がない。 元は森で狩人のような生業をしていたところを、ドラクゥに拾わ れたのだ。それが戦場での働きを続けていく内に、いつの間にか将 軍の一人のような扱いとなった。今では部隊を預けられるようにさ えなっている。 指揮をできる者が、足りていないのだ。もしドラクゥが<廃太子 >として落ち延びて来たのでなければ、ダッダは召し抱えられたと してもこのような立場にはなかっただろう。 勇気と忠誠では大魔王臣下の誰にも負けないという自負があるが、 経験不足の感が否めないのはダッダ自身もよく分かっていた。 武官の不足もいつまでも続くという訳ではない。 ドラクゥが大魔王の座に就いたことで、仕官しに来る者もこれか ら増えていくだろう。 今のドラクゥの麾下では、文官も武官も等しく頭数が足りていな い。だが、両者を比べてみた時に数の補いが付きやすいのは武官の 方だった。 特に、ダッダのような一部隊を任せられる程度の将は魔界には無 数にいる。 そういう将軍が新たに同僚となった時に、ダッダの価値は大きく 下がるだろう。 自分の地位が危うくなるという風にはダッダは考えていない。 身の丈に合ったことをする。それが一番幸せだということは、森 の中の暮らしでよく分かっていた。力量のない者を頭領に頂いた獣 の群れの末路は、悲惨だ。 だから、いつか失うかもしれない将の地位には何の未練もない。 むしろ清々するという気持ちさえある。一人の兵として戦いたい 242 とも思う。 だが今は、困難な砦攻めを指揮しなければならない。 突撃で傷付き失うのは、顔も名前も知った人熊の兵士たちだ。 とにかく、早く終わらせてしまいたい。 ﹁ダッダ殿、もう一度突撃しますか?﹂ 尋ねて来たのは傍に置いて副官として使っているまだ年嵩の人熊 だった。 ﹁いや、小休止を取る。交代で水と糒を摂るように﹂ ﹁ではそのように﹂ 伝令に指示を出す副官を見るともなしに見ながら、ダッダは小さ く溜息を吐く。 堅い砦だ。しかし、所詮は砦、という気もする。 押せば何とかなりそうなものだが、それが巧く行かない。 既に数度の突撃を退けているのは意外だ。 ﹁あの砦の守将は、誰だ?﹂ ﹁それが、妙なことになっておりまして﹂ 副官の調べでは、この砦の守将はカルキンという人鹿族の男でパ ルミナの配下の中でも名の知れた戦巧者であった。ところがその男 は今、この砦にいないのだという。 ﹁守将もいない砦に人熊の兵は苦戦しているということか?﹂ ﹁中に残った者が指揮を執っているのでしょう。ただ、カルキンも その副将も、パザンの防衛に呼び出されていたようで、向こうで既 に捕虜となっています﹂ 砦の位置付けを考えれば、ここにカルキンのような武将を置きた くなるパルミナの気持ちはダッダにはよく分かった。それほど獣王 の掠奪は恐ろしいものだからだ。 だが、北上して来ているドラクゥの軍に備えてカルキンをこの砦 から引き抜くような事態になった時、果たしてまともな戦力をここ に残しておくのだろうか。 ﹁目星は?﹂ 243 ダッダの問いに、副官は少し答えにくそうにした。 ﹁ハツカ、という主計官が﹂ 主計官ということは文官だ。帳簿の管理や物資の保管を担当する 役職の者が戦闘の指揮を執っているというのは興味深いことだった。 ﹁主計官が? 筆を剣に持ち替えたというところか﹂ ﹁いえ、剣は恐らく持っていないでしょう﹂ ﹁冗談を言うな。剣も持たずにどうやって戦を指揮するというのだ ?﹂ ﹁それが⋮⋮ そのハツカなる主計官、人鼠族にございます﹂ むぅとダッダは喉の奥から唸りを漏らす。 人鼠族も魔界に暮らす民には違いない。だが、その中から武将が 出たという話をダッダは聞いたことがなかった。 小さいのだ。 成人しても、ダッダの掌に乗るほどの背丈にしかならない。 他の種と比べて寿命が短いといったこともないが、その余りの小 ささから活躍の場はもっぱら文官や商人といった分野に限られてい る。 その事を聞いてダッダの胸に浮かんだのは、怒りでも嘲りでもな く、おかしみだった。 人鼠に、手玉に取られている。何とも妙な気分だった。 ﹁伝令を呼べ。小休止が終わり次第、再度突撃を行う﹂ ﹁突撃、ですか﹂ 少し不服そうに確認する副官をダッダは睨みつける。 ﹁ああ、突撃だ。人鼠が忠義を見せている。人熊がそれに勝てぬは ずはない。忠義と忠義のぶつかり合いだ﹂ ﹁しかし相手は小勢です。無駄に攻めて被害を増やすのは如何でし ょうか﹂ ﹁その小勢に、ここまで梃子摺らされている﹂ ﹁分かりました﹂ ここさえ陥落させれば、パザンの接収は完了する。 244 本来ならば早く終わらせて、<北の覇王>の侵攻に備えねばなら ないのだ。 ﹁人熊が、人鼠に負けるものかよ﹂ 伝令が走り、陣地に闘気が満ちる。 この雰囲気が、ダッダは、嫌いではなかった。 ダッダに預けられた二〇〇〇という兵力は、かなりのものだ。 パザン接収部隊全体の五分の一に当たる。その中に、ダッダの育 て上げた人熊の精兵五〇〇も含まれていた。 掛けられている期待の大きさよりも、今は責任感の重さがダッダ の方に圧し掛かる。 この砦だけは、落とさねばならない。 俗に攻守三倍の原則というものがある。ただそれは目安であって、 あまり当てにならないということをダッダは誰かから聞いたことが あった。 城郭を攻める場合には、守備側の三倍の兵力が要る。主君である ドラクゥの率いる軍は、その常識をいつも覆してきていた。 単純な兵力の問題ではない。兵力を巧く活かすための方法という ものが、確かに存在するのだ。 その中には、勇を奮う蛮声を上げての突撃も含まれる。 ﹁砦に籠っているのは、三〇〇と言ったところでしょうか﹂ 副官の見立てに、ダッダは小さく唸った。 ﹁どうだろうな。もう少し、隠れていると思う﹂ いや、隠していると言うべきだろう。既に二度、ダッダは砦に突 撃を掛けているが、何とも言えない得体の知れなさを感じていた。 丘の上の砦は歪な五角形の壁に囲まれている。その五つの面の全 てに均等に兵が配されているわけではない。ダッダは南向きの壁を 主攻路と定めているので、そこに一番敵が集中しているように見え る。 ダッダは精鋭の人熊族五〇〇の中からさらに選りすぐった二〇〇 を使って他の側面にも誘いと牽制の攻撃を掛け続けさせていた。こ 245 れだけの兵力差で打って出るとは考えにくいが、森の中での狩りで 培われた用心深さが、この敵に対しては全てに備えるように警告を 発している。 ﹁囲まれてなお、数を少なく見せることに、意味があるとは思えま せん﹂ ﹁少なく見せているだけではないと思う。同時に多く見せてもいる。 あの壁の上を見ろ﹂ ダッダの指差した先、東南向きの壁の上にも弓兵の一隊が列をな している。傍に侍する旗本から張りの強い大弓を受け取ると、ダッ ダは狙いを定めて立て続けに三矢放った。 狙い過たず、居並ぶ兵の首が三つ、璧外に転がり落ちた。 ﹁お見事!﹂ ﹁よく見ろ、あれは木偶だ﹂ 首を鳴らしながら、ダッダは落ちた首を指さす。 目を凝らして見れば、それはよく出来た藁の人形の首級だという ことが分かった。 壁の上に並べられているのは槍や弓の訓練で的に使う的の人形で、 この砦にまとめて仕舞ってあった物だろう。 ﹁藁人形を並べるくらいです。あちらの壁の方が手薄なのでは?﹂ ﹁そう思わせておいて、実はあちらの方がしっかりと守りを固めて いたりする。兵の数を少なく見せているのはその手当をするためだ ろう﹂ 二度の突撃で、色々なことが見えるようになってきていた。 特に相手は、手の内を知られないように気を配っているという感 じがする。狡猾な森の獣を相手している時と同じか、それ以上の興 奮がダッダの中には渦巻きはじめていた。 ﹁攻めるぞ。南西の壁だ﹂ 叫ぶと、ダッダはもう駆け出している。 大弓は手に持ったまま、愛用の戦斧を担いで壁際まで一気に走り 抜けた。壁の上からは雨のように矢が降り注ぐが、素早く動けば却 246 って当たらない物だ。 後から追いついてきた兵が、壁に取りつき始める。南で使ってい た長梯子が急遽こちら側に運ばれてきて、立て掛けられた。 梯子の先は鉤になっていて、上手く食い込ませてやれば少しのこ とでは外れない。 ﹁吶喊!﹂ 叫びながら、ダッダは璧上の敵に矢を射かけた。 今度は確かな手応えがあって、肩口を貫かれた敵が壁の中に転が り落ちてく。梯子を外そうとする敵を優先的に、ダッダは精確な射 撃で射抜いていった。 攻め掛ける兵たちは大盾を頭上に構え、一塊になって壁に近付い ていく。 梯子を上っている間は無防備だ。だが、一番に城壁を登り切った 者には一番槍の栄誉が与えられるとあって、我先にと兵士たちは梯 子に飛びついて行く。 巧く行くかと思ったが、敵はすぐに手を打ってきた。木の板を何 枚か張り合わせた物に覗きのついた楯を持った兵が、食い込んだ鉤 を手際よく外してしまったのだ。 さしものダッダも、細い覗きの間を狙って矢を射掛けることはで きなかった。 攻勢は頓挫し、三度目の退き鉦が鳴らされる。 ﹁強い﹂ 単なる人鼠の主計官と思っていた時の侮りは、ダッダの中から消 え去っていた。 孤立無援の砦である。中にいる兵の総数は、おおよそ五〇〇ほど ではないかとダッダは当たりをつけはじめていた。それが、ここま で粘る。 砦は元々、北からの脅威に備えたものだ。 本来の能力を発揮しない南側からの攻撃に対してここまでの抵抗 が続けられるのは、ダッダと中にいる守将との力の差が大きく隔た 247 っているからだとしか考えられない。 ﹁後詰を、頼みますか﹂ 副官の言葉に、ダッダは頷いた。 ここで詰まらぬ意地を張って兵をいたずらに失う愚は避けなけれ ばならない。いつかは兵に落ちる身だとは言え、今は将軍としてこ の場にいる。であるならば、最善は何かを考えて行動しなければな らない。 ﹁パザンに、後詰の要請を。但し、その後もう一度だけ突撃を試み る﹂ ﹁しかし、士気が落ちております﹂ ﹁全員に後詰の事は伝える。砦のたった一つも落とせなかった腰抜 けの汚名を着たくなければ、後詰が到着するまでにこの砦を落さね ばならん、とな﹂ ﹁⋮⋮御意にございます﹂ 策がない、というのは辛いことだ。ダッダはそう思った。 果たして、落とし切れるのか。いや、落とさねばならない。 戦斧の柄に、布を巻き直す。突撃の合図の太鼓が、もうすぐ耳に 届くはずだった。 † † † 勇戦虚しくハツカに敗れるダッダ。 ただの主計官だと思われたハツカだが、実はドラクゥにとっては 同門の師兄に当たることが分かった。 大魔王家戦術指南役のデュ・メーメルの下でかつて机を並べたハ ツカに対し、ドラクゥは自分の部下になってくれるように頼み込む。 しかし、帰ってきた答えはにべもないものであった。 248 第二章 ダイジェスト版 暖簾をくぐると、おでん出汁の香りが鼻をくすぐった。 十五人も入れば満席になるこぢんまりとした居酒屋に三つだけあ るテーブル席の一番奥で、目当ての人物はひらひらと手を振ってい る。 軽く会釈を返し、俺は男の向かいの席に腰を下ろした。 ﹁やぁ、ヒラノボンタさん。御無沙汰しております﹂ ﹁御無沙汰、というほどですかね。つい先日会ったばかりという気 がしますが﹂ ﹁あの時は突然押しかけてご迷惑をおかけしました。さ、まずは一 杯﹂ 完璧な営業スマイルを貼り付け、リンボファイナンスの男は予め 置いてあった俺のグラスに瓶のビールを注いでいく。こちらがグラ スを傾けたわけでもないのに手慣れた仕草でビール七分の泡三分の 黄金比を作り出すのはさすがだ。 お疲れ様の音頭で申し訳程度にグラスを打ち付け、よく冷えたビ ールに口を付けた。 愛想笑いを浮かべながらホタルイカの沖漬けに舌鼓を打つこの男 の会社、リンボファイナンスに俺は五億カルマ以上の借金を抱えて いる。ちょっとやそっとのことで返せるような額ではない。 その貸し手と借り手が同じテーブルでビールに喉を鳴らしている というのも妙な図だ。 以前会った時は二人組だったが、今日は背の低い方はいないよう だった。 相手から何か説明があると思って待っていたが、どうもそういう つもりはないらしい。 何も言わずに料理に箸を付けていく男を見て、俺も冷めるのが早 そうなものから処分していくことにした。 249 出汁のたっぷり沁みたふろふき大根に箸を割り入れていると、追 加注文で茹でた里芋のが笊に盛られてやってくる。皮の付いたまま 茹でてあるのだが、指で剥いてやると中からほくほくねっとりとし た芋が顔を出した。これに少しだけ塩を付けて食べてやるのだ。 他に男が頼んであった料理も、なかなか渋いチョイスをしている。 鰤のカマ焼き、ホウボウとカワハギの造りに茶碗蒸し。適当に見 繕って貰ったおでんは関西風のようで、牛すじや梅焼きなんかも入 っていた。この心配りが嬉しい。ちくわぶが入っていないのは残念 だったが、それは御愛嬌といったところだろう。 見た目は陰険そうな男だが、料理の趣味だけは合いそうだ。 運ばれてきた出し巻玉子を前に嬉しそうに手をすり合わせている ところに声をかけるのも気が引けて、俺はなんこつ唐揚げと焼きお にぎりを追加で注文した。 男二人が、ただ黙々と飯を食い、酒を飲む。 話を切り出す糸口が中々掴めず、俺の中では少しずつ苛々が募り 始めていた。 店内に客はまばらで、おでんのクツクツと煮える音と、ボリュー ムを絞ったテレビの歌謡曲だけが店内を満たしている。 男が店員に殻付きの生牡蠣を注文したところで、俺は意を決して 口を開いた。 ﹁それで、これは一体どういう状況なんですか?﹂ ﹁どういう状況と申しますと? つまり、何故こうして債務者と債 権者が居酒屋で仲良く卓を囲んでいるかということですか﹂ 債務者と債権者。確かに二人の関係はそうとしか言いようがない。 こっちの世界での常識はよく分からないが、少なくとも俺の生き てきた現代日本では和気藹々と酒を酌み交わす様な関係ではないこ とだけは確かだ。 ﹁ええ。私は、ドラクゥ⋮⋮私の信者に、どうしても急いで伝えな いといけないことがあるんです。こんな所で貴方と親睦を深めてい る余裕はありません﹂ 250 静かに、丁寧に。しかしきっぱりとした口調で告げる俺に、男は まぁまぁと宥める仕草をし、グラスの中身で口を湿らせた。 ﹁急にこんな場所にお招きしたので、さぞかし驚かれたことと思い ます。その点についてはしっかりとお詫びします。申し訳ない﹂ 頭を下げて見せようとするのを、俺は先んじて手で制する。表情 筋の一つも動かさずに、何が謝罪というのだろう。男の顔は全く悪 びれてはいなかった。 ﹁そういうのは結構です。早く俺を魔界に、パザンに返してくださ い﹂ ドラクゥに、一刻も早く伝えなければならない。 <黒髪姫>の横暴で夜魔族が壊滅し、ドラクゥの戦略は根本から崩 れてしまっている。もしその事を知らずにドラクゥが策を進めてい けば<北の覇王>を利するだけだ。 一緒にパザンに向かっていた慶永さんが上手くやってくれている と信じているが、それでも今は、ドラクゥのことが心配だった。最 初は相手が相手だからと茶番にも付き合ってやるつもりだったが、 いつまでもこんなところで酒を呑んでいる場合ではない。 ﹁残念ながら、それは致しかねますな﹂ ﹁どうして?﹂ ﹁⋮⋮もう、そうする必要がないからですよ﹂ 口調に籠っているのは、憐憫だろうか、それとも愉悦だろうか。 どちらにしても、俺に好意的な感情でない事だけは確かだ。 首筋を生温かいものが撫でるような居心地の悪さを俺は感じ始め ていた。 ﹁必要が、ない?﹂ 男は片頬だけを吊り上げ、妙に陰惨な笑みを浮かべる。 まるで爬虫類のようなその表情のまま、おもむろに生牡蠣を皿か ら取り上げると、ちゅるり、と旨そうに啜った。 ﹁だってヒラノボンタさん、あなた多分もうすぐ死ぬんですから、 ね?﹂ 251 もうすぐ、死ぬ。 そう言われても、まるで実感はない。確かにパザンに向かう途中 で既に、俺の徳はすっかり底を尽いていた。これ以上徳を使えば邪 神としての俺が消滅する。そういう限界になっていたのかもしれな い。 肩からすっかりと力が抜けてしまった。 何となく掌を見つめてみる。握っても開いても、そこには自分の 掌があるだけだ。 ﹁あまり驚かれませんね﹂ 生牡蠣の汁をおしぼりで拭い、男は次の殻に手を伸ばした。 ﹁一度死んでますから﹂ ﹁なるほど。死に対する恐怖のほとんどは、未知から来るものだ。 一度死んでしまえば、ということですか﹂ ﹁驚いた方が良かったですかね?﹂ ﹁いえ、もうすぐ死ぬかもしれないという宣告に対しては、随分と 珍しい反応ですから﹂ ﹁普通は驚きますか、やっぱり﹂ ﹁色々ですね。命乞いをする神さまもいらっしゃいますよ。もう少 し稼いでからでないと元が取れない、とか﹂ ﹁ああ、神さまになれば墓まで金が持って行けないってこともあり ませんからね﹂ ﹁そういうことです﹂ 店員を呼び、辛口の日本酒を冷やで頼む。 ビールもいいが、末期の酒にはこちらの方が合っているという気 がしたのだ。 ﹁最後の晩餐、という趣向ですか﹂ ﹁そんな良いものじゃないですよ。我が社からできる、せめてもの 手向けです﹂ ﹁手向け?﹂ ﹁ええ、債務不履行で亡くなられる神さま方にはこうするように社 252 内の規定で決まっておるんです。私どもとしては会社の金で飲み食 いできるので有難い話ですが﹂ ﹁債務、不履行﹂ ﹁だってそうでしょう。焦げ付いた五億以上の徳を、これから死ぬ 神さまから回収することはできないんですから﹂ そう言われてみればそうだ。 ということは、これまでに唯一神のせいで消滅してしまった神様 の中にも、こうやって最後の晩餐を味わうことになった人もいるん だろう。 ﹁⋮⋮これから、どうなるんです?﹂ ﹁返済不能な額の徳を借りたまま亡くなった魂は記憶を浄化され、 輪廻の流れに戻されます。そこで何回か転生を繰り返しながら、徳 を返済して頂く形になります﹂ ﹁現代日本人の一生で二億カルマくらいでしたっけ?﹂ ﹁はい。ただまぁ、徳のない状態での転生ですから、大半は細菌で すとかそういったものが生まれ変わり先になりますね。よくてヒメ ツヤメクラチビゴミムシ辺りですか﹂ ﹁それで、返済までどのくらいかかるんですか?﹂ ﹁個人差がありますが、ヒラノボンタさんの場合ですと、ざっと見 積もって一四〇〇万年くらいはかかると思います﹂ ﹁えっ、おかしいじゃないですか。人間の一生で精々長くて八〇年 ちょっとですよ? それで二億だったとしても三回転生分の二四〇年で何とかなるは ずだ﹂ ﹁ふりだしに戻る、ですよ。小さな魂は徳を稼ぐ効率が非常に悪い。 お金と同じですよ。二億円を五億円に増やすのと、一円で五億円を 目指すのではかかる時間が違う。あなたの転生履歴を確認した訳じ ゃないが、そもそも人間に転生するまでにこつこつと長い時間かけ て徳を積み上げてきたはずなんです﹂ 記憶を失って、一四〇〇万年。数字が大きすぎて、全く実感が湧 253 いてこない。 もう慶永さんにも、ドラクゥにも会うことはないということだ。 もし奇蹟が起こって何万回の転生の果てに会えたとしても、その時 には俺は記憶を失ってしまっている。 ﹁しかし残念です、ヒラノボンタさん。前回お会いした時は、返済 して頂けると思っていたんですが﹂ ﹁私もそのつもりでしたよ﹂ ﹁そりゃそうだ。踏み倒すつもりで徳を借りるような邪神には見え なかった﹂ ﹁ところで、一つ聞きたいことがあるんですが﹂ ﹁なんですかね。私でお教えできることであれば、何でも﹂ ﹁私を生き返らせることは、絶対にできないんですか﹂ ﹁“消滅してしまった神”を蘇らせることは、できません﹂ ﹁⋮⋮消滅していなければ?﹂ ﹁“私には”できません﹂ ﹁私がまだ消滅していない状態であれば、あの世界の者であれば復 活させることができる可能性がありますか?﹂ ﹁否定はしません。しかし、ほぼ不可能だと言い切ってもいい﹂ ﹁どういうことですか﹂ ﹁あなたの元々の徳が大きすぎるんですよ、ヒラノボンタさん﹂ 貧徳で徳を失ってしまった神を再起動させるためには、その神の 格に応じた規模の徳が必要になる。自転車を漕ぎはじめるのと、一 〇トントラックが走り始めるのでは最初に必要なエネルギーの量が 違うのと同じことだ。男はそう説明しながらビールを呷る。 ﹁邪神基本セットに、五億。これは破格です。異常です。その辺の 小神が軽自動車だとしたら、宇宙戦艦みたいなものですよ。それを 再度動かそうと思えば、莫大な徳が必要になってくる﹂ ﹁ドラクゥやルロが何とかしてくれるはずです。それに、慶永さん も﹂ ﹁無理でしょう。あなたは邪神だ。魔族は魂を収める魄の形が違う 254 から、いくら信仰しても徳はあなたに振り込まれない﹂ ﹁ルロは人間ですよ﹂ ﹁多寡が知れています。一応、こちらも仕事ですから計算だけはし てみたんですよ。あなたを再起動させるために必要な徳は、一一六 〇万カルマ。そのルロという少女が三二〇〇〇年くらい信仰し続け てくれれば復活できるかもしれませんね﹂ その数字を聞いて俺は鼻で笑った。 背もたれに身体を預け、天井を見上げる。 ﹁お分かりになりましたか? 覚悟を決めて頂いた方があなたのた めにもなります﹂ ﹁いえ、復活できますよ﹂ ﹁ほう、何か根拠が?﹂ 尋ねる男の目の前の皿から、俺は生牡蠣を一つ失敬した。クリー ミィで濃厚な味わいはいつ食べても、旨い。 ﹁それくらいなら、慶永さんが何とかしてくれます。絶対にね﹂ 細い指先でグラスの中の氷を転がしてやる。 すると、穏やかだった琥珀色の液体に対流が生まれるのだ。 慶永佐織は、その日五杯目のグラスを一息に干した。神界の場末 の、小さな酒場だ。 半地下になっている店内は間接照明でほのかに暗い。気の利いた 音楽の一つでも流していれば少しは様になるのだろうが、流れてく るのは耳障りな騒音のような響きだけだ。 客層が良いとはお世辞にも言えない。神や邪神に転生しても、変 わらないものは案外変わらないままなのだ。 馬鹿は死んでも治らない。それは、転生してさえも変わらない。 佐織のことを<戦女神>と知らずに声を掛けてきた頭の悪そうな 小神を二柱、既に酒場の床に沈めている。ツケが効く、という以外 に何の魅力もない。ここは、そういう場所だ。 255 徳は、思ったように集まっていない。 平乃凡太を復活させるために、佐織はここ数日神界を走り回って いた。 どれくらいの徳が必要なのか、正確な見積もりはない。それでも、 おおよそ一千万から二千万の間ではないかというのが藪先生の見立 てだった。 活動停止状態になってしまった神や邪神を再起動するためには、 それだけ大きな徳が必要になる。それが、最大級の奇蹟だからだ。 二席離れたところに座った神と女神のカップルが、お代わりを注 文する佐織を見ながら小さな声で何かを囁き合っている。貧のなさ そうな二柱連れだ。 耳をすまさなくても、それは佐織の噂をしているというのはすぐ に分かった。 街の噂にはすっかり慣れた。 佐織は次の一杯を最後にしようと大事に舐めつつ、不敵に笑う。 徳を借りようとするのは、ひどく目立つ。それが<戦女神>ヨシ ナガであればなおのことだった。 存在することにさえ倦んでいる神々にとって、噂は何よりも重要 な暇つぶしだ。 あっという間に噂は広まり、佐織に会うだけで眉を顰める者さえ いる。 同期の桜であるフォン・マルクントには一度会ったがそういう話 にはならなかった。 カーンティも、夫のユーリィが夜魔族のことで気落ちしているの で徳を貸すとか貸さないとかそういう話のできる状態でもないらし い。 他にも昔から付き合いのある子分のような神々のところを佐織は 尋ね歩いていたが、そこからも徳を借りてはいなかった。 担保もなしに徳を借りに来る非常識な奴。それが今の慶永に対す る神界の評価だ。 256 それだけならまだ手を差し伸べる神もいたかもしれない。だが、 <戦女神>が<賭博神>とは犬猿の仲だという至極もっともな評判 がセットになると、たったの一〇〇カルマでさえ貸そうという奴が 現われないのは実に面白い。 ﹁もう一〇〇〇年も前なら、義侠心のある神様もいたんだろうけど ね﹂ 困っていれば、徳を貸すどころから分け与えてくれる。そんな神 は今の神界にはもう一柱もいない。大物はとっくにアガリを迎えて いるか、どこかに隠棲しているのだ。 自分はまだまだ小神だと思っていた佐織が、いつの間にか大物扱 いされる時代である。 時々、飛び込みで面識さえほとんどない神に徳を無心してみる。 結果は当然芳しくない。施しのようなつもりで額だけ聞いてみよう とする神はいたが、一千万カルマという言葉を聞くとそそくさと話 を打ち切った。 噂には、尾鰭がつく。 一千万二千万という徳を集めて、<戦女神>が何を始めようとし ているのかに神々の関心は集まり始めた。マルクント主催のトトカ ルチョもあるらしい。 曰く、弟分に恥を掻かせた<黒髪姫>を〆るための軍資金。 曰く、かつて自身を消滅寸前にまで追い込んだ唯一神にリベンジ マッチを挑む軍資金。 曰く、神界の裏社会を統一するための軍資金。 曰く、妙な噂を流したフォン・マルクントに復讐するための軍資 金。 軍資金、軍資金、軍資金。 確かに<戦女神>の二つ名はあるが、出てくる予想はほとんど戦 いに関することばかり。 どこまで喧嘩っ早いと思われているのか、佐織は少しだけ哀しく なってしまう。 257 中には、倒れた恋人の治療のために健気にも徳を借りて回ってい るという噂もある。 一番事実に即している噂だが、これはあまり人気がないらしい。 イメージに合わない噂というのは美談でも広がりにくいものなのか もしれなかった。 ﹁まぁ、一千万だからね﹂ 貸してもいいのは、返って来なくてもいいという覚悟のある者だ けだ。 大物のアガリや唯一神勢力の伸張やらで、段々とこの世界の雰囲 気も退潮方向に向かっている。 そんな雰囲気の中で一千万もの徳をポンと投げ捨てるような真似 ができるだけの神様はやはりもういないらしい。 最後の荒稼ぎに走る者。少しでもこの世界を長持ちさせようと奔 走する者。残された時間を愉しみ尽くそうとする者。そして、ただ ぼんやりと世界の終わりを待つ者。 平乃はそのどれでもないな、ということに気付いて佐織は少し面 白くなった。 だからこそ、何としても復活させなければならない。 周囲に焦りを見せつけるようにして、佐織は物憂げに溜息を吐い てみる。 事実、心配事は一つだけではないのだ。 ﹁すいません、隣、よろしいでしょうか﹂ 声を掛けてきたのは高そうなスーツを着こなした、長身の女神だ った。 ﹁どうぞ、お好きに﹂ ﹁ありがとう。こういう店に女一人だと、ね﹂ 女神は微笑みながら軽く会釈をすると、ジンライムを注文した。 綺麗な顔立ちの女神だ。 ベリーショートに刈った金髪が顔立ちに一層の怜悧さを与えてい る。薄めの唇が少し冷たすぎる印象のような気もするが、それも一 258 つの味だろう。 足も長い。少し高めに設えられているこの店のスツールが、この 女神のために用意されていたかのように見える。パンツスーツに身 を包んだモデルのような体型は、女の佐織が少し見とれてしまうほ どだ。 美形の多い神界でも、かなり上位の部類に入るに違いない。 グラスを物憂げに傾けるのも、随分と様になっている。 女神は名をヴィオラと名乗った。 隣に座っているのが噂の渦中にある<戦女神>ヨシナガだとは全 く気付いていない風に、ヴィオラは自分の失恋譚について語ってい る。 言い寄って来た男神が碌でもない奴で、ヴィオラの持っている徳 が目当てだった。そういう種類の、下らない話だ。 同情の余地はない。そう思いながらも、佐織は懇切丁寧にヴィオ ラの話を聞いてやる。 どこにでもよくある話だったが、佐織の耳にはどうにも作り物じ みて響いた。 外見から受ける印象と、話のありきたりさが妙にミスマッチなの だ。 氷の彫刻のような美貌のこの女神が駄目な男神しか愛せないとい うタイプならそれはそれでギャップがあって好ましい。だが、少し 話しただけでもこのヴィオラという女神にはそういう隙のような部 分は一切見えなかった。 話の流れもあまりに整い過ぎていて不気味さすら感じる。所々で 佐織の挟んだ質問にも予め予想していたかのように澱みなく答える のだ。 これまでに会ったことは、ない。 佐織は、会ったことのある人の名前と顔は忘れない。神界でも相 当に交友が広く、あちらこちらのパーティにも顔を出しているが、 今までに会った神と邪神のことはすべて覚えている。 259 そもそも、これだけの美貌の持ち主の女神だ。一度見たら忘れる はずはないだろう。 ﹁ところで、貴女みたいな女神が一人で来るお店じゃないと思うけ ど?﹂ 水を向けながら、佐織はつまみのピスタチオの皿を女神の方に押 し出してやる。 奢られ慣れていないのだろうか。少し躊躇ながら皿に伸ばしたヴ ィオラの指先を、佐織は見るともなしに確認した。 ﹁それはお互いさまじゃない? 貴女だって場末の酒場で普段から 飲んでいる風には見えないわよ﹂ ﹁ま、それもそうね﹂ 適当に相槌を打ちながら、佐織はグラスに口を付けた。 氷が融けて酒の色と混じり合う複雑な模様が、グラスを傾けると 万華鏡のように変化する。それは今の佐織の心の中と同じだった。 罠だ。それだけは、はっきりと分かる。 このタイミングで、佐織の知らない女神、それも<戦女神>を知 りさえしない女神が場末の酒場でたまたま隣に座る。そんなことの 起こる確率は考えるだけでも馬鹿らしい。 誰かがグラスを傾けようとしているのだ。 それが誰なのかは分からない。性質の悪い敵か、もっと性質の悪 い敵か。 思い当たる敵が多過ぎる。佐織はヴィオラに悟られないように自 嘲の籠った溜息をそっと吐いた。確かに周りの神々から見れば取り 急ぎ軍資金が必要に思われるかもしれない。 平乃の属神として気楽に振る舞っていたから忘れていたが、今の 神界とはそういう場所で、<戦女神>ヨシナガとはそういう存在な のだ。綺麗な物だけ見ようと努力し続けなければ、嫌でも汚いもの が目に入ってしまう。 ただ、今の佐織に選択肢はない。 好むと好まざるとに拘らず、変化には乗ってみなければならなか 260 った。 次の一杯を頼むか頼まないか悩んでいる振りをしていると、ヴィ オラはさっそく食いついてきた。 いや、食い付いたのは自分の方か。 ﹁良かったらこの後二人で飲み直さない? 近くに知り合いのやっ ている店があるの。そこのカルパッチョが最高で﹂ ﹁いいわね、御相伴にあずかることにする﹂ 支払いをしようとすると、ヴィオラはそれをやんわりと嗜めた。 ﹁愚痴を聞いて貰ったのは私だから、ね。私に出させて﹂ 佐織はほんの少しだけ申し訳なさそうに笑みを浮かべてみせる。 大仰に喜んでみせるのはさすがにわざとすぎるだろう。罠だと気 付いていると知られているか知られていないか。そんなことはもう 関係ないのかもしれないが、精神衛生上の問題だ。 それにしても、相手の奢りだと知っていれば、もう少し食べれば 良かったかもしれない。そんなことを考えながら、佐織はさっさと 店の階段を上り地上へ出た。 見上げれば満天の星空が広がっているが、それも視線を降ろせば 薄汚れた夜の街の看板の灯りと地続きだ。この無数の煌めきの下、 一人きりで生きていくのは、心が寒い。 平乃を助けるためなら、どんなことでもする。それが、罠に飛び 込むことであっても。 そう心に決めている佐織だが、不安が全くないといえば嘘になる。 これからどうなるのだろうか。 わざと釣られてやったつもりが、俎上の鯉ではつまらない。そん なことを考えながら、佐織は支払いを終えて階段を上って来たヴィ オラの後に続いた。 † † † 261 ヴィオラに仕事を持ちかけられ、応じる佐織。 だが、やはり危惧した通り裏には陰謀が渦巻いていた。 神界を裏切った<悪戯の神>オイレンシュピーゲルが暗躍してい たのだ。 警戒しつつも次第に罠に絡め取られていく佐織。 そこで偶然出会った熊のエドワードは、果たして手助けになるの であろうか。 262 第三章 ダイジェスト版 雨の音が、遠くに聞こえる。 今の時期、夕刻の魔都に降る雨は烈しい。それも石壁を隔ててし まえば微かな雑音としか聞こえなくなる。 雨の音だけではない。獄に繋がれていると、この世に起こるあり とあらゆることから縁遠くなってしまうのだ。そのことを、グラン・ デュ・メーメルは半ば諦念と共に受け容れている。 牢での暮らしも、慣れれば悪いものではない。屋根も、食べる物 も、ある。 隣の房に入れられている元文官は隙間風についてしきりに不平を 漏らしていた。若いのに情けないことだとグランは思う。戦場に身 を置き続けてきた老将にとって、雨露をしのげる屋根があるだけで ありがたいというものだ。 戦いが、生きることの全てだった。 人山羊の王族に生まれたが、所詮は庶流の出だ。生きるためには 手に職を付ける必要があった。グランにとってはそれが戦争だった だけのことだ。 軍学と騎馬、弓術に励んでいたところを、親類である人山羊の魔 王に見出されることがなければ、生き方も大きく変わっていただろ う。 魔王軍騎兵総監、そして大魔王家戦術指南役。 人山羊の魔王の計らいで継承権のない養子として取り上げられた デュ・メーメルは期待に応え、出世街道を進んだ。そういう生涯を 送ることができたのも、養父のお陰だと心の底から感謝している。 ﹁しかし、あそこで見出されなければ、獄に繋がれることもなかっ たかな﹂ 豊かな顎鬚を撫でながら、獄中の老将は独り言つ。 教え子の一人である<廃太子>ドラクゥに内応し、謀反を企てた 263 と疑われ、囚われた。 抗えばそれを理由に殺されることは分かっている。特に反論する こともなく収監された。 だが、今度はそこを叩かれた。 無実であるならば反論するはずだ、という言い分である。 結局、罪状が何かも定まらないまま、グランはこの牢獄に留め置 かれていた。 魔界最大の牢獄で、最も高い尖塔の中である。グランにしてみれ ば、この塔を物見の櫓にすれば魔都での市街戦に大いに役立ちそう だと思うのだが、そのような戯言に耳を傾ける者はいない。 今はただ、無為に時間を過ごすのみだ。せめて涜皮紙と筆でもあ れば何かしらの書き物で暇を紛らわせることもできるのだろうが、 それも許されてはいない。 ふと気付くと、雨の音が弱くなっていた。もうすぐ食事の時間と いうことだ。石壁の中にいると、楽しみは食事くらいになる。 ただ、老将グランには食事以外にも、もう一つだけ特別な楽しみ があった。 食事はいつも通り質素だ。実のほとんど入っていないスープと、 ぼそぼそとしたパン。祝祭日にはここに肉が付く。 これを食べていると、グランは軍営にいた若い時分のことを思い 出す。監獄で出されるものの方が温かいだけ食べやすい。 戦場では、兵に火の通った物を食べさせることができるかどうか は士気に大きく関わる。今の魔軍にはそういうことを気にする将帥 はほとんどいない。例外中の例外が脳裏を過ったが、今のグランは ある意味ではその弟子のせいで牢に繋がっているのだ。 食事を済ませると、日課の体操をする。生きて出獄するとも思え ないが、そうなった時にみっともない姿を見せられないからだ。 一通りの動きを終えたところで、グランの房の前に衛兵が現われ た。 ﹁デュ・メーメル殿、今晩もよろしいかと長官が﹂ 264 ﹁この老体でよろしければ、お相手しよう﹂ 渡り廊下を使い、棟の違う目的地へ向かう。 手に枷の一つさえも嵌められることなく、グランは監獄の長官室 に通される。そこには既に五つの影があった。監獄の長官と副長官、 監獄付邪神官長と司厨長、それに衛兵隊長までもが揃っていた。 豪奢な部屋には暖炉があり、牢獄とは別世界のように温められて いる。 ﹁デュ・メーメル殿、御足労頂いて申し訳ないな﹂ ﹁いえ、無聊を囲っていたところです﹂ ﹁では、早速﹂ 運ばれてきたのは、戦棋の盤だ。八面ある。 監獄の長官たちは暇な任務の合間の暇つぶしとして、戦棋を愛好 する同好会のようなものだった。大魔王戦術指南役として名高いデ ュ・メーメルが収監されたと聞き、是非ともにということで対局を することになったのだ。 それがいつの間にか習慣化し、時折このように呼び出されること になっている。 そのことがグランの密かな楽しみになっていた。 ﹁デュ・メーメル殿は今日も八面指しですか﹂ 副長官が尋ねるのは、盤の数だ。ここにいる面子と戦うだけなら ば、盤の数は五つで良かった。それでも、用意される盤の数は八つ。 残りの三つは、グラン自身がグラン自身と射し合う盤になる。 ﹁ええ、そうさせて貰います﹂ ﹁せめて七面指しにして頂けるよう、我々も努力せねば﹂ 和やかな空気の中で、対局が始まった。 魔都の監獄の管理というのはよほど時間が待っているのだろう。 ここに集まってくる者たちの棋力は素人としてはなかなかのものだ。 だが、所詮はグランの敵ではない。 浅ましいと思いながらも時々苦境に陥ってやる振りをする方が、 疲れる。 265 問題はむしろ、残りの三面にあった。 本当ならこの対局中は、飲酒や望めばその他の嗜好品も目こぼし される。だが、グランにその余裕はない。稀に高価な砂糖菓子を注 文することがあるが、それは集中力を保つためだった。 心気を澄み渡らせ、三つの盤の向こうに敵を見据える。すると今 日も、薄ぼんやりとだが、相手の姿が浮かんできた。 ﹁しかし、デュ・メーメル殿の三つの盤の向こうには誰がおるので しょうなぁ﹂ 一番先に投了した司厨長が、砂糖漬けの桃を頬張りながら話題を 振る。 ﹁古の英雄であろうか。それとも畏れ多くも先の陛下とか。そう思 わんか、衛兵長?﹂ ﹁長官、それはありえます。デュ・メーメル殿は陛下の棋友でもあ ったとか﹂ グランは答えない。ただ、悠然と微笑んでいるだけである。 ここにいる連中に、正解を言い当てられるとも思ってはいない。 対局相手は、弟子だ。 ハツカ、シーナウ、そして、ドラクゥ。 長官たちを適当に往なしながら、グランの脳髄は三者三様の戦術 を採る敵を相手に振り絞られる。 攻めも守りも変幻自在のハツカ。定石を完全に押さえ、どこまで も失点の少ない戦いをするシーナウ。そして、最も読めないのがド ラクゥだった。 対局者たちも、グランのこの奇行を面白がっている。 何某かの金品を賭けている気配さえあった。三人の弟子の癖を再 現することに能力を振り向けての対局だから、グランが破れること もある。そういう楽しみなのだ。 いつまでも続けられる遊びではない。そのことも、グランは理解 していた。 自分の本を巣立って行った三つの才能は、それぞれの置かれた環 266 境で別々の方向に大きく成長しているはずだった。その変化までも 読み通すだけの力は、さしものグランにも備わってはいない。 特に、ドラクゥだった。 ハツカは天才であるが癖があり、シーナウは真面目なだけにどこ かに天井がある。 グランが最も予想し辛いのは、ドラクゥなのだ。 あの不肖の弟子は、人々の期待を敏感に読み取る。そして、それ に応えてしまうのだ。 この魔界において大魔王の血族に生まれ落ちてしまえば、そうせ ざるを得ないのかもしれない。戦術指南役としてグランの見つめて きた宮廷の凄まじさは、グランをして怖気を震うほどのものだった。 そうやって生きてきたドラクゥは、関わる者に応じてその成長の 方向が大きく変化するはずだ。叛乱軍として扱われて落ち延びたあ の弟子に、良い出会いがあったことを望むばかりである。 三面の内、ハツカには敗れ、シーナウからは辛勝を拾った。 ドラクゥの盤では、まだ戦いが続いている。だがその対局はもう、 グラン対ドラクゥではなく、グラン対グランの物になっていた。 変化を、想像し切れなくなったのだ。 ﹁お疲れ様でした、長官﹂ 適当なところで残りの盤も片を付け、グランは長官に頭を下げた。 ﹁いえ、デュ・メーメル殿。頭を上げて下さい。こちらの方こそ楽 しかった。是非またお相手願いたい﹂ ﹁この老体でよければ、いつでも﹂ そう言って笑いながら、グランは手近な所にあった酒瓶を一つ手 に取った。 ﹁申し訳ないが、今日は寒さのせいか神経が昂ぶってしまったよう です。寝酒に頂きたいが、よろしいでしょうか﹂ ﹁どうぞお持ちください。房の守衛には言い含めておきます﹂ ﹁ありがとうございます。それと、次の対局についてですが﹂ ﹁何かご注文が?﹂ 267 ﹁いえ、盤の用意は、八つではなく、七つでよろしいかと思います﹂ ﹁おお、それでは﹂ ﹁ええ、皆さまの腕も上がってきておりますからな﹂ 適当な阿諛を返し、酒瓶を片手にグランは自分の房へ戻った。 次の対局では、もうドラクゥと対峙することはできないのだ。そ う思うと、無性に寂しさを感じるのだ。 寝酒を舐めながら、次に戦うハツカとシーナウの事を考える。 だが、グランにその機会はついに訪れなかった。 翌朝、グランは時ならぬ物音に目を覚ました。 尖塔の下で、誰かが言い争っている気配がある。まさか昨日の寝 酒を咎めに来たわけでもないだろう。そう思いながらも、グランは 仲のいい守衛に酒瓶を鉄格子の隙間から無言で渡した。まだ半分残 っている。 手渡された若手の守衛も無言で頷きを返す。字が読めないという ので、合間を縫って手解きをしてやった守衛だった。叔父が昔、グ ランの軍で馬の引手をしていたらしい。 グランの渡した酒瓶は、守衛が待機する机に無造作に置かれる。 これで、風紀の緩んだ魔軍ではどこにでもある風景が完成した。見 咎められることはないだろう。 騒ぎが段々と近付いてきた。言い争いながら、尖塔の螺旋階段を 誰かが昇って来ているようだ。一方の声にはよく知っている。監獄 の副長官だ。 もう一方の女の声の主はすぐには思い出せない。ただ、どこかで 聞いたことのある声であることだけは、確かだった。 ﹁デュ・メーメル将軍、召喚状です﹂ どうやら副長官は押し切られたようだ。いつの間にか、牢屋の前 に美女が立っている。 ﹁久しいな、曾爺様は息災かね﹂ ﹁お陰様で殺しても死にそうにないほどに﹂ 268 ﹁それは良かった。<白髪姫>殿も元気そうで何より﹂ <白髪姫>ラコイト・デル・アーダ。 特徴的な白に近い銀髪を持つこのトロールとオークのハーフを、 グランはよく知っている。と言っても、関わりが深いのは曾祖父で あるダーモルトの方だ。先代大魔王を支える文武百官の中で、いつ も意見を戦わせてきた間柄だった。 ﹁ありがとうございます、デュ・メーメル将軍。それでは早く牢を 出て下さい﹂ ﹁それは無理な相談だな﹂ グランは物分かりの悪い風を装った。世を拗ねた老いぼれにはよ くある態度だ。 相手の意図がよく分からない。一度はあらぬ罪を着せて投獄した グランを今さら呼び出すのに、あまり気持ちの良い理由があるとは 思い難かった。 大人気ないグランの態度にしかし、ラコイトは表情の一つも変え ない。 ﹁過日、貴方を牢に入れる決定をしたのも、今日、貴方を牢から出 すのも、大魔王府の決定です。一方に応じて一方に応じないのは理 屈が合わないと思いませんか﹂ ﹁理屈の問題から論ずればそうなるだろうな﹂ ﹁では、何が御不満なのですか﹂ 溜息はグランの口から自然と零れた。 不満なのではない。その召喚に応じることができないのだ。 ﹁ここにデュ・メーメル将軍という者がおらんからだよ。将軍職を 解任された憐れなグラン・デュ・メーメルという老いた魔族がいる だけだ﹂ ﹁それでしたらご心配なく。グラン・デュ・メーメル将軍を本日付 で無任所の将軍として復職させる旨の内定と人事命令も同時に発令 されております﹂ ラコイトは書類挟みから二枚目と三枚目の涜皮紙を取り出した。 269 見慣れた書式だ。そこには確かに<皇太子>レニスと<北の覇王> ザーディシュの署名がある。 これはいよいよまずいことに巻き込まれたらしい。誰にでも解決 できるような匪賊討伐の責任者でも押し付けられるのかと思ってい たが、そういう話ではなさそうだ。 ﹁手回しの良いことだな。将軍を解任するのも復職させるのも涜皮 紙一枚で思いのままか﹂ ﹁遅延なき行政手続きの実行は曾祖父の目指したところでもありま した﹂ ﹁私が行かなければならない理由を聞かせて貰うことはできるだろ うか﹂ 時間稼ぎではない。そんなことが無意味なことは百も承知してい る。 だが、このままここを去るには、事態は性急に進み過ぎていた。 ﹁順を追って説明しましょう。人山羊族のグラン・デュ・メーメル 個人、つまり貴方がこの監獄に収監されている法的な根拠はありま せん。よってそのような違法状態は速やかに解消されるべきです﹂ ﹁そうだろうな。私も理由を聞いたことはない﹂ ﹁釈放されると同時に、グラン・デュ・メーメル将軍の名誉回復と、 収監以前に遡っての将軍職への復帰が自動的になされます。命令書 が作成されたのは行政手続き上の必要性があったからです﹂ ﹁なるほど、言いたいことは分かる﹂ 言いたいことは分かるが、到底納得のできる説明でもない。 勝手に獄に落としておきながら、用事があればなかったことにす る。謝罪の言葉もないのは、収監されたという事実が遡って取り消 されたからだろう。全く文官という奴はいつの時代も文書が全能だ と勘違いしているのではないだろうか。 ﹁将軍職に復した貴方には、空位である大魔王の代理を務めておら れる<皇太子>レニス様と、その輔弼をしておられる<北の覇王> ザーディシュ様の指揮権下に入ります﹂ 270 ﹁それについては些か疑義を挟む余地はありそうだがな﹂ ﹁命令権者であるザーディシュ様が署名した命令書がありますので、 デュ・メーメル将軍、貴方には直ちに出頭する義務が生じます﹂ グランには、この美貌の文官が少し危うく思えた。 仕事はできると聞いている。だが、ここまで理詰めで来られると 辟易する者もいるだろう。その部分は、美貌で補っているのかもし れない。 いずれにしろ、曾祖父である<白髯>のダーモルトとは違った型 の文官だった。 ﹁改めて問います。御同行願えますか?﹂ 行きたくはない。 老いぼれに将軍職まで与えるのだ。碌な用事ではないだろう。 押し付けられるのがどのような任務かは知らないが、そこにある のは栄光もない無様な死に場所だけに違いない。だが、生涯を戦に 捧げて来た者としては、このまま牢の中で朽ちていく死に様にも忸 怩たるものがある。 戦いが、生きることの全てだった。 ならばその終幕もまた、戦いの中で引きたい。そう思うのは道理 ではないか。 ﹁分かった。すぐ行こう﹂ 一度家に帰る間も与えられなかった。当然、妻の顔も見ていない。 馬車で大魔城の正門前まで連れて来られると、グランは下馬先に ある小さな詰め所で軍装に着替えさせられた。 詰所の中は、門の前を通る者からよく見える。見せしめのように も、グランには思えた。 ザーディシュらしからぬやり口だ。 策を弄ぶこともある男だが、こういう小さな嫌がらせに喜びを覚 えるような小物ではない。そういう部分では、グランはザーディシ ュを評価していたのだ。今回の一件を、別の者が仕組んでいる可能 性を、グランは疑うようになっていた。 271 大魔城の長い廊下を歩く。グランの周りには、多くの衛兵が同行 していた。 衛兵とはいっても、何かあればグランを取り押さえるためにいる。 向けられている感情は、決して心地良いものではなかった。視線を 少し巡らせただけで、やんわりとした注意を受けたほどだ。これな らば、監獄で扱いの方がまだしも丁重だったと思える。 通された謁見の間で待っていたのは、<北の覇王>だけではなか った。普段はあまり表舞台に姿を見せることのないと聞いていた< 皇太子>レニスの姿もある。そして、レニスの隣にはよく見知った 顔が侍っていた。 ﹁シーナウか﹂ かつての弟子は口元に笑みを浮かべ、グランに慇懃に頭を下げて 見せる。味方として数えることはできそうにない態度だった。 ﹁デュ・メーメル将軍、御前である﹂ ラコイトの叱責が飛ぶ。<皇太子>レニスに対して拝跪の礼をせ よと言いたいのだろう。ここで素直に言うことを聞いてやるのは癪 だが、刃向える状況でもない。 こうなることを予想していたグランは、着替える時に千切って握 り締めていた軍装の飾り釦を一つ、気付かれないように床に落とし た。毛足の長い毛氈は、音も立てずに釦を受け止める。 グランは拝礼をする振りをして、釦を拾うために膝を折った。玉 座とも、列席者とも距離はあるが、気付く者は気付くだろう。だが、 敢えて指摘する無粋な者はいないと信じたかった。 ﹁デュ・メーメル、大儀である﹂ 言葉を発したのは、ザーディシュだった。玉座に物憂げに腰掛け るレニスではない。 グランもザーディシュも老将という意味では同じだ。ただ、向こ うの方が少しだけ歳の若い分、声に張りがある。その事が少しだけ 羨ましい。 ﹁デュ・メーメル将軍、今日呼び出したのは他でもない。将軍に重 272 大な任務を頼まれて欲しいのだ﹂ ﹁お断りします﹂ 口を突いて出たのは、明確な拒絶の言葉だ。意図したものではな かったが、自分自身が考えていたよりも腹に据えかねていたのかも しれない。 ﹁まだ任務の内容も伝えてはいない。それを断るのは武官の重鎮と して魔軍に垂範すべき者の態度とは思えぬが﹂ ﹁私はかつて大魔王家戦術指南役として奉職した身。指南役に就く 者は生涯にわたって大魔王に第一の忠誠を誓うことを請願致します。 故に、大魔王陛下御自身の指示であれば、この老骨に鞭打って槍働 きの一つも務めましょう﹂ ﹁ならば問題はない。これは畏くもレニス殿下の命である。発案者 も、殿下だ﹂ ﹁これは異なことを。聞き違いなされたのかもしれませぬが、私の 申し上げたのは、大魔王陛下の御下命あればということです﹂ ﹁畏れ多くもレニス殿下はその至尊の座に就く御意志を示されてい る。何の問題もないではないか﹂ ﹁それは大変慶ばしいことです。では、社稷をお継ぎあそばされて から、もう一度このグラン・デュ・メーメルにお命じになられるが よかろう﹂ レニスが何事かをザーディシュに耳打ちしている。表情は、読め ない。 ﹁デュ・メーメル将軍。年長者の言には可能な限り耳を傾けたいが、 時は有限だ。こうしている間にも、刻一刻と叛徒は勢力を伸ばしつ つある﹂ ﹁叛徒とは<廃太子>ドラクゥ殿下のことか﹂ ﹁言葉を慎みたまえ、将軍。叛徒に敬称を付けて呼ぶことは、叛意 と取られかねない﹂ ﹁ならばまた監獄に放り込めばよかろう﹂ それも良いとグランは思い始めている。 273 どうせあの監獄で生涯を終えるはずだった身だ。ここで失言の一 つも取り上げられて再び獄に落ちるのも、一つの道だという気がす る。元に戻っただけのことだ。 ﹁前回は明確な証拠もなく、手続き上の問題で収監されることにな ったが、明確な叛意があるとなれば⋮⋮ シーナウ殿、どういう刑 罰が相当するだろうか﹂ シーナウが昔と変わらず秀才らしい態度で恭しく一歩前に出た。 変わったのは、額が少し広くなったことだけだろうか。 ﹁古法に照らせば“九族誅滅”が相当すると思われますが、先代陛 下の御厚情により、現在の法典では“三族誅滅”となりましょう﹂ ﹁“三族誅滅”であるか。弱ったな。将軍の系譜を諳んじているわ けではないが、確か将軍は人山羊の高貴な家の出のはず、三族を悉 く誅滅しては、魔界のためにならないのではないか﹂ ﹁しかし、法は法です。世が乱れている今だからこそ貴顕の皆々様 には襟を正して頂かねばなりますまい﹂ ザーディシュがに大仰に驚いてみせ、シーナウがそれを受ける。 下手な芝居だ。 近年ではほとんど課されることの無くなった三族誅滅刑は、文字 通り咎のある者から数えて三親等にある者の全てを処断する刑罰だ った。その対象の中に王侯が含まれていても厳正に執り行われる。 グランをこの法で脅せば必ず折れることを知り抜いての悪用だと いうことは、よく分かった。入れ知恵をしたのは、或いはシーナウ かもしれない。 処罰されるべき三族の中には、大恩ある人山羊の魔王も含まれて いるのだ。 グラン・デュ・メーメルは覚悟を決めた。 ﹁よろしい、シーナウ殿の言葉ももっともであるな。その重大な任 務とやらを、お聞かせ願おう﹂ 274 † † † 名将グラン・デュ・メーメル、動く。 その配下として出撃を命じられたのは、かつてドラクゥ自身が指 揮した精鋭中の精鋭、<赤の軍>だった。 最精鋭の騎兵部隊の心を掌握したデュ・メーメルは様々な妨害を 受けながらも南へ向かう準備を進める。 しかし、その背後ではドラクゥとデュ・メーメルの共倒れを狙う 皇太子レニスの姿があった。 275 第四章 ダイジェスト版 燃えるような赤だった。庭に植わった紅葉の数は、数千を数える。 ティル・オイレンシュピーゲルは、絶景に目を細めた。この光景 に、美しさを感じ取ったわけではない。オイレンシュピーゲルの故 郷では、落葉は樹々の死として捉えられる。 今、オイレンシュピーゲルの眼前に広がる光景は、彼にとっては 森の墓場だった。 ﹁凄まじい光景だね﹂ 庭を見下ろす東屋の二階にはオイレンシュピーゲルの他に、もう 一つ影がある。この庭の主、クリスティーナ・フォン・マルクント だ。神界に背いた大罪人を前に、マルクントは優雅に茶の香りを楽 しんでいる。 ﹁“秋の間”は、四つの部屋の中でも一番気に入っていますの﹂ ﹁良い趣味をしていると思うよ、クリス。少なくとも、僕はそう思 う﹂ マルクントを、愛称で呼ぶ。そんなことをするのは、天神地祇の 中でもオイレンシュピーゲルだけだ。それは、慣れ親しんだ習慣の 一部だった。呼ばれた方も、拒みはしない。 ﹁貴方と私では、見え方が違っているのでしょうけれど﹂ ﹁そうかもしれないね。それでも、僕はこの庭は素晴らしいと思う﹂ 言葉が途切れた。景色を眺めている風でも、静寂を楽しんでいる 風でもある。 長い、永遠とも思える沈黙の後、先に口を開いたのはオイレンシ ュピーゲルの方だった。 ﹁何故とは聞かないのかい、クリス﹂ ﹁聞いても、意味なんてありはしないことでしょう?﹂ 神界を、裏切る。オイレンシュピーゲルのしたことの意味は、と ても大きい。本来であれば、マルクントは彼を神界大会議に突き出 276 さねばならなかった。そうしなければ、彼女自身が裏切り者を匿っ た協力者として罪に問われることになる。 だが、マルクントはそれをしていない。するつもりも、無かった。 ﹁そうかな。普通は恋人が重大な決断をしたら、理由を尋ねるもの だと思うけど﹂ ﹁元恋人が重大な決断をしても、あまり関心は抱かないものですわ よ、ティル﹂ ﹁つれないね、クリスは﹂ ﹁とっくに終わった話ですもの。それこそ、前世で終わった話﹂ 恋に落ちて愛に変わり、裏切りがあって、死に別れる。そして、 再会。 オイレンシュピーゲルとマルクントの関係は、一言では説明し切 れない波瀾があった。 ﹁でも、僕をまだ家に入れてくれている﹂ ﹁前世で付き合っていた男を売り渡すというのは、少し寝覚めが悪 いかもしれないと思っておりましたが⋮⋮そういう風にからかわれ ると気が変わりそうになりますわね﹂ ﹁ああ、ごめん。謝るよ﹂ ﹁いつも形ばっかり。本心から何かを謝ったことなんて一つもあり はしない癖に﹂ 拗ねたように尖らせた唇をマルクントがティーカップに付ける。 オイレンシュピーゲルはそれを見て、小さく肩を竦めた。悪戯の極 意は誰よりも知り尽くしているオイレンシュピーゲルでも、女神の 心だけは読み通すことができない。 ﹁ところで今日は、クリスに頼み事があって来たんだ﹂ ﹁いやですわ、ティル。貴方の頼み事はもう二度と聞かないことに 決めておりますの。あのことだって、まだ謝って貰っておりません し﹂ ﹁そう言わないで聞いてくれよ。あの事は謝るから﹂ あのことというのは、ヒラノのことだった。 277 これが最後の頼みごとと、最近力を付け始めた<廃太子>ドラク ゥを守護する邪神を紹介するようにオイレンシュピーゲルが頼み込 んだのだ。マルクントは渋々それに応え、何も知らないヒラノを紹 介した。彼に対して持っていた貸しさえ、ここで取り立てている。 その結果、オイレンシュピーゲルは神界を裏切った。手酷い裏切 りと言えばこれほどのものもないだろう。 ﹁貴方のことはもう信じません。唯一神のところへでもどこでも、 好きに行っておしまいなさい﹂ ﹁そう冷たいことを言わないでよ、クリス。ね、ね?﹂ 頬を膨らませてそっぽを向くマルクントの顔を覗き込むようにし て、オイレンシュピーゲルが頼み込む。その熱意に絆されたわけで もないのだろうが、マルクントが薄っすらと片目を開けた。 ﹁で、どういう話ですの?﹂ ﹁聞いてくれるの? さすがクリス!﹂ ﹁貴方が次にどんな悪巧みをしているか興味が湧いただけですわ﹂ ﹁実は、<戦女神>のことなんだ﹂ 名前を出した瞬間、マルクントの肩がぴくりと震える。 ﹁ヨシナガがどうかしましたの?﹂ ﹁さる御方が、あの女神のことを邪魔だと仰っていてね﹂ ﹁⋮⋮唯一神が?﹂ ヨシナガはかつて唯一神に刃向ったことがあった。持ち前のカリ スマで多くの神々を糾合し、一時は唯一神を追いつめたことさえあ る。マルクントも、<戦女神>に協力した神々の内の一柱だった。 だがそれも昔の話だ。今の彼女は、ただの一柱の属神に過ぎない。 唯一神が気に掛ける程の相手ではないはずだ。 ﹁偉い神の考えることなんて僕には分からないよ。ただ、邪魔だと 仰っているらしい﹂ ﹁それであの子をどうするつもりですの?﹂ ﹁どうすると言ったって、彼女はクリスの友達だからね﹂ ﹁友達? 誰が誰と友達ですって?﹂ 278 ﹁おお、怖い、怖い﹂ 声を荒げるマルクントから、オイレンシュピーゲルは軽い身のこ なしで大袈裟に飛び退って見せる。 ﹁ともかくクリス、心配しなくていい。さる御方からは邪魔だとし か言われていないからね。徳を使い果たさせて消滅させるような真 似はしないよ。<戦女神>はヒラノの二の舞にはならない﹂ ﹁当たり前です。そんな無法は誰相手にだって許されるものではあ りませんわ﹂ ﹁その通り。だから僕は随分と穏便な方法で済ませようと苦心した んだ﹂ ﹁貴方は昔から悪戯の準備にだけは余念がありませんでしたものね﹂ ﹁お褒めに与り、光栄至極﹂ おどけてボウアンドスクレイプのお辞儀をするオイレンシュピー ゲルの仕草は、まるで悪戯者の道化師のようだ。 ﹁それで、その穏便な方法というのは何ですの?﹂ ﹁仲が悪いと言いながら随分とヨシナガのことが気にするんだね、 クリスは﹂ ﹁貴方の悪戯の被害がこちらにも及ばないように、事前に知ってお きたいだけです﹂ ﹁ではそういうことにしておこうかな。穏便な方法というのは、ア レだよ﹂ ﹁アレ?﹂ そう言ってオイレンシュピーゲルの指差す方向には、真っ青な空 に白亜の城郭が浮かんでいる。ガーフィンケルの別荘として有名な、 白鳥城だ。事情通のマルクントは、白鳥城が神々を禁錮刑に処すた めの牢獄に作り替えられていることをしっているようだった。 ﹁白鳥城を牢獄に改装するところまで貴方の仕込みではないですわ よね?﹂ ﹁まさか、まさか。とてもいいタイミングでああいう物ができると 小耳に挟んだから、上手く使わせて貰おうと思っただけだよ。<悪 279 戯の神>としては、与えられた条件を最大限利用した悪戯を仕掛け ないといけないからね﹂ ﹁本当かしら。怪しいものですわね﹂ ﹁さすがの僕も、そこまで予測することはできやしないよ﹂ ただ、妙に上手く行き過ぎているとはオイレンシュピーゲル自身 も感じている。一連の流れにあまりにも無駄がないのだ。長い歴史 の中では悪戯よりも悪戯らしい偶然が起こり得ることを、オイレン シュピーゲルは当然知っている。 しかし、それとは違う作為の匂いを、オイレンシュピーゲルは嗅 ぎ取っていた。 ﹁要するにティル、貴方はヨシナガを罠に嵌めて白鳥城に幽閉しよ うというのですわね﹂ ﹁簡単に纏めるとそうなるかな。そうなるように動いているだけで、 そうはならないかもしれないけどね﹂ ﹁“ティル・オイレンシュピーゲルの愉快な悪戯は必ず成功する” でしたかしら﹂ それは<悪戯の神>であるオイレンシュピーゲルに固有の奇蹟だ。 彼が何らかの行為を悪戯として実行する時、その行為は必ず成功す る。別の神の使うより強い奇蹟に打ち消されでもしない限り、それ は絶対だった。 ﹁⋮⋮前世で別れた男の奇蹟をよく覚えているね、クリス﹂ ﹁商売柄、そういうことについては一度覚えれば忘れませんの﹂ ﹁なら、僕が何故クリスにお願いに来たかも分かるよね?﹂ ﹁私がヨシナガを賭け事の対象にしないように、ということでよろ しいのかしら﹂ ﹁その通り﹂ オイレンシュピーゲルに固有の奇蹟があるように、マルクントに もそれがある。 “賭け事における絶対幸運”と名付けられたこの奇蹟は強力だ。ベ ットする掛け金が増えれば増える程、その威力は増していく。莫大 280 な徳さえ積めば、オイレンシュピーゲルの奇蹟を力技で打ち消すこ とも可能だった。 もちろん、絶対的な勝利が約束されているわけではない。ただ、 幸運が賦与されるだけだ。それでも、使い方次第で多くの物事を捻 じ曲げることのできるマルクントの奇蹟は、神界でも大きな脅威と して捉えられている。 ﹁分かりました。今回の件は聞かなかったことに致しますわ﹂ ﹁それはつまり、頼みごとを聞いてくれるってこと?﹂ ﹁違います。私はティル・オイレンシュピーゲルが今日言ったこと を何も聞いていないということです。ヨシナガのことも聞いていな いのなら、彼女に関する賭けなんて思いつくはずがありませんもの﹂ ﹁それを聞いて安心したよ。ヨシナガを裁く公判の結果をクリスが 賭けの対象にするんじゃないかと冷や冷やしていたんだ﹂ ﹁一度約束したからにはそういう無粋な真似はしませんわ。但し、 一つ条件がありますの﹂ ﹁何かな、クリス。今ならどんな条件でも飲むよ。約束する﹂ いつも通り調子の良いことを言うオイレンシュピーゲルに、マル クントは満面の微笑を浮かべた。 ﹁その綺麗な面を、二度と私の前に晒さないで頂けませんこと?﹂ “秋の間”の空気が凍りつく。マルクントの目は、全く笑っていな かった。 ﹁⋮⋮いやだな、クリス。冗談がきついよ﹂ ﹁馴れ馴れしくクリスと愛称で呼ぶのもこの際ですからついでに止 めて頂きたいですわね、この裏切り者。虫唾が走りますわ﹂ ﹁そんな、僕はただ﹂ 未練がましく縋ろうとするオイレンシュピーゲルだったが、マル クントには通じない。 ﹁言ったはずです。私たちのあれこれはもうとっくの昔に終わって おります。早く夢から覚めなさいな﹂ ﹁ごめん、謝るよ、クリスティーナ。許してくれ﹂ 281 ﹁もう聞く耳は持ちません。同郷の誼で待ってあげていますけど、 これ以上ガタガタ言うようなら、ヨシナガより先に貴方が白鳥城の 住み心地を確かめる羽目になりますわよ﹂ ﹁分かった、分かったよ。今日のところは退散する。でもいつか必 ず⋮⋮﹂ ﹁一昨日来やがれ、ですわ!﹂ ﹁僕は諦めないからね、クリスティーナ﹂ 捨て台詞を残して去るオイレンシュピーゲルだったが、その顔は 綻んでいる。茶番に付き合わされて醜態を演じることになったが、 マルクントがヨシナガを助けることはないという言質を手に入れた のだ。 マルクントは賭博の神などやっているからか、義理に厚い。約束 は必ず守るだろう。 最大の脅威が消えた今、ヨシナガを獄に落とすことに抵抗できる 者は、誰もいなくなったのだ。 始めてしまえば、仕事に慣れるのは早かった。 内容は事前に説明された通りに単純で、事前に話のあった神のと ころに会いに行き、品物を適当な値段で買い取る。これに少し利益 分の額を足して、どこかで売るという仕事だ。 売買の仲介もする。その場合は一割から三割の手付けを払って商 品を預かり、買い取り手を探すことになった。実際に物を見ない限 りは、買い手を納得させることは難しいからだ。品物を預けて貰え るかどうかは、信用の問題である。幸い、ヴィオラと佐織は断られ たことがほとんどない。 どちらの場合でも差額がヴィオラの儲けになり、佐織にも幾らか の取り分が渡される契約になっていた。 骨董品の買い付けと言っても、根本的には誰かと話し、信頼を築 くことだ。つまり、佐織の得意分野を活かせる仕事だった。 手伝い始めの数日こそヴィオラの秘書のようなことをしていたが、 282 いつの間にか立場は逆転している。今では佐織が交渉し、ヴィオラ はそれを補佐するような形になっていた。 会った時から感じていたが、ヴィオラには妙なところがある。教 育の行き届いた風なのだが、当たり前のことが全くできなかったり するのだ。佐織の見るところ、それは対人関係に絡む部分に多かっ た。 苦手だというわけではない。二度、三度とやってみる内に、骨を 掴む。単純な経験が不足しているという風にしか思えなかった。 前世は、何なのだろうか。どんな神でも、前世の面影はおぼろげ に分かるものだ。ヴィオラほど片鱗を覗かせない相手は初めてだっ た。 移動中や待ち時間に佐織は自分の前世について語って見せたが、 ヴィオラは曖昧に笑ってはぐらかすことしかしない。いつしかそれ は、触れてはならないこととして二柱の間に暗黙の了解ができ上が っている。 そういう距離感が掴める程度には、親密になったと言ってもいい。 ﹁ヴィオラ、次はどうするの?﹂ 遅めの昼食にサンドイッチを摂りながら佐織が尋ねる。相手のあ る仕事なので、食事は合間に食べられるものが自然と多くなった。 ヴィオラはりんごが苦手なので、今日のデザートのアップルパイは 佐織の総取りになる。 意外なことに骨董の売買という商いは非常に盛況だった。競合す る骨董商もいるが、市場は更に広く、大きい。娯楽を渇望している 暇を持て余した神々にとって、コレクションとその交換というのは 佐織が思ったよりも支持を受けていた。 顧客として会う神には佐織の旧知の神も含まれている。中には別 の知り合いを紹介してくれる者までいた。 取引される骨董のほとんどが、人界や魔界から供え物として献上 された美術品や芸術品の類いだ。だが中には、神界で造られたもの や、世界創生の前からそこにあったとされるものまで含まれている。 283 そういう物は、驚くような額で取引されていたりするのだ。 ヴィオラの手持ち資金はかなりの物だったが、さすがに大物にま ではなかなか手が出せない。ただ、いつかは扱ってみたいとヴィオ ラは佐織に言い続けていた。 今日は午前中に一件、大口の売り込みが成功している。古い壺の コレクターで、該当する手持ちの美品をほとんど買い取ってくれる という条件で成約していた。運転資金には、かなりの余裕がある。 手帳を覗き込んでいたヴィオラが、意を決したように呟く。 ﹁サオリ、アレを買い取りに行くわよ﹂ ヴィオラと佐織が目を付けていたのは、一振りの剣だった。 銘を、<滅神剣>という。元は二振りで一対となる夫婦剣だった が、片割れである<破神剣>はいつの頃からか行方知れずになって いた。 両方揃えば天文学的な値段も付くのだろうが、一方だけではその 価値は大きく減じる。 しかも持ち主の神は近日中にアガリを迎えるつもりで、多少の値 引き交渉には応じてくれそうな気配があった。 この剣なら、今の手持ちの資金でギリギリ手付けを支払える。販 売する交渉権さえ手に入れてしまえば、売り切る自信はあった。欲 しがりそうな神の目星も付けてある。 神界創生の遺産を不完全な形とはいえ扱うことができれば、骨董 商としてのヴィオラの名にも幾らか箔が付くはずだった。 上手く行けばその成功報酬の分け前で平乃凡太の復活のための徳 もかなり貯まることになる。 目当ての剣を所有している神は、神界の外れに小さな屋敷を構え ていた。 主である黒髪眼鏡の女神は、高校で図書委員でもしている風な容 貌だ。もちろん神界では相手の歳を外見から推し量ることはできな いが、佐織は何となく親しみを感じた。 屋敷の中は綺麗に整頓されている。アガリを控えているというの 284 は本当なのだろう。さしあたって必要な身の回りの物以外、全て処 分を終えたという雰囲気だった。 ヴィオラが剣の査定をする間、佐織は、縁側で茶を一杯御馳走さ れることになった。 ﹁この度は仲介を任せて頂いてありがとうございます﹂ ﹁どうせ次の世には持って行けないものですから﹂ 微苦笑を浮かべ、女神は茶を啜る。アガリを迎える神に特有の、 生きることに倦んだ表情の影は見えない。そのことが、佐織には少 し不思議に思える。 ﹁どうしてアガリを考えられたんですか﹂ 佐織の問いに、女神は綺麗な人指し指を細い顎に当て、少し考え 込んだ。 ﹁あの剣を、<滅神剣>を保管するのに疲れたからかも﹂ ﹁保管に、疲れる? というのは?﹂ ﹁あの剣は、特別ですから﹂ 神界創生の時代から存在する<滅神剣>には、どこにでもある普 通の剣だ。 美術品としては美しいが、武器として特別な付加価値があるわけ ではない。神界には奇蹟を起こすことのできる武器がいくつもある。 それに比べれば、威力という点では見劣りした。骨董品の市場でも、 ただ珍しさだけで値が付いている部分がある。佐織が知っているの は、そこまでだった。 ﹁<滅神剣>、そして対になる<破神剣>は、ただの武器ではあり ません。と言っても、神が振るっても特に何の意味もないのです。 但し、一つだけ恐るべき効果が隠されています﹂ ﹁その効果というのは?﹂ ﹁人や魔族が使えば、神を傷付けることのできる、神殺しの剣とな るのです﹂ ﹁神殺しの剣、ですか﹂ そう呼ばれる武器があることは、佐織も知識として持っていた。 285 知っているというだけではない。唯一神との戦争の時代、積極的 に探しさえしている。 それでも一切の手掛かりさえ掴めなかったものが、今になって目 の前に現われるというのは、奇縁としか言いようがない。 ﹁この剣の面白いのは、天神地祇が振るっても何の意味もないとい うところです。定命の者、つまりは人族や魔族が使わなければ、そ の効果を発揮しません﹂ ﹁以前、理由があってこの剣を探している時は、そういう制約につ いてさえ知ることができませんでした﹂ ﹁天神地祇や邪神は徳を使い果たさない限りは無謬のもの。そう信 じたい神々にとって、下界の者が自分たちを傷付け得るという事実 はあまり好ましくなかったのでしょうね﹂ 徳を使い果たすと聞いて、佐織は平乃を思う。早く、復活させな ければならない。 神殺しの<滅神剣>には興味があるが、今はただの商品に過ぎな いのだ。売って、利益を得ることだけを考えるべきだった。 ﹁仲介させて頂く相手は、信用のできる方をしっかり選ばせて頂き ます﹂ 佐織は、女神の目を見て言う。この仕事に携わってまだそれほど 経ってはいないが、根は真面目なのだ。職業倫理のようなものは心 得ていた。 ﹁そうして頂けると助かります。片割れの<破神剣>は行方不明で すけれど、神界に対する脅威の数が増えることは望ましくありませ んから﹂ ﹁承りました﹂ もし流出してしまっても、実際にはあまり脅威にならないのでは ないか。答えながらも心のどこかで佐織はそう思っている。 神と人の距離は、ますます遠くなっていた。数が減っているだけ でなく、地上に姿を現すことが、ほとんどない。下界の者が斬ろう としても、斬る相手がいなかった。 286 神界大会議ではしばしば顕現禁止の布告を出していたが、それは 禁止しても顕現をする天神地祇が後を絶たなかったからだ。いつの 間にかそれが、注意から規範になった。そうなると、地上に姿を見 せる神はほとんどいなくなってしまった。 信仰が弱くなったのではなく、距離が離れたのだ。そう思うこと が、よくある。 他の神からの誹謗中傷の的にさせないため、平乃には顕現しない ように強く言ってきた。 言いながら、おかしなことを言っているとは自分でも分かってい たのだ。だから自然と語調は強くなり、結果として平乃を困惑させ ることになった。 どれだけ注意をしても平乃が顕現を止めなかったことを、佐織は 嬉しく思っている。 平乃は、どうあるべきかを肌で感じ取って、ああしていた。その 辿り着いた答えが、自分の出したものと同じだったことに、佐織は たまらない喜びを感じているのだ。 信者が神を信じ、それに応じて御利益がある。そういう形は、本 当の信仰ではない。それは商売のような在り方だ。簡便で効率的で あっても、真髄ではない。 神と信者の関係の本質は、関わりの強さにある。佐織はそう信じ ていた。その思いは、自分を信じる民が一人もいなくなってしまっ てから、ますます強くなっている。 竹林を抜ける風が濡れ縁に座る二柱の女神の頬を撫でて行った。 笹の葉の擦れる音以外、何も聞こえない。 不意に佐織の胸に、言いようのない不安が湧き上がってきた。ね っとりとした泥の奥から、ガスの粒がぷつぷつと浮かんでくるよう な、小さな違和感だ。 それは、眼鏡の女神も感じたようだった。 ﹁⋮⋮お連れの方、遅いですね﹂ ﹁丁寧に拝見させて頂いているのだと、思います﹂ 287 ﹁<滅神剣>の拵えは確かに立派で、魅入られそうなものですが、 美しい剣を見慣れているはずの骨董商の方からすると﹂ 不安の泥から湧く粒が次第に大きくなり、泡になる。佐織は大き くかぶりを振った。 いつから自分は、ヴィオラを信じてしまっていたのだろう。 ﹁ヨシナガさん、私、少し見てきます﹂ ﹁ご一緒します﹂ 立ち上がろうとした佐織を、女神は手でそっと制した。 ﹁いえ、貴女はここでお待ちになって下さい﹂ 静かだが、有無を言わさぬ気迫の籠った口調だ。 ヴィオラが<滅神剣>を鑑定している小部屋は、濡れ縁からほん の少しの距離しか離れていない。念のため、女神に仕えている属神 の下男が一緒に控えていた。 佐織は、唇を強く噛みしめて天を仰いだ。さっきまでは薄曇りだ った空が、薄墨を流したような色になっている。降るだろう。そう 思った時には、見えるか見えないかというほどの小さな雨粒が、竹 林に降り始めていた。 油断は、どこで切れたのだろう。エドワードにコースターを託し た時、佐織はまだヴィオラを強く警戒していたはずだ。彼女の見せ た、ちょっとしたどんくささや手際の悪さも、こちらを油断させる 演技だったのではないかという疑念が、心の中に広がっていく。 罠に、嵌められたのだ。仕掛けるなら、もっと直接的な方法だと 思っていた。 女神の上げる悲鳴を、佐織はどこか遠くの物のように聞いている。 ヴィオラは、消えているだろう。<滅神剣>を持ったまま。 雨足が、強くなる。雨粒が竹の葉を叩く音が、奇妙に美しく耳に 響いた。 動くと決めると、ギレノールは早かった。 信頼のできる属神に声を掛け、<戦女神>ヨシナガを監視してい 288 る連中を調べるように手を回す。金の撒き方は、徹底していた。必 要経費もたっぷりと先渡ししてあるので、何かに巻き込まれている のなら数日で分かるはずだという。 得意なことは、得意な者に任せる。 調査や尾行など、ギレノール自身にできるとは思わない。それに、 趣味でも無かった。 最終的に手遅れになりさえしなければいいのだ。どれだけ悔やん でも、時間だけは徳で買えない。打てる手は、全て打つ。それがギ レノールのやり方だ。 それに、ギレノールには別にやるべきこともあった。 ﹁本当に良いんですか?﹂ ﹁一千万なら、出せない額じゃない。友達のためならね﹂ 神界大図書館に借りた小会議室で、ギレノールはエドワードと落 ち合っていた。 ヒラノを復活させる。それが急務だとギレノールは思っていた。 長く身体が活動停止状態にあると、神はアガリを迎えてしまうこ とがある。徳が足りないからそうなるのではなく、復活の希望を失 うからそうなるのだ。少なくとも、ギレノールはそう考えていた。 あのヒラノはそうそう簡単に諦めない。そう信じていても、早く 復活させるべきだという点に変わりはなかった。 活動停止状態の神が、どのように外部を知覚しているのかはギレ ノールにも全く分からない。完全に外界からの情報が遮断された、 魂の牢獄のような状況に置かれている可能性も十分に考えられた。 如何に邪神の精神構造が転生前とは異なるとは言え、あまり長く そういう状態に放置されていることは望ましくない。 ﹁ヨシナガさんはなんで最初からギレノールさんに頼まなかったん ですかね﹂ ﹁気持ちは分かるよ。自分が振った相手に、自分の好きな相手を助 ける手伝いをさせようってほど、<戦女神>は厚顔無恥じゃないさ。 頼られなかったのは少し寂しいけどね﹂ 289 ﹁そういうものですか﹂ ﹁そういうものだよ。男女の仲は難しいものさ。さ、そんなことよ りも﹂ ギレノールは書類鞄から羊皮紙の束と何冊かの本を取り出した。 紙は神界でも作られているが、下界から献上されるのは基本的に 羊皮や牛皮などを使った涜皮紙になる。値段も、却って羊皮紙の方 が安かった。 ﹁一千万、より正確には一一六〇万カルマの徳をそのまま流し込ん でも、邪神ヒラノは復活しないということが明らかになった﹂ ﹁なにか工夫がいるということですか﹂ ﹁そういうことだ、エドワード。察しが良いな﹂ ﹃天神地祇の長期間活動停止状態からの再起動施療と魂魄への影 響/奇蹟発動プロセスの再始動に関する観察﹄という長ったらしい 書名の本から目当てのページを開く。そこに書かれていることを読 み下すのは、門外漢のギレノールには少し骨が折れたが、知り合い の神医に幾らか包んで解説して貰い、内容は概ね理解出来た。 支払うべき徳について、ギレノールは随分と楽観的な心持ちにな っている。 遥か昔、と言っても数千年程前に東方へ去った青い肌をしたエル フの一氏族からの信仰が、復活していた。原因は思い当たらない。 これほど長く祭礼が途絶えていたのが再び正しい形で行われるよう になった例を、ギレノールは他に知らなかった。恐らく前例のない ことだろう。 それでも、徳は徳として懐に入って来る。いずれ、何があったの かを確かめに行かねばならないと思っていた。 ﹁天神地祇、それに邪神の身体というのは一種の奇蹟だ。物質とい うよりは、現象に近い。本当はもっと根源的なものだが。つまり奇 蹟を発動させ続けることで、魂と魄を守り、活動ができるようにな っていると考えてくれればいい。それが一度停止してしまうと、徳 を流し込むだけではどうしようもない﹂ 290 ﹁よく分かりません﹂ ﹁そうだな。上手い喩えはないものか。車のエンジンにガソリンを 流し込むだけでは動かないようなものと言えばいいか⋮⋮車のキー が必要になるんだ。もう一度動くためにはね﹂ ﹁よく分かりません﹂ く、る、ま、のキーと大きな字でメモを取りながらエドワードが 答える。十一世紀初頭にスコットランドで天寿を全うしたヨーロッ パヒグマに対する説明としては、あまり出来の良いものではなかっ たらしい。 ﹁要するには冬眠ボケした熊を起こすためには腹いっぱいにするだ けじゃなく、魔法の呪文を唱えてやらねばならないってことだ。問 題はその蹴り方にコツがあるということだな﹂ ﹁お姫様のキスでは駄目なんですか﹂ ﹁そのお姫様は現在監視されているというからね。取り急ぎ別の方 法を考える必要がある。必要があるんだが﹂ ギレノールの開いたページは、乱暴に破り取られていた。目次の 内容から察するに、このページには活動停止に陥った神の復活に関 わる手掛かりが書かれていたはずだが、今は見る影もない。わずか に残された部分からでは、内容を類推することは不可能だった。 ﹁ひどい⋮⋮誰がこんなことを﹂ ﹁手回しの良いことだ。大図書館だけでなく、分館に収蔵されてい る物も含めて、関係するものは全て破り取られていた﹂ ﹁なんでそんな酷いことをするんでしょうか﹂ ﹁破られた跡はどれも比較的新しいものばかりだった。誰かよほど あの邪神を復活させたくない奴がいるんだろうな﹂ ﹁そんなに恨まれるような邪神だとは思わないんですけど﹂ ﹁賭け碁で毟り取ったとしても、ここまで恨まれることはないだろ うからな﹂ 苦笑しながら、ギレノールは別のことを考えている。 これだけの動きは、個神や小さな集団では難しい。<戦女神>の 291 一件も含めて、相当大きな敵が動いているのではないか。判断に足 る材料はなかったが、嫌な予感がする。 ﹁念の入ったことに、焼き捨てられていた資料もあるそうだ。書物 を再生させられるような奇蹟を扱える神も探してみたが、望み薄だ な。こういうことをする奴こそ、白鳥城に放り込まねばならんよ﹂ ﹁家に持ってる神さまはいませんかね?﹂ ﹁どうだろうな。活動停止自体があまり症例のないことだ。ヒラノ の罹ったという貧徳ほどではないにせよ、ね。そういう稀覯書を所 蔵しているコレクターは知り合いにいないな﹂ ﹁じゃあ、一体どうすればヒラノさんは⋮⋮﹂ 悲嘆に暮れるエドワードの肩にギレノールは手を置いた。 ﹁実は方法がないわけじゃない﹂ ﹁本当ですか?﹂ ﹁ああ、一一六〇万カルマをそのままゆっくりと流し込んでも、ヒ ラノは目覚めない。空っぽの燃料タンクが満たされるだけだ。腹が 膨れただけということだ﹂ ﹁その状態で、魔法の呪文、ですよね﹂ ﹁そう。だが、その魔法の呪文が分からない。ならば多少強引な方 法を使うしかない﹂ ﹁強引な方法?﹂ ﹁なかなか目を覚まさない熊を起こすには、尻を蹴り上げるしかな いってことさ﹂ 奇蹟を使い、強制的かつ瞬間的にヒラノの肉体に大量の徳を一気 に注ぎ込む。 エンジンキーが無いのなら、無理矢理シリンダーを動かしてしま え。そういう種類の乱暴極まりないやり方だが、これならばギレノ ールにも成算があった。 天神地祇ではなく、建物に施す結界を再起動させる方法に近い。 この方法が使えるならば、やり方はいくらでも思いつく。結界につ いては、ギレノールは神界でも最高峰のプロフェッショナルだった。 292 ﹁但しこの方法には、一つだけ大きな問題がある﹂ ﹁何ですか、ギレノールさん﹂ ﹁結界を作動させるために、更に莫大な徳が必要になる。ざっと計 算して、一億以上だ﹂ ﹁一億⋮⋮そんな⋮⋮﹂ 一億ともなると、並の人間が一生かかって蓄える徳のおおよそ半 分に相当する額だ。さすがのギレノールも簡単に用立てられる額で はない。ただ、時間的な猶予もあまりない。長期間の活動停止がど のような影響を与えるのか、誰も知らないからだ。 その時、小会議室の扉を誰かが開いた。 ギレノールとエドワー ドが振り返る。そこには銀髪縦ロールの少女神が立っていた。 ﹁その一億、出して上げてもよろしくてよ﹂ ﹁<賭博神>か⋮⋮﹂ ﹁お久しぶりですわね、ギレノール﹂ ギレノールとマルクントは旧知の間柄だ。と言っても、良好な関 係だったわけではない。暫く交流がなかったのも、随分前に喧嘩別 れしてほとんど絶縁と言っても良い状態になっていたからだ。 ﹁久しいな。今日は何の用だ?﹂ ﹁ええ、邪神ヒラノを助けるための一億カルマ、私が立て替えよう かと思いまして﹂ ﹁盗み聞きとは良い趣味をしているじゃないか﹂ ﹁そういうギレノールもあちらこちらで属神を使って探偵ごっこを させているみたいですわね。あまり成果は上がっていらっしゃらな いようですけど。よろしければ私のお抱えを使われます?﹂ ﹁結構だ。それにしてもどういう風の吹き回しだ。利子でもたっぷ り取り立てるつもりなら生憎だな。我が友ヒラノは五億だか六億だ かの借金を既に背負っている。多重債務者にしたところで<賭博神 >のところにまで支払う余裕はないぞ﹂ ﹁それくらいのことはもう調べていますわ﹂ ﹁ならば、どうして?﹂ 293 問い掛けにマルクントは複雑な表情を浮かべた。 ﹁邪神ヒラノには、借りがありますの﹂ ﹁<賭博神>フォン・マルクントに貸しがあるとは、我が友ながら 豪儀なことだ﹂ あまり俗世間に関心のないギレノールも、邪神ヒラノが神界大会 議で査問にかけられそうになったというニュースは追っていた。そ の発端となったのが、マルクントがオイレンシュピーゲルをヒラノ に紹介したことだということも、当然知っている。 ﹁それと、もう一つ。ちょっとした個神的な事情もありますし﹂ ﹁⋮⋮誰かへの意趣返しか﹂ ﹁さぁ、どうですかしら。とにかく、あの邪神を復活させるなら無 理矢理にでも急いだ方が良さそうですわよ﹂ ﹁<賭博神>に言われるまでもないさ。徳さえあればすぐにでも取 り掛かるつもりだ。だが、何かあるのか﹂ ﹁<戦女神>ヨシナガが、逮捕されました﹂ ﹁⋮⋮逮捕、だと?﹂ ﹁なんでヨシナガさんが逮捕されるんですか?﹂ 蚊帳の外に置かれていたエドワードも、思わず悲しそうな鳴き声 を上げた。 ﹁容疑は窃盗。共犯者は逃亡しているみたいですわね﹂ ﹁<戦女神>がそんなことをするはずがない!﹂ ﹁そんなことは私が一番よく知っています。誰かに嵌められたんで しょうね﹂ ﹁それで今、<戦女神>は?﹂ ﹁まだ、神界大会議が裁いておりませんけれど⋮⋮白鳥城に運ばれ るのに、あまり猶予はなさそうですわね﹂ ﹁⋮⋮エドワード、すぐに取り掛かる。ヒラノの肉体はどこだ!﹂ ﹁地上の、アルナハの邪神殿です﹂ ﹁私も同行します﹂ ﹁分かった。今は休戦だ﹂ 294 マルクントが頷きを返した。 魔界へ向けて飛ぶ。結界と儀式の手順は、頭の中で組み立てるし かない。逸る気持ちを何とか落ち着かせようとしながら、ギレノー ルは飛ぶ速さを増した。 † † † 白鳥城に囚われた佐織には、いつの間にかあらぬ嫌疑がかけられ ていた。 このままでは二〇〇年近く収監されることになってしまう。 一方、眠り続けるヒラノを助けるためにギレノールたちも動きは じめていた。 莫大な量のカルマを直接ヒラノに注ぎこむギレノール。 しかし、それでもヒラノは蘇らない。 もうだめかと思ったその時、エリィナはある決断をする。 295 第五章 ダイジェスト版 神界の大通りをヨハンは早足で歩いていた。走っているようにも 見えるだろう。 時折、行き違う神と肩がぶつかりそうになるが、気にも留めなか った。 事態は想像した以上に悪い。事務所に使っている三階建てのビル に戻り、狭い階段を駆け上る。ノックはせず、扉を開けた。 ﹁やぁヨハン。どうしたんだい、随分早いお戻りじゃないか﹂ 事務所の中にはオイレンシュピーゲルしかいない。間借りしてい るくせに、ここの主のように鷹揚な態度だった。そのオイレンシュ ピーゲルが、買い置きの茶菓子を頬張りながら涼しげな顔で荷物を 纏めている。大きなトランクだ。まるで長い旅行にでも使うような 大きさだった。 ﹁どういうことだ、ティル!﹂ ﹁何をそんなに怒っているんだい、ヨハン。この僕が言うのもおか しな気がするけど、苛々はあまり身体に良くないというよ﹂ 呑気な顔のオイレンシュピーゲルに、ヨハンは部下からの報告書 を投げつける。そこには昨晩脱獄を成功させた<戦女神>ヨシナガ についての第一報が記されていた。 ﹁ああ、脱獄したんだね﹂ ﹁脱獄したんだね、じゃないぞ、ティル。どうするんだ。一度逃げ 出した<戦女神>をもう一度獄に落とすなんて、至難の業だ。どう せどこかに逃げてしまっている﹂ ﹁もう一度捕まえるっていうのは骨が折れそうだね。僕ならあまり 引き受けたい仕事じゃないなぁ﹂ ﹁何を他人事みたいに言っているんだ! それもこれもティル、お 前の奇蹟が通用しなかったからじゃないか!﹂ ティル・オイレンシュピーゲルの<悪戯の神>としての奇蹟は、 296 悪戯の成功だ。どのような形であれ、奇蹟が発動していれば悪戯は 達成される。少なくともそういうふれこみにはなっていた。それが 何故、ヨシナガは脱獄できたのか。 ﹁何を言っているかよく分からないな、ヨハン。僕の奇蹟は多分成 功していると思うよ﹂ ﹁ならどうしてヨシナガは脱獄できた?﹂ ﹁ヨハン、ちょっと頭を働かせてくれよ。ヨシナガを白鳥城に禁錮 するなんて詰まらないことに僕が奇蹟を使うと思う?﹂ ﹁何だと?﹂ ﹁今、僕が奇蹟を使っているのは別のことに対してだよ。<戦女神 >を獄につなぐことができたのはヨハン、純粋に君と君の育てた組 織の功績だ。それは誇っていいと思うな﹂ 組織。そう、組織だ。<初神者喰い>ヨハンにとって、自ら手塩 にかけて育てた組織は、何物にも代えがたい値打ちのあるものにな っていた。 これだけの規模で深く広く神界に根を張っている組織は他にない。 いつの間にか組織は、ヨハンにとって子供のようなものになってい る。 前世では、早くに子供を亡くした。流行り病だ。天災のようなも のとして諦めるしかなかった。それが、心の奥底では諦めきれてい なかったのだろう。燠のように胸の中で燻っていた思いは、年を経 るごとに強くなっていった。転生して、今度こそはと思ったのだ。 しかし、神は子を成せない。そういう決まりが神界には存在した。 そのことを知ってからは組織作りに励んだ。分かりやすい代償行為 だった。 その組織が漸く軌道に乗って来たのだ。それが、今回の<戦女神 >の脱獄でどうなってしまうのか。噛み締めた奥歯が軋む。唯一神 の心証次第では、組織の未来は閉ざされることになるかもしれない。 たった一回の失敗だが、失敗してはならない一回だった。 いや、失敗したのは組織ではない。間抜けな白鳥城の連中だ。だ 297 が、そのことを大天使たちが理解してくれるという保証はどこにも なかった。 ﹁そんなことよりもヨハン、君も早く荷造りをした方がいいと思う よ﹂ ﹁荷造り? 悪いがオレは暇なお前さんと違ってやることが山のよ うにあるんだ。物見遊山に出掛けている暇なんぞないよ﹂ ﹁そうかな。暇ならいくらでもあると思うけど﹂ オイレンシュピーゲルが口元だけで笑った。 そのおぞましい表情に、背筋を嫌な汗が伝う。黒い澱のような不 安が、肚の底に溜まっていくのが分かった。悪戯は<戦女神>に仕 向けられたものではなかった。ならば一体、誰に向かって奇蹟は使 われているというのか。 ﹁ヨハン、この間行ったドイツ料理店を覚えているかい?﹂ ﹁ああ、お前とヴィオラとで行ったあの店か。それがどうかしたか﹂ ﹁⋮⋮店主がね、あの日のことを神界大会議に密告したんだ﹂ オイレンシュピーゲルが、トランクの蓋を閉める。荷物が多過ぎ るのか、上手く閉まらないようだ。上に乗り、力を込める。それで も、鍵はかからない。 ﹁まさか。だってあそこはお前の馴染みの店だと言うから﹂ ﹁馴染みの店だよ。これまでちゃんと使う度に口止め料も払ってい たしね﹂ ﹁なら急にどうして⋮⋮﹂ ﹁ヴィオラだよ。神界大会議は<戦女神>ヨシナガの共犯者として あの女神を指名手配している。唯一神側に寝返った僕よりも、彼女 の方が目立ったみたいだね﹂ 目の前が真っ暗になる。 神界を裏切ったオイレンシュピーゲルと、指名手配犯のヴィオラ。 その二柱と一緒に会食をしていた自分だけが疑われないわけがない。 叩けば埃の出る身体だ。それだけに、これまでは十分な注意を払っ て生活してきた。何故今回に限って、こんな初歩的なミスをしてし 298 まったのか。 ﹁まさかティル、お前﹂ ﹁はい、御明察。僕が悪戯を仕掛けていたのは<戦女神>ヨシナガ じゃなくて、ヨハン、君の方だったんだよ﹂ ﹁どういうことだ⋮⋮どういうことなんだ?﹂ ﹁<戦女神>ヨシナガを罠に嵌めるというのは確かに僕の受けた仕 事だけど、指示を受けたのは社会的な信用を失墜させる所までだか らね。それについては完全に果たせたと思う﹂ ﹁そんなことを聞いているんじゃない!﹂ ﹁まぁ、そう怒らないで。ちゃんと順を追って説明するからさ。僕 は仕事と悪戯は分けて考えるタイプなんだ。美意識としてね。昔は 命じられた仕事を如何にしてぶち壊しにしてやろうかって考えてた んだけど、最近はそれも飽きちゃった。だからヨハン、君に目を付 けたんだ﹂ ﹁ティル、お前が何を言っているのかさっぱり分からない。何故そ こでオレの名前が出るんだ。関係ないじゃないか﹂ ﹁だってヨハン、君は日々を懸命に生きてるんだもん。そういうキ ラキラしたものって、壊したくならない?﹂ 思わず拳を握りしめた。目の前の少年神を、殴りたい。泣き喚い て許しを乞うまで、殴り続けることができたら、どれだけ幸せだろ う。だが、そんなことをしても何もならないことに、ヨハンは気付 きはじめていた。 ﹁僕はねヨハン、君の失脚を失脚させるために奇蹟を使っていたん だ。もちろん、君の組織を壊滅させることも含めてね﹂ ﹁どうしてそんなことを⋮⋮﹂ 考えてみれば思い当たる節がある。重大な決断をする時に何故か 注意力が散漫になったり、慎重になるべきところで不思議と自信が 湧いて来たり、普段なら有り得ないようなことがヨハンの中で起こ っていた。 まともな精神状態なら、ヴィオラなどという素人を重要な任務に 299 就けるはずはなかったのだ。打ち合わせも、信用のおける場所でし かやらなかったはずだ。それもこれも、オイレンシュピーゲルの奇 蹟の効果だったということだろう。 ﹁ま、運が悪かったと思って諦めてよ。僕は随分と楽しめたんだけ ど。本当のところは、僕の目的は邪神ヒラノの復活だったんだ。復 讐するためにね。そのために、マルクントを焚きつけることまでし たんだから、随分と手間がかかったよ﹂ ﹁ティル、いやオイレンシュピーゲル、貴様という奴は!﹂ ﹁怒らない、怒らない。形ある物はね、いつかは必ず壊れるんだ。 組織だって同じことさ﹂ ﹁そうだ、組織だ。唯一神側の組織で、神界にここまでの規模を持 っている組織は無いぞ。それを失う責任をお前は取れるのか?﹂ 末端の情報屋も含めれば三〇〇柱を数える組織だ。唯一神がそれ を手放すとは考えられない。何らかの救済があると思ってもいいの ではないか。いや、そのはずだ。ヨハンの頭の中で激しく計算が行 われる。まだ助かる道はある。そのはずだった。 ﹁ヨハン、まさにその一言が、君の無能の証明なんだよ﹂ ﹁何だと?﹂ ﹁君の組織の構成員は確か三百十七柱だったっけ? 確かにちょっ とした規模だと思うけど、神界全体を監視したり、何か大規模な工 作をしたりするには、ちょっと小さいと思わない?﹂ ﹁それでも最大は最大だ。規模はこれからもっと大きくなる﹂ ﹁違うんだ、ヨハン。君は全く分かっていない。神界には、もっと 大きな組織があるんだ﹂ ﹁⋮⋮えっ﹂ オイレンシュピーゲルが何を言っているのか、一瞬理解できなか った。いや、信じることができなかったのだ。信じるわけにはいか なかった。 神界に、ヨハンの物よりも大きな組織がある。もしそんなものが あったとして、ヨハンがその事に気付かなかった理由は一つしかな 300 い。あちらの方が、上手なのだ。狡猾で、賢明で、強力な組織。そ んなものが神界に存在するのなら、ヨハンのやっていたことはとん だ茶番だということになる。 ﹁考えてもみて欲しいね。どうしてこのタイミングで白鳥城のよう な物ができたのか﹂ ﹁それは、<黒髪姫>が⋮⋮﹂ ﹁切っ掛けに過ぎないよ、ヨハン。それだけで腰の重い神界大会議 が本当に動くと思っているの?﹂ オイレンシュピーゲルの言っていることは本当なのだろうか。ヨ ハンは自問した。もう一つの組織は、大会議の意思すら思いのまま だと言っている風に聞こえる。そこまでではないにしろ、何かしら の影響を与えることはできる。そういう組織の存在を考えた方が、 確かにしっくりくることは多かった。単なる誇大妄想じみた嘘には 聞こえない。 ヨハンは、天井を仰いだ。 これまでに積み上げてきたものが、一瞬にして崩れていく。組織 は持たないだろう。三〇〇を纏めるのは、長であるヨハンだけの仕 事だった。自身がいなくなった組織がどうなるかは、想像するまで もない。それは、胸に穴の開くような感覚だった。 ﹁分かった、オレも逃げる﹂ ﹁逃げるつもりなら、さっさとした方がいいよ。ヨシナガの脱獄で、 大会議も気が立っているみたいだからさ﹂ ﹁ああ、なるべく早く逃げることにするよ﹂ 裏口から逃げ出すオイレンシュピーゲルの背中を、ヨハンは見送 った。 不思議と、怒りは消えている。失ったものが、大き過ぎたのかも しれない。 逃げる当てもないまま、ヨハンはのろのろと緩慢な動きで証拠の 隠滅を始めた。どう考えても間に合わない。このままここにいれば 捕まってしまう。そうとわかっていても、身体が動かないのだ。 301 そこに、逃げたはずのオイレンシュピーゲルがひょっこりと顔を 出した。 ﹁うっかり約束を忘れてたよ、ヨハン﹂ ﹁約束? 何か約束したか?﹂ ﹁ああ、忘れてた? それなら無理して戻ることもなかったかな﹂ ﹁勿体ぶるなよ。何の約束だ﹂ ﹁ヴィオラの正体だよ。分かったら知らせるっていう約束だった﹂ 変なところだけ律儀な奴だとヨハンは思った。そんなことはもう、 どうでもいい。 ヴィオラというあの女神が今どこで何をしているのかにも、全く 興味が湧かなかった。 ﹁ま、聞くだけ聞いておくよ。ティル。あのヴィオラっていうのは、 一体どこのどいつだったんだい?﹂ ﹁隠し子だよ﹂ ﹁隠し子? 何を言ってるんだ、ティル。お前も知ってるだろう。 神は子供を作ってはならない。重罪だ﹂ ﹁重罪でも何でも、できちゃったものはしょうがないんじゃないか な。生命の誕生はそれがどんな理由であっても祝われるべきだと僕 は思う﹂ ﹁そんなことはどうでもいい。で、誰の隠し子なんだ﹂ ヨハンの耳にオイレンシュピーゲルが顔を近づけ、そっと囁く。 ﹁唯一神の、だよ﹂ 不意に目が覚めた。 寝苦しいという訳ではない。ドラクゥが公邸として使っている屋 敷は、元々パザン随一の商館の主が使っていたものだ。それを献上 された時のまま、手を加えずに使っている。建物の風通しに工夫が あるのか、暑い夜でも快適に過ごすことができた。 仰向けに天井を見つめながら、ドラクゥは去っていった兄弟子の 言葉を思い出している。 302 王が王であるためには、孤独でなければならない。その一言は今 も、胸の中で別の生き物のように蠢いている。 生まれてからずっと、孤独はドラクゥの側にあった。対等な者は、 誰もいない。最初からそれが当たり前だったのだ。 エリィナやハツカ、あるいはシーナウは、近くにいたと言えるか もしれない。しかしそれは距離的なものであって、心は離れたまま だった。 周囲の家臣は、近しい者を作ることで敢えて違いを際立たせよう と仕向けていたとさえ思える。それはいつしかドラクゥにも感染し、 自然なものになっていった。 家族もなく、友もなく。祖父という絶対者と、臣下だけがドラク ゥの関わる者の全てだったのだ。小さな振る舞いの中にも、謙譲を 示される。幼いドラクゥには心地良さよりも、拒絶としてしか受け 取れないものもあった。 孤独は、ドラクゥを鋭く研ぎ上げる砥石だ。それは、実感として あった。 ハツカの言うことは、正しいのだ。ただそれは一面的なものだと いう気がしている。 孤独によって研ぎ澄まされた力が強いのであれば、何故<北の覇 王>ザーディシュに敗れたのか。そのことが、ずっとドラクゥの心 の中に引っ掛かっている。 邪神を選び、ハツカを諦めたのも、そのためだった。 今のドラクゥは、以前と比べて確実に強くなっている。 怜悧さや、小手先の強さは失ったかもしれない。だが、全体とし ては新しい強靭さを手に入れた。それは民や臣下に寄り添う心から 生まれたものだった。孤独が研いだものではない。その切っ掛けは、 あの邪神のくれたものなのだ。 夜具を剥ぎ、寝台から足を下した。 薄く大理石の張られた床のひんやりとした感触が心地良い。胸の 中で蠢く者は、さっきよりも随分と静かになっている。 303 渇いた喉を潤そうと水差しに手を伸ばした時、窓を小さく叩く音 が聞こえた。 この寝室は三階にある。そのような訪いを入れるのは、魔族であ るはずがない。 ﹁ヒラノ様!﹂ そこには邪神ヒラノと女神ヨシナガ、そして大きな熊の邪神の姿 があった。人熊の邪神、エドワードだろうか。アルナハから報告に 来ているエリィナより、顕現したという話だけは聞いている。ドラ クゥは二柱にも、敬意の籠った挨拶をした。神とこれだけ接するな ど、普通ではありえないことだ。 † † † ヒラノと再会し、戦いへの気持ちを新たにするドラクゥ。 その頃、はるか北の魔都では、ドラクゥの師、グラン・デュ・メ ーメルが出撃の準備を終え、闘志をみなぎらせていた。 304 第一章ダイジェスト 山の向こうに、夕陽が沈もうとしていた。 稜線に消える寸前、陽光は名残のように一瞬、強さを増す。 ドラクゥは、馬上でその光を見つめていた。訓練の後の、つかの 間の休息だ。夜の帳が辺りを闇に閉ざす前に、宿営に一〇〇〇の兵 と共に戻らねばならなかった。 指揮する兵は、騎兵ではない。馬に乗ってはいるが、まだそう呼 べるほどの練度ではなかった。兵も馬も、訓練を通して戦うことに 慣れなければならない。 対峙しなければならない相手が<赤の軍>だと考えると、今のま まの一〇〇〇では、何の役にも立たないだろう。だが、鍛えるため に費やすことのできる時間は、あまりにも短い。 ﹁主上、いかがですか人界の馬の乗り心地は﹂ ﹁タイバンカか。存外に、良いな。鍛えれば面白いことになる﹂ タイバンカは、ドラクゥが南に落ち延びて来た時からの武将だっ た。元は<赤の軍>で上級の将校として出仕していたが、出奔して ドラクゥに付いてくることを選んだ。 小役人風の男だが、一〇〇〇や二〇〇〇の騎兵を扱わせると、驚 くほどの力を見せる。これまでドラクゥの麾下には騎兵がいなかっ たので、無任所の武将としての役割しか与えることができていなか った。 漸く、馬を手に入れることができたのだ。歩兵だけで戦うよりも、 使うことのできる戦術の幅は、格段に広くなる。 歩兵の訓練は、ゴブリンのロ・ドゥルガンやル・ガンといった将 に任せている。元傭兵のロ・ドゥルガンの練兵はさすがで、歩兵は 平原での戦い方を既に身につけつつある。 連携の訓練もしなければならない。騎兵だけ、歩兵だけといった 訓練のやり方では、どちらの兵種も本当の強さを引き出すことはで 305 きないのだ。 ただ、それにはまず騎兵が騎兵としての戦い方を学ぶ必要がある。 ドラクゥの騎馬隊は、まだまだその段階にも達していない。 ﹁馬はこれからも増えます。牧場はもう少し広くした方がよろしい かと﹂ ﹁それは余も考えていた。獣王から租借できるよう、親書も送って ある﹂ 人界から購入した馬は、魔界でも最上級の馬に遜色がないほどに 大きく、力強い。一瞬の速さでは魔界の産に一歩譲るが、持久力が あることがドラクゥは気に入っている。 長く駆けることができるということは、それだけで大きな武器に なるはずだ。戦略を考える上で、手数を増やすことができる。相手 の思わぬところに指すことのできる駒は、得難い存在だった。 ドラクゥの置かれている状況は、厳しい。 かつての師<万化>のグラン・デュ・メーメル率いる南征軍が、 獣王領を経由して南進を続けている。その基幹となる戦力は、廃嫡 される前のドラクゥが率いていた<赤の軍>だ。 その数は、二万。 魔界でも最強の呼び声高い騎兵集団である敵を迎え撃つには、ま だ準備が整っていないと言わざるを得ない。 ﹁それで、南征軍の足取りはその後掴めたのですか﹂ ﹁いや、はっきりとしたことはダークエルフでも探り出せていない。 南に向けて分進しているようだが、どこが目的地なのか、いつ集ま るかということまでは分からないということだ﹂ 魔都を進発した後、<赤の軍>は忽然と姿を消していた。 二万の軍を、見失う。あってはならないことに、諜報を任せてあ るダークエルフも随分と色めきたったものだ。調べてみると、五〇 〇程度の塊に分かれてばらばらに進撃しているらしいということは、 分かった。 ダークエルフを街道周辺に重点的に置いたことが、完全に裏目に 306 出ている。四〇に分かれた敵の全てを追うことは、もはや不可能と いってもいい。敵は道もない平原を、掠奪しながら進んでいる。< 万化>のグランらしい、意表を突いた策だった。 ﹁珍しいこともあるものです。ダークエルフであればそのようなこ と、すぐに調べ出しそうなものですが﹂ ﹁どうやら、妨害を受けているらしい﹂ ﹁ダークエルフを妨害できる者が?﹂ ﹁ああ、シェイプシフターが動いている気配がある。もちろん、残 党ではあるが﹂ ﹁シェイプシフターとは穏やかではありませんな﹂ 魔界には色々な種族が住んでいる。自在に姿を変えることのでき るシェイプシフターもその一つだった。彼らはその特性を活かし、 隠密活動を得意とする。ドラクゥの抱えるダークエルフの密偵とは、 仇敵の間柄にあった。 特定の種族を、敵にしたくはない。それはドラクゥの思いの根底 にある。 大魔王として、魔界の百族全てを等しく統べたいと本気で考えて いた。その中には当然、シェイプシフターも含まれている。今は敵 対していても、それは置かれている状況によってやむなく敵対して いると考えたかった。いつかは、味方にすることができる。 ﹁寝返らせることはできないでしょうか﹂ 何をとタイバンカは言わなかったが、<赤の軍>のことだという ことは、はっきりと伝わった。元は<赤の軍>で将校をしていたの だ。抜けたとは言え、今でも仲間だという意識があるのだろう。そ の気持ちは、ドラクゥにも何となく分かる。 ﹁難しいだろう。そのことは、お前自身が一番よく分かっているは ずだ﹂ ﹁はい。<赤の軍>は近衛です。易々と裏切ることはないというこ とは分かっております。しかし、近衛が立つべきはドラクゥ様のお 側であるべきです﹂ 307 ﹁<大魔王>だからか﹂ ﹁それも、あります。ただ、それだけが理由ではありません。大魔 王の地位にあることのみが<赤の軍>の忠誠を受ける理由になるの であれば、<北の覇王>がレニスを擁立したとしても条件を満たす ことになります。しかし、私はそうは思いません﹂ ﹁分からんな、タイバンカ。忠義の対象は好みで決めるものではな い。そんなことを許せば、魔界の一統など夢のまた夢だ﹂ ﹁畏れながら、押し付けられたものを甘受することも、忠義ではな いと考えます。尽くすべき相手にこそ、忠義は発揮されるべきです﹂ ドラクゥは、小さく唸った。 忠誠は、忠誠だ。その思いは変わらない。近衛である<赤の軍> が寝返ることはないだろうという思いも、変わってはいない。ただ、 そう思い込もうとしている自分がいるということに、タイバンカの 言葉は気付かせてくれた。 汚れることを無意識の内に恐れていたのかもしれない。 策を使う相手には、策を使った。それは相手の手も汚れているか らで、ドラクゥ自身の中で道理が通ったから使うことができたとい う気がする。 次に戦わねばならない<赤の軍>には、それがない。指揮官であ るグラン・デュ・メーメルは幾らかの策を使うだろうが、それはあ くまでも盤上の策だという気がする。清いものを戦うのに、汚れた 手で指したくない。それは、自分の思い上がりではないのか。 秩序のある魔界。それを理想に掲げるドラクゥにとって、忠誠の 対象とは濫りに変えることはできないものだ。しかしそれは、目指 すべき姿、あるべき姿の話だった。 理想と現実は異なる。理想を実現するためには、目を開いて現実 を見つめねばならない。 ただ、そうと分かっていても、手を汚すことには躊躇いがある。 誰かに相談を持ちかけたい。そう思って脳裏に浮かぶ相手は、グ ランであり、ハツカであり、そして邪神ヒラノだった。 308 これが、弱さなのだろう。甘さと言えるのかもしれない。王であ るドラクゥは、最後の最後には自分で全てを決めねばならないとい うことは分かっていた。だが、迷いは強い。 ﹁<赤の軍>が余の麾下に加われば、それは心強いことだと思う﹂ 希望を、口に出してみた。 これまであまり、実現の道筋が思いつかない願いは言わないよう にしていたのだ。 ドラクゥの育った宮中では、不用意な一言が利権を生み、政争を 呼ぶ。いつの間にか、そういう言葉を口にすることは無くなってい たのだ。それが何故か、口を突いた。 ﹁主上はそう思っておられるだけで良いと思います。それを口に出 して頂ければ﹂ ﹁どうすればいいのか、余に策はないのだぞ?﹂ ﹁そのために、臣下がおります﹂ ﹁余の個人的な願いのために、臣下を動かすというのはな﹂ ﹁全てを抱え込まれるべきではありません。私も含め、臣下は主上 の目指す魔界のために命を捨てる覚悟で働いているのです﹂ ﹁命を無駄にさせることになるかもしれん。犠牲を厭うているわけ ではないのだ。ただ、命というものは、使うべきところで使うべき だと思う﹂ ﹁ご立派です。しかし、もう少し臣下を頼って頂きたい﹂ ﹁しかしな、汚いことも、させることになるかもしれん﹂ ﹁そういう命令を、厭う臣下もいるでしょう。それは仕方のないこ とです。ただ、主上はもっと大きな視野でものを見て下さい。たっ た一言、お命じになられれば良いのです﹂ 小メーメルを、消せ。その言葉は、喉の奥まで出かかっていた。 軍監を除けば<赤の軍>はこちらに転がり込む。そうでなくても、 気持ちはこちらに傾くだろう。タイバンカがそう言わせたいという ことは分かった。言えば、タイバンカ自身が動くであろうというこ とも、分かる。 309 ﹁主上、私が﹂ ﹁もう良い、タイバンカ。もう良いのだ﹂ タイバンカの言葉を遮った。内心ではまだ、迷っている。 いつの間にか、草原の空は満天の星の光に埋め尽くされていた。 夜になると、草原は冷える。馬上にいても、地から冷たさが這い上 ってくるようだ。 ﹁分かりました、主上。差し出がましいことを申し上げたと反省し ております﹂ ﹁諫言は、ありがたく受け取る。だが、この話はこれまでだ﹂ ﹁御意にございます﹂ それだけ言うと、タイバンカは陣に戻った。兵を纏め、宿営に戻 る準備を進めている。 兵たちが馬に跨り、列を作った。まだ時間がかかり過ぎている。 ドラクゥの中にある騎馬隊とは<赤の軍>で、全ての騎兵はそれと 比べてしまうのだ。 寝返らせることはできないだろうか。そのことは、ずっと考えて いる。 それでも、確実な方法は一つも思いつかない。 師も<赤の軍>も、本来ならばこちら側にいて不思議のない存在 なのだ。それが、釦のかけ違いのように、敵対せざるを得ない。惜 しいとも悔しいとも違う、何か胸の奥が焦げるような感情が、ドラ クゥの中にはあった。 ﹁戦うしかない。戦うしか、ないのだ﹂ 口の中で唱えるように呟く。 戦う相手は、師であるグラン・デュ・メーメルだ。悩みながら戦 って、勝てる相手ではない。全力を尽くして戦っても、なお勝てな い可能性の方が大きい相手なのだ。 馬腹を蹴る。残された時間は少ないが、やるべきことは無数にあ った。 310 ××× 鍋の中身がくつくつと音を立てていた。 煮えているのは麦の粥だ。挽いた小麦を水に浸し、煮る。それだ けの単純な粥だった。塩があればそれで一味加える。獣王領で野営 する時に摂る、一般的な兵糧だった。こういう腹を満たすだけの粗 末なものでも、温かいというだけでありがたみを感じる。 リ・グダンが野営をしているのは、サスコ・バウ近くの平原だっ た。 天幕を張り、兵を鍛える。抱えている兵は、カタニアから落ち延 びた一〇〇〇ほどの元傭兵だった。練度も士気も、低くはない。 獣王の食客という扱いである。普段の糧食は保障されるが、いざ 戦いになれば尖兵として戦う。そういうきまりになっている。リ・ グダン自身は、陣借りのつもりだった。 負け癖が付いたとは思っていない。ドラクゥが強く、自分は弱か ったのだ。 敗戦の理由を考え、それを一つ一つ頭の中で潰していく。負ける ことには必ず理由があるが、勝つことはそうではない。敵と比べて、 どれだけ負ける理由が少ないかによって、最終的な勝者は決まるの だ。だからこそ、同じ負け方をしないようにすればいつかは勝てる のではないかという思いがある。 今は、一〇〇〇の兵を鍛え上げることだけに集中していた。 アルナハ出身のリ・グダンは、原野での戦いに不慣れだ。部下で ある元傭兵に教えられることも、少なくない。 以前持っていた自信のようなものは、リ・グダンの中から消え去 っていた。それが良かったという気もしている。 陣形の組み方、行軍方法、斥候の出し方、そういうことを学びな がら、ドラクゥとどう戦うかを組み上げていく。勝つ方法ではなく、 負けない方法を考えるのだ。迂遠な道かもしれないが、今のリ・グ ダンにできることはそれだけだった。 311 炊けた粥を椀によそわせる。量は兵たちと同じだ。 獣王から施される糧食から、リ・グダンは少しずつ蓄えを作って いる。元より、それほど多くの援助があるわけではない。それを切 り詰めてでも自分の糧食を用意するのは、いつか自立して再び魔王 に返り咲くためだった。 ﹁リ・グダン様、食事が終わりましたらサスコ・バウの本営へ参り ましょう。獣王が会いたいと使者を寄越しております﹂ いつの間にか、副官のカルティアが隣に座っている。この女ハー ピィを、リ・グダンは獣王との連絡係に据えていた。面倒事を押し 付けたというところもある。 獣王の都、サスコ・バウは外様の者には暮らしにくい場所だ。 ﹁分かった。しかし、また軍議か﹂ ﹁はい。<赤の軍>の扱いをどうするか、決めかねているようです﹂ ﹁降って湧いた災厄のようなものだからな。考えあぐねるのも無理 はない。問題はどう動くべきか、ということだ﹂ ﹁随分と揉めているようです﹂ 領内深くに侵入されても、<赤の軍>に対する獣王の動きは鈍か った。 原因は、兵が集まらないことだ。どこにいるのか分からないとい うこともある。 獣王の下には、八体の魔王がいた。人虎や人豹、人猫の魔王たち は人獅子の魔王を兼ねる獣王と擬似的な血縁関係を結び、その結束 は固い。本来であれば、獣王が一声かけるだけで、七万の死を恐れ ぬ兵士がサスコ・バウに参集するはずなのだ。 それが、ほとんど集まっていない。魔王自身は、サスコ・バウに 揃っているが、その下の、各部族の動きが悪いのだ。 ﹁鉄の結束を誇る獣王軍が、一度乱れるとこうも脆いとはな﹂ ﹁仕方ありません。獣王の当代がこれまで戦ったのは格下がほとん どですから﹂ ﹁相手があのドラクゥの師では荷が重いか﹂ 312 リ・グダンが本営に付いた時には既に八魔王は揃っていた。 天幕の中に、気が充溢している。魔王が集うということにはそれ だけの意味があった。 獣王はまだ姿を見せていない。リ・グダンは九番目の魔王のつも りで下座に陣取った。そういうふてぶてしさは、いつになっても抜 けるものではないらしい。 すぐに人猫族の茶坊主が藁の円座を運んでくる。獣王が世話をす る食客は多いが、一〇〇〇の兵を抱えるリ・グダンはその中でも特 別な扱いを受けていた。他の食客たちは、この場の空気に圧倒され ているようだった。 ﹁<万化>のグランに上手くはめられたな。兵が集まらんでは身動 きが取れん﹂ 人豹族の魔王が溜息混じりに呟く。運び込まれた机の上には獣王 領の巨大な地図が置かれている。兵を表す駒は各部族の集落に置か れたままになっていた。 グラン率いる<赤の軍>が中隊単位で進むことなど、誰も事前に 想像していない。斥候も全てが無駄になっている。獣王軍は、完全 に後手に回っていた。 ﹁しかし、だ。豹の叔父貴、ここまで虚仮にされて<赤の軍>に素 通りされちゃあ、獣王軍の名が廃るだろう。集まった兵を糾合して、 せめて一太刀なりとも浴びせにゃ﹂ ﹁虎の。お前さん、威勢が良いのは結構だがな。そもそも<万化> のグランがどこにいるかが分からんのだぞ。軍を出しても、叩きよ うがなかろう﹂ 集まった八魔王の中でも主戦派の人虎の魔王を、穏健派の人象の 魔王が宥める。 叔父や甥のような呼びかけをしているが、実際に血の繋がりがあ るわけではない。 人獅子、人豹、人虎、人猫の魔王は契りの盃を交わし、義理の血 縁関係を作っている。そうやって、争いが起こりがちな西の平原を 313 纏め上げて来たのだ。 リ・グダンは机の上の地図を覗き込む。赤字で書き込まれている のは、<赤の軍>の中隊や斥候が目撃された地点だった。書き込み は数え切れないほどあり、目撃された順に線で結ぶことも難しい。 これだけの地点で目撃されているからこそ、各部族は兵を出し渋 っていた。内応している部族もあるという噂が、より猜疑心を掻き 立てている。 グランが兵を集結させるのはどこだろうか。リ・グダンの目は、 地図の南側を舐めるように見渡す。候補は多いように見えて、意外 に少ないのかもしれない。 最終的にドラクゥと対峙することを考えれば、サスコ・バウより も南、パザンの近くだろう。ただ、近過ぎても駆け引きができなく ない。 そうやって考えれば、いくつかの城市が怪しく見えてきた。内海 の沿岸、人魚族の城市であるオルビス・カリスなどを除けば、五つ か六つの城市が浮かび上がってくる。 ここに重点的に斥候を置くことで、機先を制することはできるか もしれない。 そう発言しようとした時、大天幕の入り口が俄かに騒がしくなっ た。 ﹁静まれ、獣王様の御出座である!﹂ ﹁獣王様御出座!﹂ <赤の軍>が如何に精強であっても、食料がなければ餓える。 そう喝破した獣王だったが、グラン・デュ・メーメルは思わぬ奇 策に出た。 獣王との戦いを回避し、内海に面したオルビス・カリスを掌握し たのだ。 314 これによって海路で魔都からの物資を受け取ることができるよう になった<赤の軍>は大方の予想に反し、持久策の構えを見せる。 その頃一方、<青>のダッダはパザンの酒場である男の姿を探し ていた。 ハツカ。 大魔王ドラクゥの師兄である彼に、どうしてももう一度会ってお きたかったのだ。 315 第二章ダイジェスト 馬車の揺れが酷くなった。 草の匂いが強い。街道を外れたのだろう。ここから先、大きな都 市はもうない。広がる草原の中にぽつりぽつりと集落が点在してい るだけだ。 人の世界の涯、魔の世界の入り口。 アイザックは狭い幌馬車の中で、じっと蹲っていた。手にしてい る羊皮紙は揺れが酷くて読めない。錬金術の奥義に近付くためには 一刻も無駄にはできないのだが、この場合はそうも言っていられな かった。 研究拠点の移動、と言ってしまえば聞こえはいいが、要するに逃 亡だ。 それも、確実に追っ手が掛かっている。逃げ切れるかどうかは全 く分からないが、それでも今までの場所に留まることはできなかっ た。 ﹁若、あと数日も走れば大河が見えます。そこを越えれば、魔の領 域です﹂ 祖父の代から家宰として雇っているウォーレンが御者席から覗き 込む。 魔の領域に逃げ込もうと提案したのは、このウォーレンだった。 若、と呼ばれることに若干の苛立ちを覚えながら、アイザックは 座り直す。ずっと同じ姿勢で座っているから、尻が痛い。 これまでにいくつもの検問を荷物に紛れて越えて来た。はここま で捕まらなかったのは奇蹟と言ってもいい。 ﹁爺、本当に魔族の者は我らを受け容れると思うか?﹂ ﹁受け容れると信じましょう。錬金術を研究する若と学派の皆様の 知識は、彼らにとっても有益であるかと存じます﹂ ﹁有益無益で魔族が物事を判断するものだろうか﹂ 316 ﹁“聖堂”が流布しているような者ばかりでもありませんよ、魔族 も﹂ “聖堂”という名を聞くと、アイザックの胸は痛んだ。 錬金術には無数の学派がある。研究分野や真理に関する考え方の 違い、哲学性の差は埋めることのできない溝として、錬金術師を分 断してきた。 アイザックの家は“白の学派”を代々統べる家柄である。 白などと冠しているが、研究の内容は他の学派と比しても尖鋭的 で、危なげな物も含んでいた。その縁で、父の代に“聖堂”と密か に関わりを持つようになったのは皮肉としか言いようがない。 “聖堂”に敵視され、排除される筈の錬金術師が彼らのために働 く。 そのことに疑問を感じて去っていく弟子は多くいたが、残る者も 少なくなかった。 “白の学派”に籍を置く限り、“聖堂”から排斥されることがな かったからだ。 その蜜月に終わりがやってきたのはほんの半年ほど前だった。 これまで“聖堂”の命で様々なものを研究してきた父が突如疎ん じられ、最終的には不審な死を遂げたのだ。原因は恐らく“火精の 秘薬”だろう。 “聖堂”は再三にわたってその秘薬の研究を止めるように勧告し てきたが、父は聞き入れなかった。 錬金術師としては周りの見える方だったが、それでも一度のめり 込んだ研究を途中で止めることのできるような男が学派を統べるこ となどできるはずがない。 ﹁まるで魔族を知っているかのような言い草だな、爺﹂ ﹁アイザックさまはご存知ないと思いますが、お父上の若い頃には 魔族の行商があちらの珍しいものを売りに来ていたものでございま す﹂ ﹁へぇ。はじめて聞いた﹂ 317 ﹁コボルト族の商人で、確かクォンという名でしたか。なかなか良 いものを扱っておりました。アイザックさまの叔父上とは随分と親 しくしておりました﹂ ﹁叔父上は変わり者だったからな﹂ ﹁変わり者でない錬金術師などおりますまい﹂ ﹁それもそうだ﹂ 馬車がまた大きく揺れ、荷物を入れた箱が軋んだ音を立てる。 この中には羊皮紙に纏められた学派の研究をはじめ、様々な試料 が詰められていた。 魔界に移住して研究を続けるために必要だということもあるが、 残していけばそれだけで色々な悪事が露見しそうなものも含まれて いる。 ﹁変わり者、といえば例のアレも持って来られたのですか?﹂ ﹁⋮⋮ああ、持ってきた。アレさえ積まなければもう少し書物も載 せられたのだが﹂ ﹁書物については分かれて魔界を目指しておられる学派の方々に期 待しましょう。アレは曾祖父様の研究ですからな﹂ アレとは、蜘蛛だ。学派の紋章にもなっている。 曽祖父の代から“白の学派”で殖やし続けている、少し変わった 種の蜘蛛だった。 そんなものを後生大事に育てていたせいで“白の学派”は他の錬 金術師から随分と莫迦にされている。 ﹁⋮⋮向こうでは餌が安く買えればよいのだが﹂ ﹁そうですな﹂ 途中で妨害を受けることもなく、馬車は大河の畔まで辿り着いた。 夜だというのに、妙に明るい。対岸と中洲に、無数の松明の光が 煌めいているのだ。 馬車を下りてその様子を眺めていると、身体が鱗に覆われた魔の 者が近付いてきた。 古い伝承にあるリザードマンだろうとアイザックは当たりを付け 318 る。 だが、妙だ。アイザックの知る限り、ことはこれほど西にリザー ドマンは住んでいない。 魔界でも南東部の湿地に彼らは住んでいるはずのリザードマンが 何故、人界との境で補償などしているのか。 ﹁ようこそ、人の子よ。何か用だろうか﹂ 意外にもリザードマンは大陸共通語を使った。舌が長いからか舌 の擦過で訛りがある。 それでも、田舎の農村で聞くよりも余程聞き取りやすい。 ﹁移住を考えている﹂ リザードマンの目が、くるりと動いた。表情は、読めない。 人の顔と根本的な構造が違うのだ。そこから何かを見出すのは難 しそうだ。 ﹁取引ではなく、移住を望むのか﹂ ﹁そうだ。馬車を見てくれ。家財道具一式を持ってきた。この城市 は、人も魔も分け隔てなく受け容れると聞くが、それは偽りか?﹂ アイザックの問いに、もう一度リザードマンの目が動く。 今度の動きの意味は、何となく分かった。笑ったのだ。それも嘲 笑ではない。 リザードマンも笑顔を浮かべるのだ、と当たり前のことにアイザ ックは気付いた。 ﹁ようこそ、人の子よ。当市は移住者を歓迎する﹂ 手続きは簡潔だが、的を射ていた。 元よりアイザックには魔族を見下すつもりはない。それでもここ まですんなりと話が進むということには舌を巻いていた。 この城市の法は丁寧に整備されている。人界を広く見渡しても、 ここと同じ水準の戸籍を持ったところはほとんどないだろう。 ﹁錬金術の工房、ですか﹂ ﹁はい。研究を継続するためにも、それに適した場所が必要です。 何とか用意して頂けないでしょうか﹂ 319 アイザックの要求はたった一つ。錬金術の研究に使える工房に住 まわせて欲しいということだけだ。最低でも、ウォーレンとは一緒 に暮らす必要がある。 それなりの大きさの居住区域と、工房。通いでも構わない。だが、 研究の効率から言えば、住居と工房は併設されていることが望まし かった。 コボルトの役人は少し考え、手元の羊皮紙に何事かを書き付けて 封蝋を捺した。 それを逓送用と縫い取りのされた布袋に入れる。こういう手続き も予め定められているのだろう。 ﹁特別な技能を持った新住民の方は、それに応じた住宅の配給を受 けることができます。とは言っても、用途によって適不適があるで しょうから、城市の執政府の方にこの書類を持って行ってください。 そちらで対応させて頂きます﹂ コボルトの丁寧な扱いには、職務に定められている態度以上の好 意が感じられた。 人族がどう扱われるかというのは、全くの無用の心配だったよう だ。 アイザックはウォーレンと共に移民事務所を後にする。 拡張途中の街路は活気に充ち溢れ、アイザックが名も知らぬ種族 の魔物が日干し煉瓦や木材を抱えて往来を闊歩していた。 ﹁賑やかな街だな、ウォーレン﹂ ﹁ええ、王都に匹敵するかもしれませんな﹂ 白の学派の本拠地があったのは、アルディナ王国の王都だ。 新興国としては大きな王都を抱えていた。だが、防禦に拘るあま り商業にはあまり向いていない。それに引き替え、この新しい城市 は完成すれば商業も大いに潤うであろうという気配がある。 石畳の道は幅が広く、傾斜が付けられていた。水捌けをよくする 工夫だろう。 こういう心配りは、新たに街を作る時に組み込んでおかなければ、 320 後から手を加えることは難しい。 外敵からの攻撃に備えることよりも、都市を富ませることに主眼 が置かれている。そういう街づくりが徹底されているようだ。 アイザックは軍事には疎いが、城壁の破られた城市が守りを続け ることが容易ではないということは想像がつく。 こういう街を作ろうとするのは、どんな考え方の魔族なのか。 人界では最高峰の知識人と渡り合ってきたという自負がある。魔 族の知恵者が何を考え、何を語るのか。今のアイザックの関心はそ れだけに向いている。 要所に建てられている高楼は見張り櫓のように見えた。しかし、 よくよく見れば凝った意匠を施されている。一つ一つが邪神を崇め る神殿になっているらしい。 ﹁すいません、ここの神殿ではどのような神を崇めているのです?﹂ アイザックが尋ねると、神殿の高楼を見上げていた人族の青年は 慌てたように振り向いた。黒髪に黒目。この辺りではあまり見ない 服装をしている。 ﹁ここでは、商いの邪神を祀るらしいですよ﹂ ﹁商いの邪神。そういう信仰もあるのですか﹂ “聖堂”への信仰が普く人界では、神と云えば唯一神の事だ。 天使への祈りも捧げるが、帰依するのは唯一絶対の神に限られる。 邪神という物が複数存在することはアイザックも錬金術の研究で知 っていた。ただ、こうまで開け広げに人族の青年の口から邪神とい う言葉を聞くと、違和感を覚えてしまう。 ﹁商いの邪神と云っても、元は雷の邪神なんですけどね。商業にも ご利益がある、ということみたいです﹂ 商業の神について尋ねたのに、何故か照れくさそうに青年が応え る。 この神に帰依している信者なのだろう。自分の崇める神を褒めら れればうれしくなるという気持ちも分からなくはない。 信仰しなければならないのなら、錬金術の邪神にしたいという思 321 いがある。問題は、そういう邪神がいるかどうかだ。 ウォーレンは先程から何か考え込んでいるのか、一言も発してい ない。 ﹁一柱の神に複数の御利益ですか。思っていたよりも邪神信仰は奥 深そうだ。どの神に帰依するか、今からしっかり考えないと﹂ ﹁色々な邪神がいますよ。熊の邪神なんかも、人気が高いです﹂ ﹁熊ですか。しかし、唯一神への信仰を捨てて新たに帰依するのな ら、よほどしっかり考えないと⋮⋮﹂ アイザックの言葉に、青年は不思議そうに首を傾げた。 ﹁捨てる必要はないですよ﹂ ﹁えっ﹂ ﹁唯一神への信仰を持ったままこの街に移り住むことはできますし、 その上で別の邪神を信仰することもできます﹂ ﹁二柱以上の神を信仰することもできる、ということですか﹂ ﹁そう言うと少し語弊がありますね。<大魔王>ドラクゥは個別の 民の信仰の問題に口を出さないということです﹂ この青年は何を言っているのだろうか。 アイザックには俄かには理解ができなかった。 もし彼の言っていることが本当であれば、魔界ではいわゆる<聖 堂>に代わるような強力な信仰の砦は存在しないということになる のではないか。これまでは邪神殿がその役割を担っているのではな いかと思っていたが、そうでもないらしい。 個々人が好き勝手に信仰をし、複数の神に祈りを捧げる。そんな 信仰のあり方が、果たして本当に存在し得るのだろうか。 ﹁そういう信じ方で、邪神がお怒りになることはないのだろうか﹂ ﹁俺はあんまり気にしていませんけどね﹂ ﹁ああ、それは信者の方では気にしないかもしませんが⋮⋮﹂ 不思議なことを言う青年だ。 邪神殿の高位聖職者かとも思ったが、それにしては気負いがなさ すぎる。職業柄、色々な人間を見て来たアイザックだが、この青年 322 の生業にはとんと想像がつかない。 ﹁何にしても、この街は良い所です。もっといい街になる。移住さ れるのでしたら、歓迎しますよ﹂ ﹁確かに。ここは良い街だ。そして、もっと良くなる﹂ どちらにせよ、アイザックもウォーレンも、人界に居場所はない のだ。歓迎されようがされまいが、しがみついてでもこの街で暮ら す必要がある。 何となく青年と道行きになり、そのまま城市の政庁に案内して貰 うことになった。 工事中の街路の辻々には樹が植えられており、涼しげな木陰を作 っている。その下では物売りたちが声を嗄らし、水や酒、ちょっと した果物を桶から売っていた。 水を飲む客にはコボルトやゴブリンが多いが、人族も交じってい る。 賑わいは、既にできあがった街のもののようだ。 大通りを真っ直ぐに東へ向かっていると河に突き当たった。 上流からは何艘もの平底船が切り出された石を積んで下って来て いる。この城市の建設は豊富な石材に支えられているようだ。 中洲には城郭にも見える広壮な建物が聳えていた。 ﹁あれが政庁です。なかなかのものでしょう﹂ 青年の指差す先に見える政庁は、建設途中だが確かに大きい。ア イザックの目には、大きすぎるようにさえ見える。一国の首都を管 掌する役所として、いや、王城としてさえ使えそうな規模に見えた。 ﹁確かに立派ですが⋮⋮あちらにはどう渡るのでしょうか?﹂ 橋を探していたウォーレンが呟くように尋ねた。河に架かる大き な橋梁は無い。渡し舟を使うということもアイザックの頭を過った が、それでは対岸とこちらに二つの別々の城市が存在するようなも のだ。 青年は子供が取って置きの玩具を披露するような顔で笑った。 ﹁これです!﹂ 323 青年の指示した先には、変わった形をした橋があった。 見慣れた形の橋梁ではない。それはむしろ、連なった小舟の群れ に見える。 ﹁小舟の上に板を渡しているだけのようにも見えますが﹂ ﹁ええ、リザードマンが浮桟橋を作る時の工法だそうです。﹂ ウォーレンの問いに青年は嬉しそうに説明する。 ﹁石造りの橋を架けるには、この河は水量が多過ぎます。水深も、 かなりある。もし長い時間をかけて橋ができあがったとしても、何 かがあって壊れてしまうと再建するのにまた莫大な時間がかかりま す。それに比べれば、この浮橋はとても合理的です﹂ それだけではあるまい。 アイザックにはこの橋の本当の意味が薄々感じられた。 人界と魔界とを繋ぐ橋だ。頑丈であれば、“聖堂”が東征する際 の足掛かりにもされかねない。この橋であれば、惜しげもなく焼き 捨てることができるだろう。 その狡猾さと周到さは、アイザックにとって好ましいものだ。 この城市の支配者が“聖堂”に対して警戒心を持てば持つほど、 アイザックと白の学派が生存することのできる可能性は飛躍的に向 上する。 河には中洲に辿り着くまでにもいくつかの小島があり、そこを経 由するようにして浮橋は向こう岸に辿り着くらしい。 ﹁これは面白いな。ウォーレン﹂ ﹁はい、若様﹂ 中洲までの距離はかなりの物だ。三角測量をすれば大まかな距離 は分かるのだろうが、少なくとも人界の橋梁技術ではこの長さの橋 を渡すことは不可能と言っていい。 そうかと言って、舟による渡しだけに頼る方法では、熟練の船頭 の数が物流の上限を決めてしまう。この方法なら、確かに船頭の負 担を減らすことはできるだろう。 ﹁問題は、舫い綱なんですよね﹂ 324 ﹁舫い綱に何か問題が?﹂ 問題の解決は錬金術師の仕事である。何か手伝えることがあれば、 と軽い気持ちでアイザックは青年に尋ねた。 ﹁強度の問題です﹂ ﹁強度?﹂ ﹁ええ、今の方法では、重い荷物を運ぶときは綱が切れないように 細心の注意が必要になりますし、何よりも一直線に中洲に渡すこと ができない﹂ ﹁綱を固くすればいいと?﹂ ﹁材料は色々試してはいるみたいなんです。ただ、木の繊維や革紐 では限界がありますから、何か別の方法があればなぁと﹂ その言葉を聞いて、アイザックはウォーレンと顔を見合わせた。 浮橋は意外にも渡り易かった。 見た目で想像していたほど、橋は揺れない。はじめは恐る恐ると いう格好だったウォーレンも、馬が横を渡るのを見て、普通に歩く ようになった。 錬金術師としての活動に便宜を図って貰うためにアイザックが提 示したのは岩蜘蛛という生き物だった。 鉱物を食べると鋼糸を吐きだすこの蜘蛛の存在を見て、ヒラノは あることを思い付く。 一方その頃、魔界の東では冥王の元に身を寄せる<法皇>リホル カンが怪しげな動き魅せつつあった⋮⋮ 325 第三章ダイジェスト 草原の濃い緑を、赤が断ち割って来る。 それは一本の槍の様であり、同時に一匹の獣の様でもあった。 獣の名を、<赤の軍>という。 揃いの赤の軍装で固めた精鋭騎兵が疾駆するだけで味方の意気は 上がり、敵の士気は沮喪する。しかもその軍を率いるのは当代最強 の騎兵指揮官、グラン・デュ・メーメルだ。 丘の上から迫りくる馬群を見下ろし、ドラクゥは口元だけで笑っ た。 馬の行き足に、戦意が充溢していない。 見せ掛けの突撃だ、と思った瞬間には獣は頭から二つに割れ、元 来た道を帰り始める。 ﹁飽きませんね、デュ・メーメル将軍も﹂ ﹁我慢比べだ、タイバンカ。突撃はないとこちらが甘く見た途端に、 演技ではない本物の突撃が来る﹂ 偽の突撃は既に何度も繰り返されていた。 パザンの城壁よりわずかに北、丘の上にドラクゥは陣取っている。 嘲弄するかのような動きグランの動きは、訓練も兼ねているのだろ う。 逸った兵が矢を射掛けるが、敵は射程のすぐ外を悠々と回避して いく。 最初は長駆の疲れを感じさせた動きが、ここ数日で見る見る内に よくなっていた。 ﹁大したものです。デュ・メーメル将軍は<赤の軍>を完全に掌握 してしまった﹂ ﹁さすがは我が師だ。<赤の軍>をまるで手足のように動かす﹂ ﹁近衛の動かし方とは、少し違うように見えます﹂ ﹁魔軍式というか、デュ・メーメル式というか。実戦では、その方 326 が役に立つ﹂ 近衛騎兵の操典と、一般の魔軍騎兵のそれは若干異なる。 グラン・デュ・メーメルは大魔王家戦術指南役であると同時に、 魔軍騎兵総監の職も兼ねていた。その戦術は魔軍騎兵の精髄と言っ ていいが、普通の騎兵であれば一朝一夕に身に付けられるものでは ない。 ドラクゥは<赤の軍>のやり方にグランが合わせるのかと思って いたが、どうもそうではないようだ。この僅かな期間に、<赤の軍 >はグラン・デュ・メーメル好みの機動を修得つつある。 元々の<赤の軍>の動きは、美しかった。美し過ぎると言っても、 過言ではない。 それは彼らが皇太子の為の軍であり、見られることを目的とした 軍だということを意味している。儀仗用の騎兵だ。 平時であれば、それで良い。威風堂々と進む<赤の軍>に敢えて 抗しようとする愚か者は存在しないし、仮にそのようなものがいて も、軽々しく粉砕できるだけの力はある。 但し、今は戦時であり、対峙するのはドラクゥの軍だった。 今の<赤の軍>は、美しいだけではない。 かつてドラクゥが指揮した時にはなかった、荒々しさも兼ね備え ている。 戦う為の騎兵にグラン・デュ・メーメルが仕上げたのだ。 一度二つに別れた騎兵が距離を取って再び集結し、また突撃を仕 掛けてくる。 今度は誰も矢を射掛けなかった。予め目印となる灌木が定められ ていて、敵の先頭がそれを超えるまでは、本当は撃ってはならない 決まりになっている。 ﹁難しい戦いですな﹂ ﹁兵はよく耐えている。今は、耐えること、待つことが戦いだ﹂ ひっきょう ﹁嫌な攻め方をしてくる敵です﹂ ﹁戦いとは畢竟、相手の嫌がることをすることということだろう。 327 我が師らしい、実に嫌な手を考えてくる﹂ ﹁嫌な手、という意味では主上も負けてはおられません﹂ ドラクゥとグランの主な戦場はここだ。 だが、ここでの戦いを有利にするためにドラクゥも盤外戦を仕掛 けている。 リザードマンとの戦いで大規模な軍を編成できなくなった妖鳥族 を使って、魔都からこちらへ南下してくる輸送船を攻撃させている のだ。 戦果としては然程の影響はないが、いつ襲われるか分からないと なれば船に護衛を置く必要も出てくる。その護衛は食事もするし、 水も飲む。手間賃が掛かるようになれば実入りが悪くなり、応徴さ れる船主の数も自然と減ってしまう。 ダークエルフの報告では、効果は着実に出つつある。折角ダーモ ルトが買い集めた糧食の一部は船に積み込めずに魔都に溜まり始め ているのだ。 そこに火を掛けることができないかということをダークエルフの シュノンに諮っているが、そこまでは難しいということだった。 また、赤い装束を身に付けた馬群が迫ってくる。 これが、日に何度も繰り返されるのだ。 長槍や弓を構え、耐える兵にも疲れは溜まる。師の狙いがドラク ゥには手に取るように分かるが、今はここを動かずに耐えることし かできない。 丘の上に陣を張れば、駆け上がってくる騎兵の勢いは落ちる。 細かく纏まる竜鱗の陣を組んでいれば、突撃してくる騎兵も無傷 では済まない。それに加え、ドラクゥは簡単な鹿砦も備えさせてい た。 先に仕掛けた方が、不利になる。これはそういう駆け引きだ。 だが、慢心した方が負ける。 ドラクゥは<赤の軍>の駈け方に、あるかなきかの違和感を覚え た。 328 それは、隣にいたタイバンカも同じようだ。 ﹁主上﹂ 呼び掛けに、頷きだけで応える。 タイバンカが小さく手を振ると、その動きが各級指揮官に漣のよ うに伝わっていく。 正面に陣取る長槍隊には、敢えて伝えない。こちらが何に気付い たと気取られてはならないのだ。 弓と連弩に、静かに矢が番えられる。 職工に作らせている連弩は、漸く数が揃うようになってきた。 “聖堂”との戦いを控える南の新城市にも纏まった数を納入して いるので、充足は非常に緩やかな速さで進んでいる。 赤が、迫る。 その色は血のようにも炎のようにも見え、隠されているが猛り方 はいつもと違った。 嘶き。いつもは折り返す地点を、一歩踏み込む。そこは弓の射程 でもある。 ﹁射よ!﹂ タイバンカの聲。 連弩と弓から放たれる矢の雨が降り注ぐ中を、赤い獣が這い上が ってくる。 蹄で鹿砦が粉砕され、最前面の長槍隊と馬群の先頭がぶつかった。 圧倒的な突破力。 訓練を積んだ長槍兵の隊が、弾かれるように断ち割られる。 弓兵、連弩兵も、もう一射した後は予てからの指示通りに槍に持 ち変えた。だが、それで通用する相手ではない。 馬上に、師の姿が見える。 得物である硬鞭を手に喊声を上げる姿は、とても老将の物とは思 えない。 ドラクゥが高台から床几に腰掛けたまま師を見遣ると、向こうも 見返してきた。 329 笑っている。 戦場での昂揚からだろうか。ドラクゥもそれに、笑みを返す。 断ち割ったはずの<赤の軍>が、挟撃され始めていた。 突撃を見越して最初から指示を出していたのだ。堅陣を組んでい るつもりで断ち割られるのと、予め断ち割られる道を作っておいて やるのとでは、兵士の動きはまるで違う。 全ては駆け引きだ。 師と戦棋をしているような錯覚に、ドラクゥは襲われている。 グランはここで留まる愚を犯さず、さっと兵を退くだろう。 そういう引き際もまた、一流のなせる技だ。 その時ふと、妙なことが気に掛かった。 <万化>のグランはここにいる。では、<千変の>ジャンはどこ にいるのだ? ドラクゥが気付いた時には、既に手遅れだった。 グラン・デュ・メーメルが悠々と兵を引き上げようとするのと入 れ違いに、伝令が駆けこんでくる。 ﹁申し上げます! パザンの東壁を敵攻城兵器部隊が攻撃中!﹂ ﹁何だと!﹂ ﹁指揮官は、<千変>のジャン・デュ・メーメルです!﹂ 城壁の見える場所にジャンは本陣を構えた。 聳える壁は厚く、高い。 元は人熊の城市だったパザンは、華美さよりも剛健さを求めて縄 張りがされている。 それはシェイプシフターの統治時代を経ても変わることはなかっ た。 祖父グランの騎兵が動いているお陰で、城の守りは北側に集中し ている。お陰でここまでに接触したのは小さな歩哨の部隊だけだっ た。 敵の気が緩んでいるのではない。<赤の軍>を抑えるだけで、精 330 一杯なのだ。 張り詰めた横っ面を、相手の想定していない手で殴り付ける。 それが祖父グランの示した策だった。 ﹁行け﹂ <千変>のジャン・デュ・メーメルの号令で、攻城兵器部隊はパ ザンの東の城壁に取り付きはじめる。主力は、衝車と雲梯だ。 屋根の付いた衝車は城壁の上からの攻撃に耐えながら破城槌で城 門を攻め立て、雲梯の隊は巨大な梯子で城壁の上への攻撃を試みる。 どちらも魔都のダーモルト・デル・アーダにグランが依頼して取 り寄せた品だ。 途中、妖鳥族の妨害があったという報告があったが、組み立て式 の攻城兵器の存在は露見していない方にグランとジャンは賭けたの だ。 船便で運ばせたそれの使い方を傭兵に訓練させるのには随分と時 間がかかった。 その間、港近くに迫った斥候は、所属がどこの物であっても完膚 なきまでに叩きのめした。今日のこの攻撃をドラクゥに悟らせない ためには必要なことだ。 衝車と雲梯は森の中の道を縫うように進んできた。 脱落したのは、衝車が三輌と雲梯が二輌。 当初はそれぞれ五輌程度駄目になると見積もっていたから、これ は良い数字だった。 城壁からの反撃は激しいが、どこか間が抜けていた。指揮官のせ いだろう。 カルキンという人鹿の将が、東の城壁の守将だ。 そのことは、 シェイプシフターの調べではっきりしていた。防禦の得意な将だと いう触れ込みだったが、評判倒れも甚だしい。 森の中の間道も、シェイプシフターの手引きだ。元々パザンを領 有していた彼らは、この城市のことに詳しい。人熊の時代にはなか った間道も彼らが整備した。 331 シェイプシフターの魔王<淫妖姫>パルミナは自分の城市が落と された後のことまで考えていたということだ。 ﹁軍監殿、もう少し本陣を城壁に近付けますか?﹂ <赤の軍>からこちらに出向しているアルカスが、試すように聞 いてきた。 役割ははっきりしている。祖父グランの付けた、教育係だ。 グラン・デュ・メーメルという教育者はこの南進作戦で孫にあり とあらゆることを叩きこもうというのだろう。その中にはジャン自 身よりも軍歴の長い部下を扱うという訓練も含まれているに違いな い。 ﹁いや、良い﹂ アルカスの眉が動く。怯懦を疑われただろうか。 だが今は、そういうことを気にしている場合ではない。 ﹁全体を見たい。攻城戦ではどうしても前のめりになる﹂ ﹁前のめり、ですか。なるほど﹂ ﹁周囲の状況を見るのが、部隊指揮官の務めだ、と思う﹂ ﹁そこははっきりと務めだと言い切って下さい。部隊指揮官は部下 に心の動揺を見せるべきではない。それが誤った判断であってさえ﹂ ﹁誤った判断であってさえ、か﹂ どうやら先程眉を動かしたのは、嘲りのためではなかったらしい。 <赤の軍>の最先任からすれば、まだまだ<千変>のジャン・デュ・ メーメルも見縊られていたということだ。 出来の悪いと思っていた生徒が思わず正解を漏らして驚いたとい うところだろう。 二〇〇までの部隊の扱いなら魔軍でも相当の上位に入る。そうい う自負がジャンにはあったが、一千や一万を指揮するにはまた違っ た部分があるようだ。 ﹁周辺の敵はどうだ?﹂ ﹁シェイプシフターの報告では、グラン将軍が相手と対峙を始めた 三日前から、この周辺では目立った動きはありません。隠密行動で 332 すので、<赤の軍>から事前の斥候は出しておりません。攻城の開 始と同時に斥候を放ちましたが、報告はまだ入っておりません﹂ ﹁なるほど﹂ 予期せぬ攻撃、完全なる奇襲の成功。 さすがは名将の誉れ高き<万化>のグラン・デュ・メーメルとい うことだ。 弟子であるドラクゥでさえ、その掌の上という訳だ。 喜ばしいことだが、腹立たしくもある。祖父の名誉が高まれば高 まるほど、孫である自分はその陰でくすんでしまうという嫉みがジ ャンの腹の底にはあった。 苛立ちを収めるため、ジャンは手にした硬鞭を撫でる。 祖父の持つ物と揃いのものだ。作られた頃は一対の双鞭であった ものを、いつの頃からか二つに分かれて伝えられるようになった 銘は<千変>。 祖父の持つ<万化>と共に二つ名の元になっている。 これも、<北の覇王>に貰ったものだ。人山羊の王家から売りに 出されていたものを、ザーディシュがジャンに買い与えてくれたの だ。当時のジャンの俸給では、何年分積んでも購えるような値段で はなかった。 強くなりたい。その思いが、今のジャンを支配している。 それは良いことでもあるし悪いことでもある。戦争は戦争であり、 教育の場ではない。 結果として戦争から何かを学び取ることはあっても、学び取るこ とそれ自体は目的ではないはずだ。 しかし、今回の出征での祖父には違った考え方があるようだ。 戦争を戦争としてではなく、それ以外の何かとして捉えている。 結果として、名将グランの戦争が損なわれているわけではない。 むしろ、他の誰をこの役に充ててもグラン・デュ・メーメル以上に 上手く演じられるものはいないだろう。 与えられた二万の騎兵を持て余し、ドラクゥと対峙するところま 333 で持って来ることさえできない者が大半だという気がする。 他ならぬジャン自身がそうなのだ。 グランの手本を見た今でこそ、自分なりの南進策を思い付くこと ができる。以前の自分では思い付かないような策だ。 戦争で、教育されている。祖父の一番大切な戦争で、だ。それが 悔しくて、嬉しくて、妬ましくて、悩ましい。 言葉にできない感情がジャンの中で渦巻いている。 ﹁雲梯、取り付きました﹂ アルカスの報告に、目を凝らす。 一輌の雲梯が、城壁の最上部に鉤を掛けることに成功したようだ。 敵の抵抗。鉤が外され、梯子が倒れる。しかし、もう一度。 下から弓兵が支援し、再度梯子が固定される。 ﹁いけるか﹂ ﹁いけます。衝車も﹂ 城壁上の混乱に、衝車は格段に動きやすくなったようだ。 城門前に上手い具合にできた空隙に一輌、入り込んだ衝車が破城 槌で突き続けている。 守将であるカルキンはどうでるか。 自然とそう考えている自分に、ジャンは驚いた。視野が、広くな っている。 前のめりにならずに戦況を見渡すと、見えるものもあるはずだ。 ﹁アルカス、弓隊に伝令。向かって右の塔を狙え﹂ ﹁はっ。投石器も向かわせます﹂ 伝令が走り、弓が射掛けられる。 あの塔には逆襲部隊が集まっている気配があった。そこを攻撃し、 動きを鈍らせれば雲梯や衝車への反撃を遅らせることができる。 ﹁良い読みです、ジャン将軍﹂ ﹁前のめりにならずに済んだというところかな﹂ ﹁全体が、見えておられる﹂ アルカスからの呼び方が変わったが、敢えて指摘するほど無粋で 334 はない。 試験は一先ず合格ということだろう。 今回の攻撃は守将の失点で上手く行きつつあるが、そろそろ引き 上げだ。 祖父の読みでは、ドラクゥは<赤の軍>との対峙を選び続けるは ずだった。 攻城兵器部隊は脅威だが、単独でパザン市を掌握できるだけの規 模がないと読み切っているという“信頼”だ。 グラン・デュ・メーメルという将軍は、敵とその能力を信頼する。 その信頼に基づいて、敵の行動を戦棋のように読んでいくのだ。 ﹁そろそろ頃合いを見て、退く準備をはじめる﹂ ﹁傭兵たちは逸っておりますが﹂ ﹁深入りは禁物だ。どうせこの人数ではどうにもならない。そのた めに高い金を払っているのだ。その事は傭兵もよく分かっているだ ろう﹂ 予想外の事態は常に起こり得る。 ドラクゥがもし、グランとの戦いを放棄し、後ろを襲われること を看過しながらも攻城兵器部隊に逆襲を考えたとしたら。 それは、グランにとってもジャンにとっても厄介なことになる。 攻城兵器は素早く動かせないから、全て捨てていくことになるだ ろう。そうすれば再び準備するには多くの時間を要する。 今回はドラクゥに“こういう手もある”と見せるための攻撃だ。 そうすることで、ドラクゥの心に疑心暗鬼を生み、戦術の幅を狭 める。 やはり、グランはドラクゥとの戦いを楽しんでいるのだ。 気付かれぬように、衝車が退きはじめる。 雲梯も、目立つ二輌を除いて折り畳みが始まっていた。 全てを持ち帰ることはできないが、損害は許容できる範囲に収ま りそうだ。 そう思った時、背後の森から何かが聞こえてきた。 335 奇襲。 思わぬ伏兵から痛烈な一撃を受けたジャンは、この攻撃そのもの に疑念を覚える。 祖父グランは本当にこの攻撃を予見できなかったのか。 疑心が渦巻く中、ジャンの元を訪れたバルバベットはグラン・デ ュ・メーメルが裏切ろうとしているという可能性を示唆する。 336 第四章ダイジェスト ティル・オイレンシュピーゲルが通されたのは古い会議室だった。 今回の部屋は調度を全て中華風に揃えている。 “神界”に幾つか設えられているこういった部屋は、どれも華美 に過ぎず、それでいて凝った造りになっていた。持ち主の趣味なの だろうが、ティルには少し物足りない。 先に席に着いていた大天使たちがティルに気付いて顔を上げた。 その表情は様々だが、視線にはどれも軽侮の色が混じっている。 中にはあからさまに見下した目でティルを見ている者もいた。灰色 の髪を角刈りにした大天使だ。その顔を、ティルはしっかりと記憶 に刻みつけた。 どうしてここに呼ばれたのか。 理由はいくつか考えられるが、恐らく碌なものではない。思当た る節については、多過ぎて数え上げれば限がなかった。 程なく大天使長が入室し、一番の上座に着く。 一番の下座を占めることになったティルとは、対面の位置になる。 若々しい姿でいることを好む大天使の中にあって、大天使長だけ は小柄な老婆の姿をとっていた。 しかし、威厳があるという風ではない。 売れない元女優か何かと紹介されれば信じてしまいそうな風貌だ。 セシリーという名のこの大天使長の顔をティルが見るのは、これが 初めてだった。 ﹁さて諸君、定例外に集まって貰ったのは他でもない﹂ 口を開いたのは、会議の進行役を務めている大天使だ。先程ティ ルを小ばかにした目で見つめていた角刈りだった。 ﹁これまで長く停滞を続けていた“天界”で大きな動きがあった。 ごく一部ではあるが神や邪神が“天界”を離脱し、独立を宣言して いる﹂ 337 列席する三〇ほどの大天使たちが一斉に呻く。 これまでにほとんど想定されていない動きだった。“神界”は“ 天界”の活動を緩やかにさせ、事態の複雑化を防ぐ方向に物事を進 めて来ている。このまま世界の終りまで、対だと享楽に浸らせてお くのが既定の路線だ。 その前提がここに来て、根本から崩れる恐れが出てきた。 ﹁数はどうなのだ。ごく一部、というのは﹂ 尋ねたのは、隻腕の女大天使だ。長髪をサイドに垂らした文句な しの美人だが、少し近付き難い凛々しさがある。 ﹁まだはっきりとは分からない。現在確認できているのは一〇柱に 満たないが、“天界”の非主流派の中には同調の動きがある﹂ ﹁たった一〇柱の神が離脱した程度で、大天使を招集するのか?﹂ ﹁⋮⋮その中には、<戦女神>ヨシナガも交じっているのだ﹂ 今度の呻きは先程よりも深いものになった。ヨシナガという名に は、ここの大天使たちを刺激する何かがあるのかもしれない。女大 天使が今はもう無い片腕を擦っているのが、ティルの目には奇異に 映った。 角刈りが続ける。 “独 ﹁この“独立派”が単に彼らの政治的主張の為に集っただけであれ ば、“神界”への脅威はほとんどない。しかし厄介なことに 立派”の中には魔界の現在の<大魔王>が信仰する邪神、ヒラノが 含まれている。そして愚かなことにこのヒラノという邪神は科学技 術の提供を惜しみなく行う方針を採っている可能性がある﹂ ヒラノの名を聞いた時、ティルは思わず小躍りしそうになった。 白鳥城から<戦女神>ヨシナガを攫ったところまでは把握してい たが、まさかそんなにおもしろいことになっていたとは。 “天界”からの独立という発想も良い。何なら“神界”からそち らに寝返ってもいいくらいだ。もちろん、そこまでの軽挙はしない が、将来の方策としてはあり得る。 そして、獅子身中の虫としてヒラノに復讐をするのだ。 338 ﹁惜しみなく、というのはどの程度か?﹂ 別の大天使の質問に、角刈りは不快そうに顔を歪めた。 ﹁⋮⋮全て、と考えて貰って構わない。“神界”と“天界”の条約 に掣肘されない彼らの勢力は、基本的にありとあらゆる技術の発展 を容認する可能性がある。既に彼らが紙の技術を下界に開放したこ とも確認されているのだ。魔界では最低でも二つ、多ければ五つの 製紙工場が既に稼働状態にある﹂ ﹁馬鹿な、早過ぎるぞ﹂ ﹁これまで無理に押さえ付けてきたのだ。社会の進歩が歪である以 上、必要とされる素地はあったと考えるべきだ。そしてさらに憂慮 すべきことに、彼らの領域に錬金術師が逃げ込んだ恐れがある﹂ その言葉に、上座の大天使長セシリーが反応した。 書見用の眼鏡を取り、両掌を合わせて唇に当てる。 ﹁それは大きな問題ですね。これまで“聖堂”は何をしていたのか﹂ 凛とした声に、場が静まり返った。ほんの少し前までは小柄な老 婆にしか見えなかったのが、今ではその威厳は一国の女王にも匹敵 する。いや、正に今の彼女は“神界”を統べる女王のような立場に いるのだ。 ﹁“聖堂”には錬金術師を狩り出すように神託を何度も下しており ます。高い技術力を持ったものはほとんど始末を終えているという 報告は受けております﹂ ﹁その方針自体は問題ないでしょう。唯一神の御心に叛く背教の輩 は誅されるべきですからね。問題となるのはその方法です。どうし て彼らを一網打尽にできなかったのか﹂ ﹁はい﹂ 俯いた角刈りが視線を臨席の大天使を見遣る。その男が、“聖堂 ”の担当者の様だ。 視線を向けられた男は居心地が悪そうに腕を組み、小さく咳払い をした。 大天使といえども、大したものではない。少なくともティルには 339 そう見える。 徳をどれだけ持っているか、ということなのだろう。この中で悪 戯を仕掛けて楽しそうなのは、大天使長とあの長い髪の女大天使く らいしかいない。 ﹁いずれにしても、状況はあまり芳しくないようですね﹂ ﹁現在、詳しい状況は調査中です﹂ ﹁構いません。調査は打ち切りにしましょう﹂ 大天使長の強い語調に、大天使たちの視線が集まる。 ﹁“聖堂”に神託を。錬金術師が逃げ込んだという都市ごと、踏み 潰してしまえばよろしい。そうすれば何も後腐れはありません﹂ ﹁しかしそれでは⋮⋮﹂ 損害が大き過ぎる、とでも言おうとしたのだろう。 しかしその大天使は二の句を告げなかった。 ﹁唯一神の御名の元に!﹂ ﹁ゆ、唯一神の御名の元に!﹂ セシリーがそう口に出すと、慌てて周りの大天使たちも唱和する。 それで全てが決まった。議題は“聖堂”にどのような神託を下す かという方に移る。 “聖堂”の僧侶たちは神託に基づいて行動するが、微妙な言い回 しについての理解に齟齬があると、思わぬことをすることがあるよ うだ。 大天使たちが魔界侵攻の策を次々と組み立てていく。 一度方針さえ決まれば、会議は上手く進むようだ。“聖堂”軍に 加護を与えるため、どの程度の天使を動員するのかが慎重に話し合 われる。 その様子を詰まらなそうに見ていたティルに、上座から声が掛け られた。 ﹁ティル・オイレンシュピーゲルと言いましたね。話があります。 奥の間へ﹂ 340 一対の椅子と小さな卓、それだけの部屋だった。 壁の四方は白く塗り固められ、明かり取りの窓が天井近くに一つ あり、そこから柔らかい光が差し込んでいる。暗くもないが、明る くもない。 白で統一された中に一点、卓の上の一輪挿しに赤い花が活けられ ている。 ティルの知らない花だった。 ﹁どうぞ、お座りなさい﹂ 席を勧めるセシリーはたった一人だ。護衛もいない。 もっとも、懸絶した徳の違いがあるから、不埒なことを考える者 もいないのだろう。 椅子に座る所作の一つ一つがたおやかで、ほんの少し前に大天使 を一喝して黙らせた女傑と同じ女性とは思えない。 ﹁ここに呼ばれた理由は分かりますね?﹂ ﹁いいえ、分かりかねます﹂ ティルの答えを聞いて、セシリーが柔らかく微笑む。 冗句の一つでも言ってみようかと思ったが、物静かな雰囲気の奥 に見え隠れする何かに気圧され、止めた。大天使長というのは、名 前だけのものではない。 悪戯の神としての本能が、ティル・オイレンシュピーゲルにそう 教えている。 ﹁⋮⋮ヴィオラのことです﹂ その名前を呟くとき、セシリーはまるで秘密の魔法でも唱えるよ うに、静かに、はっきりと、そして密やかな口調だった。 すぐには返答せず、ティルは椅子の背もたれに身体を大きく預け る。何か交渉して引き出せる相手でもないということは分かってい た。だが、性分がそうさせてしまうのだ。 ティル・オイレンシュピーゲルは、ヴィオラのことなど何も知ら ない。 古い記録を調べ、推測に推測を重ねて彼女が唯一神の娘だという 341 結論に到っただけだ。 そのことも“天界”でスパイ組織を差配していた<初神者喰い> のヨハンに漏らしただけだ。それがこれだけの短時間でセシリーの 耳に入っていることに、正直驚いていた。 ﹁知っている、ということはご存知でしょう?﹂ ﹁私が貴方に尋ねているのは、どこまで知っているのか、というこ とです﹂ 知的な光を湛えた女大天使長の瞳を見ていると、抗い難く全てを 話してしまいたくなる。きっと、そういう奇蹟を身に付けているの だろう。こういう相手とじっくり話をするのはなかなか骨が折れる。 ﹁大凡のことは、知っています﹂ ﹁大凡、とは?﹂ ﹁大凡は大凡です、セシリー様。口に出すことも憚られる真実も含 めて﹂ ﹁⋮⋮なるほど、大凡の事は知っているようですね﹂ ヴィオラは、唯一神の娘だ。 通婚を禁じられている神々の中で、実際に子を成したものは非常 に少ない。 ティルの知る限り、<風の神>リルフィスと、唯一神だけのはず だ。しかも、リルフィスの娘は人である。神として扱われているの は、ヴィオラだけということになる。 ﹁⋮⋮では、何処にいるのかも?﹂ ティルは口を噤み、活けられた花の赤に意識を集中した。 ここで知らないと一言いってしまえば、会談はここで終わりだ。 恐らくティル・オイレンシュピーゲルは世界の終りまでセシリーと 再び見える機会はないだろう。 下手をすると、色々な理由を付けて消されることさえ考えられた。 ヴィオラという女神が、唯一神の娘であるということが大きな秘 密であるということは、考えなくてもよく分かる。 ﹁それをお教えする理由は?﹂ 342 ﹁ティル・オイレンシュピーゲル、質問に質問を返すのはよくあり ませんね﹂ ﹁しかし、そうせざるを得ません、セシリー様。ボクにはヴィオラ 様について貴女にお話していいかどうかの、確証が得られないので す﹂ ハッタリだった。 ヴィオラの件については、ひょっとすると大天使長の権限の埒外 にあるのではないか。その可能性に賭けたのだ。 唯一神にも親心があるのなら、娘については好きにさせているか もしれない。 セシリーは、答えなかった。 ティルは心の中で密かに想い人に感謝する。危ない橋を当たる時、 いつもティルはクリスティーナの顔を思い浮かべることにしていた。 ﹁ヴィオラの居所を、知る必要があります﹂ ﹁知る必要がある、というのは穏やかではありませんね。大天使長 の力を使えば、すぐに見つけることはできるのではありませんか﹂ ﹁ティル、事態は秘密裏に進める必要がある事くらい貴方も分かっ ているでしょう?﹂ ヴィオラが唯一神の娘であることを伏せたまま、行方を知らなけ ればならない。 その為には大天使長の権限を使うことができないのは当然だった。 しかし何故、セシリーはこれほど焦っているのだろうか。 唯一神の娘がいなくなったというのは、確かに重大事だ。大天使 長の忠誠が篤いというのも、理解できる。ただ、その焦りの方向に 何か違和感を覚えるのだ。 ﹁どうしてヴィオラ様の居所を知る必要があるのです? それも、 早急に﹂ ﹁行方不明になっている者がいれば、探すのが当たり前でしょう﹂ ﹁それは分かりますが、焦ることはないでしょう。この世界に、神 を害せるものなどありはしないのですから。ゆっくりと探すわけに 343 いかないのは、何か理由が?﹂ ﹁貴方の知るべきことではありません、ティル﹂ ﹁では私も、知っていることを貴女にお話することはできません。 セシリー様﹂ 向けられる視線が、冷たく刺すものに変わった。 やはり、セシリーは焦っている。少し、悪ふざけが過ぎたかもし れない。 ここでまさか知らないと明かしてしまえば、消滅させられる恐れ さえある。或いは、世界が終わるか自分でアガリを迎えるまで拷問 に掛けられるという可能性もあった。 それはどちらも、ティルの趣味ではない。 ﹁分かりました、セシリー様。ここは一つ別の方法を使いましょう﹂ ﹁⋮⋮聞くだけ聞きましょう﹂ ﹁ボクが、ヴィオラ様をお連れします。そうすればお互いに、話し たくないことは話す必要がない。違いますか?﹂ ﹁ふぅん、なるほど。考えましたね﹂ セシリーが身を乗り出し、顔が近付く。 吐息を頬に感じるほどの距離になると、老いているとは思えない ほどの艶がある。 ﹁⋮⋮本当は何も知らないのでしょう?﹂ ﹁⋮⋮だとしたら?﹂ ﹁適当なことを言って、逃げるつもりね﹂ 背筋を冷たい汗が伝うが、顔には出さない。 それでも、凄まじいまでの威圧感にたじろぎそうになる。 ここで、死ぬかもしれない。死自体は全く怖くないが、この世界 ではまだやり残したことがある。そう考えると、射竦められたよう に動けなくなった。 ﹁⋮⋮ま、いいわ。今回は見逃してあげる﹂ 不意に、威圧感から解放される。 思わず椅子からずり落ちそうになるのを、何とか踏みとどまった。 344 悪戯を愛する者は、常にスマートでなければならない。 ﹁では早速、取りかかります﹂ ﹁そうね。なるべく早くして頂戴。年寄りは少しせっかちなの。さ もないと﹂ ﹁さもないと?﹂ セシリーは、今日見せた中で一番の笑顔を見せる。 ﹁苦しむのは、貴方ではなくてクリスティーナ・フォン・マルクン トになりますよ﹂ 押し寄せる<聖堂>軍に、クォンたちは新戦術で臨んだ。 電信を使い、各塹壕が連携して戦う。連弩と組み合わせたこの戦 い方により、クォンは敵を上手く翻弄することに成功する。 ヒラノたち邪神も戦う中、エリィナはもう一つ大きな作戦を仕掛 けるために動いていた。 345 第五章ダイジェスト 外套の襟を掻き合わせた。 初秋とは言え、草原では払暁前にはっとするほど寒くなることが ある。 気の利いた従者が、本陣の火鉢に火を熾した。これで少しだけ、 過ごしやすくなる。 視線の遥か先に、<赤の軍>が野営をしている火が見えた。師で あるグランも、この寒さに耐えているのだろう。そう思うと、ドラ クゥの胸に言い表せないものが去来する。 かつてあれだけ多くの事を教えてくれた師が、敵になった。 事情があったということはダークエルフの調べで分かっている。 グラン・デュ・メーメルを縛る策略を、<北の覇王>は隠そうとす らしていない。 三族誅滅。 古い刑罰だ。元は九族誅滅であったものが、時代と共に六族にな り、三族になった。 咎のあった者の三親等以内の者を血族姻族の別なく、鏖殺すると いう大時代的な処罰は、今の時代にはそぐわないとドラクゥは考え ている。 まして、その刑罰を盾に誰かの行動を自由に操ろうなどというこ とは、上に立つ者のすべきことではない。 そういう風にして始まったのに、師はこの戦いを楽しんでいる。 互いの知恵を限界まで引き出して、戦う。そういう戦棋じみた戦 いが、パザンの北では続いている。ドラクゥでさえ、古い書物の中 でしか見たことのないような戦術を、グランは余すところなく繰り 出してくるのだ。 損害は無視できない所にまで来ていた。薄皮を剥がすように、歩 兵が削り取られていく。 346 相手は<赤の軍>だ。油断をすれば、一回の攻撃を受けただけで も再起不能に陥ることにもなりかねない。 ただ、敵にも疲労は貯まりつつある。騎兵を長期間全力で戦える ようにしておくことは難しい。馬は辛抱強い生き物だが、兵士ほど ではないのだ。 いや、敵の兵も疲れているのかもしれない。シュノンの報せでは グラン・デュ・メーメルは毎晩、<赤の軍>の兵達と膝を詰めて話 し込んでいるという。一組一組の数が少ないので、ダークエルフと いえども紛れ込むことは難しいらしい。 何を話しているのかは分からないが、毎夜毎夜何組もの兵と話を する底抜けの体力には、老いが全く感じられない。 全身全霊を賭けた戦いの中で、ドラクゥの方もこれまで試したこ とのない戦術を試してみたりもする。師との対陣は、肉体よりも精 神に疲労が貯まるものになりつつあった。 ﹁主上、南の戦いは膠着しておるようです﹂ 本陣に入って来たのは、ロ・ドゥルガンだった。 元々傭兵生活が長かっただけあって、歩兵の扱いでは思わぬ巧妙 さを見せる。 その腕を買って、ドラクゥはこのゴブリンジェネラルの猛将に、 遊撃隊を任せていた。パザンとこの本陣の間を自由に動き回り、< 赤の軍>による連絡線の遮断を防ぐ狙いだ。 ﹁膠着か。圧し込まれているわけではないのだな﹂ ﹁はい。事前の準備が良かったのでしょう。人界側は塹壕を攻めあ ぐねておるようです﹂ ﹁元々は相手の戦術だというのにな﹂ ﹁だからこそでしょう。騎兵を使って迂回突破すれば、孤立する塹 壕は脆い。そんなことは子供にだって分かる道理です﹂ ﹁それをクォンは何とかしたということだな﹂ ﹁戦場の絵図面を見せて貰いましたが⋮⋮あれだけの範囲を塹壕で 囲んで相互に連結させておけば、後方に回り込むのは指南でしょう。 347 丘や林も上手く使っています﹂ 新しい戦術、というわけだ。 それも小手先のものではなく、考え方自体が違う。兵と兵がぶつ かり合う戦場で、それだけ長大な塹壕を掘るということはこれまで の戦いでは考えられなかった。 特殊な条件が重なって初めてできたことだが、それでも、その着 眼点の新しさは賞讃されるべきだ。 ﹁それと、電信だな。あれがないと、広い塹壕の全てに指示を出す ことは不可能だ﹂ ﹁ええ、あれは大層便利なシロモノです。ああいうものが戦場にあ ると、色々とできることの幅が広がる﹂ ﹁だが、塹壕のような固定した陣地でしか使えないのではないか?﹂ ﹁それもまた工夫でしょう。何にしても笛や太鼓や鉦、喇叭でドン チャン騒ぎをしなくても部下に指示が飛ばせるというのは、その、 助かります。実際にどう使うかというのは、そっちの方に向いた賢 い奴が考えればよいのです﹂ ﹁そういう考え方もあるか﹂ 南での戦いの様子は、フィルモウから詳し過ぎるほどの報告が届 けられていた。 ドラクゥはあまり心配していない。心配しても意味がないからだ。 何かあっても、手助けに行ける距離ではない。 北での敗北は、南での敗北。南での敗北は、北での敗北。 どちらの戦いも、負けることの許されない戦いだ。それだけに、 持てる全ての力を出し切らねばならないという意識がある。 ﹁ロ・ドゥルガン。電信をこちらの戦場でも役立てることはできな いだろうか﹂ ﹁そう仰ると思って、数日前に銅線と邪神官、それにゴナンをこち らに寄越してもらえるよう、書状は送っております﹂ ﹁やけに手回しが良いな﹂ ﹁奥方様の入れ知恵ですよ。ラーナ様も電信には興味がおありの様 348 で、エリィナ様と書状のやり取りを。私はそれに乗っかっただけで す﹂ ラーナらしい、と言えば実にラーナらしい。 文官としては有能なシュリシアでも、新しいものにここまで関心 は示さないだろう。あるものでどうにかするという意識の方が強い。 ラ・バナンの特質は、また違うところにある。電信というものが 普及した後にそれを上手く差配する方法を考えるのには、最も適し ている男だ。 そういう能力の差も、見極めてやらねばならない。 ﹁なるほど。しかし、ゴナンもか。報告では辞書は既に完成したと あったが﹂ ﹁ゴナニリフ、でしたか。やはりアレは実用には適さないというか、 いろいろ難しいようです。クォンが何か工夫を思い付いたようです が、まだ実践の段階ではないと。ですから念の為、ゴナンも送って 貰うように頼みました﹂ ﹁それもラーナの入れ知恵、という訳か?﹂ ﹁はっはっはっ。御見通しですか。主上の前では隠し事はできませ んな﹂ ﹁ラーナの事はよく知っている、というだけだ。その実験は、遊撃 部隊の方で頼むぞ﹂ ﹁ええ、不確かなものを使わせてくれるほど<万化>の爺さまは甘 くないですからな﹂ 豪快に笑いながら、ロ・ドゥルガンは本陣から出ていった。 悠然と歩いているように見えて、意外に速い。兵卒にどう見られ ているかを計算しつつも、仕事は早くこなしたいということだろう。 戦場での一刻は千金に当たる。その事が理解できている部下を得 られていることに、ドラクゥは密かな満足を感じていた。 陽が東から昇るのに合わせ、タイバンカの指揮する前衛が慌しく 戦の支度を始める。 師の<赤の軍>はまだ、不気味な静けさを保っていた。 349 五〇〇〇騎。 それが、<千変>のジャンに新たに与えられた戦力だった。 ただの五〇〇〇ではない。魔界最強の騎兵、<赤の軍>を五〇〇 〇である。 装備、練度、忠誠。 どれ一つ取っても、何の不満も懐きようのない戦力だ。 それを、ジャンは苛めるように走らせた。 朝は払暁前から、夕は隣を走る兵士の顔が判然としなくなるまで。 幾度かの休憩を走りながら、ただひたすらに駆ける。 ジャンの思い付きではない。れっきとした、<万化>のグランの 指示だ。 <赤の軍>を率いて、グランとドラクゥの対峙する草原の一角を 窺う獣王の斥候を討つ。 任務の割には、過剰な戦力だ。 騎兵に慣れさせようとしている。 命令を受けながら、その言葉の端々にジャンは反感を覚えた。 直接の薫陶は受けていなくとも、魔軍騎兵総監の孫だ。 他の何よりも熱心に、魔軍騎兵操典は読み込んでいた。諳んじて、 各頁に注釈をつけることもできる。魔軍の同輩の中では最も騎兵に 詳しいはずだ。 その自信は、一日目に打ち砕かれた。 二〇〇の“馬に乗った兵”を扱うのと、五〇〇〇の“精鋭騎兵” を扱うことは、全く違った種類の技能だ。その事を、隊列の最後尾 を走りながら思い知った。 騎兵を指揮して率先垂範を示すには、まず自身の馬術の腕前が不 可欠なのだ。 老いた祖父の背が曲がっているのを見たことがない理由を、ジャ 350 ンは初めて知った。 駆け、休み、また駆ける。 獣王の斥候はどれだけ討ち払っても、湧き出すように現われた。 移動城市サスコ・バウに漸く大部隊を集結した<西の獣王>とし ては、自分の領内で好き勝手に戦いを続けるグラン・デュ・メーメ ルが気に食わないのだろう。 斥候の規模は日に日に大きくなるが、それでもまだ、余力を持っ て撃退できる。 本格的にぶつかることにはあちらもまだ抵抗があるのかもしれな い。 ﹁そろそろ、馬の背にも慣れたか﹂ 報告に訪れた野営では、グラン・デュ・メーメルが自ら迎えてく れた。 部下にも馬乳酒が振る舞われている。ジャンがパザン東壁で敗走 させた傭兵隊は、オルビス・カリスと野営地の間を往復する輜重隊 の護衛として使われているようだ。 ﹁はい。慣れたかどうかは分かりません。ただ、脾肉は締まってき たように思います﹂ その答えに満足したように、グランは何も言わず頷き、馬乳酒の 椀を呷った。 度を過ごすほど飲むとは聞いたことがないが、今晩の祖父は顔が 赤い。篝火に照らされているからだろうか。 オルビス・カリスで飲んだ物と違い、ここで供される馬乳酒は割 らずに飲む。酸味が強く臭いもきついが、飲めば気持ちが落ち着い た。 火に照らされる部下たちの顔を、ジャンは確かめる。 顔と名前を一致させるのは、疾うに諦めていた。一〇〇〇人まで は覚えられるかと思ったが、その先はどうしても無理だ。二〇〇を 統禦する方法と、五〇〇〇を統禦する方法は違う。まして、二万と もなれば全く異なる世界の話になるだろう。 351 今、祖父が対峙しているドラクゥは最大で十九万の大軍を率いた ことがある。 対する<北の覇王>は二十四万だ。その数の大きさは、二〇〇を 指揮しているだけでははっきりと理解できなかった。今ではその偉 大さと異常さが、少し分かる気がする。 一〇〇〇を超える兵を指揮すると、それは兵であって兵ではなく なる。 血の通った部下であるが、同時に、数字としか見られなくなるの だ。そのことが悲しいと思いつつも、それでいいのだと考える自分 もいることを、もうジャンは知っている。 パザンでは、多くの部下を失った。 顔も名前も一致した傭兵が、多くいたのだ。 それを失いつつあった時、心は圧し潰されそうになっていた。正 常な指揮が執れていたとは、思わない。あの場合、被害を減らすた めに少しでも早く退くべきだったのだ。 情が移れば、指揮はできない。 情が移ってもなお、鋼の精神力があれば指揮ができるのかもしれ ないが、今のジャンにはそれはまだできそうになかった。 グランが、炙った鳥の腿肉に齧り付いている。 脂が口周りの髭を汚すが、不思議と格好良く見えた。ジャンも倣 って、骨付きの炙り肉に手を出す。 よく焼けた皮の中から肉汁が滲み出し、思わず声を上げそうにな った。 それを、祖父が微笑ましげに見ている。 思えばこんな夕餉を共にしたのは、初めての事かもしれなかった。 ﹁美味いか、ジャン﹂ ﹁ええ、美味いです。とても﹂ ﹁長期の帯陣では、粗餐に耐えねばならん。冬の寒い中でも、火の 通っていないものだけを何日も食べたりすることもあるし、酷い時 には何もなかったりだな。だが、たまにこういう食事にありつける 352 と、堪らなく美味い﹂ ﹁ダーモルト殿のお陰ですね﹂ ﹁ああ、あの爺様には感謝せねばならん﹂ 魔都からオルビス・カリスまでの船便が妖鳥族に襲われていると 知ると、ダーモルトはすぐさま船にハーピィ族の傭兵を据えた。予 算が付くはずはないから、四秘で賄ったのだろうとグランは笑った が、それほど安いはずはない。 魔都の政治は複雑怪奇で、ジャン如きでは見通すことができなか った。ダーモルトのようにその闇をも使いこなす文官がいればいい が、そうでなければ弊害の方が大きいという気もする。 祖父や、ダーモルト。それに、<北の覇王>ザーディシュ。 こういう老臣がいなくなった時、自分のような若い世代は魔界を 担えるのかという不安が、不意にジャンを襲った。 ﹁そう言えば、<青>のダッダと戦ってみて、どうだった?﹂ ﹁⋮⋮アルカスに報告させた通りです﹂ ﹁お前自身の口から、聞いてみたい﹂ 大徳利から馬乳酒を注ぎ足しながら、グランが尋ねる。その目は 酔っているように見えて、鋭い。しかし、将帥の目というよりは場 末の酒場で賭け戦棋をしている者の目のようにも見える。 ジャンの中で、疑念がまた渦巻き始めた。 バルバベットの書状は、分からないように軍装の隠しに仕舞って ある。 祖父は、内通の首尾を確かめようとしているのではないか。 ﹁見事な伏兵でした。こちらは森の間道を使って行軍しましたが、 その間、誰も敵に気付きませんでした﹂ ﹁斥候は?﹂ ﹁奇襲でしたので、最低限に。敵の部隊の動きには、十分配慮をし ていたのですが﹂ ﹁十分ではなかった、ということだな﹂ ﹁⋮⋮はい﹂ 353 譴責という口調ではない。ただ淡々と、事実を延べているだけだ。 そもそもグランの目は、ジャンを見ていてジャンを見ていない。 遥かパザンの森の中に、人熊の部隊を見出そうとしているようだ。 ﹁装備はどうだ。何か変わったことは?﹂ ﹁普通の弓と併用して、速射性の高い弓を使っていました。後は、 全身を汚して森の中に溶け込んでいたようです﹂ そう言った瞬間、目の前の祖父が呵々と笑い始めた。 ﹁ハツカだ。やはりハツカは向こうに付いたな﹂ ﹁ハツカというと、お弟子の?﹂ ﹁ああ、ハツカは三弟子の中でも一番伏兵が巧い。いや、上手いな んていう言葉では失礼に当たるな。邪神懸っている﹂ ﹁それほどまでに、ですか﹂ ﹁ああ、そうだ。ジャン。恥じ入ることはないぞ。あれの伏兵は、 儂でもおいそれとは見破れぬからな﹂ 祖父の言は、事実か欺瞞か。 内通の疑念を抱かれないために、演技をしているのではないか。 そういう風な目で祖父を見てしまう自分を恥じながらも、ジャンは 全てを信じ切ることができない。 何と言っても祖父は、<万化>のグランなのだ。 ﹁しかし未だに腑に落ちないのは、どうやってあの場に伏兵を移動 できたかということです。部隊の動きは全てシェイプシフターに逐 一報告させていたのです﹂ ﹁簡単だよ。移動していない﹂ ﹁移動、していない?﹂ ﹁そうだ。それがハツカの伏兵の妙技たる由縁だな。最初から、伏 兵する場所に伏せていたのだ。恐らく、五日はその場にいたのでは ないかな﹂ ﹁そんなことが﹂ ﹁できるはずのないことをするのが、謀術というものだ﹂ 仮にそんなことができるとして、どうして場所が分かったという 354 のだろうか。 あの間道は、シェイプシフターの物だ。ドラクゥがパザンを制圧 した後も、調査が入ったという形跡はなかった。 ﹁やはり妙です。それならどうしてあの場所に伏兵を置くことがで きたのか。こちら側に内応している者が⋮⋮﹂ ﹁内応している者がいるかいないかは知らんが、ハツカに限って言 えば、そんなものがなくてもあの場所を読み切ることくらいはする だろうな﹂ ﹁しかし、あの間道は⋮⋮﹂ ﹁知っているということを知られないようにする、というのは基礎 の基礎だ。ドラクゥもその事はよく理解している﹂ ﹁どうしてそこまで自信を持って断じることができるのですか!﹂ 激高し、思わず地面に打ち付けた椀が跳ねる。 中身の馬乳酒が軍装を汚したことも気にせず、グランは小さく鼻 を鳴らし、少しだけ気恥ずかしそうに呟いた。 ﹁それはそうじゃろう。どちらも、儂の弟子だからな﹂ 信じていいのか、疑うべきなのか。 祖父を助けるべきなのか、<北の覇王>に従うべきなのか。 書状は本物なのか、偽物なのか。 宵闇の中で炎に頬を炙られているからか、それとも酒が回ったの か、ジャンの頭の中には様々な疑問が去来し、混淆されていく。 はっきりとした感情は、羨望だ。或いは嫉妬と言い換えても良い かもしれない。 祖父がそれだけ手塩にかけた三弟子に、ジャンは言い知れないも のを感じている。 つまりそれは、ジャンが祖父を慕っているということだ。 魔都を出るまでは憎みこそすれ、ここまでの気持ちを抱くことに なるとは思っていなかった。いや、最初からそうだったのかもしれ ない。名前の付けられない感情を、無理矢理憎しみと思い込んでい たのだという気すらしてくる。 355 バナー モットー だが、そのことが、ジャンの為すべきことを決めてくれるわけで もない。 <赤の軍>の戦旗が目に入る。旗幟にはただ一言、“忠義”。 忠とは何か。忠に殉じたいという気持ちが、ジャンにはある。 その忠をどこに向けるかが、問題なのだ。 ﹁デュ・メーメル将軍、戦争とはなんでしょうか﹂ 口を突いて出たのは、愚にも付かない問いだった。 この貴重な時間を割くには、あまりにも惜しい。哲学に属する質 問を、武官である祖父に投げてどうするのか。答えなど、明確に帰 ってくるはずがないのだ。 しかし、返事は思わぬ物だった。 ﹁政治だよ、戦争とは﹂ ﹁政治、ですか﹂ ﹁政治の延長というべきだな。政治そのものではないが、一部では ある﹂ ﹁しかし戦争は武官の物で、政治は文官の物です﹂ 言ってしまってから、莫迦な物言いをしたと思った。そんな当た り前のことを言ってしまう自分が、途轍もなく恥ずかしい。祖父に、 莫迦と見られたくないという気持ちが今の自分を支配していること にジャンは気付いた。 ﹁武官も文官も、大魔王の臣下だ。言ってしまえば、統治の手足と いうことになる﹂ ﹁大魔王の臣下﹂ ﹁そうだ。頭があって、はじめて手足は動く。そういうものだ﹂ ﹁しかし先程、戦争は政治の延長だと﹂ ﹁ああ、少し言葉を惜しんだようだ。つまりは、政治も戦争も、目 的を達成するための手段ということになる。だが、政治の為に戦争 をすることはあっても、戦争の為に政治をすることはあってはなら ない。そういうことだ﹂ 言われてみれば、そうだという気がする。 356 だが、戦争をする為に政治の方を捻じ曲げた例は魔界の歴史の中 では枚挙にいたと間がない。武官の暴走は、しばしば魔界の統治を 危うくしてきた。その事を、祖父は簡素な言葉で痛烈に批判してい る。 ﹁では、将軍は統治に対する忠誠こそが大切だと考えている、と?﹂ ﹁それこそが魔界を魔界たらしめている。武官が武官で好き勝手に 動けば、魔界はすぐに倒れてしまうだろうからな﹂ ﹁それでは何故⋮⋮﹂ ﹁⋮⋮それでは何故?﹂ 言葉が喉に絡まる。頬が熱い。動悸が、速くなる。この一言を発 わたくし すれば、後には引けなくなるだろう。それでも、問わねばならない。 ﹁⋮⋮それでは何故、将軍はこの戦いを私しているのですか?﹂ 場が、水を打ったように静まり返った。 いや、そんなことはない。周りの兵たちは気付かずに談笑を続け、 酒を酌み交わしている。祖父が発した気迫が、そう感じさせたのだ。 ﹁この戦を、自分自身の物にしていると? 儂が?﹂ ﹁そのように、見えます﹂ ﹁そう見えるか﹂ ﹁少なくとも、楽しんではおられる﹂ ﹁楽しんでいるか﹂ ﹁まるで、ドラクゥと戦棋の盤を挟んでいるように見えます﹂ そう指摘すると、祖父は口角を上げて、申し訳なさそうに笑った。 こういう表情をするのを、はじめて見る。 ﹁そういう面が、ないでもない。戦棋で儂と互角に指せる者など、 そもそもあまりおらんのだ。弟子をとっていた時も、ハツカ、ドラ クゥ、シーナウの三面を相手にしていた﹂ ﹁それは、戦争の私的な利用ではありませんか﹂ ﹁おいおい、勘違いするなよ。儂は、勝とうとしている。相手も、 勝とうとしている。そのやり取りが結果として楽しいのであって、 楽しむために戦っているわけではない﹂ 357 ﹁ならばどうして全力でドラクゥを攻めないのです? 少しずつ削 り取るような戦い方しかしておられません﹂ ﹁全力でぶつかるだけが戦争ではない。それに、ジャン。この戦い の目的を忘れては居らんだろうな﹂ 目的、と言われてジャンは咄嗟に言葉が出て来なかった。 ドラクゥを倒し、南方を安定させる。魔都の支配が行き届く領域 に復さねばならない。 それが、出征に当たっての命令だった。 ﹁しかしあれは、絵空事です﹂ ﹁絵空事だよ。あんな大目標、いくら精鋭とは言え騎兵二万にさせ る仕事ではない﹂ ﹁では⋮⋮﹂ ﹁できぬ戦争でも、しなければならん。三族誅滅のこともあるしな﹂ ﹁三族誅滅ですか﹂ 祖父が反旗を翻せば、人山羊の魔王は誅滅の対象になる。 その事が祖父に出征を決意させたということは、ジャンも聞いて いた。大恩ある相手の為ならば、無理な戦いもしなければならない。 ﹁だからこそ、ドラクゥとの決戦は、機を図らねばならぬ﹂ ﹁どういうことですか?﹂ ﹁この大目標を達成するには、一度の決戦で敵を完膚なきまでに叩 き潰さねばならんということだ。決戦の地以外に余力を残した状態 で勝ったとしても、敵将を何とかできなければ再起される恐れがあ るだろう。﹂ ﹁ではまさか﹂ ﹁そうだよ。大目標を達成する為に、策を練っているのだ。騎兵二 万で敵を制する。これほど楽しい詰め戦棋はなかなかないぞ﹂ そう嘯く祖父の目を見て、ジャンは全てがどうでもよくなった。 自分は、祖父が好きだ。それでいい。 壮語している大作戦が本当か嘘かなどは、どうでもよくなってい た。 358 軍装の隠しから、バルバベットの書状を取り出すと、それを火に くべる。 燃えていく書状は祖父にも見えている筈だが、何も言わない。 全てが燃えて灰になった後、祖父が馬乳酒の並々入った椀を、手 渡してくれる。 ついにグランの軍が、動く。 その酒は、これまで飲んだどんな酒よりも、美味く感じられた。 ` 一匹の獣のように襲い掛かる︿赤の軍﹀に対し、ドラクゥは持て る全ての策を振り絞って迎撃する。 しかし、戦いの決着がつこうとしたまさにその時、これまで座視 していた獣王の軍が不気味に動き始めるのだった。 359 第六章ダイジェスト 卑怯だ、という考えはほとんどなかった。 むしろこうでもしなければ倒せない相手だ、と思っている。 だからリ・グダンはこの進軍に意を唱えなかった。積極的に賛成 さえしたのだ。 その見返りとして、<西の獣王>から幾らかの兵を預けられた。 必死に鍛え上げた部隊は、もう残っていない。生きているのは、 オクリ神に助けられたリ・グダン自身とカルティアだけだ。それほ どまでに、<赤の軍>は強かった。 今回の進撃の決め手になったのは、誰かの入れ知恵だという噂も ある。 シェイプシフターの奸計だとも、<皇太子>レニスの腹心の策だ とも言われていた。実際にそういう者を見たという話も聞く。 だが、そんなことはリ・グダンにとってはどうでもいい。 どうやってドラクゥと、グランを倒すかだ。 草原を埋めるようにして、獣王の軍が進む。 途中で現われた<赤の軍>の分遣隊五〇〇〇には、一万の兵を当 てていた。倒そうとは考えていない。精強を以って知られる<赤の 軍>を諸部族連合の兵がどうこうできるはずがないのだ。その場で 拘置させることが目的だった。 相争うドラクゥとグランを、六万の兵で襲う。それが<西の獣王 >ガルバンドの策だった。 策と呼べるほど高尚なものではない。ただ、力で叩き潰す。そう いう戦い方の方が、小細工は却って通じないものだ。 その一隅を、リ・グダンは占めている。与えられた兵は一千と少 ないが、この戦いで功を上げようと逸る若者だけを集めた、良い部 隊だ。 これならば、良い働きができるかもしれない。そういう気合いが、 360 充溢している。 遠目に見えていた丘陵が、次第に近付いてきた。 事前に獣王から伝えられていた情報の通り、ドラクゥとグランは 雌雄を決するつもりになったようだ。これまで長々と対峙していた が、決戦となると速い。 既に趨勢は決したのだろう。丘一つを使った陣は、不気味に静ま り返っていた。 ﹁カルティア。どっちが勝ったと思う?﹂ ﹁<万化>のグラン・デュ・メーメルでしょう。あの老将には底知 れぬ恐ろしさがあります﹂ ﹁そうだな。グランは強い﹂ だが、それでもドラクゥは生きている。その確信が、リ・グダン にはある。 理屈ではない。生きていなければならないという、強い思い込み だ。自分でもその事は痛いほどよく分かっている。 ドラクゥだけは必ず自分の手で倒さなければならない。そういう ある種の妄執のようなものだった。そうしなければ、自分は自分に 戻ることができない。 ﹁⋮⋮あれは何だ?﹂ 丘陵を、何かが駆け下りてくるのが見えた。目を細めると、小さ な馬群に見える。 斜面を下るに従って、次第に兵の数が増えて行く。すると、黒い 粒にしか見えなかったそれが、段々と赤い色を帯びて行った。 ﹁<赤の軍>か!﹂ 勝敗は分からないが、<赤の軍>は健在らしい。 草原で食い止めている五〇〇〇と、オルビス・カリスにも分遣隊 がいるという報告は受けている。つまり、丘からこちらに向かって いる<赤の軍>は、最大でも一万といったところだろう。 <赤の軍>が一万と、<西の獣王>の軍が、六万。 鍛え上げられた騎兵とは言え、六倍の軍には勝てるはずがない。 361 まして、<赤の軍>はドラクゥとの死闘を終えたばかりなのだ。 動ける数も、最大で一万程度というだけで、実際には数千といった ところだろう。 獣王の本隊から太鼓の音が聞こえる。それに合わせてゆっくりと 陣形が変わり始めた。 敵騎兵を数で侮らず、竜鱗の陣で迎え撃つ。そういう策の様だ。 一枚一枚の鱗を撃ち破ることができても、それが一〇枚二〇枚と なると、簡単には断ち割ることができなくなる。大きく一纏まりに なっているよりも、遥かに突破しにくい形になるのだ。 歩兵が、長槍を構える。 数千の騎兵が一つになった手負いの獣が、そこに飛び込む。 罠のようなものだ。どれだけ強力な騎兵とは言え、六倍の兵で組 む竜隣の陣を相手にすれば、たちどころに身動きが取れなくなる。 そんなことは、子供にだって分かることだ。 それなのに。それなのに何故、リ・グダンの膝は震えているのか。 カルティアの羽根が忙しなく羽ばたいているのか。 先頭が、ぶつかった。喊声は後方で竜鱗を組むリ・グダンの耳に も聞こえる。 味方の鬨の声が、一瞬で悲鳴に変わった。 一枚目。 これは予想していたことだ。丘から駆け下りて行き足の付いた騎 兵の逆落としを、まともに受けたのだ。想定内の損害だった。 二枚目。これも、撃ち破られるべくして撃ち破られた。相手は< 赤の軍>なのだ。 三枚目と敵がぶつかるところで、左右から責め上げる。そういう 調練を積んでいた。 太鼓の音も、そうすべきだと伝えている。 だが、止まらない。四枚目。五枚目。そして、六枚目。 一〇〇〇の兵で組む竜鱗が、六〇枚。六枚破られれば、後背に抜 ける。 362 ﹁向きだ! 向きを変えろ!﹂ リ・グダンが叫ぶより前に、衝撃が来た。先頭には、片角の人山 羊。 グランだ。 <万化>のグラン・デュ・メーメルが、硬鞭を振り上げて突入し てくる。 衝撃。獣王から与えられた兵が、涜皮紙でも吹き飛ばすように蹴 散らされていく。 一瞬、リ・グダンとグランの視線が交差する。 その瞳に湛えられているのは、まごう事なき憤怒の色だった。 将であるリ・グダンには、何の価値も見出していない。そういう 眼だ。 鱗は食い破られ、怒号と悲鳴があちこちで上がる。 <赤の軍>の兵も、減ってはいるのだ。 はらわた 鎧を赤く染めるのは自分の血の色に怯まないためだという噂は、 本当らしい。 失血し、落馬する兵もいる。 それでも、<赤の軍>は止まらない。獣王軍の腸を良いように食 い破りながら、何度も何度も突入と脱出を繰り返す。 獣王に、打てる手はない。竜鱗の陣は、一度組んでしまえば別の 陣に変えるのに酷く手間がかかるのだ。 リ・グダンにできることは、混乱の隙をついて、カルティアと共 に密かに陣を離れることだけだった。 駆けている。その感覚だけが、グランを動かしていた。 硬鞭を振るい、眼前の敵を叩き伏せる。そんな力が老?の何処に 残っていたのか、グラン自身にも分からなかった。 自分が自分であって自分でない。 363 そういう不思議な感覚の中で、馬を走らせている。身体は若かっ た頃のように軽い。 身体とはこんなにも軽かったのか。硬鞭も、自由自在に操ること ができる。 獣王の組んだ竜鱗陣を一枚ずつ砕いて行く。 敵の数は六万。一枚の鱗が一〇〇〇の兵からなっているとして、 六〇。対してこちらは五〇〇〇と言ったところか。 <赤の軍>でも、この差は覆らない。まして、此方は手負いの獣 だ。 平時でも厳しいものが、今の状況での勝機は無いに等しい。 それでも、グランは駆ける。 竜鱗陣は堅牢な陣形だが、動きは鈍い。一度形を決めてしまえば、 余程の良将でもなければ何もできない陣形だ。それでも、騎兵の突 撃に耐えるにはこうするより外ない。 それが、これまでの常識だ。弟子のドラクゥは、それを見事に覆 した。 電信や<鉄の荊>という新技術を、古い戦術を組み合わせる。 竜鱗陣を組むことしかできなかった戦術を、ドラクゥは変えて見 せたのだ。 戦場に、生きてきた。それが、生涯の全てだと言っても良い。 魔界における古今東西の戦いは、可能な限り調べた。 将軍の能力や性質も、ほとんど把握している。それを自分の頭の 中で組み合わせ、必勝を自らに課して来たのだ。 そのグランが、敗れた。 理由は、自分の頭の中に入っていない戦術を使われたことだ。一 つや二つであれば、補いも付く。だがドラクゥはそれを、次々に繰 り出してみせたのだ。 それほど臨機応変な戦い方ができる弟子ではなかった。 成長したのだ。少し見ない間に、弟子は大魔王へと成長していた。 自分で育て上げた雛が鳳凰の如く成長して、自分を打ち負かす。 364 これほど美しい結末があるだろうか。いや、ない。 将として、師として、自分の終わり方にこれ以上のものがあるは ずはないのだ。 自分の望み続けてきた、最良の最期を弟子は送ってくれた。 それに、獣王は水を差したのだ。許せるはずがない。 戦争を私物化してまで得た、至上の敗北に泥を塗るような獣王の やり方に、グランは心の底から腹を立てていた。 誰の差し金かの見当は付く。シェイプシフターか、<皇太子>レ ニスか、<北の覇王>ザーディシュか。或いはその全てなのだろう。 三方から甘言を吹き込まれて自制心を保てるほど、当代の<西の獣 王>は出来物ではなかったということだ。 獣王の器を、大きく見過ぎていたらしい。決着がつくまで手は出 さないと信じていた。 或いはそこにグラン自身の期待が紛れ込んでいたのかもしれない。 予想を願望で曇らせるとは、どうやら<万化>のグランにも焼きが 回ったとみえる。 硬鞭が唸り、目の前の敵が吹き飛んだ。 もう何枚の鱗を剥いだか分からない。いつの間にか、腹に矢を受 けていた。 血を、失っている。助からない量だということは、分かっていた。 それでも、馬を駆けさせる。意識は、益々明瞭になっていく。視 界だけが、霞む。 横を駆けているのは、アルカスだった。 右にしか硬鞭が振るえなくなったグランを庇うように、左に付く。 魔都で引き合わされるまでは、言葉を交わしたこともなかった。 今や、十年も二十年も連れ添った戦友のように、轡を並べている。 死なせるべきではない。ごく自然に、そう思った。 その時初めて、自分がこれから死につつあるのだということに、 気が付く。 また、矢が刺さった。左の肩口だ。もうあまり、長くは戦えない 365 だろう。 痛む左手に<万化>の銘が彫られた硬鞭を持ち変え、アルカスに 手渡す。 馬上のアルカスは、不思議そうな、そして、今にも泣きそうな表 情を浮かべた。 ﹁これを、孫に﹂ 言葉少なく、硬鞭を託す。 事前にアルカスとは相談していたことだ。それで、通じる。 いや、ジャンの事は相談していたが、アルカスの処遇については 敢えて何も言っていなかった。アルカス自身、ここで身を捨てる覚 悟だったのかもしれない。 ﹁せめて、剣を﹂ アルカスは腰から予備の剣を引き抜き、手渡してくる。 右手に持ち替え、振ってみた。悪くはない。最後の最後を共に戦 う剣は、武骨な方が良い。そういう妙な美意識が、グランの中に芽 生えている。 ﹁それではな、アルカス。達者で﹂ ﹁<万化>のグラン将軍も、御達者で﹂ そう言われてグランは小さく首を振り、顎をしゃくって硬鞭を指 した。 ﹁儂はもう<万化>のグランではないよ。ただのグランだ。グラン・ デュ・メーメルだ﹂ 会話はそれで終わらせ、馬に拍車を掛ける。 呆気にとられるアルカスを尻目に、敵の最も密集した辺りに馬の 鼻先を向けた。 思ったより多くの兵が、此方についてくる。 近衛が守るべきは大魔王だろうにと文句の一つも言いたくなった が、それは止めた。 今のグランは<万化>のグランではない。ただの一騎の騎兵に過 ぎないのだ。 366 頬で風を感じながら、剣を振るう。 鱗を剥がすのは、もう止めた。何枚剥いだところで竜は死なない。 殺すには、心の臓腑を一突きに突くだけだ。 獣王の陣の場所は、すぐに分かった。巨大な旗が、はためいてい る。 喊声を上げ、突っ込んだ。後ろから、<赤の軍>が圧してくれる のが分かった。 切り裂き、突き、潰す。 本陣に近付くにつれ、敵の抵抗が強くなった。槍が、馬の腹を穿 つ。 左肩を庇うようにして、転がった。取り囲もうとする兵の足を切 り付け、立ち上がる。 口元に浮かんだ笑みは、自嘲からだけではない。 何だ、意外と楽しい戦争ではないか。そんなことを思いながら、 剣を振るう。 獣王の傍に侍っていた虎の魔王が、戦斧を叩きつけてきた。耐え 切れずに剣が折れる。 手近な敵から短槍を奪い取り、胸を突き刺した。虎の魔王の表情 が苦悶に歪む。 槍は、抜けない。 諦めて戦斧を拾おうとするが、左肩が上がらなかった。その隙に、 周りの兵が押し包んでくる。地面に落ちていた剣を拾い上げたとこ ろで、背中に痛みが走った。 何が起こったのか、分からない。ただ、振り向きざまに剣を振る った。 刺してきたのは、獣王の旗本だったらしい。自分の仇は、始末で きた。 <赤の軍>の残党がこちらに突っ込んでくるのが、霞んで見える。 最後の最後に来て、面白い戦争だった。 崩れ落ちるようにして、草原に倒れ込む。 367 秋の空はどこまでも高かった。 辿り着いた時には、全てが終わっていた。 獣王軍が引き揚げるのを、ジャンは馬上からただ見ている。 撤退なのか、それとも敗走なのか。獣王軍の撤収は、判然としな い。相当の損害を受けていることだけは確かだが、それでもまだ、 ドラクゥと戦うだけの余力は残しているように見えた。 それでも退いているということは、何かがあったのだろう。 相手を圧倒する戦力で臨んだ時には、些細な瑕疵でも許せないこ とがある。ジャン自身にも経験があった。匪賊討伐に十分な戦力を 投じたのに、思わぬ損害を被ったのだ。作戦は継続すべきだったが、 部下の戦意低下はそれを許さなかった。 獣王の軍の整然とした移動は、そういう予想外の被害を思わせる。 祖父はどこにいるのだろうか。デュ・メーメルの旗が、見当たら ない。 オルビス・カリスに急使が辿り着いてから、休みなく駆けてきた。 替え馬も、疲れ果てている。それだけの強行軍だった。休んでいた 五〇〇〇騎も連れてきている。 初めはドラクゥとの交戦が始まった、という報せだった。何かの 間違いではないか。三度、軍使を問い質した。間違いないことが分 かると、次に去来したのは置いて行かれたという思いだ。 それが、使いの持ってくる文の内容は次第に変わり、ついには獣 王と戦っているというものになった。 赤い軍装の騎兵が駆けてくる。アルカスだ。 手には、持っている筈のないものを、持っている。 ﹁アルカス。グラン将軍は、どちらにおられる?﹂ ﹁⋮⋮立派な、御最期でした﹂ ﹁莫迦を言うな、アルカス。南征軍の軍監だ。グラン・デュ・メー メル将軍ともあろう名将が、軍監の見ていない所で死ぬわけがない﹂ 368 アルカスは黙って手にしていたものを差し出した。目を背けよう とするが、できない。 銘を確かめるまでもなかった。それは紛れもなく、祖父グラン・ デュ・メーメルが長年愛用してきた硬鞭、<万化>だ。 受け取り、持ち重りを確かめる。 手にしっくり馴染むのは、ジャンの硬鞭<千変>と元は一対の双 鞭だったからだ。 まだ温かい。その温もりが段々と消えていく。 ﹁ジャン将軍に、言伝がございます﹂ ﹁言伝?﹂ ﹁はい。グラン将軍からは、ドラクゥ様との決戦の後ジャン将軍に お伝えするように、とのことでした﹂ 瞑目し、天を仰いだ。 計画通りだったという訳だ。 オルビス・カリスの軍を呼び集めてから決戦に臨まなかったのは、 偶発的にドラクゥ軍との戦いが始まったからかもしれない。そうい う淡い期待を抱いていた。 アルカスの言葉は、それを否定している。 最初から、ジャンは生き延びる予定になっていたのだ。その前提 で、<万化>のグランは全てを組み立てていた。<赤の軍>も最低 五〇〇〇は、残る。 ドラクゥに降れ、と言うのだろう。 そんなことを言われずとも、ジャンには分かる。ドラクゥとレニ ス。どちらが戴くべき大魔王であるかなど、考えるまでもない。 <北の覇王>への恩義は、今も感じている。ただそれも、虚しく なった。 祖父への反発をザーディシュが利用していることには、気付いて いたのだ。それでもなお、取り立てて貰ったという恩義はある。 ただ、迷いはない。 グランが、祖父がドラクゥに降れと言うのなら、それに従う。ジ 369 ャンの気持ちはすでに固まっていた。魔都を出てからの戦いの中で 祖父が教えてくれたことを役立てたいという気持ちの方が、今は大 きかった。 気持ちを整え、アルカスの目を見る。アルカスも、緊張している ようだ。 ﹁どうしたアルカス。早く言ってくれ﹂ ﹁では、お伝えします﹂ ﹁ああ、頼む﹂ ﹁⋮⋮“自由に生きろ”です﹂ ﹁続きは?﹂ ﹁ありません。これだけです﹂ 二つの硬鞭を、握り締めた。 祖父のことを厭っていると言いながらも、無意識の内に頼ってい たらしい。 武官として生きて来た。歩む道は、いつも誰かから示される生き 方だったと思う。 自分で決めたことと言えば、武官になるということだけだ。 それが、窮屈だと思ったことはなかった。当たり前だとさえ思っ ていたのだ。 顔を上げると、目の前には草原が広がっている。 そこに、画された道はない。ただただ、無限の緑が地平の果てま で広がっているように見えた。この光景は、祖父の残してくれたも のだ。 双鞭を振り、ジャンは麾下の<赤の軍>に向き直った。 ﹁これより<千変万化>のジャン・デュ・メーメルは<大魔王>ド ラクゥに降る﹂ 思ったよりも、声が朗々と響いた。声音が、どこか祖父に似てい る。錯覚かも知れないが、そう感じた。勘違いであっても、それは 嬉しいことの様だ。 ﹁異議のある者は、去れ。追うことはしない﹂ 370 宣言すると、すぐに騎兵たちが唱和する。 ﹁異議なし! 異議なし! 異議なし!﹂ ﹁この若輩に、付いて来てくれるか!﹂ ﹁ジャン将軍! ジャン将軍! ジャン・デュ・メーメル!﹂ 手槍を掲げ、それを喪った者は拳で天を突く。 敗軍の筈だったが、意気は勝ったはずの獣王軍よりも高い。 獣王軍の足止めをしていた五〇〇〇騎の残党も加われば、一万数 千はまだ残っている。 手負ってなお、<赤の軍>はその精鋭ぶりを損なっていない。 ﹁ジャン将軍、丘の上の陛下に謁見を申し込みますか﹂ ﹁そうしよう﹂ ﹁しかし、大魔王陛下の元に近衛が合流するのです。恥ずかしくな いように身支度などは必要ありませんか?﹂ アルカスの問い掛けに、ジャンは大笑で答えた。 ﹁騎兵に戦塵以上の身支度はあるまい﹂ ジャンが号令を掛けると、兵達は即座にそれに応える。 <赤の軍>は、騎兵であれば、武官であれば誰もが斯く在りたい と望むような完全な隊列で整然と丘を登って行った。 一つの戦いが終わり、また次の戦いが始まる。 ドラクゥ、レニス、そしてリホルカン。 大魔王の血を引く三者はそれぞれのやり方魔界の統一に向けた動 きを本格化させる。 そのころ一方、︿黒髪姫﹀の元に身を寄せたオイレンシュピーゲ ルもまた、怪しい動きを見せ始めるのであった⋮⋮ 371 01、古い革袋の使い方 政庁は活気に満ちていた。 若い文官から闊達に意見が出ていることにダーモルトは驚きを禁 じ得ない。 廊下を歩きながら見る文官たちの動きは、まだまだ無駄も多いが 若々しい情熱に満ちている。ドラクゥの旗が翻るパザンには相当数 の文官が詰めているが、大魔城の内奥で行われていたような政治的 暗闘の臭いはここにはまだほとんどなかった。兆候となりそうなも のはいくつか見受けられたが、まだまだ可愛らしいものだ。 魔都から大魔王の陣営に寝返ったダーモルト・デル・アーダがこ れまで生きてきたのと同じ政治の世界とは思えぬ清浄さが、ここに はある。 最上階に設えられた大魔王の執務室の戸を敲くと、驚いたことに ドラクゥが手ずから開けてくれた。室内にはドラクゥとダーモルト の他には誰もいない。ダーモルトがパザンに来て、はじめてのこと だ。 これまでは必ず、誰かがドラクゥの傍についていた。まさか弑逆 を図っていると疑われていたわけではないのだろうが、漸く緊張も 解けて来たということだろうか。 ﹁爺、この政庁をどう見る﹂ 筆を走らせながら、ドラクゥが下問して来た。 以前対面した時よりも、大魔王としての風格をよく身に付けてい る。師であるグラン・デュ・メーメルを討ったことで、ひと回り成 長したのだろう。口調にも、落ち着きと威厳が感じられるようにな った。 372 ﹁よく治まっていると思います。⋮⋮ほんの僅かな期間に作られた ものとしては﹂ ﹁何か改めるべき点があると言いたそうだな﹂ ﹁私は権限のない顧問のような位置におりますから、御下問頂いた ことには個別にお答えすることはできます。ただ、全体を見渡して の事となると﹂ 宰相ラ・バナンの顔を立てねばならない、ということをダーモル トは言外に奏上した。死に場所を求めてここへ来たが、若い後進の 芽を摘むのは本意ではない。 ダーモルトから見て、ラ・バナンという文官はよく育っている。 今すぐ魔界全土の内政を管掌しろというと無理が出るだろうが、 いずれはその能力を身に付けるであろうという気配を感じさせるゴ ブリン・シャーマンだ。 創業期を担う文官とはそうしたものだろう。立場が能力を育て、 成長させる。 ﹁そのラ・バナンからも言われているのだ。爺の経験と知恵を拝借 したいと﹂ ﹁それはどういう分野に於いてでしょうか。私も観ての通りの老骨。 できることとできかねることがございます﹂ 頼られるのは嬉しいが、甘えられるようならそこまでの話でもあ る。 強大な官僚組織に頭は二つ要らない。政治的生き物である官僚は 気を抜けばすぐに派閥を作り出す生き物だ。ラ・バナンの差配に少 しでも不満を持つ者は、すぐにダーモルトを神輿として担ぎ上げる だろう。 担ぎ上げる値打ちもないと自嘲するほど、ダーモルトは謙遜家で 373 はない。 ﹁調整だ。今ラ・バナン、シュリシア、それとフィルモウが担当し ている分野が、重複したり不足したりしているようなのだ。改革と 言い換えても良いだろう。爺にはそこを見て貰いたい﹂ ﹁なるほど、それは確かに﹂ 若い組織であるだけに、新たなる大魔王府では行政が上手く縦割 りになっていない部分がある。拡大を続ける領地を維持しながら改 革を進めているという意味では驚嘆に値する統治機構の出来栄えだ が、経験不足も見え隠れしていた。 ﹁受けてくれるか?﹂ ドラクゥが顔を上げる。 その表情は既に、大魔王のものだ。ダーモルトは感に堪えず、目 を閉じ、開いた。 ﹁主命です。謹んでお受けいたしましょう﹂ 応えながら、ダーモルトは自分の心の中に熾火のように温かなも のが芽生え始めていることに気が付いている。 改革。 なんと甘美な響きだろうか。大魔城の深奥で政治的駆け引きの遊 戯に莫大な掛け金を投じながら参加することも男子の本懐であった が、改革ほどに心を動かされることはない。 官僚機構とは常に自己の延命と保身を図るものであり、時折どう にもならない事情で海を絞り出す以外に何かを改めるということは ほとんどなかった。 374 五千年の長きにわたって魔界を支配し続ける官僚団にとっては、 改革などという言葉は石の裏に潜む虫に陽光を当てるが如き要らぬ 節介として捉えられていたのだ。 今からダーモルトが関わることは、まさに調整という名の改革だ った。 権限の整理と分配。 これほど難しく、やりがいのある仕事があるだろうか。 当然、新たに作られる組織図の中にダーモルトの名前はない。そ うすることで、反宰相派に担ぎ出される恐れもなくなる。時限的な 権限で組織を一気に整えてしまうという意味で、ダーモルト以上の 適任はいない。 爺と慕う老臣を使い捨てにできるだけの度量が、今のドラクゥに はある。 ﹁正直なことを言えば、爺が来てくれなければ危うかった﹂ ﹁そうでしょうか。ラ・バナン殿も他のお二方も、良い文官です。 時間はかかるでしょうが、組織は育って行きます﹂ ﹁その余裕はあまりない﹂ ドラクゥが広げて見せたのは魔界だけの地図ではなかった。 精緻ではないが、人界も含まれている地図だ。ダーモルトも長く 生きてきたが、初めて目にするものだった。 ﹁人族の方も色々とあるようだ。新しい城市への民の流入が留まる ことを知らない﹂ ﹁良いことではありませんか。民の数は国力に直結します﹂ ﹁そう良い事ばかりでもないのだ﹂ ﹁と、仰いますと?﹂ ﹁集まって来るのは、<聖堂>に虐げられた者達だ。生活の基盤も 375 なく、持っている財貨も乏しい。中には反社会的な者も含まれてい る﹂ ﹁なるほど。一筋縄では治められない、ということですな﹂ ゴナン 魔界の統治に関して言えば、ダーモルトの右に出る者はいない。 堅き者のような例外を除けば、多くの種族について統治に適切な助 言ができるという自負がある。 だが、人族は違う。 全くの異種族であって、どう扱うべきかという知見がない。フィ ルモウは優秀な総督だが、例外の多い統治には骨が折れるだろう。 ﹁例の電信を使って、主上が直接統治するというのは如何でしょう か?﹂ ﹁総督の権限を制限することになる。フィルモウには自由に仕事を させてやりたいのだ﹂ ﹁しかし、細かな問題もあるでしょう﹂ ﹁ああ、だから余、自らが新城市に居を移そうと思うのだ﹂ それは、と反射的に言い掛けてダーモルトは口を噤んだ。 言われてみれば、妙案かも知れない。フィルモウの統治には口出 しをせず、ただ後ろ盾としてドラクゥが新城市に居を構える。ドラ クゥが口出しをしない限りはフィルモウの行動は信任されているこ とになるし、突発的な事態にも対応しやすい。 ﹁では、パザンはどうされますか?﹂ 軍事的にも政治的にも、パザンの位置は重要だ。 タイバンカ率いる部隊が内海に面した港町オルビス・カリスを掌 握したが、最前線は今でもパザンである。大きな損害を負った<西 の獣王>の軍は沈黙を守っているが、パザンの守備を疎かにするこ 376 とはできない。 ﹁ジャン・デュ・メーメルに<赤の軍>を任せる。平原での戦いに 不安はない。政治はラ・バナンがいることでもある﹂ その補佐を、ダーモルトがすることになる。なるほど、よく考え られた配置だ。 改革が終われば閑職に回されることになるダーモルトはこの機に、 ラ・バナンに持てる内省的な技術の全てを伝授することが期待され ている。何とも胸の躍る話だった。 ﹁御意にございます。パザンについて何か注意すべきことはありま すか﹂ 軽い気持ちで尋ねたつもりだったが、ドラクゥは軽く目を伏せる。 ﹁⋮⋮何かございますか﹂ ﹁叔父のことだ。リホルカンが、オーク諸氏族に号令を発した﹂ ﹁ああ﹂ <法皇>リホルカンが代統領として立ったことは、ダーモルトも 知っている。オークの諸氏族に声を掛けたということも、噂では聞 いていた。 ﹁オークを文官に縛るのを止めた、ということでしたな﹂ ﹁余もそこまでは思い到らなかった。ずっと傍にオークの家臣が居 たというのにな﹂ オークはドラクゥたちトロルと最後まで魔界の覇を競った種族だ。 戦いの趨勢が決した時、武器を持たぬことを誓わされ、この五千 377 年間文官として職を奉じ続けてきた。 ﹁さて、どうでしょう。この身は筆しか持ったことがないので、戦 いの衝動に身を任せる生き方がどういうものかは分かりかねますが﹂ ﹁しかし、爺と違う考えの者も多いらしい﹂ ドラクゥが放って寄越した涜皮紙には、ダークエルフのシュノン からの報告が書き記されている。その内容は、凄絶だった。 ﹁大魔城の文官が、離反ですか﹂ いちどき ﹁魔界の統治はオークを中心とする文官に支えられてきたのだ。そ こから一時にオークが抜けては、通常の業務もままならないだろう﹂ ﹁⋮⋮想像もできぬことです﹂ ﹁それに伴って、難民も発生している﹂ ああ、とダーモルトは嘆息を漏らす。 魔都の食糧事情はダーモルトが出奔する前でさえ、限界に達しつ つあった。曾孫である<白髪姫>ラコイトの能力が低いとは思わな いが、既に周辺地域からの収税にも問題が出ていたのだ。それでさ らに文官が抜けるようなことになれば。 ちょうさん ﹁断続的な旱魃や豪雨も魔都を悩ませているという。逃散した民の 一部は、食料と住処を求めてパザンを目指しているということだ﹂ ﹁それを受け入れる態勢を整えろということですな﹂ ﹁我が妃であるラーナをその任に充てるつもりだが、何くれなく世 話を焼いて貰えると嬉しいな。これは、命令ではないが﹂ ﹁承知いたしました。しかし、奥方を新城市へはお連れしないので すか?﹂ 竜裔族であるラーナは慣例では側妾の立場にあるはずが、実際に 378 は正室としての扱いを受けている。大魔王が居を移すのであれば、 帯同するのが当たり前だ。 ﹁今は文官の数が足りないから手助けがしたいと、自ら申し出てき た。その気持ちをむげにするのもな﹂ ダーモルトは小さく首を竦めた。この主上には、やはりまだ抜け たところがある。 ﹁分かりました。難民の受け入れはお任せください。この老骨でも、 それくらいのことはやり遂せます﹂ ﹁いや爺、だからそれは⋮⋮﹂ ﹁奥方様のお気持ち、お察しくださいまし﹂ ﹁ふむ﹂ 顎に指を添えて考え込む仕草は、先代の大魔王とそっくりだ。 ﹁分かった、任せる。ラーナには向こうでも手伝って貰いたいこと があるのだ﹂ そうしてくださいと答えながら、ダーモルトは既に次のことを考 えている。 ﹁なんだ、まだ気になることでもあるのか?﹂ ﹁いえ、旱魃や豪雨が魔都周辺で起こっているという話でしたので、 それを利用できないかと思いましてな﹂ ﹁流言蜚語か﹂ ﹁邪神の恩寵が失われつつある、とか﹂ ドラクゥが形の良い眉を顰めた。 379 ﹁それは余の好みではないな。必要な策とも思えないが﹂ ﹁と仰いますと﹂ ﹁天災によって家族や家を失った者も多いだろう。それを徒に思い 返させるのは、治世に携わる者のなすべきことではないと思う﹂ ﹁なるほど、御意にございます﹂ この大魔王は、優しいのだ。 そのことに、ダーモルトは改めて気付かされた。優しさは弱さだ と思っていたが、今の魔界では意外な強さとして活きてくるかもし れない。 ﹁後の事は宰相殿と何とか致します。主上に置かれましては、後顧 の憂いなく新城市へ御移り下さい﹂ ﹁ああ、頼んだぞ、爺﹂ そう言うなり、ドラクゥはまた机の上に広げられた書類に視線を 落とした。 一礼して退室しながら、ダーモルトは考える。 どうして天災が急に魔都を襲うようになったのか。詮無いことで はあるが、理由がどうにも気に掛かった。 380 PDF小説ネット発足にあたって http://ncode.syosetu.com/n6415bc/ 邪神に転生したら配下の魔王軍がさっそく滅亡しそうなんだが、どうすればい 2015年2月11日03時22分発行 ット発の縦書き小説を思う存分、堪能してください。 たんのう 公開できるようにしたのがこのPDF小説ネットです。インターネ うとしています。そんな中、誰もが簡単にPDF形式の小説を作成、 など一部を除きインターネット関連=横書きという考えが定着しよ 行し、最近では横書きの書籍も誕生しており、既存書籍の電子出版 小説家になろうの子サイトとして誕生しました。ケータイ小説が流 ビ対応の縦書き小説をインターネット上で配布するという目的の基、 PDF小説ネット︵現、タテ書き小説ネット︶は2007年、ル この小説の詳細については以下のURLをご覧ください。 381
© Copyright 2026