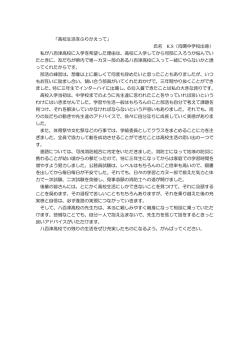咎のドラゴンと冬の王 - タテ書き小説ネット
咎のドラゴンと冬の王 神前ながれ タテ書き小説ネット Byヒナプロジェクト http://pdfnovels.net/ 注意事項 このPDFファイルは﹁小説家になろう﹂で掲載中の小説を﹁タ テ書き小説ネット﹂のシステムが自動的にPDF化させたものです。 この小説の著作権は小説の作者にあります。そのため、作者また は﹁小説家になろう﹂および﹁タテ書き小説ネット﹂を運営するヒ ナプロジェクトに無断でこのPDFファイル及び小説を、引用の範 囲を超える形で転載、改変、再配布、販売することを一切禁止致し ます。小説の紹介や個人用途での印刷および保存はご自由にどうぞ。 ︻小説タイトル︼ 咎のドラゴンと冬の王 ︻Nコード︼ N4692CK ︻作者名︼ 神前ながれ ︻あらすじ︼ 前王がたおれ玉座に座ることになったフリジット国の第一姫・ ハンナは、国王としての資質を疑われ、城の片隅で老爺と顔を合わ せながら毎日を暮らしていた。ある日、蔑視に耐えれなくなったハ ンナは逃亡を企てるも、一匹のドラゴンと出会う。美しいドラゴン の青年は、ハンナのことを﹁運命の相手﹂だと主張し忠誠を誓うが、 彼の心には拭い去れないひとつの想いが宿っていた。 ﹁冬の王﹂として顰蹙を買っている少女ハンナが、春を願いなが ら成長していく物語。 1 プロローグ 冬をまねく王 べんたつ すこし、風にあたるといい︱︱。 うわの空で鞭撻を聞いていたハンナに、老爺はあきれ顔でそう言 った。 その忠告を甘んじて受け入れたわけでもなかったが、ハンナはこ うして雪の降りしきる城外へ出てきている。厳しい寒気と雪に閉ざ された王国は、さらに壮絶な盛りを迎えようとしており、どちらに 目を配っても眩しいばかりの白銀の世界が広がっている。 ハンナを包み込む空気もいまにも凍りつきそうだった。防寒着に 身を包んでも肌が露出している場所を狙って雪片が忍び込み、息を のむような冷感をまねく。耐えかねて吐きだした息は白く、雪にか わりそうなほどだった。かじかんだ唇を噛みしめてハンナはぐっと 拳をつくった。 ︱︱城にはもどるまい。 その一心が寒空の下、ハンナを留まらせている。 外にやった気のいい老爺は、なかなか帰ってこないハンナにしび れを切らしているだろう。人のよい柔和な顔が怪訝にゆがむさまを 想像し、ハンナはわずかに空気を揺らした。笑ったのだ。くつくつ と肩が揺れてもハンナの顔は鉄面皮のように動いていない。表情す らも固まってしまったのかと危惧するほどだったが、ハンナにとっ てそれはいつもと同じだった。 名君として知られていたベルモンドが急逝してしばらく︱︱。 すでに王妃は亡きあと、後継者として名があがったのがハンナだ まつりごと った。ベルモンドの愛娘︱︱第一姫として周知されていた彼女が玉 座に座るのは妥当だったが、政に造詣が深くないハンナにとっては、 2 混乱をきわめる事態だった。とうぜん、その日に行われた会議では、 臣下の質問や提案に色よい返答など返せるはずもなく、愚行をさら けだしただけだった。 ゆっくりでいいのですよ、と教育係を買ってでた変人の老爺は笑 うが、ハンナには紡がれる言葉そのものが他国の言語のような気が して、そうそうに尻尾をまいて逃げ出してしまいたかった。現に勉 学からの解放を宣言されると城外に飛び出し、辺鄙な湖に逃げ込ん でいる。 春先になれば雪がとけ、青くかがやく湖も、いまは分厚い氷に覆 われ見えない。ハンナのささくれた心にいやしを運んでくれるわけ ではなかった。それでも、幼少時から避難場所として親しんでいた ために、足は自然と向かっているのだ。 会議の時間が苦手だった。だれもが馬鹿にした目つきで玉座をみ やり、したり顔で問いかける。答えに窮するとあきれたように顔を ふり、勝手に話を進めていくので、それにうなずいてわけも分から ぬままに了承する。そうすると、なりゆきを見守っていたものが視 線を下ろしてうつむく。そうして、溜め息を落とすことを知ってい る。それは、身をきるばかりの雪片よりも、冷たく痛い。 ﹁︱︱わかるわけないわっ!﹂ 慟哭するようにハンナは声をしぼりだした。 膨大な量の問いかけも、求められる期待も、臣下の諦観も︱︱。 すべてを投げだしてしまいたかった。 逃げだして、重責から解き放たれたかった。 ﹁父上が︱︱﹂ 父親が名君だったとして、その子供まで名君になるとは限らない。 それでも、一度あがりきってしまった敷居は、なかなか下がらな いものだ。だれもがハンナに期待をよせる。最初はだめでも、次こ そは︱︱そのまた次こそは。そうやって、期待を先送りにして、う まくできないと勝手に失望していくのだ。ハンナの意思など関係な 3 い。 泣きだしてしまいたいのに、ハンナの表情筋はぴくりとも動かな い。涙も一滴すらこぼれない。 知っている。民草や見下す臣下が、自分をなんと呼んでいるのか を︱︱。 政もできず、ただひたすらに民を貧困に追いやる。表情一つ変え ない愚王。 ︱︱恵みを隠し覆い尽くす季節の主、冬の王。 ﹁雪解け﹂と評された前王と比べられ、彼女に名づけられた名称 は侮蔑だった。 土地柄、寒気をまともに受けるフリジットでは良政を冬の終わり にたとえることが多い。それとは逆に悪政を評する言葉には、冬の 盛りや終わりのない冬をたとえることが多かった。ハンナの政治手 腕はもちろん後者の意味でたたえられている。それも、悪質で辛辣 な言葉で。 ハンナはよく笑う少女だった。国王として担ぎ上げられる十六歳 までは、明朗快活としていて、城内を温かくしてくれると誰もが褒 めそやした。しかし、玉座についてから飛びかうのは叱責や溜め息 ばかりで、ハンナの顔からはしだいに笑顔が消えていった。それと 比例して、城内の空気も妙に冷え冷えとしていったのを覚えている。 民草のために政策をだせば、国庫をつぶす気ですかと寒々しく言 われ、しまいには、﹁民を甘やかすことだけが良策ではありません﹂ とハンナの案を鼻で笑い却下されてしまう始末だ。 困窮し肩身を狭くするハンナを擁護してくれる臣下などいるはず もなく、ハンナは城の片隅で老爺と顔を突き合わせ、たいして面白 くもない書簡に目を通すことだけが仕事になった。その老爺は数奇 にも、ハンナに温かく接してくれたが、それを支えとするには心も とない。老爺はハンナの戦地ともいえる会議場には、けっして足を 4 踏み入れることができないのだから。 ﹁︱︱⋮⋮さむい﹂ 身が冷え切ったのか、心が冷え切ったのか分からず、ハンナは空 を見上げた。 厚く雲がたれこめる空は白銀に混じってわずかに灰色に染まって いる。重く、大きく落ちてくる雪がハンナの目元におりて水滴にか わり、また氷にかわろうとしている。固まってしまわぬうちに拭お うとしたハンナは、雲間に黒い点がぽつりと浮かぶのを見とがめ動 きをとめた。 それはじわりじわりと距離を詰めてくると、黒ではなく、灰色へ と姿を変えていく。 その姿を目視して、ハンナは自然と唾を飲みこんだ。 ﹁︱︱うそよ﹂ わずかに言葉尻は半音あがり、震えは顕著にあらわれた。 ﹁そんなはずないわ﹂ 否定するハンナを嘲笑うように、影はみごとに滑空し、降りたっ た。 ︱︱それは、一匹のドラゴンだった。 フリジットには、ドラゴンなどいない。 遠く温かい場所には、ドラゴンが生息する場所があるという。む かし、父親が招いた旅人が、生育したドラゴンを連れてきていたが、 飼いならすには難しいとこぼしていたのを思い出した。幼心にも、 獰猛な体躯と熱い息づかいに気圧され、怯えていたのを覚えている。 それが、ハンナの目と鼻のさきに降りたってきたのだ。 体が逃走本能を呼び覚ましたように、血液を循環させているのを 感じた。真冬の中にいるというのに、頭が熱く沸騰し、ハンナに警 告を叫んでくる。逃げなくては、と思うのに、いやに足先だけが凍 っていて、降り積もった雪に絡めとられ盛大に尻もちをついた。絶 5 望に顔を青くするハンナを尻目に、雄々しくも美しいドラゴンは、 爪をたてながらのしのしと歩み寄ってくる。 ﹁ひっ︱︱﹂ 叫びたいのに、喉がひりついてか細く風を吸いこんだだけだった。 ︱︱もう、すぐそこにいるのに。 逃げたいと少しでも考えてしまった罰なのか、とハンナが迫るド ラゴンの顔に目を閉じようとしたときだ。 ハンナを食べようと口を開くわけでもなく、ドラゴンは彼女の足 元に口先を押しつけた。固い鱗の感触が防寒ブーツを通じて伝わっ てきて、ハンナはどきまぎとするばかりだった。ドラゴンはしばし、 ハンナに低頭していたが、やがて押し殺すように息を吐いた。 ﹁やっと、見つけた﹂ それは、年若い男の声だった。 最愛のものを見つけたかのように目元をほころばしたドラゴンは、 ふと体を横たえた。どさっという重苦しい音とともに突風が吹き荒 れ視界を隠すと、ハンナが目を開いたさきには線の細い青年がひと り、ひどく寒々しい格好で倒れ伏していた。 ﹁︱︱は﹂ 雪が降りしきるフリジットの辺境。 事態を飲み込めないハンナと、雪国にふさわしくない格好の青年 がひとり。 ハンナの身を心配して老爺が走らせた兵隊がふたりを見つけ出す まで、ハンナは遭難者のように固まり続けていた。 6 第一話 灰色の進言 ︱︱ご無事で何よりです。 老爺︱︱ガイルは皺の寄った顔をさらにしわくちゃにさせてハン ナの手を握りそう言った。ハンナは逃亡を企てていたために、ガイ ルの顔を直視できず不自然に目をそらし、話を切り替えるように尋 ねた。 ﹁あの者は?﹂ ﹁ハンナさまのご要望通り、丁重に保護しておりますよ﹂ ﹁⋮⋮そう﹂ じわりと安堵が広がってハンナは困惑した。見ず知らずの異国の 者を案じている自分がいることに驚嘆するとともに、彼が言った﹁ やっと、見つけた﹂という言葉が気がかりでならなかった。寒々し い格好でやってきた青年は、頭に奇妙な角をつけていた。それは灰 色のドラゴンと同じ色合いをした角で、簡単に折れないほどの強度 をほこっているように思えた。 ﹁ねえ、ガイル。あなたはとても知識が豊富だわ。だから聞きたい の﹂ ﹁なんなりと﹂ ﹁あの者はいったい何?﹂ ドラゴンに姿を変え、おおよそ人間が持つとは思えない角をもち、 ハンナを探していた。 ﹁あの者はおそらく、ラフィールの角つきかと﹂ ﹁ラフィール⋮⋮﹂ フリジットとは違う。温暖な気候と緑に包まれた土地。そこは、 ハンナたちが住むフリジットから遠く離れた場所にある。あの青年 はそこからおのれの翼だけを頼りに、ハンナを探しもとめていたの だろうか。いったい、何のために? ﹁ラフィールの角つきは運命の相手を探すと言われています。おそ 7 らく、彼の運命の相手が、ハンナさま⋮⋮あなただったのではない か、と﹂ ﹁いやだわ、ガイル。運命の相手なんておとぎ話じゃないんだから﹂ 一笑にふすようにハンナは言うと、ガイルは大仰に首を振ってみ せた。 ﹁いえいえ。角つきたちはそれこそ本当に、運命の相手を見つけ出 すのですよ﹂ その顔に冗談は混じっていなかった。ハンナは言葉に窮し、ガイ ルの皺だらけの両手を見つめる。 雄々しく立派なドラゴンだった。そこから現れた青年もまた美し いつくりをしていた。鱗と同じ灰色の髪と角。雪国に住まうハンナ よりも焼けた肌。細くしなやかな体は、どっしりとしたドラゴンで あることを認知させないほど、華奢だった。青年の艶やかな容姿を 思い浮かべ、ハンナは居心地悪く姿勢を正した。 運命の相手。 ハンナを探していたならば、綺麗な青年はハンナの運命の人とい うことになる。むずがゆさに目線を泳がせたハンナに、しかしガイ ルはとがめるように続けた。 ﹁しかし、あの者︱︱もしかすると?咎落ち?したのやもしれませ んな﹂ 咎落ち︱︱それは不穏な響きをはらんだ言葉だった。聞き覚えの ないハンナはガイルが続きを話すまで理解できるはずもなく、ただ じっと耳をすませて待っていた。そこにドタバタと走り回る足音が 聞こえたかと思うと書斎の扉が開け放たれ、一人の兵士が転がり出 てきた。 ﹁お、お知らせします!﹂ ﹁ハンナさまの御前で騒々しいぞ﹂ ﹁申し訳ありません! 件の青年が目を覚ましたのでお知らせを︱ ︱﹂ ﹁ほんとう?﹂ 8 真っ先に腰を浮かせたのはハンナだった。ガイルが兵士を叱責す るのを横目に扉を抜けると、彼がいるだろう医療室の扉を心持ち乱 暴に叩いた。そこはハンナたち王族の健康を維持するために集めら れた優秀な医者たちがいる。どれも古くからの馴染みであるから、 ハンナの顔を見ると深く頭を下げてさきに促してくれた。 青年は清潔そうなシーツにくるまり、呆然とあたりを見回してい る。ハンナが入ってきたことにも気づいていない様子だった。運命 の相手と言われてしまえば、その気がなくても色目で見てしまうも のだ。とっくに枯れ果てたと思っていた感情が脈打つのを感じて、 ハンナは絞り出すように声をだそうとして出鼻をくじかれた。 ﹁メルクゥ⋮⋮﹂ その切なげな響きにハンナの心は拒絶反応を起こした。 青年がハンナに気づいて自己紹介をするころには脈打っていた鼓 動は静かになっていた。咲こうとしていた感情は根元からごっそり と取り払われたように、無感動だけを伝えてくる。 運命の相手などいないのだ。 なぜならば、彼の心には自分とは違う﹁誰か﹂が眠っているのだ から。 9 2 咎落ち︱︱それは運命の相手を選択しなかった罰。 ラフィールの角つきは神に愛されている。強靭な身体。ドラゴン へ変異する能力。そして、定められた相手がいる喜び。彼らは迷う ことなく運命の相手を選び取り、ともに歩むことが約束される。し かし、もし選ばなかった場合、理性をなくし、人の姿をなくし、永 遠と運命の相手を探し求める暴竜と化す。 彼︱︱アルクゥもまた、運命の相手を取り違えた一人である。 ハンナはガイルからその話を聞き終えると、﹁呪い﹂のようだと 思った。神が相手を選択し与えてくれるなんてただの綺麗ごとだ。 実際、彼は愛したはずの人と分かたれ、遠く離れたフリジットまで ハンナという見知らぬ人物を探してやってきた。初対面の女と引き あわされて、運命の相手などと言われても、とてもではないが受け 入れられるはずもない。ハンナはそう考えてアルクゥを憐れんだが、 彼は意外なことにけろりとして受け止めた。 ﹁なあなあ、これなんだ?﹂ ﹁︱︱それは、万年雪よ。こうして瓶に入れて密封すれば溶けない の﹂ ﹁へー。チビどもが喜びそうだなあ﹂ 手のひらで瓶を転がしながら遊んでいる姿を一瞥し、ハンナは手 渡された書類を流し見ていく。どれもハンナには分からない政の案 件で、判を押してくれさえすればこっちでなんとかするといった感 じで臣下に渡されるので、気を入れて確認するつもりもなかった。 どうせ、ハンナの意見など採用されるはずもないのだ。飾りの王な どいてもいなくても︱︱。 がしゃん︱︱。 10 硝子の割れる音があたりを満たし、ハンナは何ごとかと顔をあげ た。アルクゥがしまったとばかりに口を開けたまま固まった下には、 もっさりと雪の塊が落ちている。その周囲に瓶の破片が散らばって いるところを見ると、どうやら万年雪の入った小瓶を落としてしま ったようだ。 ﹁わ、悪い﹂ バツの悪そうな顔でこちらを見やるアルクゥに、ハンナは冷たく あしらうように言った。 ﹁べつにいいわ。万年雪なんてここでは喜ばれるものでもないもの﹂ ﹁えー、そんなこと言うなよ。取ってきてやるからさあ﹂ どうやらアルクゥは、ハンナが腹を立てたからおざなりに返した と勘違いしているらしい。 ﹁ほんとうにいいのよ。フリジットの民は冬をきらうの。もちろん、 雪も。春を遠ざけるだけの溶けない雪なんて、誰の心も癒しはしな いのよ﹂ ﹁ふーん? じゃあ、なんであんたは大事に持ってんの?﹂ 大事に持っていたつもりは毛頭なかった。贈り物だから飾ってい たに過ぎない。 ﹁⋮⋮似ているじゃない。終わらない冬を連れてくるわたしに﹂ ほんとうは亡き王妃からの贈り物だったのだが、口から出てきた のは皮肉めいた言葉だった。ガイルあたりが発見したら、アルクゥ を叱り飛ばしてハンナに平謝りさせそうなものの、いまはちょうど 留守にしている。ガイルがそうして留守にするとき何をしているの かは、ハンナの知るところではない。詮索するつもりもなかった。 ﹁あんた、神様みたいなやつなんだなあ。すげえ!﹂ ﹁は?﹂ アルクゥのとんちんかんな言葉にハンナは低くうなった。 ﹁季節を自由に操れるなんて、すごいことじゃないか!﹂ ﹁馬鹿ね。操れるならとっくに春にしてるわよ。わたしは︱︱春を つれてこれない愚かな王なの!﹂ 11 終わらない冬。やってこない春。それはフリジットでは致命的な ものになる。厳しい冬がある国なのだから、王政は緩やかで穏やか な春を思わせることをしなくては、民の心中は凍えるばかり。しま いには、凍死させてしまいかねない。フリジットの冬は長く厳しい。 苛烈を極める環境に、倒れ伏してしまう民も少なくない。 ﹁あんた王さまなの?﹂ ﹁⋮⋮そうよ。そう見えないかもしれないけど、王なの﹂ ﹁じゃあ、なんでこんなとこにいんの? 政務は?﹂ 純粋な質問ほどハンナを痛めつける鋭さを持っている。きらきら と光り輝く銀色の瞳に気圧されてハンナは視線をそらすと、﹁べつ に﹂と答えになっていないぼやきをこぼした。﹁わたしがいなくて もいいのよ﹂という毒づきは言い訳というよりは負け惜しみに聞こ えた。 ﹁でも、あんた王さまだろ? マスクベル様はたいして用事なくて も玉座に座ってるぞ? まあ、ラフィールは国なんて立派なものじ ゃないけどな! はははっ﹂ あっけらかんと笑うアルクゥを尻目に、ハンナはマスクベルって 誰よ、と胸中で肩を落とした。 アルクゥとの会話には、知らない単語がよく出てくる。ラフィー ル、エンカ、マスクベル。アナベルにエディ、クロト。そして︱︱ メルクゥ。アナベルやエディ、それからクロトをまとめて呼ぶとき には、﹁チビども﹂と総称することから、彼らが子どもでアルクゥ が世話をやいていることが分かる。ラフィールやエンカは地名。マ スクベルがラフィールの王であることは、さきほど判明した。しか し、ハンナの心内をくすぶるメルクゥに関しての情報は与えられな い。 アルクゥは神に愛された角つきでありながら、それを感じさせな いほどに明るく普通の青年だった。ドラゴンに転変すると雄々しく 立派な姿をしていて、人間でないことを強調させるが、平時の姿で はきわめて普遍的なことしかしない。 12 暇を見つければ臣下の手伝いや給仕の手助けを買ってでているよ うで、王宮の主であるハンナよりも馴染み、自由に歩いているよう に思えた。それでも突然現れた謎の青年に不信感を募らせる臣下も いるものだ。露骨に肩をぶつける様を見て、ハンナは﹁ガキ﹂と胸 中で舌をだす。悪意をぶつけられた当人はぼけっと突っ立って、不 思議そうに首を傾げているので、対して効果のない悪戯であること が分かる。 おおらかというよりは鈍感なのだと思う。 ﹁わあ、冷てぇ﹂ 落とした万年雪を素手で拾い上げ割れた瓶の破片を集めている様 子を視界に入れ、ハンナは息を吐いた。 万年雪はフリジットの特産品だ。空気に触れさせなければ溶ける ことがない。アルクゥが落とした万年雪は空気に触れたせいで溶け はじめ、敷き詰められた上等な絨毯に染みをつくっていた。凍える ような冷たさは健在しているのか、アルクゥの手が赤く変色してい る。 ガイルが留守でほんとうによかった。 最後の一枚に判を押せば、ハンナの一日の政務は終わる。難しい ことなどひとつもない。そういう仕事だけを与えられるということ は、ハンナに対する期待は地に落ちたことを証明していた。乱暴に 判を押すと紙束をまとめて机の端に放る。しばらくすれば臣下がや ってきて、口だけの労いを残して持っていくのを知っている。 むっつりと肘をついて黙り込んだハンナに、アルクゥが話しかけ てきた。 ﹁なあ。これ、溶けちまったけど⋮⋮﹂ べとべとに汚した両手を掲げて見せても、そこにはわずかな雪の 塊しかなかった。ハンナは困ったように眉尻をさげたアルクゥを一 瞥して、棚から飾り用のワイングラスを取りだすと無遠慮に突き出 した。わずかに唇が尖るのを感じる。 ﹁これに入れておきなさいよ。瓶の欠片もね。あとで処分させるわ﹂ 13 ﹁えー! もったいねぇ﹂ ﹁空気に触れた万年雪はただの雪よ。お土産に持って帰りたいなら、 新しいのを用意してあげるわ﹂ つっけんどんな言い方になっているのは分かっていた。 アルクゥは望んでフリジットに来たわけではない。もともと暮ら していたのはフリジットとは似ても似つかない豊かなラフィール。 ハンナはラフィールがどのような場所なのかは知らないが、雪に苦 しまなくてすむ土地には羨望を抱いている。代わり映えのしない白 と灰色だけの世界が、色とりどりに輝く瞬間など、フリジットには やってこない。どちらがいいのかなど目に見えている。目の前にい る変わった客人もいずれは故国に帰ってゆくだろう。 ﹁んー。いいや、別に。おれ、帰る気ねぇし﹂ ﹁⋮⋮いま、なんて言ったの?﹂ ﹁ん? おれ、帰らねぇから、土産なんていらねえよ﹂ 平然と言ってのけたアルクゥに、ハンナの方が頭を抱えてしまっ た。 てっきり、ラフィールに帰るとばかり思っていた。そのため、滞 在を望んだときのことなど考えてすらいなかった。幸いなことに王 宮内には空き室が存在するし、アルクゥが使用している来客用の一 室を、彼専用にあててしまっても問題はない。 浮上するやっかいごとは、ひとつだ。 彼の存在をどうやって臣下に納得させるかということである。ア ルクゥは現在、異国からやってきた来客という扱いで滞在を許され ている。しかし、客人はいつか帰るもの。ずっと生活していくもの を客人として抱え込むには不自然だった。けれど、とハンナはワイ ングラスに万年雪を入れているアルクゥの横顔を見つめた。 運命の相手などと言って、臣下が納得してくれるはずがない。 いつものように氷に似た刺々しい視線を寄こして、ハンナを鼻先 で笑うのだ。 ハンナと臣下の間には埋まらない溝がある。それを埋めたいとは 14 不思議と思わなかった。埋めたところでどうなるのだろうか。ハン ナが玉座をあけてから幾日も経つというのに、フリジットは当然の ように運営されている。見せかけの王がいなくとも厚い雪に閉ざさ れた小さな国は存在していけるのだ。 それならば、自分にできることはひとつ。 余計なさざ波を立てないように気をつけて、城の片隅でうずくま っていればいい。 ﹁帰ろうにもどうやって飛んできたのかわかんねぇし。どうせ、帰 ってもまたここに戻ってくるだろうしなあ。ちょっと寒いけど、雪 とかきらきらしてて綺麗だからすぐに慣れるよ﹂ ﹁⋮⋮のんきなものね﹂ フリジットに長年住んでいると、雪は忌避されるもので大手を振 って喜ばれるものではなくなる。実りを減らし、厚い壁を作っては 外界とも遮断される。人々の心も暗く重く閉ざされていくのだ。そ うして、誰もが願う。 ︱︱はやく、春がきますように、と。 小馬鹿にした響きが伝わったのかアルクゥがむっとして言った。 ﹁なんだよ。ラフィールには雪なんて降らないんだぞ?﹂ ﹁あら、そっちの方がいいじゃない﹂ ﹁なんで︱︱﹂ ﹁あなたは実りが多い土地で育ったから分からないのよ。雪は不幸 しか連れてこない﹂ 草木を覆い、太陽を隠し、厳しい寒さを引き連れる。 冬が嫌いだった。大好きな湖も厚く閉ざされて覗けなくなる。吹 雪になれば外にも出られず、馬車は深みにはまり抜け出せなくなり、 客人の来訪も極端に減った。大雪になる度にどんよりとした気持ち で窓から外を眺めていた幼少期が思い浮かんだ。 そんなハンナは、嫌いな冬に例えられて、白い目を向けられてい 15 る。 民草が嫌悪する冬と同じ︱︱。ハンナは冬の主そのものなのだ。 むすりと黙り込んでいたアルクゥは、拗ねたように唇を尖らせる と、 ﹁おまえ、自分の国のこと嫌いなんだな﹂ それだけを言い捨てて万年雪が入ったワイングラスを持って出て いった。 ただひとり。残されたハンナは誰もいなくなった室内に寒さが広 がるのを感じた。傍らに設えられた暖炉には薪がくべられ赤い舌に 舐めとられているというのに、心中には雪風が忍び寄ってくる。 ぎゅっと胸元をかき集め、ハンナはひとり呟いた。 ﹁⋮⋮さむい﹂ 16 3 怒らせてしまったのだろうか、と考えがいきついてハンナは知ら ず手を止めていた。 ペン先からにじみでたインクが羊皮紙に落ち染みを形つくってか らわれに返った。目前には皺が刻まれた目元に怪訝な色をのせたガ イルがいる。ハンナはごまかすように肩をすくめてみせたが、書類 を机に当てて整えながらガイルは問いかけてきた。 ﹁どうかなさいましたか?﹂ ﹁ガイルは︱︱﹂ どうして、自分の世話をしてくれるのだろう。 王として指導者として何もできない自分を、臣下の多くは見放し た。最初のころは付き添っていた人々も、いまはもう見る影もない。 ただひとり。教育係りを買ってでたガイルだけがこうして飽きもせ ずにハンナと顔を合わせて、空いた時間に物事を語って聞かせてく れる。フリジットだけではない。さまざまな場所のことを話して聞 かされるたびに、ハンナは見ず知らずの土地に想いを馳せることが できた。 ハンナの世界は、城の片隅にあった古臭い書斎とガイルが聞かせ る空想の場所だけだ。 ﹁どうして、わたしの傍にいてくれるの?﹂ じっとガイルの目を見すえた。逸らしもせずにガイルは柔和に笑 う。 ﹁ハンナさまを信じているからですよ。あなたはいい王さまになる﹂ ﹁そんなの︱︱﹂ ﹁嘘、だとお思いですか?﹂ おだやかで諭すようなガイルにしては珍しく強い語調だった。返 す言葉に惑ったハンナは、ぎこちなく首を縦に振って肯定した。 誰よりも知っている。自分が王に向かないことに。 17 ﹁私は、ハンナさまの笑顔が好きでした﹂ 天気の話でもするようにガイルは言った。 ﹁見るだけで春を思わせる。あなたは誰よりも春に近い。だから信 じています﹂ ﹁⋮⋮もう、笑えないわ﹂ 表情が張りついたように変化しなくなってずいぶんと経っている。 笑うこと。泣くこと。怒ること。すべてをなくしたハンナの顔。 ガイルは悄然と呟くハンナに困り果てて眉尻を下げた。 ﹁ガイルの望む王にはなれない。わたしには無理なの﹂ ﹁そんなことはありません﹂ ﹁︱︱無理よっ! ガイルには分からないっ!﹂ 弾かれるように机を叩いて腰をあげた。平行になっていた視線が ずれてガイルを見下す形をとる。背が曲がり、年相応の風貌をした ガイルはしかし、気をみだしたハンナとは対照的にひどく穏やかだ った。 行き場をなくした憤りを抱えたまま、ハンナは腰を下ろし謝罪を 口にする。 ﹁言い過ぎたわ。ごめんなさい﹂ ﹁いいえ、ハンナさま﹂ よいのです、とガイルは続ける。 子どものように癇癪を起こしてしまったハンナをとがめることも なく、ガイルは整えた書類に目を配りはじめた。さきほどの話はす っかり打ち切りになってしまった。そのことが、ガイルの信用すら も断ち切ってしまったように感じて、ハンナはいよいよ心がしおれ そうだった。 ﹁ハンナさま、ひとつだけよろしいですか?﹂ ﹁⋮⋮⋮⋮ええ﹂ ハンナにはガイルの考えを読み取ることはできない。ガイルにと ってはハンナの心境をくみ取ることなど容易なのだろうが、ハンナ はいつまでたっても柔和な老爺の思考を見透かすことができなかっ 18 た。なにを言われるのかと身構え言葉を待つことしかできない。 ﹁私の信用を疑うのは構いません。ですが、どうか笑ってください﹂ ﹁︱︱それは﹂ 不可能だとハンナは落胆する。 笑わなくなったのではない。笑えなくなったのだ。 以前までの自分がどのようにして笑っていたのかも霞んでしまっ て思い浮かばない。表情筋は抜け落ちたようにぴくりとも動かず、 頬は引きつったように痙攣を起こす。無意識に頬に手をやり、息を 吐いたハンナに、ガイルは憂いを帯びた視線を向けた。 ﹁ならば、春のおとずれを、あなただけは信じてください﹂ ︱︱春のおとずれ。 それはきっと、ハンナとはもっともほど遠い言葉のはずだ。 恵みを覆い隠す﹁冬の王﹂。ハンナの呼び名はそれひとつ。春を 切望する民に絶望を与え、臣下に軽蔑をうながす最悪の呼び名だ。 わかっていながら否定しないのは、自分がそう理解しているからに 他ならない。誰よりも何よりも知っている。 自分は愚王である、と。 ﹁ハンナさま。誰が疑おうともあなただけは信じなくては、春はや ってきません﹂ ﹁春のおとずれを、信じる﹂ ﹁そうです。それがこの老いぼれのたったひとつの願いです﹂ 澄んだ瞳がハンナの心を打ちふるわせた。 ガイルがハンナに望みを伝えることはそうなかった。いい王にな れ、などと言葉遊びもしない。ただハンナの歩調に合わせて隣で助 言を与えてくれるだけだったので、しっかりとした意思を伝えられ たのは初めてだったように思う。それも自らの利益を望むものでは なく、ハンナとフリジットの将来を憂えての言だ。ハンナはますま すガイルにかなわなくなってしまう。 春を信じる。それは考えたこともないことだった。きっと、ガイ ルではない誰かに言われれば、﹁馬鹿にして!﹂と激怒しても仕方 19 ない言葉でもある。それほどまでに、ハンナの政務に春をあらわす ものはない。 寒さをしのぎ、まぎらわせ、耐えさせることしかできない。 そして、以前までのハンナならば、たとえガイルであろうとも素 直に受け止めることはできなかったはずだ。心が凍り、表情が抜け 落ち、疑心にまみれたハンナの心中に、綺麗なもので固められた言 葉など届きはしなかっただろう。しかし、いまのハンナにはガイル の願いは震えるように届いて輝いた。じわりと温もりが広がるのを 感じる。 ﹁不思議ね﹂ ハンナがひとり言のように呟くと、ガイルは首をかしげた。 ﹁ガイルはきっといつもと同じ口調と考えを言っているだけなのに、 わたしはこんなにも素直に受け止めることができる。信じてくれて うれしいと、心が喜びに震えている﹂ うれしい。自分の政権下で春を信じられていることがこんなにも、 うれしい。 それは、まぎれもないハンナ自身の変化だ。 溶けるはずがないと思っていた疑心。 よみがえるはずがないと思っていた感情。 すべてが鼓動するように内側から溢れてくる。 うれしいとハンナは噛みしめるように思った。いつぶりの感情だ ろう、と。 ﹁ハンナさま。人は変わるもの。いまは歩んでください。春を信じ、 春を迎え入れるために﹂ 春を迎えいれる。 輝かしい実りの季節。厚い雪が薄まり、緑が深まる。目を閉じる だけで温かい風が頬を撫でるのを思い出す。フリジットの民は厚く 覆われた雪の中、身を寄せ合って春を待つ。忍耐と激情にあふれた 素晴らしい民だ。 その民に、春を贈る。それは、とても幸福なものだと感じた。 20 誰もが願い乞う春を、自分の手で迎え入れることができたなら、 どれほどの至福だろう。 ﹁そして、できることなら︱︱﹂ ガイルは、すっかり書き物をやめてしまったハンナを見すえてゆ っくりと言った。 ︱︱どうか、もう一度、笑ってください。 21 4 フリジットの王宮内で甲高い笑い声が響き渡っていた。肩口で切 りそろえられた金色の髪をひるがせた少女は、曇りのない笑みを浮 かべて背後の人物に一回転してみせた。質素なワンピースドレスが 広がるのを見とがめたフリジットの王ベルモンドは目を細めて少女 に注意する。 ﹁およしなさい、ハンナ。下着がみえてしまう﹂ 少女は慌てたように裾を引っ張ってなおした。それから困ったよ うに立ち尽くしている自らの父親に甘えるように抱きつく。雪国に ふさわしい厚手のマントが少女の鼻先をくすぐった。ベルモンドは すがりつくわが子をもてあましていたが、やがて無骨な手で頭を撫 ではじめた。 ﹁今日もハンナさまはお元気そうで﹂ ﹁ああ。︱︱︱︱。元気すぎて困ってしまうよ﹂ ﹁私はハンナさまの笑顔が好きですよ。まるで春をおもわせる﹂ ベルモンドが親しそうに話す男の顔は不可思議にもやがかって少 女には見えなかった。男の名をベルモンドが呼んでもぽっかりと抜 け落ちたように聞こえる。しかし、少女はそんな男に怯えることな く駆け寄ると、父親にしたように抱きついてにっこりと笑んでみせ た。そんな少女に男も口をゆるませる。 ﹁春! わたし、春が好きよ﹂ ﹁ええ、ハンナさま。私も好きですよ﹂ ﹁あったかくて、いろんな食べ物があるの! もうすぐ春がくるの ね!﹂ 踊るように身をひるがえす少女は、悪戯を思いついたように舌を だし、﹁でもね﹂と続けた。 ﹁わたし、冬も好きよ。だって︱︱﹂ 22 だって︱︱。 あのとき、自分が何と言ったのかハンナはずっと思い出せなかっ た。 男の顔はぼやけて見えず、父はいつもよりもぎこちなかった。 その日、ハンナの母であるシーナが息を引き取った。 冬の終わり。春がこようとしていた。ハンナは親子三人で春を迎 え入れようとしていた。しかし、母は春がくる前に遠くにいってし まい、幸福なはずの春のおとずれはハンナに大きな傷跡を残して立 ち去ってしまった。 母が亡くなり、暗くよどんだ城内でもハンナは笑い続けた。父の ため。臣下のため。そして他ならぬ自分のために。ハンナはほほえ み続けた。明るく振る舞い続けた。身を引き裂かれたように悲しか ったはずなのに、幼いハンナは泣かなかった。あれほどの悲劇のあ とにも枯れることのなかった笑顔は、いますっかりと枯れ果ててし まった。 笑顔が好きだ、とのたまった男をハンナは思い浮かべる。 他でもない。男の正体はガイルだ。 笑ってほしいとガイルは願った。笑顔が好きだとガイルは言った。 ︱︱ハンナの笑顔は凍りついてしまった。 城の廊下を歩くとき、ハンナはいつもうつむきがちに歩く。通り 過ぎる給仕たちが深々と頭を下げるのを尻目に逃げるように古臭い 書斎に向かう。そこにいけばガイルがいて、臣下の目に触れること がなくなるのを知っている。廊下を移動している最中に臣下に鉢合 わせることは避けたいことだった。 ﹁ほら﹂ それなのに、書斎の前でハンナは待ち伏せしていたアルクゥに捕 23 まった。 ぶっきらぼうに差し出された掌上には万年雪が詰められた瓶がの っている。アルクゥが割ってしまったものとは違う赤いリボンが施 されたそれは新品に思えた。受け取ることも忘れてハンナはじっと りと瓶を眺めやった。何の変哲もない万年雪だ。 ﹁お土産に買ったの?﹂ 帰らないからお土産は買わないと言っていたのに。 ﹁ちげぇよ。この前、あんたのやつ割っちゃっただろう﹂ ﹁⋮⋮気にしなくていいと言ったわ﹂ ﹁そんなこというなよ﹂ アルクゥはどこか憮然として続けた。 ﹁母親からの贈り物なんだろ﹂ ﹁どこでそれを⋮⋮﹂ 彼には話した記憶がないが、確かにあの万年雪は母からの贈り物 だった。雪を嫌うフリジットで、なぜ﹁万年雪﹂を贈られたのかを ハンナは知らない。けれど、冬の王と蔑まれているハンナにはおあ つらえ向きだったと思う。戒めのつもりで持っていたつもりだった それが、思わぬ形でめぐり返ってきてしまった。 万年雪の入った瓶を受け取りながらハンナは微妙な心持になる。 ﹁爺さんが教えてくれた。あんた、嘘ついたな﹂ なじるようにアルクゥが言うので、ハンナの眉根が寄った。 ﹁身に覚えがないわ﹂ そもそも、嘘をつくほどアルクゥと会話をしたことがない。 ハンナはいつもガイルと書斎に閉じこもっているし、彼は城内を 歩いては給仕や臣下と友好を深めている。とがめるつもりはないが、 覚えのないことで非難されるつもりもなかった。眉尻が跳ね上がる のを感じながら彼を睨みすえると、逆に睨みかえされた。 ﹁みんな、べつに雪が嫌いなわけじゃない。あんたは嘘つきだ﹂ ﹁なっ⋮⋮﹂ ﹁街におりて、それを買ってきたとき、贈り物にするって言った。 24 誰も止めなかったし、嫌そうな顔もしなかった。笑顔ですすめてく れたよ。大事な人にはぴったりな贈り物だって﹂ ﹁⋮⋮⋮⋮﹂ 万年雪。溶けない雪。 それは溶けない関係をあらわす。色恋にはうってつけの贈り物だ。 ﹁知ってたんだな? じゃあ、なんで雪が嫌われてるなんて言うん だ﹂ ﹁わたしは、きらいよ﹂ ﹁︱︱っおまえ!﹂ かたくなに閉ざした心でハンナは目をつぶった。 たとえ殴られてもかまわない。雪はきらいだ。冬も、きらいだ。 ︱︱すべてを覆って隠してつれていく。 ﹁なにを騒いでいる﹂ ﹁⋮⋮ガイル﹂ 書斎の扉が開かれて顔をのぞかせたガイルは怪訝な顔を一変させ て柔和に笑った。 ﹁これはハンナさま。遅いと思っていたら捕まっていたのですね﹂ ﹁ええ。ごめんなさい。すぐに執務にとりかかるわ﹂ 幸いとばかりにハンナはアルクゥに背を向けた。 ハンナにとって彼の瞳はいつでも真っ直ぐで苦しめる。そうやっ て苦しめるのに、彼の心にはハンナの入る余地はなく、顔も知らな い誰かがわがもの顔でおさまっている。そのことに目くじらをたて ることも、張り合うつもりもなかった。だからこそ、そっとしてお いてほしかった。 フリジットは雪国。ラフィールとは違う。ハンナの国だ。 逃げるように背を向けたハンナに、それでも棘をするどく言葉は 飛んだ。 ﹁おまえの国のものを、おまえがないがしろにするなよ!﹂ 25 書斎の扉を閉める直前、ハンナは耐えるように瓶を握りこんだ。 26 5 ﹁大丈夫ですか?﹂ ﹁⋮⋮ええ。平気よ﹂ 万年雪の入った瓶は可愛らしい赤いリボンが添えられている。ア ルクゥが思案しながら選んだのかと思うとお礼のひとつも口にしな かったことが心残りだ。 それでも、ハンナは雪が嫌いだ。嫌いだと言っている人物にわざ わざ贈りつけるものだろうか。自嘲するように鼻で笑うと、瓶を棚 に押しやった。せっかくの贈り物を乱暴にあつかうわけにもいかず、 ハンナは棚にしまうといそいそと椅子に座りなおす。あいもかわら ず訳のわからない文脈がのった書類が待ち受けていた。 ﹁︱︱これ、おかしくないかしら?﹂ 書類をめくって目を通し、判を押していたハンナはふと手をとめ た。 書類に書かれているのはフリジットの西端に位置する村を結ぶ道 路整備の案件だ。几帳面な文字の連なった書類は一見すると、当た り前のことを書いているように見える。しかし、引っ掛かるものを 感じてハンナはよくよく目をこらした。 ﹁ほらやっぱり。ここは雪崩のせいで削り取られた場所よ? そこ に道などつくれないわ﹂ ﹁ああ、たしかに。再提出させましょう﹂ ﹁必要ないわ。ここの地盤が固い場所をひらいて道をしきましょう。 そうすれば王都にも近くなる。民の負担も減っていいじゃない︱︱﹂ すらすらと口からでる言葉にハンナは思わず口を塞いだ。 ガイルは驚いたように瞠目し、口を押さえて固まるハンナをまじ まじと見つめた。 ﹁ごめんなさい。勝手に︱︱﹂ ﹁いえ。そうしましょう﹂ 27 ハンナを呼ぶ声はどこまでも優しく響いた。 ﹁あなたの案がいちばん民にやさしい﹂ ﹁⋮⋮そうかしら﹂ ガイルにほめられるのは慣れている。できの悪いハンナを叱るわ けでもなく、前日できなかったことが翌日にできるようになると、 顔をしわくちゃにさせてほめそやしてくれるのだ。そのたびにハン ナはくすぐったい心地になって、じわりと温かみを感じる。 ﹁ゆっくりでいいのです。そうやって政務に関わっていただければ、 いつか臣下もわかりましょう。政は長い目で見なければ何もわから ないもの。時間はあるのです。ゆっくりと︱︱﹂ ガイルはハンナの言葉に耳を貸す。臣下は耳を貸さずに拒否をす る。 民にやさしい政策は民を怠惰にさせる。だからこそ生かさず殺さ ずの政策を取るというのが臣下の提示する政策だった。そのたびに ハンナは緩めようと提言したが、何も聞き入られることはなく、訳 のわからない地名や数字を用いて言い負かされてしまう始末だった。 そのうちにハンナの心には諦観がうまれ、玉座に座るのが苦痛に なった。 提示される政策にただうなずいて日々を浪費するのが癖になった とき、臣下のひとりが判を押すだけの仕事にしてしまえばいいと提 案した。それは駄目だと立ち上がろうとしたハンナを尻目に臣下た ちは話をすすめ、ハンナはこうして判を押すことだけが役割になっ た。 王である。そう胸を張っていえなくなった。 ﹁ゆっくりしていていいのかしら﹂ ﹁慌てたところでよいことはありませんよ、ハンナさま。あの者が やってきて、ハンナさまには目に見えぬ変化があった。私はそれが うれしくてたまらないのですよ﹂ ﹁たとえば?﹂ ﹁表情が柔らかくなった。こうして、政務にも身をいれてくださる。 28 そのすべてですよ﹂ 意識したことはなかった。 凍りついたままの表情は変わることをしらない。 臣下のせいで打ちのめされた意欲は地に落ちたまま。 ハンナは城の片隅。古臭い書斎にガイルと閉じこもって判を押す。 ただ、それだけのことをしているだけだった。 たしかに、アルクゥはよくも悪くもハンナの心を揺らしては、無 責任に去っていく。運命の相手だというわりには冷たくあたり、ハ ンナを深くえぐりとっていく。眩しいのだ。ハンナには彼のすべて が眩しく輝いて、目がくらみ見ていられなくなる。そうして、目を ふさいでしまえば何も見えない。ただの暗闇がせまってくる。 ﹁ねえ、ガイル﹂ 呼びかける声は覇気もなく、しおれて途中でくび折れた。 ﹁わたし、雪がきらいなの﹂ ﹁存じておりますとも﹂ そうだ。ハンナは雪が嫌いだ。 重く大きく落ちては積もり、溶けずに残る。そうして草木を覆い、 恵みを隠す。生命の循環を鈍くして終わりをはやくつれてくる。生 き物の呼吸すら白銀の世界に閉じ込めて、フリジットを外界から切 り離す。 雪は悪魔だ。絶望しかもたらさない。 それでも、とハンナは人知れず思った。幼い無邪気なときを思い 浮かべた。 ﹁冬は好きだったの﹂ だって、と舌足らずな声が聞こえた。 まぎれもない幼い自分が立っている。すました顔をしてお気に入 りのワンピースドレスを着こなし一回転してみせる。ハンナが忘れ てしまった真昼の笑顔をふりまきながら無邪気に言うのだ。何も知 らず。いや、知っているからこそ。幼いハンナは笑い続けた。 ﹁冬は︱︱春をよりいっそう、美しくすばらしいものにしてくれる﹂ 29 ﹁⋮⋮ハンナさま﹂ 冬が好きだと言った。幼いハンナは迷うことなく口にした。 長く苦しく、厳しい冬の終わり。耐え忍び、身を寄せあい、待ち つづけたそのさき。 ︱︱美しい実りの春がやってくる。 白い雪からこぼれでる緑のうつくしさ。 覆われてもなお育つ生命の脈動。 すべてが輝く春は、長い冬を終えてこその壮麗をほこっている。 ﹁だから、好きなのよ﹂ こぼれでる言葉のすべてに偽りはなかった。 春を想い、冬を耐え、そして身を寄せあって生きるフリジットの 民。 まるで、春に恋をしているように、誰もが望み願う。そのすべて を。 ﹁︱︱わたしは、この国が愛おしい﹂ 穢れをしらず、ただ白く積もる雪。 春に恋い焦がれ、身を焼いていく民たち。 望まれ、恵みをもたらす冬の終わり。 ︱︱その名を、春。 30 6 緑にあふれた大地は美しい。青く広がる空を飛ぶのは心地よい。 厚い灰色の雲がたれこみ雪を落としていくフリジットの空を、ア ルクゥはひとり見上げた。 故郷の空とは似ても似つかない。自分はほんとうに遠い国にきた のだと納得し、寂寥を感じる心中に苦笑した。雪片が羽をうっても 高く飛びたてる自信はあったが、フリジットに来てからというもの ドラゴンに転変したことはない。苦痛に思うことはなかったが、大 空を飛びまわる解放感を知っている身としては、わずかばかりの落 胆もある。 ︵一緒に飛んだりしないかな︶ 無表情で書類をめくっているハンナの顔を思い浮かべアルクゥは 嘆息した。 生まれ育ったラフィールを離れ、知らぬまにフリジットにやって きた。自分が﹁咎落ち﹂してしまったことはわかっている。人の体 をたもてなくなった時から、いずれ理性をうしないドラゴンとなっ て飛び立つことは目に見えていた。その最後の瞬間まで、寄り添っ てくれた人を想って目を閉じる。 罪なのか。罰なのか。アルクゥには何ひとつわからない。 フリジットにやってきて、はじめて雪を見た。 綺麗だと言ったアルクゥにハンナは反感をしめした。雪はここで は喜ばれないと嘘までついた。街におりて見た人々は、苦労をにじ ませていたがちゃんと共存していた。彼女が顔をゆがめてまで忌避 した雪はどこにもなかった。 くれない 言の葉を剣にして刺し貫いたアルクゥに、ハンナはそれでも弱さ を見せなかった。 薄い瞼はふかく閉ざされ、すました唇には紅がやどる。その身に まとう空気はただひたすらに清廉。だからこそ、アルクゥは思った。 31 彼女はきっといやがるだろう。侮辱だと口をゆがめるかもしれない。 けれど、彼女はまさしく極寒の国フリジットにふさわしい冬の王 だ。 ﹁ここにいたのか﹂ ﹁⋮⋮爺さんか﹂ 城の二階から張り出したバルコニーには厳しい風が吹きすさぶた めに誰もやってこない。雪がかからないように頭上には屋根がはり だしているが、横ざまにやってきた雪片が手すりにうっすらと積も っていた。ガラス張りの扉を遠慮がちに開きながら顔をのぞかせた のはガイルだ。 ハンナのかたわらに寄り添い、教育をほどこしているという老爺 は、皺だらけだったが背筋は針金をとおしたように真っ直ぐだった。 ハンナの前ではおだやかにゆるむ表情も、いまは厳格さをたもった ままだ。 ガイルを一瞥しただけで、また空を見上げたアルクゥに低いしゃ がれた声がかかる。 ﹁万年雪を贈ったようだな﹂ ﹁あんたが怒ったからだろ?﹂ ﹁それは怒る。あれは亡きシーナさまの形見。︱︱ハンナさまには 痛みがともなう品でも、だいじなものだ﹂ ワイングラスを片手に万年雪のとれる場所を聞いてまわっていた アルクゥは、ガイルに見つかり叱責をうけた。話を聞けば亡くなっ たハンナの母親が彼女に贈った唯一の品だという。割ってしまった ことにさらなる罪悪感をつのらせるとともに、アルクゥの頭によぎ ったのはハンナの態度だった。 実母の大切な贈りものが壊れた。それなのに、彼女はどこまでも 冷たく静かだった。 壊したアルクゥに怒るわけでもなく、平坦な声で処分すると言っ た。割れた小瓶を見つめる瞳にはわずかな悲しみと、隠しきれない 安堵がやどっていた。その意味するところをアルクゥは読み取れず 32 にいる。 ﹁痛み⋮⋮﹂ ぼんやりと呟いたアルクゥに、ガイルはバルコニーに身をさらし て続けた。 ﹁そうだ。ハンナさまは覚えていない。いや、覚えていないほうが 幸せなのかもしれない﹂ ﹁なにを?﹂ さきをうながしたアルクゥにガイルは言葉をにごした。 ﹁︱︱自分の罪の記憶というものか﹂ ﹁罪の記憶⋮⋮﹂ ︱︱それは、罪なのか。罰なのか。 ︵メルクゥ︶ 心に思い浮かぶのはただひとり。 交わした言葉を、重ねた想いを、分かちあった温もりを。忘れな いように。 ﹁ひとつ、勘違いしないでもらいたいことがある﹂ ガイルは皺だらけの顔を気難しげにゆがめてから口を開いた。 ﹁ハンナさまは雪が嫌いだが、冬は嫌いではない﹂ ﹁それの︱︱﹂ なにが違うのか、という問いかけは口中に消える。 ﹁雪はハンナさまから大切なものを奪い取っていった。それこそ、 王妃さまからの贈りものを無下にあつかってしまうほどに、彼女の おもんぱか 心をふかく傷つけた。おぬしの言葉は真をとらえたものだ。非難は できない。それでも⋮⋮ハンナさまの心中を慮ってほしい﹂ 雪は嫌いだ、と口にした。ハンナの顔は蒼白だった。 目前に立っていたアルクゥを突き抜けて、彼女の視線ははるか遠 くに投げ出されていたように思う。そのさきで、彼女はなにを見て、 なにに恐怖し、なぜ目を閉ざしたのか。憤りをぶつけたアルクゥに、 33 耐えるように瞼を閉ざした様子が思い浮かび、わずかに身じろぎす る。 凍りついた唇を動かして放った言葉は、ひどくぎこちなかった。 ﹁⋮⋮わかった﹂ ﹁そうか﹂ ガイルはそれ以上、なにも言ってこなかった。 やがてまつげのさきまで凍ろうかというとき、雪がやんだ。 ﹁あ﹂ ﹁ああ、やんだな﹂ フリジットに重く降り積もる雪がとぎれ、灰色の雲がかすかに明 るんだ。 雲間からじわりと滲むのは黄色。そこだけ丸く形をとって白い筋 が降りたってくる。フリジットにはめずらしい太陽が落とすカーテ ン。その光のさきに目を細め、アルクゥは息を吐いた。湯気に似た 吐息が目前を通りすぎ、澄んだ空気が肺を膨らませる。 となりのガイルが噛みしめるように落とした言葉はどこまでもふ かく重い。 ﹁いい天気だ﹂ 灰色の雲を押しやって覗きこんだ太陽は、下に広がる国を見て何 を思っただろうか。そうして太陽をのぞむアルクゥは白く輝く光の 輪に、かつて愛したものを見ていた。 34 7 重厚な扉の向こう。大きな暖炉が設えられたその場所は、室内こ そ暖かいものの中の空気は凍えるほどの冷感をもっている。そのこ とを理解しているハンナは、綺麗に磨かれた取っ手を握ろうかと逡 巡しているところだった。 ︵また、白い目を向けられるだけ︶ 会議場で行われるのは政の議論。ハンナには理解の範疇をこえる 言葉が飛びかい、ため息を落とされ冷えた視線を送られる。苦い記 憶しかない場所だ。 城内は外の寒気をふせぐ術がとりそろえられ、どこもかしこも暖 かだったが、ハンナの心中は扉を前にして吹き荒れていた。戦場だ と揶揄したのはハンナ自身だったか。扉のさきに広がるなんの変哲 もない場所が、近寄りがたいものになったのは確かだった。父親で あるベルモンドが幾度もこの場所に踏み入っては、気難しい顔でで てきていたことは知っている。 ︱︱逃げてはいけない。 いつまでも城の片隅で、判を押すだけの仕事をしていていいわけ がない。 臣下との間にうがたれる溝を埋めたいとは思わなかった。そのま までいいと目をそらした。それでも、と唇をうるおわしてハンナは ひとりごちる。 忍耐と激情をあわせもつフリジットの民は、他でもないハンナが 庇護しなければならない。 ガイルは言った。ハンナの案がいちばん民にやさしい、と。 やさしいだけの政策は民を怠惰にさせると臣下は言った。 双方の意見。どちらが正しいのか、いまだハンナにはわからない。 雪に厚く閉ざされたフリジットの特産品は多くなく、﹁万年雪﹂ を筆頭にどれもが冬にとれる。冬の時期が長いフリジットで春先に 35 とれるものがいかほどのものでも、年中を通しての収穫にはなりえ ないからだ。ハンナにとって忌み嫌うべき雪も、民には必要な収入 源になる。それでも、わずかばかりの憩いをもとめて、民は春をま っている。 ベルモンドの政策が﹁雪解け﹂と称されていたことは知っていて も、内容はわからない。父親をほめられて喜んだ幼いハンナは、敬 愛の念をもっていても、何に対して敬愛していたのかは漠然として いた。父親は、何かすごいことをした。それ以上でもそれ以下でも ない。 何も知らないのだ。ハンナには知識も経験もない。 だからこそ、臣下はハンナに冷たいのだろう。何もわかっていな いと言葉を鋭くする。 実際、ハンナは何もわかっていないまま玉座に座り、何ごともで きず城の片隅に追いやられた。政策のすべてはハンナの名を借りて 行われる別次元の物事で、当の本人は古臭い書斎にこもっている。 しかし、民にそのようなことは関係ない。授けられる政策にあえぎ、 それでも耐えて生きる民から目をそらすことは、この上ない大罪に 思えた。 ︱︱ゆっくりでいいのです。 そうだろうか、とハンナは悩む。 張りつめられた氷の上を踏み外さないように歩いても、ハンナは まだ迷う。 前を向いてゆっくりと踏み抜かない程度に歩んでも、前には進む だろう。 けれど、とハンナの手は取っ手を握りこんだ。指先まで凍ったよ うに冷たく、肩にはずっしりと重責がのしかかってくる。肺にたま った空気が圧迫され、ハンナはひとしれず息を吐いた。小刻みに腕 が震えるのは恐怖心からなのか。 36 扉を開けば、ハンナの前にさえぎるものは何もなく、苦痛がやっ てくる。 ︵でも、開かなければ⋮⋮︶ 白銀の世界。春を望む民。 そのすべてを愛おしいと思った。 歩いていても、目前の扉が閉まっていれば、どこにもいけない。 そのさきを進もうと決意したのならば、取っ手を握り開かなけれ ばならない。たとえ、さきにある光景が苦痛をともなうものでも、 足を踏み出す場所に棘が敷き詰められていても、扉を開かなければ、 ハンナはいつまでも立ちつくすことしかできない。 柔和に笑う老爺は、ハンナにいつでもやさしかった。そのやさし さに甘えていたのは他でもない自分だ。ガイルは決してハンナを怠 惰にしようとしたわけではなかった。踏み出すための心構えを丁寧 につくろってくれたにすぎない。 ハンナの背を無遠慮に押したのは、灰色の青年だった。 厳しい声音でハンナを追い詰め、逃げれば言葉を飛ばした。その すべてを憎いとは思わない。瞼を閉ざしたハンナに、フリジットの 光景を見せつけて、そして彼は美しいと言った。ハンナが忌避する 雪を、白い世界しか広がらないフリジットを。 嫌いなのかとアルクゥは言った。自分の国を。生まれ育った場所 を。 そんなはずがない。ハンナの心中に芽生えたのは反感だった。嫌 いなはずがない。遠いラフィールからやってきて何も知らない青年 にはわからない。灰と白しかないフリジットに太陽がのぼれば光を 反射してなお美しい。余計なものを通さない空気はひたすらに純粋 で、それらを介した光の筋がどれほど美しいか。分かるものかとハ ンナは胸中でなじった。 ︱︱こんなにも、わたしの国は美しい。 37 白に閉ざされた国・フリジット。忍耐と激情をやどすフリジット の民。 男は忍耐を、女は激情を︱︱。 ならば、ハンナはフリジットの女にふさわしい激情をもって進も う。 取っ手を握りこむ腕は震えていない。凍りそうだった心中もおだ やかだ。 開かれていく扉のさき。そこから突き刺さる氷の粒をハンナは甘 んじて受け入れた。 燃えるような脈動を。内に秘めた想いを。隠すわけもなく。 そうして広がった光景に、ハンナの口の端はしらず弧を描いてい った。 38 第二話 冬の鍵 ぱちぱちと薪がはねる音が広がり書斎を満たしていた。執務をと りおこなう部屋は別にあったが慣れ親しんだ場所を離れる気もおき ず、ハンナはあいかわらず古臭い書斎にこもっている。変わったと ひんぱん ころといえば、運び込まれる書類の量が増えたことと、臣下が顔を のぞかせることが頻繁になったことだ。 会議に参加するようになってハンナはただうなずくだけではなく、 やっき 意見を口にするようになった。当然、反発はあったし意地の悪い臣 下の多くは口で負かそうと躍起になった。自分で決めたこととはい え、鋭い雪片が飛びかう会議場はやはり戦場に近しい。しかも、立 ち向かうと、前に歩き続けるために痛みは倍になった気がした。そ れでも、すがすがしい心地でハンナはいつも会議場を後にする。 いつものように朝議を終えて、毛皮の張られた椅子に腰かけたハ いたずら ンナのもとにあらわれたのはアルクゥだった。むっつりと黙り込ん ふもと だまま、空いた椅子に座っていたアルクゥに、ハンナは悪戯に言葉 をかける。 ﹁ねえ、ラフィールの話をして﹂ ﹁⋮⋮なんだよ、いきなり﹂ やにわに言われてアルクゥは眉根をよせる。 ﹁気になっただけよ。ラフィールの民はみんな角を?﹂ しょ ﹁いや、エンカのものに角はない。エンカはラフィール山脈の麓に うざん 広がる街の名だ。おれたち角つきはエンカで生まれラフィールに昇 山する﹂ ﹁昇山?﹂ ﹁ラフィール山脈の入口に教会がある。そこで角をもって生まれた 子は祝福を受けて、親元を離れ山にあがる。それを昇山というんだ。 おれも角をもって生まれたから昇山した。親の顔は知らない。角つ きはほとんどがそうだ。赤ん坊のときに山にあがるから、育ててく 39 れるのは同じ角つきなんだ﹂ アルクゥの頭にはいまも鈍く光る角がある。枯れ枝に似た形をし たそれは灰色。アルクゥの髪色と混じって生えていて根本はわから ない。ラフィールの角つきは神に愛されているという。それはラフ ィールでも祝福されることなのだと知った。 ﹁じゃあ、家族はいないのね﹂ ﹁しいていうなら、角つきたちが家族さ﹂ ああ、とハンナは納得した声をあげた。 ﹁アナベルたちがそう?﹂ ﹁そうだな。生意気なやつらなんだ。とくにエディは問題児でな。 アナベルをからかってはいつもクロトに怒られてる。クロトはラフ ィールにも珍しい黒竜で⋮⋮まあ、マスクベルさまも黒竜だけど。 とにかく優秀なやつなんだ。あいつらはいいドラゴンになる﹂ ラフィールの話をするアルクゥは普段よりもやさしい顔つきをし ていると思った。問題児となじるエディにしても語る口調はひどく 穏やかだ。その中でもひときわ彼が慈しむように話したのはアナベ ルという少女のことだった。 ﹁アナベルはまざりものなんだ﹂ 痛々しそうに顔をゆがめ言われてもハンナにはわからない。首を 傾けてさきをうながしたハンナにアルクゥはとても言いづらそうに 口を動かした。空気を押しだして震わせた声音はひそやかで、妙に ハンナの耳をうった。 ﹁︱︱できそこないなんだ。体は弱くて翼はもろい。鱗の色が同一 ひご でなく混ざっているから、まざりものと呼ばれてる。はかない存在 だと庇護するものもいるが、多くはできそこないとして扱う﹂ ﹁⋮⋮かわいそうね﹂ ハンナにはそうとしか返せなかった。 生まれつき宿した欠陥をつつくなんて卑怯だと心中でなじる。 暗くよどんだ空気を一笑したのはアルクゥのほうだった。 ﹁そんなことないさ。アナベルは負けず嫌いだから﹂ 40 ﹁え︱︱﹂ ﹁翼が強くないなら、ぶつからないように飛べばいい。力が弱いな ら素早くなればいい。そうやってアナベルは強くなった。体も心も。 いまじゃ、立派な角つきだ﹂ 誇らしく輝くアルクゥの横顔を盗み見て、ハンナはひそやかに息 をついた。 帰らないと口にして、帰らないまま滞在しているアルクゥは、ラ フィールの話をすると生き生きとしている。フリジットはアルクゥ にとって嫌な国ではないようだったが、生まれ育った地を悪く思う はずもない。アルクゥの心内では、いまも緑豊かなラフィールが息 づいている。そこに住んでいたものたちの記憶もまた鮮明に残って いることだろう。 ﹁すごい子ね。わたしとは全然ちがう﹂ 傷つくのが嫌で目を閉ざした。民を庇護する役割もかなぐり捨て て、城の片隅で判を押すだけで満足していた。自分がしなければな らない義務から逃れて、言い訳を陳列して、ハンナは何もせずに日 々を削っていっただけだ。 ﹁そんなことない。あんただって⋮⋮その、がんばってる﹂ ﹁あら、今日はずいぶん優しいのね﹂ ﹁おれはいつだって、やさしい﹂ そんなことない、という言葉は飲み込んでハンナは薄く笑った。 怖がって逃げていたことに立ち向かえば、思ったよりも苦痛では なくなった。自分に足りないものを認めてしまえば、変な意地を張 らずにもすむ。自尊心だけを高く積んだ臣下たちは、とても息がし づらそうな生き方をしていると傍観できるほどには、ハンナの心境 に余裕が生まれた。自然と強ばっていた表情もほどけていく。 ﹁じゃあ、お優しいドラゴンさん。わたしの名前を呼んでみて?﹂ ﹁はあ?﹂ ふそん ずっとハンナには疑問と不思議が渦巻いていた。アルクゥはハン ナの名を呼ばない。﹁あんた﹂や﹁おまえ﹂と不遜な呼び方はして 41 も、生来の名を口にしたことはなかった。ハンナ自身に思うところ はなくても、ガイルや側近たちは気に障るらしい。書類を持ってき た臣下はわずかに顔をゆがめ、なぜかハンナをいさめてきた。 ﹁自己紹介はしたでしょう? ほら、はやく﹂ ﹁︱︱⋮⋮うっ﹂ ﹁一国の王を不躾に呼んで、ガイルの反感を買ってもいいの?﹂ 脅すように目を細めれば、アルクゥは顔を青くした。 ﹁ぐ、う⋮⋮くそっ! 呼ぶよ! 呼べばいいんだろ﹂ 吠えるように言ったアルクゥにハンナは苦笑を浮かべる。いった いあの老爺はこの灰色の青年に何をしたのやら。アルクゥはガイル の名をだすとたちまち横柄な態度が縮小してしまう。万年雪を壊し たおりに何ごとかあったのかもしれないが、とくべつ追求すること もないように思えた。頭を抱えてもんどり打っているアルクゥの姿 を見るほうが楽しい。 ﹁⋮⋮⋮⋮な﹂ ﹁え?﹂ ﹁⋮⋮ハンナ﹂ 呼んだわりにはすぐに顔をそらす。それが変に面白くてハンナは 笑んだ。 ﹁よかったわ。名前を忘れていたわけじゃないのね﹂ ﹁当たり前だろ。おれは記憶力がいいんだ﹂ ﹁ええそうね。不器用なドラゴンさん﹂ からかうように言ったハンナに、むっとアルクゥは眉をよせた。 ﹁今日は意地悪だな﹂ ﹁︱︱いつものお返しよ﹂ 目を細めて返したハンナに何を思ったのかアルクゥはそれきり黙 り込んでしまった。 ハンナ自身も山積みにされた書類に手をつけなければならなかっ たので、静寂が書斎を満たす。ガイルの教育は政に関わるようにな ってから、ろくに時間もとれずおろそかになっていた。それでも合 42 間をみては茶を用意し、ふたりで顔をあわせる。書斎に姿が見えな いときは、何かしらの用事で城内にいないことが多い。どうやら、 本日は不在のようだ。 インクの蓋を閉じてから、暖かさにまどろんでいたアルクゥを呼 ぶ。 ﹁わたし、今日は城下におりるの。案内してもらえるかしら?﹂ ﹁へえ、めずらしい﹂ ﹁民の生活を見学したことがないの。詳しいのでしょう?﹂ アルクゥが城外にでていることは知っている。万年雪を買いつけ るときも、場所を聞いただけで買ってきたのだ。ろくに城をでたこ とがないハンナよりも外の情勢を理解しているだろう。ガイルがい れば兵隊を護衛につけられ、身分がばれてしまうおそれがある。い ないときにすませてしまうのがいい。 ﹁まあ、それなりに?﹂ ﹁じゃあ、案内をよろしくね﹂ 窓の外は一面に白。降りしきっていた雪がやみはじめた頃合いだ った。 43 2 せいたん ハンナがおとずれたいと願ったのはフリジットの西端に位置する 村だった。 雪崩が起き、王都まで続いていた道が切断され孤立していた場所 でもある。そこにハンナが立案した新しい道が整備され通行できる ようになっていた。石を敷き詰められた道はなだらかに村まで連な り、ハンナたちを迷うことなく迎え入れる。 厚い防寒具にくるまれたハンナは白い息を吐きだしながら感嘆し た。 ﹁︱︱わあ!﹂ ﹁⋮⋮そんなにはしゃぐところか? ここ﹂ 眼前に広がるのは寂れた小さな村だ。子どもたちが作った少し傾 いた雪だるまが出迎える。指先が破れた手袋を枝にさしこみ、雪だ るまの体にさしこんでいる。ハンナは手が荒れるからと雪遊びもさ せてもらえなかった。それゆえにこういった創作物ははじめてみる。 ﹁かわいいわ。いったい、どんな職人がつくったのかしら?﹂ ﹁ふつうに、子どもだと思うけど⋮⋮﹂ ﹁まあ! この村の子どもたちはみな優秀ね﹂ ﹁︱︱なんか、あんた性格変わってない?﹂ 怪訝そうに見つめてくるアルクゥにハンナは腰に手をあてふんぞ りかえった。 ﹁あら? わたし、もともとこういった性格よ﹂ ハンナはよく笑う。 フリジットの民は、男が耐え忍びむっつりと言葉を隠すかわりに、 やゆ 女が喜怒哀楽をおしみなくさらすことが多い。だからこそ、男は忍 耐を、女は激情をもっていると揶揄される。ハンナもまたフリジッ トで生まれ育った女だ。その内には激情をやどしている。凍りつい た表情がほころぶと、惜しむことなく感情があふれるのは当たり前 44 だった。 反対にアルクゥはフリジットで生まれ育った男ではないので、フ リジットにはめずらしい明朗快活な青年だった。忍耐をつかさどっ ているとは到底思えないほどに、表情が豊かなのだ。それはアルク ゥが余所者であることを知らしめている。 雪だるまを眺めてほめそやしていたハンナの背に高い声がかかっ た。 ﹁おねえちゃん、なにしてるの?﹂ ﹁︱︱あら?﹂ 振り向いたさきにいたのは、防寒用の毛皮でできた帽子を目深に かぶった少年だった。年のころは十を満たないように思える。鼻先 を赤くしてハンナを見あげる瞳は澄んだ空の色をしていた。色合い が落ちて暗く瞳を落とすフリジットにはめずらしい目の色だ。 少年の指は厚い手袋に覆われていたが、その手には小さな雪玉が のっていた。 ﹁この村の子?﹂ ﹁⋮⋮うん﹂ ﹁お名前は?﹂ 屈みこみ視線をあわせれば少年は喋るだけで凍りつきそうな小さ な唇を動かした。 ﹁⋮⋮フェル﹂ ﹁フェル。⋮⋮いい名ね﹂ 少年はハンナの言葉に喜ぶわけでもなく曖昧にうなずいてみせた だけだった。 ﹁かあさんがつけたんだ﹂ ﹁そう。お母さまはどちらに?﹂ きゅっと唇を引き結び、少年︱︱フェルはささやいた。 ﹁病気でねてるんだ。寒気にあてられたって、みんなが﹂ ﹁⋮⋮そう、なの﹂ 手足から体温を奪い取り、しめやかに冷気を運ぶフリジットの冬 45 で体調を崩すものは多い。防寒具に身をくるんでもまだ寒く、素肌 をさらせば心臓までもが凍りつきそうだった。実際に吸いこむ空気 は肺に冷え冷えとした感覚を与えてくる。か細く吐きだされた息は、 湯気のようにもうもうと立ちのぼっていった。 ﹁⋮⋮はやく、春がきたらいいのに﹂ フェルの言葉にハンナは思わず息をのんだ。 ﹁いまの王さまは冬の生まれ変わりだから期待できないって。みん なは言うけど、ぼくははやく春がきてほしい。だから、王さまに毎 日おいのりしてるんだ。︱︱はやく、春がきますようにって。そし たら、かあさんと一緒に春をむかえられるから﹂ ふにゃりと笑ってフェルは言った。汚れのない真っ直ぐな願いだ った。 ああ、とハンナは感嘆に似たうめきをもらした。ぎゅっと胸元を 握りしめると固い感触が伝わってくる。肌身離さず身につけている のは母の形見だ。それこそ、万年雪の比ではない。それを失うこと など考えられなかった。 似ているのだ。目の前にいる少年はハンナに似ている。 ﹁わたしも⋮⋮お母さまと春が見たかった﹂ ﹁おねえちゃんも?﹂ 春がくる前にこの世を去った母。厚く雪に閉ざされたフリジット で亡くなった。 幼いハンナは母と迎える春を心待ちにしていた。それは訪れるこ とのない幻になった。 ﹁かならず、春はくるわ﹂ ﹁ほんとう?﹂ ﹁ええ。王はきっと春を望んでる。フェルと同じように﹂ にこりと笑んでみせたハンナにフェルは嬉しそうにはにかんだ。 父も母も、フリジットの雪にたおれた。民の多くもまた厳しい冬 にたおれる。 ハンナ以外の誰が助けようというのだろう。玉座にいるのはハン 46 ナだ。民を守り慈しみ、そして春を迎え入れる。たとえ、期待など されていなくてもハンナは歩んだだろう。しかし、見上げてくる真 摯な瞳を、すがりつく小さな手を知ることができてよかった。それ だけで、城外にでた甲斐があるというもの。 ﹁⋮⋮フェル。風邪をひく。中へ﹂ ﹁あ。シグにい﹂ 低い声に呼ばれてフェルはくるりと回転した。 立っていたのは精悍な顔つきをした青年だった。フェルと同じよ うな防寒具に身をつつみ、猟師が使用するおおぶりの銃を背負って いた。帽子のつばからのぞく瞳は暗い色をしていて、怪訝そうに立 ちすくむハンナたちを映していた。 ﹁見ない顔だな﹂ ﹁はじめまして。王都から来たんです﹂ ﹁へえ。身分の高い方が何用で﹂ 不安げに両者を見つめるフェルの頭を叩いて家の中へうながすと、 青年は外套についた雪片をはたき落した。 王都に在住する多くは位が高いものか商いをしているものにあた る。市民がいないわけではないが、それでも地方に分散している民 よりも裕福な暮らしであることは確かだろう。そんなものがわざわ ざ地方の辺鄙な場所に足を運んでいることは奇妙にうつっても仕方 なかった。ハンナは不審に満ちた目を向けられながらも毅然として 言った。 ﹁わたし、学がないもので。地方をめぐって勉学しているんです﹂ ﹁ふうん﹂ ﹁実際に見てみないことには、実情は分かりませんもの﹂ ﹁⋮⋮へえ﹂ 青年は適当にあいづちをうつばかりでハンナの言に耳を貸してい る様子はみられない。むっとして口をとがらせたハンナの肩に手を のせいさめたのはアルクゥだった。めずらしく眉根をよせて首を左 右に揺らすので、ハンナは思わず口をつぐむ。閉じてしまえば冷気 47 がやってきて唇を凍りつかせた。 ﹁あんたは猟師? ここのうまいもの教えてくれよ﹂ ﹁⋮⋮よそものか?﹂ 頭まですっぽりと防寒具にくるまれているハンナとは違って、ア ルクゥは頭に何もつけてはいなかった。そのため灰色の髪と立派な 角がむきだしになっている。角に触られると底知れぬ違和感に襲わ れるらしい。寒気にただれることを案じて差し出したものはすべて はねつけられた。 青年はアルクゥの頭を睨みつけるようにしていたが、ふいと視線 をそらした。 ﹁⋮⋮雪鹿の肉を厚切りにしたステーキがうまい﹂ ﹁そっか。どこで食える?﹂ ﹁⋮⋮ついてこい﹂ ぶっきらぼうに返された言葉に怖気づくことなくアルクゥはハン ナの手を引いた。 48 3 無骨そうな男たちが狭い店内で円卓を囲み酒盛りをしている。客 の多くは猟を商いにしているのか毛皮を模した衣類を身につけてい た。扉を開けた瞬間に、寒気を忘れるほどの熱風と獣臭さが鼻をつ きハンナはしらず顔をしかめた。そんなハンナを尻目にシグナと名 乗った青年は人の波をかきわけて店主であろう男のもとに向かって いる。そのあとを追いかけるのはハンナではなく、身軽さを兼ねそ なえたアルクゥだった。 むすりと顔をゆがめたまま、ハンナはおもむろに帽子を脱ぎさっ た。押し込まれるようにしていた髪が解放されて散らばった。わず かに湿りを帯びた毛先が頬にあたる。途端に熱気が顔を温め、頬が 紅潮していく。 シグルが案内したのは村にあるこぢんまりとした酒場だった。店 内はお世辞にも広いとはいえず、客が押し合いながら席を囲んでい る。誰も気にしたそぶりをみせていないので、どうやらこの店では それが当たり前のようだった。 すっかり置いていかれたハンナは屈強な男たちの間を力まかせに くぐりぬける。 ﹁おっ! 嬢ちゃん、べっぴんだねぇ。酌してくれよ﹂ ﹁なっ!﹂ むんずと手首をつかまれて赤ら顔が近くにせまる。男が口を開く たびにアルコールの匂いが鼻をくすぐり頭がくらくらした。無遠慮 に掴まれた手首は男の腕力に悲鳴をあげ、顔をしかめながら、﹁お 断りよ!﹂と答えれば、げらげらと野卑な笑いに店内が包まれる。 解放された手首は少しばかり赤みをおび腫れている。 ﹁気の強い嬢ちゃんだ! 見かけない顔だな。旅人か?﹂ ﹁王都から来たんだと。飲み過ぎだぜ、おやじ﹂ いさめるように口を挟んだのはシグルだった。 49 幸いとばかりにハンナは男たちの席を離れ、いそいそとアルクゥ の隣に移動する。ハンナに逃げられ、行き場を失った手を男はしぶ しぶ下ろし、冷えた視線を向けてくる年若い青年に言った。 ﹁なんでい。シグルの客か。んー? 今日はチビの姿がみえないな あ﹂ ﹁フェルは母親の具合をみてるよ。昼間から酒飲んでだらしない﹂ ﹁いいんだよ! 俺たちが無闇に狩れば、雪鹿がいなくなる﹂ ちがいねえ、とあちこちの席から声があがり大笑いが響く。 ﹁収穫の五割は領主に持っていかれる。かといって乱獲すれば、雪 鹿はいなくなる。これが飲まずにいられるか!﹂ 木をくりぬいてつくられたジョッキを円卓にたたきつけ、男は声 を荒げた。それに呼応するように騒ぎ出す男たちを尻目にシグルは 気難しげに眉をよせる。薄い唇からは呆れの息がもれた。 うろん ﹁ただでさえ、少ない取り分を減らしてどうするんだ﹂ 男の手からジョッキを取り上げると胡乱な目つきで見られる。ハ ンナは据わった目に怖気づいておもわずアルクゥの後ろに隠れたが、 真っ向から受けているシグルは飄々としていた。 ﹁おい、シグル。飲まずにやっていけねえやつから、楽しみを奪う のか﹂ ﹁やけ酒は楽しみというわけでもないだろう。奥さんにどやされる﹂ ﹁構うものか! 五割だ! 五割! あいつもすっかり痩せちまっ た!﹂ 憤怒の顔で立ちあがった男がシグルの胸元をひねりあげた瞬間、 ハンナは声をあげた。 ﹁待って! 五割も取られているの? 税として?﹂ 蒼白な顔で問いかけたハンナに、顔を赤らめた男はゆらりと視線 をずらした。 ﹁ああ。そうだ。ただでさえ、収穫も少ない中、領主は五割を持っ ていく。税を払えなかったものは、ひさびさの収穫のおり根こそぎ 徴収された。おかげで半数は、病に伏せて死んじまったよ﹂ 50 ﹁そんな︱︱﹂ 地方には王政から権限を与えられた領主が存在する。彼らが民か ら税を徴収し、王都へと搬送するのだ。税は多くて二割。物品また は金銭が半々ずつ徴収されていく。その税のうち五分が領主の取り 分になるので、人口が多い地方の領主は裕福な部類に入った。一割 五分は王都にわたり、各地方の収穫の割合に応じ物品は他に回され る。金銭はそのまま徴収し、道路の整備などの政に使われるのがほ とんどだった。 五割も徴収すれば、領主の取り分は三割五分。破格な収入になる。 ﹁領主の名は? どこの家が担当しているの?﹂ ﹁あー、なんだったかな﹂ 髪を乱雑にかきあげて首を傾げる男につめより、ハンナは急かし た。 ﹁重要なことなの!﹂ ﹁お、おお。⋮⋮えっと、オルコットだったかな﹂ ﹁⋮⋮オルコット﹂ 呆然と呟いたハンナは力なく、男から距離をとってたちすくんだ。 聞き覚えのありすぎる名だった。 オルコットはハンナの重臣にあたる男の家名だ。そういえば、オ ルコットは親類に優秀なものがいるから地方のひとつを任せてくれ と直訴してきたことがある。まだ、政に慣れ親しんでいなかったの で思わず了承してしまったが、このようなことになっていたなんて。 唇を噛みしめてうつむくハンナに周囲にいた男たちから心配の声 があがっていく。 ﹁難しい話は後回しにしようぜ! ほら、食おう!﹂ 軽い口調で場を和ませたのは、店主から受け取った厚いステーキ がのった皿をかかげたアルクゥだった。当たり前のようにハンナの 手を引き、空いた席に座らせると、湯気のたったステーキを目前に 置いた。じゅわという肉汁の音と香ばしい匂いが鼻をつき、無意識 のうちに唾を飲みこんだ。分厚く切り取られた肉は綺麗な赤身をの 51 ぞかせている。 食べようと左右を見渡したハンナは、三つ又のフォークがだされ ていることに気づく。しかし、肝心のナイフが見当たらず戸惑って しまった。隣のアルクゥを盗みみれば、フォークを刺してかぶりつ くようにして食べている。同じ席についたシグルも慣れた手つきで 食べ始めてしまった。所作のよろしくないアルクゥを誰も責めない。 それどころか、ほぼ全員がアルクゥと同じような食べ方をしている。 ﹁食べないのか?﹂ フォークを持ったまま固まっているハンナに怪訝な顔をしてシグ ルが問うた。 ﹁食べるけど⋮⋮ナイフがないわ﹂ ﹁ナイフ? ああ。王都の人間は上品な食べ方をするんだな﹂ どこか厭味ったらしくシグルが言うので、ハンナはちろりと顔を うかがった。 ﹁店主に聞いてくるよ﹂ ﹁いいわ。これが、ここでの食べ方なんでしょう?﹂ 席から立ちあがろうとしたシグルを制して、ハンナはフォークを 握りこんだ。普段使うような持ち方ではなく、赤子のように柄をつ かむ。それから、無造作にステーキへ刺しこむと、勢いをつけてか ぶりついた。肉厚のステーキからにじみでた旨味が、じんわりと広 がっていく。 口周りがべたべたになったことを気づきながらも、ハンナはさら にひと口かぶりつく。 そうして、唖然とした顔で立ちつくしているシグルに、挑発的に 笑ってみせた。 ﹁ああ、ほんとうね。こうして食べたほうがおいしい﹂ ぺろりと唇を舐めてみせれば、シグルは呆れたとばかりに肩を落 とした。 ﹁なるほど、たしかにフリジットの女だな﹂ 52 4 たっかん 話してみれば、シグルは普通の青年だった。 少しばかり物事を達観している様子ではあったが、知り合いにか らかわれるさまを見るかぎり、別段気にするものでもない。コロコ ロと表情が移りかわるアルクゥとは違い、シグルは石でもつけてい るかのようにまったく変わらない。むっつりと押し黙り、尋ねるま では口を開かない。そういったところがフリジットの男であること を思わせて、ハンナは笑った。 ﹁そう、そんなにも雪崩が?﹂ ﹁ああ。この時期はとくに警戒しないとならない﹂ ﹁雪崩って、そんなに危ないのか?﹂ ﹁ええ。わずかな衝撃でも起こることがあるし、道も寸断されてし まうわ﹂ 実際、この村は雪崩のせいで道が切り崩され、整備するはめにな った。 困ったように眉尻を下げたハンナをシグルは鼻先で笑った。 ﹁道ならまだいい。家が巻き込まれれば、何十人と死ぬ﹂ ﹁あ⋮⋮﹂ ﹁前に雪崩が起きたときは、死者もでた﹂ どこか淡々と話すシグルにハンナは胸騒ぎを覚えた。しらず胸元 を握りこむ。 そうすると、目ざとくアルクゥが気づいて声をかけてきた。 ﹁どうかしたか?﹂ ﹁いえ、大丈夫﹂ 息をこぼすようにして答えたハンナはおもむろに胸元から首飾り を引っこ抜いた。黒い紐のさきには手のひらにおさまるほどの鍵が ぶらさがっている。古いものなのか、一部は錆びつき鈍い色合いを していた。それは、ハンナの母であるシーナの形見だ。 53 ﹁鍵?﹂ ﹁母の形見なの。これだけは肌身離さず持ってる﹂ 贈り物である万年雪とは意味合いがちがう。ハンナは店内にぶら さがっているランプにかざすように鍵を持ち上げた。その鍵を見つ めながら、アルクゥは首をかしげた。 ﹁なんの鍵なんだ?﹂ ﹁︱︱⋮⋮さあ﹂ ﹁さあって。鍵はなんかを開けるものだろ﹂ 納得できないとばかりに睨みすえられ、ハンナは首をかしげた。 鍵は何かを開けるもの。確かにそうだ。 固く閉ざされた扉。金銀財宝が眠る宝箱。自分のちょっとした秘 密を隠した箱。 閉ざされたさきを開ける鍵。鍵穴を回す瞬間は、きっと形容しが たい感情に包まれる。 ︱︱さきに眠るのは、希望か絶望か。 それなのに、とハンナは鍵を隠すように握りしめた。冷たく固い 感触がする。 いったい、いつハンナの手に渡ったのか。母が何を開けるために 持っていたのか。思いあたる節が何ひとつなく、ハンナは頭を抱え そうだった。鈍く光る鍵は、その見かけに反してずっしりと重く、 凍えるほどに冷たい。 鍵を見つめたまま動かなくなったハンナに、アルクゥは明るく言 った。 ﹁まあ、帰ってから聞こうぜ! 爺さんなら何か知ってるだろ﹂ ﹁⋮⋮ええ。そうね﹂ 明るい調子になぐさめられ、木製のカップに入ったスープを口に する。熱くやさしい味わいのするそれは、ハンナの体をさっと通っ て温めた。 54 スープを飲み終えてしまえば、客によってごったがえす店内に長 くとどまろうとは思わない。いまだに酒をかたむけて談笑している 男たちもいるが、あいにくハンナたちは酒を飲もうとは思わない。 急かされるように立ちあがったハンナを見て、シグルが片眉をあげ た。 ﹁帰るのか?﹂ ﹁ええ。そろそろでないと王都の閉門に間に合わないわ﹂ 王都にある堅牢な扉は夕方には閉じてしまう。春先ならまだしも、 寒さの厳しいこの時期は、旅人も少なく閉門がはやい。そのため、 物資の流入は朝方や昼間にすまされているのがほとんどだ。フリジ ットの最西端といっても過言でもないこの村からでは、歩いて帰る には距離があり、物資を運ぶ荷馬車を捕まえられるとは思えなかっ た。 ﹁ふうん。気をつけてな﹂ やはり、シグルはどこかそっけなくそれだけを言うと、ハンナた ちの手前、遠慮していたのだろう。店主に向かって手をあげ、酒を 注文していた。隣でアルクゥが﹁ずりぃ﹂とぼやくのを小突いてか ら、ハンナはひとつ笑み、店を後にした。 熱気の満ちた店内からでてしまえば、また凍えるような寒さに襲 われる。 火照った体から一瞬で熱を奪い去った風は、気ままに吹いて過ぎ 去った。肩をあげて身を縮ませて寒気をやり過ごし、店内で外して しまっていた帽子を被りなおした。冷気にあてられた耳がじんじん と痛むので、布地の上からこすりあげる。 ﹁さみい﹂ ぽつりと落とされた言葉に、ハンナは鼻白んだ。 ﹁ばかね。だから被りなさいって言ったのに﹂ ﹁やだね。あの不快感を知らないから、そんなこと言えるんだよ﹂ ﹁体調を崩してもしらないわ﹂ 55 ﹁平気だって。角つきは普通の人間よりも丈夫なんだ﹂ ﹁そんな意味じゃ︱︱﹂ ない、と言いかけてハンナは口ごもった。 ︵これじゃあ、まるで心配しているみたいだわ︶ 確実に隔たりのある臣下たちと比べて、アルクゥはハンナに近い といえる。 それでも、ハンナを支え続けているガイルには劣るし、知らない ことも多かった。なにより、彼はよそものであり、フリジットとは 正反対の土地柄で育ってきた。そのうえ、彼の心にはいまだに、ひ とりの女性が輝きつづけているわけで、ハンナが寄り添える場所な どない。 ぐっと唇を噛みしめたハンナに、アルクゥが声をかけようとした 時だった。 ﹁おねえちゃん!﹂ そこにいたのは、水の入った桶を抱えたフェルだった。 鼻先を赤くして肩で息をしながら駆けてくる。目線は水の入った 桶に注がれたままだったし、駆けだしたはずの足も、桶から水が跳 ねるたびにだんだん弱くゆっくりになっていく。ハンナたちの前に くるころには、衣類に跳ねた水分が凍りついていた。 ﹁帰るの?﹂ ﹁ええ。門が閉まってしまうから﹂ ﹁ふうん。またくる?﹂ ﹁そうね。雪鹿のステーキも美味しかったし。⋮⋮フェルのお母さ んも心配だもの﹂ ハンナがそう答えると、フェルは目を細めて笑った。 ﹁約束だよ!﹂ ﹁ええ。約束﹂ 手を振ってみせると、フェルは急いで家へと向かっていく。積雪 に足をとられることなく歩く姿は、雪国で生まれ育ったゆえの慣れ だろう。桶を持つ手はぎこちなくても、前に運ぶ足に迷いはない。 56 転ばないように見守っていたハンナが帰路へと体を転換した時、﹁ あ﹂と声がした。 転んだのかと振り向いたさきには、フェルがぽつんと立っている。 ﹁なだれには気をつけてね!﹂ ﹁大丈夫よ、フェル。あそこは地盤が固いもの﹂ 地盤がしっかりしていて樹木が根をはっている。草木が生い茂っ ているということは、雪崩が起きにくい場所という証明にもなる。 積もっている雪にむやみに衝撃を与えなければ、滅多なことなど起 きはしない。 ハンナが安心させるように笑ってみせても、フェルの顔は曇った ままだ。 ﹁でも、前にあそこでなだれが起きたんだって。偉いひとが亡くな ったんだよ﹂ ﹁⋮⋮え﹂ ﹁だから、おねえちゃんも気をつけてね﹂ ﹁え、ええ。⋮⋮気をつけるわ﹂ 手を振って見送ってくれたフェルに背を向けてハンナは帰路をア ルクゥと歩いていく。 さきほど、フェルに告げられたことが頭をめぐって、ハンナを揺 らし続けていた。整備されているはずの道が曲がりくねって映り、 思わず目元を覆って足を止める。足音がやんだことから、アルクゥ も立ち止まったことがわかった。 深く息を吐いて落ち着いたころに視界を覆っていた手をおろすと、 アルクゥの姿が現れる。 ﹁平気か?﹂ ﹁⋮⋮ええ。時間がないの。はやく行きましょう﹂ 門が閉まってしまえば、野宿するほかない。あいにく、フリジッ トは野宿して無事でいられる気候でもなかった。夜をこえて朝にな ってしまえば、凍りついた自分の遺体が発見されてしまうだろう。 57 ぶるりと体を震わせてさきを行こう、と足を動かせばまた視界が揺 れ動く。 ﹁うっ︱︱﹂ 思わずその場にうずくまってしまえば、頭上から呆れをふくむ息 が落とされた。 ﹁平気じゃないだろ、それ﹂ ﹁⋮⋮はあ。いいわ。置いていきなさい。わたし、さっきの村に泊 まるから﹂ アルクゥだけなら、まだ間に合うだろう。そう思って、手を振っ てうながすと、逆に手首を掴まれて持ち上げられた。ぐんと景色が 動いたせいで眩む視界の中に、眉根をよせたアルクゥが映りこむ。 不格好につりあげられたまま、唇をとがらせた。 ﹁なにするのよ﹂ ﹁そんな顔色でよくいうよ。ほら︱︱﹂ ハンナを立たせて、自分はしゃがみこむと背中を向けてくる。 ﹁まさか、おぶされってこと?﹂ ﹁そのまさかだよ! ほら、はやくしろって﹂ ﹁いいわ。みっともない﹂ ﹁いいから、はやく!﹂ 手を払って拒否しようにも、強い語調でいさめられれば折れるほ かない。 ハンナは逡巡していたが、やがてアルクゥの細い肩に手をかけた。 ためら そのまま、重心をずらして体を預ける。しっかり首に腕を回せば、 アルクゥは慣れたようにハンナの足を抱え込んだ。躊躇いなく担ぎ あげられ体が硬直したが、すぐに力を抜く。そうすれば、一定のリ ズムを刻みながらアルクゥが歩きだした。 うっすらと目を開けば、灰色の髪が近い。 ﹁具合悪いなら、はやく言えよな﹂ ﹁べつに、悪かったわけじゃないわ。いきなりなったのよ﹂ ﹁ふうん﹂ 58 背負われれば視界がぶれることもなく、フェルが危惧した場所を 抜けると、すっと胸のつかえもなくなった。それでも、もったいな いと感じてハンナは体調の回復を口に出せずにいる。ぎゅっと腕に 力を入れれば、体調が悪化したのかとアルクゥが逐一、声をかけて くれた。 ﹁はやく治せよ。あの鍵のこと聞くんだろ﹂ ﹁大丈夫。きっとよくなるわ﹂ ハンナはアルクゥの首筋に顔を埋めるようにしてささやいた。 ︱︱だって、あなたの背中、とても温かいもの。 59 5 体調は不思議なくらいすぐによくなり、ハンナはいつものように 朝議に参加していた。 会議にはガイルはもちろん、アルクゥもいない。ハンナひとりで 戦わなければならず、また味方はいないといって差し支えなかった。 ハンナが座っている場所は一段高い場所にあり、小さめの机がひ とつ目前に置かれている。そこに今回の議題にのぼる資料が整然と 並べられていた。脇には丸いテーブルが設えられ、果物や飲み物が 用意されている。そのハンナの場所から一段下がると、正方形の長 いテーブルを囲んで臣下が座っている。ハンナに近い方から重臣、 奥へ向かうたびに位が低くなる。地位が高いものほどハンナに意見 が届きやすく、地位が低いほど意見の声は届きにくい。 その一段の差がハンナは嫌いだった。それこそ、ハンナと臣下の 間にある溝を具現化しているといっても相違ない。 ハンナは柔らかい椅子に腰かけ、大仰な態度で口を開いた。 ﹁それで、クライス。調査の結果は?﹂ ﹁はい。確かに、あの村で徴収していた税は過当なものでした﹂ しれっと悪びれもなく言った男は四十過ぎの長身痩躯だった。細 身の体にすらりとしたスーツを着込み、神経質そうな顔をした男の 名をクライス・オルコットといった。フリジットに存在する貴族の 中でも上流に位置し、さきの王であるベルモンドの片腕として才能 を発揮した人でもある。ハンナ自身、彼の優秀さを評価して一任し ていたものは多い。 ﹁では、過分は領主のふところに?﹂ ﹁はい。我がオルコットの精鋭を向かわせ、差し押さえたところで す﹂ ﹁そう。あなたにしては、めずらしいことね﹂ くすりと笑ってみせると、クライスではなく周囲にいた臣下がざ 60 わめいた。 ハンナはそれらを気にすることなく続ける。 ﹁それとも、わざとなのかしら﹂ 空気が凍った。それこそ、暖炉がたてる薪の跳ねる音すら消え失 せるほどだ。 クライスは親戚に優秀なものがいる。そういって領主の座をもぎ とっていった。そうなると、あの村を統治していたのはクライスの 身内ということになる。クライスがオルコットの当主である以上、 知らなかったという可能性は低い。もちろん、気づいたからこそ甘 い蜜を受け取って見逃していた節もある。 ハンナはクライスから目をそらさずに言葉を待った。 ﹁ハンナ様にそこまでの疑心を抱かせたことは深く謝罪します。し かし、情けないことに私は存知あげておりませんでした。こうして、 即座に対処してみせたことで、ハンナ様の信頼回復と、忠誠の証と していただきたい﹂ 表情ひとつ変えることなく言い切ったクライスを、追い詰めるほ どの技量をハンナはもっていない。癒着していた証拠などなく、実 際、クライスは不正が発覚してすぐに調査に乗り出し、身内であり ながら首謀者を引き出してきた。その上、罰則はすべて一任すると 言ってきたほどだ。それを無下にして疑心を向けるほど、ハンナは 世間知らずではない。 ﹁そう、分かったわ。以後、気をつけて﹂ ﹁⋮⋮はい﹂ 席を立ち、クライスは一礼してみせた。相も変わらず、表情は動 かない。 ﹁ところで、ハンナ様はなぜあの村に﹂ ﹁あら、新しく道ができた場所を視察しにいってはいけないの?﹂ 飲み物を口に運びながら答えると、クライスは否定してみせた。 ﹁そうですか。私はてっきり、御母上の墓参りに行ったのかと︱︱﹂ 61 ︱︱がしゃん。 ﹁ハンナ様! お怪我はございませんか!﹂ ﹁⋮⋮ええ、平気。ありがとう﹂ グラスを落として割ってしまうと、隣で待機していた侍女が即座 に反応する。ハンナの身体を確認すると、飛び散ったガラス片を回 収しはじめる。そんな彼女を気にする余裕もなく、ハンナは震える 声で笑い飛ばした。視界にちかちかと光るものがある。 ﹁いやだわ。お母さまのお墓はここにあるじゃない﹂ ﹁ハンナ様。覚えていらっしゃらないのですか? あそこは︱︱﹂ ︱︱シーナ様がお亡くなりになられた場所でしょう? ◇ ずっと不思議に思っていた。 父が亡くなったときのことは鮮明に覚えているのに、どうして母 が亡くなったときのことは覚えていないのだろう、と。幼かったか ら、というのもあったのだろう。実際、ガイルは母の死を思い出せ ないハンナにそう言った。 けれど、ハンナにはただひとつ。焼けつくように残された記憶も あった。 幼いハンナがうずくまり、泣きじゃくっていた。小さな唇が震え て弾けた。 ︱︱悪魔のような白い影が襲ってくる。 ﹁そうだったのね﹂ 62 ぽつりと落とされた言葉は闇夜に消える。門はとっくに閉まって しまった。引き返したところで王都には入れないだろう。それでも、 ハンナは悲観的ではなかった。凍死してしまうかもしれないという 危惧はあったが、それよりも胸を焼く痛みのほうがつらかった。 胸元から取りだしたのは古い鍵。忘れられない母の形見。 ﹁わたしは、なんて愚かなことを︱︱﹂ 熱くこぼれた息は湯気のようにのぼる。夜に浮かぶ雲のようだっ た。 目前に広がる湖は夜中ということもあって、暗く陰影を落とすだ けだ。持ってきたランプも心もとない明かりを発するだけで、ハン ナの周りは静寂に包まれていた。だからこそ、自分が発した言葉は、 誰でもないハンナ自身に返ってくる。その刃の鋭さを理解していて なお、刺す手をとめられなかった。 苦しい、とこぼれた涙をすくいあげる影もない。 ハンナの前に広がるのは、ひたすら黒。慣れ親しんだ色はどこに もない。 それでも、ハンナの視界は白く隔たれていた。ぽつりぽつりと白 いものが浮かんでは消えていく。追いかけて歩きだした足は氷の上 を進んでいく。分厚く形成されたそれらがハンナの体重で踏み抜か れることはない。それでも、加重によりわずかに軋んだ音をたてた。 迷いなく歩むハンナの耳には聞こえない。視界に踊る白を追いかけ て、一歩︱︱。 ぎし︱︱。 嫌な音がしたのは一瞬だったように思う。 分厚くつくられた氷は中央に向かうたびに薄くなっていたようで、 ハンナの足はそこを踏み抜いてしまったようだった。亀裂が入って しまえば穴がうまれるまでの時間は早く、気づいたときには防寒具 は濡れて、衣服の中にまで冷たい水が浸入していた。伸ばした手の 63 感覚はなくなり、這い出ようと伸ばした爪先は、氷の表面を削り取 っただけだった。 ︵⋮⋮お母さま︶ 祈るように胸中で呟いて、ハンナは湖に体が沈まないように力を こめる。 それでも、フリジットの寒気は甘くない。肌を凍てつかせた水は ゆっくりと内部まで浸みこみ、ハンナの意識を奪い取っていく。吐 きだした息の行方すら分からず、ハンナの手は氷の縁から離れて泳 いだ。 ﹁ハンナ︱︱!﹂ 血相を変えて走ってくる灰色は見間違えるはずもない。アルクゥ だ。 ﹁どうして︱︱﹂ 門は閉まったはずなのに、と動かした唇は固まったまま。 ハンナはドラゴンの姿に転変したアルクゥにさらわれるようにし て救出された。水分を含んだ体に夜風はつらかったが、不思議なこ とにアルクゥの鱗で守られた胸元は温かった。胸元にかき抱かれる ようにして運ばれるハンナは安堵の息をもらす。 門は閉まっても、空を飛べるアルクゥには関係のないことだ。空 に扉はない。 ﹁⋮⋮アルクゥ﹂ 唇は紫を通り越して、青く震えている。 ﹁たすけて︱︱﹂ すがるように鱗を握りしめ、ハンナは意識を飛ばした。 ︱︱ああ。あの日も、白い雪が降っていた。 64 第三話 雪華の追憶 フリジットの王宮は広い。 その片隅でワンピースドレスにボレロを羽織ったハンナはうずく まっていた。口元には手をあてて声をひそませてはいるが、楽しそ うにくすくす音をたてる唇は、やがて来訪者を運んできた。廊下の 角を注視しているハンナが背後から近づく人影に気づくわけもなく、 肩を叩かれてはじめて、その存在に気づいた。 ﹁見つけた。ハンナ﹂ ﹁おかあさま!﹂ 穏やかに笑ってみせたのは、フリジット国王ベルモンドの愛妻で あるシーナだ。柔和な顔つきと雪を透かしたような肌が彼女を儚く させている。フリジットの女は激情を持っている。その﹁激情﹂も こそぎ落としたように、シーナはゆるく物腰低い女性だった。 シーナに抱きついて、陽だまりのように笑うハンナは、﹁じゃあ、 交代!﹂と叫んだ。遊びたい盛りのわが子を困ったように見つめて、 シーナはハンナと目線をあわせた。無邪気に笑っていたハンナはそ れだけで首をかしげて不思議そうに見やる。 ﹁ねえ、ハンナ。お母さまは、もうすぐ検診にいかないとダメなの。 許してね﹂ ﹁⋮⋮うん﹂ 返事をすると、﹁いい子﹂と頭を撫でられる。侍女に呼ばれ立ち 去った背中を見つめてハンナはつまらなそうに頬を膨らませた。父 であるベルモンドは朝議と政務に忙しく、臣下たちは気をつかうば かりで遊び相手にもならない。年の近い子どもたちは、誰もがいい とこのお嬢様たちで、お茶を囲みながら刺繍をしても、ハンナのよ うに走り回る遊びはしなかった。男の子たちに混じって遊べば、世 話係が血相を変えてやってくる。気兼ねなく遊んでくれるのは、母 であるシーナだけだ。 65 ﹁つまんない﹂ ぶすくれて呟いたハンナは、そのままふらふらと城内を歩きだし た。 シーナは体が弱く、冬の盛りになるとよく検診を受ける。その体 質をハンナが受け継がなくてよかったと誰もが言ったが、ハンナに は関係なかった。シーナが床に臥してしまえば、遊び相手もいなく なる。ただ広いだけの王宮は、ハンナにとっては大きな檻だった。 ﹁おかあさまは優しすぎるのね! だから病気もでていかないのよ !﹂ 磨き上げられた靴を床に叩きつけるようにして向かうさきはシー ナの部屋だった。 検診で出払ってしまうときには、ハンナは内緒でシーナの部屋に 忍び込んだ。いい香りのする部屋は、シーナの体調を気遣ったもの がたくさんある。そこにはベルモンドが妻であるシーナに贈ったも のも多く、ハンナはひとりの時、それらを眺めるのが好きだった。 シーナの部屋は物で溢れている。どれもが几帳面に並べられ、綺 麗に保管されていた。 ハンナの部屋はどちらかといえば閑散としていた。勉学の際につ かう書物。シーナから貰ったわずかばかりの贈りもの。それらがひ とつの棚に押し込められているだけで、あとは机と天蓋つきのベッ ドしかない。ハンナは、父に贈りものを貰ったことはない。愛され ているとは感じる。政務の合間に顔を見せれば手招いて、膝の上に 乗せてもらえる。邪見に扱われたことも、手ひどい目にあったこと もない。 しかし、ベルモンドにとって最愛はいつまでもシーナなのだ。ハ ンナではない。 ﹁あら、ハンナ。ここにいたの?﹂ ﹁あ! おかえりなさい! おかあさま!﹂ 検診を終えれば部屋に戻ってくることを知っている。ハンナは喜 んで手を引いた。 66 ベッドに腰掛けたシーナはすがりつくわが子に笑んで遊んでくれ る。部屋でする遊びは些細なものだ。絵本を読み、刺繍をし、とき には難しい書物とにらめっこして。それでも、シーナが具合を悪く すれば、ハンナは退室するほかなく、またひとりぼっちになってし まう。 窓の外では雪が降っている。ハンナにとって、見慣れた景色だ。 ﹁外にでたいなあ﹂ 外出は許されているが同伴が義務づけられる。 付き添ったもののほとんどが、ハンナを丁重に扱い、危険なこと など一切させない。あっちもだめ。こっちもだめと制限されてしま えば、何をしに外に出たのかもわからない。内緒ででてしまう手も あったが、そうすると一週間は部屋に閉じ込められて勉学をさせら れる。そのようなことになれば、シーナと遊ぶ時間も減ってしまう のだ。 ﹁⋮⋮はやく、よくなればいいのに﹂ 小さく呟かれた言葉はいっそ、清々しいほどに純真だった。 67 2 シーナの体調が悪化したのは、それから間もなくのことだった。 ベルモンドが﹁雪解け﹂と称され、民の誰もが希望を持って春を 待っていた。それは、娘であるハンナも同じでシーナの枕もとでし きりに春がきたらしたいことを提案していた。ハンナの夢のような お願い事を、シーナは少しばかりやつれた顔で丁寧に聞いていく。 ﹁花がさいたら、かんむりつくるの! それでおとうさまにあげる !﹂ ﹁いいわね。きっと喜んでくれるわ﹂ ﹁⋮⋮くれるかなあ﹂ しょんぼりと肩を落としたハンナに、シーナはうすく笑った。 ﹁ええ、もちろん。ベルモンドさまはあなたを愛しているわ﹂ ﹁でも⋮⋮﹂ ﹁ふふ。愛情表現が苦手な方なの。許してあげてね﹂ ﹁⋮⋮うん﹂ 内緒話をするように声をひそめてふたりは笑いあった。 幸せな日々が続くと信じて疑わなかった。繋いだ温もりが消える ことなど考えなかった。 ﹁ねえ! おとうさま!﹂ シーナが病に臥せるようになってから、ハンナは遊び相手を求め ていた。寝台で騒がしくすると体に障ると部屋を追い出されてしま えば、無理をおして室内に入ろうとも思わない。だからこそ、ハン ナは滅多におとずれないベルモンドの執務室に顔をだしていた。 呼びかけられたベルモンドは書きものをしていた手をとめてハン ナを見る。 いつもと同じワンピースドレスにボレロをまとったハンナは手を 68 後ろに隠して笑っていた。 その日、ベルモンドは早朝から危急の要件で呼び立てられ執務に 追われていた。可愛いわが子のことを軽んじたわけでもなければ、 邪見に扱ったわけでもなかった。それでも、嬉しげに差し出された いびつな花冠に、眉根をよせてしまったことは事実だった。 ﹁これ、あげる﹂ ﹁⋮⋮ハンナ。すまないが、そんなものは後で渡しておくれ﹂ ﹁⋮⋮え﹂ ﹁お父さまは忙しいんだ。分かってくれるね?﹂ いい子だから、とベルモンドは言った。 ︵わたし、いい子にしてるのに︶ ぷちん、と体のどこかの糸がふつ切れる音がして、ハンナは花冠 を落としてしまう。 ﹁︱︱ハンナ?﹂ ほら、やっぱりとハンナは唇を噛みしめた。喜んでなどくれなか った。 あかぎれた自分の手を見つめてから、ふいとハンナは踵を返した。 呼びかけるベルモンドの声すら耳に入らないとばかりに扉を抜ける と、駆け出して行ってしまう。 ハンナが立ち去ってひとり残されたベルモンドは、ぽつんと捨て 置かれた花冠を拾いあげた。触れれば湿り気をおび、造花ではなく 生花でつくられていることがわかる。花びらの影から一片の雪が落 ち、ベルモンドの指先を濡らした。 ﹁︱︱ゆき?﹂ そうして窓の外をみやると、白い雪片が舞い散っているのがうか がえた。 ﹁そうか。まだ、冬だったな﹂ ひとりごちて、はたと動きをとめる。 69 雪は草花を覆い隠す。フリジットの雪は重く厚い。その下で群生 している花を見つけだすのは途方もないことに思えた。何気ない一 言でわが子を傷つけたことに気づき、ベルモンドは頭をかいた。や れやれと花冠を机に置き、書類に向き直る。 走り去ってしまったわが子はおそらくシーナのもとに行ったのだ ろう。 執務に忙しくかまってやれない自分とは違い、あれは弱い体をお してまで子にかまう。結果、風邪をこじらせてしまうのだから笑え ない。病床に臥せっているシーナには医師がついているし、へそを 曲げてしまったハンナの宥めかたはシーナが心得ている。 いまは、自分に課せられた執務を終えなければ、とベルモンドは 机に向き直った。 ︱︱もうすぐ、春がくる。 そうすれば、ぶすくれたわが子も遊び場をえられるし、寒気にあ てられ安定しないシーナの体調もよくなる。長い苦しみから解放さ れるときが迫っている。気合をいれて書類を睨みつけたベルモンド はしばらくして、わが子を追わなかったことを後悔することになる。 ︱︱そして、冬は悲劇でもって終わりをむかえる。 70 3 シーナの部屋を押し開けたハンナは肺にたまった空気を押し出す ようにして怒鳴った。 ﹁おかあさまのうそつきっ!﹂ くるりと背中を向けて走りだせば、シーナの焦った声とそれを押 しとどめる医師の声が届く。 ﹁ハンナ! まって!﹂ 呼び止められる声も振り切ってハンナは全力で城内を駆けた。 雪の中に手を差しいれて刺すような痛みを我慢してつくった花冠 は無下にされた。喜んでくれると言ったから、春まで待ちきれずに 花を探しに行った。どこにいっても白く閉ざされた中で、見つけた ときは嬉しくてたまらなかった。それなのに、と。 ︵うそつき︶ ベルモンドの顔を思い出すたびに胸が苦しむ。迷惑そうだった。 もし、あれがシーナだったなら、対応はまた違ったのかもしれな い。花を見れば元気になってくれると信じていた。気難しい顔もや わらぐだろうと考えた。不器用な手先で、懸命に編み込んだ。気持 ちを閉じ込めた贈りものは、一蹴されてしまったのだ。 ﹁ふっ、うっ⋮⋮ぐす﹂ 城外まででてしまうと走っていた足はとぽとぽと覇気をなくして 落ち着いた。 目元を拭いながらうつむき歩くハンナには、自分がどこに向かっ ているのかすら分からなかった。やがて王都の門を抜け、山をのぼ るころにはすっかり涙は乾いて頬に凍りついた。顔をあげたさきに は見慣れぬ風景。切り立った山がハンナを囲むように存在している。 ボレロだけ羽織った姿では肌寒い。泣いて火照った体も寒気に気 づいて縮まった。 感情のまま飛び出してきてしまい、右も左もわからなくなったハ 71 ンナはうずくまった。寒風にあたらないように、なるべく面積を小 さくしようという考えでもある。そうして、うずくまってしまった ハンナに、やさしい声は届いてきた。 ﹁ハンナ。見つけた﹂ 顔をあげたさきには、肩で息をしたシーナがたたずんでいる。 いつもならば走りよっていくハンナはしかし、ふいとそっぽを向 いた。そんなハンナを気にした風もなくシーナは歩み寄ってくると 厚手の防寒具を手渡してくる。それを乱暴に受け取って着込むと、 逃げるように距離を取った。 ﹁帰りましょう。みんな心配してるわ﹂ ﹁心配してるのは、おかあさまのことでしょ﹂ 唇をとがらせて言えば、﹁ハンナ﹂とたしなめられる。 ﹁だって、花かんむりあげたのに⋮⋮﹂ 喜んでなどくれなかった。 ﹁あのね、ハンナ。ベルモンドさまは忙しかっただけなのよ? 帰 って会いに行きましょう。 きっとやさしく抱きしめてくれるわ﹂ ﹁⋮⋮ほんとう?﹂ ﹁ええ﹂ 近寄ってくるシーナを逃げることもせずに待っていたハンナだっ たが、シーナの体から何かが滑り落ちたのを見て固まった。それは 小さな鍵だった。シーナが首から下げて大事にしていることは知っ ていたし、おそらくベルモンドからの贈りものなのだろうとも考え ていた。落ちたそれにはひとつの感情もわかなかったのに、シーナ が慌てて拾い上げようとした瞬間、溶岩に似た熱く煮えたぎる怒り がわきあがった。 その行動が、ハンナにはシーナが自分よりもベルモンドを優先さ せたように映ったからだ。 ﹁やっぱり。おかあさまも︱︱﹂ 鍵を拾い上げてしまっている姿は、普段と何も変わらない。 それなのに、ハンナの心には嵐が吹き荒れ、残酷に映りこんだ。 72 ﹁⋮⋮うそつき﹂ 喜んでくれると言った。愛してくれると言った。すべてがうそだ った。 けっして大きくない心が悲鳴をあげて壊れていく。どうしてと疑 念がのぞきこむ。深く暗い瞳に見つめられればハンナは閉ざして逃 げることしかできなかった。底知れぬ深い穴に落ちてしまわぬよう に足を動かした。ゆっくりと、確実に。 そして、ハンナはシーナから逃げ出した。 ﹁︱︱ハンナ! まって!﹂ 雪の降り積もった山脈。地盤が固く、木々が生い茂っていた。 雪崩など起きる様子も見せなかったその山が、ハンナの怒りに呼 応するように揺れ動いた。わずかばかりの衝撃で支えを失った雪は、 静かに、しかし急激に、ふたつの影になだれこんでいく。そのこと に、気づいたのはシーナのほうだった。 もともと弱い体を無理に動かし、寒気に身をさらした。その上、 風邪までこじらせた。満足に動くこともできない足を叱咤して、目 の前で跳ねていく小さな体を追った。必死に手をさしのばして、そ の背を突き飛ばしたときには、視界は白く侵された。 背中に衝撃を受けてすっころんだハンナは、背後で地鳴りがした のを聞いた。 ︱︱山が怒っている。 そんな風にハンナには感じられた。怖くてその音が鳴りやむまで 身を縮めた。 ﹁おかあさま?﹂ 怖々と振り向いたさきは一面の白。白銀に包まれた場所に道はな く、雪だけが高く積み上げられている。そこにいたはずの人物の姿 はなく、ハンナは慌てて立ちあがった。﹁おかあさま﹂と呟きなが ら、迷うことなく雪に手をさしいれる。手袋すらしていない状態で 飛び出してきたのだ。当然、怜悧な痛みが手を襲っていく。冷たさ 73 を通り抜けて、燃えるように熱かった。 ﹁おかあさま!﹂ ﹁⋮⋮ハンナ﹂ ﹁⋮⋮っ!﹂ 白に抱かれるようにして顔をだしているシーナは青ざめて倒れて しまいそうだった。ハンナは急いで傍らにしゃがみこみ、シーナの 体を覆い隠している雪をどかそうとする。赤く腫れて痛みをうった えてくる手のことなど頭の隅にも引っ掛かりそうにない。そうして、 雪をかきわけるハンナをとめたのはシーナだった。 ﹁もう、いいの﹂ ﹁なんでっ! おかあさま、死んじゃうよ?﹂ 自分が発した言葉であるのに、ハンナは引き裂かれるような痛み に襲われた。 体調の優れなかったシーナが、平時のものでも耐えられるかわか らない雪下に埋まっている。厚くうがたれた穴に身を滑らし、唇を 震わせてすがるように見つめてくるのに、ハンナの手では救い出す ことができない。いやだ、と噛みしめるようにハンナは手のひらに 力をこめた。 ﹁ハンナ。あぶないわ⋮⋮にげて﹂ ﹁やだっ! ぜったいやだ! おかあさま︱︱﹂ ﹁ハンナ⋮⋮﹂ 体の下からはいだした手のひらでハンナの頬を包み込み、シーナ は微笑む。 およそ、人の体温ではありえない冷たさを保ちながら、気丈にシ ーナは言った。 ﹁愛しているわ。わすれないで﹂ ﹁おかあさま⋮⋮?﹂ すがりつくように握りしめた手首から伝わる脈動はよわい。 ぐっと噛みしめた唇から熱い液体がにじみでたのがわかった。鉄 くさい味がする。 74 ﹁こんなもの欲しければあげるから﹂ 固まった手に握りこまされたのは鍵。さきほど、シーナが落とし て拾い上げたものだ。綺麗に磨き上げられた鍵は、絶望が差し迫っ ているこの状況でも美しく輝いていた。ハンナはじっと鍵を見つめ る。 自分はこのような鍵が欲しかったのだろうか。 ︱︱いや、ちがう。 ハンナが欲しかったのは、こんなちっぽけな鍵ではなかったはず だ。いま、繋いでいる。体温が失われていく手を、温もりを与えて くれる存在を、ハンナはずっと欲しかった。欲しかったから、我慢 して、我慢できなくて、手に入れていたのに失おうとしている。 ひくり、と喉が震えた。絞りだすように呼びかけると、やさしく なであげられる。 ﹁⋮⋮生きて、ハンナ﹂ ずず、と雪が流れていく音がする。すがりつくようにしていたハ ンナを追いやってシーナは笑った。いつものように、安心させるよ うに。瞠目して鍵を握りしめ、人形のように尻もちをつく愛するわ が子に、最上の慈しみを向けたまま。紡がれる言葉もまた、ひたす らに純真に。 ﹁⋮⋮あいしてる﹂ ︱︱そして、白の悪魔は連れ去った。 ﹁おかあさまああっ!﹂ 雪に飲み込まれ、もてあそぶように流されていく姿を焼きつけて、 ハンナは叫んだ。 伸ばした手が二度と触れ合うことはない。 75 永遠の別れを︱︱。 76 4 寒空にさらされたわが子の顔は蒼白だった。 ハンナの自室は質素なつくりになっていた。贈りものなどあげた 記憶がない。子どもの部屋でありながら殺風景なその部屋は、愛情 をかけているとは思えないほど寂寥感に満ちている。 綺麗に設えられたベッドにハンナは横たわっている。顔色はよく なく、唇は青から紫にかわりはじめたころだった。その傍らで腰を おろしていたベルモンドは扉をノックする音で顔をあげた。低く応 答すれば、甲冑を着込んだ兵士が深々と頭を下げてくる。 ﹁⋮⋮シーナ様の、御遺体が発見されました﹂ ﹁そうか﹂ ﹁⋮⋮失礼します﹂ 再び閉ざされた扉を見やってから、ハンナの頬に指を滑らせる。 発見されたときには、冷え切って呼吸も浅かった。すがるように シーナの鍵を握りしめていた。何があったのかを問いかけることも できないほど衰弱していたため、いそいで治療をした。ろくに防寒 具を着ないまま外出したのだ。手足は凍りつき、その命さえも尽き ようとしていた。 ﹁すまない、ハンナ﹂ あのとき、自分が無下に扱わなければ、起こらなかった出来事だ。 いい子だと言ってやれば、ハンナは我慢をした。シーナの病につ いても、幼心に思うことがあったのか無理強いをする素振りは見せ なかった。けれど、糸が切れてしまったようにハンナは、はじめて 我が儘を言った。その一度の我が儘が取り返しのつかない悲劇を生 んだ。 支えなければ、と思う。小さな心が壊れないように。守らなけれ ばならない。彼女はまだ、十にも満たないのだから。 ﹁⋮⋮おとうさま?﹂ 77 ﹁ああ。気がついたんだね、ハンナ﹂ 虚ろにまばたきをしていたハンナは、ゆっくりと体を起こして首 をかしげた。 ﹁わたし、眠っちゃったの?﹂ ﹁そうだよ。ゆっくり寝ていた﹂ ﹁⋮⋮ふうん。ねえ、おかあさまはどこ?﹂ あまりにも自然にたずねられ、ベルモンドは硬直してしまった。 おそらく、ハンナはシーナが雪崩に飲み込まれる瞬間を目撃した はずだ。それなのに、ハンナの目はどこまでも真っ直ぐにベルモン ドを映していた。不思議そうにあたりを見回して、シーナの姿をさ がしている。ハンナの具合が悪ければ、いつも寄り添っていたのは シーナだったから、その行動は当然ともいえた。それでも、シーナ はもういない。 ﹁まだ、具合がわるいの?﹂ ﹁⋮⋮ハンナ。覚えていないのかい?﹂ ﹁⋮⋮え、んー? なにを?﹂ ぱちぱちと目を開閉させる。顔色はよくない。嘘をついていると も思えない。 そうか、と呟いてベルモンドはハンナを抱きしめた。突然の抱擁 に戸惑いながらも、ハンナは嬉しそうに顔をほころばせる。冷え切 った体に温度をうつすように、ベルモンドは胸の内からわきあがる 感情をおさえつけた。 ﹁なら、いいんだ。気にしなくていい﹂ ﹁へんなおとうさま。ねえ、おかあさまに会いに行ってもいい?﹂ 身じろぎするハンナを離さず、こぼれた雫がわからないようにベ ルモンドはささやく。 ﹁ああ、もちろんだよ。でも、まずは自分の体調を治そう﹂ ﹁⋮⋮はーい﹂ しぶしぶといったように返事をするハンナにベルモンドは安堵の 息を吐いた。 78 これでいいとおのれの頭に言い聞かせる。そして、わびしい部屋 を後にした。 ハンナの心はきっと目の前で母親を失ったことに耐えられなかっ た。だから、防衛本能が彼女の記憶から母親の死を消し去ったと考 えてよかった。そしてそれは、彼女のためにも、ベルモンドのため にも救いのあることのはずだ。覚えていないなら、忘れたままでい い。思い出して壊れてしまうなら、いっそ記憶の彼方で埋まってい るほうがいいに決まっている。 ハンナを愛していないわけではない。それでも、シーナを愛した。 その結果、シーナを失い、ハンナをひどく傷つけた。 自分の命が消えるまで、誰にも明かさない。ハンナにも、自分自 身にも。 ﹁それで、よろしいのですか?﹂ ﹁ああ。お前にもそのつもりでいてもらう。シーナは病でたおれた ことにしてくれ﹂ ﹁もしも、ハンナさまが思い出されれば、また傷つくことになりま す﹂ ﹁いま、知るよりはいい。ハンナの未来を、わたしは信じることに する﹂ ﹁⋮⋮ベルモンドさま﹂ いさめるように傍に仕えるガイルは声をかけた。それにひとつ、 笑ってみせる。 ﹁わたしは、ハンナの世話をシーナに任せてばかりだった。⋮⋮ガ イル。許してくれるならば、これからのわたしの時間を、民ではな くハンナに注がせてくれ﹂ ﹁なにを!﹂ ﹁︱︱わたしは、償わなければならない。そして、ハンナもこのさ き、償わなければならない日がくるだろう。なに、政務を投げ出す つもりはない。シーナの激情を受け継ぐだけだ﹂ 79 線が細く、はかないシーナはフリジットの女らしくはなかった。 それでも、激情を持ってベルモンドを愛し、そしてハンナを愛した。 それこそ、強くもない体を動かして、全身全霊で愛をささげて死ん だ。いまさら、彼女に返せるわけがない。ならば、彼女が最期まで 愛そうとしたハンナに与えたいのだ。 ﹁フリジットの女の激情は甘くないですよ﹂ ﹁わかっているさ。誰よりもな⋮⋮﹂ からかうように笑むと、ガイルからため息がこぼれた。 ﹁それより、もしハンナが思い出したときわたしがいなければ、ハ ンナをたのむ﹂ ﹁⋮⋮私があなたをさきに死なせるとでも?﹂ ﹁⋮⋮ああ。思っていないさ。もしものときだよ﹂ 執務室から外の様子がよく見える。城下に広がる街さえも雪に覆 われていた。空から重く大きい雪片が降ってきて、フリジットの冬 を彩っていた。普段ならば、共存しなければならないその風景に、 憤りを感じることはなかった。しかし、ベルモンドは拳をつくる。 シーナはほんとうに死んでいるのかと錯乱するほど、綺麗な姿で 見つかった。それでも、触れた手は冷たく、肺は動くことをやめて いた。赤く色づいていたはずの唇は血色をうしない、固く閉ざされ た瞼の下には空虚な瞳が埋まっているだけだった。ただ、口元だけ は幸福なものを見続けたように、弧を描いて固まっていたのだ。 ﹁春はまだこないのか⋮⋮﹂ 誰もが喜び震えるその季節︱︱。その始まりは、いまだ遠く。 フリジット国歴︱︱一七六五年。 ﹁雪解け﹂と称されたベルモンドは、その生涯で﹁春﹂を有する言 葉で称えられることを忌避した。民に信頼と豊かさを与えた王は、 生涯の中で笑うこと少なく、ただひとり娘にだけはやさしく微笑み 続けていた。春を誰よりも願い乞うていたその男は、やがて春のこ ない極寒の冬にたおれることになる。﹁雪解け﹂の終焉であった︱ 80 ︱。 81 第四話 月下の貪欲 氷に覆われた水面に落下したとき、わずかではあるが母の気持ち がわかった。 寒かっただろうと思う。フリジットの冬のさかり。その雪に包ま れ亡くなった母は、良質なベッドに横たわったまま、おだやかに幸 福そうに笑っていたように感じる。ハンナの手足はいまだしびれた ように痛み、冷気に食われたことをまざまざと思いださせた。 ちゃりと鍵がこすれる音が静寂の中にしみわたる。ハンナの手に おさまった鍵は、母がたくすように与えたものなのだ。矮小な心を 黒に落として、ハンナは逃げようとした。その癖は、いまなおなお っていない。逃げたところで何が変わるのだろう。立場や重責は、 避ければ避けるほど、重く苦みをまして追ってくる。背中にのせら れるころには、ハンナに耐えられるものではなくなっている。支え てくれるものもまた、ハンナには残っていない。 ︱︱こんなもの。 母は鍵をそう言った。欲しければあげる、と。 階下を見渡せるベランダの手すりには、オルゴールがついた小物 箱が置いてある。落ちないように片手で押さえているハンナもまた、 外気にその身をさらしていた。刺すような痛みに眉をしかめても、 ハンナは室内に戻ろうとしなかった。途切れ途切れのオルゴールの 音色が耳にやさしく触れていく。 ﹁︱︱なにやってんだよ!﹂ ﹁あら?﹂ 怒気をふくんだ声がかかってハンナは振り返った。仁王立ちした アルクゥがこちらを睨みつけている。その手には湯気がたった食事 をのせた銀トレイがあった。 ハンナの世話役の侍女がすることを、なぜかアルクゥが率先して やっている。見慣れはじめたその光景にハンナはごまかすようにひ 82 とつ笑ってから、小物箱を手に取ってベランダから室内に戻った。 寒気を招かないよう、扉をきっちりと閉める。それでも、室内はひ んやりとしていた。 ﹁また無茶でもする気か? いい加減にしろよ!﹂ ﹁そんなに怒らないで。すこし風にあたりたかったの﹂ ﹁そんなの昼間にすればいい。なんで夜にするんだ!﹂ ﹁わかったわ。ごめんなさい。⋮⋮食事をもらえるかしら?﹂ ﹁⋮⋮ほら﹂ 丸テーブルに置かれた食事は美味しそうな匂いをただよわせてい る。ハンナは一度、鼻先を動かしてから椅子に座りこんだ。真正面 にはアルクゥが腰を下ろす。無作法に肘をつき、そこに頬をのせて じとりと睨みつけてくる。どうやら、さきほどのハンナの行動を許 していないらしい。 本来なら、ベランダから外の風景を眺め、侍女が用意してくれる 紅茶をたしなむ席は、ハンナが食事をとるために使用されている。 美しく盛りつけられた食事も、綺麗に整理整頓された自室も、この 国の中ではすべて一級品だろう。スープを口にしてから細く息をつ く。 ﹁じっと見ないで。食べにくいわ﹂ ﹁︱︱あっそ﹂ ﹁ちゃんと聞いてる?﹂ ﹁どうして、あんなことした? 爺さんも心配してた﹂ ﹁?も?ってことは、あなたも心配したのね﹂ ﹁︱︱したよ﹂ 否定されると思っていた言葉を受け止められ、ハンナは困惑した。 ごまかすために笑おうにもアルクゥは真顔でいるので、乾いた息が もれるだけだ。揚げ足をとって話題をそらすことはできないらしい。 射すくめられたハンナは、軽く肩をあげて苦笑した。食事さえもぴ りぴりと痛む。口の中まで寒気に当てられたようだった。 ﹁聞いてどうするつもり?﹂ 83 ﹁聞いてから考える﹂ ﹁受動的ね。そんなことで話すとでも?﹂ ﹁話さずに、また行くのか﹂ 責めるようにアルクゥは瞳をきらめかせた。 ﹁︱︱⋮⋮行かないわ﹂ こつんと指先に固い感触がする。母が残していた小物箱。形見の 鍵で開けた箱だ。 ﹁こんなものと母は言った︱︱﹂ ためら 白に覆われ、体を抱きしめられ、病に苦しみながらはっきりと。 すべてを思い出したハンナは、踏み入ることを躊躇っていた母の 自室に行った。使用人が掃除をおこなっているために埃ひとつなく、 父が与えた物品が整然と並ぶその場所。隠されるように鎮座してい たのが、彫刻がほどこされた小物箱だった。開けることを迷わなか ったわけではない。ただ、死の間際、母が与えてくれたものだと言 い聞かせて鍵を回した。 ﹁母は、自分の命をそう言ったのよ﹂ こんなもの。欲しいならあげる。 いつだって母はハンナにやさしかった。いつだって愛してくれた。 最期の瞬間まで︱︱。 ﹁この箱には、薬が入っていたの。母の薬よ﹂ 蓋をあけて見つけたのは、月日が経過し変色した薬だった。それ を視界にいれた瞬間、ハンナにはすべてわかった。ハンナが見えも しない嫉妬にかられたとき、母は自分の命とハンナを天秤にかけた。 かけざるをえなかった。そして、母は選んだのだ。ハンナを︱︱。 自分の命すら、こんなものと言った。そこにかたむけた激情のほ どを思い知る。 ﹁母の愛情は本物だった。償わなければならないと、思ったの﹂ ﹁それで、死ぬつもりだったのか?﹂ ﹁︱︱⋮⋮まさか。そんなはずないわ﹂ ハンナが水中に身を沈めたとき、心内には混乱がうずまいた。死 84 にたくない、と爪をたてた。 ﹁母はわたしを愛してくれた。だから、わたしも愛すことに決めた の﹂ かちゃりとナイフを置く。すべての皿が綺麗になって、食事を終 えたことをしらせた。口の中には美味が広がっていたが、どうにも 食べた気がしない。空腹を感じることがなかったので、腹には食べ 物が流れ込んでいるのだろう。ハンナは静かに目を閉じて開いた。 驚くほど静寂に包まれた心境には、不思議と自分の声が響く。 ﹁わたしは、もう決めた。とまることもしない。だから、あなたは 帰りなさい﹂ ﹁なにいって⋮⋮﹂ ﹁ここからさき、わたしとともに歩むならもう帰れないわ。あなた はどうするの?﹂ ガイルはきっとハンナにつき従ってくれるだろう。ハンナが覚悟 を決める前からずっとそばにいたのだから、柔和な顔をひしゃげて 笑うだけだ。しかし、アルクゥはちがう。帰る場所も想いをよせる 人もいる。きっとハンナにはお荷物を引きずって進むことはできな い。捨てなければ進めなくなる。ぐっと拳を握って、もう一度言っ た。 ﹁帰りなさい。あなたが想う人のもとへ。わたしはあなたを責めた りしないわ﹂ 運命の相手など馬鹿らしいとハンナはなじった。 そのようなものに頼らなければ歩めないのか、と。 しびれた足を叱咤して、ハンナは自室を後にする。背後から弱弱 しい声がかかった。 ﹁⋮⋮おい﹂ ﹁すぐにとは言わないわ。好きなときに帰りなさい﹂ 残した言葉は辛辣だった。閉ざされた扉は拒絶の証だ。 吐いた言葉は鋭い剣技をともなってふかく突き刺さる。流した涙 は決別を意味する。 85 ぐいっと涙をぬぐってハンナは書斎に向かった。 胸に秘めたる確固たる決意を知らせるために︱︱。 86 2 肌をさすフリジットの寒気には慣れてきた。無機質に広がる灰と いろどり 白の世界にもすっかり目がなじみ、夢うつつのように浮かんでいた ラフィール山脈の彩が薄れはじめている。それと同じように傍らに いたはずの温もりさえも消えていくようでアルクゥは眉をよせた。 ハンナが決意を表明してから、アルクゥは逃げるように行動して いる。本調子でないまま執務にあたる姿は痛ましく、何度口をはさ もうとしても自分にはその資格すらないのだと絶望する。気軽にか けていた言葉も、すっかり雪に覆われたようにでてこない。すれち がうハンナの雰囲気は以前と明らかにちがう。決めた、と口にした ハンナは気高く映った。 帰還をうながされてもアルクゥはいまだ旅立てない。ラフィール しんらつ は遠いからと言い訳をつくっても成熟したドラゴンの生態を知って いる自分には効果がない。嘘をつくなと脳内から辛辣な声がかかる。 はじめて、アルクゥはかなわないと感じた。 帰りたくないわけではない。しかし、帰ったところでアルクゥは またここに戻ってくるだろう。それでも、ハンナはただ戻っただけ では受け入れてはくれない。きっと自分は彼女にとって足手まとい になったのだ。確固たる意志をもって進むことを決めた彼女に中途 半端な気持ちでついていってはいけない。 ﹁︱︱⋮⋮メル﹂ 明るくて美しいひと。愛したひと。 誰からも好かれた。アナベルたちにも慕われていた。ラフィール 山脈の家族たちに囲まれて中心で咲いている花のようなひと。そん なひとを愛して慈しんだ。咎に落ちて苦しんでも最後まで寄り添っ た。ここまできても帰りたいと思っている。それなのに︱︱。 ︱︱たすけて。 87 知っている。ハンナが苦しみあえいでいたことを。ずっと呼んで いたことを。 そっと自分の角に触れた。角つきは角があるから祝福される。 角がなければどうなるのかと考えた男がいる。角を折った男はド ラゴンに転変できなくなった。誇り高い角を折ったことで仲間から も迫害された。引き裂かれたくなかった恋人にすら裏切られ、男は とが ひとり山を去った。 角を折れば咎がなくなる。そんな噂がある。 あのとき、咎に落ちる前に折ってしまえば、彼女とともにあるこ とは許された。誰にも見つからない場所で手を取りあって生きるこ ともできたはずだ。それでも、アルクゥは折れなかった。自分の角 を折ろうとはしなかった。それはくだらない自尊心だったのかもし れない。迫害されることを恐れたのかもしれない。いずれにせよ、 アルクゥには角がある。 ︱︱ほんとうに愛していたのだろうか。 フリジットにやってきてアルクゥはそればかり考えるのだ。 角を折ることは角つきの誇りを失い、神の庇護を離れる。それで も、折るものはいたし、険しい山脈から追い出されても幸せそうだ った。手をつないで山をおりる人たちは、きっと誰もしらない場所 でひそやかに生きていくのだろう。 ︵メルも望みはしなかった⋮⋮︶ アルクゥが苦しむ横でなにもいわずよりそい、静かに旅立ちを見 守った。かすむ意識の中で毅然と見すえるメルクゥの姿がある。翼 をはためかせれば少し後ずさりして、永遠の別れと思わせないよう に微笑んで手を振った。彼女もまたラフィールの角つきだった。 戻れば彼女は出迎えてくれるだろう。あの慈しむ笑顔で︱︱。 ﹁ごめん、メル﹂ 88 寒気が厳しく誰も近づかないバルコニーはアルクゥの避難場所に なっていた。ひらけた空にのぞく太陽にメルクゥの笑顔を重ねてみ た日もある。吐きだした息は白く、ラフィールではおこらなかった 現象だ。 自分は遠いフリジットにやってきた。ラフィールを離れて翼を動 かして山をこえて︱︱。 そして、出会ったひとはメルクゥに似ても似つかない。無表情で 感情をおしころす。泣きそうな顔をした肌の白い少女だった。美し いと思った。容姿ではない。その生き方に、前を見すえた瞳に、ア ルクゥはかなわないと感じた。出会ってからさほど経っていない月 日。その中でハンナは成長し、アルクゥを置いていった。 下ろしていた腰をもちあげて、アルクゥはひとつ息をのむ。ぐっ と伸びをする。 ﹁おれ、帰らねえや﹂ 帰りなさい、と口にしたハンナの味方など誰もいない。柔和な顔 をした老爺ぐらいだろう。ハンナが進む道の厳しさなどアルクゥに は想像もつかない。それでも生易しい道ではないだろう。やっと笑 顔がみられるようになった。軽口をたたくまでには仲良くなったは ずだ。それでも、身近な死に心を沈ませ、民のために身をけずり、 ひとり玉座にたたずむ。その傍らにたつものはおらず、やがて彼女 は朽ち果てていく。 ﹁まあ。長い道草ってやつかな﹂ ぼやいた言葉に悲哀はない。アルクゥは満足そうに太陽へ笑って みせた。 89 3 ﹁よう!﹂ ﹁⋮⋮まだ、帰る気にならないの?﹂ 書類を抱えて立ち止まったハンナは金髪をゆるくリボンでまとめ あげていた。その両脇には同じように紙の束を抱えた男たちがいる。 ハンナは手をあげて挨拶したアルクゥを一瞥し、立ち止まっていた 男たちにさきをうながした。不躾に視線を浴びせながら彼らはアル クゥをすり抜けていく。 ﹁さまになってきてんな﹂ ﹁いいえ。そう見せかけてるの﹂ つんと唇をとがらせてハンナは言う。その仕草が慣れ親しんだ彼 女を思わせてアルクゥは安堵の息を吐いた。気後れしていたのは自 分だけのようで、ハンナはいたって変わらない。少しだけ背伸びを して見せかけているにすぎなかった。 ﹁おれ、帰らないよ﹂ ﹁また、そうやって。もう客人としてここには置いておけないわ﹂ ﹁じゃあ、臣下としてなら?﹂ 天気の話でもするように、するりと言葉が落ちた。ハンナは瞠目 してから眉根をよせる。 ﹁⋮⋮どういう意味かわかっているの?﹂ ﹁わかってるよ﹂ ﹁故郷に帰れないわよ。この地で骨を埋める覚悟がある?﹂ ﹁あるよ﹂ うなずいてはっきり返答すると、呆れたとばかりにため息をつか れた。 ﹁大切なひとがいるのでしょう?﹂ ﹁いたよ。いまも大切だし﹂ 瞼を閉じればいまも晴れやかに笑うすがたが思い浮かぶ。 90 ﹁それなら︱︱﹂ ﹁でも、おれ捨ててきたんだ﹂ 角を折らなかったのは誰だ。罪を与えたのは誰だ。罰を与えたの は誰だ。 愛したもののために角を折り、迫害にあい、愛したものにさえ手 をほどかれた。山をおり、ひとり去っていった男は、それでも女の ことを愛していたのだ。おのれの誇りを捨ててもかまわないと思っ つるぎ たのだ。それは角を折った誰もがそうなのだろう。自尊心、身のふ りかた。すべてをなげうっても愛したいと思ったから、自分に剣を 落とした。 アルクゥには落とせなかった。自尊心も、なにもかもを︱︱。 それでも、角つきは愛されている。神によって相手を選別され与 えられる。 漠然と、出会ってしまえば離れがたいだろうと思っていた。咎に 落ちながら自分を呼ぶ声に耳をかたむけ、心をよせた。必死にあえ ぐその声の切なさに胸をうたれ、わずかでありながら会いたいと願 った。そして、会った。会えばなおさら、ひとりにはしておけない 危うさがあった。 しかし、その危うさは杞憂にもハンナ自身によってかき消されて いる。そして、アルクゥは選択をせまられた。神の庇護をほうりな げ、雲海をこえて故郷に戻るのか。与えられた運命に従事し、ハン ナとともに歩むのか。 ﹁おれも、決めた。だから︱︱﹂ ざれごと 角つきには誓約がある。決まった言葉もなく、証もない。ただま まごとのような戯言。 ﹁翼になるよ。扉が閉まって進めなくなっても、おれが空を飛んで 進ませてやる﹂ ﹁⋮⋮痛いかもしれないわ﹂ ﹁かまわない﹂ ﹁氷の粒が貫くかもしれない﹂ 91 ﹁いいよ、べつに﹂ ﹁︱︱わかってないのね﹂ つむがれた言葉は冷たいのに、声は不思議とあたたかい。言葉尻 が震えていたからかもしれないが、そっと書類を握りしめている手 を取った。苦労をしらない手はきめ細かく、太陽を浴びていないた めに青白い。華奢で力をこめてしまえば折れそうなほど弱い。 彼女はこれから、この小さな体ひとつで国を守って、立ち上がっ ていく。脇には誰もいない。支えもない。荒れ狂う海に小舟で挑む ような無謀さで︱︱。それでもハンナはフリジットの激情をともな って足を踏み出す。 その支えになりたいと、心からそう思う。 ﹁わたし、すべてを守れるほど強くないわ﹂ ﹁しってるよ﹂ ﹁だから、あなたが途中で倒れても助けられない﹂ ﹁⋮⋮覚悟してる﹂ ﹁踏みにじって進むわ。足元になにが転がっても︱︱﹂ 途切れた言葉のさきに蓋をするように、アルクゥはハンナをかき 抱いた。水中に身を沈めた体はいまだに冷感をともなって、じわり とアルクゥを浸食する。解放された書類は廊下に散らばり乾いた音 をたてた。すこしだけ漂う柑橘系の匂いが鼻をくすぐった。遠慮が ちに掴まれた手の力は弱い。 ﹁︱︱もう、いいから﹂ ﹁⋮⋮⋮⋮ん﹂ 国を背負う。ひとりの人間が何万という命を管理する。そこに息 づく生命を庇護する。 ハンナは守りたいのだ。フリジットが嫌いなのか、とアルクゥが なじれば苦痛に顔をゆがませた。身をていして命を繋いだ母の気持 ちに呼応して、絶望するでもなく決意した。 出会った当初、アルクゥはハンナのことを泣き虫だと感じた。泣 きはしない。ただずっと泣きそうだった。ひとりで耐えて逃げよう 92 としていた。逃がしてもよかったはずだ。自分ならそれができた。 それでも、ハンナは一国の王だったのだ。玉座に選ばれたのは運で はない。 腕に抱いた温もりはいまだ小さく弱い。それでも、熱く脈打って いる。 ああ、きっと。 アルクゥは感嘆するように思った。 ︱︱彼女こそが、おれの女王陛下なのだ。 93 4 ﹁美しいと思わない?﹂ ﹁んー﹂ ﹁あら、気のない返事﹂ ﹁んー﹂ 書斎はいまだに執務室として使用されている。棚に押し込められ た本は背表紙もバラバラで、管理のずさんさを思わせた。主である ガイルでさえも整頓する気はなさそうなので、ハンナもことさら触 ることはなかった。 すっかりハンナの執務室とかした書斎には、ハンナとアルクゥが 当然のように居座っている。 もともとの主であるガイルでさえも特別な用事でもないかぎり、 たずねることは少なくなった。ハンナをのぞいて頻繁に出入りする のはアルクゥぐらいで、そのほかの臣下は書類の運搬以外で顔をだ したりしない。そのため、書斎はいつも静寂に包まれていた。 暖炉の前で椅子をこいでいたアルクゥは瞼をうとうとさせてまど ろんでいる。 ハンナはそんなアルクゥに呆れながらも、強く言葉を重ねること はしなかった。広げていた写真をわきに押しやり、左右に揺れてい る灰色の頭を眺めた。 ラフィールを思わせる緑にあふれた写真は、この時期にはめずら しい商人から買いつけたものだった。気まぐれに購入してアルクゥ に見せたものの、気がのらないようだった。ハンナ自身も額面で見 る緑にはどこか嘘くささがただよい、晴れやかな気持ちにはなれな い。ここ最近のフリジットはさらに灰と白に閉ざされているのだ。 食料の不足。寒気にあてられ倒れる民の人数︱︱。 朝議でもそれらの重苦しい会話がかわされ、気分もふさぐ。慣れ てきたハンナとはちがい、アルクゥは最近参加しはじめたのだ。真 94 面目に聞こうとはしているが、やはり理解のおよばない話というの は眠気をさそう。うつらうつらとしているアルクゥは、それでもフ リジットのことを考えてくれているようで、わからないなりに発言 はしてくれていた。 ﹁⋮⋮疲れているのね。しかたないわ﹂ そっとアルクゥの頭を撫でていると、扉をノックする音がした。 ﹁あら、めずらしい﹂ 書類はすでに持ち運び、処理されている。緊急の用件でもあるの か、とハンナは扉を開く。 ﹁失礼いたします﹂ ﹁クライス。どうかしたの?﹂ ﹁はい。火急の知らせが︱︱﹂ ﹁そう。なに?﹂ クライスはいつも冷静な顔つきをわずかにゆがめて口を開いた。 ﹁我がオルコット領内で反乱が起きました﹂ ﹁反乱? どこで﹂ ﹁以前、身内が不正に税を徴収していた場所です﹂ ああ、とハンナは納得した。 フェルとシグルが暮らしている村のことだ。あの一件があったと はいえ、いまだに領主はオルコットのままだ。不正を働いたものは 役をとかれ地位も落とされている。新たに赴任したものは真面目に 業務にあたっていると聞くし、反乱が起こる理由としては弱い気が した。あそこの村のものはみな気のいいひとだったように思う。 ﹁やはり、長く大雪が続いたせいでしょうか︱︱﹂ ﹁みなを集めてクライス。緊急に議会を開くわ﹂ ﹁⋮⋮はい﹂ 深々と頭を下げて去っていったクライスを尻目に、ハンナは書斎 を振り仰いだ。暖炉の前で眠りにふけっているアルクゥはぴくりと も動かない。叩き起こして議会に連れて行くのは不憫に思え、ハン ナは手近にあった布を背中にのせると、薪を減らして火勢を弱めた。 95 ふうと息を吐いてから、ささやくように言葉を落とす。 ﹁すこしでてくるわ。ゆっくり休んで﹂ 書斎を後にすれば廊下に設えられた窓から外の様子がうかがえる。 フリジットの大雪は、それこそ命に関わる。 物資の流入が遅れ、最悪の場合は途絶える。雪崩など起きようも のならば、村がまるごと孤立してしまう。その上、防寒の行き届か ない地方では寒気にあてられて体調を崩すものが多く、医者に診て もらおうにも雪が吹きすさぶ中では満足に歩けない。 荒れ狂ったように通り過ぎる白い世界に目を閉じて、ハンナは臣 下が待っているであろう会議場に足を進めた。 96 5 会議場にはすでに臣下の大半が集まり席についていた。それぞれ 顔を見合わせなにごとかとささやきあっている。そのさざめきをす り抜けてハンナは自分の定位置に座り、備え付けられた飲み物で喉 をうるおす。 ﹁オルコットが治める領地で反乱が起きた。鎮圧せねばならない。 そこで、みなの意見を聞きたい﹂ ︱︱反乱? ︱︱また、どうして。 ざわめいていく臣下にハンナは嘆息した。 ハンナ自身、反乱など予想していない出来事だった。鎮めなけれ ば武装した民に兵士がやられる。しかし、兵士を向かわせ武力を行 使すれば民の中に死傷者がでることは確実だった。ぎりっと歯がみ する音は誰にも届かず消えていく。やはり、オルコットが課した税 は民にとって重かったのだ。取り分が必要以上に搾取されていたた めに、あの村では貧困がはやくきてしまったに違いない。 ︱︱ほんとうに反乱なのか? ︱︱あそこはオルコットの重税もあっただろ。 ︱︱それで反乱とは⋮⋮浅はかな。 民を嘲笑うような言葉にハンナは瞑目する。臣下はいつだって民 に厳しい。 ﹁わたしは︱︱﹂ ハンナが口を開けば、水をうったように静まりかえる。揚げ足を 取ろうと耳をすませるのか、純粋に聞き耳をたてているのかは判断 97 つかなかったが、騒然としていた場内が静かになったのはありがた かった。いくつもの視線に貫かれるようにして、ハンナは言葉をつ むぐ。 ﹁民を傷つけたくない。できれば、武力以外での解決をのぞむ﹂ ﹁お言葉ですが、ハンナ様。それは厳しいです﹂ ﹁︱︱⋮⋮それはわかっているよ﹂ 立ちあがり発言した老騎士にハンナはおざなりに答えた。 武力を言葉で鎮圧することの難しさはよくわかる。それでも︱︱。 ﹁お願い。わたしは民が傷つくところを見たくない﹂ 慈しみたいと願った。母がハンナにかたむけてくれた愛情のよう に。 ﹁では、私に任せていただけませんか?﹂ そう発したのは沈黙を守っていたクライスだった。神経質に顔を ゆがめ、言いづらそうに口ごもる。そんなクライスに鼻白んだのは ハンナではなかった。 ﹁ふん。名誉挽回か?﹂ ﹁そうとらえてもらってかまわない。⋮⋮いかがですか?﹂ ﹁策はあるの?﹂ ﹁考えならひとつ︱︱﹂ クライスのきらめく瞳にハンナは口を閉ざした。 在位してから月日は経った。政にも知識がふかくなったし、政務 にも真面目に取り組んでいる。しかし、雪に閉ざされたフリジット では国防は重要ではなく、また資源にもとぼしいために他国からの 圧力もない。ゆえに軍の話というのは希少なものだ。ハンナには判 断つかない面もある。 オルコットはさきの課税で不正をした。けれど、クライスが有能 であることに変わりはない。むしろ、信頼回復を狙って貢献してき た物事には目をみはるものがある。 無下にしてしまうには口惜しい。 ﹁わかった。一任しよう﹂ 98 ﹁かならず、吉報をお届けします﹂ 感極まるクライスとは違い、ハンナはそっと息をはく。 変わると決めたのに、と落胆する。 わからないものを自分で考えず、また理解しようともせず臣下の いいなりに事を進める。判断をゆだねたために、目につくおこない があっても強くはでられない。最初のころとなにも変わらない。変 わったのは基礎的な政の部分で、全体で見渡せばハンナが関わって いるものなど限られている。それでも、成長したとはいえるのだろ う、とむりやり自分を納得させた。 ﹁期待しているわ。もうわたしを失望させないで﹂ 言葉に棘はあるのだろうか。冷たくひびく自分の声に偉そうにと 自嘲する。 対案がだせずに民を傷つけない方法も見つけられず、他者に頼っ たあげくに釘をさす。なんて傲慢な王なのだろう。それでも、弱み こっけい をみせればまた仕事のない毎日をおくるはめになる。空位の玉座は 寒々しく、見せかけだけの玉座は滑稽だ。ハンナの尻はいまだに玉 ごうしゃ 座になじまず、浮いているような錯覚をもたらす。 謁見の間にある豪奢な椅子に座ったことは数度だけ︱︱。 それも儀礼的な物事のときだけで、座っている長さでは書斎の椅 子がひとつ抜きんでている。 きめたと意気込んだ威勢はどこへいってしまったのだろう。ハン ナはいまだ迷い玉座に浮いている。臣下の溝を埋められず、顔色を うかがって反応をみる。一任している政務は数知れず、国防にいた っては丸投げ状態だ。それは最初のころにそうしてしまったからに 他ならないが、いきなりぜんぶ取り決めるというのも無茶な話にな ってしまう。ひとつずつ、切り崩していく途中で、予想外の出来事 がハンナを揺らす。 難しいと頭を抱えるハンナはよそに臣下は慣れたように議論をす すめる。 頭をかすめていくのは厳格だった父の顔︱︱。 99 父は迷わなかったのだろうか、と想像する。 ﹁雪解け﹂という名誉ある称号をあたえられた。厳しくもやさし い父の政策は、民を怠惰にさせず痛めつけもしなかった。ハンナの 案では民が怠惰になっていくと誰もが口にする。しかし、重税を課 せられたあの村が怠惰だったとは思わない。彼らのように目のつか ないところで民が苦しむのはいやだ。倒れていくのはいやだ。 ︱︱フリジットの冬はいまだに厳しく閉ざされているというのに。 100 6 ◆ フリジットの景色を彩るのは灰と白。それからわずかばかりのぞ ちんうつ く太陽のくすぶった黄色。厚く雪が降り注げばそれすらも消え去り、 沈鬱とした風景がただ広がるだけだ。 フリジットの赤といえば、実りを意味する幸福なもの。 暖炉の灯り。果物の熟した色。熱く焼き上げられた肉の断面。 それでも、フェルの眼前で暴れる赤は、とても幸福とは思えなか った。 呆然と立ち尽くしていると、全焼した家屋から飛び散った火の粉 が頬をなでる。かすかな痛みとともに現実へと引き戻され、フェル は息をはいた。平時なら白くにごる息も、周囲の熱気により姿を消 しさっている。 ︵かあさんは︱︱?︶ 鈍る頭で懸命に我が家の方向へと目を向ける。 怒鳴り声とともに銃声が鳴り、怒号が嵐のように地面を走ってい く。見慣れたはずの村は跡形もなく、ゆがんで傾き火を噴いた家屋 がフェルの行き先を閉ざしている。顔なじみの男たちが武器を手に しては、小さいフェルなど見えていないように追い越していく。中 年の女性は大きいバケツを抱き上げ、悲鳴をあげながら消火にあた っていた。それでも、わずかに委縮するだけで火のいきおいはおさ まらない。 ﹁⋮⋮かあさん!﹂ 床に臥せって動けない母の蒼白に揺れる面差しが思い浮かび、フ ェルは悲鳴じみた叫びをもらした。踏み込むことをためらっていた 業火の中に飛び込み、顔を熱風から守りながら駆けていく。ときお 101 り、視界の端に鎧を着こんだ人々が見えたが、フェルにはそのよう なことは関係なかった。 大雪のおかげで母の体調は芳しくなく、落ち着いた頃合いを見計 らって医者に来てもらったばかりだ。その医者を街道まで見送って 帰ってきたときには、村は火の海と化していた。ただでさえ、安静 を言いつけられるほど悪化した体調で、母が逃げられるわけもない。 やけに背筋が冷たく、気ははやるばかりだった。 ﹁そこの子ども! 待て!﹂ よろい かぶと 貫く言葉は鋭く、フェルは勇んで踏み出した足を止めてしまう。 雪を思わせる白銀の鎧に、深く兜を被った男が口をへの字に曲げ て近寄ってくる。木材が炎上し悲鳴をあげる中で立ち止まったフェ ルをしっかりと見据え、大振りの剣を持っている。表情はよくわか ごうまん らないが、気難しい顔をしているのだろう。放たれる言葉はどこま でも傲慢だった。 ﹁どこにいくつもりだ?﹂ ﹁︱︱⋮⋮かあさんが、まだ﹂ ﹁ほう。そうか﹂ にやりと男の口元がゆがむ。ぞくりと体が震えた。 ﹁危険だぞ。一緒についていってやろう﹂ ﹁⋮⋮っ﹂ フェルは騎士らしき男が握りしめていた剣を一瞥して息をのんだ。 剣の根本からさきに向けて、液体がしたたりおちていく。業火によ って色彩がにぶる中でも、その色は不吉なものをあらわし、フェル の胸中を追いたてた。 ︱︱血だ。 母を探すために顔を庇い走っていたフェルはあらためて周囲を眺 め愕然とする。 熱い舌が舐めとるのは家屋や生きた人間だけではない。血に濡れ 102 倒れ伏したものも舐めとっていく。ぐったりとした人々が道にぽつ ぽつと存在し、つんざくような悲鳴が赤い景色の向こうから飛んで くる。目前の男の口元がぐにゃりと曲がる。 ﹁い、いいです。べつに﹂ 心中に居座るのは底知れない恐怖︱︱。 目前にいるのは人なのか。それともケダモノなのか。フェルには わからない。 ﹁遠慮するな﹂ ﹁ひっ! こないで!﹂ 露骨に身をすくめて距離をとったフェルに、柔和に対応していた 男は豹変した。 ﹁そうか! なら、楽には死ねないな! このくそ餓鬼がっ!﹂ ﹁︱︱︱︱ひゃっ﹂ 振り上げられた剣は容赦なく、小さなフェルの体を狙いすえた。 身を守るものがなにもないフェルは悲鳴とともに体を縮める。足は 恐怖のせいで地面にはりつき、わずかにも動く気配がない。逃げる ように転がって、初手をかわしたフェルは情けない声をあげながら 地面をはった。その背中に無遠慮に靴が乗り、鈍痛とともに重みが かかる。肺が圧迫されて咳き込み、視線をめぐらせば悪魔のような 形相をした男が見えた。 ︵︱︱かあさん! かあさん!︶ 逃れようにも大人の体重にはかなわない。無様に這いつくばるフ ェルを鼻で笑った男は、外さないようにゆっくりと剣の柄を握りこ む。小さな頭に白銀をそえて、刺し貫こうとした。 ﹁やだ! やだあっ! かあさん!﹂ ﹁くそ! 黙ってろ!﹂ ﹁⋮⋮黙るのはおまえのほうだ﹂ ぼしゅっとくぐもった音とともにフェルの上から重みがなくなっ た。怖々と体を起こしたフェルに浴びせられるのは赤い液体。生臭 い匂いとともに生温かさが伝わってくる。絶命した男を乱雑に投げ 103 捨てたシグルは、呆然と座り込んでいるフェルの頭を撫でつけた。 ﹁無事か?﹂ ﹁⋮⋮うん﹂ シグルは片手に猟銃をたずさえていた。その銃口からは煙がのぼ っている。 ﹁おばさんは?﹂ ﹁まだ、家にいる﹂ ﹁⋮⋮そうか。時間がない。急ぐぞ﹂ 地面に座り込んだままのフェルを片手でひきあげシグルはそう言 った。 村の建造物の大半は焼け落ち、なけなしの消火活動もむなしく火 はおとろえていない。 肺にしのびこむ熱い空気にフェルは咳き込んでから、引き倒され て負傷した体を起こす。手のひらはすりむけ、足をのせられていた 背中はずきずきと痛む。圧迫にあえいだ肺は、よどんだ空気をため こみ、フェルをむしばんだ。 ぐっと手をついて体を起こし、差し出された手を握る。フェルの 顔をみてシグルはうなずくと、鋭い視線を周囲に向けた。おそらく、 さきほどの男と同じ鎧のものを警戒しているのだろう。ざあっと恐 怖が頭の上からふってきて、フェルはいっそうシグルの手を握った。 ﹁⋮⋮どうして?﹂ 呟いた言葉は力なく、火のはぜる音が消し去っていく。 豊かではなかった。それでも狩猟で生計をたて厳しい冬を乗り越 える村だ。その村が予期せぬ大火にのまれ、理解のおよばぬうちに 滅ばされようとしている。フェルのつくった雪だるまも熱風のおか げで溶けてしまっているだろう。 ぼろぼろとこぼれる涙を凍りつかす寒気もいまは見る影もない。 さきを行くシグルの表情は読み取れない。しっかりと繋ぎ合わさ れた手は燃えるように熱い。悲哀をおびた叫びは耳に痛く、鮮やか な赤は目にささる。フリジットの色とは違う光景は、フェルを異世 104 界へとつれていったように思えた。うずくまる人々も、泣き叫ぶ声 も、閉ざして蓋をしてしまいたい。フリジットを覆う雪のように︱ ︱。 それでも、フェルの目の前には紅蓮の炎が揺れ動く。危険をさけ てふたりで歩く。見慣れたはずの馴染まない風景の中を、フェルは 逃げるように顔をうつむけて足を進める。足取りは重く、頭は熱気 のせいでぼんやりとかすんでいく。 がっくりと首をさげて向かうさきは、無事かどうかもわからない 家。 そこに母がいればいい、とフェルは思った。 最悪の想像をごまかすように、きつく唇を噛みしめた。 105 7 フェルの家は村の入口近くの奥まった場所にある。 火の手があがる村々とは外れた場所にあったために、フェルたち がたどりついたときにも発火はしていなかった。迷いなく家屋に踏 み入るシグルの背中をフェルは小走りで追った。やけに胸が高鳴っ て脈動が耳に届いてくる。 ﹁︱︱フェル?﹂ か細くはあったが聞きなれた声に、フェルはわっと駆けだした。 医者に見せたときと同じように安っぽいうすい掛け布団をかけ、 やつれた顔で笑う母がいた。飛びかかる勢いで抱きつくフェルに苦 笑しながら、無表情に眺めているシグルに目を配る。沈痛そうな面 持ちでフェルの母をみやる姿に、ふと笑んだ。 ﹁外は大変なことになっているようね﹂ ﹁はい。おばさんも一緒に︱︱﹂ シグルが早口につむぐ言葉の隙間にもぐりこむように流れる声。 ﹁わたしは、いいの﹂ 静かに残酷につむがれる言葉に目を見開いたのはどちらだったの だろう。 ﹁かあさん?﹂ ﹁あなたたちだけでも逃げなさい。わたしはろくに動くことができ ないから﹂ 困ったように眉をさげ、おのれの体を一瞥してからフェルをみや る。 うすい布団に隠された体は細く、体には覇気のひとつも見受けら れない。母が歩くことができないのはフェルが一番わかっている。 寝たきりの母にかわり、凍りつかない深い井戸から水をくみ、近所 のひとから分け前をもらう。肩身のせまい想いをさせてすまないと 謝罪されるたびに、胸がきゅうと縮まってうまく言葉がでなかった。 106 ﹁⋮⋮迷惑でしょう?﹂ 震えるようにささやかれ、フェルは言葉をうしなって泣き崩れた。 一度でも母をないがしろにした覚えはない。それでも、フェルの おこないはそう見えていたのだろうか。いいえも知れぬ寂寥が胸に おしよせ、フェルは子どものように泣きじゃくった。母が病にふせ て、物乞いのような生活になっても、周囲から奇異に見られても流 れなかった涙が、いまになってろうろうと流れ落ちてしみていく。 ﹁そんなことっ! 言わないでよ、かあさん!﹂ さきほど、フェルを貫こうとした剣が、母のうすい胸を刺し貫い てしまう。 地面に押しつけられ、絶望にさらされたフェルは動けもしない母 に助けを求めた。 最期のまばたきひとつの間に、姿をみたいと願った︱︱。 ﹁ぼくが! ぼくが背負うから! ほら!﹂ 華奢で力ない手をとって無理に動かし、フェルはせまい背中を母 に向けた。 ぼろぼろととめどなく流れ落ちる涙を分厚い服の袖でふく。湿気 を帯びてかさついた衣類は肌にいたく、涙にぬれてひりついていた。 しゃくりあげながらおぶさるようにせがむフェルに、困惑した視線 を向けながら、母は名を呼びかける。その声の節々に否定の意味を 感じ取り、フェルはあえいだ。 ﹁︱︱かあさん!﹂ ﹁フェル。おれが背負うから﹂ 見かねたようにシグルはそういって持っていた猟銃をフェルの手 に押しつけた。ずっしりと重い猟銃を両手で抱えもち、フェルはし ゃくりあげながら様子をうかがう。線の細い母の上半身を起き上が らせ、首に手を回させるシグルに体格のちがいを思い知る。無骨な 銃を抱え持つ手はふっくらと丸く、幼稚さを忘れさせない。 ﹁⋮⋮やめて、シグル。放っていって﹂ ﹁おばさん。いい加減に︱︱﹂ 107 怒気をまとってシグルが言うと、母は優しく静かに笑んだ。 ﹁ねえ、シグル。あなたはフェルを弟のように扱ってよく面倒を見 ていてくれたわね﹂ 思い出を語るようにゆっくりと、懐かしむように喜色を浮かべ、 母はひとり笑っていた。 ﹁あなたなら、フェルを守ってくれる。きっと、この中を逃げ切れ ていけるわ。だから、足手まといになりたくないの。ふたりとも、 無事に逃げて。そして︱︱﹂ ︱︱生きて。 ﹁お願いだから⋮⋮﹂ すがるようにシグルを抱擁し、母は距離をとるために背を押した。 力などほとんどない。それにも関わらずシグルは前のめりになっ た。支えをうしなった母の体は安っぽい布団に逆戻りしてしまう。 顔はフェルにも向けず、奇妙な空気がその場に落ちる。ぐったりと 倒れ伏した母に近づくフェルを押しとどめたのはシグルだった。 猟銃を取り上げると、乱暴に手を握りこむ。痛いほどに握られた 手にフェルはいやな予感を覚えた。母に背を向けたシグル。ぴくり とも動かない母。ともに逃げることを拒絶したか弱い肢体。そのど れもがフェルを追いたてて、ますます胸が苦しく泣き叫ぶ。 戸口に向かうシグルに引きずられ、フェルの体もまた母から遠ざ かっていく。 拒絶するように踏ん張っても、使いこまれ表面が滑る床では無駄 な抵抗に終わっていく。 ﹁かあさん! やだ! なんでだよ! かあさんが︱︱!﹂ 獣の叫びのように息を荒くし、目を血走らせたフェルはシグルの 手にかみついた。 さすがのシグルも拘束をゆるめ、フェルを手放してしまう。自由 になった体で母のもとに駆けつけたシグルは倒れ伏す母にすがりつ 108 いた。浅く呼吸を繰り返す姿にほっと安堵の息をはく。 ﹁フェル。行きなさい﹂ ﹁やだ! かあさんも行くんだ!﹂ ﹁いうことを聞いて。お願いだから﹂ ﹁いやだ! うー﹂ 無理にでも動かそうとするフェルの両頬を冷たい手が包み込んだ。 やつれた顔をした母はおどろくほどの美麗さをたたえ、生きてい ることを実感させる。 ﹁お願い。生きて⋮⋮﹂ ﹁⋮⋮っ。かあ、さん﹂ 震えるわが子を抱きしめるために肘をつき体を起こす。 寒い冬を乗り越えて春がくれば、助かったのかもしれない。春に なれば行商も流通し、薬も豊富になる。春がくるのを楽しみにふた りで待ち望んでいる日々は、満ち足りたものだったと確信する。そ のおとずれは、やってきそうにない。 ﹁ごめんね﹂ フェルは母に謝られることが好きではなかった。 父は猟をしているときに熊におそわれ亡くなった。大黒柱がいな くなった家で、母は懸命にフェルを養った。その母が寒気にあてら れ病になった。家を支えられるのはフェルだけになった。そのこと に、母が苦心していたことはしっている。申し訳ないと口にされ続 けた。 ︵そんなことないよ︶ 悲しいことなどひとつもなかった。シグルはじつの兄のように接 してくれたし、一人身の猟師は気がよく、ときどき分け前をくれた。 ひとりで遊んでいると捕まって、酒場につれていかれ、たらふくご 飯を食べさせられた。くだらない話を聞かされて、母の病のことを 励まされた。 もしも、悲しいことがあるなら。それは、そんな村が滅びようと していることだ。 109 ﹁かあさん。ぼく、かあさんといられて、しあわせだったよ﹂ ずっと胸にしまいこんで、つむぐことが恥ずかしかった本音。 謝罪されるたびに吐きだしてしまいたかった。ほんのちょっとの 勇気。 ﹁かあさん、だいすき﹂ ぎこちなく笑っていうと、母は瞠目してから、いつものように微 笑した。 ﹁わたしもよ。フェル、だーいすき﹂ 回された腕も、抱きしめられる感覚も、フェルをしめつけてはな さない甘美なもの。 それでも、フェルはふりしぼるように体を離してシグルの傍に行 った。噛みついたことを怒るでもなく、フェルの頭を撫でつけて背 中を押すシグルの手はわずかに震えていた。振り返り、最期に見た 母の顔はひどく穏やかで、これから待つ悲劇など、幻のようだとフ ェルは思った。 110 8 ◆ ﹁フェル。ここで隠れてろ﹂ シグルがフェルを押し込めたのは、フェルの家の近くに設えられ た牧舎だった。質素な枠組みでつくられたそこには、一匹の毛深い 雪牛がのんびりと草を食んでいて、シグルはその雪牛の縄を解くと 山に向けて尻をはたいて逃がした。雪牛は温厚な性格なので追いた てられてもゆっくりと歩みをはじめる程度ではあったが。 ﹁おばさんはああ言ったけど、ようはここが無事ならいいんだ。す こし目を引いてくる﹂ ﹁あぶなくない?﹂ わらを被りながら身を隠したフェルは隙間からシグルをうかがう。 ﹁大丈夫だ。なにがあってもでてくるなよ﹂ 粗末な牧舎には少しばかりのわらしかない。小さな体をもったフ ェルならば身を隠せるほどだったが母はもちろん、シグルさえもは みだしてしまうだろう。大人しくわらを被って身を隠す姿をみまも ってからシグルはひとつうなずいて踵を返した。向かうさきはおそ らく、悲惨なことになっている村だ。 シグルが去ってからフェルは膝を抱えてうずくまった。陽が落ち たせいで村の炎がはっきりと浮かびあがり、フェルの目を焼いてい く。すぐそこにある我が家には、息をした母が眠っているのだろう。 このまま、何ごともなく朝がきて、すべてが夢だったらいいのに、 と想像する。それでも、突き付けられた恐怖はフェルを震わせたし、 踏みつけられた背や泣きはらした目は痛みを感じさせていた。 思えば、重税を課されたのち村にいいことなどなかった。 課税を減らされ領主が変わったかと思えば、大雪がやってきた。 111 飢えに耐え切れず倒れるものがでても、身を寄せあって生きた。吹 雪の中を山に入り、獲物をしとめるものもいれば、そのまま帰って こないものもいた。それでも、貢献できないフェルの家にまで心を 配り、みなで難を逃れた。その矢先に、村は思いもよらぬ大火に襲 われている。 ﹁とうさん。かあさんを守って﹂ 父は立派な猟師だったように思う。フェルは幼心にも猟師になろ うと決意していた。 村では猟師が一般的な職業だったし、それ以外は商いのために村 を出ていった。山中には雪鹿をはじめとした動物が生育していて、 父は不運にも熊に襲われ絶命した。父の死を聞かされたとき、母は フェルを抱きしめて泣いていた。仲のいい夫婦だったと感じる。あ とにもさきにも、母が泣いたのはあの一度きりだった。 ﹁⋮⋮まだかな。はる﹂ 母と心待ちしていた春は、まだやってきそうにない。 村にやってきた不思議な女性を思い浮かべる。春を待つフェルを やさしく励まし、母と春が迎えられるように言葉を落とした。春の おとずれを信じさせてくれた。かすむような憧憬にフェルは息をこ ぼす。白い湯気がもうもうと視界をけぶらせ、空へとのぼっていく。 どうもう 古ぼけた牧舎は天井に穴があいていて、そこからのぞく月はとても きれいだった。 ﹁あれ︱︱?﹂ 金属のかすれる音。獰猛な息づかい。 猟師の卵として磨き上げられた五感がつげてくる来訪者はおだや かな音をたてない。 ︵ああ。きてしまった︶ フェルは膝を抱えて小さく丸まった。 ﹁おい。家があるぞ!﹂ ﹁もう、逃げたあとか?﹂ 落とされていく憐憫のかけらもない声。踏み荒らす乱暴な足音。 112 ︱︱こすれあう金属の音。 どれもがフェルを震えさせ委縮させる。 ﹁⋮⋮女がいた。眠ってるようだぞ﹂ ﹁のんきなことだ。おい、引きずりだせ﹂ ﹁⋮⋮っ!﹂ 飛び出そうとした体を押さえつけたのは、いったいなんだったの だろう。 フェルは声を出さないように手でふさぎ、ぎゅっと目をつぶった。 ︵かあさん! かあさん!︶ 生きて、とささやかれた優しい声を思い浮かべる。 頭をなでてくれた。ほめてくれた。愛してくれた。 そのすべてが色鮮やかな思い出となってフェルを襲う。 たったひとつの惨劇だ。大きな国の片隅に位置するちいさな村。 そこで起こった語り草になるような悲劇。時の流れにうすれゆくわ ずかな光景。その中で、フェルはいま息を押し殺し、生きている。 飛びだしてしまいたい。最期まで寄り添っていたい。 けれど、母の悲しむ顔が浮かんで、力強く唇を噛みしめることし かできない。 叫んでしまわないように。怒りがあふれでないように。 押しよせるざわめきに混じる悲鳴の切なさを︱︱。 ︵かあさん︶ あっけなく途切れた断末魔に、フェルは息をこぼした。 熱く燃えるような液体が頬を伝っている。ぬぐってみても、暗が りではわからない。 ︵赤くないかな︶ たぎるように脈動する心臓に、フェルは手を置いた。 流れた涙はちゃんと透明だろうか。フェルの激情がもれでてはい ないだろうか。 113 ﹁おい。よく探せ。こっちには火が回ってないからな﹂ ﹁一人残らずは無理でしょう。こちらにも被害がでているわけです し﹂ ﹁隊長︱︱。俺たちこんなことして大丈夫でしょうか?﹂ おどおどとした声音が届いてフェルは身をのりだした。わらが動 きをみせたが、発言したものに気を取られているため、気づかれて はいないようだ。年若い騎士は村の方へ視線を走らせ、怯えるよう に震えた。 ﹁反逆罪とかで裁かれたりとか︱︱﹂ ﹁馬鹿をいうな。王の命令で俺たちは反乱を鎮圧しにきたんだ﹂ ﹁でも! 反乱なんてなかったじゃないですか?﹂ 頭を抱えてむせぶ騎士に周囲のものたちがなだめすかす。 ﹁王に一任されたクライス様の命だ。俺たちはただそれを遂行した だけにすぎない﹂ でも、と言いつのる騎士を一喝すると、隊長と思しき男はもう一 度、フェルの家を検分した。 自らが斬り捨てた痩せ細った女性が転がっているだけで、人影は 見当たらない。傾いた牧舎には家畜はおらず、寒々とした光景が広 がっている。尻込みした部下を一瞥し嘆息すると、くるりと踵を返 す。村内におりる道へ足を踏み出すついでに命令を告げる。 ﹁燃やしておけ。もう誰もおらん﹂ おざなりに投げられた言葉に従って騎士が火をつけていく。 母と身を寄せあった家が燃やされることを知っても、フェルには 動く気力すらない。 ︵なくなっちゃった︶ 母も。母と過ごした家も。育った村も。すべてが赤く熱く染まっ ている。 114 9 立ち去った隊長に続いておりていく騎士の最後尾。罪悪感にむせ んでいた青年はひとり、燃え盛っている家を眺めて立ち止まった。 入口付近には引きずり出され、むごたらしく斬られた女性が微動だ にせず横たわっている。息がないことは明白だった。血に濡れた剣 を見つめ、震える腕に苦笑する。 むこ 国を守るために振るう剣に迷いなどないと思っていた。斬り伏せ たのが無辜の民でなければ︱︱。 ﹁すみません﹂ その謝罪の言葉を聞きいれたのは、わらに隠れたフェルしかいな かった。 たったひとり。炎が渦巻く家の前でとどまり、兜を取り去った青 年は、疲弊しきった顔で母の遺体に頭を下げた。それを見た瞬間、 あれほど出ることを阻害した体が軽やかに動いた。わらをどかして 青年に近寄る。近寄れば母の亡骸がよく見えて、血のにおいも漂っ ていた。 うつむいていた青年は、足音に気づいたのか顔をあげて瞠目した。 ﹁き、きみは?﹂ ﹁︱︱⋮⋮かあさん﹂ ﹁え、あ⋮⋮﹂ おざなりに投げ捨てられた母の遺体に寄り添い手を握る。まだ、 温もりがある。 蒼白に固まった顔を抱え込み、フェルは泣いた。こらえるように 唇を噛んだ。 ﹁きみのお母さんかい? あの、俺は︱︱﹂ どぎまぎと話しかけてくる青年に、フェルは視線を配って嘲笑し た。 ﹁ぼくも、ころすの?﹂ 115 赤く染まった剣はあいつらと同じだ。誰かを殺して、ここまでき た。 生きてと願われ、生きようとした。それでもこれほどにつらい。 ︵斬られてもいいや︶ シグルがいたなら怒られただろう。きっと母にも怒られた。 ︱︱しかし、いまは誰もいない。 ﹁⋮⋮殺したりしないよ﹂ 手に持っていた剣を投げ捨てて青年は言った。 支給品である剣はつくりだけは上等らしく、重い音をたてて地に 落ちる。それに目もくれず、母の遺体を抱え込むフェルの頭をやさ しく撫でた青年は泣きそうな顔で笑った。その笑い顔にフェルは不 思議と憤りを感じなかった。ただ、納得した。彼もおなじように痛 いのだ、と。 村をうしない、家をうしない、母をうしなった。 ﹁もう、ここも安全じゃない。はやく逃げるんだ。いいね?﹂ ﹁︱︱︱︱﹂ ﹁つらいかもしれないけど、お母さんは置いていくんだよ﹂ 言い含めるように青年は言うと、脱いでいた兜をかぶりなおした。 そうすれば、もう見分けはつかずフェルは戸惑ってうつむいた。母 の体温はすっかりと冷え切り、フリジットの気候に似た寒々しさを つれてくる。それでも、周囲を取り巻く炎はあつくフェルをなぶり 続けている。 ﹁山間の捜索はしないと思う。ことがすむまで隠れるんだ﹂ ﹁また、ころしにいくの?﹂ 鈍く光る剣はまがまがしく、フェルの心をそいでいく。 ﹁⋮⋮わからない。でも、俺はもう殺したくないと思っているよ﹂ 疲れたように一笑すると、青年はもう一度フェルの頭をなでつけ 去っていった。 116 残されたのは動くことのない母と、立つ気力すら失ったフェルだ け。 かんまん かく乱をしにいったシグルが帰ってくる兆しはみえず、フェルは 緩慢に首をめぐらす。血痕さえみえなければ、母は眠っているよう だった。青ざめた顔も病におかされていたときから見慣れていたの で、よりいっそう感じられる。しかし、平時ならほんのりとともっ ていた温もりもなく、閉ざされた瞼は固い。その裏には虚ろな瞳が 光りなくおさまっているのだろう。 ︱︱きっと。 脳裏に響くのは甘くやさしい女性の声。 慰めるようにフェルを包み、励ますように笑ってみせた、そのひ と︱︱。 ﹁おねえちゃん⋮⋮﹂ 春を母と迎えたいと願った。フェルの未来を約束してくれたひと。 王もそれを望んでいると口にし、フェルの気持ちに寄り添った。 春がくる前に母をうしない、その痛みをわかっていたはずの彼女 しょうぜん は、いまどこにいるのだろう。一片のくもりもない笑顔をたたえて、 フェルのしらない場所にいるのだろうか。悄然とたたずむことしか れんびん できないフェルに、彼女はどんな言葉を落とすのだろう。叱責だろ うか。激励だろうか。憐憫だろうか。 いずれにせよ、フェルも同じになってしまった。 フリジットの冬は色濃く、春は遠い場所で立ちつくしている。生 命の芽生えを待つ前に、母の灯火は消え、まばゆいばかりの未来は 幻のように揺らいでいる。掴もうと手を伸ばして、すっかり腕が震 え、縮み上がっていることに気づいた。 ﹁︱︱︱︱っ﹂ 叫ぶようにフェルは息を吐いていた。獣の遠吠えのような声だっ た。 117 苦しくてたまらなかった。奪われた命も、未来もすべて。もとか らフェルのものではない幻だったことを、まざまざと見せつけられ た。あわれみのひとつもかけずに、略奪しつくしたものは、きっと どうこく 晴れやかな気持ちで春を迎えるのだ。そのことが苦しく、憎く、フ ェルは咆哮する。 それは、哀痛に満ちた慟哭だった。 せいひつ ひとり、母の遺体を抱いて泣き叫ぶフェルを、雲の切れ間からの ぞいた月だけが静謐に眺めていた。 118 第五話 春の足音 ﹁それで︱︱?﹂ フリジット王城内、重臣が困惑した顔を見合わせている中、会議 場では怜悧な声が響いていた。その冷たさに本来ならざわめく室内 も水をうったように静まっている。そのことを気にした風もなく、 ハンナは無表情に臣下を見下ろしていた。 オルコット領内の反乱が発覚し、事態の収束をはかりに行った兵 士が一夜明けて帰還した。 気がかりでろくに眠りにつけなかったハンナは、けだるい体をお して彼らを出迎えた。そして、絶句した。雪国のフリジットにふさ わしい銀白を模した鎧は血で汚れ、兵士の顔は沈み、重苦しい雰囲 気を漂わせていたからだ。隊長と思わしき人物が、ことのなりゆき をかいつまんで説明すれば、ハンナはさらに押し黙り、そのことが 起因し、朝議では冷ややかな口調になる。 ﹁わたしは、民の血が流れることは好まないと言った﹂ 落とされる言葉に反応を返すものはいない。そのことがハンナの 心中を揺さぶる。 湧きあがるものは、居場所のない怒りと、さまよい続ける後悔、 それから悲痛︱︱。 ︵あのとき︱︱。判断を任せなかったら︶ クライスは父の片腕として実権を握っていたときから、どこかつ かめない男だった。華美な生活の裏では不正を行っているであろう ことを匂わせていたが、けっして尻尾をつかませるようなことはな く、いつも綺麗に物事を片付けていた。そんな男が無様にも、捕ま えてくれと言わんばかりの失態を演じてみせた。 笑ってやりたい。しかし、クライスは狡猾な男なのだ。 ﹁本当なの? 反乱はなかったと?﹂ ハンナの嫌う部分をつついてえぐり、傷つけていったのだ。 119 失望させないで、とささやいたハンナに失望以上の惨事を見せつ けた。それほどまでに、とハンナは考える。クライスは父のことも 好きではなかったろう。そして、政治力ももたないハンナが玉座に つくことは、なによりも許せなかったはずだ。 ぎりっと唇を噛みしめて、こらえるようにたずねたハンナに、兵 士をまとめる老騎士バージルは淡々と言った。 ﹁口を割らした兵士によれば、村民に反乱の意思はなく、みな平穏 に暮らしていたと﹂ ﹁それで、その平穏に暮らしていた村民を手にかけて帰ってきたと ︱︱?﹂ ぶるりと拳が震える。恐怖からではない。これは、こらえきれな むこ い憤りだとわかっている。 無辜の民を惨殺せしめるほどにクライスはハンナのことが嫌いだ ったのだろうか。ハンナが民を憂えて一任したとき、クライスは胸 の中で笑っていたのだろう。あとに起きる惨劇を︱︱。それによっ て傷つくハンナを待ち望んでいたに違いない。 ﹁クライスはバージルの監視下に置く。ことの次第を話すまで外出 を禁じる﹂ ﹁︱︱承りました﹂ ほんとうは、地下牢にでもぶちこんでやりたい。 それでも、長きにわたってフリジットの政を支えてきた男には支 持者が多く、王たるハンナの実権でも無下に扱うことはできない。 バージルに忠誠厚い兵士が口を割らなければ、クライスは兵士の暴 走と、勘違いでことをすますつもりだったのだろうか。少なくとも、 ハンナの味方に立つものほとんどない。悔しさにうつむいたハンナ は、それでも口の端をあげてみせる。弱みを見せるわけにはいかな い。見せかけでも国の頂点に立つものとして、迷ったとしても、そ れを見せるわけにはいかないのだ。 ﹁バージル。お前の良心を信じている。よろしく頼むわ﹂ ﹁︱︱はい﹂ 120 ハンナにはバージルが裏切るかどうかもわからない。クライスと 通じていれば、近いうちに彼は姿をくらませてしまうだろう。不正 の証拠や虚偽の事実を隠したまま、永遠にハンナの前には現れない。 それでも、ハンナには信じることしかできないのだ。いまはただ、 父を支えてきた重臣を自分の臣下として信頼するしかない。 ﹁余ったものは事態の収束にあたって。村民の保護をはじめ、失わ れた物資の供給を主に実施してほしい。まだ冬は続く。寒波に倒れ るものもいるだろう。もしも︱︱﹂ 脈動はあつく、猛りくるっている。ハンナの心中もまた穏やかで はない。 ﹁民の命を軽んじるようなことをすれば、雪の上に寝転がるのはあ なた達のほうかもしれないわね﹂ ああ、とハンナは息を吐いた。 こんなにも鼓動は早く、あつく打っているというのに、空気は寒 い。きっと臣下が見上げたさきには冷ややかな顔をしたハンナがい る。その内に燃え盛る炎が渦巻いていることに、いったい誰が気づ くのだろうか。嘲笑するようにくつりと口の端で笑うと、ハンナは 水を口に含む。 冷たい水が喉をうるおし、少しばかり炎を弱めた気がした。 ﹁知恵のない小娘と侮らないで。これでも、一国を背負う覚悟はし ているつもりよ﹂ 父から譲り受けた国という感慨はもうない。 ハンナ自身がこの国を愛し、生活をいとなむ民を愛している。 他でもない。ここはハンナの国。 冬が長く、厚く雪に閉ざされ、色彩は少なく、生命の脈動は弱い。 それでも、短い春の美しさ。一瞬の生命の発芽と輝き。長く耐え たからこその最上の喜びをもって春を迎えるからこそ、フリジット の民は雪に覆われても強く生きている。閉ざされていてもなお、そ こに居座ろうと思う魅力を、フリジットはもっている。 その冬が、耐えられないほど痛く冷たいものだったとしたら、民 121 はどうするのだろうか。 閑散とした会議場でひとり残されたハンナは、ひっそりと瞼を下 ろした。 平時なら温かく迎え入れてくれるガイルがいる書斎も、いまは凍 てついた空気に覆われ、重苦しい雰囲気が漂っていた。ハンナがか いつまんで話したことの次第を耳にするなり、ガイルは黙り込んで しまい、ハンナもそれにならって口を閉ざせば、書斎は静まり返っ た。 帰還した兵士の多くは、民が抵抗を示したと口をそろえて言う。 しかし、バージルの側近にあたる兵士はオルコット領内で反乱があ ったことすら認知していないとこぼした。反乱がほんとうにあった のか、それともなかったのかもわからず、ハンナの頭は揺らぎ困惑 している。クライスは強かにも、バージルに近しい兵士を編成に組 み入れることはなかった。あの村でなにが起こったのかを、ハンナ は空想するしかない。 ﹁やっかいなことになりましたね﹂ ﹁わたしの未熟ゆえだわ。クライスに任せたのが間違いだった﹂ ﹁起こってしまったことを悔いてもはじまりません。対策のほうは ?﹂ ﹁とにかく、生き残ったものの保護を優先的におこなうことにした わ。まだ冬だもの﹂ 大雪が去ってから安定した気候が続いているとはいえ、夜間には 身をきる寒さが襲う。 報告では民家の大半が焼け落ちたらしく、村民は寒空の下で丸ま っていることしかできないはずだ。道が途絶えて孤立していたこと もある。暖を取るための燃料の備蓄も十分とは思えなかった。兵士 の中でもとりわけ足の速い馬をつかって物資を輸送したものの、は 122 たして足りるのかどうか。混乱の中では、どれくらいの村民が生き 残ったのかもわからない。 ︵フェル⋮⋮シグル⋮⋮︶ 母と迎える春を待ち望み、王であるハンナに祈っていた少年と、 不器用ながらもそんな彼を支え続けていた青年。ふたりの姿が瞼に こびりついたように、ちらついて離れようとはしない。どれほどの 惨状なのだろう。ふたりは無事だろうか。最悪の想像にいきついて は、ハンナは頭を振ってかき消した。 ﹁ガイル。しばらく、城をあけるわ。代役をお願い︱︱﹂ ﹁ハンナさま?﹂ 怪訝そうに視線をよこすガイルにハンナは眉尻を下げた。 ことの次第はけっして安易なものではなく、ハンナが玉座をあけ ることの危険性は承知している。けれど、どうしても知り合ったふ たりの安否が気がかりだったし、なにより自分の目で村の現状を見 ておきたかった。ハンナの判断ひとつで、壊滅状態に陥った。いわ ば、失策の犠牲となった村。そこにはハンナが庇護するべき民たち が寒さに震えている。 ﹁すこし村に行ってくるわ﹂ ﹁危険です。いまは民たちの気も荒立っているのですよ!﹂ ガイルの静止を気にもとめず、ハンナは厚手の防寒具を手に取っ た。 ﹁平気よ。まだ立志式もとりおこなっていないもの。だれも王の顔 など知らないわ﹂ 父の喪に服すため、一年のあいだ行政は動きをとめていた。 ハンナが玉座についてからも、臣下が政をとりおこない、ハンナ は立志式のまえに書斎に閉じこもるようになった。王として民に顔 を披露したこともなければ、そういった式典でたいそうな儀礼句を 述べたこともない。ハンナの顔はいまだに臣下︱︱とくに重臣たち にしか覚えられていない。 防寒具を身につけて、にっこりと笑ってみせたハンナにガイルは 123 苦笑した。 ﹁あなたはときどき、ひどく頑固になられる︱︱﹂ ﹁あら? もしかすると、先生に似てしまったのかしらね﹂ ちんうつ 悪戯っ子のように軽口をたたいて見せると、ガイルは虚をつかれ たように口を閉ざしてから、吹きだすように大笑いをした。沈鬱と していた空気がガイルの笑い声にかき消され、いつもの書斎独特の 温もりが戻ってきたような気がする。 ﹁言うようになられた。しかし、お早いご帰還を願います。あなた の立場はいま非常に危うい﹂ ﹁わかってるわ。大丈夫。彼もつれていくから﹂ 灰色の髪をもったハンナの腹心︱︱アルクゥは書斎のまえで待っ ているはずだ。 事態の収拾に追われるハンナを横目で見ては、なにか言いたそう にしていたが、落ち着いて話すこともできずにハンナは出立しよう としている。それでも、アルクゥは臣下としての分をわきまえるよ うにはなったと感じる。それが嬉しくもあり、また一定の距離を置 かれているようで寂しくもあった。ハンナがひとりで書斎にいると きは、遠慮なく居座ってはいるが、ガイルやほかのものが立ち入っ た話をするときは、なにも告げず席を立つ。 ハンナもアルクゥもお互いに公私の混同はしないつもりだ。 ︵わたしだけ、寂しいなどとこぼしてはいけない︶ 王として踏み出すと決めたのはハンナだ。アルクゥはそんなハン ナを認めて忠誠を誓い、臣下として仕えることを決めた。客人とし て扱うわけにもいかず、特別扱いするわけにもいかず、すこしだけ 開いた距離を埋めることもできずに、お互いの正しい距離感で接す る。ハンナが望み決めた結果なのだ。自分が弱音を吐くことはでき ない。 だから足元をうすら寒い空気が通っても、ハンナは前を向いて、 王として踏み出すのだ。 124 2 ◆ ﹁寒くはないか?﹂ ﹁平気よ。あなたこそ、また帽子を被ってないわね﹂ ﹁仕方ないだろ。あれ、すごく気持ち悪いんだ﹂ 王城から馬車を使いオルコット領内に入ると、ふたりは注目を避 けるために馬車をおりた。 突き刺すような寒気に身震いすると、アルクゥがひと声かけてく る。それに返事をしながら、ハンナはアルクゥの軽装に口をとがら せた。本人は苦痛を感じていないものの、傍で見ているハンナから すれば、アルクゥの姿はじつに雪国にふさわしくない。ドラゴンの ときならまだしも、アルクゥはいま生身である。その体を覆ってい るのは防寒服のみだ。厚い鱗などではない。 村に向かう街路で言い合いながら歩むふたりは、村の様子がうか がえるようになってから閉口した。鼻孔をくすぐるのは、焼け焦げ た臭気。目を奪ったのは焼け落ちた家屋と、絶命した村人たちを搬 送している兵士のすがただった。 ハンナの指示は的確に伝わったらしく、兵士たちはせわしなく動 いている。それにも関わらず作業が停滞しているのは、白銀の鎧に 恐怖をあらわにし、石つぶてを投げつける村民が少なからずいるか らだろう。復興作業にあたっている兵士を遠巻きに眺めている人々 が多数をしめ、協力的なものたちは見当たらない。誰もが不審そう に気味悪そうに兵士を見つめている。 ﹁ひどい状況だな。どうする?﹂ ﹁そうね。とりあえず、それとなく話を聞くわ﹂ シグルやフェルの安否も気になる。 するりと村の入口をすりぬければ、フェルが作っていたはずの雪 125 だるまも見当たらなかった。熱風でとけてしまったのだろう。残骸 のように木の枝が残されている。それも踏み荒らされたのか粉々に 砕け散ってしまっていて、ハンナは少しばかり眉をひそめた。 生き残った村民は広場のようなひらけた場所に固まって暖をとっ ていた。防寒具をきっちりと着こみ、体を震わせて火に近寄ってい る。ときおり、炎がはぜれば誰ともなく肩をはねて身を引いた。お そらく、村を襲った業火を思い出しているのだろう。ハンナはアル クゥを引き連れて彼らに近寄り話しかけてみる。 ﹁あの︱︱﹂ ﹁︱︱なんだい﹂ 疲弊しきった男は返答するのも億劫そうに口を開いた。 ぼろのような防寒具に隠れるように担がれた猟銃が目を引き、ハ ンナは体を強ばらせる。猟をしてきたという風情でもなさそうだっ たので、それを所持している理由に行き当たり、胸がきしんだ。沈 黙を落としたハンナを不思議そうにみやった男は、後ろにいたアル クゥを見てぽかんと口を開いた。 ﹁あ! あんた、この間の︱︱じゃあ、嬢ちゃん。酒場にいた子か﹂ 酒場︱︱おそらく、シグルに案内された場所のことだろう。 ていかん 目の前にいる男は疲労を色濃く残しているが、どうやら酒場にい た猟師たちのひとりらしい。 ﹁驚いただろう。村がこんなことになっちまってて⋮⋮﹂ せきりょう 苦笑するように、男は口端をあげた。ぎこちない笑いには諦観と 寂寥がつのり、ハンナはどのように返していいのかわからず、あい まいに笑んでみせる。きっと、あの酒場も燃えてしまったはずだ。 残っていれば村民はそこに集まって暖をとる。このような寒空の下 で身を寄せあう必要はないはずだ。 ﹁シグルたちも無事だ。会ってやってくれ﹂ ﹁︱︱⋮⋮よかった。どこにいますか?﹂ ふたりの無事を聞かされ、そっと胸をなで下ろしたハンナは嬉々 としてたずねる。 126 ﹁子どもたちは、屋根のある場所にいるんだ。︱︱あっちだよ﹂ 男の指さした方向にはかすかに建物らしきものがみえる。 業火の中で形として残ったものを補強して、体力のない老人や子 ちんつう どもに積極的に使用させているらしい。そのため、外で暖をとって いるものも多くは若い男女だった。だれもが沈痛している中でも、 心配りを忘れていない。このような村が反乱をたくらむということ は、考えられないように思えた。 ハンナとアルクゥは男に礼をいうと、すぐに建物に向かった。 近寄ってみれば、傾いてはいるものの基礎はくずれていない民家 がある。真新しい木材で補強されているものの、崩れ落ちても不思 議ではない見た目だった。中に踏み入ることにためらって右往左往 していると、ふいに声がかかる。 ﹁おまえ︱︱﹂ ﹁ああ! シグル! よかった。無事だったのね﹂ 配給された食糧を担いで立っていたのはシグルだった。まえに会 ったときと同じように少しばかり険がつよい顔立ちには、疲労はみ てとれない。重そうな物資を持っていても微動だにしていないとこ ろをみると、やはり猟を商いにしている強さをみせていた。 ﹁どうしてここに︱︱。まあいい。ちょっとどけてくれ﹂ ハンナが場所をあけると、シグルはずかずかと屋内に入っていく。 中からは嬌声と感謝を告げる女性の声がもれ聞こえてきた。どうや ら、子どもたちとその母親は、この場所で身を寄せあっているらし い。不安定な家屋を見つめて、ハンナは家屋の修繕も優先しなけれ ばならないとひとり頭をひねる。 やれやれという風にでてきたシグルは肩を回しながら、ハンナた ちへと話しかけた。 ﹁悪いな。みんな気落ちしているから、動かないといけないんだ。 男はほとんど︱︱その⋮⋮いなくなっちまったから﹂ ﹁ええ、そのようね。反乱があったと聞いたけど?﹂ ﹁︱︱反乱?﹂ 127 ハンナの問いにシグルは眉根をよせた。 ﹁俺たちが?﹂ ﹁そうよ?﹂ ますます訳がわからないという顔をしたシグルは、しばらくして どこか納得したように息をこぼした。 ﹁俺たちは大雪が終わってから食糧を確保しに山に入った。穴があ いた家屋もあったから修繕するための木材もとっていたし、反乱な んてしている暇はなかったよ。⋮⋮でも、それで納得いったよ。と つぜん、王都の騎士たちが軍勢率いてやってきたのはそういうこと か﹂ ﹁反乱を起こしたわけではないのね? それを話したの?﹂ ﹁当たり前だろ。それで一度は下がっていったんだ﹂ その話はハンナにとって初耳だった。 村に踏み入った兵士は、村民の抵抗にあい、やむなく武力を行使 したと主張している。反乱の兆しがないことを知り、兵を引いたと いうことは、彼らはそのあとにもう一度、村に踏み込み民を惨殺せ しめたということになる。その報告はハンナのもとにはあがってき ていない。 ﹁じゃあ、どうして︱︱?﹂ ﹁それが、男連中が山に入っている間にやってきたらしくてな。俺 が戻ってきたときには、もう火の手があがっていたんだ。みんな、 えらく動揺していたし混乱もしていた。俺はフェルを見つけてかく まうので精一杯だったよ。応戦した男たちの大半は返り討ちにあっ たし︱︱﹂ 詳しいことはわからないと首を振り、シグルは小さめの袋を持ち 直した。おそらく大袋に入っていた食糧を小分けにしていれている のだろう。中にフェルがいるならシグルがともに引き連れてきても おかしくはない。おそらく、その袋の中にある食糧はフェルのもの だ。 ﹁あ、そうだわ。⋮⋮フェルは?﹂ 128 ﹁ここにはいない。こっちだ﹂ シグルは先頭にたってハンナたちを誘導しはじめた。 さきほどの広場を抜け、村から離れた場所にひっそりと隠された けもの道にはいる。そこから道なりに進むとひらけた場所にでた。 そこにも家屋が存在したが黒焦げて焼け落ちている。シグルはその 家屋すら通り過ぎ、こぢんまりとした小屋にふたりを案内した。乾 いたわらや牧畜の用具が置かれているようすを見るに、どうやら牧 舎のようだ。しかし、中に家畜のいる様子はなく、わらと毛布にお おわれた山がひとつあるだけ。 シグルは当たり前のように、その山に言葉をかける。 ﹁おい、フェル。起きてるか?﹂ ﹁︱︱⋮⋮ん﹂ もぞりと山が動いて顔をのぞかせた空色の瞳をまたたかせるフェ ルだった。 ぼんやりとした視線がシグルの顔をなぞり、その手元にある食糧 を認めると、さらに揺れ動いてハンナを映した。そこで焦点が定ま ったのか二度、瞳を開閉してから体をもちあげる。わらに包まれて いたせいか髪には数本のわらごみがついており、ハンナは思わず微 笑した。 ﹁よかった。大きな怪我はなさそうね。︱︱おはよう、フェル﹂ ﹁あ︱︱⋮⋮お⋮⋮﹂ フェルはそろりと視線を動かしながら言葉をさがしているようだ ったが、口からでるのは吐息にも似たかすかな音声のみで、ハンナ の耳を揺らすにはすこしばかり覇気がなかった。それでも、言葉を 待つハンナにシグルはバツの悪そうな顔で言う。 ﹁悪い。フェルは、その、ショックで喋れないんだ﹂ ﹁⋮⋮どういうこと?﹂ 外傷はなく、防寒も可能なかぎりできているようで皮膚に変色は でていない。栄養もシグルが持っている食糧ぶんは確保しているの だろう。極端にやせ衰えているようにも見えなかった。 129 首をかたむけ疑問をぶつけるハンナに、シグルはぎゅっと眉をゆ がめた。 ﹁母親を︱︱失ったんだ﹂ だれともなく息をひそめる音が耳につく。 あい ひそやかにとめていた息を吐きだしてハンナはこわごわとフェル を見やった。 せつ やせてもおらず、発狂してもいない。ただ静かなたたずまいは哀 切を含んでいるようにも思えた。空をくりぬいた瞳はいまなお輝き をまし、ハンナをひたりと見据えている。 ﹁⋮⋮そうだったの﹂ ハンナの落とした呟きを最後に、あたりは静寂に包まれた。 どのように言葉を発していいものか考えあぐねているうちに、シ グルは袋をあけてフェルに食糧を手渡している。母親をうしなった ショックで食欲がないというわけでもなさそうで、フェルはただ機 械的に食事を取っていた。それを観察するように眺めるシグルもま た、痛ましさを感じさせないほど平然としている。 ハンナはひとり︱︱拳を握りしめてたえるしかなかった。 いますぐに、自分が王なのだと暴露して、ふたりのまえに頭を垂 れたかった。 フェルはハンナの政権で唯一、春をのぞんでいた子だった。いつ かくる春を切望し、母親と迎える日を心待ちにして祈っていたとい う。それを叶えてやりたいと、ハンナはそう遠くない過去に誓った。 しかし、誓いは果たされることなく無残に破れさったのだ。ハンナ の未熟さがうんだ悲劇のもと、フェルの母親は生命の脈動をとめて しまった。 震える唇はなにもつむぐことはない。ただひっそりと息を吐く。 背後で揺れるアルクゥの瞳だけが、ハンナの弱さをとらえている ように感じた。 130 3 ﹁大丈夫か?﹂ ﹁⋮⋮大丈夫そうにみえる?﹂ ﹁いや、みえないな﹂ 冗談がきついわとハンナはこぼすように告げた。 シグルたちと別れて村を回っていたハンナは、ひとがいない場所 で休憩していた。 村民の遺体が安置されている場所。物資が集められている場所。 さまざまな場所をめぐって話を聞き、ハンナはひとつ確信した。 ここでは、反乱など起きていない。大雪のあと、枯渇した食糧を集 め、家屋を修繕するために山に入っているのが大半で、反乱などし ている暇などない、というのはシグルの言葉だった。そのとおり、 村のだれからもそのような情報しか得られず、当事者であるものた ちが反乱をしらない。反乱の噂を耳にして納得するものもいれば、 やりきれない想いに涙し怒るものもいた。 ﹁やはり、兵は一度引いてから戻ってきているのね﹂ ﹁変だよなあ。反乱がなかったんだから、王都まで引き返せばいい のに﹂ 反乱の鎮圧はクライスに一任していたため、兵の選択もクライス 本人がおこなっただろう。バージルの下についている兵士をいれな いあたり、兵士の多くはクライスの息がかかっているに違いない。 おおもとの隊長はすでに自害をはかり、口を割らすことはできず、 一兵卒になれば詳しくはしらないと口を閉ざすばかりだ。やはり、 あの隊長を存命できなかったことは痛い。 クライスからの直接的な指示があったと証明することもできず、 事態は自害した隊長が起こした惨劇という話でまとまってしまいそ うだ。そうなればクライスの監視をといて、また王城に迎えいれる ことになる。ハンナは歯がみしながら、悔しがる。 131 ︵この際、適当な理由をつけて辞めさせようか︶ 反対はもちろんでてくるだろう。しかし、今回の不行き届きを盾 にして重要な立場から移動させることは可能なはず︱︱。そこまで 考えてから、ハンナは軽く首を振った。いまは、事の収拾が先決だ。 クライスへの処罰はそのあとに考えればいい。 ﹁とりあえず、王都に戻りましょう。優先しなければならないこと は、だいたいわかったわ﹂ ﹁わかった。馬車のところまで戻ろう﹂ ﹁ええ︱︱。なにかしら?﹂ さざめきのような怒号が届いたのは、休憩していた場所から腰を あげたときだった。 アルクゥをみれば同じように首をかしげて、声のするほうへ顔を 向ける。方向からすれば、暖をとっていた人々がいた広場のようだ。 ハンナは軽く雪をはたいてから、足早に喧噪へと向かっていった。 広場にはあきらかに暖をとるのが目的ではない人々があふれかえ っていた。隠れるように息をひそめていていたときにはわからなか ったが、生き残った人たちは数多くいたらしく、小さな広場は埋め つくされている。その中心で、怪我を負いながらも怒声を飛ばして いるのは大柄な男だった。手には猟銃を持ち、不安げに視線をさま よわせる人々に怒鳴り散らしている。 ﹁︱︱立ちあがるんだ!﹂ 男の言葉に呼応するように声があがる。 どうかつ 兵士たちがいさめようと間にはいっては、肩をどつかれて転ばさ れる。あげくの果てには剣をとりあげ恫喝し、兵士を村外へと追い たてるものもいる。兵士の多くは抵抗をみせたが、彼らの鬼気迫る 様子に口を閉ざして、ひとり、またひとりと村外へとでていった。 ハンナは目を丸くし事態を一目すると、怖がるように身を縮めて いた女性に声をかけた。 ﹁あの、いったいなにが?﹂ 132 ﹁それがねえ。どうにも、王が反乱を疑って兵をさしむけたらしく て︱︱﹂ 困ったように女性が眉尻を下げた瞬間、ひときわ大きい歓声が広 場を包んだ。 ﹁見せてやろうじゃねえか! 俺たちのほんとうの反乱とやらをっ !﹂ そうだと呼応する声は嵐のように猛り、ハンナの耳を焼いていく。 ハンナは思わず広場の中央に身を躍らせた。木材を大雑把に組み合 わせた台の上で演説していた男は、目前に転がりでた小柄なハンナ に目をまたたく。しかし、すぐに剣呑な色をのせて唇をとがらせた。 ﹁なんだ、お前は﹂ ﹁今回の惨劇は王の一存ではないわ! 王はご存じなかったのよ!﹂ そうだ。ハンナは知らなかった。 反乱などなく、クライスがたくみにくるんだ罠におどらされた。 それでも、ハンナは民の命が軽んじられることを願ったわけでも、 望んだわけでもない。むしろ、民の命を保護しようと命令を下した はずだった。相手がハンナをおとしめようとさえしていなければ︱ ︱。 必死につむいだ言葉は、男の怜悧な瞳に気圧され、周囲に満ちる ことはなかった。だれもがハンナを不審な目つきでみやる。 ﹁なぜ、そう言える? お前、王の知己か?﹂ ﹁わ、わたしは︱︱﹂ 王自身である、とは口にできない。 迷いながら言葉を探すハンナに焦れたのか男は台の上からおりる と、ずかずかと歩み寄ってきた。不穏な空気を察したアルクゥが男 をとめるより早く、ハンナの胸倉を片手でつかみあげる。喉元がし まり息もたえて、ハンナは顔をゆがめた。烈火のような男の眼差し に胸中が焼けただれていく。そこに揺らぐのはおさえることのでき ない怒りだった。 ﹁ふざけやがって!﹂ 133 せいひつ ふりあげられる拳を甘んじて受けいれることを覚悟して、ぐっと 口を引き結ぶ。 ﹁︱︱待ってくれ﹂ 周囲の熱気をかき消すように落ち着いた静謐な声が届く。 腕をふりあげたまま固まった男は、いつもと変わらない無表情で たたずむシグルに視線を向ける。ほとばしるような眼差しにも反応 をみせず、シグルはハンナに歩み寄ると、胸倉をつかみあげていた 手をふりほどいた。すぐに寒気に似た空気が肺をみたし、ハンナは 安堵の息をつく。しらず恐怖していたのか、手のひらはびりびりと しびれていた。 ﹁とめるなよ。この女、王をしっている風だぞ﹂ ﹁俺の友人なんだ。王都で生活してる。口が過ぎたことは謝るよ﹂ シグルは淡々と周囲をいさめるように言葉を落とすと、ハンナに はあきれたように言った。 ﹁あまり刺激するようなことはいうな﹂ ﹁でも⋮⋮。ねえ、あなた達、なにをするつもりなの?﹂ 広場に集まっている面々をみれば、武器をたずさえているものが ほとんどだった。 それこそ、反乱を起こしかねない不穏な空気がただよい、熱気に あてられたものたちは遠巻きに彼らを見ている。その中でも興奮さ めやらぬといった風の男は、ハンナを高圧的に見下ろして鼻で笑っ た。そこには、ハンナをまざまざと嘲笑う感情がやどっている。 ﹁王に俺たちのほんとうの反乱を教えてやる。こっちは我慢の限界 なんだ!﹂ ﹁また、死者がでるわ。むやみに血を流すことは得策じゃない﹂ ﹁血ならとっくに流れた! 見ろ!﹂ ﹁︱︱⋮⋮っ﹂ 男は乱暴に布を取り払うと、生々しい傷口をハンナに見せつけた。 男が激しく動いたせいか傷口は開いて赤い血が流れでている。それ が腕を伝って雪に落ちると、じわりと染みていく。 134 血は流れた。この男のだけではない。村民の多くは血を流し、そ して倒れふした。 だからこそ、ハンナはこれ以上、血を流させたくないと思ってい た。それでも、彼らの中にはやむことのない激情がせめぎあい、わ きたつ憤りはその手に武器を取らせるのだ。彼らをそのようにかり たてたのはクライスであり、ハンナでもある。立ちつくすハンナの 心中を察するものはおらず、ひとりハンナはうつむいた。 喧噪の中に覆われるようにハンナは口を閉ざしてなりゆきを見守 った。男に呼応するものは多く、とめるものはいない。すこしばか どうけい り疲れた表情をしたものたちは、彼らを困惑したように見つめてい たが、その瞳には憧憬がうかがえ、心根は彼らに寄り添っていると いってもよかった。ただ、ハンナとアルクゥだけが取り残されたよ うに熱気にあおられている。 ぼんやりとした視界で、シグルが彼らに近寄るようすがわかり、 ハンナは思わず引きとめていた。手を引かれたシグルはおどろいた ようにハンナを見つめ、そっと視線をそらす。信じられないものを みるようにハンナは瞠目した。 ﹁シグル。まさか、あなたも︱︱﹂ 武器を手に取り、王都へ乗り込むのかと。すがるように掴んだ手 をシグルは払ってみせる。 ﹁︱︱⋮⋮悪い﹂ その一言の重さを、ハンナはきっと忘れないだろう。 シグルが落とした言葉の重みは、ハンナがおかした罪の重さだ。 不器用でもやさしくフェルを思いやる青年に、自分は武器をとらせ てしまった。断罪したいと思わせるほどの憎しみを抱かせてしまっ たのだと、そう思うほどに胸が苦しく圧迫される。 悲しみとも、悔しさともちがう。ただ、ぽっかりと空洞がうまれ たようだった。 ︵ああ。もう、たてない︶ 民のために国を治めようとした。すべてがくつがえされた。 135 足元はおぼつかず、大地についた足は幻のように揺らぐ。目前の 喧噪はとおく、シグルの背中もまた遠ざかっていく。ぼやけた視界 の中にまじってなくなる瞬間、ハンナの足は支えをうしなってよろ けた。 無駄だったのだろうか。すべて︱︱。 ﹁ハンナ!﹂ ﹁⋮⋮あ、アルクゥ﹂ ﹁大丈夫かよ﹂ ハンナの背中を支えるように手をまわし、心配そうに顔をのぞく 姿に、ハンナの虚ろな瞳が輝きを取り戻す。力をうしなった四肢に も血流がはじまったように感覚が伝わってくる。どうにか自分の足 で体勢をたてなおすと、アルクゥに礼を述べた。まだすこし、宙に 浮いているような不可思議な感触は残っている。 ﹁⋮⋮帰りましょう﹂ ﹁お、おう。わかった﹂ 怒号は耳に新しく、ハンナを責めたてる。 ︵まだ、だいじょうぶ︶ 民のために動ける。いまはまだ、支えてくれる手が残っている。 ︱︱まだ、王として立っていることはできる。 136 4 ◆ 王城に帰るなり、ハンナは書斎に飛び込んだ。紅茶を飲んでいた ガイルはハンナのただごとではない様子に、即座に顔をひきしめて 話を聞いてくれた。村で起こっていたこと、これから起ころうとし ていることを包み隠さず伝えると、ガイルは頭を抱えてしまった。 ﹁なぜ、そのようなことに︱︱﹂ ﹁あいつらの様子じゃ、すぐに王都まで来そうだったな﹂ ﹁︱︱ふむ﹂ ガイルは疲弊しきって口を閉ざしているハンナにひとつ笑み、思 わぬことを口にした。 ﹁では、ハンナさま旅路の支度をいたしましょう﹂ ﹁⋮⋮ガイル?﹂ 旅などとのんきなことをしている場合ではないと怒りそうになっ て、ハンナははたと気づいた。ガイルがいいたいこと、行おうとし ていることに気づいて、しらず眉根がよる。気難しい顔をしたハン ナに、ガイルは苦笑しながらも言った。 ﹁ハンナさまのお顔は幸いなことに知られておりません。このガイ ルを、あなたさまの身代わりとしておつかいください﹂ ﹁⋮⋮それを、わたしが許すとでも?﹂ ﹁お許しください。あなたはここで死んではならない﹂ おおげさなほど、ふかく息を吐きだし、ハンナは瞑目した。 怖くないといえば嘘になる。いまだってこびりついたように怒号 が残っている。冬とは思えないほどの熱気に包まれ、ハンナに毒を はいた民の顔。苦しまぎれに謝罪を口にし、去ってしまった知己の こと。すべてが真新しく、ハンナに幻ではないことを告げてくる。 137 ゆっくりと瞳をあけたさきには、穏やかに微笑むガイル。そして、 アルクゥ︱︱。 ﹁なぜ、そこまでしてくれるの?﹂ ガイルはもとからクライスとおなじ、父に仕えていたものだ。ハ ンナに心酔し、忠誠を誓ったわけではない。そういった意味合いで は、実質的にガイルよりもアルクゥのほうがハンナに近しいといえ たが、長年の経験からハンナはガイルを支えにしてきた。父が残し た愛娘︱︱。その一言ではすまされないなにかが、ガイルにはある のだろう。 ﹁私は、償いをしたいのです。亡きベルモンドさまに﹂ ﹁父に⋮⋮?﹂ ﹁あの一杯のさかずき。その償いを︱︱﹂ ひゅっと喉に風が通り抜けたようだった。反射的に喉元に手をや ってハンナは息をひそめる。 母の死の間際はよく覚えていなくても、父のことはよく覚えてい た。まだ二年しかたっていない。父が、たった一杯のさかずきでこ の世を去ったことは記憶に新しい。歓談の中、父がかかげたワイン グラスのきらめきと、その中で揺れ動く真紅の液体。ためらうこと なく口づけられたそこには、溢れんばかりの悪意が満たされていた。 ︱︱毒だ。 倒れていく父のすがたも、引き裂かれんばかりの悲鳴も、よく覚 えている。 ﹁あれは、ガイルのせいじゃないわ﹂ 父の側近であったガイル。そしてクライスはあの一件からひどく 気落ちしていた。ハンナも両親をうしなったことで一年の喪に服し、 その間、内政は動きをとめてしまった。だれもが、父の死を悼んだ。 悪意を落としたものをのぞいて、フリジットには冷感がおとずれた はずだ。 138 ﹁私より、さきに死なせないと誓ったのです﹂ 真っ直ぐに見つめるガイルの目元にはしわが刻まれ、声もしゃが れている。 ずいぶん、年老いてしまったと思う。たった二年で、ガイルは老 せいかん 人と呼ぶにふさわしい見た目に変貌し、父やクライスと並んでいた 精悍な男のすがたは見る影もなかった。 普通の人間が、二年でそこまで様変わりするはずがないことをハ ンナは知っている。 つと走らせた視線のさきには白髪頭があり、つるりと丸みを帯び た頭部にはわずかな凹凸も見受けられなかった。そうして、視線を 固定したまま、ハンナは吐きだすように言う。 ﹁角も落ちてしまったわね﹂ 思いだしたことはわずかでも痛みをともなってよかったのだと考 える。思い出すことに意味があったのだとも。母の記憶と一緒にう ずもれていたものは、ハンナにとって役にたつものも含まれていた のだ。思い出の中で微笑む。あのハンナの笑顔をほめてくれた男に は、たしかに角が生えていた。アルクゥとおなじ、神に愛された証 があったはずだった︱︱。 ﹁⋮⋮覚えていらっしゃったのですか?﹂ ﹁いいえ。思い出したのよ。角は、どこへ?﹂ ﹁ベルモンドさまがお亡くなりになられたときに、ひとりでに落ち てしまいました﹂ 懐かしむようにガイルは頭を撫でさすった。それで、納得がいっ たのかアルクゥが言う。 ﹁どおりで、角つきにくわしいわけだ﹂ おなじ角つきならば、彼らのことにくわしくて当然だ。自分が歩 んできた物事を語るにすぎない。運命の相手に出会った感動も、ガ イルは経験している。ハンナの父を主として慕い、そしてうしなっ たのならば、そこに待ち受ける寂寥も理解しているのだろう。ガイ ルはちらりとアルクゥを一瞥してから、ひたとハンナに視線を戻し 139 た。 ﹁ハンナさま。私に角つきとしての役目をお与えください。どうか 償いを﹂ 償いとガイルは口にする。ハンナはふと目線をずらして棚をみや る。そこにはアルクゥが贈ってくれた万年雪がひっそりと置かれて いた。降りやまない雪のように、ガイルの心もまた、底知れない悲 しみと後悔が積もっているのだろう。やがて、ガイル自身をおおっ て、苦しさの中に閉じ込めてしまうのかもしれない。ガイルは許し を必要としているのだ。ハンナに許してもらうことで、父であるベ ルモンドに許されたいのだ。 角つきにとって主をうしなうということは、自身の死よりもおそ ろしいものなのかもしれない。もしかすると、ハンナはアルクゥを ガイルとおなじ道に追いやってしまうかもしれない。角がおち、老 衰し、理由もわからぬ傷心によって長いときを苦しめるのだ。そこ に謝意がうまれないはずがない。それでも、とハンナは唇をかんだ。 王であるためにハンナはアルクゥに寄り添うことを諦めた。閉ざ されたフリジットから逃げだすこともやめた。そんなハンナにアル クゥは臣下として支える側へうつることで寄り添ってくれた。けし て近しいわけでもないその距離を、ハンナはアルクゥにとらせてし まった。 だからこそ、ハンナは最期まで王としてあらねばならないと感じ る。 ﹁︱︱⋮⋮できないわ﹂ 不思議なほど静かで、張りつめた空気の音すら聞こえてきそうだ った。 ぴくりとも反応しないふたりに、ゆっくりと笑んで、ハンナは続 けた。 ﹁この国は美しいでしょう?﹂ ハンナが見るフリジットはすべてではないだろう。王城からのぞ む雪はどこまでも白く。気づけば雪片が窓をたたいている。その下 140 では忍耐と激情をもった民たちが寒気に負けず、動き働いて国を支 え、それによってハンナたちが行政を執り行ってきた。外界とは関 わりが少なく、春になれば行商が行きかう閉鎖的な国で、豊かとは いえない風土。 それでも、美しいとハンナは噛みしめるように口にした。 ﹁もったいなくて、あげられないわ﹂ 玉座の重さはいやでもしっている。そこに座る意味も、責務もわ かっている。逃げたいと思うときはあった。無力な自分を自嘲して、 書斎に閉じこもった。民の声も、期待もすべて投げ打って逃亡して も、ハンナは結局、国というものを捨てられなかった。 産まれ育った故郷ということもあったが、だれかに玉座をゆずる ことはしなかった。 すがりついた分だけ重くなる。軽くなることはけっしてない。 ごうまん ﹁この国も、民も、すべて。わたしのものだから﹂ 利己的で傲慢。そうあることが許されたのは、ハンナが玉座にい たから。 おりてしまえば楽になれた。それこそ、クライスにゆずってしま えばよかった。それでも、父が残したからという建前を武器に、玉 座を保持して、いままで王としてふるまった。ほかでもないハンナ が、王であることをのぞみ、そうあることを切望した。 民のため。国のため。父のため。そのどれでもない。 ﹁︱︱わたしは、この国を愛している﹂ 愛しているからこそ、添い遂げよう。 たとえ、後世に愚王として名を残すことになろうとも、最期だけ は潔く︱︱。 ﹁だから、あとのことはお願いね。混乱が起きるでしょうから﹂ ハンナのあとを引き継ぐものはいない。これからさきに待ってい るのは騒乱だ。 ﹁それが、わたしがあなたに与える償いよ﹂ 震えてはならない。落とす言葉もふるまう所作も、すべてに精神 141 を研ぎ澄ませる。 ﹁あなたにこの美しい国は、もったいないわ!﹂ 高慢に笑ってみせたハンナは、おどるようにくるりと回転してみ せた。唇がひきつらないように気をつけて、ガイルを視界にいれる と、彼は面食らったような顔をしていた。冷静でおだやかなガイル には見慣れない顔に、ハンナはくすりと笑いをこぼした。 きっと、大仰にふるまうハンナの心中を、ガイルはさとってしま うだろう。いくら、怖気づかないように叱咤しても、くずおれてし まいそうな手足は、立っているだけでも精一杯だ。これから起こる ことも、しなければならないことも、街灯のない闇夜の道を歩くよ うに手探りの状態だ。そこへひとりで踏み出し、決意するのはひど く怖い。 ガイルはゆるめていた顔をひきしめて、じっとハンナを見つめた。 心中までさぐる瞳に、ハンナは戸惑いながらはにかんでみせる。そ こに諦観は浮かんでいないだろうか。絶望は顔をだしていないだろ うか。ハンナはまだ、迷っていないわけではないのだ。ガイルがひ とたび、ハンナをつつけば泣き崩れてしまいそうで、ぐっと目を閉 ざす。そうすれば、さきも見えない暗闇がやってきて、ハンナの視 界を隠していく。 ﹁私は︱︱﹂ ようやく落とされた声はとても静かで低く、耳触りのいい音を奏 でている。ひらけた視界の中には明るさの中にぼんやりと、くしゃ りと笑んだガイルの顔が浮かんでいて、ハンナはしらずとめていた 息をゆっくりと吐きだした。肺の中は凍るように冷たいのに、こぼ れた吐息は熱く、ハンナをなぐさめる。 ﹁あなたの笑顔が、大好きでしたよ﹂ そこにいるのは、記憶の中にあった精悍さを思わせるガイルのす がただった。 ハンナの笑顔に春を連想し、好きだとのたまったあげく、笑えな くなったハンナに笑ってほしいと望んだ。ハンナを見捨てることな 142 く教育をほどこし、支え続けたひとは、ようやっと寄り添うことを やめたのだ。温もりが離れることはさびしくつらい。 けれど、ハンナはゆっくりと溢れんばかりの笑顔をガイルに向け た。 彼が好きだと言った春を思わせるひだまりのような笑顔を、最期 に残したかった。 143 5 ◆ 許してほしいと望まれたから、すべてを許そうと思った。 目前のきっちりと磨きこまれたテーブルには高価な茶器に注がれ た紅茶が湯気を立てている。質素でも華美でもないセンスのよさを 感じさせる茶器には、これまた品のいい茶葉が使われているのか、 かぐわしい香りがハンナの鼻をくすぐった。警戒しているというこ とを隠しもしないハンナに、正面に座っていたクライスは嘲笑する ように言う。 ﹁毒などいれていませんよ﹂ クライスの屋敷にある応接間は家主の性格を反映しているように、 きっちりと整理整頓がほどこされ、磨き上げられた家具たちがラン ちんうつ プの明かりを反射している。真夜中ということもあり、暗く落とさ れたランプはふたりの顔に影をつくり、沈鬱な雰囲気をかもしだし ていた。じっさい、ハンナはここにきてから押し黙ったように固ま りつづけていて、出迎えたクライスがぽつぽつと話す声しか届いて こない。 ﹁⋮⋮そんな心配していないわ。父が好きだった紅茶にあなたが毒 をいれるはずないもの﹂ ようやく口を開けば、張りついたように喉がかすれ、気弱な声が もれる。それをたいして気にしたようすはみせず、クライスはほう と感心するような色合いをみせた。 朝になれば、武器を持った村民がやってこないともかぎらず、ハ ンナは城を抜け出してクライスの屋敷にやってきた。夜更けにおと ずれたハンナをクライスは驚きとあきれをもって丁重に迎え入れて くれた。甘んじてそれを受け入れたハンナは、美しい装飾がほどこ 144 された屋敷をぐるりと眺めながら、こうしてクライスと対面したわ けである。 ﹁︱︱あなたを国外追放するわ﹂ 紅茶に口をつければ、かすかに甘く舌をさわり、すっきりとした 後味をのこす。父が好んだ紅茶はハンナにとってはすこし大人向け の味わいで、あまり好みではなかったが、クライスのてまえ素知ら ぬ顔で飲み下すしかなかった。 さらりと告げた言葉にも、クライスはおおきな反応をしめさず、 ただ一言。 ﹁やはり、あなたは甘い﹂ そうこぼしただけだった。 そこには、ハンナをあざける意図もなく、感情もないように思え た。だからこそ、ハンナもまた素っ気なく、﹁そうね﹂と返すほか なく、静かな沈黙がふたたびおりようとしていた。 ハンナにとって対面して話したことがあるのはガイルとアルクゥ だけで、ほかの臣下とはこうして真正面に話したことはなかった。 すくなくとも、あのふたりを除いた最初の人物がクライスになると は想像もしていなかったし、あとわずかな時間を彼に割こうとは考 えてすらいなかった。それでも、こうしてクライスと話しているの は、純然たる事実だ。 そこには、クライスと話す価値があり、意味がある。 ﹁あなたは、わたしが嫌いなの?﹂ ﹁︱︱まさか﹂ じっとりと見すえながらたずねると、肩をすくめながら返される。 予想していた反応に、ハンナはくすりと笑ってみせた。 ﹁そうよね。あなたはわたしが嫌いなわけじゃない。父以外の王が 嫌いなのよね﹂ クライスの上に君臨していた王はただひとり。ハンナの父である ベルモンドだけ。 玉座がほしいなら、このような回りくどく危険な手段を用いずと 145 もよかった。それこそ、父を死にいたらしめた毒でハンナを葬って しまえばよかったのだ。クライスほどの男なら、証拠など残すはず もない。それでも、彼はしなかった。いや、父を苦しめた毒など、 クライスがいちばん嫌っているものだろう。使うはずもない。 ひとり納得していたハンナに、クライスは挑発するように鼻で笑 う。嘲りをふくむ不穏さにハンナは片眉をつりあげてクライスをみ やった。几帳面で神経質な彼にしては無作法で悪意のこもった所作 だ。その口から滑り落ちる音も、真っ黒な色をしている。 ﹁私が嫌いなのは、愚鈍で間抜けな民たちですよ﹂ ハンナの耳に痛く、突き刺さるような色を残してから、クライス は紅茶を口にした。 ﹁︱︱なぜ﹂ あぜんとして落としたハンナの言葉にクライスは目線をそらした だけで返答はすることなく、また静寂がふたりを包み込もうとして いた。ハンナとクライスしかいない応接間は無駄に広く、音が反響 することはない。音源であるふたりが言葉をなくせば、しびれるよ うな静けさがやってくる。そこには温度もなく、色もない、無だけ がじわりじわりと広がっていく。 ﹁たったひとつのさかずき︱︱﹂ ﹁え?﹂ ﹁たったひとつのさかずきであの方はいなくなった﹂ ぽつりと語りだしたクライスに、ハンナは声をかけようか迷い、 口を閉ざした。 ひせん ﹁聡明なひとだった。民を思いやり、臣下に平等な機会をあたえ、 人望も厚かった。卑賤の身でありながら、私がここまでのぼりつめ たのも、ひとえにあの方が等しく見ていてくださったからに他なら なかった﹂ たしかに、父は立派なひとだった。 いまフリジットを支えている領地制はベルモンドが提唱し、実施 したものだ。領地を区分し、領主をすえ、税率を取り決める。それ 146 は人口が増えれば領主の利益が増える図式になっていて、統治して いる場所が発展すればするほど、そこを治めているものも豊かにな る政策だった。逆に民を苦しめて搾取すれば、そのぶんほかの領地 に民が流れ、一時的には裕福になるものの、持続性はうすくなる。 そんな政策の中、クライスは不正をおこなった。利益などないこと は、父の片腕だったのだから、明確にわかっていただろう。それで も、民を虐げた。虐げたくなるほど、民を憎んでいた。 愚鈍だ、とクライスは言う。ハンナが激情と忍耐をもちすばらし いと称賛する民を、クライスはこともなげにけなしてみせた。父の ことが民を虐げる理由だというならば、ハンナは否定しなければな らない。けれど、舌の根は凍りついたように動かず、言葉はうまれ なかった。 ﹁あの方は、シーナ様をうしなって変わられた。あなたを慈しむよ うになった。政務の時間を割いて、民に傾けていた愛情をあなたに そそいだ。そのことに、私たち家臣は口をはさまなかった。あの方 が、この国になにを成し遂げたのか。どれほどの尽力をそそいでい たのかをしっていたからだ。あなたと過ごすベルモンド様はほんと うに幸せそうだった︱︱﹂ 私たちも幸せだったと、クライスは呟く。 ハンナも幸せだった。母が亡くなって、父がよく顔を見せるよう ゆうぎ になった。うしなった愛情をそそぐように与えてくれた。旅商人の 見世物や父の臣下と遊戯に明け暮れた日々は、ハンナの記憶にも残 っている。その裏でしめやかに動いていた悪意など、だれも気付か なかった。あのとき、フリジットはもっとも春に近いように思われ たし、父がだれかの手にかかるなど考えもしなかった。それでも、 父はもっとも卑劣なもので殺害された。 ﹁しかし、民はじつに我が儘だった。ベルモンド様が政務を削って かんしゃく 家族につくすのを許さなかった。あの方が、どれほどのものをあた えてくださったのかを理解もせず、一時のこどもの癇癪のように、 あの方を死にいたらしめた。すべての民がそうであったとは言いま 147 ごうまん せんよ。けれど、あれほどまでに尽力なされた方が、王だというだ けで家族と過ごすことも許さないなどと、そのような傲慢をふりか ざす民を、慈しむ気はありません﹂ ﹁クライスは︱︱父が好きだったのね﹂ 憤慨を押し殺すようなクライスの話を聞いて、ハンナが抱いた感 想はそれだった。 父の片腕として支え続けたのだから、とうぜん父の苦悩も知って いただろう。そばで苦心しているのを見守っていたからこそ、クラ イスは父が得ようとしたわずかばかりの幸せを奪いさった民が憎く てしかたないのだ。それほど、クライスは父に忠誠を誓っていた。 ﹁⋮⋮たったひとりの国王陛下ですから﹂ その言葉だけでじゅうぶんだと思った。 許しを求められたから、すべてを許そうとハンナは思った。ガイ ルへの許しとクライスへの許しはちがう。彼が望むのは、きっとハ ンナからの解放だろう。クライスが心から求める王はハンナではな く、ベルモンドただひとり。父の愛娘だからといって、ハンナに仕 える気すらない。いっそ清々しいまでの忠誠心だと、ハンナは苦笑 した。 ﹁あなたを解放するわ。この国からでていきなさい﹂ ﹁⋮⋮私をつきだす必要がありましょう。民のまえに﹂ ﹁もう民は、この騒動を王が起こしたものだと思っているわ。いま さらよ﹂ そう、いまさらなのだ。 クライスの心境をくみとって解放するのも遅かった。彼を理解し てあげるのも遅かった。ハンナは臣下との間に溝があってもいいと 思っていた。どうせ、だれもハンナの心中などわからないとありも しない壁をたてた。わからないのはハンナもおなじなのだ。クライ スがどれほど父を敬愛し、民を憎んでいたのかわからなかった。父 を忘れゆく民をみることも、新しい王権が形つくられていくのも、 クライスを追い詰める毒だったにちがいない。 148 許しを望まれたから、すべてを許そうと思った。だから︱︱。 ︵⋮⋮わたしもゆるされたい︶ 長く溝を埋めなかったことも、ずるずると頼ってきたこともすべ て、許されたい。 ﹁だからあなたを追放するのよ。あなたのためじゃない。わたしと 父のために、この国に貢献したあなたを生かしておくの。でも、二 度とこの国に足を踏み入れることは許さないわ﹂ クライスのしたことはとてつもなくむごい行為だったのだろう。 けれど、クライスにとっては、父に民がしたことはおなじことなの だ。どちらも等しくむごく、悲しく、やりきれない気持ちにさせる とハンナは思った。一時の安息をもとめて、生涯の後悔を残してお きたくないのだ。ハンナはただ純粋に、クライスが生きることを望 みたかった。父がそう望んだように︱︱。 ﹁︱︱⋮⋮あなたは、じつに甘い﹂ そのお小言を聞くのは最期になるだろうと、ハンナは笑い飛ばし てみせた。 ﹁そうね。でも、わたしは王だから。民を愛するのが仕事なの﹂ もとより、玉座はひとりで座るものだ。孤独なものだ。 気まぐれに称賛されて、嵐のように非難される。そこにどのよう な葛藤があっても、多くのものにとっては気にとめるほどではない。 弱さをみせてはならないし、民には愛を注がなくてはならない。た とえ、その民に武器をつきつけられ、玉座から引きずりおろされた としても、ハンナは彼らを愛さずにはいられないだろう。 クライスはそのような王は甘いと言う。 しかし、ハンナにとって﹁王﹂とは父ではなくハンナ自身が思い 描く理想なのだ。どれほど、みじめでも甘くても、ハンナは民を愛 したいと思うし、彼らの幸福を祈りたいと思う。たとえ、ハンナの うすい胸を、無機質な剣が貫いても、ハンナが理想を捨ててしまえ ば、それは王ではないし、ハンナでもないだろう。どれほど、甘い と言われようと、ハンナは望まずにはいられないのだ。 149 ︱︱ハンナが恋をしたひだまりのような春に似た自分の国を。 がらがらと馬車が舗装された地面を走る音が耳を叩く。 年若い王は、律儀にも用意していた馬車にクライスを押し込み、 悲しみや恐怖を隠すように笑んで手をふり見送った。その小さなす がたを瞼に思い浮かべ、クライスはふかく息をはく。彼女がたどる 道は暗く閉ざされたものだ。閉鎖的なフリジットにふさわしい末路 が、彼女を待ち受けている。 節くれた手のひらを見つめ、クライスは自嘲した。 屋敷をたずねてきたとき、自分の死というものを覚悟した。たど りやすいようにばら撒いた証拠は、くしくも忠誠厚い部下によって あいがく 覆い隠され、クライスの身に危険がおよぶことはなかった。計画を 任せた隊長が自害を図ったと聞き、クライスに芽生えたのは哀愕だ った。もとより、卑賤の出だった自分をほんとうに敬愛しているも のなどいないと思っていた。すぐに口を割るだろうと予想していた。 それが、口を割るどころか、すべてを隠して遠い場所にいってしま ったのだ。クライスのために、そうさせたのだ。 愚かだとなじることはできた。しかし、口をついてでたのは謝罪 だった。監視されている中、その呟きはだれにも届くことはなかっ ただろうが、クライスは彼の心内をくみとることなく、寄り添うこ となく、ひとりでいかせてしまったことを悔いた。せめて、最期に あったときに、酒でもくみかわせばよかったといまになって思う。 そして、その後悔はクライスを見送った年若い王にも向けられたの だ。 ﹁ほんとうに愚かな︱︱﹂ 愛したい、と彼女は言った。民を愛するのが仕事だと。 そんなはずがない。王というのは、そのようなものが仕事なわけ ではない。しかし、彼女は政治にくわしくなく、また書斎に閉じこ 150 もりすぎたのだ。政の多くは臣下がおこない、彼女に残された仕事 は、民の平穏をいのり慈しむことくらいだったのだろう。彼女なり に、王としての責務を担おうとしていたのだ。 怖いだろうに、彼女は笑うのだ。 実の父親が亡くなったときも、彼女だけは笑っていた。身内であ る彼女が笑うから、臣下の多くは泣き言をもらすことができなかっ た。クライスもまた、立ち止まることが許されなかった。それでも、 彼女の笑顔が消えたときはある。王として責め立てたとき、彼女は ひどく戸惑い、思い悩んでいた。書斎に閉じこもってしまったとき は、だれもがどうしようもないと落胆した。しかし、彼女はまた王 として、ゆっくりと歩もうとしたのだ。 それを潰したのはクライス自身だ。たとえ、その気がなくとも結 果的にそうなった。 ﹁また、繰り返すのだな﹂ 前王が愚かだったわけではない。彼女も愚かだったわけではない。 しかし、フリジットはまた、血を流しうしなっていくのだ。民が そう望むかぎり︱︱。 クライスは解放をのぞんだ。重臣という立場をうしないたかった。 敬愛していたものを奪ったものたちに、惨劇をあたえて、自らもま た裁かれたかった。それはひどく利己的な償いと報復の仕方だった のだろう。ハンナはそこに巻き込まれてしまっただけにすぎない。 それなのに、彼女は責めることもなく、愛したいと言った。 きっと彼女がうちたてる国は、もっとも春に近しいものになる。 そうクライスは確信する。 けれど、彼女もまた、フリジットの冬にたおされて消え失せるの だろう。 フリジットの冬は気まぐれで、太陽をのぞかせたと思えば、つぎ は雪を落とす。あげくの果てには大雪や雪崩を起こして、道を寸断 してしまう。それでも、フリジットの民は冬と共存してきた。気ま ぐれで我が儘な彼らとながく連れ添ってきた。 151 なるほど、とクライスはひとり呟く。民は冬によく似ていると、 そう思った。 気まぐれなところも、一時の感情で大切なものを壊していくとこ ろも︱︱。 なんて、そっくりでいまいましいのだろう、と。 クライスはゆっくりと馬車の固い背もたれに身を任せて瞼をおろ した。車輪が路面を叩く音だけが響いていく。だれもが寝静まって いる時間帯だ。ひっそりと静まりかえったフリジットには、いまも 雪が降っている。 そうして、瞼を押しあけたさきにはなにもない。対面の座席はか らっぽだ。 ﹁⋮⋮私もまた、フリジットの民だったのだ﹂ いまいましげに落とされたその呟きを、聞き取るものはだれもい なかった。 152 6 ◆ いまごろ、クライスを乗せた馬車は王都の門を抜け、寒波の厳し い中、山中に入る頃合いだろうと、自室から眼下を眺めハンナはひ とり考えた。夜が明けて、王都の正門が開かれれば、そこには武器 をたずさえた村民がひしめきあうはずだ。だれもが憤慨し、王を裁 くために声をあげ立ちあがる。見せしめのために引きずりだされる 王のすがたに、興味津々とばかりに人々が押し寄せてくる。とんで もない立志式になりそうだ、と息を吐く。 体調のためにも、はやく眠ったほうがいいことは理解している。 けれど、自分の命があとわずかだと考えれば、瞼をとざしてしまう ことがもったいなく感じる。ほんのわずかでも、自分の国である故 郷を焼きつけておきたいと、こうして闇夜に目をこらしたところで、 ぽつぽつと光る街灯だけが視界に入り、いっそうわびしい気持ちに させた。落ち着いて横になることもできず、椅子に座り朝を迎える だろうと漠然と予想したとき、遠慮がちに扉が叩かれた。 ﹁だれ?﹂ ﹁⋮⋮おれだけど﹂ 聞きなれた声音にハンナはすばやく立ちあがり部屋の扉をあけた。 使用人たちもすっかり寝つき、暗いばかりの廊下に浮かび上がる ようにしてアルクゥが立ちすくんでいる。普段着のようなやけに軽 装な格好に、またそんな薄着でと唇をとがらせそうになり、ハンナ はあわてて中に引きいれた。 ﹁どうしたの? こんなに遅く﹂ ﹁どうせ、寝てないんじゃないかって思ってさ﹂ ﹁⋮⋮寝られるはずないわ﹂ 153 わずかな時間すらおしいと思ってしまう。 フリジットの白を明るく照らす太陽がのぼれば、ハンナの命は数 えるほどでなくなるだろう。悲観的に物事を考えるのはよくないと わかってはいるが、身の潔白を証明するものはなく、ことの発端だ ったはずのクライスもいない。ハンナ自身が追放してしまったから だ。彼を引き立てれば、変わっていたこともあるはずだろう。けれ ど、それをおこなっていれば、ハンナはこうして穏やかに朝を待つ ことはできなかったはずだ。いやに心臓はおとなしく、アルクゥと 話す自分は枠組みから外れたように異質に思えた。 アルクゥのほうがよっぽどつらそうな顔をしている。 ﹁あなたには申し訳ないことをしたわ﹂ はるばるラフィールからやってきて、ハンナのために尽くそうと してくれた矢先のことだ。ガイルのように角がとれてしまえば、ド ラゴンになって故郷に戻ることもできず、端麗な容姿をうしなって しまうかもしれない。ハンナから解放されれば、アルクゥは故郷に 残した彼女のもとへ帰りたいだろう。ハンナはいつもこの灰色の青 年を縛りつけてばかりだ。 ﹁⋮⋮ごめんね﹂ ぎゅっとアルクゥの頭を抱え込めば、彼は抵抗をしめすことなく おとなしく抱きしめられた。慈しむように灰色のなめらかな角をな でる。ハンナの命がたえるとき、この角は役目を終えたように落ち るのだろう。アルクゥを雪に閉ざされたフリジットへ置き去って、 神さまというものはずいぶん手ひどいことをするものだと思う。願 わくは、彼が故郷に戻るまで見せかけでも角がくっついていればい いのに、と胸中で見えもしない神さまに毒ついて、ハンナはしっか りとアルクゥを抱きしめた。 ﹁角、なくなるかもしれないんだぞ﹂ とがめるように、アルクゥは口にする。 ﹁わかってる﹂ ﹁ひどいやつだ﹂ 154 美しいドラゴン。愛しい忠臣。ハンナにすべてをくれた運命のひ と︱︱。 ﹁ごめんね﹂ そう返すことしかできない切なさをどうかわかってほしい。 淡々と謝罪するハンナの腕から顔をあげて、じっと瞳をみすえる とアルクゥは言った。 ﹁⋮⋮死ぬかもしれないんだぞ﹂ ﹁うん﹂ ﹁︱︱ばか﹂ 死ぬかもしれない、とアルクゥは口にする。死ぬだろうとハンナ は考える。 フリジットの歴史には、謀略や恨みによってたおれた王も多い。 ハンナの父であるベルモンドもまた、信頼厚い王ではあったが毒に えんこん よって玉座をおろされた。たくさんのひとに愛されていても、その 裏で育っていく怨恨はたえない。もちろん、私益をむさぼっていた 王もいる。彼らも等しく、玉座を無残なすがたでおりることになっ た。 ハンナが民にしたことなど数えるほどしかない。道を整備して、 貧困にあえぐ村がすくなくなるよう物資を分配することを推し進め た。すべては春を迎え入れるために、目前の冬を乗り越えるために 必死だったからだ。しかし、冬を乗り越えるまえに、ハンナはたお れようとしている。そのことを嘆いてくれるものも、ハンナにはわ ずかしかいなかった。 いちばん嘆きたいはずの自分ですら、どこか遠くに行ってしまっ たようだ。 ﹁︱︱ごめんね﹂ 王として生きることと、ハンナとして生きることは似ているよう で違う。 朝日が昇ればフリジットの王がいなくなる。そして、ハンナとい う少女が消えるのだ。 155 抱きしめた体は熱く、春を思わせる温もりに涙がこぼれそうにな る。まだ、王として立っているかぎり、弱さを見せてはいけない。 民の前では王として振る舞い、王として終わらなければならないの だ。いまだにハンナは称されているのだろう。冬の王という侮蔑の 名称で︱︱。 ﹁これが最期だから﹂ 重ね合わせた唇をどちらともなく寄せ合って、こぼすように息を 吐けば、満たすようにアルクゥの吐息が肺を満たしていく。温かい 空気が体内を通る違和感にすこしだけ唇を離せば、アルクゥがきょ とんと瞬きをした。それから、ゆっくりと目を細めてハンナの頬を 撫でると、もう一度くちづけを交わしてくれる。 冷え切った唇は冷たく、極寒のフリジットに相応しいキスだと思 った。 惜しむように、けれど距離を開けるのはもったいなくて、おたが いに額をつけて手を絡める。軽装と思えないほどアルクゥの手のひ らは温かく、いつの間にか震えてかじかんでいたハンナの手をなぐ さめた。穏やかでとても幸福なひとときだった。それだけで、ハン ナは胸がつまったようにぎゅっと切なく苦しくなる。 これが最初で最後のくちづけになるだろう。ハンナの生涯でただ 一度だけの︱︱。 ﹁この国を好きになれてよかった﹂ 母がハンナを愛してくれたように、ハンナもこの国を愛そうと決 めた。 灰色と白に閉ざされるフリジット。長い冬とわずかばかりの春し かやってこない極寒の国。そこに住まう民たちの忍耐と激情を、美 しいとハンナは評した。フリジットそのものだともいえる民たちは 気まぐれで、とても残酷なことをする。それでも、愛したいとハン ナは望んだ。王として、この国を愛したかった。 ﹁あなたに出会えてよかった﹂ 自分の国が嫌いなのかとハンナをなじったひと。不器用でぶっき 156 らぼうで世話焼きなひと。 ハンナが王として立ちあがるすべてのきっかけを与えたような存 在だ。それなのに、ハンナは王として彼を手放さなければならなか った。ひとりで歩むには厳しく、愛したものを守るにはさらに険し い道が続くその場所に、アルクゥは臣下として歩んできた。帰るこ ともせず、愛したものにすら決別して、ハンナの手をとってくれた。 いまこうして、アルクゥにすがりつくことは、彼とした約束をた がえることになる。それでもいまだけは王としてではなく、ひとり のハンナという少女に立ち戻って甘い夢に浸っていたかった。つぎ に訪れる動乱の出来事をひとりぼっちで乗り越えるためにも。ハン ナはきつくアルクゥの手を握りしめて、ぐっとこらえるように言っ た。 ﹁だから、一緒にいてほしい。最期まで︱︱﹂ 命絶えるその瞬間まで、彼の灰色を見続けることは、ハンナをな ぐさめてくれるだろう。 胸の内を明かさずに背を向けることはひどいことだ。さらに消え 失せることはもっと辛辣だろう。瞳をからめて、くちづけを交わし て、なおハンナの口から想いが滑りでることはない。その一言を発 してしまえば、ハンナは王として立っていられなくなる。言ってし まえば、ハンナはひとりの少女に逆戻りし、すべてを投げ捨ててま で、彼の翼にすがってしまう。空を飛んでふたりで逃げることはで きる。しかし、アルクゥと約束したことは、ハンナが王としてある べきときなのだ。けっして、甘えから逃げだす少女のために捧げら れたものではないことを、ハンナ自身がよくわかっている。 ︵だからこそ、いまだけは︱︱︶ 許されるならば、この手のひらから伝わってくる温もりを手放し たくなかった。やがて、空が白んで温もりが離れてしまえば、ハン ナを襲うのは身を凍らせるほどの寒気だ。そこにハンナを慈しむも のはなにもない。ただひたすらに鋭い悪意と冷気がハンナをなぶり つづけるのだ。そうして、終わるのだ。ハンナの人生は、自分で思 157 っているよりもあっけないものだった。 こうして、アルクゥと体温を共有しているだけで、ひだまりにい るようなのに︱︱。 まるで春の足音がそこまで聞こえているかのように、幸福感に満 たされていた。 ハンナは自らが望んだ春を迎えるまでに倒れていく。あれほどま でに恋い焦がれた春が、遠ざかっていくように思え、ひとり見下ろ すフリジットはどこまでも冷たかった。それなのに、アルクゥと寄 り添うだけで、春が駆け寄ってきたようだった。こんなにも温かい とハンナはいっそう身を寄せる。なぐさめるように回される腕はど こまでもやさしい。 張り裂けそうなほどの温もりに、ハンナはしかし、凍えるように 涙した。 きっとこれが、ハンナ自身がする最期の恋になる、と︱︱。 158 第六話 万年雪がとけるとき 目覚めたとき、そこにアルクゥのすがたはなかった。 一時の夢から覚めたように、ハンナの心中には戸惑いがうまれる。 ただ、寄りかかるようにして意識をうしなった感覚と、だれかがや さしく頭をなでていた感触は夢うつつの中でも残っており、ほんの りと胸中が温かくなったように思えた。 王都の正門が開かれる時間になると、外から聞こえるざわめきも 届くようになる。優雅に紅茶を飲むハンナの傍らでは侍女が窓から 外を見下ろしては顔を曇らせた。すっかり身を整えたハンナはその 瞬間がくるのを待っている。兵には民がおさえきれなくなれば、無 用な抵抗はせずに道をあけ下がるように伝えている。とっくに終わ った朝議では、臣下にあとの手はずを口早に伝えた。ハンナが消え 去れば、ガイルが臨時的に玉座におさまることになるだろう。 いつ、だれが自室の扉を押しあけ、ハンナを引きずりだすのかは わからない。 一緒にいてほしいと哀願したアルクゥもおらず、ハンナは自嘲す るように笑った。 ﹁ハンナさま、おかわりは︱︱?﹂ ﹁ありがとう。いただくわ﹂ 注がれる紅茶は父が愛し、ハンナが苦手とするもの。 すこしでも、父に寄り添えば、この不安もかき消されるだろう。 すっきりとした風味が舌をなでて、ハンナは眉根をよせて飲み続け た。苦みもいずれは感じなくなる。ハンナの五感はいまだ機能して いるが、いずれそれもフリジットの寒空に置き去られることになる だろう。 それを悲しいとも思わない。 灰色の彼がいないことがなによりもハンナを揺らし、困惑させる。 こびりついたように残っている唇の感触が幻だったのかもしれない 159 と考えさせてハンナを苦しめた。なぐさめるように、ナフキンで口 元をぬぐうと、その感触すらぬぐってしまったようで悲しくなった。 ﹁門前にたくさん集まってきていますね﹂ 世間話をするように侍女は言う。 平時ならハンナと会話をすることは禁じられており、職務だけを こなしている彼女が話しかけてくることはめずらしかった。とくに とがめるつもりもなく、ハンナはおそらく人々でごった返している だろう門扉の方向に視線を向け、また一口、押し込むように紅茶を 飲んだ。 ﹁⋮⋮あなたも危険だから下がっていなさい﹂ 兵士との衝突も予測できたために、丸腰というわけでもないだろ う。それぞれの手には武器を持ち、怒鳴り声をあげて侵入してくる ことは明白だった。あの村で見てきた光景を知っていれば、その熱 気も激情も想像するにたやすいものだ。華奢な体つきをした侍女が 対面するには酷だろうとハンナは忠告を口にする。しかし、侍女は 震えるように言葉をつむいだ。 ﹁わたくし、ハンナさまの侍女であれて幸せです。ですから最後ま でおそばに︱︱﹂ はにかむように笑う彼女に虚をつかれたのはハンナのほうだった。 唖然とするハンナを気にもとめず、侍女は慣れた手つきで紅茶を注 ぎ、ハンナに笑いかける。そこにあるのは、いつもとおなじ光景で はあったものの、異なる意味合いを含んでいた。 玉座に座ればハンナはいつだってひとりだった。寒々しい椅子は 冷たくハンナをなぐさめることなどない。しかし、そこからおりて しまえば、暖炉のともった書斎にはガイルがいて、自室に戻れば世 話を焼いてくれる侍女がいた。体調を崩せば昔馴染みの医師がほが らかな顔で出迎えてくれた。なにより、アルクゥがきてから、ハン ナは孤独を感じることがすくなくなった。 ひとりで歩いているつもりだった道は、たくさんの人に見守られ ていたのだ。 160 ちんうつ 朝議ではだれもが沈鬱な表情でハンナの決意を聞いていた。ガイ けそう ルとおなじ提案をするものもいた。不仲だと思っていた臣下が、ハ ンナを気遣ったのだ。命終わるにはしのびないと懸想してくれた。 埋めなくていい溝など、存在していなかった。すべて、視野の狭い ハンナの虚妄に過ぎなかったのだ。 そう気づいたところでハンナに残されている時間はわずか︱︱。 ﹁ねえ、わたしの好きな紅茶をいれて﹂ ﹁は、はい!﹂ 固く閉ざされた扉は安穏とした時間を遮らない。城門でおさえて くれる兵士がいるかぎり、ハンナの身の安全は保障される。やがて それも瓦解して愚王として引きずりだされる瞬間がやってくる。そ のときに、灰色の彼はあらわれてくれるのだろうか。最期の瞬間ま で、この瞳に焼き付けていたいと願ったハンナの約束をたがえるこ となく︱︱。 新たに注がれた紅茶はハンナの好きな茶葉だ。甘く後味がしっか りと残る。 ハンナを甘いとなじったクライスの顔が浮かんだ。彼の舌にはお よそ馴染まない甘さが口内を満たしていく。この甘さがハンナ自身 であり、王政であったのだ。父の真似事をしたわけではない。ハン ナは父がどのように政務をしていたのかをしらない。なにもわから ない状態で、よくここまで頑張ったと自賛する。その終わりがどれ ほどの悲痛でもかまわない。 春に恋をして、民を愛して、そして冬にたおれていく。 悲惨な末路だと他人は考えるから、顔をゆがめてハンナを憐れむ のだろう。 ただ、ハンナだけが不幸だと思っていないから、穏やかに出迎え ることができる。 ﹁⋮⋮信じているわ﹂ ハンナに一足早い春を贈ってくれたひとを想う。 こぼした言葉に反応した侍女が不思議そうに首を傾げるので、ハ 161 ンナは苦笑をかえした。 幻のように消えてしまったひとは、ハンナを置いてどこに行って しまったのだろう。故郷が恋しくて帰ってしまったのだろうか。そ れとも、ハンナを逃がす算段でもたてているのだろうか。あいにく、 逃げようといわれて逃げるような性格でないことは、彼もわかって いるはずだ。ハンナがどれほど、フリジットを愛しているのかを理 解しているからこそ、彼は臣下となってともに歩む道をとってくれ たのだ。 アルクゥが信じたように、ハンナもアルクゥを信じている。 もう、人との間にふかく溝をつくったまま、後悔にさいなまれる 別れをしたくなかった。 ﹁いままで、ありがとう。感謝しているわ﹂ ﹁おやめください、ハンナさま。わたくしは、いつまでも︱︱⋮⋮﹂ くしゃりとゆがむ顔に苦笑いを浮かべて、ハンナは窓に視線をや る。 フリジットにはめずらしく太陽がのぞいていた。雪に反射して眩 しいばかりの景色だ。 ﹁この国は好き?﹂ ﹁⋮⋮はい。大好きです﹂ ﹁そう。それなら、よかった﹂ にっこりと笑いかけると、侍女はなにかしら言いかけて口をつぐ んでしまった。紅など引いていない唇はわずかに血色が悪く、侍女 をさらにひ弱にみせる。彼女が言葉をつむぐまで沈黙を貫いていた ハンナだったが、その静寂を割いたのはけたたましい足音だった。 ついに来た、とハンナが口にするまでもなく、乱暴に扉が叩かれ 外側から壊すように開けられる。怒声とともに入ってきた男たちに 侍女が驚いて悲鳴をあげた。一瞬で騒がしくなった室内で、ハンナ ごうしゃ だけが優雅に紅茶をすすり、ゆったりと席を立った。 質素でありながら高級な衣服を身にまとい、豪奢な髪飾りを身に つけた。普段のハンナならけっして好まない格好だったが、せっか 162 く最期の舞台にあがるのだからと、戸惑う侍女をせっついて身を飾 らせた。ゆえに遠目でみればそれなりの迫力はあるだろう。 ﹁︱︱待ちくたびれたわ﹂ 大仰で生意気な口調は、ハンナが虚勢を張っているときのもの。 そのことに気づくものはここにはいない。その場にいるのは、民を さいなむ冬の王と、そんな王に怒り武器を持った民だけだ。縮こま った侍女は、ハンナを心配そうにうかがっているが、無骨な男たち にすっかり気圧されている。そんな彼女に守ってもらおうと考える ほど、ハンナは諦めが悪いわけではない。 ただひとつ。王を見つけて興奮する男にまぎれて立ちすくむ青年 をみとめ、ハンナは困惑するように笑んだ。音もなく、ゆっくりと 見慣れない顔で笑うハンナにその青年は動揺したのか、わずかに後 ろに下がった。そのため、後方にいた男にぶつかりなにやら文句を 言われている。 ハンナ、とその青年の唇が動いた気がした。 手荒に拘束してくる男たちにさもうんざりしている顔を向けなが ら、ハンナは息を吐く。 嘘をついていてごめんね。黙っていてごめんね。 口にしたいことはたくさんあったが、痛いほど自分を締めつける 縄と、狂ったように罵声を浴びせる男たちの足元にうずくまり、そ っと目を閉じることしかハンナにはできなかった。 163 2 ◆ ハンナと連れ添って訪れることはあったが、こうしてアルクゥひ とりでたずねるのは初めてだった。フリジットではめずらしい太陽 が輝いていることもあり、村内の人々はがやがやと話しながら作業 をしている。しかし、村民の多くが出払っていることもあり、いる のは老人や子どもばかりに思えた。女たちは倒壊していない家屋に 集まって食事をつくっている。燃料が確保されはじめている証でも あった。 おそらく、王城は取り囲まれ、ハンナは心細い想いをしているだ ろう。 一緒にいてと願われたときは、彼女の傍にいることが最善に思え たが、寄りかかるようにして寝息をたてる顔を眺めていれば、やが てその考えもとけるように消えていった。まだあどけなさの残るす がたに相応しくない重荷を乗せられて、やってもいないことで裁か れる。それを受け入れられるほど、アルクゥは温厚な人柄ではなか った。 眠りについたのをいいことに、ハンナを連れ去って逃げてしまお うかとも画策したが、傷つくのは故郷を捨てることになったハンナ であり、アルクゥはハンナを苦しめたいわけでもなかった。しかし、 指をくわえて彼女が処刑されるのをみるつもりもなく、こうして騒 動の火種でもある元オルコット領内に踏み入っているわけである。 ハンナはいなくなってしまったアルクゥに気づいてなにを思うだ ろう。また、泣きそうな顔でひたすらたえるのだろうか。彼女はい まだにアルクゥがラフィールに帰りたがっていると思っているし、 恋仲だったメルクゥのことを気にしている素振りをみせる。こぼす ように願われたことも、アルクゥからしてみればいまさらなことだ 164 った。 とりあえずと目を向ければ、残された村人が兵士に怯えながらも 家屋を立て直しているのがわかる。すっかり嫌われものになってい る兵士は、それでも献身的につくしているようだった。 男手がいなくなった村の復興もゆっくりではあるが進んでいるよ うに思う。この村を立て直すために兵士を送るように命令したのは ハンナだ。物資が枯渇しているという報告もあり、かなり無茶な方 法で取り組んでいたことをしっている。しっているからこそ、言え ない現実が歯がゆくてたまらないのだ。 ﹁わっ︱︱﹂ ﹁おっと、悪い。大丈夫か?﹂ ぼけっと突っ立っていたせいで、背後からきた人物と接触してし まった。前を向いて歩けよと愚痴る暇もなく振り返ったさきには、 視界を覆い隠すほどの荷物を抱えた若い兵士がいた。衝撃で落とし た荷物をわたわたとかきあつめ、手伝うために屈んだアルクゥと目 があい、照れたようにはにかんだ。きっちりと着こまれ兵服とは違 い、のんびりとした性格がうかがえる。毒気を抜かれたように息を 吐いてから、アルクゥはおろおろと手探りで集める兵士とは真逆に 手早く転がった野菜などを掴み取った。 大きな荷物だったためか散乱したものは多く、遠くに転がってい るものもある。見逃しはないか視線を滑らしていたアルクゥの視界 に真っ赤な色が飛び込んできた。真下から差し出されるそれは熟し た果実。かぶりつけば果汁が溢れそうなほど美味しそうな色合いを している。差しだしている本人は、虚ろな瞳でアルクゥを映しだす だけでなにも喋らない。 喋れないと言ったほうが正しいのか。 ハンナが親しくしているために名前はしっているがどうにも慣れ ない。ラフィールにいた子どもたちとは違って、ぼんやりと空を映 す瞳を持ったフェルは、沈黙を保持したまま果実を受け取らないア ルクゥに首を傾げた。そこでようやく果実を受け取るために手を伸 165 ばし、﹁ありがとな﹂というぶっきらぼうな言葉を返したが、やは りフェルはうんともすんとも言わなかった。 ハンナと会いにきたときは曲がりなりにも喋ろうと努力している 節はあったが、いま目前にいる少年は、どこか虚ろに存在している だけでいっそ不気味に思えるほどだった。もちろん、フェルの母親 が殺されたことも、村になにがあったかもしっている。だからこそ、 泣きじゃくるわけでもなく、静かにたたずむフェルが不可思議に思 えるのだ。 ﹁ああ! そんなところにまで︱︱すみません﹂ どこか気の抜けるような声がアルクゥとフェルの間に溜まってい た奇妙な空気を断ち切り、ようやくアルクゥは小さな頭から目をそ らした。へこへこと謝罪しながらやってきた兵士は、やはり気の抜 けるへらへらとした笑いを顔面にはりつけて、アルクゥから果実を 受け取った。ぎっしりと身のつまった果実は重く、離れていけば行 き場をうしなったように手が泳ぐ。 ﹁いやあ、ご迷惑をおかけして︱︱⋮⋮助かりました﹂ ﹁いや、べつに﹂ 人懐っこい笑みはフリジットでは稀有だ。男はむっすりと口を引 き結び黙々と作業にあたるものが多く、感情の起伏が明白なアルク ゥにハンナはいつも﹁やっぱり余所者なのね﹂とこぼしていた。彼 女に悪気はなかったのだろうが、アルクゥはその言葉をつむがれる たびに、尻がもぞもぞとして落ち着かない気分になる。自分がフリ ジットのものではないということを、再確認させられているようで 嫌だった。 フリジットでは、明るい虹彩はめずらしく、どこか暗い色合いを している。兵士の瞳もまた陰りがさした色をしており、空色を映し こんだフェルのほうがよっぽど余所者に思える。そんなフェルはむ っつりと口を閉ざしているから、フリジットの男に相応しい性格を しているが。 ﹁お、おはよう! 今日の気分はどうかな?﹂ 166 むすりと押し黙っているフェルに、兵士は気安く話しかけた。 知り合いかとフェルを一瞥すれば、ぐっと唇をかみしめ睨みつけ ている。どうやら、兵士の一方的な片思いのようだ。あどけなさの 残る顔ですごまれ、まごまごとしているところを比較しても、どち らが年上かわからない。なにより、可愛らしい顔をゆがめて嫌悪を しめしているフェルが物珍しく、アルクゥは無責任にも傍観を決め こんだ。 ﹁もうすぐ、食事ができるから一緒に食べようか?﹂ フェルはなにも答えない。ぷいっと顔すら背けてしまう。 兵士はあーともうーともつかない呻きをもらして思いついたよう に果実をかかげた。 ﹁これ食べる?﹂ ﹁いらない!﹂ 噛みつくようにフェルが怒鳴ったことにも驚いたが、声を発した ことにも驚いた。 唖然としてたたずむ二人を置いてフェルはくるりと身をひるがえ し駆けていく。声すらでないアルクゥを置いて兵士はひとり頭を抱 えてうなだれた。ぶつぶつと﹁落ちたものをあげようとするなんて、 俺のあほ!﹂などと自責してはため息をこぼす。 ﹁いつから喋るようになったんだ﹂ ぼやくようにアルクゥが言うと、兵士が反応して答えてくれる。 ﹁ああ。たしか会いたかったひとが会いにきてくれたらしくて︱︱ そこから、発声の練習をしていたそうですよ。話せるようにはなっ たけど、心は閉ざしたままで、俺もあまり声を聞いたことがないん です。もう一度、その人が来てくれたらなあ﹂ 懇願に似た声音にアルクゥは顔をくもらせた。 フェルが会いたかったのはハンナだろう。さきほどアルクゥに果 実を渡したときも探るように視線を走らせていた。一緒にたずねた 際には言葉を発せず、またハンナ自身も多忙であったために慌ただ しい再会になったのだ。ハンナのために喋れるようになったのだか 167 ら、彼女と話したいという気持ちで胸がいっぱいなのだろう。落胆 こそ見せなかったが、瞳から興味がうせたのは明らかだった。 負に交わった感情が永久にフェルの心から消えないものになろう としていることを、アルクゥは知っている。村の中にいたのでは、 ハンナが王であったことも知らずに別たれてしまうだろう。そんな ことをさせないつもりでアルクゥはいるのだが、もしもという最悪 の事態はつきまとっている。硬い角に触れればすこしだけ安堵が浮 かぶ。この角がついている限り、ハンナの心臓がまだ脈打っている 証になる。 ﹁詳しいな、あんた﹂ ﹁えっ? う、うん。まあ︱︱知り合いというかなんというか﹂ もごもごと落ち着きがない。掌中にある果実を無駄に触っては指 紋をつけていく。すっかり熟した果実が兵士の手にもみこまれて、 完熟を通り越して腐りおちていくのではないかという懸念を抱くほ どには、彼は果実をもみくちゃにしている。 動揺もここまでくるといっそ清々しいものだ。 ﹁おれの名前はアルクゥ。おまえは?﹂ ﹁へ。あ、マーカスっていいます。どうぞ、よろしく︱︱あ!﹂ にへらと笑って握手を求めてきたので差しだせば、マーカスは思 いだしたように声をあげてぱっと手を引っ込めた。すっかり行き場 をうしなった手を泳がせてアルクゥが見やれば、急いだように荷物 をかき抱いている姿がうつりこむ。申し訳なさそうに眉根をさげて、 やはりどこか落ち着きなくマーカスはせっつくように言う。 ﹁すいません! はやく持っていかなくちゃいけないんです! ま たあとでゆっくりと︱︱﹂ 反省などという言葉は彼には存在しないのだろう。 さきほどと同じように視界をおおいつくす量の荷物を抱えて危な っかしく歩きだしたかとおもえば、おそらく遊ぶために飛びだして きた子どもと盛大に衝突した。不安定な形で持ち上げられていた荷 物は当然のように散らばり、尻もちをついた子どもは衝撃に驚いた 168 のだろうかしましく泣き声をあげた。マーカスはまたもや散乱した 荷物を見て、大泣きする子どもを確認して、どっちに対処していい のかわからず混乱し、おろおろと視線をさまよわせている。 そんな姿を遠巻きに傍観していたアルクゥはさきほど見た光景よ りも悲惨な現状にため息をついて、こんなことしている場合じゃな いのにと胸中で愚痴をこぼした。そのようなアルクゥの嘆きなどお かまいなしに、子どもの声は甲高く響きわたり、マーカスがなだめ ようとするたび、音階があがっていくような気がした。 アルクゥは呆れ半分に歩を進め、マーカスをぼんやりと眺めて思 った。 こいつはやっぱり、あほなのかもしれない。 169 3 ぎゃあぎゃあ大泣きしていた子どもをなだめたころには、マーカ スが荷物を集め終えていた。 ラフィールでは、角つきの体が丈夫ということもあり、子どもた ちが掴みあいの喧嘩をすることが日常茶飯事だった。そのため、怪 我をしては号泣する子どもが続出し、それをなだめることは角つき の年長者の役目だった。懐かしい思い出に浸りながら、すっかり泣 きやんだ子どもに手を振り見送れば、マーカスは首がとれそうなほ ど上下に揺らして謝罪してきた。 ﹁すみません! 一度ならず二度までも﹂ ﹁いや、いいけど。持つの手伝うよ﹂ ﹁え! いや、いいです。悪いですし﹂ わたわたと拒否するマーカスを睨みつけて、アルクゥはすごむ。 ﹁またぶちまけて迷惑かけるのと、どっちがいい?﹂ ﹁⋮⋮あ、う︱︱お願いします﹂ マーカスと一緒に荷物を運べば、そこには赤ん坊を抱いてうずく まる女性たちがいた。そんな彼女たちを守るように仁王立ちしてい た恰幅のいい中年の女性に、マーカスはほがらかに笑って話しかけ ている。マーカスは極めて好意的でさわやかではあったものの、相 手をしている女性は仏頂面でむしりとるように荷物を受け取ると、 アルクゥにさえ刺々しい視線を向けて背を向けた。なんだありゃと 説明を求めるように投げかけた目線も、誰にも見向きされずにしお れていく。 ﹁いやあ、あいかわらず嫌われてるなあ!﹂ のんびりと笑うマーカスには嫌でも毒気を抜かれる。 すっかり馴染んだ二人は、身軽になった体を家屋に預けて、閑散 170 とした広場を眺めていた。 さきほどの無礼な態度の理由を問いただそうとすれば、マーカス はあっけらかんとそう言ったのだ。兵士が嫌われる原因はわかって いる。村で起こった災難を考えれば、理解できないこともない。そ れでも、いかにもいい人を表現したマーカスが化け物のように扱わ れていることが不思議でならなかった。 広場にはマーカスの他にも兵士が存在しているが、おっかなびっ くり話しかけられて協力を仰がれているすがたも散見できる。兵士 同士が集まって談笑しているときもあったが、マーカスは不自然に もそっちを見ないように視線を泳がせているようだった。 そんなマーカスと並んでいるアルクゥはさきほどから不躾な視線 を浴びている。 ﹁ずいぶん、嫌われているんだな﹂ 村人にも、兵士にも。マーカスは冷えた視線を一蹴するように声 をたてて笑う。 ﹁仕方ないんですよ。俺、当事者ですから﹂ ﹁︱︱は?﹂ ﹁この村を襲撃したひとりなんです。ほんとうは顔すら見たくない って思われているんでしょうけど、なにもしないと逆にそわそわし て落ち着かなくて。許可なく手伝いにきてるんですよ。ボランティ アってやつですかねえ﹂ のんきにもほどがあるとアルクゥはうなだれた。 ただでさえ歓迎されていない兵士たちの中で、惨劇に加担してい たと知られれば風当たりがきつくなるのは当然のことだろう。まし てや、マーカスのようにへらへらと笑っていれば、反感を買われて も仕方あるまい。どうしようもないと考えつつも、アルクゥはマー カスのことを憎めなかった。つらくても笑おうとするところがハン ナを思わせたからだ。 ﹁俺、この国を守るために兵士になったんです。厳しい訓練とかに も頑張って耐えて︱︱耐えた結果が、あんなことをするためだった 171 なんて、いまでも信じられなくて﹂ 呆然と手のひらを眺めるマーカスにアルクゥはかける言葉をうし なった。彼の手のひらはフリジットの人間に相応しく色素がうすい。 雪のように真っ白なそこにマーカスはなにかを見ているように思え た。それは彼の中にこびりついてきえないものだ。ゆっくりと削り 取るように残酷な足音が忍び寄ってくるような気がした。 ﹁⋮⋮どうしてクライスさまは、あんな命令をしたんだろう﹂ マーカスにとっては疑念に満ちたつぶやきだったのだろう。 しかし、アルクゥにとってはきらきらと輝く希望の一言のように 感じた。マーカスの落としたぼやきは、アルクゥが探し求めていた ものに限りなく近く確証をともなっている。村の惨劇を体験したマ ーカスと、そんな彼がこぼした命令を下したものの名前。そこには 王都で待っている彼女の名前は含まれていない。 がっしりとマーカスの肩をつかむと、彼はひるんだように口を閉 ざした。驚いてだした声は高く、言いたいことは口内でもつれたの かやけに聞き取りづらい発音で返ってきた。それすら気にせずアル クゥはどくどくと脈打っている心内を落ち着けるために、ゆっくり と息をはく。 あまり時間がないことはわかっている。王都にいるハンナがすで に拘束されている可能性もある以上、無駄に時間を浪費することは 避けなくてはならない。幸いといっていいものかマーカスはすこし ばかり緊張感も頭も足りていないように感じるが、アルクゥにとっ てはありがたいことだ。この際、選り好みしている暇はない。 ﹁ななな、なに?﹂ ﹁頼みがある﹂ ﹁え、え?﹂ 正直に言ってしまえばマーカスに任せるのは、ものすごく不安だ。 しかし、背に腹はかえられないのは事実だ。切羽詰まっているの もまた事実。 ﹁お前にヒーローになってもらう﹂ 172 ﹁⋮⋮へ、え﹂ 理解したような納得していないような微妙な返答をしたマーカス にいらつき、返事はとすごめば飛びあがって首をぶんぶんと振り回 す。もちろん縦にではなく横に。やっぱり駄目かと諦めかけながら も、ちらちらと浮かぶのはハンナの顔だ。チャンスは一度きり。も し、その一度が目の前に転がっているなら逃したくはない。アルク ゥはすがるような気持ちで、いささか不遜にマーカスを見下ろした。 ﹁お前だけが頼りなんだ。ハンナのためにも﹂ ﹁む、むりです︱︱って、ハンナってだれですか﹂ 頑なに拒否するマーカスに、いっそのこと気絶させてでも連れて いくと覚悟を決めたとき、 ﹁おねえちゃん?﹂ こわごわと確認するように落とされた声は、向かい合うどちらの ものでもなかった。 ぽつんと立ちつくす小柄な影を視界の端にとらえ、アルクゥはマ ーカスから手を離す。解放されたマーカスはほっと安堵の息をはい ていたようだが、アルクゥには逃がすつもりはなかった。明らかに もめていた二人を不思議そうに見比べてから、フェルはひっそりと 口を開いた。 ﹁おねえちゃんが、どうしたの﹂ ﹁ちょっと危ないことになっててな﹂ 純真な目を向けてくるフェルをごまかすのは良心を傷つけたが、 ほんとうのことを言えるはずもない。ハンナが王であることも、い ままさに命の瀬戸際に立たされていることも、フェルに伝えるには 酷に思えた。それでも、フェルはじっと瞳をそらさない。空色の輝 きがアルクゥの心をのぞきこんでいるようだった。 ﹁ぼく、行く﹂ ﹁行くってハンナのところにか?﹂ こくりとうなずいた顔は真剣そのものだった。 フェルの確固たる意思は尊重したいと思っているが、なにぶんフ 173 ェルではハンナの無実を証明できない。いま、ハンナに必要なのは 被害にあったものの言葉ではなく、加害をあたえたものの言葉だ。 もっとくわしくいえば、村の襲撃を企てたのはハンナではないこと。 ハンナはなにも知らなかったことを明確にしなければならない。た とえば、あの日、命令を下したのはハンナではなくクライスであっ たことを告発するだれかが必要なのだ。 それを実行できるはずのマーカスは、びくびくとアルクゥをおび えた目で見るだけで戦力になりそうにない。困ったような呆れたよ うな息をこぼせば、フェルは丸い瞳をマーカスに向けて、およそ子 どもとは思えない冷えた声音で言った。 ﹁ぼくが行くんだから、行くよね﹂ ﹁う、え︱︱﹂ ﹁行くよね。つぐないたいんでしょ、ぼくに﹂ ﹁⋮⋮はい。行かせていただきます﹂ あれほど駄々をこねていたマーカスの尻を蹴りつけるような言葉 を吐いたフェルは、やはり可愛らしい天使のような顔で、アルクゥ に振り向いた。ぼくも行くからねという拒否を許さない声音に文句 をいうこともできず、おかしなことにアルクゥは、うなだれている マーカスの肩をなぐさめるように叩いていた。 174 4 ◆ フリジット王都の広場には古ぼけた処刑台がある。 数百年ほど前にいた極寒に相応しい暴君を処するためにつくられ たものらしい。長年、使われることのなかったそれは老朽化が進ん でいるようだったが、使用できないわけでもなさそうだった。もち ろん、ぶら下がっていた縄は朽ち果てていて、新しく用意するはめ になったらしいが。そんな物騒なもので処刑されるのかと、ハンナ はうんざりと息をこぼすしかなかった。 拘束されてから処刑はすぐには行われず、手狭な家屋に押し込め られ見張りをつけられてハンナはじっとしていた。見張り役を買っ てでたのは、動揺を隠しきれていないシグルで、説明を求めるよう に投げかけられた視線から、逃げるようにハンナは顔を背けた。そ れから、一言も喋らず、外から聞こえてくるざわめきが沈黙をごま かしてくれていた。 外では大衆を相手に演説がおこなわれている。ハンナを処罰する ための原因などを声高に叫んでいるのだろう。ときおり、怒号のよ うな歓声がハンナの耳を焼いた。とくに抵抗する素振りもみせなか ったからか、ハンナの拘束はじつに簡易だった。椅子に座らされ、 手首を無骨な縄で縛りあげられているだけで、痛めつけられていた りはしない。取り押さえられたときに、髪飾りは乱れてしまったの が残念だ。 ﹁なあ﹂ ぼんやりとこれからのなりゆきを考えていたハンナに声がかかる。 無視をするわけにもいかず、ハンナは首を動かしてシグルのほうを 向いた。動揺はおさまったようだが、戸惑いは見受けられる。拘束 されたハンナを見る目は痛ましく、苦しみに満ちていた。事情をし 175 らないものが見れば、処刑されるのはハンナではなくシグルのよう にも思えるだろう。 ﹁そんな暗い顔をしないでちょうだい。嫌気がさすわ﹂ ﹁なんで黙ってた﹂ 不遜な言葉をものともせずにシグルは言う。ハンナのほうがたじ ろいでしまった。 ﹁いう必要などないでしょう﹂ 崩した物言いにならないように気をつけながらハンナは答える。 処刑が終わるまで、ハンナは王であり続ける。あり続けなければ ならない。 民が処するのはハンナという少女ではない。フリジットの国王な のだ。そう思わせなければならない。民たちには尊いことをおこな ったと思わせて、終わらなければならない。なまじ、ハンナを慕う ものを残すと、クライスのようになりかねない。ガイルもクライス も、父を慕っていたからこそ、うしなってなお痛々しい。 考えないようにしても、ついアルクゥのことを思い浮かべる。 彼はクライスのように民を憎んだりしないだろうか。これからく る春を恨んだりしないだろうか。フリジットの冬も、春も、彼に見 せたくてたまらなかったものすべてを置き去って、ハンナが消え失 せることを受け入れてくれるのだろうか。それによって彼の心がい びつに曲がったりはしないだろうか。心配なことは山ほどあって、 留まることをしらない。 ︵ああ。駄目だ︶ 考えてはいけない。いま、自分が考えるべきことは民のこと。フ リジットのこれからだ。 でも、とささやく声はハンナをさいなむ。もういいのでは、と誘 惑する声がやまない。 ハンナを支えていた頼りない糸がぷっつりと切れてしまったよう に、ハンナの心内は揺れている。最期なのだからと気を張っていよ うとする意識と、最期なのだからと自分を甘やかす声はせめぎあう 176 ようにぶつかりあって、ハンナを苦しめ続けていた。 惜しくないわけがない。アルクゥと歩める未来を捨てることはと ても悲しい。 ぽっかりと足元に穴があいたようだった。けっして落ちない。け れど、確かにあいている穴からは寒々しい空気がわきあがり、ゆっ くりとハンナの体を凍らせていく。そのまま心さえも凍結してしま えば、どれほどよかったのだろうと考える。くしくも、アルクゥと 寄り添えば、ハンナはより人間らしく、ハンナらしくいられた。そ して、戻りがたくなるのだ。甘く気持ちのいい夢から起きづらいよ うに。わずかでも願って目をつむってしまう。 ﹁言ってほしかったよ﹂ ぶっきらぼうに落とされる言葉の真意をはかりそこねてハンナは 顔をあげた。 そらされているため視線は合わなかったが、横顔からは不満の色 がうかがえる。むすりと引き結ばれた唇は軽く噛まれている。わず かに血がにじんでいるのをとらえて、いたたまれなくなってしまっ た。思いのほか、シグルを傷つけてしまったらしい。 ﹁言えば、どうしていたの?﹂ ﹁すくなくとも、こうやって武器を向けなくてよかった﹂ 金属質な音が耳をついて、銃口が向けられる。そこにためらいも なければ本気もない。 ただ、銃口を向けているだけだ。発砲するつもりなどないから、 引き金にすら指をかけていない。そうやってシグルに武器を持たせ たのは自分なのだと再確認させられて、ハンナは泣きそうな気分だ った。うんざりしたというよりは、ただひたすらに悲しくてやりき れない。 自分がしてきたことを考え、民の心痛を考え、クライスの苦悩を 思い、そして疲れてしまった。考えることに疲弊すれば、ぼんやり と時間が過ぎて、無為に流れることに絶望していく。もしかすると、 これから待ち受ける物事を憮然として受け入れられるのは、とっく 177 に疲れ果ててしまっていたからかもしれない。あまりにもしんどい から、休みたいのだ。たとえ、永遠に目が覚めなくてもいいと思っ てしまうほどに。 ﹁なにかしたいことはあるか?﹂ 死地におもむくものへとはなむけをあたえるようにシグルは言う。 喧噪に包まれる市街へと目をやって、ハンナはこぼすように願っ た。けっして叶わないことを。 ﹁⋮⋮春を、みたいわ﹂ あともうすこしでおとずれる。フリジットの輝かしい未来を。 無茶なことを言ったことはわかっている。シグルは押し黙ってい るだけでなにも言わない。意地悪をするつもりでいったわけではな かったが、どうにもやっかみ半分な願いごとだ。あとすこし、とい うところでハンナの手は春を掴み損ねた。だからこそ、ハンナは瞼 に浮かべるのだ。思い出の中にある春はすこし色あせていて、香り もなにもないけれど、どれほど美しいかを噛みしめるほどに想像す る。 ﹁だからね、シグル。わたしのかわりに見てね﹂ どれほどの春だったかを、ハンナに教えてほしい。そのころのハ ンナにはもう五感がなくなって、自分がどこにいるのかもわからな くて、フリジットの冬よりも寒々しい場所にいるかもしれなくても、 ずっと待ち望んでいたことだったから。それぐらいの情けはかけて ほしかった。 ﹁ハンナ︱︱﹂ ふわりと落とした笑顔は、乱暴に叩かれた扉にけがされていく。 ﹁おい! 時間だ!﹂ がなり立てる声に、もう恐怖を感じることはない。 胸を張れ。顎を引け。ゆっくりと深呼吸をすれば、ハンナは王に なる。 どこまでも冷徹で、フリジットにふさわしい﹁冬の王﹂になれる はずだった。 178 後ろ手に拘束されて背中に銃口をつきつけられ、せっつかれるよ うに歩かされる﹁非道﹂の王に野次馬は興味津々だった。演説は大 成功だったらしく、投石がおこなわれてはあたりが騒然とした。幸 いなことに石つぶてはハンナを傷つけなかったが、心をおおきくえ ぐりとって道端に転がった。それでも、ハンナはじっと前をみすえ る。ちらちらと視線をよこすシグルすらも、頭から飛びだしていっ たように気にかけない。 ハンナが処刑台へと足を進める中、ひそやかに落とされる言葉に はあわれみもあった。初めて王の顔を見たのだ。年若い少女だとは 想像していなかったのだろう。子どもを抱きかかえた女性は顔をゆ がめて見守っている。あまりも痛ましくこちらを見るものだから、 ハンナは気付かれないように口の端をあげて笑ってみせた。なんて ことはない。平気だと言い聞かせるために。 処刑台にたどりつけば、しっかりと結ばれた縄を首にかけられる。 罪状を書いた紙をわざわざ作ったのかわざとらしく咳払いをしてそ れを読みあげ始める。そんな男の足元にはレバーがあって蹴り上げ られれば、ハンナの足元にある四角い木板がぱっかりと開き、太い 縄がハンナの細い首を絞めつけあげる仕組みだ。いつその時がおと ずれるのかはかりかねて、ハンナは落ち着かず視線をくるくると動 かした。民衆のだれもがつりあがった目でハンナを睨みつけている。 きっとハンナは悪魔のように見えているに違いないと考えて自嘲し た。なんてちっぽけでひ弱な悪魔なのだろう。こんな細腕ではだれ も殺せない。守ることもできない。 読み上げる男の声が興奮をともなっていく。ハンナを横目でうか がっては、いつレバーを蹴り上げるかを計算している。そんな生々 しい光景から逃げるようにハンナは空を見上げた。フリジットの冬 だとは思えない晴れ晴れしい空の色。どこまでも澄んだ色はフェル の瞳を思い起こさせ、ハンナはぐっと唇を噛んだ。言ってほしかっ 179 たとシグルは嘆いた。もしも、あのとき王だと言ってフェルに頭を 下げれば、彼はどのような顔をしただろう。謝っていないことが悔 しくて、同時に知られることが怖くて、ハンナは涙がこぼれないよ うに眉根をよせた。 ﹁おい! おい!﹂ ﹁⋮⋮?﹂ ﹁なにか最期にいえよ。おら﹂ ﹁最期⋮⋮﹂ ああ。そうか。もう最期なのか。もうそんな時間なのか。 見渡せば、だれもがハンナを注視している。ハンナの口からつむ がれる言葉を待っている。正しくはハンナが謝罪をするのを待って いるのだろう。あの村での顛末を謝罪することは容易だったが、ど うしてだが意固地にもハンナは口にしようとは思わなかった。 ﹁どうか、よい春を︱︱﹂ ざわりと空気が揺れる。もちろん、いい意味でなく。しかし、ハ ンナは憮然とした顔でたたずむだけで、それ以上、言葉を続けるつ もりはなかった。 村の出来事を謝罪するのは簡単だろう。心無い謝罪ほど楽なもの はない。ハンナが謝りたいと思うのはフェルだけだ。約束を守れず、 彼のささやかな夢をぶちこわしたのは、ハンナだ。けれど、村をお びやかしたのはハンナではない。いまさら、あきらめ悪く言い訳を 並べているように思えたが、ハンナはどうしても釈然としなかった。 それはきっとクライスの悲痛を聞いてしまったからだろう。ハンナ が考えなしに謝ることは、クライスの覚悟を蹴り飛ばし、頭を踏み つけていることと同じに思えた。それはきっと、正しくないのだ。 後悔などしない。 怒りが頂点に達したであろう男の足がレバーを蹴り上げようとし ているのを見て、ハンナはひっそりと瞼を閉じた。暗闇がやってく る瞬間まで、灰色を探し求めたが、ただひたすらに黒い色だけがハ ンナの視界を満たしただけだった。 180 PDF小説ネット発足にあたって http://ncode.syosetu.com/n4692ck/ 咎のドラゴンと冬の王 2015年3月17日14時45分発行 ット発の縦書き小説を思う存分、堪能してください。 たんのう 公開できるようにしたのがこのPDF小説ネットです。インターネ うとしています。そんな中、誰もが簡単にPDF形式の小説を作成、 など一部を除きインターネット関連=横書きという考えが定着しよ 行し、最近では横書きの書籍も誕生しており、既存書籍の電子出版 小説家になろうの子サイトとして誕生しました。ケータイ小説が流 ビ対応の縦書き小説をインターネット上で配布するという目的の基、 PDF小説ネット︵現、タテ書き小説ネット︶は2007年、ル この小説の詳細については以下のURLをご覧ください。 181
© Copyright 2026