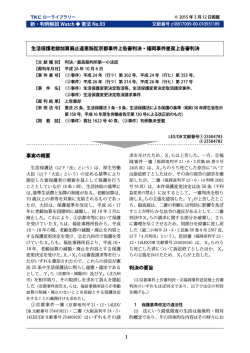責任能力と期待可能性の関係
ローライブラリー ◆ 2015 年 2 月 6 日掲載 新・判例解説 Watch ◆ 刑法 No.86 文献番号 z18817009-00-070861177 責任能力と期待可能性の関係 【文 献 種 別】 判決/大阪高等裁判所 【裁判年月日】 平成 26 年 10 月 3 日 【事 件 番 号】 平成 25 年(う)第 1432 号 【事 件 名】 各傷害致死、監禁、傷害、逮捕監禁、死体遺棄被告事件 【裁 判 結 果】 被告人Aにつき原判決破棄、被告人B及び被告人Cにつき控訴棄却 【参 照 法 令】 刑法 39 条 【掲 載 誌】 判例集未登載 LEX/DB 文献番号 25505292 …………………………………… …………………………………… の死体を搬出し、倉庫のドラム缶に入れて放置し、 もって死体を遺棄した。 3 被告人Aは、Dと共謀の上、Eの死後Dの 怒りが向けられるようになっていたBに対し、顔 面を多数回殴打するなどして、傷害を負わせると ともに、本件居室で同人を不法に逮捕監禁した。 4 第一審(神戸地判平 25・10・31LEX/DB 文献 番号 25502421) で、被告人 3 名は、責任能力の 有無・程度と期待可能性の有無を争ったが、裁判 所は責任能力についても期待可能性についても肯 定した。検察官の求刑はAにつき懲役 5 年、B及 びCにつきそれぞれ懲役 4 年であったが、裁判 所はAを懲役 3 年 6 月、Bを懲役 3 年執行猶予 4 年、Cを懲役 2 年執行猶予 3 年に処した。 5 被告人 3 名は控訴し、心神喪失及び期待不 可能を主張するとともに、Aについては量刑不当 も主張した。 事実の概要 1 鉄道会社に勤務していた被告人Aは、ク レーム対応を契機として、妻である被告人Cとと もにDと個人的に交際するようになった。AとC はDに怒鳴られ叱責される関係となり、Dの指示 でAは会社を退職し、AとCは離婚した。さらに 同居していたAとC及びCの実母Eはそれぞれ別 に暮らすことになり、AはDの居住するマンショ ンのすぐ横にある居室(以下、本件居室) に住む ことになった。 その後、家族会議と称するDを交えた長時間の 話し合いの結果、Cは育児放棄や虐待をしていた とDから責められ、Dの指示でD方や本件居室で 生活するようになったが、Dの怒りを買い、継続 的な暴行や起立強制などの虐待を受け、食事や飲 み水を制限されるなどした。さらにCの姉である 被告人Bも本件居室に同居するようになり、Aと BはDの指示で、Cを殴る等の暴行に加担するよ うになった。そして、Dの指示によりEも、A、B、 Cとともに本件居室で共同生活を営むようになっ た。 2 被告人 3 名は、Dと共謀の上、本件居室で Eに対し、食事回数、トイレ使用回数、飲み水を 制限した上、時折、長時間立ったままの姿勢でい ることを強制し、また同人に暴行を加え、これら の継続的な虐待行為により、同人が衰弱した状態 になったのに、その後も虐待行為を継続し、一連 の行為に基づく傷害により同人を死亡させた。ま た、 Eが本件居室から逃げ出そうとしたことから、 Dと共謀の上、Eの動静を監視するなどして、もっ て同人を不法に監禁した。さらにEの死亡後、D 及びDのいとこと共謀の上、本件居室内から、E vol.7(2010.10) vol.17(2015.10) 判決の要旨 被告人Aにつき原判決破棄、懲役 3 年執行猶 予 5 年。被告人B及びCにつき控訴棄却。 1 責任能力に関しては、「被告人各人に対す るDらの暴行等の制裁は、その時期、期間の長短、 内容、程度などの点で異なるところがあるが、E に対する死体遺棄の犯行やAのBに対する傷害、 逮捕監禁の各犯行をも含め、Dらから更に暴行等 の制裁を受けることに対する恐怖心が本件各犯行 の原因となっていたと認定することができ……、 当時の状況等に精神障害の存在をうかがわせるよ うな特異な点は見出し難い」。 2 期待可能性に関しては、「逃亡や警察相談 などをした場合には、その後Dから暴行等の厳し 1 1 新・判例解説 Watch ◆ 刑法 No.86 い制裁が加えられることが予想され、そのような 行動をとることは心理的に困難であったと認めら れるが、被告人らはそれぞれDらから常に監視さ れていたわけではなく、本件居室から逃亡して警 察官等に助けを求めるなどする機会がそれなりに 存したのである。……被告人らが、本件各犯行に 及んだ際にそれ以外の適法行為を選択することが 客観的に期待できなかったといえるような状況に はなかったと認められる」。 「Dこそが被告人らそれ 3 量刑に関しては、 ぞれに対して圧倒的な影響力をもつ立場にあった ことが明らかであって、各犯行の実行に当たって は、AとB及びCとの間に上下・主従の立場の差 などはなく、BやCがAの指示を受けて傷害致死 の実行行為たる暴行を行ったとか、AがBやCに よる暴行を積極的に利用して傷害致死の犯行を実 現したとみるべき事情もない。以上のように、E に対する各犯行についての被告人各人の犯情ない しは行為責任に関わる事情を中心に検討すると、 AがBやCと比べ目に見えて重い責任を負うべき ものと評価するに足りる事情は見受けられない」。 ず、結果として相手の思いどおりになるというこ とが何度も繰り返されると、その人間は自発的に 考えることを停止し、それがその人間の行動原理 全般に普遍化され、これまで得てきた常識や問題 解決能力等を喪失してしまうなどという心理状 態」のことをいう。 二 責任能力に関しては、精神の障害という生 物学的要素の存在を前提に、それによって是非善 悪を弁識する能力もしくはその弁識に従って行動 する能力という心理学的要素が欠如していれば心 神喪失、著しく減退していれば心神耗弱と判断す るということで、基本的に異論を見ない(大判昭 6・ 12・3 刑集 10 巻 682 頁)。 この点について一審判決は、鑑定を踏まえて、 学習性無力感が心理学の概念であり、鑑定人が明 らかな精神障害がなかったと明言している以上、 生物学的要素を欠くとして、直ちに責任能力あり との結論を下している。これに対して、本判決 は、「責任能力の判断はいわゆる生物学的要素及 び心理学的要素の両方についての検討をふまえ、 究極的には裁判所においてなされるべき問題であ る」という理由で、心理学的要素として犯行の動 機、犯行状況等の要素についても併せて検討して おくのがより適切であると述べつつ、動機などを 含む犯行状況に精神の異状を窺わせる点はないと する。他方で、本件鑑定については、学習性無力 感以外に精神障害の存在を認定せずに直ちに判断 能力・制御能力について結論を下しており、また 仮に学習性無力感に陥った状態が精神障害と呼ぶ べきものに相当すると評価したとしても、いかな る精神状態・症状を呈し、それが犯行動機の形成 や当時の被告人らの行動にどのような影響を及ぼ したかにつき具体的かつ十分な検討がなされてい ないなど、確立した責任能力に関する鑑定判断の 在り方とかけ離れた検討過程を経るもので、これ を採用すべきではない合理的事情が認められる、 と評価する。 本判決の判示は、生物学的要素についても究極 的には裁判所の評価に委ねられるとする判例(最 決昭 58・9・13 判時 1100 号 156 頁)を踏まえている。 しかしこの判例の趣旨は、鑑定が精神障害の存在 を全く示唆しないのに、裁判所独自の判断で精神 障害の存在を認定してよい、というものではない だろう。そうした経験科学的基盤から全く遊離し 判例の解説 一 本件は、兵庫県尼崎市を中心的舞台として 発生した連続不審死事件の一部を構成する事件で ある。一連の事件では、確認されただけで 8 名 が不審死を遂げているが、主犯格と目されていた Dが勾留中に留置場で自殺するという異例の経過 をたどっている。本件以外にも、ごく普通の生活 を送っていた複数の家族が些細な弱みからDに支 配され、家庭内で暴行や食事制限といった虐待事 件を引き起こした末に死者を出すに至ったとされ 注目を集めた。本件においては、心理的支配に対 する人間の脆弱さが浮き彫りとなり、その刑事責 任をいかに評価するかが問題となった。 一審で行われた鑑定は、被告人らには明らかな 精神障害があったとまではいえないが、学習性無 力感に陥っており1)、A及びCについては善悪の 判断能力及び行動制御能力がともに完全に失われ ており、Bについては判断能力が著しい程度に障 害され、行動制御能力が完全に失われていたとす る。学習性無力感とは、一審判決によれば、「人 間関係において一方的な支配関係が続き、自律的 に反応し自分自身の考えを述べてもそれが報われ 2 2 新・判例解説 Watch 新・判例解説 Watch ◆ 刑法 No.86 無力感とは、コントロール不能の状態で無力感を 学習して無気力に陥ることでコントロール可能な 状態になっても抵抗を行わなくなる状態を指すの であるから4)、責任能力に影響するとすれば主と して制御能力についてであり、弁識能力が保持さ れていたと指摘するだけでは十分でないと思われ る。 本判決は、本件鑑定はいかなる精神の状態に陥 り、それが動機形成や行動にどう影響したのかに つき具体的かつ十分な検討がされていないと批判 する。この指摘が正しいとすれば、判例である 20 年判決(最判平 20・4・25 刑集 62 巻 5 号 1559 頁) にいう、鑑定を尊重しないでよい合理的な事情が あると評価できるだろう。しかしそうであれば、 被告人らの精神状態について何ら判断の手がかり が得られていないことになるため、再度の鑑定を 実施すべきだったのではないだろうか。 た責任能力の認定は、極めて恣意的になってしま う。確かに、鑑定を経ずに責任能力判断をしても よいとするのが判例(最大判昭 23・11・17 刑集 2 巻 12 号 1588 頁)ではあるが、現在ではこれが妥 当するのはあくまでも精神障害の疑いがないとし て完全責任能力を認定する場合であり、責任能力 が損なわれていたとの判断には当てはまらないと 見られる。したがって、本判決の趣旨は、学習性 無力感という心理状態がある場合、何らかの精神 障害の存在を疑いつつ、心理学的要素の検討を行 うべきで、検討の結果、弁識能力・制御能力に毀 損が見られれば、精神の障害も存在するとした上 で、心神喪失・耗弱の余地を認めるものだと解さ れる。学習性無力感が心理学的概念であるという 意味は、実験を通じて確立されたという概念の出 自2) を表すに過ぎない。本件では通常人にはお よそ想定し難い行動がなされていることからする と、何らかの精神的な異常を疑うのがむしろ素直 であろう。現代の精神医学で主流とされる、アメ リカ精神医学会の診断マニュアル(DSM)を見て も、精神疾患の範囲は極めて広範囲に及んでおり、 統合失調症など確立した精神病のみが生物学的要 素を構成するとの伝統的立場はもはや維持し得な い。心理学的概念が問題になっているというだけ で、直ちに生物学的要素が欠けるという扱いはす べきでないだろう。 本判決は、心理学的要素の検討において、①「そ の経緯からすると、被告人らは、一貫してその時々 の場面や状況に見合った判断からその行動を選択 していたものということができ、動機の点を含む 各犯行の状況に精神の異状をうかがわせる不自 然、唐突な点はない」こと、②遺体を遺棄するな ど犯罪行為を行っている認識があったこと、③犯 行当時の記憶認識が十分保たれていることから、 結局のところ精神障害の存在を否定している。し かしこの判断には疑問がある。①については、D らからさらに暴行等の制裁を受けることに対する 恐怖心が犯行の原因となっているとしつつ、 「そ の経緯からすると」動機等に異常はないとするが、 学習性無力感に陥っていることを前提として、異 常性を否定している疑いがある。統合失調症等で あっても、その症状を前提とすれば、それに支配 されて犯行に至る過程に不自然さはないことに なってしまうのであり、安易な動機の了解可能性 判断には問題がある3)。②③については、学習性 vol.7(2010.10) vol.17(2015.10) 三 期待可能性に関して、一審判決が責任能力 に関する 20 年判決に従って、鑑定を尊重しない でよい合理的事情の有無を検討しているのに対 し、本判決は「客観的に」適法行為の選択が期待 できたかを検討している。 この問題は責任能力と期待可能性の役割分担に 関わる。両者は他行為可能性判断の下で統合され るものの、行為者の内部的な事情に関係する異常 性が責任能力の問題、外部的事情に関係する異常 性が期待可能性の問題という切り分けが一般的か と思われる5)。その具体的意味合いは、状況に応 じた行為者の対応が通常人の性格のバリエーショ ンの範囲内にある場合は期待可能性の問題、通常 人には考え難い対応がなされている場合は責任能 力の問題と考えることにあるだろう。そうだとす ると、生物学的要素の欠如を理由に完全責任能力 を肯定しつつ、期待可能性において心理学的要素 の検討を行うかのような一審判決よりも、行為者 の内部的異常性を責任能力の問題として考慮した 上で、別途期待可能性の検討を行う本判決の整理 の方が、妥当だと思われる。 ただしそのことは、本判決のように客観的判断 を行うべきかどうかとは別問題である。客観的判 断の強調は、期待可能性の標準について、平均人 標準説と行為者標準説の対立があり、前者が通説 とされていることと関係している可能性がある6)。 しかし本件の場合に、学習性無力感に陥っていな 3 3 新・判例解説 Watch ◆ 刑法 No.86 犯情とは客観的な犯行の事情のみを意味するので はなく、主観面における動機や犯意の形成過程等 も含めた判断である。本件のように共犯者が強度 の心理的支配を及ぼす場合は、実行行為を行った ことはもはや決定的重要性を有しなくなる。だか らこそ一審判決もBやCには執行猶予付き判決を 選択したのであり、Aについてのみ実行行為を重 視するのは一貫しない。犯情とは違法性に関わる 事情だけでなく、責任面を含めた総合判断である ことを改めて確認した点に、本判決の意義がある。 また一審判決は、Aは理不尽かつ粗暴な言動が 顕著なDをおそれながらもDに依存して生きる道 を選択し、その指示に盲従するようになったと指 摘するが、本判決は仮にその指摘が妥当だとして も、犯行の遠因ないし発端にとどまり、犯行に直 接的、具体的に結びつくものではないと指摘する。 この点についても本判決の評価に妥当性が認め られる。被告人が支配服従関係に入る際にその関 係を自ら受け入れたと評価し得る面が仮にあった としても、その時点ではその選択が犯行をせざる を得ない状況に結びつくと予測することは困難で ある。それを独立した非難の対象として、行為 時の非難可能性の低下を補う事情と評価するなら ば、行為責任を上回る責任を負わせることになり、 責任主義に反するためである。 い人にとって適法行為が可能であったかを問うて も無意味であることは、明らかであろう。平均人 標準説を採るとしても、学習性無力感に陥った平 均人を措定しなければならない7)。行為者自身の 精神状態を加味しない「客観的」判断は不適切で ある。 また、期待可能性判断において、精神鑑定がな されている場合に、20 年判決に従って、鑑定を 尊重した判断をする必要がないかも別問題であ る。本判決は、20 年判決は「臨床精神医学上の 専門的知見を要する精神鑑定等が責任能力の判断 において占める位置づけなどを踏まえ」たものだ として、一審判決の鑑定の取扱いを批判する。し かし、20 年判決は、精神障害の有無や程度、そ れが行為者の心理状態にいかなる影響を及ぼした かの診断は「臨床精神医学の本分」であることか ら、鑑定意見の十分な尊重を求めたものである。 規範的判断の名の下で恣意的になりかねない素人 的判断を戒めるとの要請は、鑑定が責任能力判断 のためのものかどうかによらず妥当すると思われ る。 なお、本判決は期待可能性を肯定する根拠の一 つとして、 「本件居室から逃亡して警察官等に助 けを求めるなどする機会がそれなりに存した」こ とを指摘する。しかし、学習性無力感に陥ってい たとすれば、状況のコントロール可能性が回復し た後も自律的行動ができないことは十分にあり得 ると思われ、こうした判断において、鑑定の内容 を尊重しないで裁判所独自の判断を行うことの危 うさが表れているように思われる。 ●――注 1)一審はさらに、鑑定が取り上げた、心理的監禁状態と いう概念についても検討を加えているが、控訴審はこの 点についての言及がない。その理由は判決文のみからは 詳らかではないため、検討を控える。 2)大芦治『無気力なのにはワケがある』 (NHK 出版、2013 年) 四 量刑判断に関して、一審判決が被告人Aの 刑事責任は特に重いとしてAのみを実刑判決とし たのに対し、本判決はAのみが特に重い責任を負 う根拠はないとして、Aについても執行猶予付き 判決としている。 両判決が判断を分けた理由の一つは、一審判決 は、AがEのみならずBに対しても虐待を加えた ことを重視したのに対し、本判決は、本件で特に 重要な量刑事情は、被告人らがDらの制裁に対し 強い恐怖心を有し、厳しい精神的、肉体的抑圧を 受けていたことにあり、その限度で被告人らの間 で異なるところはないとした点にある。 この点は本判決の方が妥当であろう。昨今は量 刑において犯情を重視すべきとされているが8)、 4 は、多種多様な実験を通じて学習性無力感の概念が生成 されてきた過程を紹介しており、参考になる。 3)近藤和哉「責任能力判断における『了解』について (1)」 上法 39 巻 2 号(1995 年)110 頁。 4)大芦・前掲注2)14 頁参照。 5)団藤重光「責任能力の本質」 『刑法講座第 3 巻』 (有斐閣、 1963 年)35 頁。 6)平均人標準説を明言する裁判例として、東京高判昭 23・10・16 高刑集 1 巻追録 18 頁がある。 7)ただし、学習性無力感に陥るか否かには個人差がある とされていることに注意が必要である。大芦・前掲注2) 128 頁参照。 8)司法研修所(編)『裁判員裁判における量刑評議の在り 方について』(法曹会、2012 年)6 頁。 一橋大学教授 本庄 武 4 新・判例解説 Watch
© Copyright 2026